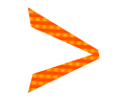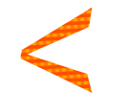<< 0:00>> 2:00




訳が分からなかった。
夢でもみているのかと思った。
私はいつの間にか、私の知らない世界へ連れてこられていた。
名前を呼んだ。
さっきまで一緒に居たはずのやつらの名前を呼んだ。
でも、声は返ってこない。あるのは大きな時計台と、気味悪い男の笑みだけ。
私は少し、満月のような時計台の灯りを憎んだ。
私の目の前で、血の色をしたなにかが蠢いているのが、ハッキリわかったから。
あの男――たしか榊と名乗った――は、それを指してウォームアップなどと抜かしていた気がする。
でも、男の説明なんて、ほとんど耳に入ってなかった。
「ア゛ア゛ア゛ア゛ァァ…………」
その"成れの果て"の嗚咽を聞いた瞬間――
「――ぁああああああああッ!!!」
――私は剣を抜き放っていたのだから。
光の剣を、私の証を、死に物狂いで振るい続けた。
多分、頭が真っ白になってたんだと思う。戦いのことはよく覚えていない。
ただ、斬っても斬ってもまだ死なないって感覚が、とても強かった。
その時の私は気づいてなかったんだろう。
きっと、色んな種類の恐怖で頭がいっぱいで、グチャグチャになってた。
目の前の何かが一片たりとも動かなくなるまで、剣を振るっていた。
いや、動かなくなっても、その痕跡が消えるまで刻み続けていた……と、思う。
磨きに磨いたと思っていた心など、脆いものだと今になって感じる。
それでも、共に磨いた戦技だけは、私を裏切らなかったのは救いだった。
自身の足元を染めた赤色をしばらく見つめていた。
息も切らしてるのに気づいた頃には、だんだん身体の震えが止まらなくなってた。
嫌な汗がたくさん出てきた。凍りついた脳味噌が急に溶け出したみたいだった。
目の前の血溜まりから逃げ出すように、私は駆け出した。
私の知ってる人の名前を、片っ端から叫びながら、駆け回った。
青い光の剣を抜き放った、そのまま。
でも、その光だけじゃ、あるかも分からない道の先まで照らしきってはくれなかった。



ENo.6 雪瀬 かりん とのやりとり

ENo.157 三廻 冬霧 とのやりとり

ENo.198 魔人王モロバ とのやりとり

ENo.413 伊上 司 とのやりとり

ENo.709 ティーナ とのやりとり

ENo.791 ミロワール とのやりとり




特に何もしませんでした。








武術LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
センジュ(93) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『ルクスフィクス』を作製してもらいました!
⇒ ルクスフィクス/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
センジュ(93) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『壱式発動機』を作製しました!
ItemNo.5 不思議な石 から防具『レガーススキン』を作製しました!
⇒ レガーススキン/防具:強さ30/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
リッカ(810) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『あの日のお守り』を作製しました!
ユキ(270) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議な刺身と山盛りの山葵』をつくってもらいました!
⇒ 不思議な刺身と山盛りの山葵/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
雫(939) とカードを交換しました!
[N]Strength (ブレイク)


イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
エキサイト を習得!
イレイザー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
ユキ(270) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



――目の前の時計台は、まるで満月のようだった。
それと、私の足元へ転がった血色の塊だけは、よく覚えている――
それと、私の足元へ転がった血色の塊だけは、よく覚えている――
 |
咲那 「……クッソ、どうなってやがる…… おい、皆どこに……!」 |
訳が分からなかった。
夢でもみているのかと思った。
私はいつの間にか、私の知らない世界へ連れてこられていた。
名前を呼んだ。
さっきまで一緒に居たはずのやつらの名前を呼んだ。
でも、声は返ってこない。あるのは大きな時計台と、気味悪い男の笑みだけ。
私は少し、満月のような時計台の灯りを憎んだ。
私の目の前で、血の色をしたなにかが蠢いているのが、ハッキリわかったから。
あの男――たしか榊と名乗った――は、それを指してウォームアップなどと抜かしていた気がする。
でも、男の説明なんて、ほとんど耳に入ってなかった。
「ア゛ア゛ア゛ア゛ァァ…………」
その"成れの果て"の嗚咽を聞いた瞬間――
「――ぁああああああああッ!!!」
――私は剣を抜き放っていたのだから。
 |
咲那 「チクショウ、ふざけやがって…………クソッ!!」 |
光の剣を、私の証を、死に物狂いで振るい続けた。
多分、頭が真っ白になってたんだと思う。戦いのことはよく覚えていない。
ただ、斬っても斬ってもまだ死なないって感覚が、とても強かった。
 |
咲那 「クソッ! 早く! くたばれ! 早く!!」 |
その時の私は気づいてなかったんだろう。
きっと、色んな種類の恐怖で頭がいっぱいで、グチャグチャになってた。
目の前の何かが一片たりとも動かなくなるまで、剣を振るっていた。
いや、動かなくなっても、その痕跡が消えるまで刻み続けていた……と、思う。
磨きに磨いたと思っていた心など、脆いものだと今になって感じる。
それでも、共に磨いた戦技だけは、私を裏切らなかったのは救いだった。
 |
咲那 「ハァ……ハア……! ……ッ、ハァ…………」 |
自身の足元を染めた赤色をしばらく見つめていた。
息も切らしてるのに気づいた頃には、だんだん身体の震えが止まらなくなってた。
嫌な汗がたくさん出てきた。凍りついた脳味噌が急に溶け出したみたいだった。
 |
咲那 「ハァ……ッ、クソ、探さないと……みんな!」 |
目の前の血溜まりから逃げ出すように、私は駆け出した。
私の知ってる人の名前を、片っ端から叫びながら、駆け回った。
青い光の剣を抜き放った、そのまま。
でも、その光だけじゃ、あるかも分からない道の先まで照らしきってはくれなかった。



ENo.6 雪瀬 かりん とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.157 三廻 冬霧 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.198 魔人王モロバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.413 伊上 司 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.709 ティーナ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.791 ミロワール とのやりとり
| ▲ |
| ||



特に何もしませんでした。







武術LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
センジュ(93) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『ルクスフィクス』を作製してもらいました!
⇒ ルクスフィクス/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
千手 「武器整備は任せて。技師の人に色々教えてもらってるの」 |
センジュ(93) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『壱式発動機』を作製しました!
ItemNo.5 不思議な石 から防具『レガーススキン』を作製しました!
⇒ レガーススキン/防具:強さ30/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
リッカ(810) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『あの日のお守り』を作製しました!
ユキ(270) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議な刺身と山盛りの山葵』をつくってもらいました!
⇒ 不思議な刺身と山盛りの山葵/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
ユキ 「多分生で食べられるよ。多分ね」 |
雫(939) とカードを交換しました!
[N]Strength (ブレイク)


イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
エキサイト を習得!
イレイザー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
ユキ(270) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――







千夜天水
|
 |
仄暗い否定の世界から
|


ENo.539
天宮寺 咲那



天宮寺 咲那(てんぐうじ さな)
年齢:17歳 身長:164cm 相良伊橋高校に通う高校2年生。
長い黒髪を結わえて流した、凛とした雰囲気の女子高生。
突如告げられた侵略、そして異変の到来とともに、
イバラシティで出会った仲間たちを護るため立ち上がった。
元"自称風紀委員"の、現「風紀委員長」。
自信家で男勝り・媚びへつらわない性格。
どのような相手であっても堂々とした振る舞いをする。
その分悩む時は、一人で悩みがちのお年頃。
「六峰天流」と呼ばれる古武術を、幼少期より習っている。
武芸十八般を6つの大きな括りとして捉えた古武術で、
咲那は剣術と体術において、目録の位まで修めている。
自身の過去と師の教えから、力の振るい方や戦い、争い事にはシビアなスタンスを貫いている。
実家は神社で街の外。祭神は木花咲耶姫命。
休日に巫女役として駆り出されていた。信心は意外と深め。
最近は帰れていない。別のバイトを始めるか思案中。
リスニングによる記憶が得意。授業も聞くばかりで家で勉強することは殆ど無い。本人曰くちゃんと点は取れているらしい。
◆異能
《光の救世者/ライト・セイヴァー》:光の剣を生成する
光と熱量を持った非実体の刃を形成する。
形成された刃は、触れたものを溶断し破壊する。
完全な円筒状の構造物に本人が触れている間のみ発動できる。また、構造物が損壊した場合にも異能の発現は解除される。
咲那は異能を使用する為の装備を特注し、複数所持している。
刀身の威力は本人の意思で非殺傷まで低下させられる。
刀身の発光色も本人の意志である程度まで変化させられる。
なお、上記特性は全て咲那本人の訓練による成果である。
◆魔術
《術符・木花咲耶姫命/天宮寺咲那》
黒木蒔那より贈られた、1枚のカード。
片面には、木花咲耶姫命を象られた絵が描かれ、もう片面には、咲那をモチーフとした光を頂く女性の絵が描かれている。
複数の魔術師によりブランクカードとして作成され、咲那の手によって絵柄が具現化された。咲那はこれをご神体の一種として捉えている。
術具ではあるが、その実態上、性質はほぼ神具と化している。
《術符展開(バレル・オープン)/祝詞奏上・木花咲耶姫命》
術符による起動式。咲那のみに行使が許されている。
「木花咲耶姫命」そのものを呼び、それに纏わる力や加護を得、行使できる。また、その能力は咲那と共に成長する事ができる。
年齢:17歳 身長:164cm 相良伊橋高校に通う高校2年生。
長い黒髪を結わえて流した、凛とした雰囲気の女子高生。
突如告げられた侵略、そして異変の到来とともに、
イバラシティで出会った仲間たちを護るため立ち上がった。
元"自称風紀委員"の、現「風紀委員長」。
自信家で男勝り・媚びへつらわない性格。
どのような相手であっても堂々とした振る舞いをする。
その分悩む時は、一人で悩みがちのお年頃。
「六峰天流」と呼ばれる古武術を、幼少期より習っている。
武芸十八般を6つの大きな括りとして捉えた古武術で、
咲那は剣術と体術において、目録の位まで修めている。
自身の過去と師の教えから、力の振るい方や戦い、争い事にはシビアなスタンスを貫いている。
実家は神社で街の外。祭神は木花咲耶姫命。
休日に巫女役として駆り出されていた。信心は意外と深め。
最近は帰れていない。別のバイトを始めるか思案中。
リスニングによる記憶が得意。授業も聞くばかりで家で勉強することは殆ど無い。本人曰くちゃんと点は取れているらしい。
◆異能
《光の救世者/ライト・セイヴァー》:光の剣を生成する
光と熱量を持った非実体の刃を形成する。
形成された刃は、触れたものを溶断し破壊する。
完全な円筒状の構造物に本人が触れている間のみ発動できる。また、構造物が損壊した場合にも異能の発現は解除される。
咲那は異能を使用する為の装備を特注し、複数所持している。
刀身の威力は本人の意思で非殺傷まで低下させられる。
刀身の発光色も本人の意志である程度まで変化させられる。
なお、上記特性は全て咲那本人の訓練による成果である。
◆魔術
《術符・木花咲耶姫命/天宮寺咲那》
黒木蒔那より贈られた、1枚のカード。
片面には、木花咲耶姫命を象られた絵が描かれ、もう片面には、咲那をモチーフとした光を頂く女性の絵が描かれている。
複数の魔術師によりブランクカードとして作成され、咲那の手によって絵柄が具現化された。咲那はこれをご神体の一種として捉えている。
術具ではあるが、その実態上、性質はほぼ神具と化している。
《術符展開(バレル・オープン)/祝詞奏上・木花咲耶姫命》
術符による起動式。咲那のみに行使が許されている。
「木花咲耶姫命」そのものを呼び、それに纏わる力や加護を得、行使できる。また、その能力は咲那と共に成長する事ができる。
25 / 30
50 PS
チナミ区
J-5
J-5





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | ルクスフィクス | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 5 | レガーススキン | 防具 | 30 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 不思議な刺身と山盛りの山葵 | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 20 | 身体/武器/物理 |
| 防具 | 20 | 防具作製と、防具への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]イレイザー | [ 2 ]パワフルヒール |

PL / ねこれー