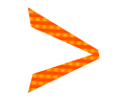<< 0:00>> 2:00




――夜明け前。潮騒の向こうに遠く、嘶きを聴いた気がした。
***
藻噛叢馬は創峰大学に通う学生であり、第二学部で海洋生物学を専攻する修士課程の二年生である。
学者だった両親は、彼が高校生の時にフィールドワーク中の事故で他界した。
それまで親族とは疎遠だったが、彼の祖父は代々続く学者の家の息子が大学にも行かず就職するなど恥であると考え、大学院までの学費とその間の最低限の生活費は援助すると一方的に告げた。彼としても特に異存はないのでありがたく受け取っているが、もし学者志望でなかったらさぞ揉めたのだろう。
祖父からの援助は寮に入っていることが前提であるため、寮を引き払ってアパートを借りている今現在、彼の懐事情はかなり厳しい。何故わざわざアパートに住んでいるかと言えば、理由はただひとつ。寮が狭いからだ。
1DKのアパートの部屋の真ん中に敷いた布団を囲むように、うず高く積み上げられた標本の数々。これが寮の部屋に入り切らなくなった、それだけだ。それどころか、この部屋の容量も既に限界が見え始めている。
奇妙な海の生物達に心惹かれるようになったのは、いつからだったか。それは親からの影響というにはあまりにも強すぎる欲求に思えた。
幼少の頃に読んだ図鑑の隅、子供が好みそうなコラムとして欄外に小さく載せられていた図版。
船乗りを惑わす人魚。
船を襲う巨大蛸。
そして、無害な獣のふりをして人を喰い殺す、海辺の妖馬。
それらを初めて見た時、彼の胸に湧き上がったのは懐かしさだった。まるで生まれる前から知っていたかのような郷愁に幼い彼は陶酔し、以来海辺に出かけては目に留まったものを拾って帰るようになった。
いつか、あの図版に描かれたモノに出逢いたい。
その存在を証明したい。
一度抱いたその願望は成長しても消えるどころか、知識が増えるほどに強くなっていった。
単眼の鮫や、鋏が三つある蟹や、不思議で不気味な姿をしたありとあらゆる海の生物。標本を作る知識を得てからは、打ち上げられたそれらを拾い、標本にしては棚に詰め込んだ。
そうして増え続けた異様な蒐集物は彼の居住スペースと生活費を圧迫するに至っているが、趣味というより自身の一部となってしまったこの行為をやめるという発想などあるはずもなく、彼の頭を占めるのは専ら、どうやってより多くの標本を部屋に詰め込むか、管理に適切な湿度と室温を保つには何が必要か、というような事柄であった。
――これが、この世界における藻噛叢馬という男。
かつてある世界で否定され、アンジニティに落とされた存在をイバラシティに紛れ込ませるために何者かが用意した、仮の姿。
辻褄合わせの仮初である彼自身は知る由もないが。
イバラシティを手に入れようと目論む侵略者の一体、それが彼の正体である。
***
狭間の世界に、巨大な馬が立っている。
艶のある青い毛並みに覆われた太い首を堂々と反らし、逞しい四肢からも海藻のような鬣からもとめどなく水を滴らせ、大きな蹄は地面をしっかりと踏みしめている。
「――まだだ」
人々の恐れによって澱み、深さを増していった海。今や人は海を恐れない。
かつての魔の海域、囁かれなくなった遭難譚。海への畏怖が産んだ幻想は、忘却によって死を迎える。そのはずだった。
「俺はここにいる」
ここは狭間。
現世と異界、現実と幻想の境界。ここなら、まだ、この姿を保つことができる。
「俺は、まだ、消えていない。死んでいない」
確かめるように呟く。
ここならまだ、声が届く。
この脚はまだ動く。硬い蹄も、整然と並んだ歯も、全盛期のままだ。
それどころか、この戦いに勝てば。取り戻すことができるのだ。懐かしい海を。
歓喜に毛皮を震わせて、蒼い馬が嘶いた。大きく首を仰け反らせて後脚で立ち上がり、頭部を振り下ろすように前脚で地面を踏み砕く。
その一瞬の間に、馬の姿は変化していた。
青い毛並みの首は人の胴部に変わり、不釣り合いに長い腕は土を掴むように地面に爪を立てている。体も腕も顔も、人の形に似た部分の肌は全て、赤く剥けたような悍ましい肉の色。俯いていた顔を上げると、変わらぬ色の鬣の間から人間の顔が現れる。
赤く光る目を持つその顔は。
獰猛に歯列を剥き出し、怒りと獣性を露わにしたその貌は。
藻噛叢馬という男によく似ていた。



ENo.570 安藤規雄 とのやりとり

ENo.909 スカリム・ヴェノケルコス とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。








駄石(50 PS)を購入しました。
駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
アンディ(570) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『不思議な投擲斧』を作製してもらいました!
⇒ 不思議な投擲斧/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
齊一(975) の持つ ItemNo.5 清刀 【心】 から防具『外套【霧雨】』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
スカリム(909) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議な謎肉スペアリブのロースト』をつくってもらいました!
⇒ 不思議な謎肉スペアリブのロースト/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
エキサイト を習得!
アクアヒール を習得!
アイスバインド を習得!
イレイザー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 I-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
アンディ(570) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
エディアンからのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ





[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



――夜明け前。潮騒の向こうに遠く、嘶きを聴いた気がした。
***
藻噛叢馬は創峰大学に通う学生であり、第二学部で海洋生物学を専攻する修士課程の二年生である。
学者だった両親は、彼が高校生の時にフィールドワーク中の事故で他界した。
それまで親族とは疎遠だったが、彼の祖父は代々続く学者の家の息子が大学にも行かず就職するなど恥であると考え、大学院までの学費とその間の最低限の生活費は援助すると一方的に告げた。彼としても特に異存はないのでありがたく受け取っているが、もし学者志望でなかったらさぞ揉めたのだろう。
祖父からの援助は寮に入っていることが前提であるため、寮を引き払ってアパートを借りている今現在、彼の懐事情はかなり厳しい。何故わざわざアパートに住んでいるかと言えば、理由はただひとつ。寮が狭いからだ。
1DKのアパートの部屋の真ん中に敷いた布団を囲むように、うず高く積み上げられた標本の数々。これが寮の部屋に入り切らなくなった、それだけだ。それどころか、この部屋の容量も既に限界が見え始めている。
奇妙な海の生物達に心惹かれるようになったのは、いつからだったか。それは親からの影響というにはあまりにも強すぎる欲求に思えた。
幼少の頃に読んだ図鑑の隅、子供が好みそうなコラムとして欄外に小さく載せられていた図版。
船乗りを惑わす人魚。
船を襲う巨大蛸。
そして、無害な獣のふりをして人を喰い殺す、海辺の妖馬。
それらを初めて見た時、彼の胸に湧き上がったのは懐かしさだった。まるで生まれる前から知っていたかのような郷愁に幼い彼は陶酔し、以来海辺に出かけては目に留まったものを拾って帰るようになった。
いつか、あの図版に描かれたモノに出逢いたい。
その存在を証明したい。
一度抱いたその願望は成長しても消えるどころか、知識が増えるほどに強くなっていった。
単眼の鮫や、鋏が三つある蟹や、不思議で不気味な姿をしたありとあらゆる海の生物。標本を作る知識を得てからは、打ち上げられたそれらを拾い、標本にしては棚に詰め込んだ。
そうして増え続けた異様な蒐集物は彼の居住スペースと生活費を圧迫するに至っているが、趣味というより自身の一部となってしまったこの行為をやめるという発想などあるはずもなく、彼の頭を占めるのは専ら、どうやってより多くの標本を部屋に詰め込むか、管理に適切な湿度と室温を保つには何が必要か、というような事柄であった。
――これが、この世界における藻噛叢馬という男。
かつてある世界で否定され、アンジニティに落とされた存在をイバラシティに紛れ込ませるために何者かが用意した、仮の姿。
辻褄合わせの仮初である彼自身は知る由もないが。
イバラシティを手に入れようと目論む侵略者の一体、それが彼の正体である。
***
狭間の世界に、巨大な馬が立っている。
艶のある青い毛並みに覆われた太い首を堂々と反らし、逞しい四肢からも海藻のような鬣からもとめどなく水を滴らせ、大きな蹄は地面をしっかりと踏みしめている。
「――まだだ」
人々の恐れによって澱み、深さを増していった海。今や人は海を恐れない。
かつての魔の海域、囁かれなくなった遭難譚。海への畏怖が産んだ幻想は、忘却によって死を迎える。そのはずだった。
「俺はここにいる」
ここは狭間。
現世と異界、現実と幻想の境界。ここなら、まだ、この姿を保つことができる。
「俺は、まだ、消えていない。死んでいない」
確かめるように呟く。
ここならまだ、声が届く。
この脚はまだ動く。硬い蹄も、整然と並んだ歯も、全盛期のままだ。
それどころか、この戦いに勝てば。取り戻すことができるのだ。懐かしい海を。
歓喜に毛皮を震わせて、蒼い馬が嘶いた。大きく首を仰け反らせて後脚で立ち上がり、頭部を振り下ろすように前脚で地面を踏み砕く。
その一瞬の間に、馬の姿は変化していた。
青い毛並みの首は人の胴部に変わり、不釣り合いに長い腕は土を掴むように地面に爪を立てている。体も腕も顔も、人の形に似た部分の肌は全て、赤く剥けたような悍ましい肉の色。俯いていた顔を上げると、変わらぬ色の鬣の間から人間の顔が現れる。
赤く光る目を持つその顔は。
獰猛に歯列を剥き出し、怒りと獣性を露わにしたその貌は。
藻噛叢馬という男によく似ていた。



ENo.570 安藤規雄 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.909 スカリム・ヴェノケルコス とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。







駄石(50 PS)を購入しました。
駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
アンディ(570) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『不思議な投擲斧』を作製してもらいました!
⇒ 不思議な投擲斧/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
タウラシアス 「そらよ。せいぜい大事に使うんだな」 |
齊一(975) の持つ ItemNo.5 清刀 【心】 から防具『外套【霧雨】』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
スカリム(909) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議な謎肉スペアリブのロースト』をつくってもらいました!
⇒ 不思議な謎肉スペアリブのロースト/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
スカリム 「こんな感じでどうかな?君の味覚はあの街と同じだろうか、それとも――」 |
エキサイト を習得!
アクアヒール を習得!
アイスバインド を習得!
イレイザー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 I-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
アンディ(570) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「1時間が経過しましたね。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャットで時間が伝えられる。
 |
エディアン 「ナレハテとの戦闘、お疲れ様でした! 相手を戦闘不能にすればいいようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「さてさて。皆さんにご紹介したい方がいるんです。 ――はぁい、こちらです!こちらでーっす!!」 |
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
エディアン 「陣営に関わらず連れて行ってくれるようですのでどんどん利用しましょー!! ドライバーさんは中立ってことですよね?」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
エディアン 「たくさん・・・ 同じ顔がいっぱいいるんですかねぇ・・・。 ここはまだ、分からないことだらけです。」 |
 |
エディアン 「それでは再びの1時間、頑張りましょう! 新情報を得たらご連絡しますね。ファイトー!!オーッ!!」 |
エディアンからのチャットが閉じられる――









ENo.1017
藻噛 叢馬



藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君、あんた
24歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人は特に気にしていない。
嫌いな食べ物は馬肉とホルモン。それ以外の肉は寧ろ好き。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳がない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
住まいは『コーポロザ111号室』。故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む青い馬。
または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■主な出没場所
コーポロザ(http://lisge.com/ib/talk.php?s=145)
海洋生物学専攻斑目研究室(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1296)
アンディの骨董屋(http://lisge.com/ib/talk.php?p=230)
■個人・交流ログまとめ
微睡む藻屑の幻想海(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1336)
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
46歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能︰"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
***
現在プロフ絵2種。
置きレス多めですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
自重しないついった:@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君、あんた
24歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人は特に気にしていない。
嫌いな食べ物は馬肉とホルモン。それ以外の肉は寧ろ好き。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳がない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
住まいは『コーポロザ111号室』。故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む青い馬。
または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■主な出没場所
コーポロザ(http://lisge.com/ib/talk.php?s=145)
海洋生物学専攻斑目研究室(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1296)
アンディの骨董屋(http://lisge.com/ib/talk.php?p=230)
■個人・交流ログまとめ
微睡む藻屑の幻想海(http://lisge.com/ib/talk.php?p=1336)
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
46歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能︰"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
***
現在プロフ絵2種。
置きレス多めですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
自重しないついった:@yaneura_coqua
25 / 30
0 PS
チナミ区
I-6
I-6















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な投擲斧 | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な謎肉スペアリブのロースト | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]活力10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]器用10(LV20) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 防具 | 20 | 防具作製と、防具への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| アイスバインド | 5 | 0 | 80 | 敵:水撃&凍結 |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 異形の体躯 (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / こか