<< 16:00~17:00




凪いだ心でいる。それだけが感想で、それだけが思考だった。
叩き伏せることができた侵略者と、本質は何も変わりはしないのかもしれない。少し、ほんの少しだけ変わったスタート地点から、歩み出す方向が違っていただけ。否定の世界を否定するため、あるいはなんとしてでもそこを抜け出すため、その歩みを進めて――残り半分。
強化された聴力と視力が、少しばかり後ろを行くもうひとつの集団を捉えている。
彼らは何か変わっただろうか。彼らはこの道程の中で、何か見つけただろうか。自分は見つけた。ようやくというべきか、実に灯台下暗しだった。
「先生」
それはいつの間にかこちらを追いかけてきていた。かつてのペット……まあ、ペットだったのだろう、同じ研究室で世話の当番を回していた生き物だったものは、今は体毛の色が自分と違う。つまり、別の所持者が何らかの思惑でこちらに放ってきたものだ。
パライバトルマリン、あるいは神の御使いは、今仕えている人間の色をよく表す。……と、いう結論になった……と、記憶している。本の世界で解き放ってから、もう二度と会うことはないと思っていたが、世界とはどうにもうまく行かないものだ。
「……あまり話をするつもりはないよ」
「うん、それはそうだと思う。ぼくのこと得体が知れないな、って思っているんでしょう」
「ああそうだとも。今のお前からは俺と同じにおいがするから」
比喩だ。要するに、今これを所持しているのは、知識探求に対して意欲があり、頭がよく、“わざわざこんなことをしてでも”この場所を知ろうとしている。迂闊に何かを曝け出すことは避けたい、と思っていた。それは今の状況にも言えることで、分断された上で引きずり回されて、引きずり回して、全てが上手くいかないことは当たり前だが、イラつく要素は複数たった。だがそれを前にしてもなお、自分の心は凪いでいる。不思議なことに。
ずっと懐に忍ばせている刃が、全てを語っている。いつでも自分を切り離せる。自分を放棄し、自分に呑ませ、新しい自分になる。たった一本握りしめただけで、こんなに余裕が生まれるなんて、とても。
「同じにおい。それは、要するに、探し求める人間だということ?」
「その物言いからしてそうだよ。俺のとこにいたときはそんなんじゃなかった」
「じゃあしょうがない。ぼくは生憎そういうもので、今は先生にだって強気だ。ぶっちゃけ先生のこと、先生って呼ばなくていいしね」
ついてきていることには気づいていた。けれど、別に話をする理由もなかった。向こうから何か仕掛けてくるまでは、何もしないと決めていた。
パライバトルマリンは、その特異性が故に、生物学的に下位の存在だったとしても警戒しなければならなかった。彼がわざわざ意思を持って出向いてくるということは、自分に用がある誰かがいるのだ。それ以外の理由で、わざわざ会いにくるようなことは絶対にない。そう、自分で言っていたのを記録している。
「じゃあそうしたらいい。どうしてわざわざ先生とか呼ぶんだ」
「今でも尊敬しているから。それは理由にならない?」
「……余計な知恵をつけたね、ほんと」
ない眼鏡を直しそうになる。この世界に現れるに当たって、眼鏡は不要なものだった。五感は強化され、ありとあらゆる力が増幅されている。視力は矯正せずとも遠くまで見通せたし、なんなら調節することさえできた。
ピントを合わせた先の生き物は、合わせる先の目が存在していない。それらしいところはあっても、それはただの模様だ。この生き物の感覚器官は触覚だけだ。
「先生。先生は、いかにも怪しいけれど、それしか頼れそうなものがないとき、それに手を伸ばす?」
「……」
瞑目する。
かつては振り払った手のことを思い出した。
「意地が悪い言葉回しをするね」
「先生もそうだと思うよ。ぼくは質問の答えを待ってる」
「……ったく。考える期限は?」
何かがある、と確かに思った。けれども、悪い予感はなかった。人間をやめた成れの果てにわざわざ縋ってくるようなことなのだから、どうせ相手だってろくでもない。恐らくこの解答も、出すまでの時間にほぼ猶予はない。
「うーん。あと三時間くらいで出してほしいかな」
「……はあ」
その通りだった。
瞳の奥は伺えない。存在しないものの奥は見れない。ただ、体毛の色だけを見ている。具体的にどこの人間、というのを割るには、情報量が足りないし、そもそもどこの誰が何をしようとしているかを確かめたところで、これが自分のもとに来た事実は覆らない。
要するに、もう何か大きなことが動いていて、そのためにこれを利用していて、自分にも何かしらの用がある。そういうことだ。
「考えさせる前に、今の持ち主くらいは明かしてもいいんじゃあないの。得体の知れないやつの相手はお断りだよ、それどころではないから」
「ふうん……?でも、絶対知っているよ。それでも?」
「それでもだ。あとで後悔するかそうじゃないか、くらいの違いしかない」
わざとらしく考え込むようなポーズを取って、それは言った。
「大日向深知。先生の、向こうの姿の先生だけど」
「いつ聞いても後悔する名前だよ」
圧縮されて送り込まれてくる名前のひとつだ。大日向深知、知識のためなら手段を選ばない蛮族。ある意味で理想的な研究者で、絶対同僚としては存在していてほしくない研究者。
若く優秀で、それでいて貪欲で強気と来れば、同じ世界の同じ時期に生きていたら。絶対にどこかでやり合うことになっていただろう。
それがパライバトルマリンを握っている、ということについて、少しだけ思考する。
彼女の目的は間違いなくこの狭間の世界にあり、そのためにこの生き物を利用していることは目に見えて明らかだ。“招待”がなければ踏み入ることも敵わない世界に、どうやってこれを送り込んできたのか、そもそもこの世界に何の用事があるのか――分からないことばかりだ。何を目的にして声を掛けてきたのか、そこから疑っている。
「まあ無理もないか。先生は大日向さんのことたぶん苦手だもんね」
「できたら関わりたくないのは確かだけど。目的が読めない相手とどうのこうのするのが嫌いなんだよ」
「ああ、それは簡単だよ、先生。先生も絶対納得するもん、自分がもう一度やらなきゃならないって」
「……なに?」
もしそれに表情があったのなら、ねっとりと笑っていたに違いない。
ただ愛らしく、小首を傾げることしかしないのだ。けれど、それは明確な意思を持っていた。
『望遠水槽の終点のために、先生は動くよ』

終点。つまり、どん詰まりの袋小路。かつて自分が陥ったどうしようもない状態。右に行けども左に行けども解はなく、前には進めず後ろには戻れない。追われに追われて、逃げることすら頭から抜け落ちてしまうのだ。その極限を味わったからこそ、分かる。
極限下にあるとき、ひとは何も分からない。そもそも、自分が極限下にいることすら感じることができない。あとから指摘されて、俯瞰して、それでようやく納得する。――例えばほんの十八時間前のように。
(何を考えているのだろうね)
三時間後と言えば、一度準備のために戻るタイミングだ。ゆるく首を傾げる。
あの場所ももう、安全圏ではなくなると聞いた。どこにいても、誰がどうしていても、皆等しくこの世界の理によって振り分けられる。それだけで済んでくれればよかったのに、時に何もかもうまくいかない。それでも、自分は落ち着いている。
「なあ、スズヒコ」
何を問われても。
「……どう思う?あのうさんくさい奴の通信も、さっきの通信も」
「どうも思わない。それが世界かゲームの理なんでしょう」
焦りに満ちている顔を見ても。
「……俺は、ナレハテになんかなるんなら、その前にここで死んでいいと思ってる」
訴えかけるような声を聞いていても。
「……そんな事あり得ないって言いたげだな」
当然そう思っていた。
絶対にありえない。させない。そう思っている。
「絶対無いって言いきれるのかよ。絶対なんて、無いんだろ?もしかあった時には俺は、迷いたくない」
「絶対はない。ならば可能性もないわけではない。俺は迷わないことを尊重する」
それが不安定になっていることが分かっていても。
「……最悪な事にだけは、なりたくねえんだ」
「最悪ねえ」
ここに来るまで、最悪なんていくつも転がっていた。それを俯瞰できるようになったのは、自分に余裕が生まれたからだ。まるでその時が来たときのエクジステロイドのように、自分はどこまでも冷静で平穏だ。
「……そもそも、俺は、あんたがまた狂っちまったら耐えられる自信が無い。もしそうなっても、あんたを殺して俺も死ぬつもりだ」
「できるならいくらでも。そうならないつもりだから抵抗はするけど」
いつの間にこんなに追い詰められていたのだろう。自分は彼を見ているが、彼は何も言わない。何も言わないということを良しとしていた責任?そんなわけはない。それで良しと言えなくなったから、こうして言いに来ているはずなのだから。
「……じゃあ、万が一、俺が駄目だと判断したら、すぐに全てを終わらせる。弁解も、抵抗もさせない」
「終わらせることができるならいくらでも。」
傘を荒れた大地に突き刺して、思わず両手を広げてしまった。そうしても今なら勝てるという自信が強くあった。それは相性とかいうものではなく、もっと根本的な、自分が大地に強く足をつけている、という自覚から来るものだった。
ここで終わることは本意ではない。だからこそ、あらゆる可能性を考慮する。自分がいたい場所はどこでもない。仮初の平穏でも、罪に塗れた大地でも、その狭間でも、どこでもない。
「……俺は、アンタの言葉を信じるよ。そんな事、ありえないんだろ?」
「そう、ありえないよ。俺は最後まで可能性を捨てないことにしたから。……あ、今暇なら手を貸してもらえる?」
「は?」
長く編んだ髪を抱え込んで、ひたひたと歩き出した。
フェデルタから何か言われても、その歩みを止めるつもりはなかった。ついてくるだろうと思っていたから。
翻るのは刃。
“俺”に咥えさせた長い三編みを、ざんばらに切っている。三編みのまま刃を入れさせているために、髪の毛を焼いてもいいことにした。そうでもしないと、武器にすらする髪に刃が通らない。
「……いいのか」
「仕上げは自分でするから」
何なら何かお守りにでもして仕込むかい、という冗談を飛ばせるくらい、自分は落ち着いている。今刃を入れている彼がどう思っているかは知らないが、どのみちこの髪の毛は使いみちがないなら“俺”が全てしまってしまう。
「いや、そうじゃなくて……」
「だから、焼いて切ったぶんもあとで俺がどうにかするっつってんの。具体的に言ったほうがいい?もうちょっと短くする」
もみあげの毛が巻き込まれないよう押さえながら、ばさばさと落ちていく髪の音を聞いている。例えるのならこれは罪だった。例えるのならこれは足枷だった。ずしりと重く引きずるように、自分から伸ばした。いつでも切ることができたはずなのに、そうしなかった。それは、自分に相応しい枷だと思っていたからだ。
故に、これはもういらないものだ。
「……ああ」
「何?」
どさり。
髪の束が落ち、すっかり軽くなった肩で振り向く。

「初めて会った頃みてえだ」
「クッサいこと言わないでよ」
獣がひときわ大きく鳴いた。



ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.32 羽 を破棄しました。
ItemNo.33 羽 を破棄しました。
ItemNo.16 毛 を破棄しました。
ItemNo.21 毛 を破棄しました。
順(39) に ItemNo.7 クリアグロリエバインド を手渡ししました。
ItemNo.27 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









メリーナ(646) から 150 PS 受け取りました。
百薬LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
付加LV を 5 DOWN。(LV50⇒45、+5CP、-5FP)
領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 10 UP!(LV50⇒60、-10CP)
順(39) により ItemNo.15 看板 から装飾『コンサーティナペンダント』を作製してもらいました!
⇒ コンサーティナペンダント/装飾:強さ327/[効果1]攻撃30 [効果2]- [効果3]-
順(39) の持つ ItemNo.32 ビーフ から料理『牛すき(ふきのとう添え)』をつくりました!
メリーナ(646) の持つ ItemNo.14 土筆 から魔香『耐疫香』をつくりました!
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.18 ビーフ から料理『チーズ付きミートソース』をつくりました!
フェデルタ(165) により ItemNo.17 リアリズムカレントブラスト に ItemNo.5 ポプラ を付加してもらいました!
⇒ リアリズムカレントブラスト/大砲:強さ306/[効果1]体力20 [効果2]追風15 [効果3]-【射程4】
春秋 楪(405) とカードを交換しました!
疾痛猶予 (パワフルヒール)

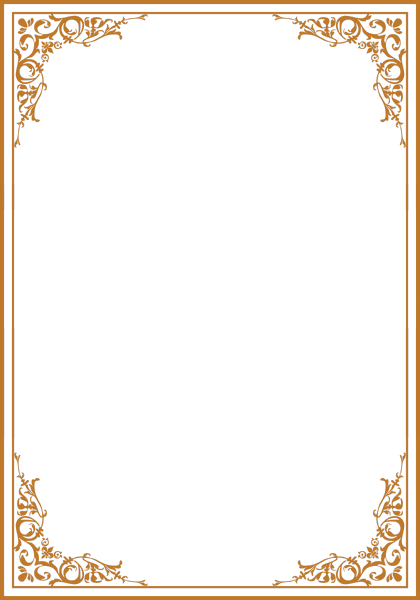
ディケイドミスト を研究しました!(深度0⇒1)
ディケイドミスト を研究しました!(深度1⇒2)
ディケイドミスト を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
マジックミサイル を習得!
アイスソーン を習得!
シャドウラーカー を習得!
ファゾム を習得!
瑞星 を習得!
ブロック を習得!
バックフロウ を習得!
タクシックゾーン を習得!
アバンダン を習得!
リストア を習得!
エリアグラスプ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は チャート を入手!
フェデルタ(165) は コベリン を入手!
スズヒコ(244) は 角閃石 を入手!
スズヒコ(244) は すごい石材 を入手!
スズヒコ(244) は 装甲 を入手!
スズヒコ(244) は 鱗 を入手!



マガサ区 R-2(山岳)に移動!(体調18⇒17)
マガサ区 S-2(森林)に移動!(体調17⇒16)
マガサ区 T-2(山岳)に移動!(体調16⇒15)
ミナト区 A-2(山岳)に移動!(体調15⇒14)
ミナト区 B-2(山岳)に移動!(体調14⇒13)
MISSION!!
マガサ区 S-2:スターロッジ が発生!
- 順(39) が経由した マガサ区 S-2:スターロッジ
- フェデルタ(165) が経由した マガサ区 S-2:スターロッジ
- スズヒコ(244) が経由した マガサ区 S-2:スターロッジ





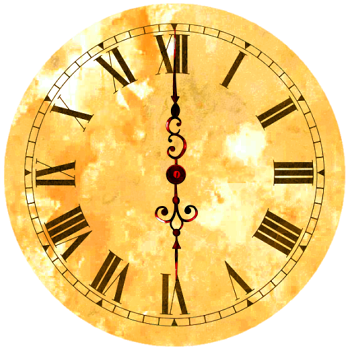
[870 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[443 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[190 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[380 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[296 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[204 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[143 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[61 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[123 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[108 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[129 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[12 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[37 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映るふたりの姿。
清々しい笑顔を見せるふたり。
ふたりの愚痴が延々と続き、チャットが閉じられる――











入口すぐ近くのベンチに、青年が座っている。

星空を背に、確かにそこにいるのだが何だか存在が希薄そうに感じる。
空がピキッと割れて、裂け目から小さな光が漏れ出てくる。
ジョシュアが弦楽器を奏でる。
綺麗な音色とともに、光が少しずつ消えてゆく。
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



























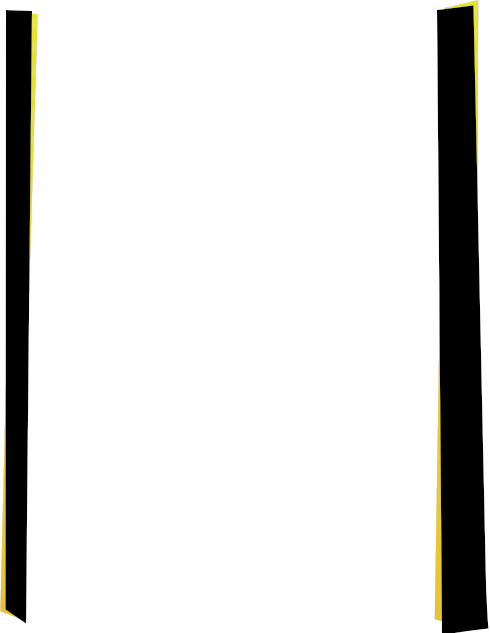
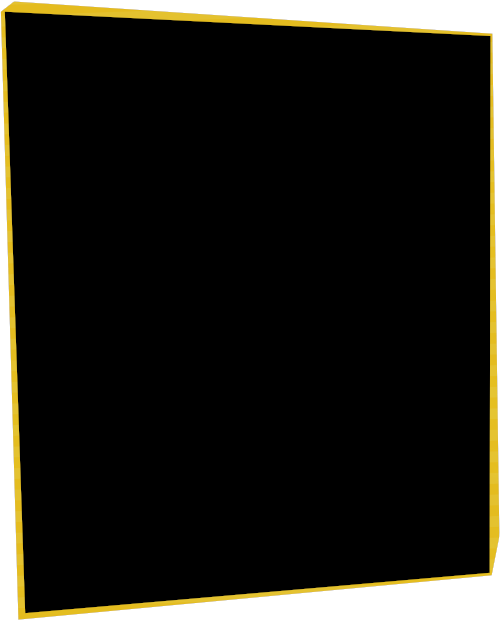





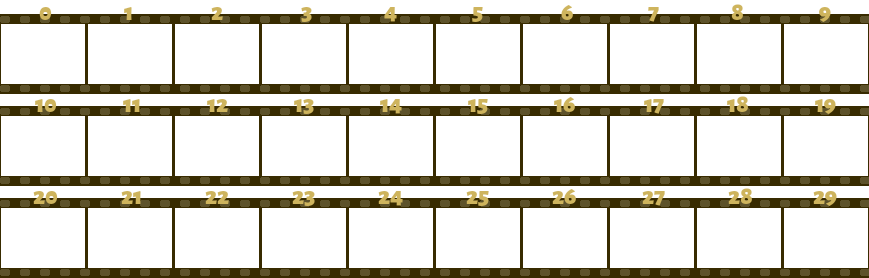









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



凪いだ心でいる。それだけが感想で、それだけが思考だった。
叩き伏せることができた侵略者と、本質は何も変わりはしないのかもしれない。少し、ほんの少しだけ変わったスタート地点から、歩み出す方向が違っていただけ。否定の世界を否定するため、あるいはなんとしてでもそこを抜け出すため、その歩みを進めて――残り半分。
強化された聴力と視力が、少しばかり後ろを行くもうひとつの集団を捉えている。
彼らは何か変わっただろうか。彼らはこの道程の中で、何か見つけただろうか。自分は見つけた。ようやくというべきか、実に灯台下暗しだった。
「先生」
それはいつの間にかこちらを追いかけてきていた。かつてのペット……まあ、ペットだったのだろう、同じ研究室で世話の当番を回していた生き物だったものは、今は体毛の色が自分と違う。つまり、別の所持者が何らかの思惑でこちらに放ってきたものだ。
パライバトルマリン、あるいは神の御使いは、今仕えている人間の色をよく表す。……と、いう結論になった……と、記憶している。本の世界で解き放ってから、もう二度と会うことはないと思っていたが、世界とはどうにもうまく行かないものだ。
「……あまり話をするつもりはないよ」
「うん、それはそうだと思う。ぼくのこと得体が知れないな、って思っているんでしょう」
「ああそうだとも。今のお前からは俺と同じにおいがするから」
比喩だ。要するに、今これを所持しているのは、知識探求に対して意欲があり、頭がよく、“わざわざこんなことをしてでも”この場所を知ろうとしている。迂闊に何かを曝け出すことは避けたい、と思っていた。それは今の状況にも言えることで、分断された上で引きずり回されて、引きずり回して、全てが上手くいかないことは当たり前だが、イラつく要素は複数たった。だがそれを前にしてもなお、自分の心は凪いでいる。不思議なことに。
ずっと懐に忍ばせている刃が、全てを語っている。いつでも自分を切り離せる。自分を放棄し、自分に呑ませ、新しい自分になる。たった一本握りしめただけで、こんなに余裕が生まれるなんて、とても。
「同じにおい。それは、要するに、探し求める人間だということ?」
「その物言いからしてそうだよ。俺のとこにいたときはそんなんじゃなかった」
「じゃあしょうがない。ぼくは生憎そういうもので、今は先生にだって強気だ。ぶっちゃけ先生のこと、先生って呼ばなくていいしね」
ついてきていることには気づいていた。けれど、別に話をする理由もなかった。向こうから何か仕掛けてくるまでは、何もしないと決めていた。
パライバトルマリンは、その特異性が故に、生物学的に下位の存在だったとしても警戒しなければならなかった。彼がわざわざ意思を持って出向いてくるということは、自分に用がある誰かがいるのだ。それ以外の理由で、わざわざ会いにくるようなことは絶対にない。そう、自分で言っていたのを記録している。
「じゃあそうしたらいい。どうしてわざわざ先生とか呼ぶんだ」
「今でも尊敬しているから。それは理由にならない?」
「……余計な知恵をつけたね、ほんと」
ない眼鏡を直しそうになる。この世界に現れるに当たって、眼鏡は不要なものだった。五感は強化され、ありとあらゆる力が増幅されている。視力は矯正せずとも遠くまで見通せたし、なんなら調節することさえできた。
ピントを合わせた先の生き物は、合わせる先の目が存在していない。それらしいところはあっても、それはただの模様だ。この生き物の感覚器官は触覚だけだ。
「先生。先生は、いかにも怪しいけれど、それしか頼れそうなものがないとき、それに手を伸ばす?」
「……」
瞑目する。
かつては振り払った手のことを思い出した。
「意地が悪い言葉回しをするね」
「先生もそうだと思うよ。ぼくは質問の答えを待ってる」
「……ったく。考える期限は?」
何かがある、と確かに思った。けれども、悪い予感はなかった。人間をやめた成れの果てにわざわざ縋ってくるようなことなのだから、どうせ相手だってろくでもない。恐らくこの解答も、出すまでの時間にほぼ猶予はない。
「うーん。あと三時間くらいで出してほしいかな」
「……はあ」
その通りだった。
瞳の奥は伺えない。存在しないものの奥は見れない。ただ、体毛の色だけを見ている。具体的にどこの人間、というのを割るには、情報量が足りないし、そもそもどこの誰が何をしようとしているかを確かめたところで、これが自分のもとに来た事実は覆らない。
要するに、もう何か大きなことが動いていて、そのためにこれを利用していて、自分にも何かしらの用がある。そういうことだ。
「考えさせる前に、今の持ち主くらいは明かしてもいいんじゃあないの。得体の知れないやつの相手はお断りだよ、それどころではないから」
「ふうん……?でも、絶対知っているよ。それでも?」
「それでもだ。あとで後悔するかそうじゃないか、くらいの違いしかない」
わざとらしく考え込むようなポーズを取って、それは言った。
「大日向深知。先生の、向こうの姿の先生だけど」
「いつ聞いても後悔する名前だよ」
圧縮されて送り込まれてくる名前のひとつだ。大日向深知、知識のためなら手段を選ばない蛮族。ある意味で理想的な研究者で、絶対同僚としては存在していてほしくない研究者。
若く優秀で、それでいて貪欲で強気と来れば、同じ世界の同じ時期に生きていたら。絶対にどこかでやり合うことになっていただろう。
それがパライバトルマリンを握っている、ということについて、少しだけ思考する。
彼女の目的は間違いなくこの狭間の世界にあり、そのためにこの生き物を利用していることは目に見えて明らかだ。“招待”がなければ踏み入ることも敵わない世界に、どうやってこれを送り込んできたのか、そもそもこの世界に何の用事があるのか――分からないことばかりだ。何を目的にして声を掛けてきたのか、そこから疑っている。
「まあ無理もないか。先生は大日向さんのことたぶん苦手だもんね」
「できたら関わりたくないのは確かだけど。目的が読めない相手とどうのこうのするのが嫌いなんだよ」
「ああ、それは簡単だよ、先生。先生も絶対納得するもん、自分がもう一度やらなきゃならないって」
「……なに?」
もしそれに表情があったのなら、ねっとりと笑っていたに違いない。
ただ愛らしく、小首を傾げることしかしないのだ。けれど、それは明確な意思を持っていた。
『望遠水槽の終点のために、先生は動くよ』

終点。つまり、どん詰まりの袋小路。かつて自分が陥ったどうしようもない状態。右に行けども左に行けども解はなく、前には進めず後ろには戻れない。追われに追われて、逃げることすら頭から抜け落ちてしまうのだ。その極限を味わったからこそ、分かる。
極限下にあるとき、ひとは何も分からない。そもそも、自分が極限下にいることすら感じることができない。あとから指摘されて、俯瞰して、それでようやく納得する。――例えばほんの十八時間前のように。
(何を考えているのだろうね)
三時間後と言えば、一度準備のために戻るタイミングだ。ゆるく首を傾げる。
あの場所ももう、安全圏ではなくなると聞いた。どこにいても、誰がどうしていても、皆等しくこの世界の理によって振り分けられる。それだけで済んでくれればよかったのに、時に何もかもうまくいかない。それでも、自分は落ち着いている。
「なあ、スズヒコ」
何を問われても。
「……どう思う?あのうさんくさい奴の通信も、さっきの通信も」
「どうも思わない。それが世界かゲームの理なんでしょう」
焦りに満ちている顔を見ても。
「……俺は、ナレハテになんかなるんなら、その前にここで死んでいいと思ってる」
訴えかけるような声を聞いていても。
「……そんな事あり得ないって言いたげだな」
当然そう思っていた。
絶対にありえない。させない。そう思っている。
「絶対無いって言いきれるのかよ。絶対なんて、無いんだろ?もしかあった時には俺は、迷いたくない」
「絶対はない。ならば可能性もないわけではない。俺は迷わないことを尊重する」
それが不安定になっていることが分かっていても。
「……最悪な事にだけは、なりたくねえんだ」
「最悪ねえ」
ここに来るまで、最悪なんていくつも転がっていた。それを俯瞰できるようになったのは、自分に余裕が生まれたからだ。まるでその時が来たときのエクジステロイドのように、自分はどこまでも冷静で平穏だ。
「……そもそも、俺は、あんたがまた狂っちまったら耐えられる自信が無い。もしそうなっても、あんたを殺して俺も死ぬつもりだ」
「できるならいくらでも。そうならないつもりだから抵抗はするけど」
いつの間にこんなに追い詰められていたのだろう。自分は彼を見ているが、彼は何も言わない。何も言わないということを良しとしていた責任?そんなわけはない。それで良しと言えなくなったから、こうして言いに来ているはずなのだから。
「……じゃあ、万が一、俺が駄目だと判断したら、すぐに全てを終わらせる。弁解も、抵抗もさせない」
「終わらせることができるならいくらでも。」
傘を荒れた大地に突き刺して、思わず両手を広げてしまった。そうしても今なら勝てるという自信が強くあった。それは相性とかいうものではなく、もっと根本的な、自分が大地に強く足をつけている、という自覚から来るものだった。
ここで終わることは本意ではない。だからこそ、あらゆる可能性を考慮する。自分がいたい場所はどこでもない。仮初の平穏でも、罪に塗れた大地でも、その狭間でも、どこでもない。
「……俺は、アンタの言葉を信じるよ。そんな事、ありえないんだろ?」
「そう、ありえないよ。俺は最後まで可能性を捨てないことにしたから。……あ、今暇なら手を貸してもらえる?」
「は?」
長く編んだ髪を抱え込んで、ひたひたと歩き出した。
フェデルタから何か言われても、その歩みを止めるつもりはなかった。ついてくるだろうと思っていたから。
翻るのは刃。
“俺”に咥えさせた長い三編みを、ざんばらに切っている。三編みのまま刃を入れさせているために、髪の毛を焼いてもいいことにした。そうでもしないと、武器にすらする髪に刃が通らない。
「……いいのか」
「仕上げは自分でするから」
何なら何かお守りにでもして仕込むかい、という冗談を飛ばせるくらい、自分は落ち着いている。今刃を入れている彼がどう思っているかは知らないが、どのみちこの髪の毛は使いみちがないなら“俺”が全てしまってしまう。
「いや、そうじゃなくて……」
「だから、焼いて切ったぶんもあとで俺がどうにかするっつってんの。具体的に言ったほうがいい?もうちょっと短くする」
もみあげの毛が巻き込まれないよう押さえながら、ばさばさと落ちていく髪の音を聞いている。例えるのならこれは罪だった。例えるのならこれは足枷だった。ずしりと重く引きずるように、自分から伸ばした。いつでも切ることができたはずなのに、そうしなかった。それは、自分に相応しい枷だと思っていたからだ。
故に、これはもういらないものだ。
「……ああ」
「何?」
どさり。
髪の束が落ち、すっかり軽くなった肩で振り向く。

「初めて会った頃みてえだ」
「クッサいこと言わないでよ」
獣がひときわ大きく鳴いた。



ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| フェデルタ 「……」 |
ItemNo.32 羽 を破棄しました。
ItemNo.33 羽 を破棄しました。
ItemNo.16 毛 を破棄しました。
ItemNo.21 毛 を破棄しました。
順(39) に ItemNo.7 クリアグロリエバインド を手渡ししました。
ItemNo.27 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
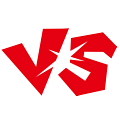 |
陸海空イバラ征服するなんて
|



メリーナ(646) から 150 PS 受け取りました。
百薬LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
付加LV を 5 DOWN。(LV50⇒45、+5CP、-5FP)
領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 10 UP!(LV50⇒60、-10CP)
順(39) により ItemNo.15 看板 から装飾『コンサーティナペンダント』を作製してもらいました!
⇒ コンサーティナペンダント/装飾:強さ327/[効果1]攻撃30 [効果2]- [効果3]-
 |
順 「大事に扱ってくださいね?」 |
順(39) の持つ ItemNo.32 ビーフ から料理『牛すき(ふきのとう添え)』をつくりました!
メリーナ(646) の持つ ItemNo.14 土筆 から魔香『耐疫香』をつくりました!
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.18 ビーフ から料理『チーズ付きミートソース』をつくりました!
フェデルタ(165) により ItemNo.17 リアリズムカレントブラスト に ItemNo.5 ポプラ を付加してもらいました!
⇒ リアリズムカレントブラスト/大砲:強さ306/[効果1]体力20 [効果2]追風15 [効果3]-【射程4】
| フェデルタ 「ん」 |
春秋 楪(405) とカードを交換しました!
疾痛猶予 (パワフルヒール)

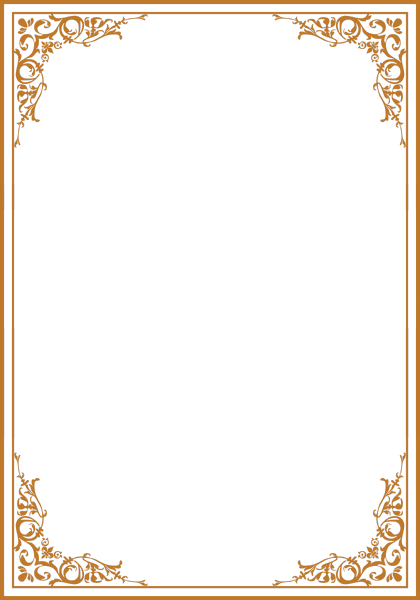
ディケイドミスト を研究しました!(深度0⇒1)
ディケイドミスト を研究しました!(深度1⇒2)
ディケイドミスト を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
マジックミサイル を習得!
アイスソーン を習得!
シャドウラーカー を習得!
ファゾム を習得!
瑞星 を習得!
ブロック を習得!
バックフロウ を習得!
タクシックゾーン を習得!
アバンダン を習得!
リストア を習得!
エリアグラスプ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は チャート を入手!
フェデルタ(165) は コベリン を入手!
スズヒコ(244) は 角閃石 を入手!
スズヒコ(244) は すごい石材 を入手!
スズヒコ(244) は 装甲 を入手!
スズヒコ(244) は 鱗 を入手!



マガサ区 R-2(山岳)に移動!(体調18⇒17)
マガサ区 S-2(森林)に移動!(体調17⇒16)
マガサ区 T-2(山岳)に移動!(体調16⇒15)
ミナト区 A-2(山岳)に移動!(体調15⇒14)
ミナト区 B-2(山岳)に移動!(体調14⇒13)
MISSION!!
マガサ区 S-2:スターロッジ が発生!
- 順(39) が経由した マガサ区 S-2:スターロッジ
- フェデルタ(165) が経由した マガサ区 S-2:スターロッジ
- スズヒコ(244) が経由した マガサ区 S-2:スターロッジ





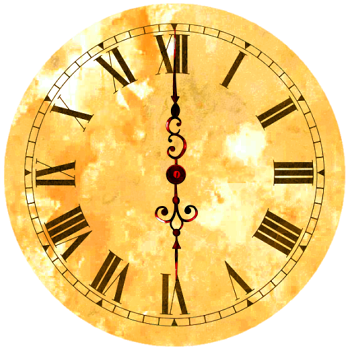
[870 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[443 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[190 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[380 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[296 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[204 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[143 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[61 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[123 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[108 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[129 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[12 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[37 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面に映るふたりの姿。
 |
エディアン 「・・・白南海さんからの招待なんて、珍しいじゃないですか。」 |
 |
白南海 「・・・・・いや、言いたいことあるんじゃねぇかな、とね・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・あぁ、そうですね。・・・とりあえず、叫んでおきますか。」 |
 |
白南海 「・・・・・そうすっかぁ。」 |
 |
白南海 「案内役に案内させろぉぉ―――ッ!!!!」 |
 |
エディアン 「案内役って何なんですかぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |
 |
白南海 「役割与えてんだからちゃんと使えってーの!!!! 何でも自分でやっちまう上司とかいいと思ってんのか!!!!」 |
 |
エディアン 「そもそも人の使い方が下手すぎなんですよワールドスワップのひと。 少しも上の位置に立ったことないんですかねまったく、格好ばかり。」 |
 |
白南海 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・いやぁすっきりした。」 |
 |
エディアン 「・・・どうもどうも、敵ながらあっぱれ。」 |
清々しい笑顔を見せるふたり。
 |
白南海 「・・・っつーわけだからよぉ、ワールドスワップの旦那は俺らを介してくれていいんだぜ?」 |
 |
エディアン 「ぶっちゃけ暇なんですよねこの頃。案内することなんてやっぱり殆どないじゃないですか。」 |
 |
エディアン 「あと可愛いノウレットちゃんを使ってあんなこと伝えるの、やめてくれません?」 |
 |
白南海 「・・・・・もういっそ、サボっちまっていいんじゃねぇすか?」 |
 |
エディアン 「あーそれもいいですねぇ。美味しい物でも食べに行っちゃおうかなぁ。」 |
 |
白南海 「うめぇもんか・・・・・水タバコどっかにねぇかなー。あーかったりぃー。」 |
 |
エディアン 「かったりぃですねぇほんと、もう好きにやっちゃいましょー!!」 |
 |
白南海 「よっしゃ、そんじゃブラブラと探しに――」 |
ふたりの愚痴が延々と続き、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



マガサ区 S-2 周辺
スターロッジ
海と星空に囲まれたスターロッジ。スターロッジ
入口すぐ近くのベンチに、青年が座っている。

ジョシュア
銀色の長髪に青い瞳。
旅人風の格好をしていて、大きな弦楽器を持っている。
旅人風の格好をしていて、大きな弦楽器を持っている。
 |
ジョシュア 「初めまして、私はジョシュアという・・・・・詩人?とでも。 唄うことは少ないんだけどね、いろいろな世界の物語を追っては楽しんでいるんだ。」 |
星空を背に、確かにそこにいるのだが何だか存在が希薄そうに感じる。
 |
ジョシュア 「ここにも、小さな物語がひとつ・・・・・と、来てみたんだけどね。 どうも折角の物語を邪魔するものたちがね・・・」 |
 |
ジョシュア 「・・・・・ほら、まただ。」 |
空がピキッと割れて、裂け目から小さな光が漏れ出てくる。
 |
ジョシュア 「こら・・・ここには遊びに来てはいけないよ。この世界については、・・・ナンセンスだ。」 |
ジョシュアが弦楽器を奏でる。
綺麗な音色とともに、光が少しずつ消えてゆく。
 |
ジョシュア 「・・・すべては戻せないね。形になるか、役を得る前に対処したほうがいい。 面倒をかけてすまないね。」 |
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
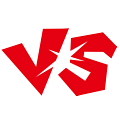 |
立ちはだかるもの
|

| 665 | 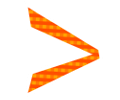 |
452 |
1st
フェデルタ


フェデルタ
2nd
小さな光の玉


小さな光の玉

3rd
小さな光の玉


小さな光の玉

4th
小さな光の玉


小さな光の玉

5th
小さな光の玉


小さな光の玉

6th
小さな光の玉


小さな光の玉

7th
小さな光の玉


小さな光の玉

8th
小さな光の玉


小さな光の玉

9th
小さな光の玉


小さな光の玉

10th
スズヒコ


スズヒコ
11th
順


順


ENo.244
鈴のなる夢

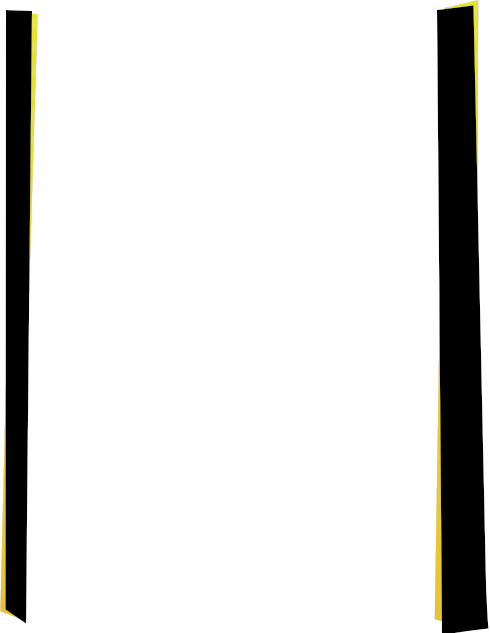
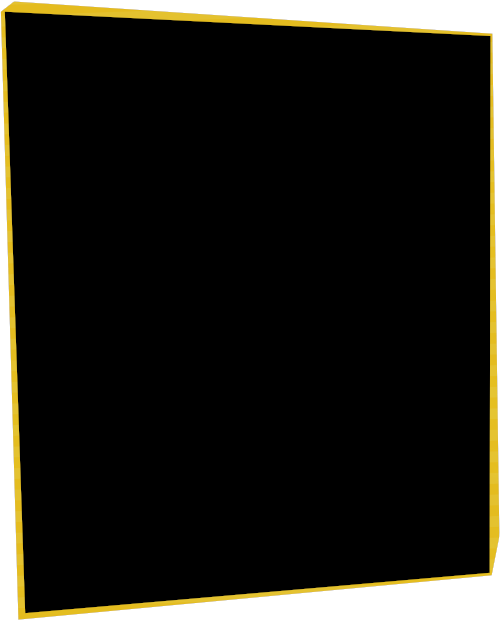
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
13 / 30
978 PS
ミナト
B-2
B-2







痛撃友の会
7
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
1
アイコン60pxの会
1
#片道切符チャット
#交流歓迎
2
アンジ出身イバラ陣営の集い
3
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
3
カード報告会
4
とりあえず肉食う?
4



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | 閃光10 | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | 角閃石 | 素材 | 40 | [武器]連撃35(LV70)[防具]閃撃35(LV80)[装飾]耐地35(LV65) | |||
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||
| 8 | 火焔茸 | 素材 | 35 | [武器]猛毒30(LV70)[防具]反毒35(LV75)[装飾]舞衰30(LV70) | |||
| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | 耐疫15 | - | |
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | 風柳10 | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | バンブーエディトリアン | 防具 | 300 | 加速20 | 活力30 | - | |
| 15 | コンサーティナペンダント | 装飾 | 327 | 攻撃30 | - | - | |
| 16 | 装甲 | 素材 | 35 | [武器]全護25(LV55)[防具]防御35(LV75)[装飾]耐災30(LV60) | |||
| 17 | リアリズムカレントブラスト | 大砲 | 306 | 体力20 | 追風15 | - | 【射程4】 |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 21 | 鱗 | 素材 | 20 | [武器]朦朧25(LV55)[防具]反水30(LV60)[装飾]耐火25(LV45) | |||
| 22 | 生姜焼き | 料理 | 109 | 攻撃13 | 防御13 | 増幅13 | |
| 23 | レッドバーンビブリオ | 薬箱 | 81 | 耐疫15 | 耐疫15 | - | |
| 24 | |||||||
| 25 | 串焼き | 料理 | 109 | 攻撃12 | 防御12 | 増幅12 | |
| 26 | 装甲 | 素材 | 35 | [武器]全護25(LV55)[防具]防御35(LV75)[装飾]耐災30(LV60) | |||
| 27 | |||||||
| 28 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 29 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 30 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 31 | すごいお魚 | 食材 | 30 | [効果1]活力30(LV25)[効果2]敏捷30(LV35)[効果3]強靭30(LV45) | |||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 30 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 30 | 呪詛/邪気/闇 |
| 変化 | 20 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 45 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 60 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 10 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 8 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| フィーバー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 6 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 6 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 15 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 6 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |
| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| リストア | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+環境変調を守護化 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 7 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 | |
| イラプション | 5 | 0 | 180 | 敵列:地撃+敵味全:火撃&炎上 | |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| グレイシア | 8 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| ウィザー | 5 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |
| サモン:ビーフ | 7 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 | |
| イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 | |
| ドレインライフ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&MHP奪取 | |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 | |
| グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 | |
| コンフィデンス | 6 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |
| スノーホワイト | 5 | 0 | 200 | 敵4:水痛撃&朦朧 | |
| ディープブルー | 5 | 0 | 200 | 敵:水撃&水特性増 | |
| バーニングカード | 5 | 0 | 80 | 敵3:火撃+自:強制炎上 | |
| ディケイドミスト | 5 | 1 | 300 | 敵全:AG減(4T)&腐食+味全:DX増(4T)&腐食 | |
| タイダルウェイブ | 5 | 0 | 330 | 敵:5連鎖水撃&DX・AG減(2T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 瘴気 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘離脱前】敵6:猛毒・麻痺・衰弱 | |
| 肉体変調特性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
| 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 | |
| 凍縛陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど凍縛LV増 | |
| 治癒領域 | 8 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 凍結耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:凍結耐性増 | |
| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |
| 腐食耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:腐食耐性増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |
| 生殺与奪 | 5 | 6 | 0 | 【攻撃命中後】対:火撃+対:水撃&味傷:HP増 | |
| 星火燎原 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】敵味炎:粗雑火撃&炎上奪取&自:炎上をAT化 | |
| 火霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:魔術LVが高いほどSP・火特性増 | |
| 水霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:命術LVが高いほどSP・水特性増 | |
| 闇霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |
| 千変万化 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |
| 火特性回復 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:火属性スキルのHP増効果に火特性が影響 | |
| 魔香作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で料理「魔香」を選択できる。魔香は体調が回復せず効果3しか付加されないが、食事に指定しても消費されない。 |
最大EP[25]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 | |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
|
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
|
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
|
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
|
ギフトカード (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |
5 | 500 | 自:エンペラー召喚 | |
|
余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター) |
0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 | |
|
フリーリィ・スカイシー・ダイブ (ワールウィンド) |
0 | 200 | 敵傷7:風撃 | |
|
血眼 (ブラッドアイズ) |
0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
|
スミの炭になりたい (ミゼラブルメモリー) |
2 | 200 | 敵:6連鎖SP闇撃 | |
|
疾痛猶予 (パワフルヒール) |
0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]タイダルウェイブ | [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]クリエイト:モンスター |
| [ 3 ]プチメテオカード | [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]グラトニー |
| [ 3 ]ディケイドミスト | [ 3 ]クリエイト:コーラス | [ 3 ]クリエイト:メガネ |
| [ 3 ]ミゼラブルメモリー | [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]プロテクション |
| [ 3 ]ゴッズディサイド | [ 3 ]フレイムインパクト | [ 3 ]アブソーブ |
| [ 3 ]イディオータ | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]フィジカルブースター |

PL / 紙箱みど











































