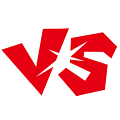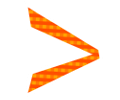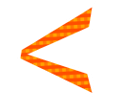<< 15:00~16:00




力が解放されていく。それは大日向が知り得なかったことで、世界は流動的である証左だった。世界構築システムの収集も仕事である以上、それは見過ごせない事象だった。
かの狭間へ送り込んだパライバトルマリン曰く、【鈴のなる夢】自体は安定していて、いつでも問いかければ協力を仰げそうである、ということだった。あとは機を見、適切な駒を動かせば良い。大日向は自在に世界を跨ぐ術を持たないが、持っている男とは偶然にも知古であった。ユッカ・ハリカリだ。
“誰でもない”、故に誰にでもなれる。ありとあらゆる世界の可能性を殺し、観測しうる範囲の平行世界の全ての己を、たったひとりに集約させた異界観測学の権威――と言うには人格に難がありすぎて、実績もどこにも出ていないが故に認められていない。正確に述べるのなら、彼が出さないのだ。仮に彼の研究が表に出ようものなら、とんでもない革新が起こる。そしてこの面倒くさがりは、それをよしとしていない。
ほんの少しの聞きかじりによれば、自分たちが元々いた世界は上下の積層構造を成していて、故に上から転げ落ちてきやすいのだという。横に連なっている場合もあれば、ねじれの位置にある場合もあり、一概にどうとは言えず、そして理論は自分のいる世界から離れるほど、通用しない。故にハリカリはごく小さな世界に店舗を構え、それごと移動してしまうのだ。いつだって自分の世界の理論の元にあれば、何もかもがほとんど思いのままだ。もちろんそれには欠点もあり、ハリカリは基本的にそこから出ない。世界のさらに上位にある神々により、世界は常に管理されていて、滅んだ――文明がなくなったと判断されたり、災害に襲われたりした――世界は、それごと消されてしまう。ごく小さな世界の中に一人で収まるということは、“外”に出た瞬間居場所を失うということに等しい。
要するに、あまりにも完璧な引きこもりになる代わり、あらゆる自由を失ったのだ。大日向から言わせればそうで、彼はまた別の表現をするだろう。好みは人それぞれだ。
「次のシークエンスへ移る。幸いなことに【透翅流星飛行】はスムーズに捕縛され……まあまだよからぬ可能性は捨てきれないが、一旦脇に置いていいと判断した」
「はい」
「データ回収等、まだありますが……」
「話はつけてある。忘れずに甘味を持って出向け」
久々に大日向研のメンバーがずらりと揃っている。大日向が外に出れない分、彼らにはあちらこちらに走り回ってもらっているからだ。神に渉外するものがあれば、データ解析を行うものもいるし、土地の情報を集めるものもいる。
「さて。今回全員を揃えたのには理由がある」
「はいはーい!あれですね!!」
「紀野」

はしゃぐな、と窘められている一番年下の学生が次のキーになる。
打倒すべき怪異は三体いて、そのうちの一体は神の気まぐれにより捕縛された。そのうちの一体は今も街を歩いているだろう。最後の一体――【望遠水槽の終点】だけが、不気味なほどに沈黙を守っている。
「かの世界に【望遠水槽の終点】がいるのであれば。こちらにそれに対応するヒトがいるはずだ、それは分かるな」
「はい!!仮初の姿……アレッでもそれってつまり堕ちているということなのでは」
「そうだ。今のところそのように推測している」
世界同士の侵略戦争。かの狭間はその試合会場で、パライバトルマリン曰く『地形すら異なり荒れ果てている』。陸だった場所が水場になり、その逆もまた然り。歩みは厳しく、よくわからないモンスターも出る。時には侵略相手と斬り結ぶこともあるらしい、三十六時間というにはあまりにも圧縮された時間、吉野暁海の感じた何週間かが圧縮され、【鈴のなる夢】に届けられているはずだ。そんな空間で報告上は“それなりに”正気を取り戻してくれたのだから、感謝して然るべきだろう。もちろんその時が来たらの話だが。
「【望遠水槽の終点】には謎が多い。まず何故いるのか?何故【終点】なのか?【鈴のなる夢】との関連性は何か?」
怪異も神秘も等しく、その名前から能力を読み取ることができる。名付けは固定する行為であり、そして呪いだからだ。名もない事象、不明不可思議を一部分でも固定し、それを足掛かりにして攻略する。断崖絶壁に一段ずつはしご、あるいは階段として機能を持つことのできる金属を刺していくように、外堀りを埋め、こちらの定義を強引にでも当てはめるのだ。名付けにはそれほどの意味がある。故に慎重になるか、名乗りを待つべきだというのが通例だった。
【望遠水槽の終点】には、その通例が通用しない。
「……あれは【哀歌の行進】がそう呼んでいただけかと思っていたのですが」
「名がないよりマシだ。そこに何が潜んでいようとな」
会ったこともなければ会話を交わしたこともない。そもそも全く興味はないと言い張るくせに、【哀歌の行進】はそれを【望遠水槽の終点】と称した。年頃の髪の長い女、虚ろな目、そしてあてもなく彷徨い続けているということまで告げて。
「ホイホイ釣られに行くようなものではないんですか、【哀歌の行進】に」
「全くもってそうだ。だが、奴も今は決定打を欠いている」
「……ああ、あの神のおかげですか」
理由は不明だが、【哀歌の行進】はひどく例の神を嫌っており、ここ最近は周辺で見かけることすらなくなっている。紫筑にいたころは常々人の邪魔をするためだけに些細なトラブルを起こしては人を動かしていたのに、だ。本来神の存在するレイヤーは怪異と同一になることはないから、畏れているのであれば納得はできる。畏れているのなら、もっとらしく振る舞うはずだ。それが大日向の持論であり、その通りに考慮するなら、この世界自体を放棄しているはずだった。
そもそも【哀歌の行進】という存在自体がイレギュラーの塊で、故にそれを狩ろうとしている。あるいは力を削ごうとしている。等しいと証明が可能なものが、同じ世界にあってはならない。大日向を始めとする神秘研究における基本原則であり、頻繁に出没するドッペルゲンガーに対する基本対応の仕方だ。自分の姿を見ると死んでしまうのであれば、先にその自分を倒せば良い。自分のドッペルゲンガーを見ると死ぬということ自体が俗説で、学びさえあれば恐れる必要はなにもないが、全ての人が神秘や怪異に興味を持っているわけではない。専門家とはそのために存在している。
「望遠水槽とは厳密に定義されたものではないが、おおよその想像はつく。水槽という時点でな。そうだろう」
「はいっめっちゃ分かります!だからあたしですね!!」
「……正直他にも向いている人間はいたと思うんですが、何故?」
「クレールパイセンはもっとあたしに優しくしてくれてもいいと思うんスけど!?」
「そこを突かれると痛いな。だが陸羽も手を回せんと来てはどうしようもない」
水槽。すなわち水族館。
紫筑大学第四学群神秘研究科には海の神秘や怪異に特化した部門が存在し、人魚研究科のある陸羽大学との連携を強く推し進めている。神秘・怪異学の総合が紫筑なら、人魚学に特化しているのが陸羽大学で、人魚ゲノムデータベースをアルモーグ大学との連名プロジェクトで構築し、今まさに人魚学のトップに存在している。そこから人員を借りてくるのが最も早かったが、あいにくその手は使えなかった。彼らは今子供の人魚の観察と観測に忙しい。
であれば、自分の手元の手札で代用するしかない。最も海に近く、魚に近いのは紀野いずもの能力だ。多少の難があっても、そのためにサポート要員を用意している。遠隔サポートの二ノ平、戦闘サポートのクレール、移動サポートの宮城野。可能性を正しい方向に導きたいのであれば、そこに投資を惜しむべきではない。
「……チッ。陸羽が無理ならうちのラボも無理か」
「何かあったんスかね?」
「お前はもうちょっと情報にアンテナを立てろ」
「そう貶めても何も出んぞ、クレール。もうお前の仕事は分かったろう」
視線がごく一瞬交わった。
気づく上級生、気づかない下級生。明確に出る差を見、大日向は笑う。
「……はいはい承知。要項をまとめておいてください」
「もう少し後になる。まず気づいてもらう必要があるのでな」
では解散、という鶴の一声に、学生たちが散り散りになっていく。
同じ場所をずっと回っている。それは本能で感じていたが、出方も何も分からなかった。
ここがどこで、わたしが誰か、何もわからないまま歩き続けている。こんなどん詰まりの間隔は、いつかに味わったようなものの気がしていた。
歩けど歩けど先はなく、鮮やかな青色と魚影だけが続いている。大きな貝が口を開け、そこから盛んに泡が立ち上っていた。壁沿いに歩いているはずなのに、どこにも辿り着かない。辿り着けない。
『迷っているのか?』
「……」
知らない男の人の声だった。男の人は怖かったから、自然と距離を取ってしまった。距離を取っても、視界には青しかない。
『いいのさ、そのままで。外は怖いところだ』
「……わたし……」
わたしは誰。
言葉は泡にすらならずに消え、ただ虚空を見つめている。
外は怖い。怖いところだ。隣の国に行ってしまった父と姉のことは何も分からず、母は病で死んでしまった。ひとりで生きていくのに、外の世界は恐ろしすぎた。
だから、そう、
『ここは誰にも邪魔されない狭間。そして向こうには、望んだ平和な世界がある。簡単なことだ、勝ち取ればいい。できるだろう?』
「わたし、」
『武器を使えるのだから。』
血の臭い。むせ返るかのごとき死の臭い。そうしている限り永遠についてきて、獣ではなく人のものへ塗り替えられていった、錆びた鉄の臭い。
初めて己の両手を見て、“わたし”はびっくりしてしまった。それは人の形こそしていたが、青く透けていた。そこにべったりと血が張り付いていた。
『さあ、ここを終点としよう。君という可能性の不幸せの歩みの。そして、ひとつ前に進みたまえ。そうすれば活路は見えるだろう。』
誰かが甘く夢のような言葉で囁いてくる。
わたしは、従っていいのだろうか?わたしはここで立ち止まっていいのだろうか?わたしには行かなければいけない場所があるのではないか?
いけない。それ以上いけない。わたしはこの言葉を聞いてはいけない。
「――触らないで」
貝が閉じる。
青い目がぎらりと光り、全てを追い出す。拒む。能力によって生み出される強固で絶対な防御、そして拒絶。

わたしはずっとひとりだった。

深く、深く、潜っていく。落ちていく。子供は溺れた時、何が起こったのかわからないまま静かに沈んでいくらしい。そんなことを思い出している自分も、何が起こっているのか分かっていないのだろう。
深く、深く――堕ちていく。堕ちていく。誰も助けてくれなかった。周りで見ているだけだった。わたしはどうしようもなく不器用で、人付き合いができなかった。わたしは何もできなかった。わたしは、わたしに、罰を与えたかった。
不出来なわたしに。誰の期待にも答えられないわたしに。何も救えないわたしに。この世にいるべきではなかったわたしに。
一粒零れた涙がどこかに落ちた瞬間、視界は真っ赤に染まった。ああ、これがきっとわたしへの罰だ。ようやく不出来なわたしを罰してくれる誰かが現れたのだ。卑怯なわたしを攻め落とす正義の剣が、わたしを無限に突き刺してくれる。
そのはずだったのに。




ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.20 ロールキャベツトマト煮込み を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 増幅10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








ユキ(424) に 100 PS 送付しました。
魔術LV を 25 DOWN。(LV30⇒5、+25CP、-25FP)
変化LV を 10 DOWN。(LV30⇒20、+10CP、-10FP)
呪術LV を 30 UP!(LV0⇒30、-30CP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
順(39) により ItemNo.23 腐肉 から薬箱『レッドバーンビブリオ』を作製してもらいました!
⇒ レッドバーンビブリオ/薬箱:強さ81/[効果1]耐疫15 [効果2]- [効果3]-
順(39) の持つ ItemNo.31 ビーフ から料理『牛肉のとろとろ煮込み』をつくりました!
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.32 お野菜 から料理『冷やし茄子のペースト』をつくりました!
ユキ(424) により ItemNo.22 お肉 から料理『生姜焼き』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 5 2 3 = 10 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ 生姜焼き/料理:強さ109/[効果1]攻撃13 [効果2]防御13 [効果3]増幅13
ユキ(424) により ItemNo.25 お肉 から料理『串焼き』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 4 2 1 = 7 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ 串焼き/料理:強さ109/[効果1]攻撃12 [効果2]防御12 [効果3]増幅12
フェデルタ(165) により ItemNo.14 バンブーエディトリアン に ItemNo.15 公孫樹 を付加してもらいました!
⇒ バンブーエディトリアン/防具:強さ300/[効果1]加速20 [効果2]活力30 [効果3]-
ItemNo.23 レッドバーンビブリオ に ItemNo.24 腐肉 を付加しました!
⇒ レッドバーンビブリオ/薬箱:強さ81/[効果1]耐疫15 [効果2]耐疫15 [効果3]-
スミ(532) とカードを交換しました!
スミの炭になりたい (ミゼラブルメモリー)
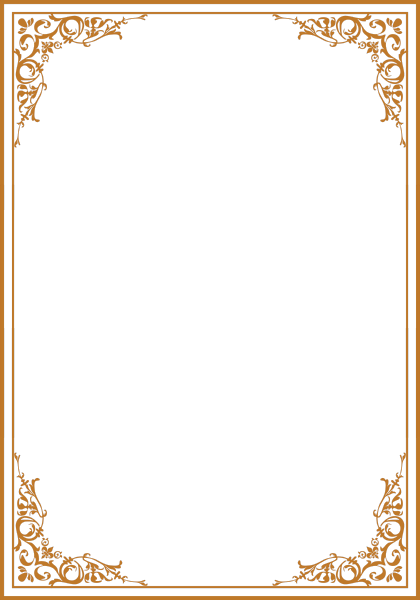
タイダルウェイブ を研究しました!(深度0⇒1)
タイダルウェイブ を研究しました!(深度1⇒2)
タイダルウェイブ を研究しました!(深度2⇒3)
カース を習得!
ヒールポーション を習得!
ダークフレア を習得!
フィーバー を習得!
ボロウライフ を習得!
アクアリカバー を習得!
ラトゥンブロウ を習得!
ポイズン を習得!
デッドライン を習得!
ウィークネス を習得!
クイックレメディ を習得!
ダークネス を習得!
ファーマシー を習得!
ディープフリーズ を習得!
水特性回復 を習得!
敗柳残花 を習得!
瘴気 を習得!
肉体変調特性 を習得!
闇の祝福 を習得!
凍縛陣 を習得!
ウィザー を習得!
ダウンフォール を習得!
ドレインライフ を習得!
腐食耐性 を習得!
ファルクス を習得!
スノーホワイト を習得!
闇霊力 を習得!
ディケイドミスト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は 看板 を入手!
フェデルタ(165) は 欠けた刃 を入手!
スズヒコ(244) は 看板 を入手!
スズヒコ(244) は 鉄板 を入手!
フェデルタ(165) は 毒液+3 を入手!
順(39) は 鉄板 を入手!



マガサ区 N-3(森林)に移動!(体調22⇒21)
マガサ区 O-3(森林)に移動!(体調21⇒20)
マガサ区 O-2(草原)に移動!(体調20⇒19)
マガサ区 P-2(山岳)に移動!(体調19⇒18)
マガサ区 Q-2(山岳)に移動!(体調18⇒17)






[871 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[441 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[177 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[377 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[286 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[199 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[137 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[56 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[122 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[92 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[90 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[83 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[0 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[8 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――

チャットにノウレットが現れる。
・・・が、どうも雰囲気が異なっている。
チャットが閉じられる――











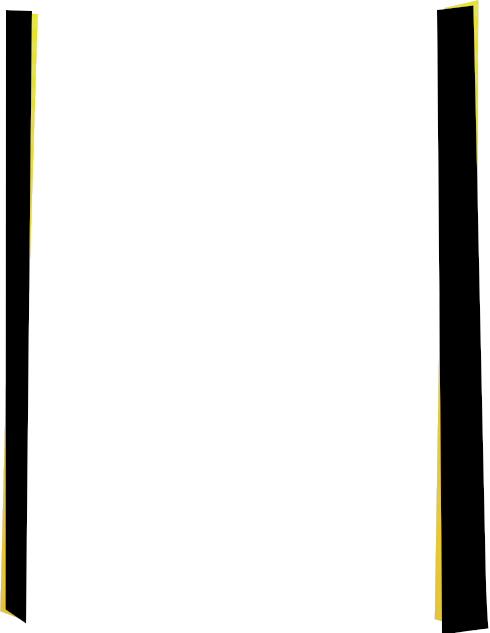
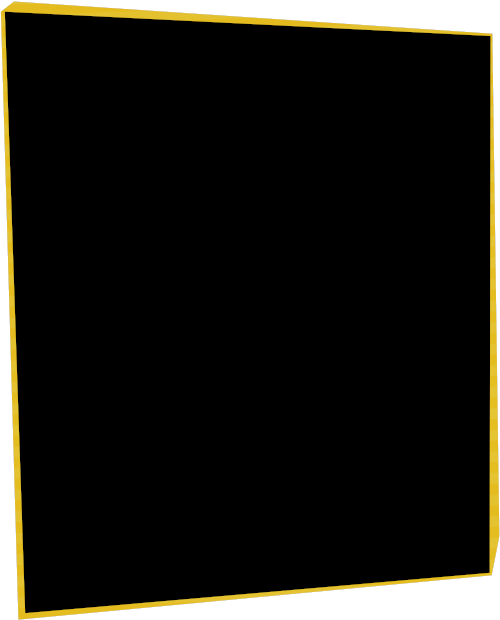





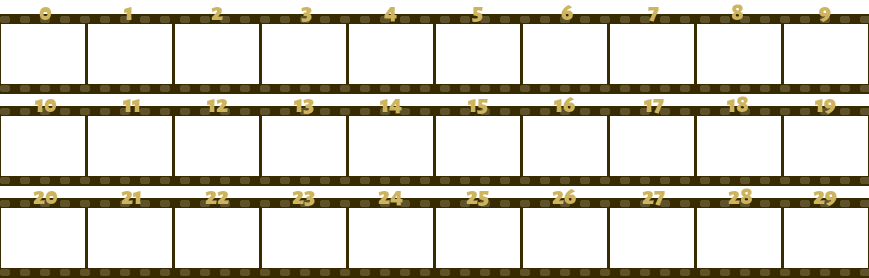









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



力が解放されていく。それは大日向が知り得なかったことで、世界は流動的である証左だった。世界構築システムの収集も仕事である以上、それは見過ごせない事象だった。
かの狭間へ送り込んだパライバトルマリン曰く、【鈴のなる夢】自体は安定していて、いつでも問いかければ協力を仰げそうである、ということだった。あとは機を見、適切な駒を動かせば良い。大日向は自在に世界を跨ぐ術を持たないが、持っている男とは偶然にも知古であった。ユッカ・ハリカリだ。
“誰でもない”、故に誰にでもなれる。ありとあらゆる世界の可能性を殺し、観測しうる範囲の平行世界の全ての己を、たったひとりに集約させた異界観測学の権威――と言うには人格に難がありすぎて、実績もどこにも出ていないが故に認められていない。正確に述べるのなら、彼が出さないのだ。仮に彼の研究が表に出ようものなら、とんでもない革新が起こる。そしてこの面倒くさがりは、それをよしとしていない。
ほんの少しの聞きかじりによれば、自分たちが元々いた世界は上下の積層構造を成していて、故に上から転げ落ちてきやすいのだという。横に連なっている場合もあれば、ねじれの位置にある場合もあり、一概にどうとは言えず、そして理論は自分のいる世界から離れるほど、通用しない。故にハリカリはごく小さな世界に店舗を構え、それごと移動してしまうのだ。いつだって自分の世界の理論の元にあれば、何もかもがほとんど思いのままだ。もちろんそれには欠点もあり、ハリカリは基本的にそこから出ない。世界のさらに上位にある神々により、世界は常に管理されていて、滅んだ――文明がなくなったと判断されたり、災害に襲われたりした――世界は、それごと消されてしまう。ごく小さな世界の中に一人で収まるということは、“外”に出た瞬間居場所を失うということに等しい。
要するに、あまりにも完璧な引きこもりになる代わり、あらゆる自由を失ったのだ。大日向から言わせればそうで、彼はまた別の表現をするだろう。好みは人それぞれだ。
「次のシークエンスへ移る。幸いなことに【透翅流星飛行】はスムーズに捕縛され……まあまだよからぬ可能性は捨てきれないが、一旦脇に置いていいと判断した」
「はい」
「データ回収等、まだありますが……」
「話はつけてある。忘れずに甘味を持って出向け」
久々に大日向研のメンバーがずらりと揃っている。大日向が外に出れない分、彼らにはあちらこちらに走り回ってもらっているからだ。神に渉外するものがあれば、データ解析を行うものもいるし、土地の情報を集めるものもいる。
「さて。今回全員を揃えたのには理由がある」
「はいはーい!あれですね!!」
「紀野」

はしゃぐな、と窘められている一番年下の学生が次のキーになる。
打倒すべき怪異は三体いて、そのうちの一体は神の気まぐれにより捕縛された。そのうちの一体は今も街を歩いているだろう。最後の一体――【望遠水槽の終点】だけが、不気味なほどに沈黙を守っている。
「かの世界に【望遠水槽の終点】がいるのであれば。こちらにそれに対応するヒトがいるはずだ、それは分かるな」
「はい!!仮初の姿……アレッでもそれってつまり堕ちているということなのでは」
「そうだ。今のところそのように推測している」
世界同士の侵略戦争。かの狭間はその試合会場で、パライバトルマリン曰く『地形すら異なり荒れ果てている』。陸だった場所が水場になり、その逆もまた然り。歩みは厳しく、よくわからないモンスターも出る。時には侵略相手と斬り結ぶこともあるらしい、三十六時間というにはあまりにも圧縮された時間、吉野暁海の感じた何週間かが圧縮され、【鈴のなる夢】に届けられているはずだ。そんな空間で報告上は“それなりに”正気を取り戻してくれたのだから、感謝して然るべきだろう。もちろんその時が来たらの話だが。
「【望遠水槽の終点】には謎が多い。まず何故いるのか?何故【終点】なのか?【鈴のなる夢】との関連性は何か?」
怪異も神秘も等しく、その名前から能力を読み取ることができる。名付けは固定する行為であり、そして呪いだからだ。名もない事象、不明不可思議を一部分でも固定し、それを足掛かりにして攻略する。断崖絶壁に一段ずつはしご、あるいは階段として機能を持つことのできる金属を刺していくように、外堀りを埋め、こちらの定義を強引にでも当てはめるのだ。名付けにはそれほどの意味がある。故に慎重になるか、名乗りを待つべきだというのが通例だった。
【望遠水槽の終点】には、その通例が通用しない。
「……あれは【哀歌の行進】がそう呼んでいただけかと思っていたのですが」
「名がないよりマシだ。そこに何が潜んでいようとな」
会ったこともなければ会話を交わしたこともない。そもそも全く興味はないと言い張るくせに、【哀歌の行進】はそれを【望遠水槽の終点】と称した。年頃の髪の長い女、虚ろな目、そしてあてもなく彷徨い続けているということまで告げて。
「ホイホイ釣られに行くようなものではないんですか、【哀歌の行進】に」
「全くもってそうだ。だが、奴も今は決定打を欠いている」
「……ああ、あの神のおかげですか」
理由は不明だが、【哀歌の行進】はひどく例の神を嫌っており、ここ最近は周辺で見かけることすらなくなっている。紫筑にいたころは常々人の邪魔をするためだけに些細なトラブルを起こしては人を動かしていたのに、だ。本来神の存在するレイヤーは怪異と同一になることはないから、畏れているのであれば納得はできる。畏れているのなら、もっとらしく振る舞うはずだ。それが大日向の持論であり、その通りに考慮するなら、この世界自体を放棄しているはずだった。
そもそも【哀歌の行進】という存在自体がイレギュラーの塊で、故にそれを狩ろうとしている。あるいは力を削ごうとしている。等しいと証明が可能なものが、同じ世界にあってはならない。大日向を始めとする神秘研究における基本原則であり、頻繁に出没するドッペルゲンガーに対する基本対応の仕方だ。自分の姿を見ると死んでしまうのであれば、先にその自分を倒せば良い。自分のドッペルゲンガーを見ると死ぬということ自体が俗説で、学びさえあれば恐れる必要はなにもないが、全ての人が神秘や怪異に興味を持っているわけではない。専門家とはそのために存在している。
「望遠水槽とは厳密に定義されたものではないが、おおよその想像はつく。水槽という時点でな。そうだろう」
「はいっめっちゃ分かります!だからあたしですね!!」
「……正直他にも向いている人間はいたと思うんですが、何故?」
「クレールパイセンはもっとあたしに優しくしてくれてもいいと思うんスけど!?」
「そこを突かれると痛いな。だが陸羽も手を回せんと来てはどうしようもない」
水槽。すなわち水族館。
紫筑大学第四学群神秘研究科には海の神秘や怪異に特化した部門が存在し、人魚研究科のある陸羽大学との連携を強く推し進めている。神秘・怪異学の総合が紫筑なら、人魚学に特化しているのが陸羽大学で、人魚ゲノムデータベースをアルモーグ大学との連名プロジェクトで構築し、今まさに人魚学のトップに存在している。そこから人員を借りてくるのが最も早かったが、あいにくその手は使えなかった。彼らは今子供の人魚の観察と観測に忙しい。
であれば、自分の手元の手札で代用するしかない。最も海に近く、魚に近いのは紀野いずもの能力だ。多少の難があっても、そのためにサポート要員を用意している。遠隔サポートの二ノ平、戦闘サポートのクレール、移動サポートの宮城野。可能性を正しい方向に導きたいのであれば、そこに投資を惜しむべきではない。
「……チッ。陸羽が無理ならうちのラボも無理か」
「何かあったんスかね?」
「お前はもうちょっと情報にアンテナを立てろ」
「そう貶めても何も出んぞ、クレール。もうお前の仕事は分かったろう」
視線がごく一瞬交わった。
気づく上級生、気づかない下級生。明確に出る差を見、大日向は笑う。
「……はいはい承知。要項をまとめておいてください」
「もう少し後になる。まず気づいてもらう必要があるのでな」
では解散、という鶴の一声に、学生たちが散り散りになっていく。
同じ場所をずっと回っている。それは本能で感じていたが、出方も何も分からなかった。
ここがどこで、わたしが誰か、何もわからないまま歩き続けている。こんなどん詰まりの間隔は、いつかに味わったようなものの気がしていた。
歩けど歩けど先はなく、鮮やかな青色と魚影だけが続いている。大きな貝が口を開け、そこから盛んに泡が立ち上っていた。壁沿いに歩いているはずなのに、どこにも辿り着かない。辿り着けない。
『迷っているのか?』
「……」
知らない男の人の声だった。男の人は怖かったから、自然と距離を取ってしまった。距離を取っても、視界には青しかない。
『いいのさ、そのままで。外は怖いところだ』
「……わたし……」
わたしは誰。
言葉は泡にすらならずに消え、ただ虚空を見つめている。
外は怖い。怖いところだ。隣の国に行ってしまった父と姉のことは何も分からず、母は病で死んでしまった。ひとりで生きていくのに、外の世界は恐ろしすぎた。
だから、そう、
『ここは誰にも邪魔されない狭間。そして向こうには、望んだ平和な世界がある。簡単なことだ、勝ち取ればいい。できるだろう?』
「わたし、」
『武器を使えるのだから。』
血の臭い。むせ返るかのごとき死の臭い。そうしている限り永遠についてきて、獣ではなく人のものへ塗り替えられていった、錆びた鉄の臭い。
初めて己の両手を見て、“わたし”はびっくりしてしまった。それは人の形こそしていたが、青く透けていた。そこにべったりと血が張り付いていた。
『さあ、ここを終点としよう。君という可能性の不幸せの歩みの。そして、ひとつ前に進みたまえ。そうすれば活路は見えるだろう。』
誰かが甘く夢のような言葉で囁いてくる。
わたしは、従っていいのだろうか?わたしはここで立ち止まっていいのだろうか?わたしには行かなければいけない場所があるのではないか?
いけない。それ以上いけない。わたしはこの言葉を聞いてはいけない。
「――触らないで」
貝が閉じる。
青い目がぎらりと光り、全てを追い出す。拒む。能力によって生み出される強固で絶対な防御、そして拒絶。

わたしはずっとひとりだった。

深く、深く、潜っていく。落ちていく。子供は溺れた時、何が起こったのかわからないまま静かに沈んでいくらしい。そんなことを思い出している自分も、何が起こっているのか分かっていないのだろう。
深く、深く――堕ちていく。堕ちていく。誰も助けてくれなかった。周りで見ているだけだった。わたしはどうしようもなく不器用で、人付き合いができなかった。わたしは何もできなかった。わたしは、わたしに、罰を与えたかった。
不出来なわたしに。誰の期待にも答えられないわたしに。何も救えないわたしに。この世にいるべきではなかったわたしに。
一粒零れた涙がどこかに落ちた瞬間、視界は真っ赤に染まった。ああ、これがきっとわたしへの罰だ。ようやく不出来なわたしを罰してくれる誰かが現れたのだ。卑怯なわたしを攻め落とす正義の剣が、わたしを無限に突き刺してくれる。
そのはずだったのに。




ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.20 ロールキャベツトマト煮込み を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 増幅10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







ユキ(424) に 100 PS 送付しました。
魔術LV を 25 DOWN。(LV30⇒5、+25CP、-25FP)
変化LV を 10 DOWN。(LV30⇒20、+10CP、-10FP)
呪術LV を 30 UP!(LV0⇒30、-30CP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
順(39) により ItemNo.23 腐肉 から薬箱『レッドバーンビブリオ』を作製してもらいました!
⇒ レッドバーンビブリオ/薬箱:強さ81/[効果1]耐疫15 [効果2]- [効果3]-
順(39) の持つ ItemNo.31 ビーフ から料理『牛肉のとろとろ煮込み』をつくりました!
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.32 お野菜 から料理『冷やし茄子のペースト』をつくりました!
ユキ(424) により ItemNo.22 お肉 から料理『生姜焼き』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 5 2 3 = 10 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ 生姜焼き/料理:強さ109/[効果1]攻撃13 [効果2]防御13 [効果3]増幅13
ユキ(424) により ItemNo.25 お肉 から料理『串焼き』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 4 2 1 = 7 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ 串焼き/料理:強さ109/[効果1]攻撃12 [効果2]防御12 [効果3]増幅12
 |
ユキ 「料金通りの仕事はしたから」 |
フェデルタ(165) により ItemNo.14 バンブーエディトリアン に ItemNo.15 公孫樹 を付加してもらいました!
⇒ バンブーエディトリアン/防具:強さ300/[効果1]加速20 [効果2]活力30 [効果3]-
ItemNo.23 レッドバーンビブリオ に ItemNo.24 腐肉 を付加しました!
⇒ レッドバーンビブリオ/薬箱:強さ81/[効果1]耐疫15 [効果2]耐疫15 [効果3]-
スミ(532) とカードを交換しました!
スミの炭になりたい (ミゼラブルメモリー)
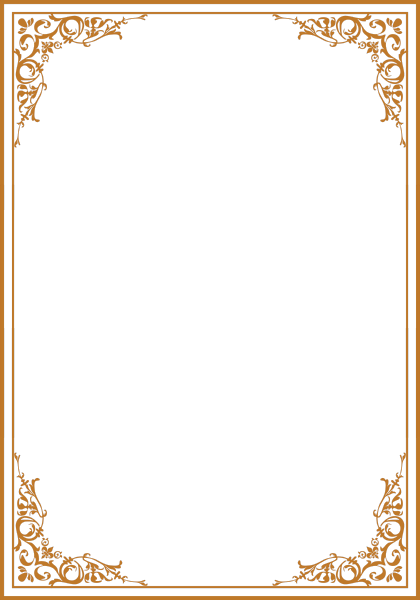
タイダルウェイブ を研究しました!(深度0⇒1)
タイダルウェイブ を研究しました!(深度1⇒2)
タイダルウェイブ を研究しました!(深度2⇒3)
カース を習得!
ヒールポーション を習得!
ダークフレア を習得!
フィーバー を習得!
ボロウライフ を習得!
アクアリカバー を習得!
ラトゥンブロウ を習得!
ポイズン を習得!
デッドライン を習得!
ウィークネス を習得!
クイックレメディ を習得!
ダークネス を習得!
ファーマシー を習得!
ディープフリーズ を習得!
水特性回復 を習得!
敗柳残花 を習得!
瘴気 を習得!
肉体変調特性 を習得!
闇の祝福 を習得!
凍縛陣 を習得!
ウィザー を習得!
ダウンフォール を習得!
ドレインライフ を習得!
腐食耐性 を習得!
ファルクス を習得!
スノーホワイト を習得!
闇霊力 を習得!
ディケイドミスト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は 看板 を入手!
フェデルタ(165) は 欠けた刃 を入手!
スズヒコ(244) は 看板 を入手!
スズヒコ(244) は 鉄板 を入手!
フェデルタ(165) は 毒液+3 を入手!
順(39) は 鉄板 を入手!



マガサ区 N-3(森林)に移動!(体調22⇒21)
マガサ区 O-3(森林)に移動!(体調21⇒20)
マガサ区 O-2(草原)に移動!(体調20⇒19)
マガサ区 P-2(山岳)に移動!(体調19⇒18)
マガサ区 Q-2(山岳)に移動!(体調18⇒17)






[871 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[441 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[177 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[377 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[286 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[199 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[137 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[56 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[122 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[92 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[90 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[83 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[0 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[8 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「ごきげんよう皆さん。案内人さんには悪いですが、場所を借りますよ。」 |
チャットにノウレットが現れる。
・・・が、どうも雰囲気が異なっている。
 |
ノウレット 「何やら妙な輩が妙なことを言っておりましたが、全て戯言でございます。 ゲームへの支障はありませんのでご安心ください。」 |
 |
ノウレット 「混乱を招くような者は、こちらで対処させていただきます。」 |
 |
ノウレット 「そして・・・・・共に条件を満たしましたので、以前お伝えしました2件・・・18:00より開始いたします。」 |
 |
ノウレット 「ひとつ。影響力が低い状態が続きますと皆さんの形状に徐々に変化が現れます。」 |
 |
ノウレット 「最初に皆さんが戦った相手、ナレハテ。 多くは最終的にはあのように、または別の形に変化する者もいるでしょう。」 |
 |
ノウレット 「ふたつ。決闘を避ける手段が一斉に失われます。 ベースキャンプにいる場合でも避けられませんので、ご注意ください。」 |
 |
ノウレット 「・・・それでは引き続き、ゲームをお楽しみください。」 |
チャットが閉じられる――









ENo.244
鈴のなる夢

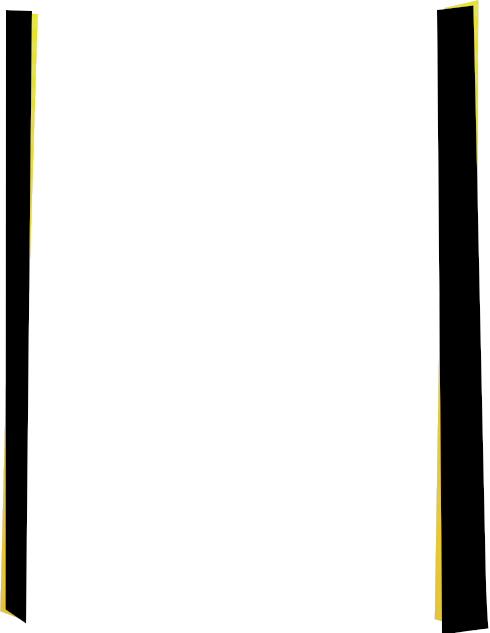
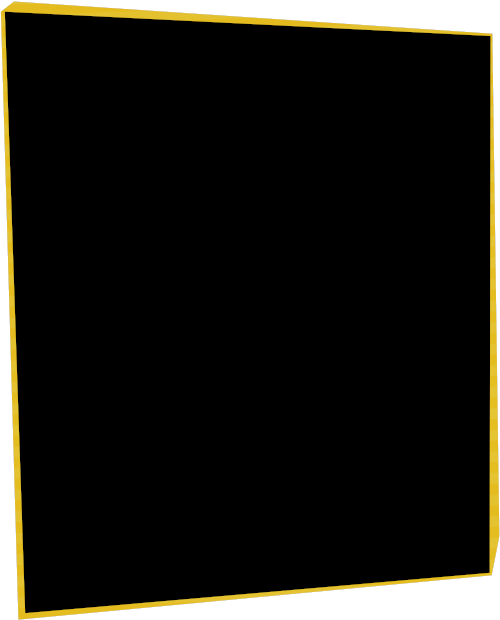
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
17 / 30
552 PS
マガサ
Q-2
Q-2







痛撃友の会
7
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
1
アイコン60pxの会
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
3
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
2
カード報告会
5
とりあえず肉食う?
7



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | 閃光10 | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | ポプラ | 素材 | 25 | [武器]追風15(LV35)[防具]耐災25(LV35)[装飾]風纏25(LV40) | |||
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | クリアグロリエバインド | 装飾 | 260 | 活力20 | 活力20 | - | |
| 8 | 火焔茸 | 素材 | 35 | [武器]猛毒30(LV70)[防具]反毒35(LV75)[装飾]舞衰30(LV70) | |||
| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | 耐疫15 | - | |
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | 風柳10 | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | バンブーエディトリアン | 防具 | 300 | 加速20 | 活力30 | - | |
| 15 | 看板 | 素材 | 30 | [武器]列撃30(LV65)[防具]閃撃25(LV50)[装飾]攻撃30(LV60) | |||
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | リアリズムカレントブラスト | 大砲 | 306 | 体力20 | - | - | 【射程4】 |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 21 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 22 | 生姜焼き | 料理 | 109 | 攻撃13 | 防御13 | 増幅13 | |
| 23 | レッドバーンビブリオ | 薬箱 | 81 | 耐疫15 | 耐疫15 | - | |
| 24 | |||||||
| 25 | 串焼き | 料理 | 109 | 攻撃12 | 防御12 | 増幅12 | |
| 26 | 装甲 | 素材 | 35 | [武器]全護25(LV55)[防具]防御35(LV75)[装飾]耐災30(LV60) | |||
| 27 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 28 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 29 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 30 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 31 | すごいお魚 | 食材 | 30 | [効果1]活力30(LV25)[効果2]敏捷30(LV35)[効果3]強靭30(LV45) | |||
| 32 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 33 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 34 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 30 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 30 | 呪詛/邪気/闇 |
| 変化 | 20 | 強化/弱化/変身 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 50 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 50 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 10 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 8 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決2 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 決2 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| 決1 | ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| 決3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 決1 | フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| フィーバー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 6 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| 決3 | ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 6 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 決3 | クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 決1 | ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 |
| 決3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| 決3 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 14 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 6 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| 決1 | クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 7 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 決3 | セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 |
| イラプション | 5 | 0 | 180 | 敵列:地撃+敵味全:火撃&炎上 | |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| 決3 | パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| グレイシア | 7 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| ウィザー | 5 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |
| サモン:ビーフ | 7 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| 決1 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 | |
| イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 | |
| ドレインライフ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&MHP奪取 | |
| 決3 | サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 |
| グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 | |
| コンフィデンス | 6 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |
| スノーホワイト | 5 | 0 | 200 | 敵4:水痛撃&朦朧 | |
| 決2 | ディープブルー | 5 | 0 | 200 | 敵:水撃&水特性増 |
| バーニングカード | 5 | 0 | 80 | 敵3:火撃+自:強制炎上 | |
| ディケイドミスト | 5 | 1 | 300 | 敵全:AG減(4T)&腐食+味全:DX増(4T)&腐食 | |
| タイダルウェイブ | 5 | 0 | 330 | 敵:5連鎖水撃&DX・AG減(2T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 瘴気 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘離脱前】敵6:猛毒・麻痺・衰弱 | |
| 肉体変調特性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
| 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 | |
| 凍縛陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど凍縛LV増 | |
| 決3 | 治癒領域 | 8 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 凍結耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:凍結耐性増 | |
| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |
| 腐食耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:腐食耐性増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |
| 生殺与奪 | 5 | 6 | 0 | 【攻撃命中後】対:火撃+対:水撃&味傷:HP増 | |
| 星火燎原 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】敵味炎:粗雑火撃&炎上奪取&自:炎上をAT化 | |
| 火霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:魔術LVが高いほどSP・火特性増 | |
| 水霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:命術LVが高いほどSP・水特性増 | |
| 闇霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |
| 千変万化 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |
| 火特性回復 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:火属性スキルのHP増効果に火特性が影響 | |
| 魔香作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で料理「魔香」を選択できる。魔香は体調が回復せず効果3しか付加されないが、食事に指定しても消費されない。 |
最大EP[25]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 決3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 決2 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 決1 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| 決2 |
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
|
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
|
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
|
ギフトカード (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |
5 | 500 | 自:エンペラー召喚 | |
|
余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター) |
0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 | |
|
フリーリィ・スカイシー・ダイブ (ワールウィンド) |
0 | 200 | 敵傷7:風撃 | |
|
血眼 (ブラッドアイズ) |
0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
|
スミの炭になりたい (ミゼラブルメモリー) |
2 | 200 | 敵:6連鎖SP闇撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]フレイムインパクト | [ 3 ]アブソーブ |
| [ 3 ]クリエイト:コーラス | [ 3 ]イディオータ | [ 3 ]レーヴァテイン |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]フィジカルブースター |
| [ 3 ]グラトニー | [ 3 ]プチメテオカード | [ 3 ]マナポーション |
| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]クリエイト:モンスター | [ 3 ]ゴッズディサイド |
| [ 3 ]タイダルウェイブ | [ 3 ]ミゼラブルメモリー |

PL / 紙箱みど