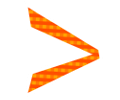<< 7:00~8:00




イバラシティはマシカ区、その隅に立つスタジアム。そこで行われるのは、学生たちの春の祭、荊闘乱祭だ。
長い時間をかけて沢山の競技が行われ、そろそろ宴もたけなわ。陽も暮れ、あとは結果発表を待つだけとなった頃。
広い会場の中ではフォークダンスの曲がかかり、参加者や来場者は思い思いの相手と手を取り合って踊っていた。
先輩に呼びつけられ、一般の来場者として会場を訪れていた金糸エリは、指先で膝をとんとんと叩きつつ、観客席から人々の様子を見つめていた。
彼女が手持ち無沙汰にしている理由はひとつ。彼女がここに居るそもそもの理由である先輩が、ふらりと何処かへ消えてしまったからである。
別に何も言わずに帰っても良いといえば良いのだろうが、それを本当に実行できるほどエリという人間は不義理にはなりきれなくて。
結果、こうして待ちぼうけを食ったような状態になってしまい。朝に買った屋台の飴をつまんでいるうち、大分その数を減らしてしまった。
「……はぁ」
ため息を吐く。あの先輩は他人の事をどう扱いたいのか、いまいち判断がつかない、と。
親か姉妹かのようにくっ付いて来たと思えば、曖昧な顔をして誤魔化したり、今日みたいにどこぞへ消えたり。
別にそういう部分を美点だとは思わない。ただ、先輩との友達付き合いを断絶するほどのネックではない。
……そんな事を思ってしまう時点で、彼女に絆されてしまっているのかもしれないな、と。今しがた暗い息を吐いた口許を抑えた。
さて、そろそろヨーグルトの飴も切れそうだ。エリが最後の一つを口に入れようとした、その時。
いつの頃からか夕焼けばかりであった彼女の視界に、ふと、人ひとり分の影が差した。
「……ごめん。待たせたね」
その声にエリは顔を上げる。一体どういった罵りの言葉をぶつけてやろうか、と。
しかし。目の前に立っている先輩——神実はふりの表情が、適当に揶揄ってやるにはいたく真剣で。
その服装が、先までのラフなパーカーではなく。どこかドレスのような、優雅なそれであれば。
「ええ、随分と。散々待たせてくれて。それで、私に何か言いたいことでも?」
そんな気はまるで失せてしまって。エリはただ、じっとはふりの金の瞳を見つめる。
後輩の様子に安堵したのだろうか、はふりは穏やかに傅いて、エリの細い手を取った。
「ああ、勿論あるよ。——私と一曲踊りませんか、マドモワゼル」
エリは思う。返す返すも、この先輩は分からない人間だ、と。
いつか何処かへ融けて消えてしまいそうな、冬の雪にも似た朧げな雰囲気を持ちながら。
誰にでも等しくけらけらと笑いかける、夏の太陽のような明るさを見せることもあって。
それらの丁度境目で暮れていく陽を追いかけるような、秋の短い夜のようにも思えて。
たった今のように、誰かの隣で暖かく存在したいと願うような、春の花でさえある。
「喜んで、マイディア。陽の落ちる前に、どこまでもこの手を引いて下さいな」
エリは朗らかに笑って、その冷たい手を握り返した。
何処の誰とも知らない旅人。明日には目の届かない深い闇へと沈んでいてもおかしくはない存在。
そんな彼女が、自分の熱を求めてくれているという事実が、ただ嬉しくて。
そうであれば。『王子様』が少し遅れて来たことくらいは許すのが、『お相手』の仕事だ。
「ありがとう、エリちゃん。……さあ、スポットライトの下で踊ろうか。
きっと世界が終わるまで、今日のこの日は私たちの舞台さ。だろう?」
そう言いながらはふりが手を持ち上げるのに合わせ、エリはふわりと立ち上がった。
それから、その言葉に同意を返すようにして、スカートの裾を摘み、お辞儀をする。
きっとその動作が終わるよりも、手を引くはふりが歩き出すことの方が早かったのかもしれない。
二人の足取りは、そう、どことなく走っているようにさえ見えた。
——はふりとエリはくるくるとただ踊る。きっと誰も、彼女達のことを見ていなかったとしても。
いいや、その逆だ。はふりとエリにとっては、彼女達以外の人間など、視界から消えてしまっていて。
夕陽を編んだ影踏みのようなステップと、互いの体温。それに、存在の証明、他人の許容。
たったそれだけの、シンプルに組み替えられた世界。二人のステージは、きっとそこだったのだ。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
「——下らない」
思考がハザマへと接続され、記憶が神実はふりの脳内へと流れ込んでくる。
闘乱祭での華やかな時間。たくさんの人の熱気。後輩であるエリと踊ったこと。
何よりも——向こうの神実はふりが、それを好いと、楽しいと思っていたこと。
邪念を払うように、握っていた無銘の刀を一度振るう。
白刃が閃くと、心の奥底がすうっと冷えていくのが分かった。
そうだ、この凍える体温だけが、『私』なのだと。
「……」
そうだ。私は他人の熱を啜り、奪うことでしか生きていけない存在なのだ。
言ってしまえば——アンジニティの樹木の化生が言っていたのとまるで同じ、『生きるために必要なこと』。
それについて、善だ悪だと論じる余地は無く。そもそも、その事について考えるのは、私の埒外である。
黙ってただ目的を果たすだけ。……そうであれば、こんなにも心がざわつく事はなかったはずなのに。
「違う」
足下に落ちていた小石を思い切り蹴飛ばす。それは崩れた建物に当たって、鈍い音を立てて落ちた。
違うのだ。『それ』は、救いではない。神実はふりという存在の求める幸福の形ではない。
そんなものを求め続けたって、私はどうにもならないし、凍えが収まることも、普通の人間になることもない。
永久に大人になれない私には、今以上の未来なんて無い。
「……っ……。……いい加減に、しろよ。本当に……うざいな」
何時頃からだったろうか、私は頻繁に頭痛に襲われるようになった。
それはきっと、このハザマの昏さが原因なのだろうと、分かってはいながらも。
どうせ目を逸らすことはできないのだからと、気にしないつもりではいたが。
……それにしたって、こうも続くと、鬱陶しい。
けれど、そんな事を言ってもいられない。ゲームはこれからターニングポイントを迎える。
これから初めてかぎ君以外の戦力を加え、新たなる守護者との戦いへ赴くのだから。
がん、と。煮え切らない感覚を蹴りとして地面へぶつけてから、三人のもとへとゆらり歩いていく。



ENo.399 嬉野聖 とのやりとり

ENo.474 イデオローグ とのやりとり

ENo.515 フタバ とのやりとり




ノジコ(456) に ItemNo.15 何かの骨 を手渡ししました。
ノジコ(456) から 松 を手渡しされました。
ItemNo.11 炊き込みごはん を食べました!
体調が 0 回復!(30⇒30)
今回の全戦闘において 貫撃10 器用10 深手20 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



かぎ(170) から 90 PS 受け取りました。
すごい木材(400 PS)を購入しました。
すごい石材(400 PS)を購入しました。
武術LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
時空LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
制約LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
解析LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV55⇒60、-5CP)
雀部(606) の持つ ItemNo.16 爪 から装飾『つきもの』を作製しました!
かぎ(170) の持つ ItemNo.13 すごい木材 から装飾『翡翠の鉤針アンクレット』を作製しました!
Dr.笹子(831) の持つ ItemNo.2 大蒜 から装飾『増殖試験管』を作製しました!
雀部(606) により ItemNo.11 すごい木材 から射程1の武器『白光の刀』を作製してもらいました!
⇒ 白光の刀/武器:強さ210/[効果1]攻撃20 [効果2]- [効果3]-【射程1】
かぎ(170) により ItemNo.11 白光の刀 に ItemNo.15 松 を付加してもらいました!
⇒ 白光の刀/武器:強さ210/[効果1]攻撃20 [効果2]器用10 [効果3]-【射程1】
Dr.笹子(831) により ItemNo.7 パーカー に ItemNo.13 駄木 を付加してもらいました!
⇒ パーカー/防具:強さ82/[効果1]敏捷10 [効果2]敏捷10 [効果3]-
タケシ(635) とカードを交換しました!
いいサングラス (クリエイト:ラビリンス)

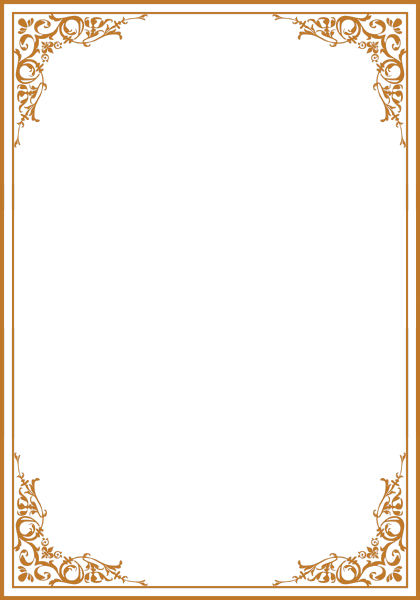
バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
クイックレメディ を研究しました!(深度0⇒1)
プリディクション を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を習得!
見切 を習得!
死線 を習得!
ショックウェイブ を習得!
高速配置 を習得!
ウィークサーチ を習得!
ウィンドコイル を習得!
スクランブル を習得!
インペイル を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



かぎ(170) は 毛 を入手!
キリン(310) は 剛毛 を入手!
キリン(310) は 剛毛 を入手!
ノジコ(456) は 剛毛 を入手!
ノジコ(456) は 触手 を入手!
かぎ(170) は 触手 を入手!
キリン(310) は 触手 を入手!
ノジコ(456) は 触手 を入手!



次元タクシーに乗り ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 に転送されました!
キリン(310) がパーティから離脱しました!
ノジコ(456) がパーティから離脱しました!
ヒノデ区 M-10(道路)に移動!(体調30⇒29)
ヒノデ区 N-10(森林)に移動!(体調29⇒28)
ヒノデ区 O-10(森林)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 P-10(森林)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 P-9(森林)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- はふり(42) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)
- かぎ(170) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- はふり(42) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)





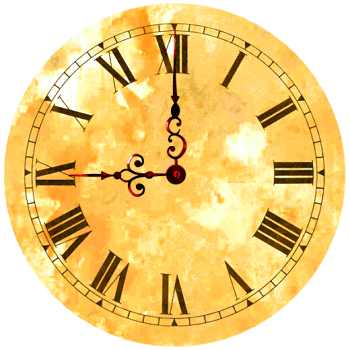
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
ザザッ――
ザザッ――
ザザッ――
チャットが閉じられる――








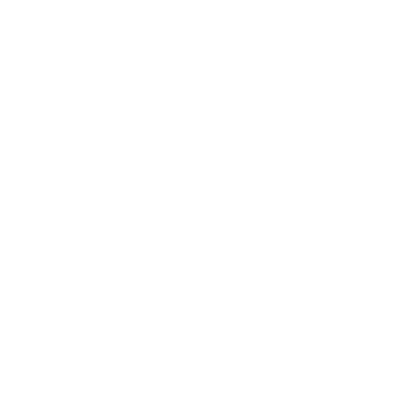
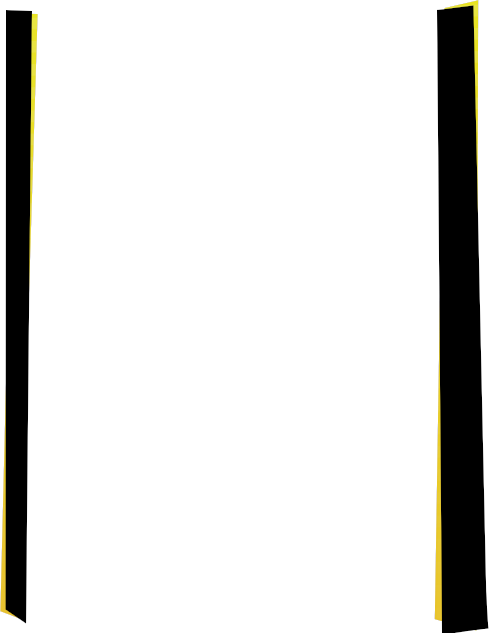
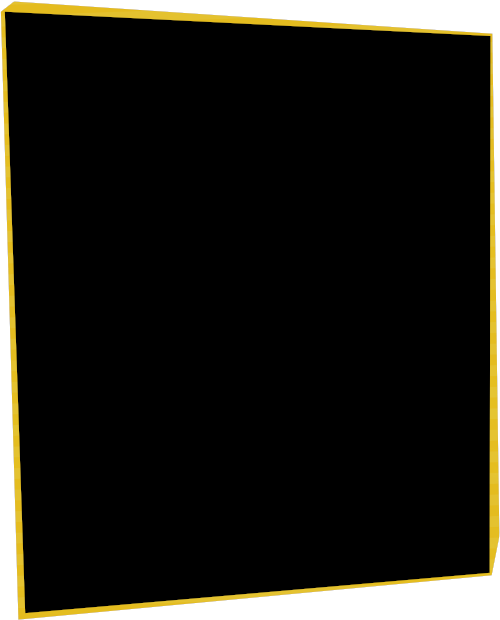





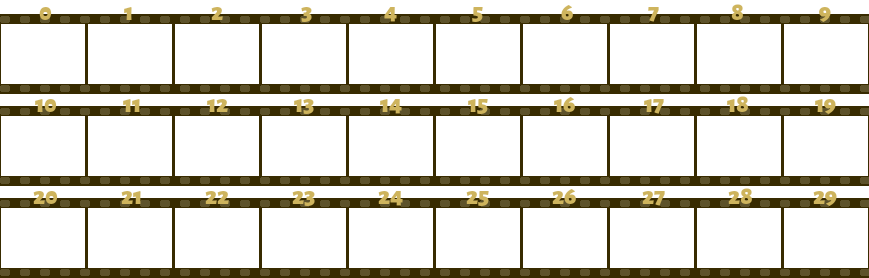





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



イバラシティはマシカ区、その隅に立つスタジアム。そこで行われるのは、学生たちの春の祭、荊闘乱祭だ。
長い時間をかけて沢山の競技が行われ、そろそろ宴もたけなわ。陽も暮れ、あとは結果発表を待つだけとなった頃。
広い会場の中ではフォークダンスの曲がかかり、参加者や来場者は思い思いの相手と手を取り合って踊っていた。
先輩に呼びつけられ、一般の来場者として会場を訪れていた金糸エリは、指先で膝をとんとんと叩きつつ、観客席から人々の様子を見つめていた。
彼女が手持ち無沙汰にしている理由はひとつ。彼女がここに居るそもそもの理由である先輩が、ふらりと何処かへ消えてしまったからである。
別に何も言わずに帰っても良いといえば良いのだろうが、それを本当に実行できるほどエリという人間は不義理にはなりきれなくて。
結果、こうして待ちぼうけを食ったような状態になってしまい。朝に買った屋台の飴をつまんでいるうち、大分その数を減らしてしまった。
「……はぁ」
ため息を吐く。あの先輩は他人の事をどう扱いたいのか、いまいち判断がつかない、と。
親か姉妹かのようにくっ付いて来たと思えば、曖昧な顔をして誤魔化したり、今日みたいにどこぞへ消えたり。
別にそういう部分を美点だとは思わない。ただ、先輩との友達付き合いを断絶するほどのネックではない。
……そんな事を思ってしまう時点で、彼女に絆されてしまっているのかもしれないな、と。今しがた暗い息を吐いた口許を抑えた。
さて、そろそろヨーグルトの飴も切れそうだ。エリが最後の一つを口に入れようとした、その時。
いつの頃からか夕焼けばかりであった彼女の視界に、ふと、人ひとり分の影が差した。
「……ごめん。待たせたね」
その声にエリは顔を上げる。一体どういった罵りの言葉をぶつけてやろうか、と。
しかし。目の前に立っている先輩——神実はふりの表情が、適当に揶揄ってやるにはいたく真剣で。
その服装が、先までのラフなパーカーではなく。どこかドレスのような、優雅なそれであれば。
「ええ、随分と。散々待たせてくれて。それで、私に何か言いたいことでも?」
そんな気はまるで失せてしまって。エリはただ、じっとはふりの金の瞳を見つめる。
後輩の様子に安堵したのだろうか、はふりは穏やかに傅いて、エリの細い手を取った。
「ああ、勿論あるよ。——私と一曲踊りませんか、マドモワゼル」
エリは思う。返す返すも、この先輩は分からない人間だ、と。
いつか何処かへ融けて消えてしまいそうな、冬の雪にも似た朧げな雰囲気を持ちながら。
誰にでも等しくけらけらと笑いかける、夏の太陽のような明るさを見せることもあって。
それらの丁度境目で暮れていく陽を追いかけるような、秋の短い夜のようにも思えて。
たった今のように、誰かの隣で暖かく存在したいと願うような、春の花でさえある。
「喜んで、マイディア。陽の落ちる前に、どこまでもこの手を引いて下さいな」
エリは朗らかに笑って、その冷たい手を握り返した。
何処の誰とも知らない旅人。明日には目の届かない深い闇へと沈んでいてもおかしくはない存在。
そんな彼女が、自分の熱を求めてくれているという事実が、ただ嬉しくて。
そうであれば。『王子様』が少し遅れて来たことくらいは許すのが、『お相手』の仕事だ。
「ありがとう、エリちゃん。……さあ、スポットライトの下で踊ろうか。
きっと世界が終わるまで、今日のこの日は私たちの舞台さ。だろう?」
そう言いながらはふりが手を持ち上げるのに合わせ、エリはふわりと立ち上がった。
それから、その言葉に同意を返すようにして、スカートの裾を摘み、お辞儀をする。
きっとその動作が終わるよりも、手を引くはふりが歩き出すことの方が早かったのかもしれない。
二人の足取りは、そう、どことなく走っているようにさえ見えた。
——はふりとエリはくるくるとただ踊る。きっと誰も、彼女達のことを見ていなかったとしても。
いいや、その逆だ。はふりとエリにとっては、彼女達以外の人間など、視界から消えてしまっていて。
夕陽を編んだ影踏みのようなステップと、互いの体温。それに、存在の証明、他人の許容。
たったそれだけの、シンプルに組み替えられた世界。二人のステージは、きっとそこだったのだ。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
「——下らない」
思考がハザマへと接続され、記憶が神実はふりの脳内へと流れ込んでくる。
闘乱祭での華やかな時間。たくさんの人の熱気。後輩であるエリと踊ったこと。
何よりも——向こうの神実はふりが、それを好いと、楽しいと思っていたこと。
邪念を払うように、握っていた無銘の刀を一度振るう。
白刃が閃くと、心の奥底がすうっと冷えていくのが分かった。
そうだ、この凍える体温だけが、『私』なのだと。
「……」
そうだ。私は他人の熱を啜り、奪うことでしか生きていけない存在なのだ。
言ってしまえば——アンジニティの樹木の化生が言っていたのとまるで同じ、『生きるために必要なこと』。
それについて、善だ悪だと論じる余地は無く。そもそも、その事について考えるのは、私の埒外である。
黙ってただ目的を果たすだけ。……そうであれば、こんなにも心がざわつく事はなかったはずなのに。
「違う」
足下に落ちていた小石を思い切り蹴飛ばす。それは崩れた建物に当たって、鈍い音を立てて落ちた。
違うのだ。『それ』は、救いではない。神実はふりという存在の求める幸福の形ではない。
そんなものを求め続けたって、私はどうにもならないし、凍えが収まることも、普通の人間になることもない。
永久に大人になれない私には、今以上の未来なんて無い。
「……っ……。……いい加減に、しろよ。本当に……うざいな」
何時頃からだったろうか、私は頻繁に頭痛に襲われるようになった。
それはきっと、このハザマの昏さが原因なのだろうと、分かってはいながらも。
どうせ目を逸らすことはできないのだからと、気にしないつもりではいたが。
……それにしたって、こうも続くと、鬱陶しい。
けれど、そんな事を言ってもいられない。ゲームはこれからターニングポイントを迎える。
これから初めてかぎ君以外の戦力を加え、新たなる守護者との戦いへ赴くのだから。
がん、と。煮え切らない感覚を蹴りとして地面へぶつけてから、三人のもとへとゆらり歩いていく。



ENo.399 嬉野聖 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.474 イデオローグ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||||
ENo.515 フタバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||



 |
キリン 「…あれ(どういう経緯で合流する話になったんだっけ…?いやだな、ぼうっとしてる。五月病かな?)」 |
 |
キリン 「ええと、今回はありがとうございます。 道々よろしくお願いします…」 |
 |
ノジコ 「あっ、前に戦ってくれたお兄さんお姉さん! 元気にしてたかしらっ! わたしたちは元気元気~!!」 |
 |
もちわか丸 「キリンチャンが意見を出す前にすべてをまとめないであげて」 |
 |
ノジコ 「ちょうどまた大事なバトルのたいみんぐだったみたいだし、 二人が四人になるだけで、とっても心強いですっ! 一緒に頑張りましょっ!」 |
 |
ノジコ 「……、チャットでドライバーさんが言ってたコトも、気になるケド……。 今は、わたしたちができることを、ちょっとずつやっていくしかないわよね」 |
ノジコ(456) に ItemNo.15 何かの骨 を手渡ししました。
ノジコ(456) から 松 を手渡しされました。
 |
ノジコ 「これね、この間、森で拾ったの! イイカンジの枝って、なんか拾いたくなっちゃうわよね……ふしぎっ!」 |
ItemNo.11 炊き込みごはん を食べました!
体調が 0 回復!(30⇒30)
今回の全戦闘において 貫撃10 器用10 深手20 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





かつてヒナチュー美術部だったものたち
|
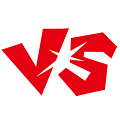 |
トレイターズ
|



ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
かつてヒナチュー美術部だったものたち
|
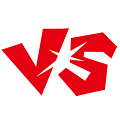 |
立ちはだかるもの
|



ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



かぎ(170) から 90 PS 受け取りました。
すごい木材(400 PS)を購入しました。
すごい石材(400 PS)を購入しました。
武術LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
時空LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
制約LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
解析LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV55⇒60、-5CP)
雀部(606) の持つ ItemNo.16 爪 から装飾『つきもの』を作製しました!
かぎ(170) の持つ ItemNo.13 すごい木材 から装飾『翡翠の鉤針アンクレット』を作製しました!
Dr.笹子(831) の持つ ItemNo.2 大蒜 から装飾『増殖試験管』を作製しました!
雀部(606) により ItemNo.11 すごい木材 から射程1の武器『白光の刀』を作製してもらいました!
⇒ 白光の刀/武器:強さ210/[効果1]攻撃20 [効果2]- [効果3]-【射程1】
 |
雀部 「この前言いそびれたこと言っていい?」 |
 |
雀部 「そっちも無理はせんように~!」 |
かぎ(170) により ItemNo.11 白光の刀 に ItemNo.15 松 を付加してもらいました!
⇒ 白光の刀/武器:強さ210/[効果1]攻撃20 [効果2]器用10 [効果3]-【射程1】
Dr.笹子(831) により ItemNo.7 パーカー に ItemNo.13 駄木 を付加してもらいました!
⇒ パーカー/防具:強さ82/[効果1]敏捷10 [効果2]敏捷10 [効果3]-
タケシ(635) とカードを交換しました!
いいサングラス (クリエイト:ラビリンス)

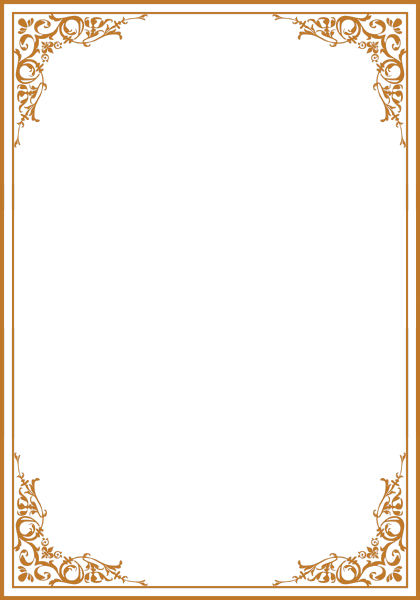
バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
クイックレメディ を研究しました!(深度0⇒1)
プリディクション を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を習得!
見切 を習得!
死線 を習得!
ショックウェイブ を習得!
高速配置 を習得!
ウィークサーチ を習得!
ウィンドコイル を習得!
スクランブル を習得!
インペイル を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



かぎ(170) は 毛 を入手!
キリン(310) は 剛毛 を入手!
キリン(310) は 剛毛 を入手!
ノジコ(456) は 剛毛 を入手!
ノジコ(456) は 触手 を入手!
かぎ(170) は 触手 を入手!
キリン(310) は 触手 を入手!
ノジコ(456) は 触手 を入手!



次元タクシーに乗り ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ひと仕事っと。一服してから次行くかねぇ。」 |
キリン(310) がパーティから離脱しました!
ノジコ(456) がパーティから離脱しました!
ヒノデ区 M-10(道路)に移動!(体調30⇒29)
ヒノデ区 N-10(森林)に移動!(体調29⇒28)
ヒノデ区 O-10(森林)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 P-10(森林)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 P-9(森林)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- はふり(42) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)
- かぎ(170) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- はふり(42) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)





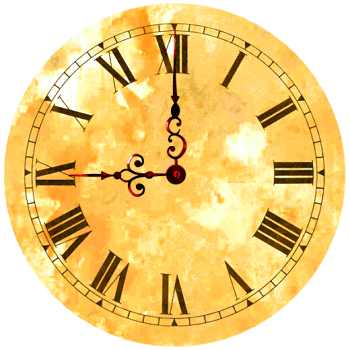
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・怖いだろうがよ。」 |
 |
エディアン 「・・・勘弁してくれませんか。」 |
 |
白南海 「ナレハテってあの!アレだろォッ!!?ドッロドロしてんじゃねーっすか!! なんすかあれキッモいのッ!!うげぇぇぇぇうげえええぇぇぇ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「私だって嫌ですよあんなの・・・・・ ・・・え、案内役って影響力どういう扱いに・・・??私達は関係ないですよね・・・????」 |
 |
白南海 「あんたアンジニティならそーゆーの平気じゃねーんすか? 何かアンジニティってそういう、変な、キモいの多いんじゃ?」 |
 |
エディアン 「こんな麗しき乙女を前に、ド偏見を撒き散らさないでくれます? 貴方こそ、アレな業界の人間なら似たようなの見慣れてるでしょうに。」 |
 |
白南海 「あいにくウチはキレイなお仕事しかしてないもんで。えぇ、本当にキレイなもんで。」 |
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
 |
白南海 「・・・っつーか、あれ本当にドライバーのオヤジっすか?何か雰囲気違くねぇ・・・??」 |
 |
エディアン 「まぁ別の何か、でしょうね。 雰囲気も言ってることも別人みたいでしたし。普通に、スワップ発動者さん?・・・うーん。」 |
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
 |
エディアン 「・・・・・?なんでしょう、何か変な雑音が。」 |
ザザッ――
 |
白南海 「ただの故障じゃねーっすか。」 |
ザザッ――
 |
声 「――・・・レーション、ヒノデコーポレーション。 襲撃に・・・・・・・・いる・・・ 大量・・・・・こ・・・・・・死体・・・・・・ゾ・・・・・・」 |
 |
声 「・・・・・ゾンビだッ!!!!助け――」 |
ザザッ――
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「ホラーはぁぁ――ッ!!!! やぁぁめろォォ―――ッ!!!!」 |
 |
エディアン 「勘弁してください勘弁してくださいマジ勘弁してください。 ホラーはプレイしないんですコメ付き実況でしか見れないんですやめてください。」 |
チャットが閉じられる――







ENo.42
神実はふり
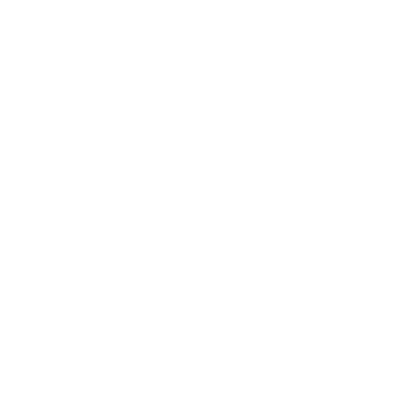
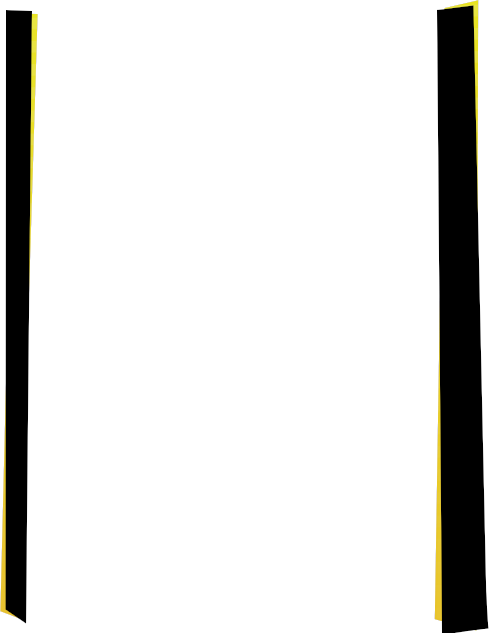
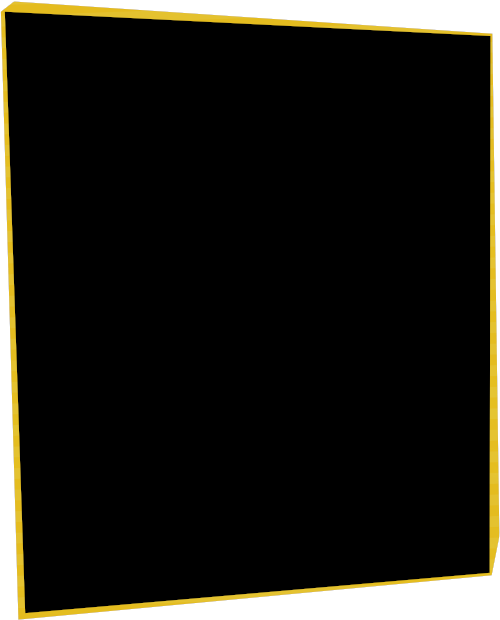
◆神実 はふり(かんざね はふり)
ある日熾盛天晴学園に転校してきた女の子。今は卒業し、大学へ通っている。
リボン付きワイシャツの上からパーカー着用。ギンガムチェックのスカート、ニーソックス、ローファーを身に着けている。
身長は150cmあるかないか。細身で小さい。黒髪ストレート、金色をしたどことなく眠たげにも映る瞳。
普段の表情もなんとなくふわっとしているような印象。よく言えば浮世離れ、悪く言えば何を考えているか読み取りづらい。
学校での彼女はいたって普通の人間である。
平均的な学力、平均的な運動能力、誰かと深く仲良くなるわけでも、激しくいがみ合うわけでもない。
まさに絵に描いたような『一般的な』女子生徒としてハレ高生活を過ごしている。
甘いものが好きであり、よくシュークリームなどを食べている。
またエナジードリンクを愛飲している。これは彼女が朝起きるのが苦手なことに起因しているらしい。
似たような理由で紙パック入りのカフェオレなども好んで買っている。
その実とある『機関』のエージェントであり、何らかの使命を負ってイバラシティに潜入している。
熾盛天晴学園はその潜伏先だった。だが、どうやら普通に高校生活を楽しんでいるようだ。
はふりの身の上を知るのは、彼女が信頼していると考えられるごくごく一部の人間に限られる。
人の体温を感じることが好き。もっと言えば『生きていると分かること』が好き。
そのためよく男女を問わず他人にくっついたり手を握ったりなどのスキンシップを図る。
スマホ中毒のきらいがあり、人と話しているときにも時たま画面に目を落としていることがある。
異能は『神通力』。
武器や体に不可思議な力を纏わせることにより、それらを強化して戦うことができる。
また、彼女には他の人間には感知しづらい『悪いもの』が見えてしまう。
加えて、ほんの些細な力ではあるが物体移動能力の真似事のようなこともできる。
そのため普段の彼女はテレキネシストとして振る舞い、本来の能力を隠している。
武器として刀を扱うが、剣道部所属というわけではなく、振り方や扱い方は完全に我流。
というよりも、もはや結果的に斬れているだけでそのやり口は鈍器のそれに近くもある。
これに上記の『神通力』を組み合わせての近接戦闘がはふりの戦い方である。
IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1585
◇金糸 エリ(かないと えり)
熾盛天晴学園の2年3組に在籍する女子。図書委員で電子工作部。
鉄色の憂いを帯びた瞳、錆色をした長く豊かな髪。色白で華奢。身長は150cm前後。
学校指定の服装を着崩さずに着用。近付けばかすかに分かる程度に香水の香り。
成績は学年トップクラス、規則を守り生活態度も良好と典型的な優等生タイプ。
一方であまり人と話したがらず、休み時間は部室や図書室にこもりがち。
あまり彼女と仲の良くない人間からすると、不愛想で冷たい人格にも見えるだろう。
彼女の有する能力は『機械の魔女(マギア・マキナ)』。
自分が所有する無機物に対して命令を与え、それを実行させる能力。
所有の基準は曖昧だが、少なくとも自身がある程度の手を加えたものに限られるようだ。
店の売り物や今拾ったものを所有物と言い張ることがエリの性格上できないからだろう。
命令について、所有したての物に関しては移動等の簡単な物に限られるが、エリが多く手を加えた物・長く所有した物についてはより複雑な命令を加えることが可能となる。
この能力を活かし、エリの部屋には料理をする機械人形、洗濯をする機械人形などが存在している。
IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1586
☆Special Thanks!!
はふりのプロフィール画像、アイコン→渡部アクサ様
はふりのサンタアイコン→霜咲様
エリのプロフィール画像、アイコン→有織様
この場を借りてお礼申し上げます!
ある日熾盛天晴学園に転校してきた女の子。今は卒業し、大学へ通っている。
リボン付きワイシャツの上からパーカー着用。ギンガムチェックのスカート、ニーソックス、ローファーを身に着けている。
身長は150cmあるかないか。細身で小さい。黒髪ストレート、金色をしたどことなく眠たげにも映る瞳。
普段の表情もなんとなくふわっとしているような印象。よく言えば浮世離れ、悪く言えば何を考えているか読み取りづらい。
学校での彼女はいたって普通の人間である。
平均的な学力、平均的な運動能力、誰かと深く仲良くなるわけでも、激しくいがみ合うわけでもない。
まさに絵に描いたような『一般的な』女子生徒としてハレ高生活を過ごしている。
甘いものが好きであり、よくシュークリームなどを食べている。
またエナジードリンクを愛飲している。これは彼女が朝起きるのが苦手なことに起因しているらしい。
似たような理由で紙パック入りのカフェオレなども好んで買っている。
その実とある『機関』のエージェントであり、何らかの使命を負ってイバラシティに潜入している。
熾盛天晴学園はその潜伏先だった。だが、どうやら普通に高校生活を楽しんでいるようだ。
はふりの身の上を知るのは、彼女が信頼していると考えられるごくごく一部の人間に限られる。
人の体温を感じることが好き。もっと言えば『生きていると分かること』が好き。
そのためよく男女を問わず他人にくっついたり手を握ったりなどのスキンシップを図る。
スマホ中毒のきらいがあり、人と話しているときにも時たま画面に目を落としていることがある。
異能は『神通力』。
武器や体に不可思議な力を纏わせることにより、それらを強化して戦うことができる。
また、彼女には他の人間には感知しづらい『悪いもの』が見えてしまう。
加えて、ほんの些細な力ではあるが物体移動能力の真似事のようなこともできる。
そのため普段の彼女はテレキネシストとして振る舞い、本来の能力を隠している。
武器として刀を扱うが、剣道部所属というわけではなく、振り方や扱い方は完全に我流。
というよりも、もはや結果的に斬れているだけでそのやり口は鈍器のそれに近くもある。
これに上記の『神通力』を組み合わせての近接戦闘がはふりの戦い方である。
IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1585
◇金糸 エリ(かないと えり)
熾盛天晴学園の2年3組に在籍する女子。図書委員で電子工作部。
鉄色の憂いを帯びた瞳、錆色をした長く豊かな髪。色白で華奢。身長は150cm前後。
学校指定の服装を着崩さずに着用。近付けばかすかに分かる程度に香水の香り。
成績は学年トップクラス、規則を守り生活態度も良好と典型的な優等生タイプ。
一方であまり人と話したがらず、休み時間は部室や図書室にこもりがち。
あまり彼女と仲の良くない人間からすると、不愛想で冷たい人格にも見えるだろう。
彼女の有する能力は『機械の魔女(マギア・マキナ)』。
自分が所有する無機物に対して命令を与え、それを実行させる能力。
所有の基準は曖昧だが、少なくとも自身がある程度の手を加えたものに限られるようだ。
店の売り物や今拾ったものを所有物と言い張ることがエリの性格上できないからだろう。
命令について、所有したての物に関しては移動等の簡単な物に限られるが、エリが多く手を加えた物・長く所有した物についてはより複雑な命令を加えることが可能となる。
この能力を活かし、エリの部屋には料理をする機械人形、洗濯をする機械人形などが存在している。
IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1586
☆Special Thanks!!
はふりのプロフィール画像、アイコン→渡部アクサ様
はふりのサンタアイコン→霜咲様
エリのプロフィール画像、アイコン→有織様
この場を借りてお礼申し上げます!
25 / 30
202 PS
ヒノデ区
P-9
P-9




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 視界 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 神気 | 装飾 | 40 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 祓 | 防具 | 97 | 奪命10 | 風柳10 | - | |
| 7 | パーカー | 防具 | 82 | 敏捷10 | 敏捷10 | - | |
| 8 | 黒い貝 | 素材 | 20 | [武器]水撃15(LV25)[防具]反闇15(LV30)[装飾]闇纏15(LV25) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 無銘の刀 | 武器 | 67 | 器用15 | - | - | 【射程1】 |
| 11 | 白光の刀 | 武器 | 210 | 攻撃20 | 器用10 | - | 【射程1】 |
| 12 | 白眼視 | 装飾 | 120 | 舞凍15 | 器用10 | - | |
| 13 | |||||||
| 14 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 15 | |||||||
| 16 | 炊き込みごはん | 料理 | 120 | 貫撃10 | 器用10 | 深手20 | |
| 17 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 20 | 空間/時間/風 |
| 制約 | 20 | 拘束/罠/リスク |
| 解析 | 20 | 精確/対策/装置 |
| 装飾 | 60 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決3 | ストライク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 決1 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| 決1 | ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| 決1 | アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| エアブレイド | 5 | 0 | 100 | 敵列:風撃 | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| クリエイト:ダイナマイト | 5 | 0 | 120 | 自:道連LV増 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| アイシング | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| タッチダウンライズ | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+HP減+連続増 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| クリエイト:メガネ | 5 | 0 | 100 | 味:DX・AG増(5T) | |
| 決3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| デストロイ | 5 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| パリィ | 5 | 5 | 0 | 自:AG増(2T)+SP増 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| フェイタルポイント | 5 | 0 | 80 | 敵:精確痛撃 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| コールドイミッター | 5 | 0 | 120 | 敵貫:水撃&凍結+自:精確火撃&炎上 | |
| エナジーウォール | 5 | 0 | 100 | 自:MSP減+味全:DF増(1T) | |
| バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |
| インパクト | 5 | 0 | 120 | 自:HP減+敵:風痛撃 | |
| アドバースウィンド | 5 | 0 | 70 | 自:隊列後退+LK増(2T) | |
| ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| 決3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| スカイディバイド | 5 | 1 | 150 | 敵貫:風撃&風耐性減 | |
| タイムリーバー | 5 | 0 | 10 | 自:混乱+瞬発LV増 | |
| 決3 | ハードブレイク | 8 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
| 決1 | ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 |
| ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |
| ウィンドコイル | 5 | 0 | 150 | 敵:風領痛撃&領域値[風]3以上なら風撃化(1T) | |
| スクランブル | 5 | 2 | 180 | 敵:4連風領撃+自:連続増&瀕死なら連続増 | |
| インペイル | 5 | 0 | 170 | 敵貫:痛撃+自:祝福消費で連続増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 幸星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:祝福 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 決3 | 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
| 修復 | 5 | 3 | 0 | 【被HP回復後】自:守護 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 見切 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率増 | |
| 死線 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃命中率増 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
奪略の牙 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
ウィンドカッター (ウィンドカッター) |
0 | 50 | 敵3:風撃 | |
|
アマルガムゴート (マナポーション) |
0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
| 決3 |
fly high (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| 決3 |
クリエイト:グレイル (クリエイト:グレイル) |
0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
| 決3 |
チャクラグラント (チャクラグラント) |
2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 |
|
カフェオレ (ラッシュ) |
0 | 100 | 味全:連続増 | |
|
調視の魔眼 (エファヴェセント) |
0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) | |
|
いいサングラス (クリエイト:ラビリンス) |
0 | 300 | 味傷5:HP増+味傷:DFかAGかLK増(3T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]マインドボム | [ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]プリディクション |
| [ 3 ]グランドクラッシャー | [ 3 ]ヒールポーション | [ 1 ]バーニングチューン |
| [ 1 ]クイックレメディ | [ 1 ]ヒートイミッター | [ 1 ]ケイオティックチェイス |
| [ 3 ]パワフルヒール | [ 3 ]インパクト | [ 3 ]ハードブレイク |
| [ 1 ]レッドショック |

PL / タカミ