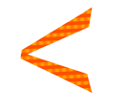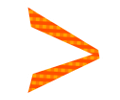<< 2:00~3:00




「――アタシ生まれ変われるの?」
怪人に改造する。そのおぞましい提案を受け入れ、案内されるままに研究室へと足を踏み入れる。薄暗い部屋の中には様々な生物のサンプルがあるという話だったが、私には難しくてよくわからなかった。準備のために麻酔が必要かと聞かれたから、聞いてくれるなら使ってくれと伝える。痩せ細った腕に針が突き立てられ、遠のくに任せて意識を手放した。それはきっと、家を出て以来はじめての、安らかな眠りだったろう。
心地良い微睡みから醒めると、液体の中に浸かっていて少し驚く。培養液と呼ぶらしい。様々な機材が私の体に繋がれていて、声を発することはできなかったが向こうにはちゃんと意思が伝わっているようだった。そんな状態で他愛もない話や、いくつかの質問に答えた。見せられた中ではクラゲが綺麗だと思ったことや、山と海なら海が好きってことや、星空が好きで手が届くんじゃないかと異能を使ってうんと手を伸ばしたこと。冗談で金髪碧眼にして欲しいなんてことを伝えたら、いいよと言われてしまって少し面食らった。なんでも伝えてみるもんだ。逆にしたくないこと、なりたくないものはあるかと聞かれ、質問に被せ気味に『親という生き物になりたくない』と答えた。
そうして再び微睡みに身を任せ、目覚めたときには改造は終わっていた。一糸まとわぬ肌が外気に触れると、夏だというのにひどく寒く、そのことを伝えたところどうやら改造も大成功ではなかったことがわかった。同時に、適正がなければ肉塊や液状になっていたであろうことも知った。『選ばれた』と思った。この日のために生まれ、耐え延びてきたのだと思った。人類真化がどういうことなのか、正しくはわからないけれど。そのひとりとして選ばれたのだと。寒さの核は下腹部の――子宮のあったであろう場所にあった。そこに今の『自分』がいると、漠然とした確信がある。いつか星空にそうしたように、外に出ようと手を伸ばす。腹を突き破るように『私』の腕が飛び出し、裏返るようにその身を転ずる。哄笑を響かせ、怪人ルナリウムが産声を上げた。

落ち着いて眠れる場所。落ち着いて取れる食事。むっしゃむっしゃとご飯を食べながら、家にいた頃よりもいい生活をしているなと思った。あれから少しずつ色々なことを教えられたり、怪人としての活動をしたりしている。いずれ学生としてどこかの学校に潜入する予定があるらしく、遅れていた勉強をさせられたり、自分の怪人態の性質について少しずつ把握していったり。いわゆる犯罪行為にも手を染めたが、元々手癖の悪かった自分には特に気負うこともなかった。すり減っていた心も調子を取り戻したのか、陽気な様を周囲に振りまいていた。やはり、すっかり生まれ変わったのだと、新しい人生は希望に満ちていた。ただ、少しだけ胸に引っかかるものがあったが、しばらくはそれが何かわからずにいた。
ある日ハカセのちょっとしたボヤキを耳にした。曰く、新しい実験体が欲しいとのことだった。自分が探してくると伝えたところ、『いなくなっても大丈夫なヒト』を選ぶようにと指示を受けた。なぜ自分から申し出たのか?それはハカセにお礼をしたかったこともあるが、それとは別に胸の引っかかりの原因はこれだという確信があったからだった。私は私の世界から『いなくなっても大丈夫なヒト』を、探しにいくことにした。

久しぶりに顔を見せ、自分だと気付いたときの曖昧な態度がひどく滑稽だった。野垂れ死んだと思っていたのだろう、少し動揺してから落ち着きを取り戻すと、高圧的に上からモノを言ってくるものだから、笑い飛ばして部屋の奥に蹴り飛ばしてやった。女の悲鳴が聞こえたから自分も中に入って見てみたら若い女が怯えた目でこちらを見ていた。連れ帰る予定も、見逃すつもりもなかったから、そこで怪人に転じて、私の姿を見て上げた悲鳴をすり潰すように、触腕で女の頭を潰した。潰れたトマトのようになったそれを見て、父親だった男は態度を一転して命乞いをし始めた。おとなしく付いてきて改造されろと伝えたところ「バケモノが馬鹿にするな」と激昂しバットで――きっとあの時のバットだったのだろう――殴りかかろうとしてきた。触腕でバットを奪い取ると、そのままそのバットを振り抜いて顎を砕き、昏倒したところをラボへ連れ帰った。

最後に会ったのは父親よりも前だったのに、私だと気付くのは母親の方が早かった。そのことが気に入らなくて、突き飛ばして尻餅をつかせる。倒れるときに腹を守るため体をひねるのを見て、舌打ちが漏れた。再婚したらしく、その腹は随分と大きくなっていた。旦那は不在のようで、頼る相手もおらず怯えたような死線を私に向けた。ずいと近寄り見下すような角度で、改造するためにおとなしく付いてくるよう伝える。混乱した口から出てきたのは「あなたお姉ちゃんになるんだから、こんなバカなことはやめて!」なんて言葉だった。何がお姉ちゃんだ。何がお姉ちゃんだ!なりたくねえよ。そんなもんなりたいなんて、思ったこともない!頭に血が登って何度も何度も、何度も、何度も、執拗にその腹を蹴り飛ばした。腹を守るように体を丸めるのが、よりいっそう怒りに火をつけた。私を見捨てたヤツが、まっとうな母親のふりをするんじゃあない。肩で息をしていることに気付いて、舌打ちを重ねる。怪人に転じ、胸ぐらを掴み無理やり私の姿を見せる。怪人の姿を目にすると、ヒュッと息を呑み、体を慄きに震わせながら、絞り出すように母娘としての断絶の言葉を私に浴びせかける。私は冷えた気持ちで、触腕でゆるやかに首を絞め意識を奪い、ラボへと連れ帰った。
怪人改造を終えたあとのある日、ハカセに名前について聞かれたことがあった。偽装した戸籍を用意するから、希望の名前はあるかと。私は少し逡巡してから、『サツキ』がいいと答えた。それは私がヒトだったときと同じ名前だった。未練があるのかと問われ、笑い飛ばす。私は真化に選ばれたが、それまでの理不尽を許すわけじゃない。私を苦しめたヒトへの憎しみを忘れないために、ヒトとして生きていたときの名前で、ヒトの世に溶け込む。この名は憎悪に火をくべる薪だ。憎しみがなければ、この新たな命に満たされてしまうだろうから。
そしてこれは、彼女がもう思い出すことのない記憶。ずっと幼い頃、まだ家族が家族のカタチをしていた頃。母親が彼女の名前の由来を聞かせていたことがあった。「私の一番好きな季節に生まれてくれたから、その月の名前を付けたのよ」そんな単純で、けれど確かな愛があったことは、憎しみの感情に塗りつぶされて隠されてしまった。愛されていた証は、その由来を見失い、憎しみの象徴となった。暦の月は失われ、狂気の月が昇った。
連れ帰った二人をハカセに引き渡し、培養液の中で改造されていくさまをぼんやりと見つめていた。途中で飽きたので終わったら呼んでと退室する。昼寝をしているところを起こされ再びラボに向かうと、ゼリー状になった肉が2つ転がっていた。適正がなくて失敗したようだと、ハカセは残念そうに言っていた。私は胸のつかえがとれたのを感じていた。ああそうだ、ずっといなくなればいいと思っていた。ヒトへの憎しみだけを残して、過去の自分との最後の繋がりが断たれたのだ。その夜、久しぶりに星空を眺めることにした。いつの日か陰っていた雲はなく、満天の星空だった。幼い日にそうしたように、うんと背伸びをして空へ手を伸ばした。異能を用いてもまだまだ届かなかったが、いつか届くかもしれないという希望が、胸にあった。
月が、満月が昇る。煌々と輝いて、近くの星の輝きを飲み込んで。
怪人ルナリウム――裏辺彩月が、真に生まれた日だった。



ENo.105 アマネ とのやりとり

ENo.262 バイタルエクス とのやりとり

ENo.821 ハニィ とのやりとり

以下の相手に送信しました




アマネ(105) から 何か固い物体 を手渡しされました。
アマネ(105) に ItemNo.8 平石 を手渡ししました。









セオリ(801) に ItemNo.9 針 を送付しました。
変化LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
望夢(238) により ItemNo.11 針 から装飾『凶夢の仮面』を作製してもらいました!
⇒ 凶夢の仮面/装飾:強さ67/[効果1]器用15 [効果2]- [効果3]-
リミュ(411) の持つ ItemNo.10 牙 から射程1の武器『あたたかまるい珠』を作製しました!
ItemNo.12 何か固い物体 から射程2の武器『残夜の天幕』を作製しました!
⇒ 残夜の天幕/武器:強さ67/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
セオリ(801) の持つ ItemNo.7 藍鉄鉱 から射程2の武器『雲錦』を作製しました!
.EXE(404) とカードを交換しました!
キャッシュクリア (エリアグラスプ)

バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
バーニングチューン を研究しました!(深度1⇒2)
バーニングチューン を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
レッドアゲート を習得!
アースタンブア を習得!
プチメテオカード を習得!
ブルーム を習得!
環境変調特性 を習得!
剛健 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



アマネ(105) は 孔雀石 を入手!
ルナリウム(777) は 藍鉄鉱 を入手!
セオリ(801) は 平石 を入手!
ハニィ(821) は 平石 を入手!
ハニィ(821) は 牙 を入手!
ハニィ(821) は 牙 を入手!
アマネ(105) は 牙 を入手!
アマネ(105) は 羽 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ハニィ(821) のもとに 大山猫 が泣きながら近づいてきます。
ハニィ(821) のもとに オオホタル が恥ずかしそうに近づいてきます。



アマネ(105) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-9(森林)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 B-4(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
セオリ(801) をパーティに勧誘しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ルナリウム(777) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- セオリ(801) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- ルナリウム(777) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- セオリ(801) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――








仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














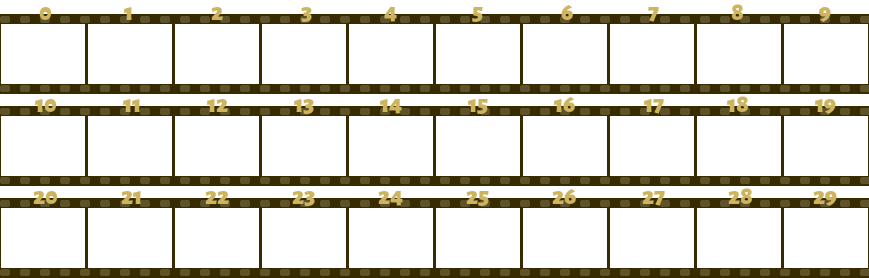







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



暴力的な表現や倫理観の欠けた表現がございます。ご注意ください。
「――アタシ生まれ変われるの?」
怪人に改造する。そのおぞましい提案を受け入れ、案内されるままに研究室へと足を踏み入れる。薄暗い部屋の中には様々な生物のサンプルがあるという話だったが、私には難しくてよくわからなかった。準備のために麻酔が必要かと聞かれたから、聞いてくれるなら使ってくれと伝える。痩せ細った腕に針が突き立てられ、遠のくに任せて意識を手放した。それはきっと、家を出て以来はじめての、安らかな眠りだったろう。
心地良い微睡みから醒めると、液体の中に浸かっていて少し驚く。培養液と呼ぶらしい。様々な機材が私の体に繋がれていて、声を発することはできなかったが向こうにはちゃんと意思が伝わっているようだった。そんな状態で他愛もない話や、いくつかの質問に答えた。見せられた中ではクラゲが綺麗だと思ったことや、山と海なら海が好きってことや、星空が好きで手が届くんじゃないかと異能を使ってうんと手を伸ばしたこと。冗談で金髪碧眼にして欲しいなんてことを伝えたら、いいよと言われてしまって少し面食らった。なんでも伝えてみるもんだ。逆にしたくないこと、なりたくないものはあるかと聞かれ、質問に被せ気味に『親という生き物になりたくない』と答えた。
そうして再び微睡みに身を任せ、目覚めたときには改造は終わっていた。一糸まとわぬ肌が外気に触れると、夏だというのにひどく寒く、そのことを伝えたところどうやら改造も大成功ではなかったことがわかった。同時に、適正がなければ肉塊や液状になっていたであろうことも知った。『選ばれた』と思った。この日のために生まれ、耐え延びてきたのだと思った。人類真化がどういうことなのか、正しくはわからないけれど。そのひとりとして選ばれたのだと。寒さの核は下腹部の――子宮のあったであろう場所にあった。そこに今の『自分』がいると、漠然とした確信がある。いつか星空にそうしたように、外に出ようと手を伸ばす。腹を突き破るように『私』の腕が飛び出し、裏返るようにその身を転ずる。哄笑を響かせ、怪人ルナリウムが産声を上げた。

サツキ
怪人1年生。
よく遊び、よく食べ、よくいたずらし、よく笑う。
すくすく育っている。
よく遊び、よく食べ、よくいたずらし、よく笑う。
すくすく育っている。
落ち着いて眠れる場所。落ち着いて取れる食事。むっしゃむっしゃとご飯を食べながら、家にいた頃よりもいい生活をしているなと思った。あれから少しずつ色々なことを教えられたり、怪人としての活動をしたりしている。いずれ学生としてどこかの学校に潜入する予定があるらしく、遅れていた勉強をさせられたり、自分の怪人態の性質について少しずつ把握していったり。いわゆる犯罪行為にも手を染めたが、元々手癖の悪かった自分には特に気負うこともなかった。すり減っていた心も調子を取り戻したのか、陽気な様を周囲に振りまいていた。やはり、すっかり生まれ変わったのだと、新しい人生は希望に満ちていた。ただ、少しだけ胸に引っかかるものがあったが、しばらくはそれが何かわからずにいた。
ある日ハカセのちょっとしたボヤキを耳にした。曰く、新しい実験体が欲しいとのことだった。自分が探してくると伝えたところ、『いなくなっても大丈夫なヒト』を選ぶようにと指示を受けた。なぜ自分から申し出たのか?それはハカセにお礼をしたかったこともあるが、それとは別に胸の引っかかりの原因はこれだという確信があったからだった。私は私の世界から『いなくなっても大丈夫なヒト』を、探しにいくことにした。

男
サツキの父親だった。
娘の逃亡後も酒に溺れ続けている。
最近若い女を部屋に連れ込んでいる。
娘の逃亡後も酒に溺れ続けている。
最近若い女を部屋に連れ込んでいる。
久しぶりに顔を見せ、自分だと気付いたときの曖昧な態度がひどく滑稽だった。野垂れ死んだと思っていたのだろう、少し動揺してから落ち着きを取り戻すと、高圧的に上からモノを言ってくるものだから、笑い飛ばして部屋の奥に蹴り飛ばしてやった。女の悲鳴が聞こえたから自分も中に入って見てみたら若い女が怯えた目でこちらを見ていた。連れ帰る予定も、見逃すつもりもなかったから、そこで怪人に転じて、私の姿を見て上げた悲鳴をすり潰すように、触腕で女の頭を潰した。潰れたトマトのようになったそれを見て、父親だった男は態度を一転して命乞いをし始めた。おとなしく付いてきて改造されろと伝えたところ「バケモノが馬鹿にするな」と激昂しバットで――きっとあの時のバットだったのだろう――殴りかかろうとしてきた。触腕でバットを奪い取ると、そのままそのバットを振り抜いて顎を砕き、昏倒したところをラボへ連れ帰った。

女
サツキの母親だった。
離婚後新しい相手と再婚した。
現在妊娠している。
離婚後新しい相手と再婚した。
現在妊娠している。
最後に会ったのは父親よりも前だったのに、私だと気付くのは母親の方が早かった。そのことが気に入らなくて、突き飛ばして尻餅をつかせる。倒れるときに腹を守るため体をひねるのを見て、舌打ちが漏れた。再婚したらしく、その腹は随分と大きくなっていた。旦那は不在のようで、頼る相手もおらず怯えたような死線を私に向けた。ずいと近寄り見下すような角度で、改造するためにおとなしく付いてくるよう伝える。混乱した口から出てきたのは「あなたお姉ちゃんになるんだから、こんなバカなことはやめて!」なんて言葉だった。何がお姉ちゃんだ。何がお姉ちゃんだ!なりたくねえよ。そんなもんなりたいなんて、思ったこともない!頭に血が登って何度も何度も、何度も、何度も、執拗にその腹を蹴り飛ばした。腹を守るように体を丸めるのが、よりいっそう怒りに火をつけた。私を見捨てたヤツが、まっとうな母親のふりをするんじゃあない。肩で息をしていることに気付いて、舌打ちを重ねる。怪人に転じ、胸ぐらを掴み無理やり私の姿を見せる。怪人の姿を目にすると、ヒュッと息を呑み、体を慄きに震わせながら、絞り出すように母娘としての断絶の言葉を私に浴びせかける。私は冷えた気持ちで、触腕でゆるやかに首を絞め意識を奪い、ラボへと連れ帰った。
怪人改造を終えたあとのある日、ハカセに名前について聞かれたことがあった。偽装した戸籍を用意するから、希望の名前はあるかと。私は少し逡巡してから、『サツキ』がいいと答えた。それは私がヒトだったときと同じ名前だった。未練があるのかと問われ、笑い飛ばす。私は真化に選ばれたが、それまでの理不尽を許すわけじゃない。私を苦しめたヒトへの憎しみを忘れないために、ヒトとして生きていたときの名前で、ヒトの世に溶け込む。この名は憎悪に火をくべる薪だ。憎しみがなければ、この新たな命に満たされてしまうだろうから。
そしてこれは、彼女がもう思い出すことのない記憶。ずっと幼い頃、まだ家族が家族のカタチをしていた頃。母親が彼女の名前の由来を聞かせていたことがあった。「私の一番好きな季節に生まれてくれたから、その月の名前を付けたのよ」そんな単純で、けれど確かな愛があったことは、憎しみの感情に塗りつぶされて隠されてしまった。愛されていた証は、その由来を見失い、憎しみの象徴となった。暦の月は失われ、狂気の月が昇った。
連れ帰った二人をハカセに引き渡し、培養液の中で改造されていくさまをぼんやりと見つめていた。途中で飽きたので終わったら呼んでと退室する。昼寝をしているところを起こされ再びラボに向かうと、ゼリー状になった肉が2つ転がっていた。適正がなくて失敗したようだと、ハカセは残念そうに言っていた。私は胸のつかえがとれたのを感じていた。ああそうだ、ずっといなくなればいいと思っていた。ヒトへの憎しみだけを残して、過去の自分との最後の繋がりが断たれたのだ。その夜、久しぶりに星空を眺めることにした。いつの日か陰っていた雲はなく、満天の星空だった。幼い日にそうしたように、うんと背伸びをして空へ手を伸ばした。異能を用いてもまだまだ届かなかったが、いつか届くかもしれないという希望が、胸にあった。
月が、満月が昇る。煌々と輝いて、近くの星の輝きを飲み込んで。
怪人ルナリウム――裏辺彩月が、真に生まれた日だった。
Luna-rium Origin 3/3
"Moon rises"
"Moon rises"



ENo.105 アマネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.262 バイタルエクス とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.821 ハニィ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
アマネ 「歩く…の何時間とかは、わからないけど、私はそろそろ休憩したい…かも。」 |
 |
「そういえば、イバラシティではバレンタインだったみたいだね。 みんなはど、どんな感じだったかな? わ…たし、実は誕生日だった。両親にお祝いしてもらったよ。えへへ。」 |
| サツキ 「チクショ~~~!!!”あっち”のアタシ!美味そうなチョコ食ってんじゃねえよ!!!」 |
| サツキ 「……ん、休憩?アタシはどっちでもいいけど、とりあえず美味いモン食おうや。我慢ならねえ。」 |
 |
バレンタインの話を聞いた途端、露骨な舌打ち。 |
 |
セオリ 「くだらぬ話題を。 ……勝手に盛り上がっておれ。儂に話を振るなら、その無駄に軟らかい頬肉を唇ごと引き裂いてやる。」 |
 |
セオリは何処かへと歩いていく。 |
 |
ハニィ 「おい、それじゃベースに帰還だ。 疲れた奴引っ張って行動が鈍くなるくらいならとっとと休憩した方がいい。 油断はするなよ」 |
 |
ハニィ 「バレンタイン・・・「はずれ」はチョコをもらってたようだな。物資が豊富なのはいいことだ」 |
アマネ(105) から 何か固い物体 を手渡しされました。
 |
アマネ 「固いんですよこれ…投げたら強そう。」 |
アマネ(105) に ItemNo.8 平石 を手渡ししました。





ホットペッパー団
|
 |
鬼彩天外
|



セオリ(801) に ItemNo.9 針 を送付しました。
変化LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
望夢(238) により ItemNo.11 針 から装飾『凶夢の仮面』を作製してもらいました!
⇒ 凶夢の仮面/装飾:強さ67/[効果1]器用15 [効果2]- [効果3]-
 |
望夢 「こちらが作製依頼品だ、うまく使ってくれ。」 |
リミュ(411) の持つ ItemNo.10 牙 から射程1の武器『あたたかまるい珠』を作製しました!
ItemNo.12 何か固い物体 から射程2の武器『残夜の天幕』を作製しました!
⇒ 残夜の天幕/武器:強さ67/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
| サツキ (コネコネ……) |
セオリ(801) の持つ ItemNo.7 藍鉄鉱 から射程2の武器『雲錦』を作製しました!
.EXE(404) とカードを交換しました!
キャッシュクリア (エリアグラスプ)

バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
バーニングチューン を研究しました!(深度1⇒2)
バーニングチューン を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
レッドアゲート を習得!
アースタンブア を習得!
プチメテオカード を習得!
ブルーム を習得!
環境変調特性 を習得!
剛健 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



アマネ(105) は 孔雀石 を入手!
ルナリウム(777) は 藍鉄鉱 を入手!
セオリ(801) は 平石 を入手!
ハニィ(821) は 平石 を入手!
ハニィ(821) は 牙 を入手!
ハニィ(821) は 牙 を入手!
アマネ(105) は 牙 を入手!
アマネ(105) は 羽 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ハニィ(821) のもとに 大山猫 が泣きながら近づいてきます。
ハニィ(821) のもとに オオホタル が恥ずかしそうに近づいてきます。



アマネ(105) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-9(森林)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 B-4(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
セオリ(801) をパーティに勧誘しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ルナリウム(777) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- セオリ(801) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- ルナリウム(777) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- セオリ(801) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







チナミ区 R-7
チェックポイント《廃ビル》
チェックポイント。チェックポイント《廃ビル》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《OWL》
黒闇に包まれた巨大なフクロウのようなもの。
 |
守護者《OWL》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.777
裏辺 彩月



うらべ さつき
【Age/Sex/Heiht】 : 【17/♀/173cm】
熾盛天晴学園 二年
背や態度や声など、何かと大きいイバラシティ出身の少女。
身勝手で自己中心的、反省することを覚えない問題児だが、軽いノリでどこにでも潜り込み、馴染んでは去っていくため、良くも悪くも、顔は広い。なぜか変わった愛称で相手を呼びたがる。
また、自身の容姿やスタイルについて自覚的であり、かつ自信がある。見られることに対しては、羞恥心よりも容姿が認められているという自尊心が上回るため、着飾ることやオシャレに対しては積極的な姿勢を見せる。
授業態度は悪く、おつむは弱い。
が、誰かと競争や勝負をするとき、偏った方向性にのみ鋭い閃きを見せる。『出し抜く』『裏をかく』『舞台から降ろす』といった方法であれば回転の良くなるその発想力が、正攻法に活かされることはない。
ヤマカンは当たるのでギリギリ赤点は免れている。
慢性的な低体温のため朝に弱く、日差しの強い日は日傘が欠かせない。逆に夜中は元気なため、様々な地区を夜歩きしている姿を見ることもあるだろう。病的なまでに白い肌は、普段は血色を良く見せるメイクでごまかしている。
彼女にとっての正しさとは自身を肯定するものであり、
社会的正義に対しては、強い嫌悪感を示す。
逆に、自身を認めてくれる相手に対しては気さくに接する。
【Talent】: 【裏面潜行≪コスモダイバー≫】
小型のワームホールを作り出す異能。
高い汎用性を持つが有機物は全身を通過させることができないなど、多くの制約があり、彼女自身の口からは『目に見える範囲に手とかを出せる穴が作れる』という表現をされる。
実際に彼女は自身の異能の本質を理解しておらず、
もっぱら生活を便利にする程度の使われ方をしている。
【Villain】:【ルナリウム】
怪人組織『XYZ』の構成員。宇宙クラゲの改造怪人。
仕込み日傘とマントの内側に広がる宇宙っぽい空間から触腕を伸ばす。
生まれ持った能力でないからか、使いこなせていない様子が見受けられる。
-----------------------------------------------------------
カード絵の枠はパクチ様(ENo661 平坂煉 PL)が作製したものを許可を得て使用しています。
この場を借りてお礼申しあげます。
【Age/Sex/Heiht】 : 【17/♀/173cm】
熾盛天晴学園 二年
背や態度や声など、何かと大きいイバラシティ出身の少女。
身勝手で自己中心的、反省することを覚えない問題児だが、軽いノリでどこにでも潜り込み、馴染んでは去っていくため、良くも悪くも、顔は広い。なぜか変わった愛称で相手を呼びたがる。
また、自身の容姿やスタイルについて自覚的であり、かつ自信がある。見られることに対しては、羞恥心よりも容姿が認められているという自尊心が上回るため、着飾ることやオシャレに対しては積極的な姿勢を見せる。
授業態度は悪く、おつむは弱い。
が、誰かと競争や勝負をするとき、偏った方向性にのみ鋭い閃きを見せる。『出し抜く』『裏をかく』『舞台から降ろす』といった方法であれば回転の良くなるその発想力が、正攻法に活かされることはない。
ヤマカンは当たるのでギリギリ赤点は免れている。
慢性的な低体温のため朝に弱く、日差しの強い日は日傘が欠かせない。逆に夜中は元気なため、様々な地区を夜歩きしている姿を見ることもあるだろう。病的なまでに白い肌は、普段は血色を良く見せるメイクでごまかしている。
彼女にとっての正しさとは自身を肯定するものであり、
社会的正義に対しては、強い嫌悪感を示す。
逆に、自身を認めてくれる相手に対しては気さくに接する。
【Talent】: 【裏面潜行≪コスモダイバー≫】
小型のワームホールを作り出す異能。
高い汎用性を持つが有機物は全身を通過させることができないなど、多くの制約があり、彼女自身の口からは『目に見える範囲に手とかを出せる穴が作れる』という表現をされる。
実際に彼女は自身の異能の本質を理解しておらず、
もっぱら生活を便利にする程度の使われ方をしている。
【Villain】:【ルナリウム】
怪人組織『XYZ』の構成員。宇宙クラゲの改造怪人。
仕込み日傘とマントの内側に広がる宇宙っぽい空間から触腕を伸ばす。
生まれ持った能力でないからか、使いこなせていない様子が見受けられる。
-----------------------------------------------------------
カード絵の枠はパクチ様(ENo661 平坂煉 PL)が作製したものを許可を得て使用しています。
この場を借りてお礼申しあげます。
30 / 30
305 PS
チナミ区
B-4
B-4
















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 闇夜の天幕 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 白夜の天幕 | 武器 | 35 | 治癒10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 雨空の怪皮 | 法衣 | 20 | 火纏10 | 火纏10 | 幸運6 | |
| 7 | ハンバーグ | 料理 | 25 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 藍鉄鉱 | 素材 | 20 | [武器]放凍15(LV25)[防具]反凍10(LV20)[装飾]舞凍15(LV25) | |||
| 9 | |||||||
| 10 | 悪夢の仮面 | 装飾 | 40 | 幸運10 | - | - | |
| 11 | 凶夢の仮面 | 装飾 | 67 | 器用15 | - | - | |
| 12 | 残夜の天幕 | 武器 | 67 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 35 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| デアデビル | 6 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| 怪人細胞再活性 (フィジカルブースター) | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |
| 練3 | プチメテオカード | 5 | 0 | 40 | 敵:粗雑地撃 |
| アラベスク | 5 | 0 | 50 | 味全:HP・AG増+魅了 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| バーニングチューン | 5 | 0 | 140 | 自:炎上+敵5:火撃&麻痺 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 怪人細胞活性・猛 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 怪人細胞活性・堅 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 怪人細胞活性・武 (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 怪人細胞活性・壁 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 怪人細胞活性・癒 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 怪人細胞活性・命 (太陽) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 怪人細胞活性・精 (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神抵抗性細胞活性 (精神変調耐性) | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
指先からビーム (ペネトレイト) |
0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
|
トキワ工房機械兵発注書 (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
|
猫のくせ毛 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
キャッシュクリア (エリアグラスプ) |
0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ウィンドカッター | [ 3 ]バーニングチューン | [ 3 ]イグニス |
| [ 3 ]ヘイルカード |

PL / やすお