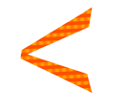<< 2:00~3:00




これは記だ。当然のことながら。
2月13日。聖ヴァレンタインデーの前日。
基本的には全てのものに敬意を払って生きていると自負していた。雨が降れば雨に敬意を払い、晴れれば太陽に敬意を払い、カスみたいなラーメンを食えば店主に敬意を払う(なんでこれほどまでにカスな逸品を?)。
ヴァレンタインデーは敬意を払われるべき深い歴史と伝統を持つイベントだ。何せ、歴史が深い。それにヴもついている。しかし、今日だけは違っていた。いわれや歴史など、そんなものはどうでも良かった。それどころではない、と言った方が正しいだろう。それもどっちでも良かった。大した問題ではない。
いいとこのホテルのヴァレンタインデープラン。正確には、ヴァレンタインデープラン(カップル限定)。既に予約は取れた。光栄にも、一緒に行く相手は決まっている。残ったのは……
「恰好……格好か」
天を仰ぐようにして椅子に全体重を預け、脱力しながら電子タバコをふかす(年齢や賃貸契約など法的な問題はクリアしているので大丈夫)。普段ならこの喉に刺さるようなミントのフレーバーが冷静になる手助けをしてくれるのだが、今回は冷静になっても何も解決しない。何せ、何が分からないのかすら分からないのだ。進みようがない。
いいとこのホテルに行くからには、それなりの服装で戦いに挑む必要があるだろう。そこまでは直感に頼らずとも瞬時に理解できた。が、その先──どんな服にしようか、という部分が想像出来ずにいた。
あまりにスパスパ吸っていたせいだろうか。味が極端に薄くなり、煙の出も悪くなってきた。リキッド切れだ。何も進展がないまま、ただいたずらに時間だけが過ぎていた事実を叩きつけられ、嘆息する。
咥えていた電子タバコを机に放り投げ、気合を入れて想像力をもう少し手前の段階に引き戻す。つまり、それなりの格好について思いを巡らせるよりも前に、いいとこのホテルに行くからにはそれなりの服装をしてくるであろう笹子さんの姿について。導き出される結論、それは普段の白衣姿とは違う、余所行きの笹子さんの姿が拝めるということでもある。私服ならば前に見たことが無いわけでもないが、あの時は単に初詣に来ていただけであって、余所行きとまではいかなかった。単純な理論展開として、あの時よりもそれっぽく着飾ってくるだろう。ならば、自分もそのラインに合わせればよい。
「合わせられるなら先にそうしてるんだよな……」
さらに追加で一時間ほど粘った結果、最終的にたどり着いた答えは””消去法””だった。勝利するためのゴテゴテした加点要素満載のSランクコーデではなく、基本に忠実に立ち回ってこそ真のコーデバトラーだ。大人しくジャケットにしとこう。身の丈に合うとはよく言ったものだ。
勝つためではない。負けないために戦うのだ──戦いの中に、答えはある。
2月15日。聖ヴァレンタインデーの翌日。
何故こうまで緊張しているのだろうか。
閉ざされていた昨日を抜け出した明日のそれは、今までのものとは質が明確に違っていた。仕事のついでだとか、大仰な行事を羅列した先にたどり着いたディナーだとか、偶然出くわしたものではない。明確に、日時と場所を指定して、誘いをかけたイベントだった。このタイミングで予定を確認しておいて、ただケーキが食べたいだけというのは、大義名分としてはいささか不十分だろう。そんなことは百も承知だった。
お誘いする側にもかかわらず、笹子さんの助け舟には驚くほど助けられた。あの冷静な観察力と、差し出される救いの的確な深さがとても好ましいと思っている──好ましさの百科事典の中の、ほんの一つの索引に過ぎないわけだが。
時計の針(デジタルだし心拍数も測れる優れもの)は集合時間の手前を指している。こんな重大な用件でもなければ来ないような人口密度の中、季節柄カップルやそれに類する表現で構成された人波を尻目に一人耐え続けるのは精神衛生上良くない行為であり、繰り返すが普段ならば絶対に利用しない乗り換えを乗り越え普段ならば絶対に足を運ばない空間で普段ならば絶対に過ごさない時間を過ごすのは孤独であり過酷だった。視界のすべてが過剰で、今日のワクワク感で何とか保っていた自我が自然とこの場からランダムに半数くらい消滅したらもうちょっと心穏やかに待てるかもしれないという過激な思想へと変化しかけた頃、ふと気配を感じて直感的に目を向け──目を疑った。
直感の通り、そこにいたのは笹子さんその人だった。それでも目を疑ったのは、当然と言えば当然だが、普段とは全く違う笹子さんの姿がそこにあり、人間が得る情報の八割は視覚からというその手の学会や専門家の間でまことしやかに囁かれている学術的見地に基づき、情報量に混乱したためだった。
何せ、髪を下ろしている……いや、いつも下ろしているか。そこはいつもと同じだ。混乱している。
人間は視界を変える際、例えば横を向く時などは、あらかじめ脳がそこにあるであろう光景をシミュレートしているとも聞く。想定外の事態に弱いのは、人間のセキュリティホールそのものと言えるだろう。
「ごめんね、待たせちゃったかしら……どうかした?」
「あ。いや、いえ、えーと……僕は大丈夫です」
おかしなことを口走る自分に向かって、おかしなことを言うのねと怪訝そうに眉をひそめるも、特に追及することなく彼女は──笹子さんは表情を変えた。期待、あるいは自分の辞書に載っていない感情が宿っているような、そんな顔で。
「……それで? 会場は向こうよね?」
「会場は向こうですが……それで、といいますと?」
「もう! 今日は貴方の予定でしょ。ちゃんとして貰わないと困るわよ」
言いながら、腰に手を当てて口をとがらせる。
基本的には全てのものに敬意を払って生きていると自負していたし、ちゃんとしているつもりだったが、彼女が言いたいのはそういうことではないらしい。見慣れぬ姿に着飾った笹子さんから目を逸らす(思考がまとまらない)ようにしてしばし無言で考え込み、どうにかこうにか答えに手を伸ばした。
「……アレですね。分かりました──今日はありがとうございます。一日だけ……当日その場限りではありますが、僕とあの、カップルを……演じて、いただいて……」
「えっ、いや……そういうのは、もっと、後で、ちゃんと聞きたかったんだけど……」
しくじった。顔が、全身がカッと熱せられたかのように上気していくのを感じる。汗の一つや二つ流れているかもしれない。自分だけではなく、笹子さんもまた顔を真っ赤にしているのが見えた。公衆の面前、天下の往来で口走ったのは間違いだったかなと臍を噛む。気まずい沈黙。
「ええと、じゃあ。えー……本日はヴァレンタインということで、不肖私めがエスコートさせていただきますね……みたいな感じですか?」
「そこ、それを聞いちゃったら台無しじゃない。でも、良いわ。今日はお誘いありがとう。……エスコートしてくれる気なら、楽しませてね?」
「……私を楽しませろって言い換えると急にラスボスっぽくなりますね」
「もう、茶化さないでよ。……あんまり茶化すと本当に立ちはだかっちゃうわよ? ラスボスみたいに」
苦笑いでかわされ、何度目かの反省をしながら。いよいよ時間も差し迫っているとの気づきを得たため、続きはケーキを食べながらと会場へと向かうことにした。道中何を話したのか、あまり覚えていない。ただ、いつもより強く周りの目を感じた。実際はそんなこともないのだろう。世間は無関心だ──人間は深淵ではないし、覗くことも覗き返すこともない。それでも、ある種居心地の悪さにも似たものが、笹子さんの隣を歩くことの誇らしさと同居していた。
その奥に、他愛のない世間話のような、気のない相槌を打っていたような、そんな記憶がかすかに残っていた。
ケーキの味は分からなかった。
別に経穴に針を刺されたわけではない。カップルプランというからには、当然席は向かい合って用意されていたのだ。正面に笹子さんが居て、普段とは違う装いの笹子さんが美味しそうにケーキに舌鼓を打つ姿を拝みながらでは、何を食べても味を感じないだろう。当初の目的は果たせなかったが、それでも十分幸せだった。
後日。
ヴァレンタインチョコレートケーキのお返しにと、笹子さんが箱入りのチョコをくれた。
部屋に帰って開けてみると、中には洒落たチョコの詰め合わせ、それに””たくさんの感謝を込めて””と記された一枚のカードが添えられていた。
一つ摘まんで口に運ぶ。とろけるような上品な口当たりの、上質(ハイグレード)なチョコレート。それでも一人で食べるチョコはどこか味気なかった。が、それは流石に贅沢というものだろう。
「はーーーーーー……なるほどね。そういう感じですか」
「背後には気を付けていたつもりなんですけどね。ままならないもんです……」
「……笹子さん、僕の背後は任せます」
もう少し賢くなるべきだったのかもしれない。伝説の探偵、ミゼンニ=フセーダのようにとは行かずとも、もっと早く気づくタイミングはあったはずだ。こうなることも、これが何を意味するのかも。
気づくのが遅かった。イバラシティでの友人が、ハザマでは敵となる可能性を考慮しなかったわけではないといえば嘘になる。ただ、信じたかったのかもしれない。自分に言い聞かせたかったのかもしれない。憔悴した様子で、それでも弱音も吐かず表情も変えぬ精神力を保っている笹子さんを、どうにか安心させるために。エゴが招いたのは危機だった。茅芽さんをつい呼びなれた方で呼んでしまうほどの、余裕のなさ。
頼りになる、とても大きな男だと思っていた。少なくとも、事実はそうだった。コインには裏と表があり、人にも裏と表があることから、人間は良くコインに例えられる。しかし、イバラシティでの彼と、ハザマで対面した彼の間には、コインの縁ほどのギャップも存在しないような気がした。表も裏もない、そのものがひとつ。例えるならば、しゃもじのような存在。メビウスの輪。
イバラでは友好的な関係性を得ていたはずだ。少なくとも、敵対的ではなかった。表裏のあるコインのように、自分にも自身ではきづけぬような表と裏があったとしても、そのどちらもが反目するような関係ではなかったと思っている。
それは誤りではないのだろう──少なくとも、イバラシティでは。ただ、楽観的過ぎただけだ。強化された異能の伸び代は、こういったところには全く生かされていないらしく、肝心な時に直感は働かない。
気づくべき遅れはもう一つあった。同様の懸念を、初めから、それこそ本当に初めの初めから──ハザマでコンタクトを取った最初の瞬間から、自分に対して笹子さんが抱いていた可能性について。
可能性。人間の可能性は無限大だ。少なくとも、正の方向にも、負の方向にも。
アンジニティの侵略者と戦いながら、いくつかの思いが去来していた。
自分は伝説の探偵には程遠いこと。直感は肝心なところであてにならないこと。笹子さんはずっと表情を隠しながらこちらに対応していたこと。この戦いを切り抜けても、更なる闇が待っているかもしれないこと。
信用出来る人間が、一人でも多く欲しかった。
いや、違う。
見えていない敵を、一人でも多く減らしたかった。
◆◇◆
http://lisge.com/ib/talk.php?dt_p=2278&dt_s=568&dt_sno=19327011&dt_jn=1&dt_kz=14
今回の日記はEno.831様との合作となっており、上記前日談からの続きとなっています。



ENo.831 Dr.笹子 とのやりとり

ENo.1097 アフレイド とのやりとり












解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
自然LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ItemNo.7 羽 に ItemNo.8 黄鉄鉱 を合成実験し、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
ItemNo.8 黄鉄鉱 に ItemNo.1 不思議な武器 を合成実験し、駄物 に変化することが判明しました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
ItemNo.8 黄鉄鉱 に ItemNo.10 硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ" を合成実験し、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
影縫(1040) とカードを交換しました!
《焼け落ちる記憶》 (ストライク)


先制 を研究しました!(深度0⇒1)
プチメテオカード を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
ブルーム を習得!
ビブラート を習得!
剛健 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 Q-8(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 Q-7(草原)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
Dr.笹子(831) をパーティに勧誘しました!
我孫子(607) をパーティに勧誘しました!
雀部(606) をパーティに勧誘しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 偽黒初(77) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 雀部(606) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 我孫子(607) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- Dr.笹子(831) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- 偽黒初(77) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- Dr.笹子(831) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














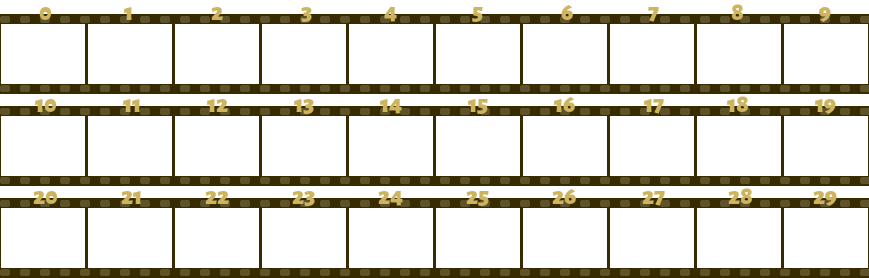







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



これは記だ。当然のことながら。
2月13日。聖ヴァレンタインデーの前日。
基本的には全てのものに敬意を払って生きていると自負していた。雨が降れば雨に敬意を払い、晴れれば太陽に敬意を払い、カスみたいなラーメンを食えば店主に敬意を払う(なんでこれほどまでにカスな逸品を?)。
ヴァレンタインデーは敬意を払われるべき深い歴史と伝統を持つイベントだ。何せ、歴史が深い。それにヴもついている。しかし、今日だけは違っていた。いわれや歴史など、そんなものはどうでも良かった。それどころではない、と言った方が正しいだろう。それもどっちでも良かった。大した問題ではない。
いいとこのホテルのヴァレンタインデープラン。正確には、ヴァレンタインデープラン(カップル限定)。既に予約は取れた。光栄にも、一緒に行く相手は決まっている。残ったのは……
「恰好……格好か」
天を仰ぐようにして椅子に全体重を預け、脱力しながら電子タバコをふかす(年齢や賃貸契約など法的な問題はクリアしているので大丈夫)。普段ならこの喉に刺さるようなミントのフレーバーが冷静になる手助けをしてくれるのだが、今回は冷静になっても何も解決しない。何せ、何が分からないのかすら分からないのだ。進みようがない。
いいとこのホテルに行くからには、それなりの服装で戦いに挑む必要があるだろう。そこまでは直感に頼らずとも瞬時に理解できた。が、その先──どんな服にしようか、という部分が想像出来ずにいた。
あまりにスパスパ吸っていたせいだろうか。味が極端に薄くなり、煙の出も悪くなってきた。リキッド切れだ。何も進展がないまま、ただいたずらに時間だけが過ぎていた事実を叩きつけられ、嘆息する。
咥えていた電子タバコを机に放り投げ、気合を入れて想像力をもう少し手前の段階に引き戻す。つまり、それなりの格好について思いを巡らせるよりも前に、いいとこのホテルに行くからにはそれなりの服装をしてくるであろう笹子さんの姿について。導き出される結論、それは普段の白衣姿とは違う、余所行きの笹子さんの姿が拝めるということでもある。私服ならば前に見たことが無いわけでもないが、あの時は単に初詣に来ていただけであって、余所行きとまではいかなかった。単純な理論展開として、あの時よりもそれっぽく着飾ってくるだろう。ならば、自分もそのラインに合わせればよい。
「合わせられるなら先にそうしてるんだよな……」
さらに追加で一時間ほど粘った結果、最終的にたどり着いた答えは””消去法””だった。勝利するためのゴテゴテした加点要素満載のSランクコーデではなく、基本に忠実に立ち回ってこそ真のコーデバトラーだ。大人しくジャケットにしとこう。身の丈に合うとはよく言ったものだ。
勝つためではない。負けないために戦うのだ──戦いの中に、答えはある。
2月15日。聖ヴァレンタインデーの翌日。
何故こうまで緊張しているのだろうか。
閉ざされていた昨日を抜け出した明日のそれは、今までのものとは質が明確に違っていた。仕事のついでだとか、大仰な行事を羅列した先にたどり着いたディナーだとか、偶然出くわしたものではない。明確に、日時と場所を指定して、誘いをかけたイベントだった。このタイミングで予定を確認しておいて、ただケーキが食べたいだけというのは、大義名分としてはいささか不十分だろう。そんなことは百も承知だった。
お誘いする側にもかかわらず、笹子さんの助け舟には驚くほど助けられた。あの冷静な観察力と、差し出される救いの的確な深さがとても好ましいと思っている──好ましさの百科事典の中の、ほんの一つの索引に過ぎないわけだが。
時計の針(デジタルだし心拍数も測れる優れもの)は集合時間の手前を指している。こんな重大な用件でもなければ来ないような人口密度の中、季節柄カップルやそれに類する表現で構成された人波を尻目に一人耐え続けるのは精神衛生上良くない行為であり、繰り返すが普段ならば絶対に利用しない乗り換えを乗り越え普段ならば絶対に足を運ばない空間で普段ならば絶対に過ごさない時間を過ごすのは孤独であり過酷だった。視界のすべてが過剰で、今日のワクワク感で何とか保っていた自我が自然とこの場からランダムに半数くらい消滅したらもうちょっと心穏やかに待てるかもしれないという過激な思想へと変化しかけた頃、ふと気配を感じて直感的に目を向け──目を疑った。
直感の通り、そこにいたのは笹子さんその人だった。それでも目を疑ったのは、当然と言えば当然だが、普段とは全く違う笹子さんの姿がそこにあり、人間が得る情報の八割は視覚からというその手の学会や専門家の間でまことしやかに囁かれている学術的見地に基づき、情報量に混乱したためだった。
何せ、髪を下ろしている……いや、いつも下ろしているか。そこはいつもと同じだ。混乱している。
人間は視界を変える際、例えば横を向く時などは、あらかじめ脳がそこにあるであろう光景をシミュレートしているとも聞く。想定外の事態に弱いのは、人間のセキュリティホールそのものと言えるだろう。
「ごめんね、待たせちゃったかしら……どうかした?」
「あ。いや、いえ、えーと……僕は大丈夫です」
おかしなことを口走る自分に向かって、おかしなことを言うのねと怪訝そうに眉をひそめるも、特に追及することなく彼女は──笹子さんは表情を変えた。期待、あるいは自分の辞書に載っていない感情が宿っているような、そんな顔で。
「……それで? 会場は向こうよね?」
「会場は向こうですが……それで、といいますと?」
「もう! 今日は貴方の予定でしょ。ちゃんとして貰わないと困るわよ」
言いながら、腰に手を当てて口をとがらせる。
基本的には全てのものに敬意を払って生きていると自負していたし、ちゃんとしているつもりだったが、彼女が言いたいのはそういうことではないらしい。見慣れぬ姿に着飾った笹子さんから目を逸らす(思考がまとまらない)ようにしてしばし無言で考え込み、どうにかこうにか答えに手を伸ばした。
「……アレですね。分かりました──今日はありがとうございます。一日だけ……当日その場限りではありますが、僕とあの、カップルを……演じて、いただいて……」
「えっ、いや……そういうのは、もっと、後で、ちゃんと聞きたかったんだけど……」
しくじった。顔が、全身がカッと熱せられたかのように上気していくのを感じる。汗の一つや二つ流れているかもしれない。自分だけではなく、笹子さんもまた顔を真っ赤にしているのが見えた。公衆の面前、天下の往来で口走ったのは間違いだったかなと臍を噛む。気まずい沈黙。
「ええと、じゃあ。えー……本日はヴァレンタインということで、不肖私めがエスコートさせていただきますね……みたいな感じですか?」
「そこ、それを聞いちゃったら台無しじゃない。でも、良いわ。今日はお誘いありがとう。……エスコートしてくれる気なら、楽しませてね?」
「……私を楽しませろって言い換えると急にラスボスっぽくなりますね」
「もう、茶化さないでよ。……あんまり茶化すと本当に立ちはだかっちゃうわよ? ラスボスみたいに」
苦笑いでかわされ、何度目かの反省をしながら。いよいよ時間も差し迫っているとの気づきを得たため、続きはケーキを食べながらと会場へと向かうことにした。道中何を話したのか、あまり覚えていない。ただ、いつもより強く周りの目を感じた。実際はそんなこともないのだろう。世間は無関心だ──人間は深淵ではないし、覗くことも覗き返すこともない。それでも、ある種居心地の悪さにも似たものが、笹子さんの隣を歩くことの誇らしさと同居していた。
その奥に、他愛のない世間話のような、気のない相槌を打っていたような、そんな記憶がかすかに残っていた。
ケーキの味は分からなかった。
別に経穴に針を刺されたわけではない。カップルプランというからには、当然席は向かい合って用意されていたのだ。正面に笹子さんが居て、普段とは違う装いの笹子さんが美味しそうにケーキに舌鼓を打つ姿を拝みながらでは、何を食べても味を感じないだろう。当初の目的は果たせなかったが、それでも十分幸せだった。
後日。
ヴァレンタインチョコレートケーキのお返しにと、笹子さんが箱入りのチョコをくれた。
部屋に帰って開けてみると、中には洒落たチョコの詰め合わせ、それに””たくさんの感謝を込めて””と記された一枚のカードが添えられていた。
一つ摘まんで口に運ぶ。とろけるような上品な口当たりの、上質(ハイグレード)なチョコレート。それでも一人で食べるチョコはどこか味気なかった。が、それは流石に贅沢というものだろう。
──────
「はーーーーーー……なるほどね。そういう感じですか」
「背後には気を付けていたつもりなんですけどね。ままならないもんです……」
「……笹子さん、僕の背後は任せます」
もう少し賢くなるべきだったのかもしれない。伝説の探偵、ミゼンニ=フセーダのようにとは行かずとも、もっと早く気づくタイミングはあったはずだ。こうなることも、これが何を意味するのかも。
気づくのが遅かった。イバラシティでの友人が、ハザマでは敵となる可能性を考慮しなかったわけではないといえば嘘になる。ただ、信じたかったのかもしれない。自分に言い聞かせたかったのかもしれない。憔悴した様子で、それでも弱音も吐かず表情も変えぬ精神力を保っている笹子さんを、どうにか安心させるために。エゴが招いたのは危機だった。茅芽さんをつい呼びなれた方で呼んでしまうほどの、余裕のなさ。
頼りになる、とても大きな男だと思っていた。少なくとも、事実はそうだった。コインには裏と表があり、人にも裏と表があることから、人間は良くコインに例えられる。しかし、イバラシティでの彼と、ハザマで対面した彼の間には、コインの縁ほどのギャップも存在しないような気がした。表も裏もない、そのものがひとつ。例えるならば、しゃもじのような存在。メビウスの輪。
イバラでは友好的な関係性を得ていたはずだ。少なくとも、敵対的ではなかった。表裏のあるコインのように、自分にも自身ではきづけぬような表と裏があったとしても、そのどちらもが反目するような関係ではなかったと思っている。
それは誤りではないのだろう──少なくとも、イバラシティでは。ただ、楽観的過ぎただけだ。強化された異能の伸び代は、こういったところには全く生かされていないらしく、肝心な時に直感は働かない。
気づくべき遅れはもう一つあった。同様の懸念を、初めから、それこそ本当に初めの初めから──ハザマでコンタクトを取った最初の瞬間から、自分に対して笹子さんが抱いていた可能性について。
可能性。人間の可能性は無限大だ。少なくとも、正の方向にも、負の方向にも。
アンジニティの侵略者と戦いながら、いくつかの思いが去来していた。
自分は伝説の探偵には程遠いこと。直感は肝心なところであてにならないこと。笹子さんはずっと表情を隠しながらこちらに対応していたこと。この戦いを切り抜けても、更なる闇が待っているかもしれないこと。
信用出来る人間が、一人でも多く欲しかった。
いや、違う。
見えていない敵を、一人でも多く減らしたかった。
◆◇◆
http://lisge.com/ib/talk.php?dt_p=2278&dt_s=568&dt_sno=19327011&dt_jn=1&dt_kz=14
今回の日記はEno.831様との合作となっており、上記前日談からの続きとなっています。



ENo.831 Dr.笹子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1097 アフレイド とのやりとり



 |
Dr.笹子 「一旦解散、ね。何も起きないといいのだけれども」 |







解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
自然LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ItemNo.7 羽 に ItemNo.8 黄鉄鉱 を合成実験し、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
ItemNo.8 黄鉄鉱 に ItemNo.1 不思議な武器 を合成実験し、駄物 に変化することが判明しました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
ItemNo.8 黄鉄鉱 に ItemNo.10 硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ" を合成実験し、何か柔らかい物体 に変化することが判明しました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
影縫(1040) とカードを交換しました!
《焼け落ちる記憶》 (ストライク)


先制 を研究しました!(深度0⇒1)
プチメテオカード を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
ブルーム を習得!
ビブラート を習得!
剛健 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 Q-8(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 Q-7(草原)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
Dr.笹子(831) をパーティに勧誘しました!
我孫子(607) をパーティに勧誘しました!
雀部(606) をパーティに勧誘しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 偽黒初(77) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 雀部(606) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 我孫子(607) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- Dr.笹子(831) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- 偽黒初(77) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- Dr.笹子(831) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







徹夜明け3日目御一行
|
 |
放課後駄弁り隊
|




チナミ区 R-7
チェックポイント《廃ビル》
チェックポイント。チェックポイント《廃ビル》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《OWL》
黒闇に包まれた巨大なフクロウのようなもの。
 |
守護者《OWL》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.77
偽黒初



とある組織の助手。正確な肩書きは部長秘書兼所長代理補佐。
白長須、スーシロナガとも呼ばれることで知られるが、今回は偽黒初を名乗る。支所立ち上げのため、上司と共に栄転してきた。
特技はトランプ手裏剣。武器はワイヤー。ワイヤー使いにしては情に厚く涙もろい一面もある男だったが――?
好き:ハーブティ(ジャスミンとカモミール)
ベリー系のお菓子 女児アニメ 定期ゲー
嫌い:辛いもの 生臭い魚 窓の無い風呂
よくないAI ツイッター
資格:普通免許三十段 ワイヤー使い(乙種) 第一種五行鑑定士
異能:有有有利有利有利(アドアドアドバンテージテージ)
リスクリターンの直感を強化する異能。
??:Unknown.....
──以下サブキャラ──
シズカ・バンクラプト
避田高の体育教師。クズ。
異能:ヨケルギウスの加護
アイコン24
〼子美麗(ますこ・みゅうる)
避田高の全聞部部長。
異能:濃縮還元(プレスリリース)
アイコン25~29
白長須、スーシロナガとも呼ばれることで知られるが、今回は偽黒初を名乗る。支所立ち上げのため、上司と共に栄転してきた。
特技はトランプ手裏剣。武器はワイヤー。ワイヤー使いにしては情に厚く涙もろい一面もある男だったが――?
好き:ハーブティ(ジャスミンとカモミール)
ベリー系のお菓子 女児アニメ 定期ゲー
嫌い:辛いもの 生臭い魚 窓の無い風呂
よくないAI ツイッター
資格:普通免許三十段 ワイヤー使い(乙種) 第一種五行鑑定士
異能:有有有利有利有利(アドアドアドバンテージテージ)
リスクリターンの直感を強化する異能。
??:Unknown.....
──以下サブキャラ──
シズカ・バンクラプト
避田高の体育教師。クズ。
異能:ヨケルギウスの加護
アイコン24
〼子美麗(ますこ・みゅうる)
避田高の全聞部部長。
異能:濃縮還元(プレスリリース)
アイコン25~29
30 / 30
132 PS
チナミ区
D-2
D-2






















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 安物のスマートウォッチ | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 守りの石 | 防具 | 35 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な料理 | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 8 | 黄鉄鉱 | 素材 | 15 | [武器]麻痺10(LV20)[防具]反光10(LV25)[装飾]光纏10(LV20) | |||
| 9 | 不可思議な料理 | 料理 | 30 | 器用13 | 敏捷13 | 耐疫13 | |
| 10 | 硬質ワイヤー"FLAME Ⅲ" | 武器 | 40 | 衰弱10 | - | - | 【射程2】 |
| 11 | 平石 | 素材 | 15 | [武器]器用15(LV25)[防具]防御10(LV10)[装飾]治癒15(LV25) | |||
| 12 | 何か固い物体 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20) | |||
| 13 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 合成 | 35 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練1 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| 練1 | ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 |
| 練1 | アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 練1 | プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) |
| エアブレイド | 5 | 0 | 100 | 敵列:風撃 | |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| イーグルタロン (デアデビル) | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| フィジカルヴースター (フィジカルブースター) | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| スキューア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:地痛撃&次受ダメ増 | |
| アジャイルフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:AG増 | |
| フィックルティンバー | 5 | 0 | 80 | 敵:風痛撃&3D6が11以上なら風痛撃 | |
| カマイタチ | 5 | 0 | 100 | 敵:風撃+領域値[風]3以上なら、敵全:風撃&領域値[風]減 | |
| 練2 | タッチダウンライズ | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+HP減+連続増 |
| フラワリング | 5 | 0 | 50 | 敵列:魅了+領域値[地]3以上なら束縛 | |
| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| プチメテオカード | 5 | 0 | 40 | 敵:粗雑地撃 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| アゲインスト (アゲンスト) | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 幸星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:祝福 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 超絶合成 | 5 | 0 | 0 | 【常時】3D6が16以上なら合成後のアイテムの強さが増加するが、5以下なら減少する。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ヒール (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
ホーリーポーション (ホーリーポーション) |
0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 | |
|
ラーメン (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| 練1 |
《焼け落ちる記憶》 (ストライク) |
0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]チャージ | [ 1 ]アイシング |
| [ 1 ]カームフレア | [ 1 ]イレイザー | [ 2 ]ハードブレイク |
| [ 1 ]先制 | [ 1 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]五月雨 |
| [ 1 ]ヒールハーブ | [ 1 ]プチメテオカード |

PL / sironagasu_koen