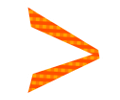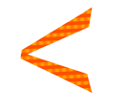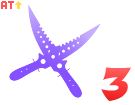<< 2:00~3:00




「今回は機械生物を使った実験を行う」
今日は戦場でのスポッターの仕事ではなく、候補生を軸とした交流会らしい。
そういった触れ込みにおずおずとラボラトリールームへと入室するや否や、体のメンテナンスを担当するドクターから言い渡されたのはそのような辞令だった。
ラボの中は緑色の液体に封じ込められた大きな試験管の中に色々な生物がいた。どれも候補生のような人材を作るため、人間以外の生物を利用した大々的な実験が行われていることを知ったのは数日前のこと。
交流会とは名ばかりの薬品のにおい漂う最中、ご覧と指し示された大きな試験管の前に立つ。
一見すると犬のようだった。
プラグ状の尾とバイザーのようなグラスアイが目元を覆い、母胎にうずくまるようにして四肢を折り曲げた狼のような何かだ。
何か、などとあいまいな表現を呈してしまうのは少女の語彙力が少ないからではなく、所々機械部品の装着面が見えていて、生体部品だけでも数種類の動物が混ざっていることが伺えるからだ。何でも形容できるがあえてをつけるなら、そういった言葉が相応しい。
体毛や尾の作りは狐と犬のようで、鋭い足は獅子ににていた。かろうじて昔見た動物図鑑の記憶を頼りになんとか動物らしい観点を見出していると、横からドクターが声をかけてくる。
「これは機械と生物のキメラだ。生体と疑似関節を使用した新兵器でな。検体名をトーヴとした」
「トーヴ」
旧世代の童話に出て来る名状し違い獣の名だったか。タヌキとトカゲと栓抜きをかけ合わせた、よくわからない生物。獣の複合体だ。
「君にはしばらくの間、彼と行動を共に生活して貰う。護衛や警察犬のようなものだと思って使いたまえ」
「あの……動物を飼ったことがありません」
「交流会と称したのはそのためだ。キメラとはいえ脳は獣がベースだ。よく動き懐きお前に従うようプログラムしてある。存分に使い倒したまえ。嗚呼一応大切な検体故、乱暴には扱わないように」
「……了解しました」
意図を掴みかねず続けて質問しようとしたが、言い切られて少女は押し黙り頷くことしか出来なかった。
「……おいで、トーヴ」
首輪を必要としないだけマシなのかもしれない。
自由気ままに動くこともしないトーヴと呼ばれた検体は、少女の声に応じてきしきしと歩み寄る。
暫くの間は実地任務も単発の仕事しかない為、仕事が終わって宿直先の居室に帰るとトーヴが出迎えるのが日常になっていた。暗い部屋の中、玄関の前でひっそりと建ち続けて待っていた姿を最初にみた時には驚いたが、もうすっかり慣れたものだ。
トーヴはバイオ燃料を必要とするのか、主食はトウモロコシだ。芯を丸ごと飲み込んで排熱する姿は狼というより蛇に近しい。
瞬間的に食事を終えた彼に続くように、少女も配給された完全栄養食を口にする。
プラスチックの食器の上に乗せられた、べたついたペースト状の良く分からない何かを温めたミルクで飲み干す。顎の力を衰えさせない為かエネルギーを効率よく摂取できる固形栄養食を指定された回数をよく噛んで食べる。
10歳にもなって離乳食かポストアポカリプスめいた食事しか体感できないこのご時世、仕方がないとはいえ少女もまた彼と同じ検体なのだ。調子を崩されたら困るし、毎日同じ食事を摂ることでコントロールできるこの手法は理にかなっている。
そう自分に言い聞かせることで、今の現状を無理やり納得させる。少女に出来るのは抵抗ではなく落ち処を見つけることだ。子供なりに納得して、嗚呼それもそうだと諦めさせるための諦観に近い。
生体パーツが使われているトーヴの毛並みを優しくなでながら、ふと呟く。
「……お前は自由で良いな。私には自由が無い」
彼に意思があるかは分からない。もしかしたら心の奥底に自我というものがあるのかもしれない。
されどそれは憶測の範疇だ。飼われ、作られた生命体はその意味を持って作られたのだ。
最初から人間として生まれ、このように実験体と同レベルの扱いを受けることは人間にとっての不本意だ。同列に扱われることを今更拒絶などしない。なるべくしてなった結果なのである。
「いつかお前のように自由に考えられたら良いな……」
ぎゅっと腰を抱き据えて抱え込むようにソファーへ寝転ぶ。物怖じも怯えも暴れもしない機械生命はこういう時に便利だ。
辛くなった時はこの愛玩動物が吐き出したものを受け止めてくれる。少しくらいの弱音ならば吐いたところで問題はあるまい。
次第に少女の瞼は重くなる。
嗚呼、明日は任務だったなと逡巡した後、女の意識は遥か彼方へ遠ざかって行った。
――あと2130日だ。



ENo.195 天使様 とのやりとり

ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり













響鳴LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
命術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
キノ(1052) とカードを交換しました!
ブービートラップ (インヴァージョン)

イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールハーブ を研究しました!(深度1⇒2)
ウォーターフォール を習得!
アクアシェル を習得!
ライフリンク を習得!
アクアヒール を習得!
五月雨 を習得!
氷水避け を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シルバーキャット(748) は 平石 を入手!
玲子(813) は 藍鉄鉱 を入手!
結(1510) は 孔雀石 を入手!
仁(1511) は 藍鉄鉱 を入手!
シルバーキャット(748) は 腐肉 を入手!
シルバーキャット(748) は 大軽石 を入手!
シルバーキャット(748) は 牙 を入手!
仁(1511) は 大軽石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
シルバーキャット(748) のもとに ワイト が微笑を浮かべて近づいてきます。
シルバーキャット(748) のもとに 歩行小岩 が恥ずかしそうに近づいてきます。
シルバーキャット(748) のもとに 大山猫 が空を見上げなから近づいてきます。



チナミ区 O-6(沼地)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――













硝煙の匂いをレモングラスの香水で紛らわす。
不条理に曝されても女は兵士として生きている。
無垢な顔立ちのまま、少女兵は此度も武器を取る。
その名は銀色の猫。数多の機械を操る科学の結晶。
少女の己を殺し、猫のように気儘に戦場を駆ける。
「敵対者を補足。猫の目は貴様を逃さない。
一匹たりとも逃がさない。徹底的に潰す。
侵略者よ、せめて敗走する権利は与えてやろう。
猫のテリトリーに立ち入った事、後悔して死ね」
【シルバーキャット】
女性/20歳(経歴詐称により27歳になっている)/177cm
【容姿】
10代後半程度の童顔。
銀髪のセミロングの髪。赤色の瞳。肌は透き通るような白さ。
白いVネックシャツと、ネイビー色の丈の短いキュロット。
カーキ色のミリタリージャケット。
ドッグタグを首から下げている。
【設定】
紛争地域のアンダーグラウンド出身。戦災孤児。
傭兵派遣会社『ブレーン・トルーパー社』に所属する。
主に市街・都市部への潜入・偵察を担当している。
今回はイバラシティに迫りくる危機(アンジニティ)を調査する為にブランブル女学院の保健・体育教師として潜り込んで来た。
潜入時の年齢は15歳。この5年間、ワールドスワップが始まるまでイバラシティを己の縄張りとして張り込み過ごしてきた。
思考速度と視神経を著しく引き上げられており、機械を自在に支配できる改造人間。
寡黙で冷徹な性格。希薄な感情の持ち主で大人しい。
ハザマではより冷酷な一面が浮き彫りになる。イバラシティで過ごした5年間の記憶を必要がある場合のみ落とし込み、深く関わりすぎた人物に対しても情を抱かない範疇で記憶操作している。
この影響でこちら側の精神年齢は10代で止まっている。
武器は銃とドローン、ロボット兵器。
特に市街戦に特化した戦闘スタイルで閉所・暗所は非常に有利。
遠近ともに殺人術に長けており、対人や包囲戦には滅法強い。
【所有ドローン】
ライオン:敵地工作用無人偵察機。クワッドコプター。
ジャガー:対電子戦用無人偵察機。戦闘機型
ピューマ:対市街調査用無人キャタピラ型兵器。戦車型
チーター:対人型用無人多脚型兵器。ベレッタM84を配備。
【異能】
・マルチクライアント
複数の機械を並行して操作できる能力。
自分は椅子に座りながらパソコンで検索しつつ、スマホでソシャゲを遊び、ドローンでコーヒーを持ってこさせるなどの使い方が出来る。
当人は戦場においてあらゆる盤面に配置した上記のドローンを大量に展開して戦闘・戦闘補助・輸送・偵察・監視を同時に行うことに利用する。
この能力が発動している間は、自分と操られている機械の眼(レンズ)が赤色に発光する。
【サブキャラクター】
天津風ヒトミのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=yfpP56Knt690e3ae4e8b6c5809bdc71325dbdb6a6d5
北野ソムクのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=P0IQAju3UlJ536e97d523c04fd97df74518e05b99cf
----
キャラクターイラスト:osisio様
アイコンイラスト:どぷり様





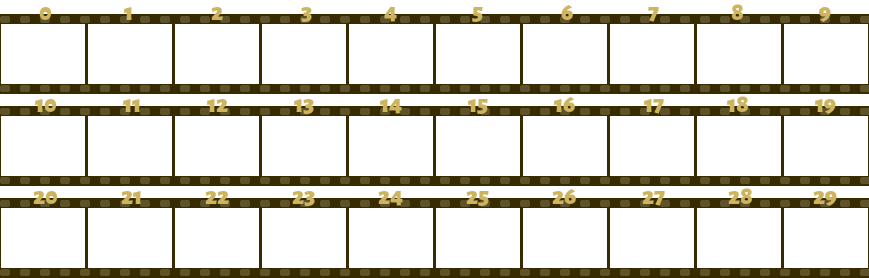




































No.1 歩行石壁 (種族:歩行石壁)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



「今回は機械生物を使った実験を行う」
今日は戦場でのスポッターの仕事ではなく、候補生を軸とした交流会らしい。
そういった触れ込みにおずおずとラボラトリールームへと入室するや否や、体のメンテナンスを担当するドクターから言い渡されたのはそのような辞令だった。
ラボの中は緑色の液体に封じ込められた大きな試験管の中に色々な生物がいた。どれも候補生のような人材を作るため、人間以外の生物を利用した大々的な実験が行われていることを知ったのは数日前のこと。
交流会とは名ばかりの薬品のにおい漂う最中、ご覧と指し示された大きな試験管の前に立つ。
一見すると犬のようだった。
プラグ状の尾とバイザーのようなグラスアイが目元を覆い、母胎にうずくまるようにして四肢を折り曲げた狼のような何かだ。
何か、などとあいまいな表現を呈してしまうのは少女の語彙力が少ないからではなく、所々機械部品の装着面が見えていて、生体部品だけでも数種類の動物が混ざっていることが伺えるからだ。何でも形容できるがあえてをつけるなら、そういった言葉が相応しい。
体毛や尾の作りは狐と犬のようで、鋭い足は獅子ににていた。かろうじて昔見た動物図鑑の記憶を頼りになんとか動物らしい観点を見出していると、横からドクターが声をかけてくる。
「これは機械と生物のキメラだ。生体と疑似関節を使用した新兵器でな。検体名をトーヴとした」
「トーヴ」
旧世代の童話に出て来る名状し違い獣の名だったか。タヌキとトカゲと栓抜きをかけ合わせた、よくわからない生物。獣の複合体だ。
「君にはしばらくの間、彼と行動を共に生活して貰う。護衛や警察犬のようなものだと思って使いたまえ」
「あの……動物を飼ったことがありません」
「交流会と称したのはそのためだ。キメラとはいえ脳は獣がベースだ。よく動き懐きお前に従うようプログラムしてある。存分に使い倒したまえ。嗚呼一応大切な検体故、乱暴には扱わないように」
「……了解しました」
意図を掴みかねず続けて質問しようとしたが、言い切られて少女は押し黙り頷くことしか出来なかった。
「……おいで、トーヴ」
首輪を必要としないだけマシなのかもしれない。
自由気ままに動くこともしないトーヴと呼ばれた検体は、少女の声に応じてきしきしと歩み寄る。
暫くの間は実地任務も単発の仕事しかない為、仕事が終わって宿直先の居室に帰るとトーヴが出迎えるのが日常になっていた。暗い部屋の中、玄関の前でひっそりと建ち続けて待っていた姿を最初にみた時には驚いたが、もうすっかり慣れたものだ。
トーヴはバイオ燃料を必要とするのか、主食はトウモロコシだ。芯を丸ごと飲み込んで排熱する姿は狼というより蛇に近しい。
瞬間的に食事を終えた彼に続くように、少女も配給された完全栄養食を口にする。
プラスチックの食器の上に乗せられた、べたついたペースト状の良く分からない何かを温めたミルクで飲み干す。顎の力を衰えさせない為かエネルギーを効率よく摂取できる固形栄養食を指定された回数をよく噛んで食べる。
10歳にもなって離乳食かポストアポカリプスめいた食事しか体感できないこのご時世、仕方がないとはいえ少女もまた彼と同じ検体なのだ。調子を崩されたら困るし、毎日同じ食事を摂ることでコントロールできるこの手法は理にかなっている。
そう自分に言い聞かせることで、今の現状を無理やり納得させる。少女に出来るのは抵抗ではなく落ち処を見つけることだ。子供なりに納得して、嗚呼それもそうだと諦めさせるための諦観に近い。
生体パーツが使われているトーヴの毛並みを優しくなでながら、ふと呟く。
「……お前は自由で良いな。私には自由が無い」
彼に意思があるかは分からない。もしかしたら心の奥底に自我というものがあるのかもしれない。
されどそれは憶測の範疇だ。飼われ、作られた生命体はその意味を持って作られたのだ。
最初から人間として生まれ、このように実験体と同レベルの扱いを受けることは人間にとっての不本意だ。同列に扱われることを今更拒絶などしない。なるべくしてなった結果なのである。
「いつかお前のように自由に考えられたら良いな……」
ぎゅっと腰を抱き据えて抱え込むようにソファーへ寝転ぶ。物怖じも怯えも暴れもしない機械生命はこういう時に便利だ。
辛くなった時はこの愛玩動物が吐き出したものを受け止めてくれる。少しくらいの弱音ならば吐いたところで問題はあるまい。
次第に少女の瞼は重くなる。
嗚呼、明日は任務だったなと逡巡した後、女の意識は遥か彼方へ遠ざかって行った。
――あと2130日だ。



ENo.195 天使様 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり



 |
傭兵 「あまりはしゃぎすぎるなよ、沢野さん」 |
 |
玲子 「この身体はね、レーコの本当の異能なんだって。みんなにはナイショにしてね!」 |
 |
玲子 「あっ、でもハザマでの事は覚えてないんだっけ。なら、大丈夫かなあ」 |





対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 2 増加!
影響力が 2 増加!



響鳴LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
命術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
キノ(1052) とカードを交換しました!
ブービートラップ (インヴァージョン)

イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールハーブ を研究しました!(深度1⇒2)
ウォーターフォール を習得!
アクアシェル を習得!
ライフリンク を習得!
アクアヒール を習得!
五月雨 を習得!
氷水避け を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シルバーキャット(748) は 平石 を入手!
玲子(813) は 藍鉄鉱 を入手!
結(1510) は 孔雀石 を入手!
仁(1511) は 藍鉄鉱 を入手!
シルバーキャット(748) は 腐肉 を入手!
シルバーキャット(748) は 大軽石 を入手!
シルバーキャット(748) は 牙 を入手!
仁(1511) は 大軽石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
シルバーキャット(748) のもとに ワイト が微笑を浮かべて近づいてきます。
シルバーキャット(748) のもとに 歩行小岩 が恥ずかしそうに近づいてきます。
シルバーキャット(748) のもとに 大山猫 が空を見上げなから近づいてきます。



チナミ区 O-6(沼地)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 O-7(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 O-8(山岳)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 O-9(山岳)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 P-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







《梟の住処》
|
 |
砲火後加害授業中
|


ENo.748
シルバーキャット



硝煙の匂いをレモングラスの香水で紛らわす。
不条理に曝されても女は兵士として生きている。
無垢な顔立ちのまま、少女兵は此度も武器を取る。
その名は銀色の猫。数多の機械を操る科学の結晶。
少女の己を殺し、猫のように気儘に戦場を駆ける。
「敵対者を補足。猫の目は貴様を逃さない。
一匹たりとも逃がさない。徹底的に潰す。
侵略者よ、せめて敗走する権利は与えてやろう。
猫のテリトリーに立ち入った事、後悔して死ね」
【シルバーキャット】
女性/20歳(経歴詐称により27歳になっている)/177cm
【容姿】
10代後半程度の童顔。
銀髪のセミロングの髪。赤色の瞳。肌は透き通るような白さ。
白いVネックシャツと、ネイビー色の丈の短いキュロット。
カーキ色のミリタリージャケット。
ドッグタグを首から下げている。
【設定】
紛争地域のアンダーグラウンド出身。戦災孤児。
傭兵派遣会社『ブレーン・トルーパー社』に所属する。
主に市街・都市部への潜入・偵察を担当している。
今回はイバラシティに迫りくる危機(アンジニティ)を調査する為にブランブル女学院の保健・体育教師として潜り込んで来た。
潜入時の年齢は15歳。この5年間、ワールドスワップが始まるまでイバラシティを己の縄張りとして張り込み過ごしてきた。
思考速度と視神経を著しく引き上げられており、機械を自在に支配できる改造人間。
寡黙で冷徹な性格。希薄な感情の持ち主で大人しい。
ハザマではより冷酷な一面が浮き彫りになる。イバラシティで過ごした5年間の記憶を必要がある場合のみ落とし込み、深く関わりすぎた人物に対しても情を抱かない範疇で記憶操作している。
この影響でこちら側の精神年齢は10代で止まっている。
武器は銃とドローン、ロボット兵器。
特に市街戦に特化した戦闘スタイルで閉所・暗所は非常に有利。
遠近ともに殺人術に長けており、対人や包囲戦には滅法強い。
【所有ドローン】
ライオン:敵地工作用無人偵察機。クワッドコプター。
ジャガー:対電子戦用無人偵察機。戦闘機型
ピューマ:対市街調査用無人キャタピラ型兵器。戦車型
チーター:対人型用無人多脚型兵器。ベレッタM84を配備。
【異能】
・マルチクライアント
複数の機械を並行して操作できる能力。
自分は椅子に座りながらパソコンで検索しつつ、スマホでソシャゲを遊び、ドローンでコーヒーを持ってこさせるなどの使い方が出来る。
当人は戦場においてあらゆる盤面に配置した上記のドローンを大量に展開して戦闘・戦闘補助・輸送・偵察・監視を同時に行うことに利用する。
この能力が発動している間は、自分と操られている機械の眼(レンズ)が赤色に発光する。
【サブキャラクター】
天津風ヒトミのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=yfpP56Knt690e3ae4e8b6c5809bdc71325dbdb6a6d5
北野ソムクのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=P0IQAju3UlJ536e97d523c04fd97df74518e05b99cf
----
キャラクターイラスト:osisio様
アイコンイラスト:どぷり様
15 / 30
183 PS
チナミ区
P-9
P-9







































No.1 歩行石壁 (種族:歩行石壁)
 |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| 火炎避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:火耐性・炎上耐性増+他者から炎上を移される確率減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |
| 瑠璃樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP・精神変調防御・領域値[地][闇]増+守護+連続減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | サタデーナイトスペシャル | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 腐り落ちたドッグタグ | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | ハンバーグ…? | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 9 | ファイターズドローン | 武器 | 40 | 束縛10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 11 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 12 | 平石 | 素材 | 15 | [武器]器用15(LV25)[防具]防御10(LV10)[装飾]治癒15(LV25) | |||
| 13 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
| 14 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 15 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 武器 | 30 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| ライフリンク | 5 | 0 | 50 | 自従傷:HP増+HP譲渡 | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |
| シュリーク | 5 | 0 | 50 | 敵貫:朦朧+自:混乱 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| 決3 | ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 |
| コントラクト | 5 | 0 | 80 | 自従:契LV増 | |
| 決3 | サモン:サーヴァント | 6 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 氷水避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水耐性・凍結耐性増+凍結によるHP・SP減少量減 | |
| 祈誓 | 5 | 3 | 0 | 【通常攻撃後】自:祝福消費でDF・LK増(2T) | |
| 狂歌乱舞 | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:混乱+自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増(2T) |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
麺ジニティ (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
五徳猫の加護 (デアデビル) |
0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
|
九尾の札#3 (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
|
ブービートラップ (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ヒールポーション | [ 2 ]イレイザー | [ 2 ]ファイアボルト |
| [ 2 ]ファーマシー | [ 2 ]アクアシェル | [ 2 ]ヒールハーブ |

PL / えーや