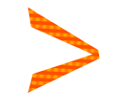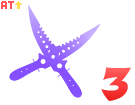<< 1:00~2:00




「ドクターは嘘吐きだ」
少女は憤慨していた。携帯していたハンドガンと工作用の通信機を握りしめて悪態をついていた。
最後の手術を終えてから、初忍務として市街戦の真っ只中に放り込まれた。町は少女が生まれ育った故郷によく似ている状態で、硝煙と砂埃が漂い、旧時代の石畳の建物が散見される。
『中央』の拠点を離れた末端中の末端の小競り合いをしている武装した少数派民族による反乱軍と現政府軍との戦いを行っているというのが事前のブリーフィングで判明している。
反乱軍が使っている中古のロボット兵器が織り成しつつ現地にいる兵士がこのただ中にいた。
少女が民営の傭兵会社より派遣された正規軍兵士としてもぐりこんだのは今から18時間前の事だ。
目的は現地の地形調査と兵士観測。可能な限りの武器情報を入手して欲しいというのが初仕事と相成った。
戦地で華々しい活躍をすれば人らしい生活が出来るやもしれんとドクターは言っていたが、実際は工作にスニーキングがメインで銃撃がご法度になっている戦場に回された。
崩落した建物のがれきの間をすり抜け、薄闇の奥底から銃口を煌かせながら厳重に警戒する。こうした狭い場所で伏せたまま状況把握を行うのは少年兵の利点である。初任務ということもあり程度の軽いものから始めた方がコスト運用としても気軽で良いというのは上の方針らしい。
少女はただの少年兵ではなくサイボーグ兵士の候補生である。その体には技術の粋を集めて作られた細胞が詰め込まれており、そう簡単に使い棄てられては困るのである。
死んだらそれまで、されど丁重に。現場の人間はきっと頭を痛めたに違いない。
だからこそこうして死ににくいポイントマンとしての役割と状況分析の仕事に当てたのは悪い判断ではなかった。よく積み荷を積んだ旧式のカーゴの通る道路の間をすり抜け、武器などの情報を写真に収める。
コンテナや兵士、銃火器に種類。敵対勢力の動向、車載物の確認、人員の把握。時間ごとの人数の変動。
あらゆる状況を把握し続け、つい寝落ちしそうになる体を瓦礫に押し付けて無理やり頭を起こした。
瞬間、耳に押し込まれた通信機から通信が届く。こちら側を観測している少年兵の総括局のオペレーターだ。
「おい、激突音にバイタルサインの乱れがあった。どうかしたか」
「あ、あの……寝そうになって」
「呑気だなオイ。お前が拠点にしている瓦礫も崩落しかけているんだ。榴弾が当たれば圧し潰される危険性も考慮しろ。建物の中も安全じゃないぞ」
「……承知しました」
「既にスポッターとして派遣した兵士が何人かが寝ているところを狙撃で死傷している。お前も気を抜くな」
とはいえ動くにも限度がある。下手な銃火器を使用すれば銃声で位置が特定され、薬莢を残したら種別が割れ、弾痕を残したら警戒される。
よりにもよって無人機蔓延る都市部相手だ。ここらは人の眼が比較的少ない代わりに監視カメラの間をすり抜け、無人機によるサーチライトを掻い潜って進むしかない。熱感知に生体認証システム、様々な科学技術が敵対してくるのだ。
少女にとっての戦場は無人兵器との戦いだ。いかに情報を引き出し、有能な彼ら兵器に対抗するかがカギとなる。
旧世代的な銃を扱わせるだけの歩兵とは違う次元の低コスト且つ情報戦を有利に進める駒。少女の行った実験もその一つ。この実地訓練もまた同様。
今回のプロジェクトが成功すればよりやりやすいビジネスになる。
……反吐が出る。
「……ちくしょう」
砂埃を被って、日がな一日寝そべるように双眼鏡を覗き込んで、敵地への潜入と調査を繰り返す。持たされた不味いレーションを食い漁って排便して寝て、砲撃音と敵の怒号にビクついて起き上がるのにももう慣れた。
数日経って帰還命令が出た。情報を割り出し終えたとのことらしい。
こんなものかという感慨と、呆気なさに胸を撫でおろす。やっと終わった。
「こちら…………」
己の名を呼ぼうとして――嗚呼、しかしこちらの名前は相手に伝えていないのだ。どこの誰が通信をしてきたのかと怒られたらどうしよう。そもそも、名前を使うなと怒られないだろうか。
様々な思惑が胸中に渦巻いて女は言葉を止める。直後にあちら側から無線が通じた。
「嗚呼、お前か。指定した合流ポイントに向かえ。そこまでの比較的な安全なルートはもう割り出している。すぐに帰投しろ」
「りょ、了解……」
「数日間よく耐えた。お前の情報は今後の戦闘に役立つことだろう」
「は、はい。ありがとうございます」
通信を切って、塒にしていた瓦礫の隙間を抜け出す。携帯したハンドガンを構えながらクリアリングを欠かさず、事前に指定されていた合流地点にたどり着いた。
戦場用のサバイバルベストを着た浅黒い男と粉塵を防ぐマスクを被った兵士が複数人いる。
「『中央』所属の兵士です。帰投しました」
瞬間的に銃を構えられそうになったのを見て怯えつつも、銃を即座に捨てて所属部隊を記したドックタグと肩のワッペンを見せながら手を上げる。
実験施設に連れてこられる前の出来事によく似て、兵士は無情にも目を見せて貰えず一方的にしげしげを見遣られている。
動悸がする、目眩がしそうになる。どこか安堵しかけている自分がいる。
ややあって、少女は猜疑の目から逃れることが出来た。
「ご苦労だった。エリアTX10/99が調査区画だったな。無人機や監視カメラの多い区画だ。人はいないが待ちの多い場所だな。退屈だったんじゃないか?」
「とんでもありません。私、いつ死んでもおかしくなくて……」
「寝落ちするような輩だからな」
そうして笑いあげる声で気付く。
「あの……オペレーターさん」
「なんだ」
「い、いえ……今回の総括局の、それもオペレーターがなぜこんな現地に……」
「ロボット兵器の調整と下見だよ。話ならいくらでも出来るからそれよりはやく乗れ」
カーゴの中へと背を叩かれながら少女が車内へ入り込む。「黒いマスクの男達に脇を固められながら発進する。
揺れ動く車内は決して快適とは言えないが、ようやく安心できる場所に戻ってこれたことを実感して、少女はうとうとと寝落ちしそうになって舟を漕いだ。
「……また寝落ちか?」
「は、……すみません何度も……」
「いや良い。年は10くらいか。女だてら数日間もあそこにいたのに根性ある」
「……恐縮です」
「根性っていうより、慣れてるのかもな。こういう世界だ。まともな感性してるかも怪しい」
隣にいたマスクの男が軽く口を叩いているのを諫めるよう、目の前のオペレーターは訝しむ。
「その感性も戦場では必要だ。究極的には統制できた方が楽だが肉体はともかく精神の規律は無くしたらならない」
――どうせこれも戦場の駒としか見ていないはずなのに、何を言っているのだろう。
微睡んできた意識の中で、少女は口にせず頭の中でごちた。段々と眼を垂らして頭を上げて、背に持たれてばかみたいな寝顔を晒すまでには時間はそう掛からない。
本格的に寝ようとする少女に、両脇の兵士が呆れたように笑う中、確かな声が聞こえてきた。
この車内で誰がそう言ったのかは分からない。
「まるで猫みたいだ」
――キャット。
その言葉がひどく頭にこびりついていく。刷り込みをされた雛鳥のように、爆撃とともに名を四散した己には丁度良い響き。彼らは冗句のたとえで言ったに違いない。何でもない言葉の筈だ。
この数日を気儘に住み、食って、忍び込んで隙間を潜った。それがひどく猫と同じように思えた。己は度重なる改造を受けた改造人間で、人たるシンボルはあれど真人間ではない。
嗚呼ならば、人ならざる猫と言う在り方も悪くないのかもしれない。
そうして少女は夢の中へと飛び込んでいった。
――あと2143日だ。
「名はなんと言ったか」
イバラシティに潜入した5年の間に多くの出来事があった。
特筆すべきはよりにもよって学院の教師と言う立場に潜り込んだことだ。15歳のシルバーキャットの選択なのか上の命令かはともかく、下手をすればすぐにバレるような年齢詐称と相まって、とりつく島もない中よく隠し通せたといっそ感動的だ。
シルバーキャットにそこまで名演の才があるのなら女優にでも転職したらどうだとからかわれそうだ。
最も面倒なのは名を思い出すことだ。この五年で関わった数百はくだらない生徒や卒業生の顔と名前を必死に思い出しつつダウンロードした記憶と照合させて話を合わせなければならない。他人事のような言動と相まってそれはひどくいびつな言葉になるが、すべては些事だ。
パーティとしてチームを組んだ中にも見知った顔がいるという記憶はあるが、こちら側のシルバーキャットにはなじみが薄く、やはり他人行儀になってしまう。
シルバーキャットという役割を演じるには五年と数時間では時間の重みも掛け方も異なる。
いかんともしがたい、しかしする必要性もない。
ワールドスワップが発生してからこの地には猶予がない。早々に調査の足を進めねばならない。
親しき者が敵であったり、愛する者が敵であったり、一目見ただけの存在が味方だったりとこの街はせわしない。
横断歩道ですれ違っただけのような他人も敵で、また味方だ。
調べねばならない、解明しなければならない。侵略行為を抑止しつつ彼らを狩り、調べ尽くして献上しなければ。
通信回線は相変わらず滞っているが、データの送信は出来ている。獲得した情報を送るだけ送っておけば、あとは誰かが引き継いでくれるに違いない。
ここで死しても代わりはいる。シルバーキャットは改造を受けてパッケージ化された兵士にすぎない。
だからせめて、猫の名を今暫し謀つらせてくれ。



ENo.17 サクマ とのやりとり

ENo.34 ぺちか とのやりとり

ENo.150 泥蘇光悪渡 とのやりとり

ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり

以下の相手に送信しました




玲子(813) から 毛 を手渡しされました。









歩行石壁 をエイドとして招き入れました!
具現LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.9 毛 から射程3の武器『ファイターズドローン』を作製しました!
⇒ ファイターズドローン/武器:強さ40/[効果1]束縛10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
結(1510) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ハンバーグ…?』をつくってもらいました!
⇒ ハンバーグ…?/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
リオ(1334) とカードを交換しました!
九尾の札#3 (カレイドスコープ)


イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールハーブ を研究しました!(深度0⇒1)
ビブラート を習得!
コントラクト を習得!
狂歌乱舞 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シルバーキャット(748) は 吸い殻 を入手!
玲子(813) は ネジ を入手!
結(1510) は ネジ を入手!
仁(1511) は パンの耳 を入手!
シルバーキャット(748) は 吸い殻 を入手!
仁(1511) は 毛 を入手!
玲子(813) は 牙 を入手!
結(1510) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
シルバーキャット(748) のもとに 鬼火 がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
シルバーキャット(748) のもとに 大黒猫 が興味津々な様子で近づいてきます。
シルバーキャット(748) のもとに 大山猫 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。
シルバーキャット(748) のもとに ヤンキー が恥ずかしそうに近づいてきます。



チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- 玲子(813) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――












硝煙の匂いをレモングラスの香水で紛らわす。
不条理に曝されても女は兵士として生きている。
無垢な顔立ちのまま、少女兵は此度も武器を取る。
その名は銀色の猫。数多の機械を操る科学の結晶。
少女の己を殺し、猫のように気儘に戦場を駆ける。
「敵対者を補足。猫の目は貴様を逃さない。
一匹たりとも逃がさない。徹底的に潰す。
侵略者よ、せめて敗走する権利は与えてやろう。
猫のテリトリーに立ち入った事、後悔して死ね」
【シルバーキャット】
女性/20歳(経歴詐称により27歳になっている)/177cm
【容姿】
10代後半程度の童顔。
銀髪のセミロングの髪。赤色の瞳。肌は透き通るような白さ。
白いVネックシャツと、ネイビー色の丈の短いキュロット。
カーキ色のミリタリージャケット。
ドッグタグを首から下げている。
【設定】
紛争地域のアンダーグラウンド出身。戦災孤児。
傭兵派遣会社『ブレーン・トルーパー社』に所属する。
主に市街・都市部への潜入・偵察を担当している。
今回はイバラシティに迫りくる危機(アンジニティ)を調査する為にブランブル女学院の保健・体育教師として潜り込んで来た。
潜入時の年齢は15歳。この5年間、ワールドスワップが始まるまでイバラシティを己の縄張りとして張り込み過ごしてきた。
思考速度と視神経を著しく引き上げられており、機械を自在に支配できる改造人間。
寡黙で冷徹な性格。希薄な感情の持ち主で大人しい。
ハザマではより冷酷な一面が浮き彫りになる。イバラシティで過ごした5年間の記憶を必要がある場合のみ落とし込み、深く関わりすぎた人物に対しても情を抱かない範疇で記憶操作している。
この影響でこちら側の精神年齢は10代で止まっている。
武器は銃とドローン、ロボット兵器。
特に市街戦に特化した戦闘スタイルで閉所・暗所は非常に有利。
遠近ともに殺人術に長けており、対人や包囲戦には滅法強い。
【所有ドローン】
ライオン:敵地工作用無人偵察機。クワッドコプター。
ジャガー:対電子戦用無人偵察機。戦闘機型
ピューマ:対市街調査用無人キャタピラ型兵器。戦車型
チーター:対人型用無人多脚型兵器。ベレッタM84を配備。
【異能】
・マルチクライアント
複数の機械を並行して操作できる能力。
自分は椅子に座りながらパソコンで検索しつつ、スマホでソシャゲを遊び、ドローンでコーヒーを持ってこさせるなどの使い方が出来る。
当人は戦場においてあらゆる盤面に配置した上記のドローンを大量に展開して戦闘・戦闘補助・輸送・偵察・監視を同時に行うことに利用する。
この能力が発動している間は、自分と操られている機械の眼(レンズ)が赤色に発光する。
【サブキャラクター】
天津風ヒトミのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=yfpP56Knt690e3ae4e8b6c5809bdc71325dbdb6a6d5
北野ソムクのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=P0IQAju3UlJ536e97d523c04fd97df74518e05b99cf
----
キャラクターイラスト:osisio様
アイコンイラスト:どぷり様










































No.1 歩行石壁 (種族:歩行石壁)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「ドクターは嘘吐きだ」
少女は憤慨していた。携帯していたハンドガンと工作用の通信機を握りしめて悪態をついていた。
最後の手術を終えてから、初忍務として市街戦の真っ只中に放り込まれた。町は少女が生まれ育った故郷によく似ている状態で、硝煙と砂埃が漂い、旧時代の石畳の建物が散見される。
『中央』の拠点を離れた末端中の末端の小競り合いをしている武装した少数派民族による反乱軍と現政府軍との戦いを行っているというのが事前のブリーフィングで判明している。
反乱軍が使っている中古のロボット兵器が織り成しつつ現地にいる兵士がこのただ中にいた。
少女が民営の傭兵会社より派遣された正規軍兵士としてもぐりこんだのは今から18時間前の事だ。
目的は現地の地形調査と兵士観測。可能な限りの武器情報を入手して欲しいというのが初仕事と相成った。
戦地で華々しい活躍をすれば人らしい生活が出来るやもしれんとドクターは言っていたが、実際は工作にスニーキングがメインで銃撃がご法度になっている戦場に回された。
崩落した建物のがれきの間をすり抜け、薄闇の奥底から銃口を煌かせながら厳重に警戒する。こうした狭い場所で伏せたまま状況把握を行うのは少年兵の利点である。初任務ということもあり程度の軽いものから始めた方がコスト運用としても気軽で良いというのは上の方針らしい。
少女はただの少年兵ではなくサイボーグ兵士の候補生である。その体には技術の粋を集めて作られた細胞が詰め込まれており、そう簡単に使い棄てられては困るのである。
死んだらそれまで、されど丁重に。現場の人間はきっと頭を痛めたに違いない。
だからこそこうして死ににくいポイントマンとしての役割と状況分析の仕事に当てたのは悪い判断ではなかった。よく積み荷を積んだ旧式のカーゴの通る道路の間をすり抜け、武器などの情報を写真に収める。
コンテナや兵士、銃火器に種類。敵対勢力の動向、車載物の確認、人員の把握。時間ごとの人数の変動。
あらゆる状況を把握し続け、つい寝落ちしそうになる体を瓦礫に押し付けて無理やり頭を起こした。
瞬間、耳に押し込まれた通信機から通信が届く。こちら側を観測している少年兵の総括局のオペレーターだ。
「おい、激突音にバイタルサインの乱れがあった。どうかしたか」
「あ、あの……寝そうになって」
「呑気だなオイ。お前が拠点にしている瓦礫も崩落しかけているんだ。榴弾が当たれば圧し潰される危険性も考慮しろ。建物の中も安全じゃないぞ」
「……承知しました」
「既にスポッターとして派遣した兵士が何人かが寝ているところを狙撃で死傷している。お前も気を抜くな」
とはいえ動くにも限度がある。下手な銃火器を使用すれば銃声で位置が特定され、薬莢を残したら種別が割れ、弾痕を残したら警戒される。
よりにもよって無人機蔓延る都市部相手だ。ここらは人の眼が比較的少ない代わりに監視カメラの間をすり抜け、無人機によるサーチライトを掻い潜って進むしかない。熱感知に生体認証システム、様々な科学技術が敵対してくるのだ。
少女にとっての戦場は無人兵器との戦いだ。いかに情報を引き出し、有能な彼ら兵器に対抗するかがカギとなる。
旧世代的な銃を扱わせるだけの歩兵とは違う次元の低コスト且つ情報戦を有利に進める駒。少女の行った実験もその一つ。この実地訓練もまた同様。
今回のプロジェクトが成功すればよりやりやすいビジネスになる。
……反吐が出る。
「……ちくしょう」
砂埃を被って、日がな一日寝そべるように双眼鏡を覗き込んで、敵地への潜入と調査を繰り返す。持たされた不味いレーションを食い漁って排便して寝て、砲撃音と敵の怒号にビクついて起き上がるのにももう慣れた。
数日経って帰還命令が出た。情報を割り出し終えたとのことらしい。
こんなものかという感慨と、呆気なさに胸を撫でおろす。やっと終わった。
「こちら…………」
己の名を呼ぼうとして――嗚呼、しかしこちらの名前は相手に伝えていないのだ。どこの誰が通信をしてきたのかと怒られたらどうしよう。そもそも、名前を使うなと怒られないだろうか。
様々な思惑が胸中に渦巻いて女は言葉を止める。直後にあちら側から無線が通じた。
「嗚呼、お前か。指定した合流ポイントに向かえ。そこまでの比較的な安全なルートはもう割り出している。すぐに帰投しろ」
「りょ、了解……」
「数日間よく耐えた。お前の情報は今後の戦闘に役立つことだろう」
「は、はい。ありがとうございます」
通信を切って、塒にしていた瓦礫の隙間を抜け出す。携帯したハンドガンを構えながらクリアリングを欠かさず、事前に指定されていた合流地点にたどり着いた。
戦場用のサバイバルベストを着た浅黒い男と粉塵を防ぐマスクを被った兵士が複数人いる。
「『中央』所属の兵士です。帰投しました」
瞬間的に銃を構えられそうになったのを見て怯えつつも、銃を即座に捨てて所属部隊を記したドックタグと肩のワッペンを見せながら手を上げる。
実験施設に連れてこられる前の出来事によく似て、兵士は無情にも目を見せて貰えず一方的にしげしげを見遣られている。
動悸がする、目眩がしそうになる。どこか安堵しかけている自分がいる。
ややあって、少女は猜疑の目から逃れることが出来た。
「ご苦労だった。エリアTX10/99が調査区画だったな。無人機や監視カメラの多い区画だ。人はいないが待ちの多い場所だな。退屈だったんじゃないか?」
「とんでもありません。私、いつ死んでもおかしくなくて……」
「寝落ちするような輩だからな」
そうして笑いあげる声で気付く。
「あの……オペレーターさん」
「なんだ」
「い、いえ……今回の総括局の、それもオペレーターがなぜこんな現地に……」
「ロボット兵器の調整と下見だよ。話ならいくらでも出来るからそれよりはやく乗れ」
カーゴの中へと背を叩かれながら少女が車内へ入り込む。「黒いマスクの男達に脇を固められながら発進する。
揺れ動く車内は決して快適とは言えないが、ようやく安心できる場所に戻ってこれたことを実感して、少女はうとうとと寝落ちしそうになって舟を漕いだ。
「……また寝落ちか?」
「は、……すみません何度も……」
「いや良い。年は10くらいか。女だてら数日間もあそこにいたのに根性ある」
「……恐縮です」
「根性っていうより、慣れてるのかもな。こういう世界だ。まともな感性してるかも怪しい」
隣にいたマスクの男が軽く口を叩いているのを諫めるよう、目の前のオペレーターは訝しむ。
「その感性も戦場では必要だ。究極的には統制できた方が楽だが肉体はともかく精神の規律は無くしたらならない」
――どうせこれも戦場の駒としか見ていないはずなのに、何を言っているのだろう。
微睡んできた意識の中で、少女は口にせず頭の中でごちた。段々と眼を垂らして頭を上げて、背に持たれてばかみたいな寝顔を晒すまでには時間はそう掛からない。
本格的に寝ようとする少女に、両脇の兵士が呆れたように笑う中、確かな声が聞こえてきた。
この車内で誰がそう言ったのかは分からない。
「まるで猫みたいだ」
――キャット。
その言葉がひどく頭にこびりついていく。刷り込みをされた雛鳥のように、爆撃とともに名を四散した己には丁度良い響き。彼らは冗句のたとえで言ったに違いない。何でもない言葉の筈だ。
この数日を気儘に住み、食って、忍び込んで隙間を潜った。それがひどく猫と同じように思えた。己は度重なる改造を受けた改造人間で、人たるシンボルはあれど真人間ではない。
嗚呼ならば、人ならざる猫と言う在り方も悪くないのかもしれない。
そうして少女は夢の中へと飛び込んでいった。
――あと2143日だ。
「名はなんと言ったか」
イバラシティに潜入した5年の間に多くの出来事があった。
特筆すべきはよりにもよって学院の教師と言う立場に潜り込んだことだ。15歳のシルバーキャットの選択なのか上の命令かはともかく、下手をすればすぐにバレるような年齢詐称と相まって、とりつく島もない中よく隠し通せたといっそ感動的だ。
シルバーキャットにそこまで名演の才があるのなら女優にでも転職したらどうだとからかわれそうだ。
最も面倒なのは名を思い出すことだ。この五年で関わった数百はくだらない生徒や卒業生の顔と名前を必死に思い出しつつダウンロードした記憶と照合させて話を合わせなければならない。他人事のような言動と相まってそれはひどくいびつな言葉になるが、すべては些事だ。
パーティとしてチームを組んだ中にも見知った顔がいるという記憶はあるが、こちら側のシルバーキャットにはなじみが薄く、やはり他人行儀になってしまう。
シルバーキャットという役割を演じるには五年と数時間では時間の重みも掛け方も異なる。
いかんともしがたい、しかしする必要性もない。
ワールドスワップが発生してからこの地には猶予がない。早々に調査の足を進めねばならない。
親しき者が敵であったり、愛する者が敵であったり、一目見ただけの存在が味方だったりとこの街はせわしない。
横断歩道ですれ違っただけのような他人も敵で、また味方だ。
調べねばならない、解明しなければならない。侵略行為を抑止しつつ彼らを狩り、調べ尽くして献上しなければ。
通信回線は相変わらず滞っているが、データの送信は出来ている。獲得した情報を送るだけ送っておけば、あとは誰かが引き継いでくれるに違いない。
ここで死しても代わりはいる。シルバーキャットは改造を受けてパッケージ化された兵士にすぎない。
だからせめて、猫の名を今暫し謀つらせてくれ。



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.34 ぺちか とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.150 泥蘇光悪渡 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
玲子 「ケガはない? 無事でよかった~! ここは危ないから、一緒にいようね!」 |
 |
玲子 「大丈夫! ボクが守ってあげるから! ちょっと怖いかもしれないけど平気だから怖がらないでね!」 |
玲子(813) から 毛 を手渡しされました。
 |
玲子 「はい、先生! でもこれ何に使うの?」 |





対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 2 増加!
影響力が 2 増加!



歩行石壁 をエイドとして招き入れました!
具現LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.9 毛 から射程3の武器『ファイターズドローン』を作製しました!
⇒ ファイターズドローン/武器:強さ40/[効果1]束縛10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
結(1510) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ハンバーグ…?』をつくってもらいました!
⇒ ハンバーグ…?/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
 |
結 「口に合うといいんだけど…」 |
リオ(1334) とカードを交換しました!
九尾の札#3 (カレイドスコープ)


イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールハーブ を研究しました!(深度0⇒1)
ビブラート を習得!
コントラクト を習得!
狂歌乱舞 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シルバーキャット(748) は 吸い殻 を入手!
玲子(813) は ネジ を入手!
結(1510) は ネジ を入手!
仁(1511) は パンの耳 を入手!
シルバーキャット(748) は 吸い殻 を入手!
仁(1511) は 毛 を入手!
玲子(813) は 牙 を入手!
結(1510) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
シルバーキャット(748) のもとに 鬼火 がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
シルバーキャット(748) のもとに 大黒猫 が興味津々な様子で近づいてきます。
シルバーキャット(748) のもとに 大山猫 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。
シルバーキャット(748) のもとに ヤンキー が恥ずかしそうに近づいてきます。



チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- 玲子(813) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。

ENo.748
シルバーキャット



硝煙の匂いをレモングラスの香水で紛らわす。
不条理に曝されても女は兵士として生きている。
無垢な顔立ちのまま、少女兵は此度も武器を取る。
その名は銀色の猫。数多の機械を操る科学の結晶。
少女の己を殺し、猫のように気儘に戦場を駆ける。
「敵対者を補足。猫の目は貴様を逃さない。
一匹たりとも逃がさない。徹底的に潰す。
侵略者よ、せめて敗走する権利は与えてやろう。
猫のテリトリーに立ち入った事、後悔して死ね」
【シルバーキャット】
女性/20歳(経歴詐称により27歳になっている)/177cm
【容姿】
10代後半程度の童顔。
銀髪のセミロングの髪。赤色の瞳。肌は透き通るような白さ。
白いVネックシャツと、ネイビー色の丈の短いキュロット。
カーキ色のミリタリージャケット。
ドッグタグを首から下げている。
【設定】
紛争地域のアンダーグラウンド出身。戦災孤児。
傭兵派遣会社『ブレーン・トルーパー社』に所属する。
主に市街・都市部への潜入・偵察を担当している。
今回はイバラシティに迫りくる危機(アンジニティ)を調査する為にブランブル女学院の保健・体育教師として潜り込んで来た。
潜入時の年齢は15歳。この5年間、ワールドスワップが始まるまでイバラシティを己の縄張りとして張り込み過ごしてきた。
思考速度と視神経を著しく引き上げられており、機械を自在に支配できる改造人間。
寡黙で冷徹な性格。希薄な感情の持ち主で大人しい。
ハザマではより冷酷な一面が浮き彫りになる。イバラシティで過ごした5年間の記憶を必要がある場合のみ落とし込み、深く関わりすぎた人物に対しても情を抱かない範疇で記憶操作している。
この影響でこちら側の精神年齢は10代で止まっている。
武器は銃とドローン、ロボット兵器。
特に市街戦に特化した戦闘スタイルで閉所・暗所は非常に有利。
遠近ともに殺人術に長けており、対人や包囲戦には滅法強い。
【所有ドローン】
ライオン:敵地工作用無人偵察機。クワッドコプター。
ジャガー:対電子戦用無人偵察機。戦闘機型
ピューマ:対市街調査用無人キャタピラ型兵器。戦車型
チーター:対人型用無人多脚型兵器。ベレッタM84を配備。
【異能】
・マルチクライアント
複数の機械を並行して操作できる能力。
自分は椅子に座りながらパソコンで検索しつつ、スマホでソシャゲを遊び、ドローンでコーヒーを持ってこさせるなどの使い方が出来る。
当人は戦場においてあらゆる盤面に配置した上記のドローンを大量に展開して戦闘・戦闘補助・輸送・偵察・監視を同時に行うことに利用する。
この能力が発動している間は、自分と操られている機械の眼(レンズ)が赤色に発光する。
【サブキャラクター】
天津風ヒトミのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=yfpP56Knt690e3ae4e8b6c5809bdc71325dbdb6a6d5
北野ソムクのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=P0IQAju3UlJ536e97d523c04fd97df74518e05b99cf
----
キャラクターイラスト:osisio様
アイコンイラスト:どぷり様
20 / 30
80 PS
チナミ区
N-6
N-6







































No.1 歩行石壁 (種族:歩行石壁)
 |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| 火炎避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:火耐性・炎上耐性増+他者から炎上を移される確率減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |
| 瑠璃樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP・精神変調防御・領域値[地][闇]増+守護+連続減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | サタデーナイトスペシャル | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 腐り落ちたドッグタグ | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | ハンバーグ…? | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 9 | ファイターズドローン | 武器 | 40 | 束縛10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 11 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 30 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |
| シュリーク | 5 | 0 | 50 | 敵貫:朦朧+自:混乱 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| コントラクト | 5 | 0 | 80 | 自従:契LV増 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 祈誓 | 5 | 3 | 0 | 【通常攻撃後】自:祝福消費でDF・LK増(2T) | |
| 狂歌乱舞 | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:混乱+自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増(2T) |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
麺ジニティ (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
五徳猫の加護 (デアデビル) |
0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
|
九尾の札#3 (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 2 ]アクアシェル | [ 1 ]ヒールハーブ |
| [ 2 ]ファイアボルト | [ 2 ]ファーマシー | [ 1 ]イレイザー |

PL / えーや