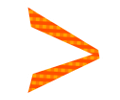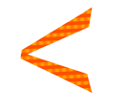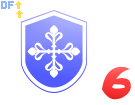<< 2:00~3:00




――昔昔のお話。
ある深い森の中に古い西洋風のお屋敷がありました。
古いといっても、そこには人が住んでおり、
屋敷の主とその家族だけではなく、
その屋敷の維持と世話をするための使用人達も住んでいたため、
お屋敷も、
その周囲の庭も綺麗に整っており、
人里から少し離れていることを除けば、
とても、とても素敵なお屋敷。
住んでいる屋敷の主も、家族の者たちの人柄も良く、
お金にも困ってはおらず、
とても幸せな……幸せな家庭でした。
たった一つ。
そう……たった一つの問題を除いて――
「……」
外では兄弟姉妹が遊んでいる中、
一人の少女が暗い……
暗い部屋の中で外の喧騒を聞きながらベッドの上で横になっていた。
闇の中で少女の紅の瞳が妖しく輝く。
しかし、少女は身じろぎもせずただ――
「……はぁ……」
深い、深いため息をついた。
視線はカーテンがかかって光すら差さぬ窓の方。
瞳がすぅっと細められる。
それは――
「私も皆と遊びたい……な……」
まだ見ぬ兄弟姉妹達と共に、
外で遊びたい。
まだ見ぬ外の世界を見てみたい。
そんな細やかな願い。
そう。
その少女こそがたった一つの問題。
ずっとずっと、この部屋に幽閉されている。
別に彼女が虐げられている訳ではない。
彼女の両親は彼女を愛しているし、
彼女の為ならばなんだって出来る事であればしてくれるだろう。
……それ故に、少女は幽閉されている。
少女の力が危険なものである……
というのもある。
だが、それ以上に少女は己の身に欠陥を抱えているからだ。
そして、それ故に、
こうして生きて世話をされている事自体そのものが、
親が裕福であり、愛がある証でもある。
その欠陥というのは、
光に対する重度のアレルギーである。
最も過剰に反応するのは日光。
僅かな日光ですら劇的な反応を示し、
瞬く間に火傷をする。
では、人工の光ならばというと……
これもまた軽度であれ酷いものである。
少しの間であれば大丈夫だが、
ほんの数分もあれば皮膚が赤くなってくる。
長時間にも及べばやはり火傷になってしまうだろう。
ならば危険な力の方はどうだろう。
漠然としているが、
この力――異能と光アレルギーは無関係とは言い切れない。
人を超えた身体能力、
再生に変化、
魅了に暗視――
多岐に渡る能力のそれは、
古の魔物、吸血鬼の力ともいえるものである。
例え信じていたとしても、
その力を満足に制御できない子供であれば、
ひょんなことから何があってもおかしくはない。
正しく、危険な力……
という訳である。
危険な力に極度の光アレルギー。
故に、こうして親と使用人以外の誰にも知らせず、
少女は幽閉するしかないのである。
ならば幽閉された少女の方はといえば、
幸か不幸か、
己の極度の光アレルギーを知るがゆえに、
その親が自分を守ってくれているのは子供心ながらに分かっていた。
不満がないとまではいえないが、
それでも……
「……」
……少女は起き上がり、
窓の傍に近寄り、
カーテン越しで見えない外をじっと見ながら、
カーテンを手で押さえつける。
遊びたい盛りの子供、
楽しそうな外の子供達の声。
自分も一緒に。
せめて一緒といわないまでも、
外で遊びたい。
想いは募る一方で、
とどまるところを知らない。
だから、いっその事――
「……!」
映美莉は飛び起きた。
全身はぐっしょりと汗に濡れ、
呼吸も荒い。
疲れている訳ではないが――
「……夢見悪すぎだろう……!」
つまりはそういう事であった。
時計を見やると午前4時。
寝入ってから1時間程度だろうか。
「……後3時間は寝るつもりだったんだが……
もう一度寝る……
気分にはなれないし、
それ以上に体が気持ち悪い……
……とりあえず、風呂にでも入るか……」
はぁ、とため息をついて、
服を脱ぎ、
シャワーを浴びる。
べとついた汗を心地よい湯が流していってくれる。
それはまるで夢の中で見たものも一緒に流してくれるようで――
「……」
思わず瞳を閉じて、
夢の続きを思い出す。
結局、あの後何かがあったわけではない。
だけど、
あの時の日々は親の愛を感じる感謝と共に、
鬱屈した全てもまたそこにあった。
戻りたいか、と聞かれると絶対に嫌だと返すだろう。
色々つらい事苦しい事もある。
だけれど、
それ以上に自由に外の世界に羽ばたけるのはとても楽しいものだ。
広い世界、
まだまだ見果てぬものがあり、
知らない事があり、
何より――
出会いがある。
綺麗なレディ達との出会いほど心躍るものはない、
というやつだ。
それに――
「……」
思い出す。
あの時から、
どうして映美莉が外の世界に来ることができたのかを。
確か、始まりは――
日々の楽しみといえば、
昼か夜かは分からないが、
何度か使用人が食事を運んでくれたり、
父や母が訪ねてくることがある。
割れ物を触れるような感じはあったが、
それは、
きっと気を使ってくれているからだろうからなのは見て取れたので、
なるべく機嫌よくしていたように思う。
実の所、幽閉状態だった時、
楽しみだった事が一つもないといえば、
それは嘘になる。
一つだけ、
少女には楽しみな事があった。
それは、
母親が話してくれる物語である。
暗闇の中、
本を読んではもらえないが、
精一杯いろんな話を聞かせてくれた母。
こういう話が聞きたいといったら、
少しずつ話してくれたところを見るに、
必死に呼んで覚えて聞かせてくれたのだろう。
本当に迷惑をかけたと思う。
そんな毎日を過ごすある日、
少女は母に思い切って一つのお願いをする。
それは、
吸血鬼の話を聞かせてほしいという事。
きっと、
少女の事を思って意図的に避けていたのだろう。
暗闇の中で母の困惑した表情がみえる。
その様子を見て取った少女は――
「もっと吸血鬼の事を知って、
力を正しく使えるようになりたい。
一人でも生きて、
父様と母様が安心できるように。」
正直に気持ちをぶつけた。
その時、
母は泣いていたように思う。
そして、
様々な吸血鬼の話を聞かせてくれた。
大体においての吸血鬼の弱点も力も似通っていたがね
時には予想もしないような力をもつもの、
弱点を持たないものもいる事を少女は知った。
そう、であるならば、
これがもしも吸血鬼の異能だというのであれば、
弱点を克服する事も可能なのではないか、
なぜなら異能がなければただの人なのだから。
そして……
もしも、もしも仮に……
異能などではなく少女が本当に吸血鬼であったのなら、
それを克服する異能を発現できるかもしれない。
そこから少女の努力が始まった。
最初は蝋燭の光から。
人工的な光に耐性をつけていく。
最初のうちはどうにもならなかったけど、
徐々に耐えれるようになってくると、
コツをつかんだのか、
問題なく人工の光、
夜の月明かりの元でなら問題なく生活できるようになった。
しかし、
問題はここからだった。
日光の克服。
これには2、3年の時を要する事になる。
人工の光を克服する数倍の年月。
どうにも、
日光には特別な力をもっているらしく、
時には一瞬で腕が灰になってしまう事もあった。
それでも、それでもなんとか――
「……」
眼を開き、シャワーを止めて湯舟につかり、
そっと手を開き上にかざしみる。
今や、光は完全に克服した。
意識することもなく何の危害も自分には及ぼさない。
他の弱点にしてもそうだ。
まったくもって普通の人の様に過ごせる。
しかし、思えば……
昔から力の制御だけは上手にできていたように思う。
やる事がなくて、
いつか他の皆と遊びたい、
せめて普通に暮らせるようになりたい。
そんな思いが作用したのだろうか。
もっとも、
お陰で強い力を引き出すのは苦労するようになった気はするが……
「――そして、我は自由と引き換えに、
大切なものと決別する事になったのだ……
いや、まぁ、別に決別する必要もなかった気はするし、
親不孝ではあったが……」
――そして、
日光に対して完全な耐性を得た数日後、
少女は窓のカーテンを全てあけて、
父と母を出迎えた。
「……父様、母様。
今日まで育てていただいてありがとうございます。
……やっと、こうして普通に生活出来るようになるまで成長いたしました。
これも、今の今まで父様と母様が育ててくださったお陰です。」
その様子と言葉に父も母も驚いていた。
それもそうだろう。
今の今まで光を少し浴びるだけで死にかけていた娘が、
こうして出迎えたのだから。
喜びもあるだろう。
だが、あり得ない状況に対して、
驚きが先に出るのは仕方ないだろう。
「……それで、私は今夜、
この家を出ようと思います。
――今まで散々迷惑をかけて、
手間をかけさせましたが、
これからはきっと一人でも生きてゆけると思うのです。
……今になって兄弟姉妹に対して、
家族の一員として会う……顔もありませんし、
ここにいては迷惑をかけるばかりだと思うのです。
……なので……
こうしてどうにかなったから直ぐに出ていくというのは、
不義理ではありますが……」
そんな少女の言葉に動揺を隠せぬ二人。
引き留める言葉もあったが、
少女は譲らず、
真っすぐ瞳を見つめる。
――決して死なない事。
そして、
連絡だけはきちんと入れる事を条件に、
少女は旅立つ事になる。
父と母。
2人が死ぬその日まで。
「……いかん、
涙腺が緩んできたな。」
思わず零れ落ちる涙を拭う。
そういえば、
父と母はともかく、
兄弟姉妹は今どうしているのだろうか。
実の所、
顔すらお互い知らない相手である。
それでもつながりがある事は映美莉の方は知っている。
また、再び交わる時が来るのだろうか。
それとも……
「ふぅ。」
風呂から出て体を拭った所で、
再び寝間着をまとい、布団に倒れこむ。
「……今度はいい夢みれるといいのだが。
しかし、
これは午前中の授業は休んだほうが良いな。
うん。
色々思い出して本当に疲れ……た……」
心地よい何かに包まれ瞳を閉じる。
ゆるりゆるりと心地よい眠りにおちてゆく。
――どうやら、今度はいい夢が見れそうだ。
「……それで、結局、陽が落ちるまで寝ていたんですか?」
喫茶店でコーヒーとケーキを一緒に食べながら、
緩やかに会話をする葵と映美莉。
「うん、夢見が悪かったので、
お風呂に入って、
色々思い出したら眠くなってね。
目覚ましをかける前に寝てしまって、
結局今日の授業はおやすみになったわけだよ。
でも、折角学校に来たからね、
そうしたら葵を見つけたのでこうしてお茶に誘ったわけだ。
うん。
無駄にはならなかったな。
こうして楽しい一時を過ごせるのだから。」
「全くもう……
……今日はお財布忘れてませんよね?
奢るとかいってましたけど。」
「ああ、きちんと財布はもってきたよ。
中身もほら。」
不幸中の幸いというか、
財布はきちんともってきたらしい。
中身もぎっちり詰まっている為、
問題なく支払いもできそうだ。
「……無駄に金持ちですよね?」
「無駄にって酷いな。
まぁ、レディに不自由させない甲斐性は必須だとも。」
「とりあえず、
今日は忘れ物しなかったようで何よりです。」
そして、他愛のない会話から、
ようやく葵から笑顔が零れ落ちた所でコーヒーをすすり、
「いや、忘れ物はあったのさ。」
そんなことをのたまう映美莉。
「?」
首をかしげる葵に対し、映美莉はいった。
「――何、些細な話さ。
授業の用意を全部忘れた。
まぁ、結局間に合わなかったから問題はない訳だけど……」
恥ずかしいと笑う映美莉に、
日常を感じる葵だった。





ItemNo.6 血液パック を食べました!
体調が 1 回復!(15⇒16)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









ピクシー をエイドとして招き入れました!
使役LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
れーこ(141) とカードを交換しました!
おにくが降ってきた! (サモン:ビーフ)

ドレインライフ を研究しました!(深度0⇒1)
ドレインライフ を研究しました!(深度1⇒2)
ドレインライフ を研究しました!(深度2⇒3)
スタンピート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



兎乃(223) は 吸い殻 を入手!
狐疑(263) は ネジ を入手!
玉護(276) は 吸い殻 を入手!
えみりん(1239) は ド根性雑草 を入手!
玉護(276) は ボロ布 を入手!
えみりん(1239) は 不思議な石 を入手!
狐疑(263) は 毛 を入手!
えみりん(1239) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
えみりん(1239) のもとに 歩行軍手 がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
えみりん(1239) のもとに 歩行石壁 が軽快なステップで近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに 大黒猫 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 H-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調12⇒11)
採集はできませんでした。
- 兎乃(223) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 兎乃(223) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 狐疑(263) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 玉護(276) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- えみりん(1239) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














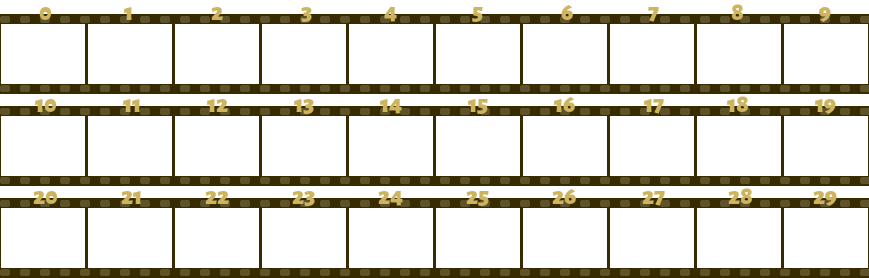


































No.1 クロ (種族:大黒猫)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



――昔昔のお話。
ある深い森の中に古い西洋風のお屋敷がありました。
古いといっても、そこには人が住んでおり、
屋敷の主とその家族だけではなく、
その屋敷の維持と世話をするための使用人達も住んでいたため、
お屋敷も、
その周囲の庭も綺麗に整っており、
人里から少し離れていることを除けば、
とても、とても素敵なお屋敷。
住んでいる屋敷の主も、家族の者たちの人柄も良く、
お金にも困ってはおらず、
とても幸せな……幸せな家庭でした。
たった一つ。
そう……たった一つの問題を除いて――
「……」
外では兄弟姉妹が遊んでいる中、
一人の少女が暗い……
暗い部屋の中で外の喧騒を聞きながらベッドの上で横になっていた。
闇の中で少女の紅の瞳が妖しく輝く。
しかし、少女は身じろぎもせずただ――
「……はぁ……」
深い、深いため息をついた。
視線はカーテンがかかって光すら差さぬ窓の方。
瞳がすぅっと細められる。
それは――
「私も皆と遊びたい……な……」
まだ見ぬ兄弟姉妹達と共に、
外で遊びたい。
まだ見ぬ外の世界を見てみたい。
そんな細やかな願い。
そう。
その少女こそがたった一つの問題。
ずっとずっと、この部屋に幽閉されている。
別に彼女が虐げられている訳ではない。
彼女の両親は彼女を愛しているし、
彼女の為ならばなんだって出来る事であればしてくれるだろう。
……それ故に、少女は幽閉されている。
少女の力が危険なものである……
というのもある。
だが、それ以上に少女は己の身に欠陥を抱えているからだ。
そして、それ故に、
こうして生きて世話をされている事自体そのものが、
親が裕福であり、愛がある証でもある。
その欠陥というのは、
光に対する重度のアレルギーである。
最も過剰に反応するのは日光。
僅かな日光ですら劇的な反応を示し、
瞬く間に火傷をする。
では、人工の光ならばというと……
これもまた軽度であれ酷いものである。
少しの間であれば大丈夫だが、
ほんの数分もあれば皮膚が赤くなってくる。
長時間にも及べばやはり火傷になってしまうだろう。
ならば危険な力の方はどうだろう。
漠然としているが、
この力――異能と光アレルギーは無関係とは言い切れない。
人を超えた身体能力、
再生に変化、
魅了に暗視――
多岐に渡る能力のそれは、
古の魔物、吸血鬼の力ともいえるものである。
例え信じていたとしても、
その力を満足に制御できない子供であれば、
ひょんなことから何があってもおかしくはない。
正しく、危険な力……
という訳である。
危険な力に極度の光アレルギー。
故に、こうして親と使用人以外の誰にも知らせず、
少女は幽閉するしかないのである。
ならば幽閉された少女の方はといえば、
幸か不幸か、
己の極度の光アレルギーを知るがゆえに、
その親が自分を守ってくれているのは子供心ながらに分かっていた。
不満がないとまではいえないが、
それでも……
「……」
……少女は起き上がり、
窓の傍に近寄り、
カーテン越しで見えない外をじっと見ながら、
カーテンを手で押さえつける。
遊びたい盛りの子供、
楽しそうな外の子供達の声。
自分も一緒に。
せめて一緒といわないまでも、
外で遊びたい。
想いは募る一方で、
とどまるところを知らない。
だから、いっその事――
「……!」
映美莉は飛び起きた。
全身はぐっしょりと汗に濡れ、
呼吸も荒い。
疲れている訳ではないが――
「……夢見悪すぎだろう……!」
つまりはそういう事であった。
時計を見やると午前4時。
寝入ってから1時間程度だろうか。
「……後3時間は寝るつもりだったんだが……
もう一度寝る……
気分にはなれないし、
それ以上に体が気持ち悪い……
……とりあえず、風呂にでも入るか……」
はぁ、とため息をついて、
服を脱ぎ、
シャワーを浴びる。
べとついた汗を心地よい湯が流していってくれる。
それはまるで夢の中で見たものも一緒に流してくれるようで――
「……」
思わず瞳を閉じて、
夢の続きを思い出す。
結局、あの後何かがあったわけではない。
だけど、
あの時の日々は親の愛を感じる感謝と共に、
鬱屈した全てもまたそこにあった。
戻りたいか、と聞かれると絶対に嫌だと返すだろう。
色々つらい事苦しい事もある。
だけれど、
それ以上に自由に外の世界に羽ばたけるのはとても楽しいものだ。
広い世界、
まだまだ見果てぬものがあり、
知らない事があり、
何より――
出会いがある。
綺麗なレディ達との出会いほど心躍るものはない、
というやつだ。
それに――
「……」
思い出す。
あの時から、
どうして映美莉が外の世界に来ることができたのかを。
確か、始まりは――
日々の楽しみといえば、
昼か夜かは分からないが、
何度か使用人が食事を運んでくれたり、
父や母が訪ねてくることがある。
割れ物を触れるような感じはあったが、
それは、
きっと気を使ってくれているからだろうからなのは見て取れたので、
なるべく機嫌よくしていたように思う。
実の所、幽閉状態だった時、
楽しみだった事が一つもないといえば、
それは嘘になる。
一つだけ、
少女には楽しみな事があった。
それは、
母親が話してくれる物語である。
暗闇の中、
本を読んではもらえないが、
精一杯いろんな話を聞かせてくれた母。
こういう話が聞きたいといったら、
少しずつ話してくれたところを見るに、
必死に呼んで覚えて聞かせてくれたのだろう。
本当に迷惑をかけたと思う。
そんな毎日を過ごすある日、
少女は母に思い切って一つのお願いをする。
それは、
吸血鬼の話を聞かせてほしいという事。
きっと、
少女の事を思って意図的に避けていたのだろう。
暗闇の中で母の困惑した表情がみえる。
その様子を見て取った少女は――
「もっと吸血鬼の事を知って、
力を正しく使えるようになりたい。
一人でも生きて、
父様と母様が安心できるように。」
正直に気持ちをぶつけた。
その時、
母は泣いていたように思う。
そして、
様々な吸血鬼の話を聞かせてくれた。
大体においての吸血鬼の弱点も力も似通っていたがね
時には予想もしないような力をもつもの、
弱点を持たないものもいる事を少女は知った。
そう、であるならば、
これがもしも吸血鬼の異能だというのであれば、
弱点を克服する事も可能なのではないか、
なぜなら異能がなければただの人なのだから。
そして……
もしも、もしも仮に……
異能などではなく少女が本当に吸血鬼であったのなら、
それを克服する異能を発現できるかもしれない。
そこから少女の努力が始まった。
最初は蝋燭の光から。
人工的な光に耐性をつけていく。
最初のうちはどうにもならなかったけど、
徐々に耐えれるようになってくると、
コツをつかんだのか、
問題なく人工の光、
夜の月明かりの元でなら問題なく生活できるようになった。
しかし、
問題はここからだった。
日光の克服。
これには2、3年の時を要する事になる。
人工の光を克服する数倍の年月。
どうにも、
日光には特別な力をもっているらしく、
時には一瞬で腕が灰になってしまう事もあった。
それでも、それでもなんとか――
「……」
眼を開き、シャワーを止めて湯舟につかり、
そっと手を開き上にかざしみる。
今や、光は完全に克服した。
意識することもなく何の危害も自分には及ぼさない。
他の弱点にしてもそうだ。
まったくもって普通の人の様に過ごせる。
しかし、思えば……
昔から力の制御だけは上手にできていたように思う。
やる事がなくて、
いつか他の皆と遊びたい、
せめて普通に暮らせるようになりたい。
そんな思いが作用したのだろうか。
もっとも、
お陰で強い力を引き出すのは苦労するようになった気はするが……
「――そして、我は自由と引き換えに、
大切なものと決別する事になったのだ……
いや、まぁ、別に決別する必要もなかった気はするし、
親不孝ではあったが……」
――そして、
日光に対して完全な耐性を得た数日後、
少女は窓のカーテンを全てあけて、
父と母を出迎えた。
「……父様、母様。
今日まで育てていただいてありがとうございます。
……やっと、こうして普通に生活出来るようになるまで成長いたしました。
これも、今の今まで父様と母様が育ててくださったお陰です。」
その様子と言葉に父も母も驚いていた。
それもそうだろう。
今の今まで光を少し浴びるだけで死にかけていた娘が、
こうして出迎えたのだから。
喜びもあるだろう。
だが、あり得ない状況に対して、
驚きが先に出るのは仕方ないだろう。
「……それで、私は今夜、
この家を出ようと思います。
――今まで散々迷惑をかけて、
手間をかけさせましたが、
これからはきっと一人でも生きてゆけると思うのです。
……今になって兄弟姉妹に対して、
家族の一員として会う……顔もありませんし、
ここにいては迷惑をかけるばかりだと思うのです。
……なので……
こうしてどうにかなったから直ぐに出ていくというのは、
不義理ではありますが……」
そんな少女の言葉に動揺を隠せぬ二人。
引き留める言葉もあったが、
少女は譲らず、
真っすぐ瞳を見つめる。
――決して死なない事。
そして、
連絡だけはきちんと入れる事を条件に、
少女は旅立つ事になる。
父と母。
2人が死ぬその日まで。
「……いかん、
涙腺が緩んできたな。」
思わず零れ落ちる涙を拭う。
そういえば、
父と母はともかく、
兄弟姉妹は今どうしているのだろうか。
実の所、
顔すらお互い知らない相手である。
それでもつながりがある事は映美莉の方は知っている。
また、再び交わる時が来るのだろうか。
それとも……
「ふぅ。」
風呂から出て体を拭った所で、
再び寝間着をまとい、布団に倒れこむ。
「……今度はいい夢みれるといいのだが。
しかし、
これは午前中の授業は休んだほうが良いな。
うん。
色々思い出して本当に疲れ……た……」
心地よい何かに包まれ瞳を閉じる。
ゆるりゆるりと心地よい眠りにおちてゆく。
――どうやら、今度はいい夢が見れそうだ。
「……それで、結局、陽が落ちるまで寝ていたんですか?」
喫茶店でコーヒーとケーキを一緒に食べながら、
緩やかに会話をする葵と映美莉。
「うん、夢見が悪かったので、
お風呂に入って、
色々思い出したら眠くなってね。
目覚ましをかける前に寝てしまって、
結局今日の授業はおやすみになったわけだよ。
でも、折角学校に来たからね、
そうしたら葵を見つけたのでこうしてお茶に誘ったわけだ。
うん。
無駄にはならなかったな。
こうして楽しい一時を過ごせるのだから。」
「全くもう……
……今日はお財布忘れてませんよね?
奢るとかいってましたけど。」
「ああ、きちんと財布はもってきたよ。
中身もほら。」
不幸中の幸いというか、
財布はきちんともってきたらしい。
中身もぎっちり詰まっている為、
問題なく支払いもできそうだ。
「……無駄に金持ちですよね?」
「無駄にって酷いな。
まぁ、レディに不自由させない甲斐性は必須だとも。」
「とりあえず、
今日は忘れ物しなかったようで何よりです。」
そして、他愛のない会話から、
ようやく葵から笑顔が零れ落ちた所でコーヒーをすすり、
「いや、忘れ物はあったのさ。」
そんなことをのたまう映美莉。
「?」
首をかしげる葵に対し、映美莉はいった。
「――何、些細な話さ。
授業の用意を全部忘れた。
まぁ、結局間に合わなかったから問題はない訳だけど……」
恥ずかしいと笑う映美莉に、
日常を感じる葵だった。
 |
えみりん 「ネタが……!ネタがつきた……!」 |
 |
えみりん 「かくなる上は思いついたネタをぶっこんでいくしかない!」 |
 |
えみりん 「そんな感じで時系列とか気にせずに思いついた話を書いていこうと思う!」 |
 |
えみりん 「その話すらも思い浮かばなかったならば――」 |
 |
えみりん 「白紙だぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!」 |





 |
兎乃 「二人ともよろしくね~♪」 |
| 葛子 「さて、食材になりそうなものがあればよいが……。」 |
ItemNo.6 血液パック を食べました!
 |
えみりん 「栄養補給だ」 |
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





TeamNo.223
|
 |
てなもんやアベンジャーズ
|



ピクシー をエイドとして招き入れました!
使役LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
れーこ(141) とカードを交換しました!
おにくが降ってきた! (サモン:ビーフ)

ドレインライフ を研究しました!(深度0⇒1)
ドレインライフ を研究しました!(深度1⇒2)
ドレインライフ を研究しました!(深度2⇒3)
スタンピート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



兎乃(223) は 吸い殻 を入手!
狐疑(263) は ネジ を入手!
玉護(276) は 吸い殻 を入手!
えみりん(1239) は ド根性雑草 を入手!
玉護(276) は ボロ布 を入手!
えみりん(1239) は 不思議な石 を入手!
狐疑(263) は 毛 を入手!
えみりん(1239) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
えみりん(1239) のもとに 歩行軍手 がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
えみりん(1239) のもとに 歩行石壁 が軽快なステップで近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに 大黒猫 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 H-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調12⇒11)
採集はできませんでした。
- 兎乃(223) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 兎乃(223) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 狐疑(263) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 玉護(276) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- えみりん(1239) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







TeamNo.223
|
 |
乾杯の歌
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



TeamNo.223
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.1239
社 映美莉



るび:やしろ えみり
本名はエミリア=S=シュライネン
のんべんだらりとやってる女好きの残念美女大学生。
欠点は物をよく忘れる事。
能力は吸血鬼。
身長:180cm
体重:秘密だ
スリーサイズ:
出るところは出て引っ込む所は引っ込んでいる。
測った内容を忘れたとかでは断じてないと思っていただこう。
思っていただこう。
本名はエミリア=S=シュライネン
のんべんだらりとやってる女好きの残念美女大学生。
欠点は物をよく忘れる事。
能力は吸血鬼。
身長:180cm
体重:秘密だ
スリーサイズ:
出るところは出て引っ込む所は引っ込んでいる。
測った内容を忘れたとかでは断じてないと思っていただこう。
思っていただこう。
11 / 30
128 PS
チナミ区
J-16
J-16




































No.1 クロ (種族:大黒猫)
 |
|
一見するとただの猫のように見えるが……?
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 巧技 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX・LK増 | |
| 見切 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率増 |
最大EP[20]
No.2 ピクシー (種族:ピクシー) |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 風特性回復 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:風属性スキルのHP増効果に風特性が影響 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | いつも忘れられる財布 | 装飾 | 25 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 7 | 焼肉 | 料理 | 25 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 11 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 12 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 13 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 使役 | 20 | エイド/援護 |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 20 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 15 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| アドレナリン | 5 | 0 | 50 | 自従傷:AT増(4T)+麻痺・衰弱をDX化 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| パワーブースター | 5 | 0 | 40 | 自従:AT・DF・DX・AG・HL増(3T) | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| マインドリカバー | 5 | 0 | 0 | 自:連続減+SP30%以下ならSP増+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| アーマメント | 5 | 0 | 150 | 自従全:連撃LV・鎮痛LV・強靭LV増+連続減 | |
| スタンピート | 5 | 0 | 50 | 自従:AT・DX・AG増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
麺棒で、えいえい! (クイック) |
0 | 50 | 敵:3連撃 | |
|
いっぱいがーど (ワイドプロテクション) |
0 | 300 | 味全:守護 | |
|
よびだす (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
|
おにくが降ってきた! (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ヒールミスト | [ 3 ]リンクブレイク | [ 3 ]ディスインフェクト |
| [ 3 ]ドレインライフ |

PL / 小鳥遊玲華