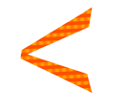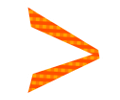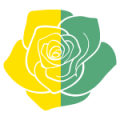<< 2:00~3:00




Her Dog
今より、うんと昔の話ですが。白いレースで編まれたドアノブカバーの上に手を這わせ、ドアノブをひねると、いつもその人はいました。
窓辺に置いている机には開きっぱなしの異国の絵本(ごく淡い、みずいろの表紙でした)が置かれていて、また、そこでは白いカーテンが揺れていて、いつも白木蓮が散っていくのが見えます(季節に関係なく、本当にいつも見えるのです)。破れないように、丁寧に楽譜の頁を繰る、黒いワンピースの袖から覗く手はやはり白っぽく、部屋の片隅にあるピアノの白黒の鍵盤を叩けば響く甘やかな音色は、一階で仕事をしている時などでも部屋の中にいるのと同じように降ってきます。あの楽器は家のどこにいても彼女の存在をこの身体に伝えてくれるので、すきでした。
あの女の子を、女の子らしく育てるために、と彼女の両親が用意した真っ白な部屋を、『清潔なだけの監獄』とまで言った彼女は、今は学生寮で暮らしていて、滅多なことがなければ帰ってきません。待てど暮らせど、帰ってはきませんでした。
BASARA
婆娑羅〈ばさら〉 とは。
秩序や伝統を無視し、自由闊達に生きる様。権威に反発する社会的風潮の事。
ぜいたくの限りを尽くすなどして、この世を謳歌すること。
「たぶん……戦争に行きたいんだと思うんです、わたし」
『女の子』であれ、『乙女』であれと育てられ、蝶よ花よと囲いこまれる幼少期を過ごしたその人は、それらしくお菓子作りに興じながらも、そう言いました。彼女も一時期は男装をしたり、荒々しい男性語を使ってジェンダーロールを抜け出そうとしていたものの、最近はそういったこともなく、穏やかにしていたので、俺は一寸びっくりして、何を言うべきか迷っていました。
どうも、その人は、最近……戦争に行く夢を見るそうです。
その夢の中では、戦場でも死体が腐っていくこともなく、人の命は花のように散っていくのだと言います。心の裡から、魂から、人は叫び、語らうように剣を交え、愛し合うように殺し合う。そんな夢を、ずっと、見ているのだと。恋の苦しみに喘ぐように、顔を真っ赤にしながら語っていました。
俺は、そのとき、
「それ作り終わったら、一緒にどっか行こか」
なんて言うのが精一杯でした。
だって、俺みたいなちっぽけな個人の力で戦争を起こすことなんてとてもとてもできませんし、まさか使用人の立場で『小規模の戦争だ』と言って喧嘩を仕掛けるわけにもいきませんでしたから。
皆さん、どうもありがとう。戦争をおこしてくれて。
あの人は、ずっと、生きているという実感を欲していたのだと思います。
形を持った死。死、そのものの圧倒的な敵と相見えることで、生が強烈なものになる瞬間を、ずっとずっと望んでいたのだと思います。
戦場を駆るみなさんは、嵐のようでした。彼女を縛り、囲い、彼女を"娘"と"乙女"と名付けた何もかもを吹き飛ばす、豊かな風。
俺が愛するその人は、大嵐によって瓦礫と化したお城を抜け出して、白馬を駆るおひめさまのように、素足で戦場を駆けていきます。
守られていたり、大人しく助けが来るのを待っていたりするのではなくって、自分の意思で自らそこを飛び出していった。自由自在に白馬をあやつるように、素足で飛び出していった。
赤い剣を一本持って大地を蹴り、彼女は前へ、前へと世界を掻い探る。懸命に、生きているその人は、生命力そのもののような姿をして輝いていました。
芽吹いたばかりの植物、産声、雪崩のような、荒々しい戦士の女の子。
返り血を浴びた髪が空を舞う様は、ごおごぉと燃える火のようで。虚弱に生まれながら、風に煽られて、その生命の燈を消すことのないようにと燃え盛る。
生命をすべて、今一瞬のための推進力に変えてしまう、向こう見ずで無鉄砲な、小さな男の子のような戦士。
止めないで、縛らないで、留めないで、名付けないで。そう叫ぶような、生命。弾丸のように撃ちだされて、転がっていくのを、ただ見ていた。
BASARA、という少女漫画が、彼女の棚にありました。砂漠で生まれ育った少女のものがたりでした。
婆娑羅。それは、旧い因習や拘束を否定し自由に振る舞い、思いのままに生きる精神のこと。
湖沼の水を煮沸したものを啜り、虫や木の根を拾って食いちぎり、戦います。今の彼女は、彼女の両親がが期待した病弱で美しい深窓の令嬢のような雰囲気はなくって……いつになく、楽しそうでした。
そんな彼女を見て……俺は、彼女が、彼女に貞淑にすることを教えた両親の前に、ホットパンツを履いて立ちはだかった日のことを思い出しました。
『いつもいい子でいるように』『控えめにするように』と言いつけてきた両親に、『うるせー!』と吐き捨てて、貴女はあの日、家を飛び出して夜の街へと出かけたのでした。
今日の貴女はあの日のように素足を晒して、飛び上がるから。俺はあの人同じことを思うのです。
この人は、まさしく、"婆娑羅"なのだろう。
荒れた街の中に投じられた金剛石の光が野に充ちる。
燃えるような髪、迸る血潮、匂う汗と崩れゆく瓦礫から付す埃の匂い。埃で荒れゆく素肌も、太陽の光を浴びて輝く魚鱗のようで、美しい。彼女の纏う何もかもが愛のようでした。
この世界、戦場に愛されて、躓きながら転がりながらも彼女は今、どんな時よりも明確に、生きていました。
婆娑羅。その語源は、ダイヤモンドを意味する。
その石言葉は、『変わらぬ愛』『純潔』そして、『不屈』。
どんなふうに転がっても、その美しさは欠けることがなく、打ち消されることもない。その光で、俺は満たされる。
〈今にも消し飛んでしまいそうな体つきをしていながら、彼女は逞ましく生きている〉



ENo.121 理外のチヨ子 とのやりとり

ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり

ENo.447 血迷い少年 とのやりとり

ENo.490 雛 とのやりとり

ENo.671 海の魔物 とのやりとり

ENo.1292 八式 とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。








武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 1 UP!(LV7⇒8、-1CP)
付加LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
料理LV を 1 UP!(LV13⇒14、-1CP)
コンテイン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 M-10(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 N-10(沼地)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 O-10(水地)には移動できません。
チナミ区 O-10(水地)には移動できません。
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――














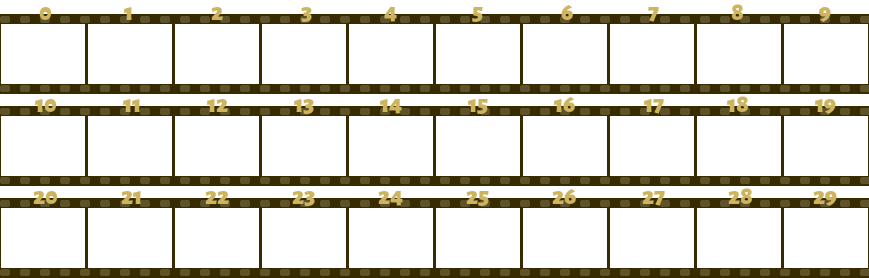









































異能・生産
アクティブ
パッシブ





[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



Her Dog
今より、うんと昔の話ですが。白いレースで編まれたドアノブカバーの上に手を這わせ、ドアノブをひねると、いつもその人はいました。
窓辺に置いている机には開きっぱなしの異国の絵本(ごく淡い、みずいろの表紙でした)が置かれていて、また、そこでは白いカーテンが揺れていて、いつも白木蓮が散っていくのが見えます(季節に関係なく、本当にいつも見えるのです)。破れないように、丁寧に楽譜の頁を繰る、黒いワンピースの袖から覗く手はやはり白っぽく、部屋の片隅にあるピアノの白黒の鍵盤を叩けば響く甘やかな音色は、一階で仕事をしている時などでも部屋の中にいるのと同じように降ってきます。あの楽器は家のどこにいても彼女の存在をこの身体に伝えてくれるので、すきでした。
あの女の子を、女の子らしく育てるために、と彼女の両親が用意した真っ白な部屋を、『清潔なだけの監獄』とまで言った彼女は、今は学生寮で暮らしていて、滅多なことがなければ帰ってきません。待てど暮らせど、帰ってはきませんでした。
BASARA
婆娑羅〈ばさら〉 とは。
秩序や伝統を無視し、自由闊達に生きる様。権威に反発する社会的風潮の事。
ぜいたくの限りを尽くすなどして、この世を謳歌すること。
「たぶん……戦争に行きたいんだと思うんです、わたし」
『女の子』であれ、『乙女』であれと育てられ、蝶よ花よと囲いこまれる幼少期を過ごしたその人は、それらしくお菓子作りに興じながらも、そう言いました。彼女も一時期は男装をしたり、荒々しい男性語を使ってジェンダーロールを抜け出そうとしていたものの、最近はそういったこともなく、穏やかにしていたので、俺は一寸びっくりして、何を言うべきか迷っていました。
どうも、その人は、最近……戦争に行く夢を見るそうです。
その夢の中では、戦場でも死体が腐っていくこともなく、人の命は花のように散っていくのだと言います。心の裡から、魂から、人は叫び、語らうように剣を交え、愛し合うように殺し合う。そんな夢を、ずっと、見ているのだと。恋の苦しみに喘ぐように、顔を真っ赤にしながら語っていました。
俺は、そのとき、
「それ作り終わったら、一緒にどっか行こか」
なんて言うのが精一杯でした。
だって、俺みたいなちっぽけな個人の力で戦争を起こすことなんてとてもとてもできませんし、まさか使用人の立場で『小規模の戦争だ』と言って喧嘩を仕掛けるわけにもいきませんでしたから。
皆さん、どうもありがとう。戦争をおこしてくれて。
あの人は、ずっと、生きているという実感を欲していたのだと思います。
形を持った死。死、そのものの圧倒的な敵と相見えることで、生が強烈なものになる瞬間を、ずっとずっと望んでいたのだと思います。
戦場を駆るみなさんは、嵐のようでした。彼女を縛り、囲い、彼女を"娘"と"乙女"と名付けた何もかもを吹き飛ばす、豊かな風。
俺が愛するその人は、大嵐によって瓦礫と化したお城を抜け出して、白馬を駆るおひめさまのように、素足で戦場を駆けていきます。
守られていたり、大人しく助けが来るのを待っていたりするのではなくって、自分の意思で自らそこを飛び出していった。自由自在に白馬をあやつるように、素足で飛び出していった。
赤い剣を一本持って大地を蹴り、彼女は前へ、前へと世界を掻い探る。懸命に、生きているその人は、生命力そのもののような姿をして輝いていました。
芽吹いたばかりの植物、産声、雪崩のような、荒々しい戦士の女の子。
返り血を浴びた髪が空を舞う様は、ごおごぉと燃える火のようで。虚弱に生まれながら、風に煽られて、その生命の燈を消すことのないようにと燃え盛る。
生命をすべて、今一瞬のための推進力に変えてしまう、向こう見ずで無鉄砲な、小さな男の子のような戦士。
止めないで、縛らないで、留めないで、名付けないで。そう叫ぶような、生命。弾丸のように撃ちだされて、転がっていくのを、ただ見ていた。
BASARA、という少女漫画が、彼女の棚にありました。砂漠で生まれ育った少女のものがたりでした。
婆娑羅。それは、旧い因習や拘束を否定し自由に振る舞い、思いのままに生きる精神のこと。
湖沼の水を煮沸したものを啜り、虫や木の根を拾って食いちぎり、戦います。今の彼女は、彼女の両親がが期待した病弱で美しい深窓の令嬢のような雰囲気はなくって……いつになく、楽しそうでした。
そんな彼女を見て……俺は、彼女が、彼女に貞淑にすることを教えた両親の前に、ホットパンツを履いて立ちはだかった日のことを思い出しました。
『いつもいい子でいるように』『控えめにするように』と言いつけてきた両親に、『うるせー!』と吐き捨てて、貴女はあの日、家を飛び出して夜の街へと出かけたのでした。
今日の貴女はあの日のように素足を晒して、飛び上がるから。俺はあの人同じことを思うのです。
この人は、まさしく、"婆娑羅"なのだろう。
荒れた街の中に投じられた金剛石の光が野に充ちる。
燃えるような髪、迸る血潮、匂う汗と崩れゆく瓦礫から付す埃の匂い。埃で荒れゆく素肌も、太陽の光を浴びて輝く魚鱗のようで、美しい。彼女の纏う何もかもが愛のようでした。
この世界、戦場に愛されて、躓きながら転がりながらも彼女は今、どんな時よりも明確に、生きていました。
婆娑羅。その語源は、ダイヤモンドを意味する。
その石言葉は、『変わらぬ愛』『純潔』そして、『不屈』。
どんなふうに転がっても、その美しさは欠けることがなく、打ち消されることもない。その光で、俺は満たされる。
〈今にも消し飛んでしまいそうな体つきをしていながら、彼女は逞ましく生きている〉



ENo.121 理外のチヨ子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.447 血迷い少年 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.490 雛 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.671 海の魔物 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1292 八式 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。







武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 1 UP!(LV7⇒8、-1CP)
付加LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
料理LV を 1 UP!(LV13⇒14、-1CP)
コンテイン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 M-10(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 N-10(沼地)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 O-10(水地)には移動できません。
チナミ区 O-10(水地)には移動できません。
チナミ区 N-9(山岳)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――





ENo.1185
夜町 乙女



概要
お姫様になりたい系女子。
夜町 乙女(よまち おとめ)
相良伊橋高校1-1(15歳)
175センチ 60キロ
1/17日生まれ A型
「もしかして、乙女の運命の人では……!?」
「わたしはわたしの自己満足を追求することにいたします。だから、あなたもすきに生きればいい」
病弱な深窓の令嬢。成金。
家の後継になる健康な妹が生まれてから、かなりはっちゃけている。元々独立心が高く、親の仕事や遺産を継ぐ意欲は弱かった様子だが、親の態度の変化についてショックが大きかったのかネジが飛んでいる。
人の話は聞かないし、意識的に嘘をよくつく。独り善がりで高慢。被害妄想強め。効率主義。友達いない系。
誰かの孤独感や絶望に寄り添えることができる自分になりたいと思っていて、人に捨てられたモノを拾って帰る習慣がある。
『夜町家嫡子である自分』という肩書がなくなったため自分の立ち位置を見失っており、すべての物語の起点である『むかしむかし』のような『おひめさま』として再定義しようとしている最中。あまりうまくいっていない。
異能 ブラッディ・メアリ
大まかな特徴は以下の二つ。
・手に触れた血液を任意の形・任意の硬さに変えることができる。他人の血だろうと動物の血だろうと問題ない。(手に触れていない状態では変形は不可能)
・半径10m以内にある血液を自分の手に引き寄せることが可能。ただし、空気に触れていない状態の血液を引き寄せることはできない。(例えば、血液の入った袋と考えて人間ごと引き寄せるようなことはできない)
ハザマにおいては以下の能力も追加される。
・手で触れた血液の量を増減させることも可能。三倍~三分の一までなら増減させることができる。
尖らせて硬くして武器に転用することも可能だが、剣など武器としての形を整えるには多量の血液が必要となる。
また、怪我をしたときに傷口に触れて血液を硬化させることで傷口を塞ぐこともできる。
サブキャラ
花蓑 釼(はなみの はがね)
相良伊橋高校OB?かも (19歳)
171センチ 63キロ
3/21生まれ O型 左利き
「ごめんなぁ、俺は女の子の命令しか聞かれへんのんよ」
「オトちゃんのために生きるのが俺の人生で、オトちゃんがおる場所が俺の生きる場所なんよ」
夜町家に住み込みで働く使用人。虐待サバイバー。
乙女が寮で生活し始めてから仕事が減り、人手が余っているため実質的に無職なんだとか。アルバイト先を探している。
明るく人懐っこい性格で、かなり素直。のんびり。寂しがり屋で独占欲が強い。
何よりもまず、愛に対して忠実であろうとする人。
異能の効果のせいで女好きと思われやすいし、実際にかなりすきではあるらしい。
異能 お気に召すまま【イエス、マイレディ】
女性に命令(あるいはお願い)をされたとき、命令されてから一時間は、身体能力が底上げされる。一時間経ったら異能の効果の全てが切れてしまう。
デメリットとしては、女性の命令を無視する事はできないこと。それに逆らおうとしても体は動かなかったり、命令を遂行するために体が勝手に動いたりする。
ハザマでは、命令に従うか従わないかの決定権を持つことも可能になる他、身体能力の補正も大きくなる。
【女性】の範囲についてだが、割とガバガバなので「体は男性でも心は女性」の人や「女装をした男性」「女性っぽい顔つきの男性」だけに留まらず「女言葉で出された命令」にも逆らえなくなる場合もある。たまに女性の命令を無視できる時もある。ごく稀。
この異能があるからといって、男性の命令に従えないわけではない。
✳︎当方のPCがはセンシティブな内容を含みます。
報告、相談、苦情などはゲーム内での連絡でももちろん受け付けておりますが、なかなか気がつかない場合もございますので、ツイッターの方へいただけますと幸いです。
Twitter ID:@Satui_Muki(現在鍵付きになっていますが、基本的にリクエストは全て通しています)
お姫様になりたい系女子。
夜町 乙女(よまち おとめ)
相良伊橋高校1-1(15歳)
175センチ 60キロ
1/17日生まれ A型
「もしかして、乙女の運命の人では……!?」
「わたしはわたしの自己満足を追求することにいたします。だから、あなたもすきに生きればいい」
病弱な深窓の令嬢。成金。
家の後継になる健康な妹が生まれてから、かなりはっちゃけている。元々独立心が高く、親の仕事や遺産を継ぐ意欲は弱かった様子だが、親の態度の変化についてショックが大きかったのかネジが飛んでいる。
人の話は聞かないし、意識的に嘘をよくつく。独り善がりで高慢。被害妄想強め。効率主義。友達いない系。
誰かの孤独感や絶望に寄り添えることができる自分になりたいと思っていて、人に捨てられたモノを拾って帰る習慣がある。
『夜町家嫡子である自分』という肩書がなくなったため自分の立ち位置を見失っており、すべての物語の起点である『むかしむかし』のような『おひめさま』として再定義しようとしている最中。あまりうまくいっていない。
異能 ブラッディ・メアリ
大まかな特徴は以下の二つ。
・手に触れた血液を任意の形・任意の硬さに変えることができる。他人の血だろうと動物の血だろうと問題ない。(手に触れていない状態では変形は不可能)
・半径10m以内にある血液を自分の手に引き寄せることが可能。ただし、空気に触れていない状態の血液を引き寄せることはできない。(例えば、血液の入った袋と考えて人間ごと引き寄せるようなことはできない)
ハザマにおいては以下の能力も追加される。
・手で触れた血液の量を増減させることも可能。三倍~三分の一までなら増減させることができる。
尖らせて硬くして武器に転用することも可能だが、剣など武器としての形を整えるには多量の血液が必要となる。
また、怪我をしたときに傷口に触れて血液を硬化させることで傷口を塞ぐこともできる。
サブキャラ
花蓑 釼(はなみの はがね)
相良伊橋高校OB?かも (19歳)
171センチ 63キロ
3/21生まれ O型 左利き
「ごめんなぁ、俺は女の子の命令しか聞かれへんのんよ」
「オトちゃんのために生きるのが俺の人生で、オトちゃんがおる場所が俺の生きる場所なんよ」
夜町家に住み込みで働く使用人。虐待サバイバー。
乙女が寮で生活し始めてから仕事が減り、人手が余っているため実質的に無職なんだとか。アルバイト先を探している。
明るく人懐っこい性格で、かなり素直。のんびり。寂しがり屋で独占欲が強い。
何よりもまず、愛に対して忠実であろうとする人。
異能の効果のせいで女好きと思われやすいし、実際にかなりすきではあるらしい。
異能 お気に召すまま【イエス、マイレディ】
女性に命令(あるいはお願い)をされたとき、命令されてから一時間は、身体能力が底上げされる。一時間経ったら異能の効果の全てが切れてしまう。
デメリットとしては、女性の命令を無視する事はできないこと。それに逆らおうとしても体は動かなかったり、命令を遂行するために体が勝手に動いたりする。
ハザマでは、命令に従うか従わないかの決定権を持つことも可能になる他、身体能力の補正も大きくなる。
【女性】の範囲についてだが、割とガバガバなので「体は男性でも心は女性」の人や「女装をした男性」「女性っぽい顔つきの男性」だけに留まらず「女言葉で出された命令」にも逆らえなくなる場合もある。たまに女性の命令を無視できる時もある。ごく稀。
この異能があるからといって、男性の命令に従えないわけではない。
✳︎当方のPCがはセンシティブな内容を含みます。
報告、相談、苦情などはゲーム内での連絡でももちろん受け付けておりますが、なかなか気がつかない場合もございますので、ツイッターの方へいただけますと幸いです。
Twitter ID:@Satui_Muki(現在鍵付きになっていますが、基本的にリクエストは全て通しています)
15 / 30
202 PS
チナミ区
N-9
N-9





































初心者マークついてます
4
侵略対策・戦術勉強会
7
#交流歓迎
3
悦乱♥イヤラシティ
7
ログまとめられフリーの会
1
【うちの子】貸し借りOKコミュ
6
コミュ・首吊り
5
両陣営の和平を真面目に考える会
17



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 論理武装:結論 | 武器 | 20 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | determination | 防具 | 17 | 防御10 | - | - | |
| 6 | おくすりのめたか? | 料理 | 23 | 器用10 | 敏捷10 | - | |
| 7 | おふくろの味 | 料理 | 23 | 器用10 | 敏捷10 | - | |
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | 松 | 素材 | 15 | [武器]器用10(LV15)[防具]応報10(LV25)[装飾]耐地10(LV20) | |||
| 10 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]列撃10(LV25)[防具]舞反10(LV25)[装飾]幸運10(LV10) | |||
| 11 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]凍結10(LV20)[防具]反盲10(LV25)[装飾]防御15(LV25) | |||
| 12 | 何かの骨 | 素材 | 20 | [武器]闇撃10(LV25)[防具]活力15(LV30)[装飾]強靭10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 10 | 武器作製に影響 |
| 防具 | 8 | 防具作製に影響 |
| 付加 | 3 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 14 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 胸を一突き (ブレイク) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ブラッディ・メアリ (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| デウス・エクス・マキナ (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ガラスの棺桶 (ヒール) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| determination (ドレイン) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| allegiance (ペネトレイト) | 6 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| Chiaroscuro (クリーンヒット) | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| UNLIMITED (フィジカルブースター) | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| determination (ファゾム) | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| カタルシス (ディベスト) | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 完璧な配役 (猛攻) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 隙のない脚本 (堅守) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 『むかしむかし』 (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 脚光 (太陽) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 |
最大EP[20]



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / メル