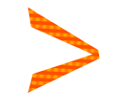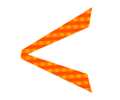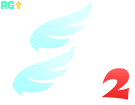<< 1:00~2:00




どうやらハザマには想像以上に多くの人間――もちろんヒトならざる者も――が入り込んでいるようだ。
それは老若男女問わず様々で……俺が合流できたのは皆学生だ。
勝手知ったる仲、とまでは行かなくとも同年代であるというのはやりやすいに違いなかった。
ひとまず次のチェックポイントへ向かうため進行したのだが、そう簡単にはいかない。
また現れた化け物達を退けて一息を吐いた。完璧な連携とはいかないが初戦でこれだけうまく戦えるのならこれからの過剰な心配は必要なさそうだと感じた。
そして戦闘を挟み、休憩が必要だろうと足を止めている所だ。
本当に危惧すべきは化け物ではなく、侵略者達なのだ。実際に遭遇するかはさておき、知り合いがもしかすると敵(アンジニティ)なのかもしれないと考えなくてはならない。
これだけは避けられない。
目を背けられない。
背けてはいけない。
嫌だった。
それでも。
その時が来るまでに向き合っておきたかった。
なし崩しに終わってしまうのはもっと嫌だ。
* * *
風の音はもうしない。
こんなことも日常的にあった。
あったはずだ。
今はもう、無かったことになっているけれど。
私は今でも覚えている。あの土の匂いも、陽射しの暖かさも、引かれた手の感触も。
……どうにも感傷的になっていけない。
次の欠片を探し出して手に取る。
うっすらと見えるこの景色は馴染みのある家。
いったい今はどうなってるんだろうか――
*『みっつめ』*
自分が裁縫をするようになったのは何時からだっただろうか。
自分の部屋。昼下がりの空を手慰みに糸を弄りながらぼんやりと眺めている。
もうはっきりと覚えてはいない。きっと物心つく前から触れていたのだろう。
うちはそういう家なのだから。
父親は特に意識をしていただろうし、外から入ってきた母親もきっと同じように考えていたに違いない。
強要こそされなかったが、日常的に我が身を囲んでいたのだからその道に興味を示すのは自然なことだった。
ぴんぽーん
チャイムが鳴る。彼女だ。
糸から手を放し玄関へと向かう。
それこそ彼女の存在も、自分にとっては自然なものだった。
生まれたときから傍に居て、何をするにも一緒だった。
親は当然違う。親戚でもない。しかし、近所で親の仲が良いというだけで子どもが一緒の居る理由としては十分だった。
扉を開けるとそこにはやはり、想像通りの姿がある。
いつものように彼女を自分の部屋まで連れていく。
これまたいつものように、付いてくるその手には縫いぐるみが抱きしめられている。

彼女はかわいいものが好きだった。縫いぐるみもその例に漏れない。
だからよく、これをつくってあれをつくってとお願いされた。
そう。本格的に裁縫を始めたきっかけも彼女だった。
初めて作品として完成したのは巾着袋。不格好でとても人に渡せるものでは無かったのだが、彼女はそれを欲しいと言い、しぶしぶプレゼントすると笑顔で喜んでくれた。
その時にきっと自分は誰かのために作る事の楽しさを知ったのだと思う。
なんとなく、手慰みに作るものがかわいくなるのも、その所為なのだ。
別に作るもの全てを贈るつもりは無いのに。そうしてしまう理由だけは分からなかった。
部屋に入れてからお茶を出す。
他人の部屋ながらまるで自分の部屋の様にくつろぐ彼女に文句をいう努力はとっくの昔に諦めている。
ぶつぶつと口をとがらせて文句を言う彼女を無視して縫いぐるみを回して見る。
1、2、3……パッと見えたところ以外にもまだ修理箇所はあるようだ。
これもやはり、よくある事だった。
一針、二針、針を入れるたびに
――ノイズが視界を覆っていった。



ENo.1268 めぇこ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ガガミネ(181) に ItemNo.10 甲殻 を手渡ししました。
杏里(978) から 羽 を手渡しされました。
ItemNo.6 謎のミックスジュース を食べました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









呪術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ガガミネ(181) により ItemNo.10 羽 から防具『風守羽』を作製してもらいました!
⇒ 風守羽/防具:強さ40/[効果1]風柳10 [効果2]- [効果3]-
杏里(978) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『緑色のガラス片』を作製しました!
牡丹(433) により ItemNo.9 ねばねば から射程1の武器『縛り糸』を作製してもらいました!
⇒ 縛り糸/武器:強さ40/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
杏里(978) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『うろおぼえのたこ焼き』をつくってもらいました!
⇒ うろおぼえのたこ焼き/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
イナバ(178) とカードを交換しました!
光芒一閃 (ハードブレイク)

ブロック を研究しました!(深度0⇒1)
タッチダウンライズ を研究しました!(深度1⇒2)
ファゾム を研究しました!(深度1⇒2)
ガードフォーム を習得!
アジャイルフォーム を習得!
ファゾム を習得!
ブロック を習得!
アドバースウィンド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





ガガミネ(181) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- 牡丹(433) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



どうやらハザマには想像以上に多くの人間――もちろんヒトならざる者も――が入り込んでいるようだ。
それは老若男女問わず様々で……俺が合流できたのは皆学生だ。
勝手知ったる仲、とまでは行かなくとも同年代であるというのはやりやすいに違いなかった。
ひとまず次のチェックポイントへ向かうため進行したのだが、そう簡単にはいかない。
また現れた化け物達を退けて一息を吐いた。完璧な連携とはいかないが初戦でこれだけうまく戦えるのならこれからの過剰な心配は必要なさそうだと感じた。
そして戦闘を挟み、休憩が必要だろうと足を止めている所だ。
 |
透司 「こんな時だけどやっぱり頼りなるのは仲間だ。いやー運が良かった」 |
| 透司 「この調子なら心配も……無いわけないよなぁ」 |
本当に危惧すべきは化け物ではなく、侵略者達なのだ。実際に遭遇するかはさておき、知り合いがもしかすると敵(アンジニティ)なのかもしれないと考えなくてはならない。
これだけは避けられない。
目を背けられない。
背けてはいけない。
嫌だった。
それでも。
| 透司 「世界も時間も、待ってはくれない」 |
その時が来るまでに向き合っておきたかった。
なし崩しに終わってしまうのはもっと嫌だ。
* * *
風の音はもうしない。
こんなことも日常的にあった。
あったはずだ。
今はもう、無かったことになっているけれど。
私は今でも覚えている。あの土の匂いも、陽射しの暖かさも、引かれた手の感触も。
……どうにも感傷的になっていけない。
次の欠片を探し出して手に取る。
うっすらと見えるこの景色は馴染みのある家。
いったい今はどうなってるんだろうか――
*『みっつめ』*
自分が裁縫をするようになったのは何時からだっただろうか。
自分の部屋。昼下がりの空を手慰みに糸を弄りながらぼんやりと眺めている。
もうはっきりと覚えてはいない。きっと物心つく前から触れていたのだろう。
うちはそういう家なのだから。
父親は特に意識をしていただろうし、外から入ってきた母親もきっと同じように考えていたに違いない。
強要こそされなかったが、日常的に我が身を囲んでいたのだからその道に興味を示すのは自然なことだった。
ぴんぽーん
チャイムが鳴る。彼女だ。
糸から手を放し玄関へと向かう。
それこそ彼女の存在も、自分にとっては自然なものだった。
生まれたときから傍に居て、何をするにも一緒だった。
親は当然違う。親戚でもない。しかし、近所で親の仲が良いというだけで子どもが一緒の居る理由としては十分だった。
扉を開けるとそこにはやはり、想像通りの姿がある。
 |
少女 「えへ、来ても大丈夫だった?」 |
 |
とうじ 「来てから聞くなよ……ほら、上がって」 |
いつものように彼女を自分の部屋まで連れていく。
これまたいつものように、付いてくるその手には縫いぐるみが抱きしめられている。

彼女はかわいいものが好きだった。縫いぐるみもその例に漏れない。
だからよく、これをつくってあれをつくってとお願いされた。
そう。本格的に裁縫を始めたきっかけも彼女だった。
初めて作品として完成したのは巾着袋。不格好でとても人に渡せるものでは無かったのだが、彼女はそれを欲しいと言い、しぶしぶプレゼントすると笑顔で喜んでくれた。
その時にきっと自分は誰かのために作る事の楽しさを知ったのだと思う。
なんとなく、手慰みに作るものがかわいくなるのも、その所為なのだ。
別に作るもの全てを贈るつもりは無いのに。そうしてしまう理由だけは分からなかった。
部屋に入れてからお茶を出す。
他人の部屋ながらまるで自分の部屋の様にくつろぐ彼女に文句をいう努力はとっくの昔に諦めている。
 |
とうじ 「で?今日は何の用?」 |
 |
少女 「別にないよー。暇だったから、かな」 |
 |
とうじ 「あのな……いつも言ってるだろ。お前他に行くとことかやる事とか無いのかよ?」 |
 |
少女 「んーと。逆に聞くけどあると思う?」 |
 |
とうじ 「はぁ。もういいや。別に困っても無いし……」 |
 |
少女 「それこそとうじだって私以外に誰かいるの?」 |
 |
とうじ 「……よく見たらその縫いぐるみまたほつれてるから直すよ」 |
 |
少女 「あっ!誤魔化したな!」 |
 |
とうじ 「うるさーい。ほら、早く貸せって」 |
ぶつぶつと口をとがらせて文句を言う彼女を無視して縫いぐるみを回して見る。
1、2、3……パッと見えたところ以外にもまだ修理箇所はあるようだ。
これもやはり、よくある事だった。
一針、二針、針を入れるたびに
――ノイズが視界を覆っていった。



ENo.1268 めぇこ とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ガガミネ 「ここの生き物、だいぶんヘンナノいるネ……」 |
| 牡丹 「街で会った他のみんなは大丈夫かなぁ?」 |
| 杏里 「ネバネバゾンビがねばねばしてるよぉー、ぼくもうかえる~」 |
ガガミネ(181) に ItemNo.10 甲殻 を手渡ししました。
杏里(978) から 羽 を手渡しされました。
| 杏里 「トウジセンパイ、これあげる~。制服のポケットに挿しとくとかわいーよ!」 |
ItemNo.6 謎のミックスジュース を食べました!
 |
透司 「これはなんとも不思議な味わいがミックスされてるな」 |
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





放課後駄弁り隊
|
 |
スーサイド・スクワッド
|



呪術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ガガミネ(181) により ItemNo.10 羽 から防具『風守羽』を作製してもらいました!
⇒ 風守羽/防具:強さ40/[効果1]風柳10 [効果2]- [効果3]-
 |
ガガミネ 「羽毛のアームカバー?みたいな感じデス。」 |
杏里(978) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『緑色のガラス片』を作製しました!
牡丹(433) により ItemNo.9 ねばねば から射程1の武器『縛り糸』を作製してもらいました!
⇒ 縛り糸/武器:強さ40/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
杏里(978) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『うろおぼえのたこ焼き』をつくってもらいました!
⇒ うろおぼえのたこ焼き/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
| 杏里 「たしかタコは入ってて……あと赤いやつ……あとソースついてた!」 |
イナバ(178) とカードを交換しました!
光芒一閃 (ハードブレイク)

ブロック を研究しました!(深度0⇒1)
タッチダウンライズ を研究しました!(深度1⇒2)
ファゾム を研究しました!(深度1⇒2)
ガードフォーム を習得!
アジャイルフォーム を習得!
ファゾム を習得!
ブロック を習得!
アドバースウィンド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





ガガミネ(181) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- 牡丹(433) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







放課後駄弁り隊
|
 |
はぐれPPP
|


ENo.304
糸尾透司



糸尾 透司(いとお とうじ)
相良伊橋高校 2年生
11月生まれ
身長170 cmくらい。
好きなものは裁縫と甘いもの。
嫌いなものは針の通らない素材と針穴に糸が通らないこと。
ざっくりした性格。真面目な話もどこか軽く流すくらいには。
人づきあいが嫌いなわけでもなく、得意の裁縫で頼まれものを直したりすることも。
異能は『物や生き物をあらゆる場所に糸の如く通す』能力。
糸を通した針を持ち歩き、対象物に縫い付けてから意識を向けた先に障害物の有無にかかわらず”通過”させる。おそらく空間操作に関わる異能であると考えられる。
術者から離れたものや同時に複数のものは対象にとれない。
基本的に攻撃性はあまり無く、本人がトラブルや危険を避けるために用いる。
連絡先
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3188
自宅:イバラタワーカスミ
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3404
-----------------------------------
既知設定ご自由に。ネタ・シリアスロールなんかも大丈夫です。お気軽に構ってくださると嬉しいです。
置きレス気味でレス遅めです。ご了承ください。
相良伊橋高校 2年生
11月生まれ
身長170 cmくらい。
好きなものは裁縫と甘いもの。
嫌いなものは針の通らない素材と針穴に糸が通らないこと。
ざっくりした性格。真面目な話もどこか軽く流すくらいには。
人づきあいが嫌いなわけでもなく、得意の裁縫で頼まれものを直したりすることも。
異能は『物や生き物をあらゆる場所に糸の如く通す』能力。
糸を通した針を持ち歩き、対象物に縫い付けてから意識を向けた先に障害物の有無にかかわらず”通過”させる。おそらく空間操作に関わる異能であると考えられる。
術者から離れたものや同時に複数のものは対象にとれない。
基本的に攻撃性はあまり無く、本人がトラブルや危険を避けるために用いる。
連絡先
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3188
自宅:イバラタワーカスミ
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3404
-----------------------------------
既知設定ご自由に。ネタ・シリアスロールなんかも大丈夫です。お気軽に構ってくださると嬉しいです。
置きレス気味でレス遅めです。ご了承ください。
16 / 30
67 PS
チナミ区
I-16
I-16

































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 骨牙脚甲 | 防具 | 35 | 活力10 | - | - | |
| 5 | お守り | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 7 | うろおぼえのたこ焼き | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]列撃10(LV25)[防具]舞反10(LV25)[装飾]幸運10(LV10) | |||
| 9 | 縛り糸 | 武器 | 40 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 10 | 風守羽 | 防具 | 40 | 風柳10 | - | - | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 15 | 空間/時間/風 |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 装飾 | 30 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カットストリング (ウィンドカッター) | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| 糸導 (プリディクション) | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| イービルカード | 5 | 0 | 50 | 敵:風撃&名前に「纏」を含む付加効果があれば、1つ消滅させて闇撃化(1T) | |
| アジャイルフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:AG増 | |
| 二重糸 (タッチダウンライズ) | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+HP減+連続増 | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
| 絡まり糸 (アゲンスト) | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| アドバースウィンド | 5 | 0 | 70 | 自:隊列後退+LK増(2T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 糸紡ぎ (風の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]プリディクション | [ 2 ]タッチダウンライズ | [ 2 ]ファゾム |
| [ 1 ]ブロック |

PL / 辻風