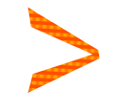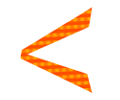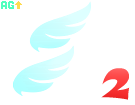<< 0:00~0:00




最初の記憶は水の音。
暗い、闇い、何も何も、見えない世界で。

水の音が、水泡の音が、こぽりこぽりと小さく届く。
真っ暗で、何も見えなくて、けれども暖かいその場所が子らは○○○だった。
光が灯る事無く、子らは消えて逝ってしまったけど。
そんな事が何千、何万と繰り返されて、気付けば世界の、宇宙の何処かで小さな小さな虚になった。
針の先の如く、まるで風穴のように。
何にもなれず、望まれず、育まれず。
子らはそういうもの同士で惹き合い、喰らい合い、気付けば虚は大きくなる。
虚はどんなものでも落としていく。
空っぽである事を空っぽだと認識できる程度の、微かな自我のようなものはあったのかもしれない。
だから、手を伸ばすのは、虚の本能だ。
それが似たようなものであっても、何かを持っていたとしても、手が伸びてしまう。
喰らおうと。
――手に入れようと。
虚に何を入れても虚でしか無くなるのに。
うつろで虚しい行為は続いていく。
・
・
・

「――――――」
意識が浮上した。
小さな無数の鍵と、懐中時計と、カチンという無機質な音を鳴らす翅。
水の音と共に、翅以外のものを内包した何かがそこに生まれる。
夢を、見ていた気がする。
長い夢だ。意識なく望んでいた夢だ。
だが夢からは覚めるもの。
夢は消えるもの。
泡沫のように。
だが、あの夢の世界も、手に入れてしまえば現になる。
あの女性が言っていたのは、つまりそういう事だと理解する。
生まれて、育って、友人を得て、恋をして。
なだれ込んでくる夢の記憶は、まるで、本当にこの手にあったかのようだ。
虹彩の煌めく瞳を閉じる。
夢で得た命は、人格は、記憶は、想いは。
――――現となってくれるのだろうか。
――――形あるものとして、自分は手に入れられるのだろうか。
「…………そらひ」
ソレから、音が零される。
こうして考えられるだけでも、きっと、きっと、少しだけでも。
手にできたのではないかと錯覚してしまう。
錯覚する。
――――――手に入れたと錯覚するその感覚さえ、きっと夢なのだ。
鍵と、時計と、水泡の音を立てながら。
からっぽは、ゆらりと動き出す。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
――――空菊の”姉”――――
・
・
・
辺りを見渡した。
息を飲んだ。
――視界に広がる様は、知っている街なのに全くしらない場所で。
手が震えた。足が震えた
告げられた事も、頭に入ってくるのに信じたくない思いが湧き上がる。
……それでも、この光景は、現実を叩きつけてくる。
怖いと、思った。
息を、飲んだ。
あぁきっと。以前の自分ならば、こんな風に恐れて震える事は無かったのだ。
いや、震える事は無くとも、意思を持って動けない自分は――
思わず息を飲んだ。
そんな”もしも”の方が、余程怖い。
大きく息を吸って、吐いてと繰り返す。
……空を見上げる。
まずは、確かめなければ。
自分を救ってくれた人が、――此処に来てしまっているのかを。



ENo.121 理外のチヨ子 とのやりとり

ENo.249 『小鷹裕吉』 とのやりとり

ENo.466 ■■の■■ とのやりとり

ENo.717 Qimranut とのやりとり

以下の相手に送信しました










お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『塩むすび』をつくりました!
⇒ 塩むすび/料理:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
ハイドリ(52) とカードを交換しました!
白き平穏の使徒 (ブラスト)

ストライク を習得!
エチュード を習得!
プリディクション を習得!
マーチ を習得!
フィジカルブースター を習得!
精神変調耐性 を習得!
ビブラート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 E-10(森林)に移動!(体調26⇒25)
独りぼっちの神父(199) をパーティに勧誘しました!
『小鷹裕吉』(249) をパーティに勧誘しました!
理外のチヨ子(121) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- 理外のチヨ子(121) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 独りぼっちの神父(199) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 『小鷹裕吉』(249) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
エディアンからのチャットが閉じられる――


















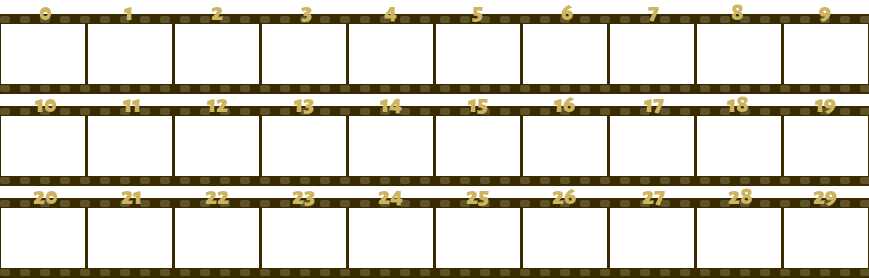





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



最初の記憶は水の音。
暗い、闇い、何も何も、見えない世界で。

水の音が、水泡の音が、こぽりこぽりと小さく届く。
真っ暗で、何も見えなくて、けれども暖かいその場所が子らは○○○だった。
光が灯る事無く、子らは消えて逝ってしまったけど。
そんな事が何千、何万と繰り返されて、気付けば世界の、宇宙の何処かで小さな小さな虚になった。
針の先の如く、まるで風穴のように。
何にもなれず、望まれず、育まれず。
子らはそういうもの同士で惹き合い、喰らい合い、気付けば虚は大きくなる。
虚はどんなものでも落としていく。
空っぽである事を空っぽだと認識できる程度の、微かな自我のようなものはあったのかもしれない。
だから、手を伸ばすのは、虚の本能だ。
それが似たようなものであっても、何かを持っていたとしても、手が伸びてしまう。
喰らおうと。
――手に入れようと。
虚に何を入れても虚でしか無くなるのに。
うつろで虚しい行為は続いていく。
・
・
・

「――――――」
意識が浮上した。
小さな無数の鍵と、懐中時計と、カチンという無機質な音を鳴らす翅。
水の音と共に、翅以外のものを内包した何かがそこに生まれる。
夢を、見ていた気がする。
長い夢だ。意識なく望んでいた夢だ。
だが夢からは覚めるもの。
夢は消えるもの。
泡沫のように。
だが、あの夢の世界も、手に入れてしまえば現になる。
あの女性が言っていたのは、つまりそういう事だと理解する。
生まれて、育って、友人を得て、恋をして。
なだれ込んでくる夢の記憶は、まるで、本当にこの手にあったかのようだ。
虹彩の煌めく瞳を閉じる。
夢で得た命は、人格は、記憶は、想いは。
――――現となってくれるのだろうか。
――――形あるものとして、自分は手に入れられるのだろうか。
「…………そらひ」
ソレから、音が零される。
こうして考えられるだけでも、きっと、きっと、少しだけでも。
手にできたのではないかと錯覚してしまう。
錯覚する。
――――――手に入れたと錯覚するその感覚さえ、きっと夢なのだ。
鍵と、時計と、水泡の音を立てながら。
からっぽは、ゆらりと動き出す。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
――――空菊の”姉”――――
・
・
・
辺りを見渡した。
息を飲んだ。
――視界に広がる様は、知っている街なのに全くしらない場所で。
手が震えた。足が震えた
告げられた事も、頭に入ってくるのに信じたくない思いが湧き上がる。
……それでも、この光景は、現実を叩きつけてくる。
怖いと、思った。
息を、飲んだ。
あぁきっと。以前の自分ならば、こんな風に恐れて震える事は無かったのだ。
いや、震える事は無くとも、意思を持って動けない自分は――
思わず息を飲んだ。
そんな”もしも”の方が、余程怖い。
大きく息を吸って、吐いてと繰り返す。
……空を見上げる。
まずは、確かめなければ。
自分を救ってくれた人が、――此処に来てしまっているのかを。



ENo.121 理外のチヨ子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.249 『小鷹裕吉』 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.466 ■■の■■ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.717 Qimranut とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
***** 「――――……」 |





お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『塩むすび』をつくりました!
⇒ 塩むすび/料理:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
 |
にぎにぎ。 |
ハイドリ(52) とカードを交換しました!
白き平穏の使徒 (ブラスト)

ストライク を習得!
エチュード を習得!
プリディクション を習得!
マーチ を習得!
フィジカルブースター を習得!
精神変調耐性 を習得!
ビブラート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「・・・はい到着ぅ。気をつけて行きな。」 |
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 E-10(森林)に移動!(体調26⇒25)
独りぼっちの神父(199) をパーティに勧誘しました!
『小鷹裕吉』(249) をパーティに勧誘しました!
理外のチヨ子(121) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- 理外のチヨ子(121) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 独りぼっちの神父(199) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 『小鷹裕吉』(249) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「1時間が経過しましたね。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャットで時間が伝えられる。
 |
エディアン 「ナレハテとの戦闘、お疲れ様でした! 相手を戦闘不能にすればいいようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「さてさて。皆さんにご紹介したい方がいるんです。 ――はい、こちらです!こちらでーっす!!」 |
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
エディアン 「陣営に関わらず連れて行ってくれるようですのでどんどん利用しましょー!! ドライバーさんは中立ってことですよね?」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
エディアン 「たくさん・・・同じ顔がいっぱいいるんですかねぇ・・・。 ここはまだ、分からないことだらけです。」 |
 |
エディアン 「それでは再びの1時間、頑張りましょう! 新情報を得たらご連絡しますね。ファイトー!!オーッ!!」 |
エディアンからのチャットが閉じられる――







スイーツ★インベーダー
|
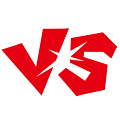 |
TeamNo.202
|


ENo.119
蝦夷森 空菊



「僕は大好きな人と、人たちと、楽しく過ごせたらそれでいいや」
『あぁ、でも、でもね。彼と親しくしようなんて、思わないでね?』
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Main -
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆名前
蝦夷森 空菊(えぞもり そらひ)
-愛称:そら
◆性別
女(男装)
-男として入学しちゃったりしてる。何やかんやして。
◆年齢
15歳
◆身長
166cm
-細め
◆連絡先
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2392
(個人IBALINE。既知設定可能)
◆好き/嫌い
幼馴染2人、とある小説家の本、甘い甘いお菓子
/好きな人に親しげに近付く子、***** *****
◆色々
黒く長い髪を、後ろで橙色のリボンで緩く結んでいる。
目は濃い青――の中に、緑や橙色、水色黄色等、虹彩が鮮やかに煌めく。
掌途中までの黒い手袋は常につけているもの。
銀の懐中時計をいつも持ち歩いている。
物腰柔らかで、気さく。
柔和な雰囲気と、中性的ながら割とそこそこの顔立ちの為か
男装しているが故かそこそこモテるっぽい。
(モブ生徒にモテる描写をたまにするかもしれない(えっ))
――――今現在、ずーっとずーっと片想いをしている相手を追いかけている。
それはそれは、病的なまでに。心から愛しているのである。
→綿貫 黒衣さん(ENo.199)ととても親しくする方に、危害を加えようとしたり異能を使おうとする傾向があります。
友達くらいなら大丈夫。危なくないちょっかいは出すかもしれない。
◆異能 -門と鍵-
心や感情、記憶そのものを鍵で封じるか、門にして入るか、弄る事ができる。
なお、彼女はこの異能を一部の人以外には【記憶を少しの間忘れてもらう】事と話している。
-鍵
主に「封ずる」為に使われる。素手を身体の何処かに突っ込む必要がある。
胸に近ければ近い程、鍵にする速度が上がる。
封じたものに合わせた色合いの鍵が作られ、
それを再び胸に差す時まで思い出したり、その心、感情を持ち合わせる事はない。
(なお、差しても痛くない。安心)
また、対象の「封じられた瞬間』の前後の記憶は、やや曖昧になる。
補足をただ言葉で告げられるだけで、それを信じてしまう程には。
行使している瞬間は、対象の時が止まる。
ただし胸から離れている程、その拘束は緩やか。
(例:意識がある、手足の何処かが動かせる、弱まるが異能が使える等)
-門
主に「入り込む」「弄る」為に使われる。
門にすると意識して相手へ触れた時、金の鍵を生成し、門を開く。
門は実行者とそれの所持者の間で実体化し、
開いたものに合わせた色合い、質感となっている。
開いたり、中に入れば覗く事ができ、
意識すれば自由に書き換えたりする事も可能。
(書き換えを行う場合はPL様にご相談をかけたりします)
弄る量が多かったり、入り込む時間が長い程、
対象は吐き気を覚えたり気持ち悪くなったり、
頭がぐらぐらしたりする。
-彼女は 侵略する者である-
◆異形
その姿は――――― *****
彼女は何も持っていない。
何を持つこともない。
持たざる者はそこにいられなかった。
望まれなかった子らはいられなかった。
空(から)にして空ろ(うつろ)は、ただ、淡々と。
流れるままに存在する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Sub -
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆名前
蝦夷森 菊璃(えぞもり きくり)
◆性別
女
◆年齢
22歳
◆身長
154cm
-軽い
◆好き/嫌い
現在、それをうかがい知ることができない
◆色々
黒い髪を下に2つに結び、光のない紫色の瞳は長い前髪で隠れている。
【東雲探偵事務所】SpotNo.345で、探偵と共に暮らしている。
幼い頃の記憶がなく、また日がな一日ぼんやりと部屋で過ごしており、たまに声は発するものの、自発的な行動を行わない。
-彼女は空菊の姉であり、また、彼女の異能により
【記憶】と【感情/心】を鍵とされ封じられている。
幼い彼女がなかば廃人で街中にいたところを、
件の探偵の家族に拾われ、今に至る。
記憶や知識は積み重ねられているものの、
揺り動かされる心や感情を再度芽生えさせるには、
空菊の持つ【鍵】が必要である。
――――しかし、
空菊は両親と姉の記憶を持ち合わせていない。
◆異能 -次元の鏡-
硝子や水、鏡など、何かを映すものを使って
【世界さえ異なる】場所を覗くことができる。
次元、時空、世界を超えたその異能は、
場所や時間を問わず【覗き鏡】を作り上げる。
上手く使えば何かの助けになるかもしれない。
――――それこそ、ハザマであったり、
またはアンジニティの――――
もう一つ、彼女たちは異能らしきものを持っている。
だがその行使には、とある道具が必要のようだ。
そしてそれを使えることを、彼女たちは知らない。
-何れにせよ、現在の彼女が異能を扱うのは難しい。
ふとした拍子に、使ってしまうこともあるかもしれないが。
◆PL
何でもフリー。ギャグほのぼのメタ戦闘不穏シリアスなんでもござれ。
メインは何かモテてる設定ありますが、勿論モブ対象なのでご安心ください。
そのうちファンクラブとかできないだろうか(できません)
あと綿貫 黒衣さん(ENo.199)へのヤンデレっぷりがなかなか畜生レベルで酷いので、その関係で不穏し始める事もあります。
ゴメンナサイゴメンナサイ。でも仲良くしよう。したいです。
既知設定等もお気軽に。
ご相談も可能!
置きレスになることもあります。
-まだまだ設定途中!-
雑多垢
@Zetsier_SoLA
『あぁ、でも、でもね。彼と親しくしようなんて、思わないでね?』
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Main -
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆名前
蝦夷森 空菊(えぞもり そらひ)
-愛称:そら
◆性別
女(男装)
-男として入学しちゃったりしてる。何やかんやして。
◆年齢
15歳
◆身長
166cm
-細め
◆連絡先
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2392
(個人IBALINE。既知設定可能)
◆好き/嫌い
幼馴染2人、とある小説家の本、甘い甘いお菓子
/好きな人に親しげに近付く子、***** *****
◆色々
黒く長い髪を、後ろで橙色のリボンで緩く結んでいる。
目は濃い青――の中に、緑や橙色、水色黄色等、虹彩が鮮やかに煌めく。
掌途中までの黒い手袋は常につけているもの。
銀の懐中時計をいつも持ち歩いている。
物腰柔らかで、気さく。
柔和な雰囲気と、中性的ながら割とそこそこの顔立ちの為か
男装しているが故かそこそこモテるっぽい。
(モブ生徒にモテる描写をたまにするかもしれない(えっ))
――――今現在、ずーっとずーっと片想いをしている相手を追いかけている。
それはそれは、病的なまでに。心から愛しているのである。
→綿貫 黒衣さん(ENo.199)ととても親しくする方に、危害を加えようとしたり異能を使おうとする傾向があります。
友達くらいなら大丈夫。危なくないちょっかいは出すかもしれない。
◆異能 -門と鍵-
心や感情、記憶そのものを鍵で封じるか、門にして入るか、弄る事ができる。
なお、彼女はこの異能を一部の人以外には【記憶を少しの間忘れてもらう】事と話している。
-鍵
主に「封ずる」為に使われる。素手を身体の何処かに突っ込む必要がある。
胸に近ければ近い程、鍵にする速度が上がる。
封じたものに合わせた色合いの鍵が作られ、
それを再び胸に差す時まで思い出したり、その心、感情を持ち合わせる事はない。
(なお、差しても痛くない。安心)
また、対象の「封じられた瞬間』の前後の記憶は、やや曖昧になる。
補足をただ言葉で告げられるだけで、それを信じてしまう程には。
行使している瞬間は、対象の時が止まる。
ただし胸から離れている程、その拘束は緩やか。
(例:意識がある、手足の何処かが動かせる、弱まるが異能が使える等)
-門
主に「入り込む」「弄る」為に使われる。
門にすると意識して相手へ触れた時、金の鍵を生成し、門を開く。
門は実行者とそれの所持者の間で実体化し、
開いたものに合わせた色合い、質感となっている。
開いたり、中に入れば覗く事ができ、
意識すれば自由に書き換えたりする事も可能。
(書き換えを行う場合はPL様にご相談をかけたりします)
弄る量が多かったり、入り込む時間が長い程、
対象は吐き気を覚えたり気持ち悪くなったり、
頭がぐらぐらしたりする。
-彼女は 侵略する者である-
◆異形
その姿は――――― *****
彼女は何も持っていない。
何を持つこともない。
持たざる者はそこにいられなかった。
望まれなかった子らはいられなかった。
空(から)にして空ろ(うつろ)は、ただ、淡々と。
流れるままに存在する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Sub -
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆名前
蝦夷森 菊璃(えぞもり きくり)
◆性別
女
◆年齢
22歳
◆身長
154cm
-軽い
◆好き/嫌い
現在、それをうかがい知ることができない
◆色々
黒い髪を下に2つに結び、光のない紫色の瞳は長い前髪で隠れている。
【東雲探偵事務所】SpotNo.345で、探偵と共に暮らしている。
幼い頃の記憶がなく、また日がな一日ぼんやりと部屋で過ごしており、たまに声は発するものの、自発的な行動を行わない。
-彼女は空菊の姉であり、また、彼女の異能により
【記憶】と【感情/心】を鍵とされ封じられている。
幼い彼女がなかば廃人で街中にいたところを、
件の探偵の家族に拾われ、今に至る。
記憶や知識は積み重ねられているものの、
揺り動かされる心や感情を再度芽生えさせるには、
空菊の持つ【鍵】が必要である。
――――しかし、
空菊は両親と姉の記憶を持ち合わせていない。
◆異能 -次元の鏡-
硝子や水、鏡など、何かを映すものを使って
【世界さえ異なる】場所を覗くことができる。
次元、時空、世界を超えたその異能は、
場所や時間を問わず【覗き鏡】を作り上げる。
上手く使えば何かの助けになるかもしれない。
――――それこそ、ハザマであったり、
またはアンジニティの――――
もう一つ、彼女たちは異能らしきものを持っている。
だがその行使には、とある道具が必要のようだ。
そしてそれを使えることを、彼女たちは知らない。
-何れにせよ、現在の彼女が異能を扱うのは難しい。
ふとした拍子に、使ってしまうこともあるかもしれないが。
◆PL
何でもフリー。ギャグほのぼのメタ戦闘不穏シリアスなんでもござれ。
メインは何かモテてる設定ありますが、勿論モブ対象なのでご安心ください。
そのうちファンクラブとかできないだろうか(できません)
あと綿貫 黒衣さん(ENo.199)へのヤンデレっぷりがなかなか畜生レベルで酷いので、その関係で不穏し始める事もあります。
ゴメンナサイゴメンナサイ。でも仲良くしよう。したいです。
既知設定等もお気軽に。
ご相談も可能!
置きレスになることもあります。
-まだまだ設定途中!-
雑多垢
@Zetsier_SoLA
25 / 30
5 PS
チナミ区
E-10
E-10





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 塩むすび | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 20 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / ねこ