<< 5:00




「疲れは取れたはずなのに、どうして体が重いのかしら」
「体の調子は悪くない。むしろ良い方だわ。
でも、どこか体が重い」
「力を使うのに疲れた?」
「そんなことはない、と思う」
「逆に慣れてきた気がするもの」
「あの丸いへんな生き物……生き物?とも戦えたもの」
「気持ちのせいかしら」
「気のせいね、きっと」
「でも、ああ、なんだか喉が渇いたわ」
「水は十分に飲んでいるはずなのに」
「力を振るうごとに、立ちはだかる何かを焼くごとに」
「喉が渇いていく気がする」
「気のせいよね、きっと」
「気のせいだわ」
「ごんならこういうとき、自動販売機にでもいくのかしら」
「あの子、自動販売機すきだものねえ。
よく、桜を見ながらお茶やジュースを飲んでるものね」
「ひよこと遊んだりもしているけど……」
「ああ、喉が渇く」
「暑いわけじゃないのに」
「息を吸う、くらいなら問題がない」
「でも、どこか焼けているような気がする」
「ごんが頭痛のことを調べようとしているわね」
「ごんひとりではどうにもならないはずだけれど……」
「いとはさんにだって、どうしようもないはずだけれど……」
「どうにもならない、のよね?」
「イバラシティにいるごんは、私とは違う。
私そのものじゃない」
「記憶だって、私とはつながらないようになっているはず。
だって、私がごんに私のことを思い出してほしいとは思っていないのだもの」
「いとはさんと話すことで、ごんは自分一人なら思い出すことのない部分に触れそうになっている」
「でも、いとはさんのおかげで、無理に思い出さなくてもいい、とも思ってくれたみたい」
「緊張はしたけれど、でも、いとはさんに感謝しないといけないわね」
「ごんがほんとうに私のことを思い出してほしくないのなら」
「イバラシティにいる『ごん』が、私と同じ顔である必要はなかった」
「そもそも、『ごん』である必要だってなかった」
「ううん、『ごん』である必要は、ある」
「私にとって、一番よく知っている他人は、ごんだったんだもの」
「家族では、だめだった」
「お父さんも、お母さんも、おじいさまもおばあさまも好きだけれど、あのひとたちになりたいわけじゃなかった」
「だってあのひとは、私とつながっているんだもの」
「だから、他人になりたかった。
消えることができないなら、他人になりたかった」
「だから、『ごん』にならなければいけなかった」
「でも、だとしたら、『ごん』が私と同じ顔である必要はない」
「私とまったく関係のない顔で、あのイバラシティで生活していてもよかった」
「たしかに、たしかにね。
ほんとうのごんは、私に化けてくれるって言ったわ」
「私は死んでしまうけれど、私の代わりに、私の姿で、友達を作ってくれるって」
「私の姿で友達を作って、私のことをその友達に話してくれれば、私が死んだ後も、その友達の中に私が生き続けることができるからって」
「ごんの気持ちがうれしかった」
「うれしかったのよ。ほんとうに」
「ほんとうなの」
「うれしかったんだから」
「だから……そのうれしさがあったから、イバラシティにいる『ごん』も、私と同じ姿をしている」
「ほんとうに?」
「……ほんとうよ」
「ほんとうに?」
「……」
「わからない」
「違うのかもしれない」
「こんなに消えたいと思っているのに、その思いは口だけなのかもしれない。
『私』をどこかに残しておきたいと、心のどこかで思っているのかもしれない」
「だとしたら……だとしたら、なんてずるいの、私」
「『ごん』に……あの子に自分のわがままを押し付けているだけだわ」
「いとはさんは、あの子が私のことを思い出せないのは、『守りたいから』とか、『二人だけの秘密にしたいからかもしれない』とか言ってくれたけれど、そんなすてきなものじゃないのかもしれない」
「ああ、神様。
どうか私の心をお読みにならないでください」
「私が、ほんとうに、ほんとうにずるいものであると、確かなものにしないでください」
「私は……」
「……」
「私の考えていることが、あの子に伝わらなくて、ほんとうによかった」
「押し花、私もすきだったわ」
「でも、少し嫌いだった」
「押し花はできあがるまで待たなければいけないから」
「2日、3日、待たなければいけない」
「待っている間に具合が悪くなって寝込んでしまうと、このまま出来上がりを見られずにしんでしまうんじゃないかと思ったから」
「でもね、早く作る方法も知ってたのよ。
電子レンジや、アイロンを使う方法」
「『ごん』には伝わっていないけれど――私がごんの前では言わなかったからだけど」
「アイロンは使わせてもらう機会がなかったけれど、電子レンジくらいは使えたから、それで押し花を作ることもできた」
「電子レンジを使えば、1時間もかからない内にできてしまうのだけれど、それはしなかった」
「兎乃おねえさんと私は似ている。
私もイバラシティでやりなおしたい」
「考えてみれば、私以外のひとがどうして侵略をしたいのかなんて、考えたことがなかった」
「考える余裕もなかった」
「ただ、侵略して、侵略して、侵略することだけを考えていたから」
「余裕ができたのは、いいことなのかしら」
「きっと、よくないことよね」
「侵略することだけ、戦うことだけ考えるのがほんとうはいい」
「だって、余裕ができてどうするの?
侵略するために私はここにいるのに」
「いるはずなのに」
「……」
「兎乃おねえさんと私、どこが違うのかしら」
「ううん、違うのはわかっているの」
「……」
「違うのかしら」
「違う、のよね」
「どこが違うのかしら」
「私は、私を消してしまいたい」
「こんなことを考えている私がいることが許せない」
「兎乃おねえさんは、そうじゃないってことかしら」
「『自分が汚れている』と思っている自分を消してしまいたいとは思わないのかしら」
「だって、そうじゃないと……」
「兎乃おねえさんの話が聞きたいわ」
「どうしてそう思えるようになったのか」
「それがわかれば……」
「いいえ、それがわかったところで……」
「だって……」
「でも……」
「押し花がね、できるまでは待てる気がしていたの」
「できるまでの間に寝込んでしまうことがあっても、今は押し花を作っているから、起き上がれたそのときには、押し花がちょうどできているんだと思えた」
「そういえば、最後のあのとき、私は押し花を作っていたのだったかしら」
「押し花……」
「作っていたような気もするし、作る元気もなかったような気もする」
「ごんは、旅に出る前に、私の部屋を見ていったかしら」
「私の部屋、今はどうなっているかしら」
「本と、折り紙と、あやとりと、びぃだまと、押し花と……」
「もう、何もなくなっているかしら」
「私がしんでしまってから、どれくらいの時間が経ったのかしら」
「押し花ができるくらいの時間は経ったのかしら」
「二人で作る押し花、楽しそうね」
「押し花で飾られた栞」
「あなたが初めて作るその栞、最初に挟まれるのはどんな本かしら」



ENo.643 ミハクサマ とのやりとり

ENo.733 ウミネコ とのやりとり

以下の相手に送信しました














アイリ(428) は ネジ を入手!
ナナキ(1016) は 不思議な牙 を入手!
黒髪の巫女(419) は 不思議な牙 を入手!
クレハ(675) は ネジ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
クレハ(675) のもとに 稲刈り機 が泣きながら近づいてきます。



れあち(415) とカードを交換しました!
願いのチーズケーキ (イバラ)


レッドインペイル を研究しました!(深度0⇒1)
フレイムレゾナンス を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)



次元タクシーに乗り『チナミ区 H-15:釣り堀』に転送されました!
チナミ区 H-16(森林)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 H-17(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-18(森林)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-19(森林)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 H-20(沼地)に移動!(体調26⇒25)
現在地が異なるためパーティが分かれました。再結成する必要があります。
採集はできませんでした。
- 黒髪の巫女(419) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- アイリ(428) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)





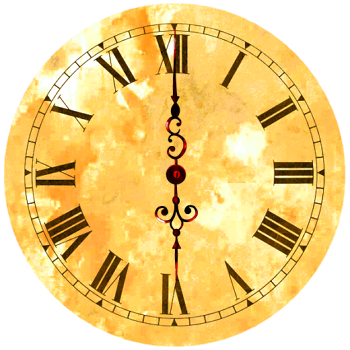
―― ハザマ時間が紡がれる。


ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
声は淡々と、話を続ける。
声はそこで終わる。
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK.



「疲れは取れたはずなのに、どうして体が重いのかしら」
「体の調子は悪くない。むしろ良い方だわ。
でも、どこか体が重い」
「力を使うのに疲れた?」
「そんなことはない、と思う」
「逆に慣れてきた気がするもの」
「あの丸いへんな生き物……生き物?とも戦えたもの」
「気持ちのせいかしら」
「気のせいね、きっと」
「でも、ああ、なんだか喉が渇いたわ」
「水は十分に飲んでいるはずなのに」
「力を振るうごとに、立ちはだかる何かを焼くごとに」
「喉が渇いていく気がする」
「気のせいよね、きっと」
「気のせいだわ」
「ごんならこういうとき、自動販売機にでもいくのかしら」
「あの子、自動販売機すきだものねえ。
よく、桜を見ながらお茶やジュースを飲んでるものね」
「ひよこと遊んだりもしているけど……」
「ああ、喉が渇く」
「暑いわけじゃないのに」
「息を吸う、くらいなら問題がない」
「でも、どこか焼けているような気がする」
「ごんが頭痛のことを調べようとしているわね」
「ごんひとりではどうにもならないはずだけれど……」
「いとはさんにだって、どうしようもないはずだけれど……」
「どうにもならない、のよね?」
「イバラシティにいるごんは、私とは違う。
私そのものじゃない」
「記憶だって、私とはつながらないようになっているはず。
だって、私がごんに私のことを思い出してほしいとは思っていないのだもの」
「いとはさんと話すことで、ごんは自分一人なら思い出すことのない部分に触れそうになっている」
「でも、いとはさんのおかげで、無理に思い出さなくてもいい、とも思ってくれたみたい」
「緊張はしたけれど、でも、いとはさんに感謝しないといけないわね」
「ごんがほんとうに私のことを思い出してほしくないのなら」
「イバラシティにいる『ごん』が、私と同じ顔である必要はなかった」
「そもそも、『ごん』である必要だってなかった」
「ううん、『ごん』である必要は、ある」
「私にとって、一番よく知っている他人は、ごんだったんだもの」
「家族では、だめだった」
「お父さんも、お母さんも、おじいさまもおばあさまも好きだけれど、あのひとたちになりたいわけじゃなかった」
「だってあのひとは、私とつながっているんだもの」
「だから、他人になりたかった。
消えることができないなら、他人になりたかった」
「だから、『ごん』にならなければいけなかった」
「でも、だとしたら、『ごん』が私と同じ顔である必要はない」
「私とまったく関係のない顔で、あのイバラシティで生活していてもよかった」
「たしかに、たしかにね。
ほんとうのごんは、私に化けてくれるって言ったわ」
「私は死んでしまうけれど、私の代わりに、私の姿で、友達を作ってくれるって」
「私の姿で友達を作って、私のことをその友達に話してくれれば、私が死んだ後も、その友達の中に私が生き続けることができるからって」
「ごんの気持ちがうれしかった」
「うれしかったのよ。ほんとうに」
「ほんとうなの」
「うれしかったんだから」
「だから……そのうれしさがあったから、イバラシティにいる『ごん』も、私と同じ姿をしている」
「ほんとうに?」
「……ほんとうよ」
「ほんとうに?」
「……」
「わからない」
「違うのかもしれない」
「こんなに消えたいと思っているのに、その思いは口だけなのかもしれない。
『私』をどこかに残しておきたいと、心のどこかで思っているのかもしれない」
「だとしたら……だとしたら、なんてずるいの、私」
「『ごん』に……あの子に自分のわがままを押し付けているだけだわ」
「いとはさんは、あの子が私のことを思い出せないのは、『守りたいから』とか、『二人だけの秘密にしたいからかもしれない』とか言ってくれたけれど、そんなすてきなものじゃないのかもしれない」
「ああ、神様。
どうか私の心をお読みにならないでください」
「私が、ほんとうに、ほんとうにずるいものであると、確かなものにしないでください」
「私は……」
「……」
「私の考えていることが、あの子に伝わらなくて、ほんとうによかった」
「押し花、私もすきだったわ」
「でも、少し嫌いだった」
「押し花はできあがるまで待たなければいけないから」
「2日、3日、待たなければいけない」
「待っている間に具合が悪くなって寝込んでしまうと、このまま出来上がりを見られずにしんでしまうんじゃないかと思ったから」
「でもね、早く作る方法も知ってたのよ。
電子レンジや、アイロンを使う方法」
「『ごん』には伝わっていないけれど――私がごんの前では言わなかったからだけど」
「アイロンは使わせてもらう機会がなかったけれど、電子レンジくらいは使えたから、それで押し花を作ることもできた」
「電子レンジを使えば、1時間もかからない内にできてしまうのだけれど、それはしなかった」
「兎乃おねえさんと私は似ている。
私もイバラシティでやりなおしたい」
「考えてみれば、私以外のひとがどうして侵略をしたいのかなんて、考えたことがなかった」
「考える余裕もなかった」
「ただ、侵略して、侵略して、侵略することだけを考えていたから」
「余裕ができたのは、いいことなのかしら」
「きっと、よくないことよね」
「侵略することだけ、戦うことだけ考えるのがほんとうはいい」
「だって、余裕ができてどうするの?
侵略するために私はここにいるのに」
「いるはずなのに」
「……」
「兎乃おねえさんと私、どこが違うのかしら」
「ううん、違うのはわかっているの」
「……」
「違うのかしら」
「違う、のよね」
「どこが違うのかしら」
「私は、私を消してしまいたい」
「こんなことを考えている私がいることが許せない」
「兎乃おねえさんは、そうじゃないってことかしら」
「『自分が汚れている』と思っている自分を消してしまいたいとは思わないのかしら」
「だって、そうじゃないと……」
「兎乃おねえさんの話が聞きたいわ」
「どうしてそう思えるようになったのか」
「それがわかれば……」
「いいえ、それがわかったところで……」
「だって……」
「でも……」
「押し花がね、できるまでは待てる気がしていたの」
「できるまでの間に寝込んでしまうことがあっても、今は押し花を作っているから、起き上がれたそのときには、押し花がちょうどできているんだと思えた」
「そういえば、最後のあのとき、私は押し花を作っていたのだったかしら」
「押し花……」
「作っていたような気もするし、作る元気もなかったような気もする」
「ごんは、旅に出る前に、私の部屋を見ていったかしら」
「私の部屋、今はどうなっているかしら」
「本と、折り紙と、あやとりと、びぃだまと、押し花と……」
「もう、何もなくなっているかしら」
「私がしんでしまってから、どれくらいの時間が経ったのかしら」
「押し花ができるくらいの時間は経ったのかしら」
「二人で作る押し花、楽しそうね」
「押し花で飾られた栞」
「あなたが初めて作るその栞、最初に挟まれるのはどんな本かしら」



ENo.643 ミハクサマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.733 ウミネコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
「なんだか様子が変ね」 |
 |
クレハ 「ま、偵察なら初回はこんなもんよね! 貴様達、割と大義であった! アンジニ側に着くなら、父君に言ってちょっと良い待遇をお願いしてあげても良いのよ!」 |
| ナナキ 「なんかあっという間だったな。さて、この世界の行く末は…?」 |



ラブアンドピースフォーエバー
|
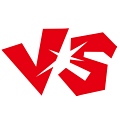 |
ハザマに生きるもの
|



花♥遊記
|
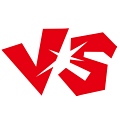 |
ラブアンドピースフォーエバー
|



アイリ(428) は ネジ を入手!
ナナキ(1016) は 不思議な牙 を入手!
黒髪の巫女(419) は 不思議な牙 を入手!
クレハ(675) は ネジ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
クレハ(675) のもとに 稲刈り機 が泣きながら近づいてきます。



れあち(415) とカードを交換しました!
願いのチーズケーキ (イバラ)


レッドインペイル を研究しました!(深度0⇒1)
フレイムレゾナンス を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)



次元タクシーに乗り『チナミ区 H-15:釣り堀』に転送されました!
チナミ区 H-16(森林)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 H-17(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-18(森林)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-19(森林)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 H-20(沼地)に移動!(体調26⇒25)
現在地が異なるためパーティが分かれました。再結成する必要があります。
採集はできませんでした。
- 黒髪の巫女(419) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- アイリ(428) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)





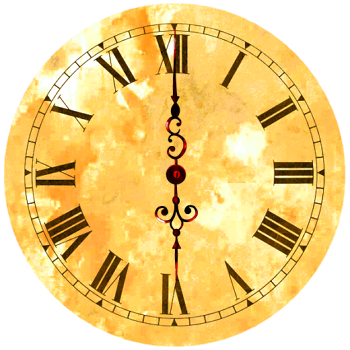
―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「……時計台に呼ばれてしまいましたが、はてさて。」 |
 |
エディアン 「なーんか、嫌な予感がします。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
 |
エディアン 「ほら……ほらぁ……。」 |
 |
榊 「どういうことでしょうねぇ。」 |
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝してます。」 |
 |
エディアン 「……ワールドスワップの能力者さんですよね。 機会を与えてくれて、感謝していますよ?」 |
 |
榊 「お姿は拝めないんですかねぇ。私は興味津々桃色片想いなのですが。」 |
声は淡々と、話を続ける。
 |
声 「どうやらこのワールドスワップ、時計の進みが狂っているようです。 特殊な因子を含めてしまった為と能力が訴えます。その因子が――」 |
 |
声 「――榊さん、貴方のようですね。何か、心当たりは?」 |
 |
榊 「大いにございます!特殊な世界の住人ゆえ、私は今や特異な存在なのでしょう。 妻に『貴方は変人』とよく言われていましたが、そういうことでしたか!納得ですッ」 |
 |
榊 「では、役目を果たすのは難しいということでよろしいですか?」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
榊 「……? ……どうしました?」 |
 |
声 「……仕切り直し、世界線を変更する、と能力が言ってきます。 貴方が案内役にならない世界線。イバラシティも、アンジニティも、新たなものになる……と。」 |
 |
エディアン 「……そ、そんなことまでできてしまう能力? ワールドスワップという名の範疇を超えてません?」 |
 |
榊 「世界線を別のものと交換する……と考えるなら、ギリギリ……ですかね。 というか、スワップから外れた現象は既に起こっていますが。」 |
 |
声 「これは能力ではなく、……呪い。呪いという言葉が合う。 今まで勝手に発動した数度、自分への利はない。制御下にない、把握できない、呪い。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「ハザマへの次の転送時間に、ハザマに転送される代わりに、世界線が変更される。 そして、案内役も、転送対象も、変わる。」 |
 |
声 「変わるものは、多いだろう。しかし変わらぬものも、あるだろう。」 |
 |
エディアン 「別の世界線、ですものね。 ……どうせなら私がアンジニティにいない世界線がいいんですけど。」 |
 |
榊 「……なるほど、奇妙な枝の正体は世界線操作者でしたかッ! 少なくとも私が案内役となれない世界線になるのですね、残念です。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「連絡は終わり。さようなら。」 |
声はそこで終わる。
 |
榊 「さて…… とても短い間ではありましたが、 エディアンさん、皆様、お付き合いありがとうございました!」 |
 |
エディアン 「お別れですか。悪人顔っぽくて敵視しやすい相手だったんですけどねー。」 |
 |
榊 「こんな素敵な笑顔を悪人顔呼ばわりとは、失礼な娘さんです。 なるほどアンジニティにいらっしゃるわけですねぇ。」 |
 |
エディアン 「……うるっさいですね。事情は人それぞれあるんですよ、色々!」 |
 |
榊 「……それでは、」 |
 |
エディアン 「……それでは、」 |
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
 |
榊 「お疲れ様でした。」 |
 |
エディアン 「お疲れ様でしたー!」 |

ENo.419
『ごん』



操術にして装術にして葬術使い。
外見は小学生ぐらいに見える。
身長は130cmくらい。
この姿は可能性。
『夢』を見ず、自らを否定した彼女の可能性。
この姿は可能性。
幼い彼女が目を落とす直前に託した願いの姿。
――託したはずのそれを彼女はねだった。
あの子になりたいと強請ってしまった。
そして彼女はあの子になった。
未来を対価にあの子になった。
あの子として彼女は生きる。
その虚しさに気づくときまで。
あの子として彼女は生きる。
それにさえ意味があるのだと気づくときまで。
……いやだ、気づきたくない。
虚しさも意味も知りたくない。
……いやよ、忘れたいの。
おれがほんとうは『私』だなんて、忘れてしまいたい。
だから、彼女は『侵略』する。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記憶力判定に成功すれば、あなたは彼女(『ごん』)の姿が、とある塔で見かけた「銀髪青目の妖狐」と同じ姿であることに気づいてもいい
(その上で洞察力判定に成功すれば、あなたは彼女が「塔にいた銀髪青目の妖狐」とは別人であることに気づいてもいい)。
また、「ハザマ」内で現れる黒髪の少女が、『ごん』と同じ顔をしており、外見年齢的にもほぼ同じであるとあなたは気づいてもいい。
※キャラクターイラストとアイコンNo0~8はすまちー様(@sumachi)に、No.9、26~29はけそ様(@kso_)に、それぞれコミッションにて描いていただきました。
※十card使用させていただいております(http://rainpark.sub.jp/palir/jucard.html)。
※メッセージ等はお気軽にどうぞ。
外見は小学生ぐらいに見える。
身長は130cmくらい。
この姿は可能性。
『夢』を見ず、自らを否定した彼女の可能性。
この姿は可能性。
幼い彼女が目を落とす直前に託した願いの姿。
――託したはずのそれを彼女はねだった。
あの子になりたいと強請ってしまった。
そして彼女はあの子になった。
未来を対価にあの子になった。
あの子として彼女は生きる。
その虚しさに気づくときまで。
あの子として彼女は生きる。
それにさえ意味があるのだと気づくときまで。
……いやだ、気づきたくない。
虚しさも意味も知りたくない。
……いやよ、忘れたいの。
おれがほんとうは『私』だなんて、忘れてしまいたい。
だから、彼女は『侵略』する。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記憶力判定に成功すれば、あなたは彼女(『ごん』)の姿が、とある塔で見かけた「銀髪青目の妖狐」と同じ姿であることに気づいてもいい
(その上で洞察力判定に成功すれば、あなたは彼女が「塔にいた銀髪青目の妖狐」とは別人であることに気づいてもいい)。
また、「ハザマ」内で現れる黒髪の少女が、『ごん』と同じ顔をしており、外見年齢的にもほぼ同じであるとあなたは気づいてもいい。
※キャラクターイラストとアイコンNo0~8はすまちー様(@sumachi)に、No.9、26~29はけそ様(@kso_)に、それぞれコミッションにて描いていただきました。
※十card使用させていただいております(http://rainpark.sub.jp/palir/jucard.html)。
※メッセージ等はお気軽にどうぞ。
25 / 30
360 PS
チナミ区
H-20
H-20




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 南天燭 | 武器 | 33 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 陽炎 | 防具 | 33 | 敏捷10 | 加速10 | - | |
| 6 | 飾り紐 | 装飾 | 39 | 祝福10 | 火纏10 | - | |
| 7 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 8 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 9 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 10 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 12 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 10 | 拘束/罠/リスク |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 付加 | 32 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 7 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| ストレングス | 6 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| オフェンシブ | 5 | 0 | 80 | 自:AT増+AG減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 80 | 自:DF増(2T) | |
| ウィザー | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| イレイザー | 8 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
| キャプチャー | 5 | 0 | 70 | 自:束縛LV増 | |
| ストライキング | 6 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 | |
| チャージ | 6 | 0 | 60 | 敵:4連鎖撃 | |
| ペイレーネー | 5 | 0 | 10 | 味傷:祝福+味傷:瀕死状態なら、自:SP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 6 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージが上がるようになる | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】[スキル使用設定不要]生産行動『効果付加』時、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
―― 壊 音 ―― (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
GE・Ammophillia欽玄 (コロージョン) |
0 | 70 | 敵貫:腐食 | |
|
鎌鼬 (クリエイト:ホーネット) |
0 | 100 | 敵:痛撃&(猛毒or麻痺) | |
|
プテラビーム (ペリル) |
0 | 130 | 敵:闇撃&何か肉体変調 | |
|
なにかじみなもの (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
願いのチーズケーキ (イバラ) |
0 | 120 | 敵3:精確地痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]ペネトレイト | [ 1 ]スパイン |
| [ 2 ]ヒールハーブ | [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]バトルソング |
| [ 1 ]ウィークポイント | [ 1 ]アグリローズ | [ 1 ]レッドインペイル |
| [ 1 ]フレイムレゾナンス | [ 1 ]イバラ | [ 1 ]サモン:ナレハテ |
| [ 1 ]デッドリィトクシン | [ 1 ]エンドレスノイズ |

PL / bisnon




























