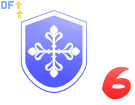<< 4:00>> 6:00





そんで?そんでて何や、あとはお前が知ってる通りやろ。
師匠について、10年……いや、もうちょい早かったか?
一人前になって、鵠様に名前を貰ってよ。
お前と会ったんは丁度そん頃やから、別にもう、話すことあらへんやろ。
何やな、話せってか?
お前ほんまに、ええ趣味しとるわ。
つっても、何から話したらええんやろな……。
とりあえずよ、お前のことは
……まあ、顔は良いと思ったよ。

目が合った。
・
・
・
…………
・
・
・
女性はここで働いているらしかった。
早朝。妖怪が弱る、つまり妖怪狩りに適した時間と、彼女の出勤時間が近いらしい。
絶好の狩り場を捨てるわけにもいかず、深谷は、彼女と話すようになった。
警備員に言いつける気配も、深谷を怪しむ様子もない。
一度警戒を解いてしまえば ——神社の事を何も知らない——彼女との会話は不快ではなかった。
神の存在は秘されている。
社殿で働いていない人間は、神のことも妖怪のことも知らないのだと、教わったときは驚いたものだ。
人が人を統べるためか、神が人に飽きたか、近代に流入した海の向こうの神の教えのせいか、科学が世界を支配する為か。
そのどれでもあるし、どれでもないかもしれない。
兎に角も深谷の生まれる前から、神だ妖怪だと白昼堂々口にする人間は「怪しい人間」だったのだが。
・
・
・
朝日に洗われる窓の前で、動かないエスカレーターの途中で、深谷と女性は幾度も言葉を交わした。
従業員はともかく、片や不法侵入者である。
ごく短い会話しかなかったが、回数を重ねれば、それなりに親しみも湧く。
・
・
・

・
・
・
四角く、ハザマの赤い空が切り取られている。
黒い街の黒い建物、壁も窓枠も黒い中に浮かぶ赤は、鮮やかとは程遠い印象を与える。
聞こえてくるのも、ラジオやスピーカーを通した途切れ途切れの音楽や声、
街の立てる硬質な音ばかりだから、癒しというものがろくになかった。
今、深谷と清がいるのは狭い部屋で、深谷は獣の四肢を折って床に座り、
赤い表紙のノートを手繰っている。
この黒い街で拾ったものだ。
あらゆる家具が床や壁に張り付き動かせない中、この日記だけは持ち運ぶことができる。
聞いていないことを解って尋ねている。
清は今、机に向かって休みなく手を動かしていた。
黒い机に黒い椅子。椅子は床に張り付いたように動かないから、
清は身を乗り出すようにして紙に筆を走らせている。
正確には、常に持ち歩かせていた筆ペンを。
形代は使い捨てだ。だから何枚も書いて用意しておかなくてはならない。
ハザマと言えど生き物は溢れていて、だから死霊にも事欠かないのは幸いだった。
紙だって、ペンだって、朽ちた家々を回れば、あちらこちらで手に入れることができる。
そもそも何故ここにいるのか忘れたか……とは、言わなかった。
それを言えば、また癇癪を起こされることが解っている。
通信が送られてきた。
複数の通信と油断、衝動のままに叩きつけた言葉は、
そのまま自らの弱みを晒すことに繋がった。
これ以上の情報も材料も誰にも与えてはならないと、こうして狭い部屋に引き篭もる事になっている。
cross+roseは、ハザマで起きるあらゆる事象を観測する。
敵味方の別のない監視の目から逃れるには、見通しの悪い場所に陣取るしかない。
言ってはみても出掛けるつもりはないのだ。
深谷はまた手帳を開き、1ページ1ページ、爪で引っ掛けるようにしてページを手繰る。
友情、愛情。
どちらも美しいと言われる。
友を、人を愛することは幸せな事だと。
本当にそうなのか、深谷には解らない。
深谷は初め、神を愛した。
父も母もない分、それらに向けるはずだったものを全て神に向けて、
そして、同じものが返ってくることを望んだ。
神は絵本を読んではくれない。頭を撫でて、お前は良い子だ、なんて言ってはくれない。
信心薄いものを社から追い出しても、わざと自分の身を落としてみても、
神の愛は、人の愛とはどうしようもなく隔たっていた。
それでも自分が在るのは、神の慈しみのゆえだ。
そして次に、人を愛した。
師に連れ回されて夜遊びを知り、かなり頻繁に騙されて、それでも楽しかったように思う。
最後に、騙される事にも飽きてきたころ。
一人の女性を愛した。
苛立ちが募る。黙って読んでいられなくなって、
深谷は、止せばいいのに、またこうして声をかけてしまう。
清は愚かだ。
愛も恋慕も、楽しいことだって、
何もかもを薪のように怒りにくべて、そうして燃やし続けても灰も残らない。
イバラシティで得たものは、何も残したくないのだろう。深谷と同じように。
だから清は、世界で二番目に愚かだ。
全身で拒絶を示しながら、清はまた机に向かう。
そして今度こそ、振り返らなくなった。
深谷はここを離れない。
自分がいなくなれば、清は今度こそ一人になる。
そうして一人で、どこまでも沈んで行こうとするから。
・
・
・




ENo.132 ラフィ とのやりとり

ENo.173 レオン とのやりとり

ENo.638 プテラ とのやりとり

ENo.780 クラウディ とのやりとり

ENo.914 例の双子 とのやりとり

以下の相手に送信しました




レッド(151) から 魂の杭 を手渡しされました。
モコ(755) に ItemNo.10 毛 を手渡ししました。
ItemNo.7 うどんがき を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(11⇒12)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








街喰らい(114) は 古雑誌 を入手!
レッド(151) は 杉 を入手!
深谷(503) は 杉 を入手!
モコ(755) は 柳 を入手!
街喰らい(114) は 美味しい草 を入手!
モコ(755) は 牙 を入手!
レッド(151) は 毛 を入手!
モコ(755) は 剛毛 を入手!



百薬LV を 2 DOWN。(LV13⇒11、+2CP、-2FP)
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
レッド(151) の持つ ItemNo.12 杉 から防具『ビリビリスーツ』を作製しました!
アザト(563) とカードを交換しました!
邪神のお戯れ (ヒールポーション)

ブラックアサルト を研究しました!(深度0⇒1)
ブラックアサルト を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
プロテクション を習得!
フリーズ を習得!
ウィルスゾーン を習得!
エリアグラスプ を習得!



街喰らい(114) に移動を委ねました。
ヒノデ区 D-5(森林)に移動!(体調12⇒11)
ヒノデ区 D-6(森林)に移動!(体調11⇒10)
ヒノデ区 D-7(草原)に移動!(体調10⇒9)
ヒノデ区 D-8(草原)に移動!(体調9⇒8)
ヒノデ区 D-9(チェックポイント)に移動!(体調8⇒7)
採集はできませんでした。
- 街喰らい(114) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- レッド(151) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- 深谷(503) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- モコ(755) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
ヒノデ区 D-9:落書き広場 が発生!
- 街喰らい(114) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場
- レッド(151) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場
- 深谷(503) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場
- モコ(755) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。












棒のような何かが壁に落書きをしている。

地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)








































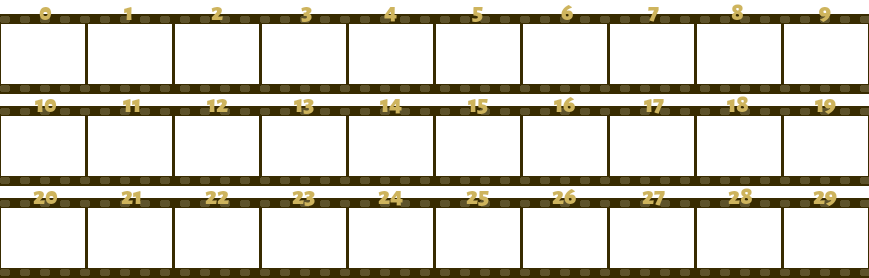





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




そんで?そんでて何や、あとはお前が知ってる通りやろ。
師匠について、10年……いや、もうちょい早かったか?
一人前になって、鵠様に名前を貰ってよ。
お前と会ったんは丁度そん頃やから、別にもう、話すことあらへんやろ。
何やな、話せってか?
お前ほんまに、ええ趣味しとるわ。
つっても、何から話したらええんやろな……。
とりあえずよ、お前のことは
……まあ、顔は良いと思ったよ。
 |
「あ〜〜〜〜〜〜〜〜〜……」 |
 |
「吐きそ……」 |

深谷
26歳。つい最近一人立ちし、名を貰い受けた退魔師。
 |
「……いい加減帰らねえと、見つかったらまずい……」 |
 |
「あ、無理。動くの無理。吐きそ……」 |
 |
「…………?」 |
 |
 |
「お」 |
目が合った。
・
・
・
 |
「あの」 |
 |
「お兄さん、この前屋上に登ってたよね?」 |
 |
「知りません人違いです」 |
 |
「怒らないから。どうやって登ったか聞きたいだけ」 |
 |
「……そりゃあ。階段を上がってよ」 |
 |
「はいはいそういうのいいから。 な、ん、で。上がったの?」 |
 |
「…………狩り場やからさ」 |
 |
「うわ、変な訛り」 |
…………
・
・
・
女性はここで働いているらしかった。
早朝。妖怪が弱る、つまり妖怪狩りに適した時間と、彼女の出勤時間が近いらしい。
絶好の狩り場を捨てるわけにもいかず、深谷は、彼女と話すようになった。
 |
「それで、妖怪狩りって何するの?テレビの撮影とかじゃないの?」 |
警備員に言いつける気配も、深谷を怪しむ様子もない。
一度警戒を解いてしまえば ——神社の事を何も知らない——彼女との会話は不快ではなかった。
 |
「……別に信じんでもええぞ」 |
神の存在は秘されている。
社殿で働いていない人間は、神のことも妖怪のことも知らないのだと、教わったときは驚いたものだ。
人が人を統べるためか、神が人に飽きたか、近代に流入した海の向こうの神の教えのせいか、科学が世界を支配する為か。
そのどれでもあるし、どれでもないかもしれない。
兎に角も深谷の生まれる前から、神だ妖怪だと白昼堂々口にする人間は「怪しい人間」だったのだが。
 |
「信じるよ。お兄さん、怪しすぎて逆に怪しくない」 |
 |
「あっそ」 |
・
・
・
 |
「あっ、お兄さーん!狩り捗ってる?」 |
 |
「おう」 |
朝日に洗われる窓の前で、動かないエスカレーターの途中で、深谷と女性は幾度も言葉を交わした。
従業員はともかく、片や不法侵入者である。
ごく短い会話しかなかったが、回数を重ねれば、それなりに親しみも湧く。
 |
「さてはお前、おれに惚れたか?」 |
 |
「え、お兄さんあたしに惚れたの?」 |
 |
「何でそうなるんだよ!」 「おれはな、顔の良い女やねぇと……」 |
 |
「………………」 |
 |
「な、なに?」 |
 |
「お前結構可愛いな」 |
・
・
・
 |
「今更だけどさ、お兄さん何て名前?」 |
 |
「ほんと今更やな。深谷や」 |
 |
「苗字?名前?」 |
 |
「……どっちでもあらへん、神に頂いた名前やから」 |
 |
「ふーん。本名は何て言うの? |
 |
「なんやなお前。おれこの名前気に入ってんねんぞ……」 |
 |
「でも私は神様とか関係ないし、変な感じがするし。 絶対呼ばれたくないってなら、それでもいいけど」 |
 |
「……三劔司」 |
 |
「いい名前じゃない」 |
 |
「いい名前?これが?」 |
 |
「親から貰ったわけでもねえのにさ。 多分、ろくな命名じゃねえぜ。巫女とかが安直に付けたんだ」 |
 |
「なんでそんなに捻くれるかなあ……」 |
 |
「つるぎ、って、強そうでいいじゃない。それで狩りなんてしてるんでしょ? 名は体を表すっていうじゃない。カッコいいよ」 |
 |
「あっ、私は千塚ね。千塚沙耶」 |
 |
「ああ、そう」 |
 |
「…………」 |
 |
「良い名前だな」 |

千塚 沙耶
当時25歳。好奇心旺盛な女性。大型ショッピングモールにある雑貨屋の店員。後の三劔 沙耶。
享年27歳。
享年27歳。
・
・
・
四角く、ハザマの赤い空が切り取られている。
黒い街の黒い建物、壁も窓枠も黒い中に浮かぶ赤は、鮮やかとは程遠い印象を与える。
聞こえてくるのも、ラジオやスピーカーを通した途切れ途切れの音楽や声、
街の立てる硬質な音ばかりだから、癒しというものがろくになかった。
今、深谷と清がいるのは狭い部屋で、深谷は獣の四肢を折って床に座り、
赤い表紙のノートを手繰っている。
この黒い街で拾ったものだ。
あらゆる家具が床や壁に張り付き動かせない中、この日記だけは持ち運ぶことができる。
 |
深谷 「化け物から、手に手を取り合って逃げる……か」 |
 |
深谷 「美しい話だなあ、清よ。 聞いてるか?」 |
 |
清 「…………」 |
聞いていないことを解って尋ねている。
清は今、机に向かって休みなく手を動かしていた。
黒い机に黒い椅子。椅子は床に張り付いたように動かないから、
清は身を乗り出すようにして紙に筆を走らせている。
正確には、常に持ち歩かせていた筆ペンを。
 |
形代は使い捨てだ。だから何枚も書いて用意しておかなくてはならない。
ハザマと言えど生き物は溢れていて、だから死霊にも事欠かないのは幸いだった。
紙だって、ペンだって、朽ちた家々を回れば、あちらこちらで手に入れることができる。
 |
深谷 「おーい」 |
 |
清 「うるさいな。そんなに暇なら、紙を探してこれば?」 |
 |
深谷 「嫌だね、そんだけあったら十分だろ」 |
 |
清 「じゃあ形代作ってれば」 |
 |
深谷 「お前、この手でペン握れると思ってんのかよ」 |
そもそも何故ここにいるのか忘れたか……とは、言わなかった。
それを言えば、また癇癪を起こされることが解っている。
通信が送られてきた。
複数の通信と油断、衝動のままに叩きつけた言葉は、
そのまま自らの弱みを晒すことに繋がった。
これ以上の情報も材料も誰にも与えてはならないと、こうして狭い部屋に引き篭もる事になっている。
cross+roseは、ハザマで起きるあらゆる事象を観測する。
敵味方の別のない監視の目から逃れるには、見通しの悪い場所に陣取るしかない。
言ってはみても出掛けるつもりはないのだ。
深谷はまた手帳を開き、1ページ1ページ、爪で引っ掛けるようにしてページを手繰る。
 |
深谷 「……やっぱりさ、お美しいよなあ」 |
友情、愛情。
どちらも美しいと言われる。
友を、人を愛することは幸せな事だと。
本当にそうなのか、深谷には解らない。
深谷は初め、神を愛した。
父も母もない分、それらに向けるはずだったものを全て神に向けて、
そして、同じものが返ってくることを望んだ。
神は絵本を読んではくれない。頭を撫でて、お前は良い子だ、なんて言ってはくれない。
信心薄いものを社から追い出しても、わざと自分の身を落としてみても、
神の愛は、人の愛とはどうしようもなく隔たっていた。
それでも自分が在るのは、神の慈しみのゆえだ。
そして次に、人を愛した。
師に連れ回されて夜遊びを知り、かなり頻繁に騙されて、それでも楽しかったように思う。
最後に、騙される事にも飽きてきたころ。
一人の女性を愛した。
 |
深谷 「……清」 |
 |
清 「今度は、なに?」 |
苛立ちが募る。黙って読んでいられなくなって、
深谷は、止せばいいのに、またこうして声をかけてしまう。
 |
深谷 「お前って馬鹿だよな」 |
 |
清 「馬鹿にするの、やめてくれない?」 |
 |
深谷 「おれが馬鹿にしなくたって、お前は馬鹿だよ」 |
清は愚かだ。
愛も恋慕も、楽しいことだって、
何もかもを薪のように怒りにくべて、そうして燃やし続けても灰も残らない。
イバラシティで得たものは、何も残したくないのだろう。深谷と同じように。
だから清は、世界で二番目に愚かだ。
 |
深谷 「おれはその馬鹿っぷりを褒めてんの」 |
 |
清 「ああ、そう」 |
全身で拒絶を示しながら、清はまた机に向かう。
そして今度こそ、振り返らなくなった。
深谷はここを離れない。
自分がいなくなれば、清は今度こそ一人になる。
そうして一人で、どこまでも沈んで行こうとするから。
・
・
・

愛
そのものの価値を認め、強く引きつけられる気持ち。かわいがり、慈しむ心。慈しみ恵むこと。また、大事なものとして慕う心。



 |
絵を描く。 描くという言葉から程遠い、紙を黒く塗るだけの行為。 それがとても楽しい事に気がついた。 何を描こうとして失敗しても、最後には塗り潰せると思えば楽になる。 |
 |
異能の行使に使う形代は、紙の形から書き順まで決まっている。 失敗したからと言って使えないわけではないが、当然精度は落ちるので、 かなり緊張感のある作業となる。 息抜きがあれば効率が上がると、気がついたのは随分と前のことだ。 |
 |
息抜きとして、以前は休憩を挟んでいた。 甘いものを作ること。食べること。 手の込んだ料理を作るのも、気分転換としては優秀だった。 だが、時間はかかるし、作ったからと言って食欲が湧くかは別だ。 気は晴れるが、あまり効率の良い方法ではない。 |
 |
その点こちらは、形代作りの延長でできる。 後始末も、洗う筆が数本増えるだけだ。 塗りつぶすだけに筆を使い分けるのも妙な話だが、 それぞれ違う手応えの筆を使い分け、線を引くのは楽しい。 そして満足すれば、後始末も簡単だ。 丸めてゴミ箱に放るだけでいい。 |
 |
黒く塗る。 黒く塗る。 白紙を、黒く汚して塗り潰していく。 |
 |
綺麗なものも、 描き出そうとしては真っ黒に塗り潰す。 後には何も残らない。 残さない。 ただ少し、気が晴れるだけ—— |
 |
『溜飲が下がる』ってのも嘘だって、思いました。 |
 |
「……ッ」 眩暈。 そうと認識する前に溢れ落ちた記憶が、紙面に大きな染みを落とす。 調子が狂う。 清は紙を捨てると、筆を手に立ち上がった。 気晴らしすら満足に出来ないなら、後は休むだけだ。 幸い、形代も最近はあまり使わない。 深谷が持っていく分を除いても、作り置きは十分のはずだ。 |
 |
筆を洗う。 黒色が排水溝に流れていく。 流し切った後に残った黒い筋をスポンジで拭って、それで後始末は終わりだ。 |
 |
こうして、いつも通りの日が暮れる。 曲がった背を伸ばすようにして、両手を上げて伸びをする。 時計に視線が向く。 |
 |
……19時59分。 ああ、もうこんな時間だと、 夕食にしようと、清は居間にいる深谷に声をかけようとして、 |
 |
そしてまた『一時間』が始まる。 |
ENo.132 ラフィ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.173 レオン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.638 プテラ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.780 クラウディ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.914 例の双子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
笑い声が響く。足音が聞こえる。助けを求める声がする。 街の至るところにある様々な機器が時折、思い思いに音を発している。 そこに実体はない。追放された者以外がいない街で新たに生まれる音はない。だから、 |
 |
 |
時々カーブミラーに、ガラス戸に、真っ暗な画面に映り込む影の全てが、既に亡い。 |
 |
なのに物は、先程まで誰かが使っていたように残っていることがあった。 この場所にあるはずのないものまで。 |
| ヒーローマスクの男が、街の端で何やら声をあげている。 |
 |
再現される、かつてあった何か。 それはハザマが生んだ幻か、街が見せた夢か。 現実に存在しないことだけがはっきりしている。 |
 |
祝福は遠く、細い糸を撒いたように深谷には感じられていた。 それがどこから来たのか、繋がっているのかは、解らない。 |
 |
深谷 「……ま、何でも良いか。 いつだってやることは同じだ……アンジニティなら侵略、ってな」 |
 |
袖から垂れた鎖がゆらゆらと揺れている |
レッド(151) から 魂の杭 を手渡しされました。
| レッド 「あぁ、これアンタ用か。ほらよ。」 |
モコ(755) に ItemNo.10 毛 を手渡ししました。
ItemNo.7 うどんがき を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(11⇒12)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







街喰らい(114) は 古雑誌 を入手!
レッド(151) は 杉 を入手!
深谷(503) は 杉 を入手!
モコ(755) は 柳 を入手!
街喰らい(114) は 美味しい草 を入手!
モコ(755) は 牙 を入手!
レッド(151) は 毛 を入手!
モコ(755) は 剛毛 を入手!



百薬LV を 2 DOWN。(LV13⇒11、+2CP、-2FP)
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
レッド(151) の持つ ItemNo.12 杉 から防具『ビリビリスーツ』を作製しました!
アザト(563) とカードを交換しました!
邪神のお戯れ (ヒールポーション)

ブラックアサルト を研究しました!(深度0⇒1)
ブラックアサルト を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
プロテクション を習得!
フリーズ を習得!
ウィルスゾーン を習得!
エリアグラスプ を習得!



街喰らい(114) に移動を委ねました。
ヒノデ区 D-5(森林)に移動!(体調12⇒11)
ヒノデ区 D-6(森林)に移動!(体調11⇒10)
ヒノデ区 D-7(草原)に移動!(体調10⇒9)
ヒノデ区 D-8(草原)に移動!(体調9⇒8)
ヒノデ区 D-9(チェックポイント)に移動!(体調8⇒7)
採集はできませんでした。
- 街喰らい(114) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- レッド(151) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- 深谷(503) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- モコ(755) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
ヒノデ区 D-9:落書き広場 が発生!
- 街喰らい(114) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場
- レッド(151) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場
- 深谷(503) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場
- モコ(755) が経由した ヒノデ区 D-9:落書き広場






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |







ブレーメン
|
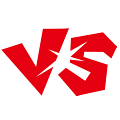 |
通り雨
|




ヒノデ区 D-9
落書き広場
落書き広場
 |
マイケル 「おやこんなところにお客ですか。」 |
棒のような何かが壁に落書きをしている。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「私はマイケルです。チェックポイント狙いですよね? 落書き会の場所取りではありませんよね?」 |
 |
マイケル 「でしたら、本気は出さなくても良さそうですね。 お茶会感覚で参りましょう参りましょう。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「では、始めましょうか。」 |
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



通り雨
|
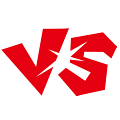 |
立ちはだかるもの
|

| 423 | 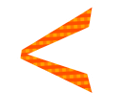 |
624 |
1st
レッド


レッド
2nd
街喰らい


街喰らい
3rd
モコ


モコ
4th
深谷


深谷

5th
マイケル


マイケル

6th
マイケル


マイケル

7th
マイケル


マイケル

8th
マイケル


マイケル

9th
マイケル


マイケル

10th
マイケル


マイケル

11th
マイケル


マイケル

12th
マイケル


マイケル

13th
マイケル


マイケル

14th
マイケル


マイケル


ENo.503
退魔師の師弟



■深谷(ふかや)
男/41/退魔師(実質ニート)
師匠の方。
神社に仕えて妖怪を狩る退魔師を名乗る。
が、このイバラシティでは妖怪なんて今のところ見たことないので、ただの飲んだくれのおじさんに等しい。
傲岸不遜で、三度の飯より酒と女が好き。
イバラシティへは、妖怪狩りの為に数年前に弟子を伴って移り住んできた。
……という記憶を持つ。
■八矢 清(はちや きよ)
女/24/退魔師見習い(実質フリーター)
弟子の方。退魔師見習いで、深谷に比べて常識人。
妖怪を探す事に余念がなく、でなければ生活を維持する為にパートやバイトに明け暮れている。
深谷に従って数年前に移り住んで来たが、一向に妖怪が見つからず、深谷が怠惰を貪っていることにやきもきしている。
……という記憶を持つ。
・異能【式神作成】
墨で特定の言葉や図形を描いた和紙に、いろいろなもの
……基本的には動物霊などを下ろし、しもべとして使役する事ができる。
ただし和紙は使い捨てのため、予め用意した分しか使う事ができない。
----------
共にアンジニティ。
『数年前に移り住んだ』というのは偽の記憶であり、本当は『年末にイバラシティにやってきた』のである。
イバラシティにおける二人の異能【式神作成】は、
二人の持つ神力が、イバラシティの『異能』として処理されたに過ぎない。
・能力【神力】
神の力を借り受け、行使する。
疑似的かつ制限のある霊魂の操作、不浄を祓い、場や物を清めるなどが可能。
----------
ロールまとめ場
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1208
自宅プレイス
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1210
ロール、メッセ等歓迎してます。既知、敵対含む関係設定もお気軽に。遊んで!ください!
@fyuki_28g
男/41/退魔師(実質ニート)
師匠の方。
神社に仕えて妖怪を狩る退魔師を名乗る。
が、このイバラシティでは妖怪なんて今のところ見たことないので、ただの飲んだくれのおじさんに等しい。
傲岸不遜で、三度の飯より酒と女が好き。
イバラシティへは、妖怪狩りの為に数年前に弟子を伴って移り住んできた。
……という記憶を持つ。
■八矢 清(はちや きよ)
女/24/退魔師見習い(実質フリーター)
弟子の方。退魔師見習いで、深谷に比べて常識人。
妖怪を探す事に余念がなく、でなければ生活を維持する為にパートやバイトに明け暮れている。
深谷に従って数年前に移り住んで来たが、一向に妖怪が見つからず、深谷が怠惰を貪っていることにやきもきしている。
……という記憶を持つ。
・異能【式神作成】
墨で特定の言葉や図形を描いた和紙に、いろいろなもの
……基本的には動物霊などを下ろし、しもべとして使役する事ができる。
ただし和紙は使い捨てのため、予め用意した分しか使う事ができない。
----------
共にアンジニティ。
『数年前に移り住んだ』というのは偽の記憶であり、本当は『年末にイバラシティにやってきた』のである。
イバラシティにおける二人の異能【式神作成】は、
二人の持つ神力が、イバラシティの『異能』として処理されたに過ぎない。
・能力【神力】
神の力を借り受け、行使する。
疑似的かつ制限のある霊魂の操作、不浄を祓い、場や物を清めるなどが可能。
----------
ロールまとめ場
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1208
自宅プレイス
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1210
ロール、メッセ等歓迎してます。既知、敵対含む関係設定もお気軽に。遊んで!ください!
@fyuki_28g
7 / 30
266 PS
ヒノデ区
D-9
D-9


































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 激情の澱 | 装飾 | 36 | 回復10 | - | - | |
| 4 | 魂の枷 | 防具 | 33 | 鎮痛10 | - | - | |
| 5 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 6 | 幽けき祝福 | 武器 | 39 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 7 | 杉 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV30)[防具]舞痺10(LV20)[装飾]加速10(LV10) | |||
| 8 | 杉 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV30)[防具]舞痺10(LV20)[装飾]加速10(LV10) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | |||||||
| 11 | 魂の杭 | 防具 | 39 | 治癒10 | 治癒10 | - | |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 11 | 生命/復元/水 |
| 百薬 | 11 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 防具 | 32 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 体当たり (ブレイク) | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 流鏑馬 (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 早駆け (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 大八洲の風 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| 憂い祓い (ヒール) | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練3 | 不浄の滝 (アクアヒール) | 6 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| 風神の寵愛 (ヒールポーション) | 6 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| 神の愛児 (プリディクション) | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| 罪業のほとり (ヒーリングスキル) | 6 | 0 | 50 | 自:HL増 | |
| フリーズ | 5 | 0 | 130 | 敵全:凍結 | |
| 黒の嬰児 (ノーマライズ) | 5 | 0 | 100 | 味肉精:HP増+肉体・精神変調減 | |
| 練3 | ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 |
| 潮騒鳴り止まず (キュアディジーズ) | 5 | 0 | 70 | 味肉2:HP増&肉体変調減 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 90 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
| 練3 | 呪い返し (コロージョン) | 6 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 |
| 界傾けよ反魂香 (リトルリヴァイブ) | 7 | 0 | 140 | 味傷:復活LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 呪歌 (攻撃) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 破魔の結界 (防御) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 神の手の写し (器用) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 獣の足音 (敏捷) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 此岸の祝詞 (回復) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 四足歩行 (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 彼岸の獣 (体力) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 滅びの否定 (治癒) | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 傷が塞がる (鎮痛) | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 曲霊四魂の存在証明 (幸運) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 清ら水の道 (水特性回復) | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ハルシ (ブレイク) |
0 | 20 | 敵:攻撃 | |
|
ここはどこ【縛】 (クリエイト:ケージ) |
0 | 60 | 敵:束縛 | |
|
「悪い世界」 (レックレスチャージ) |
0 | 80 | 自:HP減+敵全:風痛撃 | |
| 練1 |
Assist (パワフルヒール) |
0 | 100 | 味傷:精確攻撃&HP増 |
|
邪神のお戯れ (ヒールポーション) |
0 | 60 | 味傷:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]アクアヒール | [ 2 ]ラッシュ | [ 1 ]ヒールポーション |
| [ 2 ]オフェンシブ | [ 2 ]ブラックアサルト | [ 3 ]イレイザー |
| [ 1 ]エナジードレイン |

PL / フユキ