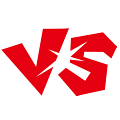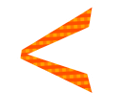<< 4:00>> 6:00




膝をけりこまれた鈍色は『自分はこのままでは無残に殺される』のだと悟った。
それが観衆の願いだとも。
彼女を何度も抱いた男たちさえも。
自分のお気に入りの命の炎が消えるかもしれない瞬間に後ろ暗い気持ちで興奮していた。
生きるだめに抱かれてきたのにその終わりがこれだなんて。
先ほどと持ったものとは違う感情がめらめらと噴出す。
吹き飛ばされれるまえに橙の髪をつかんで踏みとどまる。
どうしてだか、どうすればいいのか。本能が叫ぶ。
橙の奴隷がなぜ花形なのか。それはうわさに聞いていた。
相手を噛み千切りながらいたぶる姿はショーに映え、また奴隷たちには恐怖を与えると。
見てなさい大人たち。
腕がつかまれれる。少女の口が開く。
その喉……肩口とも呼べる部分に噛み付いたのは――鈍色の奴隷。
鋭くない歯は皮膚をかすかに破るだけ。突き飛ばされて距離が開く。
後は凄惨たる有様だった。
つかめるところには爪を。立てられる場所には歯を。顔が開いてれば目を狙い。
泥沼の中で少女たちは傷ついていく。
それでもどこかで、鈍色の少女は興奮の中に愉しささえ見出していた。
こんなものがあるのかと。
「うん、いいね。買おうか」
キャットファイトに進展がないことに不満の声が上がる前に立ち上がったのは金髪の女。
「お客様、今は「ばかっその方は「なんだぁ?」
「ねーちゃんがストリップでもしてくれんのか?」
突然変わった空気にざわつく会場。視線を受けてもなお堂々とした女は鈍色の少女に視線をやった。
---
困ります、なんだ?、今晩の目玉が、死ななければまだあれには価値が
「あー、うるさいわね」
金髪の女は億劫そうに髪をかきあげる。
青い瞳が妖しく光る。それで十分だった。
その場にいた人々は一瞬硬直し、性別問わず近くのものと深い口付けを交わしだす。
青臭い熱気が場を支配する。
「けりくらいはつけておきなさいよ」
女が髪をばっと振り乱すと鈍色の少女の中に暗い欲望が芽を出した。
いや、それは最初からあったのかもしれない。
体中を走る痛みが心地いい
御礼をしなきゃ。
金髪にとびかかった橙の首に手を伸ばした。
闘技の奴隷が動かなくなるまで、そう時間はかからなかった。
---
性別関係なく銜えて舐めて交わる狂った金持ちたちの宴を金髪と奴隷は後にする。
「あの……あるじさま、なにを?」
おずおずと切り出した少女に金髪の色欲は笑って見せた。
「なに、きみを次の席にすえようかと思ってね」
---
そうして奴隷は色欲見習いになった。
名前はいずれ失うと与えられなかった。



ENo.70 大将 とのやりとり

ENo.508 バツ とのやりとり

ENo.945 強欲 とのやりとり




特に何もしませんでした。








チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



色欲(228) は 柳 を入手!
暴食(534) は 杉 を入手!
強欲(945) は 柳 を入手!
強欲(945) は 爪 を入手!
暴食(534) は 美味しい草 を入手!
色欲(228) は 毛 を入手!
暴食(534) は 何か柔らかい物体 を入手!
暴食(534) は 何か柔らかい物体 を入手!
色欲(228) は 何か柔らかい物体 を入手!



呪術LV を 2 UP!(LV5⇒7、-2CP)
解析LV を 1 UP!(LV9⇒10、-1CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
暴食(534) により ItemNo.5 紅のリボン に ItemNo.10 不思議な石 を付加してもらいました!
⇒ 紅のリボン/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]幸運10 [効果3]-/特殊アイテム
ヴィーズィー(163) とカードを交換しました!
秘符【節制】 (アイシング)


ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度2⇒3)
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!



暴食(534) に移動を委ねました。
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!
- 暴食(534) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 を選択!
- 暴食(534) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。








瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。














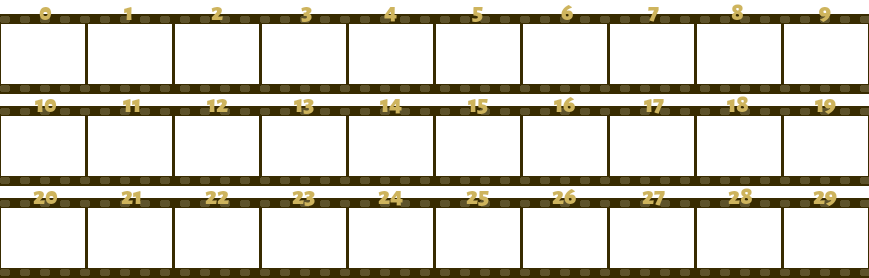





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



膝をけりこまれた鈍色は『自分はこのままでは無残に殺される』のだと悟った。
それが観衆の願いだとも。
彼女を何度も抱いた男たちさえも。
自分のお気に入りの命の炎が消えるかもしれない瞬間に後ろ暗い気持ちで興奮していた。
生きるだめに抱かれてきたのにその終わりがこれだなんて。
先ほどと持ったものとは違う感情がめらめらと噴出す。
吹き飛ばされれるまえに橙の髪をつかんで踏みとどまる。
どうしてだか、どうすればいいのか。本能が叫ぶ。
橙の奴隷がなぜ花形なのか。それはうわさに聞いていた。
相手を噛み千切りながらいたぶる姿はショーに映え、また奴隷たちには恐怖を与えると。
見てなさい大人たち。
腕がつかまれれる。少女の口が開く。
その喉……肩口とも呼べる部分に噛み付いたのは――鈍色の奴隷。
鋭くない歯は皮膚をかすかに破るだけ。突き飛ばされて距離が開く。
後は凄惨たる有様だった。
つかめるところには爪を。立てられる場所には歯を。顔が開いてれば目を狙い。
泥沼の中で少女たちは傷ついていく。
それでもどこかで、鈍色の少女は興奮の中に愉しささえ見出していた。
こんなものがあるのかと。
「うん、いいね。買おうか」
キャットファイトに進展がないことに不満の声が上がる前に立ち上がったのは金髪の女。
「お客様、今は「ばかっその方は「なんだぁ?」
「ねーちゃんがストリップでもしてくれんのか?」
突然変わった空気にざわつく会場。視線を受けてもなお堂々とした女は鈍色の少女に視線をやった。
---
困ります、なんだ?、今晩の目玉が、死ななければまだあれには価値が
「あー、うるさいわね」
金髪の女は億劫そうに髪をかきあげる。
青い瞳が妖しく光る。それで十分だった。
その場にいた人々は一瞬硬直し、性別問わず近くのものと深い口付けを交わしだす。
青臭い熱気が場を支配する。
「けりくらいはつけておきなさいよ」
女が髪をばっと振り乱すと鈍色の少女の中に暗い欲望が芽を出した。
いや、それは最初からあったのかもしれない。
体中を走る痛みが心地いい
御礼をしなきゃ。
金髪にとびかかった橙の首に手を伸ばした。
闘技の奴隷が動かなくなるまで、そう時間はかからなかった。
---
性別関係なく銜えて舐めて交わる狂った金持ちたちの宴を金髪と奴隷は後にする。
「あの……あるじさま、なにを?」
おずおずと切り出した少女に金髪の色欲は笑って見せた。
「なに、きみを次の席にすえようかと思ってね」
---
そうして奴隷は色欲見習いになった。
名前はいずれ失うと与えられなかった。



ENo.70 大将 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.508 バツ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.945 強欲 とのやりとり



特に何もしませんでした。







チナミ区 H-15:釣り堀
 |
マイケル 「上出来ですね。それでは、どうぞどうぞ。」 |
チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



色欲(228) は 柳 を入手!
暴食(534) は 杉 を入手!
強欲(945) は 柳 を入手!
強欲(945) は 爪 を入手!
暴食(534) は 美味しい草 を入手!
色欲(228) は 毛 を入手!
暴食(534) は 何か柔らかい物体 を入手!
暴食(534) は 何か柔らかい物体 を入手!
色欲(228) は 何か柔らかい物体 を入手!



呪術LV を 2 UP!(LV5⇒7、-2CP)
解析LV を 1 UP!(LV9⇒10、-1CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
暴食(534) により ItemNo.5 紅のリボン に ItemNo.10 不思議な石 を付加してもらいました!
⇒ 紅のリボン/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]幸運10 [効果3]-/特殊アイテム
ヴィーズィー(163) とカードを交換しました!
秘符【節制】 (アイシング)


ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度2⇒3)
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!



暴食(534) に移動を委ねました。
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!
- 暴食(534) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 を選択!
- 暴食(534) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |







チナミ区 P-3
瓦礫の山
瓦礫の山
 |
マイケル 「あ、来ましたかー。チェックポイントはこちらですよー。」 |
瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「遠方までご苦労さまです、私はマイケルです。 お疲れでしょう。とりあえずお茶でも。」 |
チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
 |
マイケル 「……少しは休めましたか?」 |
 |
マイケル 「それではさっさとおっ始めましょう。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんからねぇー!!」 |





ENo.228
鉄納戸 正人



鉄納戸 正人(テツナンド マサト)
26歳、男性
171cm 68kg
ウシク駅前のビルに入っている保険屋『保険カフェとげぬき本舗』の社員。
人当たりのいい温和な性格。恋人がいたことがないのが欠点画だ本人は気にしていない。
給料でおいしいものを食べたり自分を甘やかすのが趣味。
異能
おさっしいたします
『魚心蓼虫』
名刺を渡した相手の大雑把な好みがわかる。
営業周りの再訪問時に持っていくお土産の目安になる。
金曜日の夕食はカスミ区の洋食屋『六番街』のオムライスと決めている。
店舗
http://lisge.com/ib/talk.php?p=433
ヒカラビ荘に部屋を借りている。
http://lisge.com/ib/talk.php?p=329
ウシコーポA(http://lisge.com/ib/talk.php?s=240)は好きな階に好きにお店や事務所を入れてもらって構いません。
---
***
---
否定の世界『アンジニティ』の住人
咎人というにはたおやかな女性。
だがその本性は己を『色欲(Luxria)』と称する大罪の一席。
愛欲と破壊願望の入り混じった紛れもない罪人。
過度なサドでありマゾでありタチもネコもこなす。放置しても興奮する。
後述の能力で己の身体さえも改変できるので彼女の相手に性別は関係ない。
ハザマでは彼女の異能は「痛みの中に快を感じる場所を見出す目」として強化される。
また生来の在り様として『織成』を抱えており、
紐、あるいは糸といったものを操ることに長ける。
親和性の高い己の髪を伸ばし続けスカートを編みさらにはそこから櫛刃の短剣を織り成す。
そんな『罪』たる彼女は、異世界侵略に否定的である。
否定されて『堕ち』てくる者たちの欲を食らう方が暴力的で退廃的で好みだと彼女は笑う。
---
浅岡 百合子(アサオカ ユリコ)
熾盛天晴学園二年三組
(本稼働メインキャラ予定)
自分のことをリリィと呼んでと気さくに話しかけるギャル。
将来は留学を考えているらしく成績は良い。
天文部だが星に詳しいわけではない。勉強中。
電気信号に干渉するる異能『ククー・アミティエ』の持ち主だがスマホにさわらずメッセができるとかそういう。
本気を出せばインターネット上の情報を集められる。
また、本人が願えば人の強い感情も『受信』できる。
その方面で能力が暴走したトラウマがあるので自分からは使わない。
浅岡 愛菜(アサオカ アイナ)
熾盛天晴学園中等部。
現在は交通事故による怪我で入院している。
リハビリもだいぶん進んでいるとかなんとか。
---
・交流:正人も色欲も浅岡姉妹も遊んでくださる方を募集しています。
既知:両者ともに可能。オフィスが近かったり通うお店で見慣れていたり。アンジニティで彼女のうわさが流れていたかもしれない。
・許可:ラジオ紹介フリー、レンタルフリー。借りる際に報告していただけると嬉しいです。
注意書き:キャラクターがキャラクターですがよいこの栗鼠倫順守です。
---
虚無アイコンはEno.38様より。
---
取引や交流の打ち合わせなどコンタクト窓口
twitter @2904_YK_2905
26歳、男性
171cm 68kg
ウシク駅前のビルに入っている保険屋『保険カフェとげぬき本舗』の社員。
人当たりのいい温和な性格。恋人がいたことがないのが欠点画だ本人は気にしていない。
給料でおいしいものを食べたり自分を甘やかすのが趣味。
異能
おさっしいたします
『魚心蓼虫』
名刺を渡した相手の大雑把な好みがわかる。
営業周りの再訪問時に持っていくお土産の目安になる。
金曜日の夕食はカスミ区の洋食屋『六番街』のオムライスと決めている。
店舗
http://lisge.com/ib/talk.php?p=433
ヒカラビ荘に部屋を借りている。
http://lisge.com/ib/talk.php?p=329
ウシコーポA(http://lisge.com/ib/talk.php?s=240)は好きな階に好きにお店や事務所を入れてもらって構いません。
---
***
---
否定の世界『アンジニティ』の住人
咎人というにはたおやかな女性。
だがその本性は己を『色欲(Luxria)』と称する大罪の一席。
愛欲と破壊願望の入り混じった紛れもない罪人。
過度なサドでありマゾでありタチもネコもこなす。放置しても興奮する。
後述の能力で己の身体さえも改変できるので彼女の相手に性別は関係ない。
ハザマでは彼女の異能は「痛みの中に快を感じる場所を見出す目」として強化される。
また生来の在り様として『織成』を抱えており、
紐、あるいは糸といったものを操ることに長ける。
親和性の高い己の髪を伸ばし続けスカートを編みさらにはそこから櫛刃の短剣を織り成す。
そんな『罪』たる彼女は、異世界侵略に否定的である。
否定されて『堕ち』てくる者たちの欲を食らう方が暴力的で退廃的で好みだと彼女は笑う。
---
浅岡 百合子(アサオカ ユリコ)
熾盛天晴学園二年三組
(本稼働メインキャラ予定)
自分のことをリリィと呼んでと気さくに話しかけるギャル。
将来は留学を考えているらしく成績は良い。
天文部だが星に詳しいわけではない。勉強中。
電気信号に干渉するる異能『ククー・アミティエ』の持ち主だがスマホにさわらずメッセができるとかそういう。
本気を出せばインターネット上の情報を集められる。
また、本人が願えば人の強い感情も『受信』できる。
その方面で能力が暴走したトラウマがあるので自分からは使わない。
浅岡 愛菜(アサオカ アイナ)
熾盛天晴学園中等部。
現在は交通事故による怪我で入院している。
リハビリもだいぶん進んでいるとかなんとか。
---
・交流:正人も色欲も浅岡姉妹も遊んでくださる方を募集しています。
既知:両者ともに可能。オフィスが近かったり通うお店で見慣れていたり。アンジニティで彼女のうわさが流れていたかもしれない。
・許可:ラジオ紹介フリー、レンタルフリー。借りる際に報告していただけると嬉しいです。
注意書き:キャラクターがキャラクターですがよいこの栗鼠倫順守です。
---
虚無アイコンはEno.38様より。
---
取引や交流の打ち合わせなどコンタクト窓口
twitter @2904_YK_2905
30 / 30
276 PS
チナミ区
D-2
D-2







| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 2 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 櫛刃の短剣 | 武器 | 30 | 攻撃10 | 器用10 | - | 【射程1】 |
| 5 | 紅のリボン | 装飾 | 30 | 幸運10 | 幸運10 | - | |
| 6 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||
| 7 | カップルのカツカレー | 料理 | 31 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 8 | 鉄納戸色のロングスカート | 防具 | 33 | 敏捷10 | 敏捷10 | - | |
| 9 | 隙のない三つ編み | 武器 | 33 | 活力10 | - | - | 【射程1】 |
| 10 | |||||||
| 11 | エッグパフェ | 料理 | 32 | 防御10 | 治癒10 | - | |
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 13 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]風柳10(LV20)[装飾]敏捷15(LV30) | |||
| 14 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 15 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 呪術 | 7 | 呪詛/邪気/闇 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 32 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| ダークネス | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| カースバインド | 5 | 0 | 80 | 敵:闇撃&衰弱 | |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 | |
| ブラックアサルト | 5 | 0 | 90 | 敵:3連鎖闇撃&闇痛撃 | |
| イレイザー | 6 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
| クイックアナライズ | 5 | 0 | 200 | 敵全:AG減 | |
| ウィークポイント | 5 | 0 | 140 | 敵:3連痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
VERANDERING (ブレイク) |
0 | 20 | 敵:攻撃 | |
|
ルナファーファ (リトルリヴァイブ) |
0 | 140 | 味傷:復活LV増 | |
|
ひふみ祝詞 (スタードリーム) |
0 | 200 | 味全:HP増+祝福 | |
|
スタミナドリンク (ハイポーション) |
1 | 200 | 味傷:HP増&肉体・精神変調をDF化 | |
|
秘符【節制】 (アイシング) |
0 | 50 | 味傷:HP増&強制凍結 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]エキサイト | [ 3 ]キュアディジーズ | [ 1 ]サモン:ウルフ |
| [ 3 ]イバラ | [ 1 ]サモン:レッサーデーモン | [ 1 ]サモン:ナレハテ |
| [ 3 ]ポーションラッシュ |

PL / きあさゆうひ