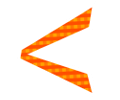<< 3:00>> 5:00




狭間世界来て、四回目の一時間。
この世界に来る度に、イバラシティで過ごした記憶を持ち込んで、狭間世界での一時間の記憶も甦る。
ふたつの記憶が入り込んだ状態が正常なのか。
それともとっくに異常が正常に成り代わっているのか。勝手に侵略されて、勝手に戦いに巻き込まれているというのに、何て理不尽なのだろうこの世界は。
赤い絵の具で真っ赤に染められたイバラシティを眺めて、少女は嘆息した。
「クロー。クロやー。おいクロ、クロクロクーロクロ」
まるで野良猫を呼び寄せるような声。
実際そうなのか分からないが、男の声に振り返る。
その男はご丁寧に膝をついて「ちっちっち」と猫を呼び寄せるアレをしていた。
「朝日ヶ丘先輩。わたしは野良猫じゃないって何度も言ってるじゃないですか」
「いやだって、クロって猫みたいだし。
実際呼ぶとこうやってすぐ来るからな。やっぱり猫でいいだろう。ほら、コーラ持ってきてやったぞ。
すまんがネクターは品切れだ」
コーラ瓶片手に、アメコミやアメリカのヒーロー映画に出てきそうなコスプレ男――此処ではマスクドアメリカと名乗る男は、そのまま地面に座ってコーラをラッパ飲みしている。
その姿、実に豪快であり、豪胆だ。
……と言いたいところだが、お気楽であることは確かで。
冷えたコーラ瓶を受け取って、男の隣に座る。
ご丁寧に蓋は開けられていて、すぐ飲めるようになっていた。
「キャンプカー引きこもり代表のクロが外にいるとは珍しいな。何だ、もうホームシックか? それとも中学生女子ならではのおセンチというやつか?
どちらにしても俺は慰めたり励ましたりしないぞ。そんなことするならキャンプカーを乗り回してラーメン屋を探しに行きたい。そろそろうどんとピザも食い飽きたからなぁ」
「大丈夫ですよ。ホームシックでもセンチメンタルでもないですから。最初に言ったじゃないですか。
わたしは、そんな繊細なメンタルを持ち合わせていないって」
瓶に口を付けて、コーラを一口。
未だにこの強い炭酸と、薬品のような不思議な味には慣れないけど、少しずつ美味しいと感じてきた。
「うむ、それでこそクロだ。
出会い頭に膝かっくんをかます強さは変わらないな。
やっぱりクロってメンタルがガンダニウム合金で出来てるんじゃないの? お母さんドムっぽいけど」
茶化しているのか、それとも本気なのか。
このマスクドアメリカこと――朝日ヶ丘マックの前では、この黒羽ももう演じることを諦めた様子で。
「母が医療従事者のドムで、父が研究者の赤い彗星ですよ。……というか朝日ヶ丘先輩、十五の小娘にガンダムネタ振るのやめましょうよ。
わたし、そんなに古いの知らないんですから」
頬を膨らませつつ、どんどん言い返す。
イバラシティでの彼女を知る人間なら、これがあの少女かと疑うかもしれない。
……そこで一旦、言葉を切って。
ゆっくりと息を吐く。
「でも、本当にそういうもので出来てたら良かったなぁって思います。そうしたらもっと、元気で長生きできて、やりたいことも沢山できたのに」
大好きなピアノも続けたかった。
歌も練習して、いつか舞台に立てるような女優も目指してみたかった。アイドルは恥ずかしいから無理だけど、舞台に立つ女優には憧れが強かった。
きっともう、誰も覚えていない。自分しか覚えていないだろう。幼稚園の頃に見に行った舞台があった。
内容はあまり覚えていないが、主人公である青年に恋心を寄せるものの、ヒロインではない彼女は選ばれず、舞台の途中で主人公にピアノを弾く――という場面が印象に残っている。
『素敵な曲だね、ありがとう』
『ご結婚おめでとうございます、ご主人様。これは、私からのせめてものお祝いです』
そんな彼女は物語の主役ではなく脇役で、この後の出番はなく、主人公はヒロインと、後から出てくるもう一人のヒロインとの間で葛藤するという……よくある恋愛ものの、人間関係が拗れて泥沼化した内容だった。
物語の結末も、主人公が誰を選んだかも覚えていない。
ただ、主人公に選ばれず、それでも祝福したいと願った彼女だけが印象に残っていた。
誰も彼も、彼女を忘れて。
主人公でさえも、舞台上で彼女の名前を一度しか呼んでなかった。
数年前、やっと見つけたパンフレット。
すっかり色褪せていたけど、登場人物やキャスト、あらすじが載っていて、時間を忘れるくらい、何度も何度も書かれている内容を読んだ。
忘れられていた彼女の名前は『黒羽』だった。
彼女の『名前』を借りたのは、本当に何となくだった。別に彼女に対して、何か強い感情やこだわりを持っていたわけではない。
強いて理由を挙げるなら――誰も覚えていない。忘れてくれる。誰の記憶にも残らない。
そんな彼女が羨ましいのと同時に、彼女みたいになりたかったからだ。
入退院を繰り返して、学校にもなかなか行けなかった。遠足や運動会、修学旅行といった学園行事にもほとんど参加できなかった。
友達と呼べる人はいなくて、きっと誰も自分の名前も存在も知らないし、覚えていないだろう。
このセーラー服だって結局、数回しか着られなかったのだから。
未練を抱えたまま、誰の記憶にも残らない。憶えていない。忘れられていく。
……否、忘れて欲しかったのだ。こんなに弱くて愚かで惨めで、何も出来ない自分を。
好きな人と結ばれることなく舞台を退場した『黒羽』と、今の自分を重ね合わせていたのかもしれない。
わたしは黒羽で、黒羽はわたし。
舞台装置の一つになることはとても気が楽で、目の前の辛い現実から逃避したかっただけ。
――わたしは臆病で、卑怯だから。
「まだ十五のガキんちょが何言ってるんだオメー。
まだ侵略戦争は終わってないぞ。せめてそのセリフはあと3話くらい進んでから言うべきだな。
そうしたら俺が平手打ち……は可哀想だからおしりペンペンして、クロがそこで親にもおしりペンペンされたことなかったのにという流れにしよう。
今の話は聞かなかったことにしてやるから、その代わり俺が今さりげなくゲップしたことも忘れてくれ。
ちょっと恥ずかしい」
「感傷に浸るわたしのすべてを台無しにしてくれる朝日ヶ丘先輩って本当にすごいですよね……わたしも今回の日記で大事なことを書いておくつもりだったのに、今のですべて吹っ飛びましたよ」
まだ半分も飲んでいないコーラ瓶を持って、呆れたようにマスクドアメリカを見上げた。
もしかしてわざとやっているのだろうか。
疑惑の眼差しを向けたところで、男はやれやれと立ち上がった。
「こんなこと言うのも何だがな、気持ちというか気概も大事だぞ。運命なんてくそ食らえだなんて俺は言わないし、そういうのは正統派主人公の台詞だ。俺は絶対言わない。大事なことだから二回言ったぞ。
だがクロは可愛い後輩だからな、先輩面してやってもいいだろう。
もっと楽のちんに考えろよ。答えはそろそろ見つかりそうなんだろう。そうじゃないのか、クロ?」
黒羽の頭をぽんぽん、と軽く叩く。
彼なりの励ましか、慰めのつもりなのか。
「あ、朝日ヶ丘せんぱ」
「おっと、感動的な場面はよしてくれよ。またゲップが出てしまう」
「いえ……ゲップはもういいんですが、何か気色の悪い草を思いっきり踏んでいるので」
マスクドアメリカが踏んだ草から、形容しがたい色の汁が溢れ出し、地面をぐっちょぐちょに濡らす。
正直……ものすごくやばい色のそれ。
ついでに異臭も放ち始める。
「…………クロ、俺が言わずともわかっているな」
「は、はい」
険しい表情の男を見て、慌てて立ち上がる。
男に向き直り、コーラ瓶を片手に持った。男は小さく頷き、少女と向かい合う。お互いに無言。訪れる静寂。空気の流れが変わり、二人の間に緊張が走る。
真剣な表情で向き合い、少女は瞬時にして、男との距離を一気に詰めた。
「エーンガチョ!」
「はい、切りました!」
空いている手で、マスクドアメリカのポーズに合わせて指と指の間にチョップ。男の指は離れ、緊張感は薄れ始めた。
――任務完了である。
「あー、でもやっぱ超臭いわこれ。ファブっても無理なやつ。
戻ったら洗おう……」
帰り道。どうにも異臭がすごいので、少し距離を置いて一緒にキャンプカーへと戻る。
歩幅が違うのでどうしてもちょこまかと男を追う形になりつつ、彼の後ろをついていく。
「そうだクロ。お前のCross+Roseなんだけどな」
「あ、はい。前回、通信の途中で急に壊れちゃって……修理しないとだめですか?」
「いや、壊れてないぞあれ。電池切れだったから充電しといた。多分もう動くんじゃないかな」
「え……あれって電池切れとかあるんですか」
前回、高宮清春への通信の途中で切れてしまい、慌ててマスクドアメリカのところへ持って行ったのだが――まさかの電池切れとは。
次に彼へ連絡する時になんて言えばいいのだろう。
いや、そもそも前回どこまで彼に通信が届いていただろうか。
(……最後の言葉、届いてなければいいのですが)
内容を思い出して、恥ずかしくなる。
ぶんぶんと、大きく頭を横に振った。今は思い出すのはやめておく。恥ずかしさで憤死するかもしれない。
「そりゃあるだろ。因みに俺はスマホの充電も欠かさない。学校の隠し部屋に充電器を持ち込み、常に残量100%だからな。そんじょそこらのにわかスマホマスターと一緒にするんじゃない。
でもクロはスマホ持ってないもんな~充電とか、そこら辺わかる? そもそも充電器の使い方知らなそうだよな」
「う……じゅ、充電って言葉の意味は分かりますから。で、でもやり方はよくわからないですけど」
まさかここにきて、電子機器に弱いことが仇になるとは予想外だった。次回からは気を付けよう、本当に。
男の後を追って、キャンプカーの中へと入っていく。
『不幸せなのは我々だけではないようだ。
この世界という広大な劇場は、
我々が演じている場面よりもっと悲惨な見世物を見せてくれる』

答えは、多分もうとっくに見つかっている。
あとはわたしが、どちらかを選ばなくてはいけない。
ただ、それだけのこと。



ENo.138 キバ とのやりとり

ENo.333 まい子 とのやりとり

ENo.420 清春 とのやりとり

ENo.761 ×××× とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 ねくた~ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(16⇒17)
今回の全戦闘において 体力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









マスクドアメリカ(107) は ド根性雑草 を入手!
黒羽(184) は ド根性雑草 を入手!
マゾメガネ(1181) は ド根性雑草 を入手!
牡丹(1200) は 吸い殻 を入手!
マスクドアメリカ(107) は 羽 を入手!
マゾメガネ(1181) は 何か固い物体 を入手!
マゾメガネ(1181) は 毛 を入手!
黒羽(184) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
牡丹(1200) のもとに 大黒猫 が微笑を浮かべて近づいてきます。



解析LV を 3 UP!(LV1⇒4、-3CP)
合成LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
マゾメガネ(1181) により ItemNo.11 何か固い物体 から装飾『フローライト』を作製してもらいました!
⇒ フローライト/装飾:強さ45/[効果1]反護10 [効果2]- [効果3]-
牡丹(1200) により ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『氷雨』を作製してもらいました!
⇒ 氷雨/武器:強さ39/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
マスクドアメリカ(107) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『そばつゆ』をつくってもらいました!
⇒ そばつゆ/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
安里杏莉(60) とカードを交換しました!
誰かへの本命チョコ (ヒール)


クリエイト:ウェポン を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:ウェポン を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:ウェポン を研究しました!(深度2⇒3)



マスクドアメリカ(107) に移動を委ねました。
チナミ区 L-14(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 M-14(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 N-14(草原)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 O-14(草原)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 O-15(草原)に移動!(体調13⇒12)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



『幕間:ハザマにて、お気に召すまま』
狭間世界来て、四回目の一時間。
この世界に来る度に、イバラシティで過ごした記憶を持ち込んで、狭間世界での一時間の記憶も甦る。
ふたつの記憶が入り込んだ状態が正常なのか。
それともとっくに異常が正常に成り代わっているのか。勝手に侵略されて、勝手に戦いに巻き込まれているというのに、何て理不尽なのだろうこの世界は。
赤い絵の具で真っ赤に染められたイバラシティを眺めて、少女は嘆息した。
「クロー。クロやー。おいクロ、クロクロクーロクロ」
まるで野良猫を呼び寄せるような声。
実際そうなのか分からないが、男の声に振り返る。
その男はご丁寧に膝をついて「ちっちっち」と猫を呼び寄せるアレをしていた。
「朝日ヶ丘先輩。わたしは野良猫じゃないって何度も言ってるじゃないですか」
「いやだって、クロって猫みたいだし。
実際呼ぶとこうやってすぐ来るからな。やっぱり猫でいいだろう。ほら、コーラ持ってきてやったぞ。
すまんがネクターは品切れだ」
コーラ瓶片手に、アメコミやアメリカのヒーロー映画に出てきそうなコスプレ男――此処ではマスクドアメリカと名乗る男は、そのまま地面に座ってコーラをラッパ飲みしている。
その姿、実に豪快であり、豪胆だ。
……と言いたいところだが、お気楽であることは確かで。
冷えたコーラ瓶を受け取って、男の隣に座る。
ご丁寧に蓋は開けられていて、すぐ飲めるようになっていた。
「キャンプカー引きこもり代表のクロが外にいるとは珍しいな。何だ、もうホームシックか? それとも中学生女子ならではのおセンチというやつか?
どちらにしても俺は慰めたり励ましたりしないぞ。そんなことするならキャンプカーを乗り回してラーメン屋を探しに行きたい。そろそろうどんとピザも食い飽きたからなぁ」
「大丈夫ですよ。ホームシックでもセンチメンタルでもないですから。最初に言ったじゃないですか。
わたしは、そんな繊細なメンタルを持ち合わせていないって」
瓶に口を付けて、コーラを一口。
未だにこの強い炭酸と、薬品のような不思議な味には慣れないけど、少しずつ美味しいと感じてきた。
「うむ、それでこそクロだ。
出会い頭に膝かっくんをかます強さは変わらないな。
やっぱりクロってメンタルがガンダニウム合金で出来てるんじゃないの? お母さんドムっぽいけど」
茶化しているのか、それとも本気なのか。
このマスクドアメリカこと――朝日ヶ丘マックの前では、この黒羽ももう演じることを諦めた様子で。
「母が医療従事者のドムで、父が研究者の赤い彗星ですよ。……というか朝日ヶ丘先輩、十五の小娘にガンダムネタ振るのやめましょうよ。
わたし、そんなに古いの知らないんですから」
頬を膨らませつつ、どんどん言い返す。
イバラシティでの彼女を知る人間なら、これがあの少女かと疑うかもしれない。
……そこで一旦、言葉を切って。
ゆっくりと息を吐く。
「でも、本当にそういうもので出来てたら良かったなぁって思います。そうしたらもっと、元気で長生きできて、やりたいことも沢山できたのに」
大好きなピアノも続けたかった。
歌も練習して、いつか舞台に立てるような女優も目指してみたかった。アイドルは恥ずかしいから無理だけど、舞台に立つ女優には憧れが強かった。
きっともう、誰も覚えていない。自分しか覚えていないだろう。幼稚園の頃に見に行った舞台があった。
内容はあまり覚えていないが、主人公である青年に恋心を寄せるものの、ヒロインではない彼女は選ばれず、舞台の途中で主人公にピアノを弾く――という場面が印象に残っている。
『素敵な曲だね、ありがとう』
『ご結婚おめでとうございます、ご主人様。これは、私からのせめてものお祝いです』
そんな彼女は物語の主役ではなく脇役で、この後の出番はなく、主人公はヒロインと、後から出てくるもう一人のヒロインとの間で葛藤するという……よくある恋愛ものの、人間関係が拗れて泥沼化した内容だった。
物語の結末も、主人公が誰を選んだかも覚えていない。
ただ、主人公に選ばれず、それでも祝福したいと願った彼女だけが印象に残っていた。
誰も彼も、彼女を忘れて。
主人公でさえも、舞台上で彼女の名前を一度しか呼んでなかった。
数年前、やっと見つけたパンフレット。
すっかり色褪せていたけど、登場人物やキャスト、あらすじが載っていて、時間を忘れるくらい、何度も何度も書かれている内容を読んだ。
忘れられていた彼女の名前は『黒羽』だった。
彼女の『名前』を借りたのは、本当に何となくだった。別に彼女に対して、何か強い感情やこだわりを持っていたわけではない。
強いて理由を挙げるなら――誰も覚えていない。忘れてくれる。誰の記憶にも残らない。
そんな彼女が羨ましいのと同時に、彼女みたいになりたかったからだ。
入退院を繰り返して、学校にもなかなか行けなかった。遠足や運動会、修学旅行といった学園行事にもほとんど参加できなかった。
友達と呼べる人はいなくて、きっと誰も自分の名前も存在も知らないし、覚えていないだろう。
このセーラー服だって結局、数回しか着られなかったのだから。
未練を抱えたまま、誰の記憶にも残らない。憶えていない。忘れられていく。
……否、忘れて欲しかったのだ。こんなに弱くて愚かで惨めで、何も出来ない自分を。
好きな人と結ばれることなく舞台を退場した『黒羽』と、今の自分を重ね合わせていたのかもしれない。
わたしは黒羽で、黒羽はわたし。
舞台装置の一つになることはとても気が楽で、目の前の辛い現実から逃避したかっただけ。
――わたしは臆病で、卑怯だから。
「まだ十五のガキんちょが何言ってるんだオメー。
まだ侵略戦争は終わってないぞ。せめてそのセリフはあと3話くらい進んでから言うべきだな。
そうしたら俺が平手打ち……は可哀想だからおしりペンペンして、クロがそこで親にもおしりペンペンされたことなかったのにという流れにしよう。
今の話は聞かなかったことにしてやるから、その代わり俺が今さりげなくゲップしたことも忘れてくれ。
ちょっと恥ずかしい」
「感傷に浸るわたしのすべてを台無しにしてくれる朝日ヶ丘先輩って本当にすごいですよね……わたしも今回の日記で大事なことを書いておくつもりだったのに、今のですべて吹っ飛びましたよ」
まだ半分も飲んでいないコーラ瓶を持って、呆れたようにマスクドアメリカを見上げた。
もしかしてわざとやっているのだろうか。
疑惑の眼差しを向けたところで、男はやれやれと立ち上がった。
「こんなこと言うのも何だがな、気持ちというか気概も大事だぞ。運命なんてくそ食らえだなんて俺は言わないし、そういうのは正統派主人公の台詞だ。俺は絶対言わない。大事なことだから二回言ったぞ。
だがクロは可愛い後輩だからな、先輩面してやってもいいだろう。
もっと楽のちんに考えろよ。答えはそろそろ見つかりそうなんだろう。そうじゃないのか、クロ?」
黒羽の頭をぽんぽん、と軽く叩く。
彼なりの励ましか、慰めのつもりなのか。
「あ、朝日ヶ丘せんぱ」
「おっと、感動的な場面はよしてくれよ。またゲップが出てしまう」
「いえ……ゲップはもういいんですが、何か気色の悪い草を思いっきり踏んでいるので」
マスクドアメリカが踏んだ草から、形容しがたい色の汁が溢れ出し、地面をぐっちょぐちょに濡らす。
正直……ものすごくやばい色のそれ。
ついでに異臭も放ち始める。
「…………クロ、俺が言わずともわかっているな」
「は、はい」
険しい表情の男を見て、慌てて立ち上がる。
男に向き直り、コーラ瓶を片手に持った。男は小さく頷き、少女と向かい合う。お互いに無言。訪れる静寂。空気の流れが変わり、二人の間に緊張が走る。
真剣な表情で向き合い、少女は瞬時にして、男との距離を一気に詰めた。
「エーンガチョ!」
「はい、切りました!」
空いている手で、マスクドアメリカのポーズに合わせて指と指の間にチョップ。男の指は離れ、緊張感は薄れ始めた。
――任務完了である。
「あー、でもやっぱ超臭いわこれ。ファブっても無理なやつ。
戻ったら洗おう……」
帰り道。どうにも異臭がすごいので、少し距離を置いて一緒にキャンプカーへと戻る。
歩幅が違うのでどうしてもちょこまかと男を追う形になりつつ、彼の後ろをついていく。
「そうだクロ。お前のCross+Roseなんだけどな」
「あ、はい。前回、通信の途中で急に壊れちゃって……修理しないとだめですか?」
「いや、壊れてないぞあれ。電池切れだったから充電しといた。多分もう動くんじゃないかな」
「え……あれって電池切れとかあるんですか」
前回、高宮清春への通信の途中で切れてしまい、慌ててマスクドアメリカのところへ持って行ったのだが――まさかの電池切れとは。
次に彼へ連絡する時になんて言えばいいのだろう。
いや、そもそも前回どこまで彼に通信が届いていただろうか。
(……最後の言葉、届いてなければいいのですが)
内容を思い出して、恥ずかしくなる。
ぶんぶんと、大きく頭を横に振った。今は思い出すのはやめておく。恥ずかしさで憤死するかもしれない。
「そりゃあるだろ。因みに俺はスマホの充電も欠かさない。学校の隠し部屋に充電器を持ち込み、常に残量100%だからな。そんじょそこらのにわかスマホマスターと一緒にするんじゃない。
でもクロはスマホ持ってないもんな~充電とか、そこら辺わかる? そもそも充電器の使い方知らなそうだよな」
「う……じゅ、充電って言葉の意味は分かりますから。で、でもやり方はよくわからないですけど」
まさかここにきて、電子機器に弱いことが仇になるとは予想外だった。次回からは気を付けよう、本当に。
男の後を追って、キャンプカーの中へと入っていく。
『不幸せなのは我々だけではないようだ。
この世界という広大な劇場は、
我々が演じている場面よりもっと悲惨な見世物を見せてくれる』

答えは、多分もうとっくに見つかっている。
あとはわたしが、どちらかを選ばなくてはいけない。
ただ、それだけのこと。



ENo.138 キバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.333 まい子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.420 清春 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.761 ×××× とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
マスクドアメリカ 「言い忘れたがキャンプカーのガソリンあと3更新分しか持たない」 |
 |
黒羽 「千の技は持っていませんが、中学生っぽくない雰囲気なら負けませんよ」 |
 |
杏梨 「おっ、お……お待たせ!」 |
 |
杏梨 「ごめん、 ちょっと長風呂しちゃったけど、ちゃんと仕事はするよ」 |
| 牡丹 「ちゃんと装備作れたかな……」 |
ItemNo.6 ねくた~ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(16⇒17)
今回の全戦闘において 体力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





はいずるものたち
|
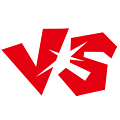 |
しわしわポテトおいしい
|



マスクドアメリカ(107) は ド根性雑草 を入手!
黒羽(184) は ド根性雑草 を入手!
マゾメガネ(1181) は ド根性雑草 を入手!
牡丹(1200) は 吸い殻 を入手!
マスクドアメリカ(107) は 羽 を入手!
マゾメガネ(1181) は 何か固い物体 を入手!
マゾメガネ(1181) は 毛 を入手!
黒羽(184) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
牡丹(1200) のもとに 大黒猫 が微笑を浮かべて近づいてきます。



解析LV を 3 UP!(LV1⇒4、-3CP)
合成LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
マゾメガネ(1181) により ItemNo.11 何か固い物体 から装飾『フローライト』を作製してもらいました!
⇒ フローライト/装飾:強さ45/[効果1]反護10 [効果2]- [効果3]-
 |
菫 「これ、中々いい感じにできたのではないでしょうか?」 |
牡丹(1200) により ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『氷雨』を作製してもらいました!
⇒ 氷雨/武器:強さ39/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
マスクドアメリカ(107) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『そばつゆ』をつくってもらいました!
⇒ そばつゆ/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
マスクドアメリカ 「蕎麦はない」 |
安里杏莉(60) とカードを交換しました!
誰かへの本命チョコ (ヒール)


クリエイト:ウェポン を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:ウェポン を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:ウェポン を研究しました!(深度2⇒3)



マスクドアメリカ(107) に移動を委ねました。
チナミ区 L-14(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 M-14(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 N-14(草原)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 O-14(草原)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 O-15(草原)に移動!(体調13⇒12)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――



アベンジャーズ新作は上映時間3時間!
|
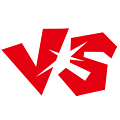 |
ハザマに生きるもの
|




家に帰ったらみんなでカピバラの特番見るんだ……
|
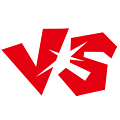 |
アベンジャーズ新作は上映時間3時間!
|


ENo.184
黒羽



◆黒羽◆【クロバネ】
15歳/154cmくらい
濡羽色の髪に蒼い瞳、スカートの長い濃紺のセーラー服。
木刀袋を持ち歩く少女は、黒羽と名乗る。
表情も感情表現も豊かで、よく笑う。大人に憧れて背伸びをしている、ちょっと夢見がちでロマンチストな中学三年生。
15歳/154cmくらい
濡羽色の髪に蒼い瞳、スカートの長い濃紺のセーラー服。
木刀袋を持ち歩く少女は、黒羽と名乗る。
表情も感情表現も豊かで、よく笑う。大人に憧れて背伸びをしている、ちょっと夢見がちでロマンチストな中学三年生。
12 / 30
234 PS
チナミ区
O-15
O-15




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | 氷雨 | 武器 | 39 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]火纏10(LV25)[防具]鎮痛10(LV15)[装飾]復活10(LV15) | |||
| 7 | そばつゆ | 料理 | 33 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 8 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 9 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]器用10(LV10)[防具]活力10(LV10)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
| 11 | フローライト | 装飾 | 45 | 反護10 | - | - | |
| 12 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 13 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 解析 | 4 | 精確/対策/装置 |
| 合成 | 29 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 細雪 (ブレイク) | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 涙雨 (ピンポイント) | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 時雨 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 氷雨 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| 玲瓏 (ヒール) | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 真朱 (ティンダー) | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| 決3 | 澪の糸 (アクアヒール) | 6 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| 決3 | 蝉時雨 (ヒールポーション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 |
| 海神 (ボロウライフ) | 6 | 0 | 60 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| アムリタ (マジックポーション) | 5 | 0 | 60 | 自:祝福 | |
| 慈雨 (ヒーリングスキル) | 5 | 0 | 50 | 自:HL増 | |
| 曼珠沙華 (ファイアボール) | 6 | 0 | 180 | 敵全:火撃 | |
| 海鳴り (シーアーチン) | 6 | 0 | 130 | 敵列:水痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 黄昏 (攻撃) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 夕闇 (防御) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 星月夜 (器用) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 三日月 (敏捷) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 十六夜 (回復) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 朧月夜 (活力) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 空色 (体力) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 藍色 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 茜色 (鎮痛) | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運の女神 (幸運) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 睡蓮 (水特性回復) | 6 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
一閃 (ピンポイント) |
0 | 20 | 敵:痛撃 | |
|
Card:blessing (プロビデンス) |
0 | 120 | 味全:祝福 | |
| 決3 |
美味しくて癒やされる素敵な紅茶 (アクアヒール) |
0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
|
誰かへの本命チョコ (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]アクアヒール | [ 3 ]クリエイト:ウェポン |
| [ 1 ]フリーズ | [ 3 ]ヒールハーブ | [ 3 ]シーアーチン |

PL / 史郎