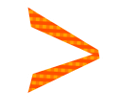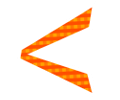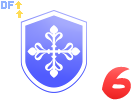<< 3:00>> 5:00




ヒト
僕は隣人を■している。
僕はあらゆる他者を■している。
カミサマ
僕は世界を■している。
■でもいい。
■■■■でもいい。
・・・・・・・・・・・・・・・
とにかく、■■■■■■に■■■■なければーーそう、■に■■■なければーー
■も■■くれない■■も。
■■を■■する■■■■■■■も。
そんな■■に■る■■■も。
何もかも、■■に■■■しまいそうだった。
この『僕』が、まともな食事を摂るのは、一体いつぶりだろう。
そもそも、あの世界には碌なものがなかったのだった、か?
よく覚えていないけれど。
とにかくーー行きずりに行動を共にすることとなった、ニコニコと愛想のよい青年が料理を作ってくれた。
しかし、実のところ。
この身体に残っている感覚は、そう多くはない。
厭に鋭敏な視覚と聴覚。僅かな触覚と、鈍い痛覚。
思い返せば、この姿に変成してからは空腹を覚えたこともない。
だから、食事をする必要がなかった。ずっと忘れていた。今も、きっと、本当は必要ないのだろう。
対応する器官が存在しないのだから、それも当然かもしれないが。
呼吸器官も、消化器官も、ーー心臓さえも。
この身体には、人体を構成する臓器の大部分が備わっていない。
『ひとのかたち』こそ保っているものの、最早『ひと』では有り得ない。
心だけでなく、遂には姿すら模倣となった。或いは、ただの残滓かもしれない。
本当に、本当に、この胸の内には空虚さが募るばかりでーー何も、無い。
それでも、青年が作ったものを『よいもの』なのだろうと認識できるだけの機微は、まだ残っている。
ここにはきっと、心が込められている。
どれほど努めても得られなかったもの。
終ぞ、理解できぬままだったもの。
決定的な欠落。致命的な欠陥。
けれど、口があって歯があるのなら。喉があるのなら。
少なくとも、噛み砕いて飲み込むぐらいは、可能な筈だ。
口へ入れる。味を感じることはできない。
嚥下する。不思議と、空の胸腔へ落ちてくることはなかった。
「……ありがとう、ごちそうさま」



ENo.492 つづり とのやりとり

ENo.708 雛 とのやりとり

ENo.1171 クロウラ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 ポイントカード付きのハンバーガー を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









蜘蛛型の女怪(175) は ネジ を入手!
ウィンストン兄弟(565) は ネジ を入手!
××××(761) は ネジ を入手!
××××(761) は ボロ布 を入手!
蜘蛛型の女怪(175) は 毛 を入手!
蜘蛛型の女怪(175) は 何か固い物体 を入手!
ウィンストン兄弟(565) は 毛 を入手!



幻術LV を 1 DOWN。(LV5⇒4、+1CP、-1FP)
領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
ItemNo.6 ネジ から装飾『普通の鋏』を作製しました!
⇒ 普通の鋏/装飾:強さ58/[効果1]貫通10 [効果2]- [効果3]-
蜘蛛型の女怪(175) により ItemNo.5 火炎瓶 に ItemNo.8 毛 を付加してもらいました!
⇒ 火炎瓶/武器:強さ36/[効果1]炎上10 [効果2]束縛10 [効果3]-【射程5】
握力(523) とカードを交換しました!
デリシャス上海は毎日営業中!! (インパクト)


ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度2⇒3)
エアスラスト を研究しました!(深度2⇒3)
テリトリー を習得!
ヒールミスト を習得!



チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調14⇒13)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



ヒト
僕は隣人を■している。
僕はあらゆる他者を■している。
カミサマ
僕は世界を■している。
■のことは■さなくていい。
ただ、■することだけ、■■に■■■■だけを■してくれるなら。
それだけで、良かった。
ただ、■することだけ、■■に■■■■だけを■してくれるなら。
それだけで、良かった。
■でもいい。
■■■■でもいい。
・・・・・・・・・・・・・・・
とにかく、■■■■■■に■■■■なければーーそう、■に■■■なければーー
■も■■くれない■■も。
■■を■■する■■■■■■■も。
そんな■■に■る■■■も。
何もかも、■■に■■■しまいそうだった。
ーー嗚呼、それは。
■■
何と■■で■■な、《■■》だろう。
■■
何と■■で■■な、《■■》だろう。
この『僕』が、まともな食事を摂るのは、一体いつぶりだろう。
そもそも、あの世界には碌なものがなかったのだった、か?
よく覚えていないけれど。
とにかくーー行きずりに行動を共にすることとなった、ニコニコと愛想のよい青年が料理を作ってくれた。
しかし、実のところ。
この身体に残っている感覚は、そう多くはない。
厭に鋭敏な視覚と聴覚。僅かな触覚と、鈍い痛覚。
思い返せば、この姿に変成してからは空腹を覚えたこともない。
だから、食事をする必要がなかった。ずっと忘れていた。今も、きっと、本当は必要ないのだろう。
対応する器官が存在しないのだから、それも当然かもしれないが。
呼吸器官も、消化器官も、ーー心臓さえも。
この身体には、人体を構成する臓器の大部分が備わっていない。
『ひとのかたち』こそ保っているものの、最早『ひと』では有り得ない。
心だけでなく、遂には姿すら模倣となった。或いは、ただの残滓かもしれない。
本当に、本当に、この胸の内には空虚さが募るばかりでーー何も、無い。
それでも、青年が作ったものを『よいもの』なのだろうと認識できるだけの機微は、まだ残っている。
ここにはきっと、心が込められている。
どれほど努めても得られなかったもの。
終ぞ、理解できぬままだったもの。
決定的な欠落。致命的な欠陥。
けれど、口があって歯があるのなら。喉があるのなら。
少なくとも、噛み砕いて飲み込むぐらいは、可能な筈だ。
口へ入れる。味を感じることはできない。
嚥下する。不思議と、空の胸腔へ落ちてくることはなかった。
「……ありがとう、ごちそうさま」
それは、何を満たしたのだろう。
それとも、ただ、無為に消費してしまっただけなのだろうか。
それとも、ただ、無為に消費してしまっただけなのだろうか。



ENo.492 つづり とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.708 雛 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1171 クロウラ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
絃 「ありがとう、ですね。装備は失くさないように、食べないように気をつけるですよ」 |
ItemNo.7 ポイントカード付きのハンバーガー を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





TeamNo.101
|
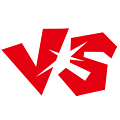 |
☆来ィやぁ☆けだまさんチーム
|



蜘蛛型の女怪(175) は ネジ を入手!
ウィンストン兄弟(565) は ネジ を入手!
××××(761) は ネジ を入手!
××××(761) は ボロ布 を入手!
蜘蛛型の女怪(175) は 毛 を入手!
蜘蛛型の女怪(175) は 何か固い物体 を入手!
ウィンストン兄弟(565) は 毛 を入手!



幻術LV を 1 DOWN。(LV5⇒4、+1CP、-1FP)
領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
ItemNo.6 ネジ から装飾『普通の鋏』を作製しました!
⇒ 普通の鋏/装飾:強さ58/[効果1]貫通10 [効果2]- [効果3]-
蜘蛛型の女怪(175) により ItemNo.5 火炎瓶 に ItemNo.8 毛 を付加してもらいました!
⇒ 火炎瓶/武器:強さ36/[効果1]炎上10 [効果2]束縛10 [効果3]-【射程5】
 |
あーん……もぐ……むぐむぐ…… 「ちょっとくらいなら味見……美味しくないですねこれ……わたくしの口の中が毛だらけ……」 |
握力(523) とカードを交換しました!
デリシャス上海は毎日営業中!! (インパクト)


ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度2⇒3)
エアスラスト を研究しました!(深度2⇒3)
テリトリー を習得!
ヒールミスト を習得!



チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調14⇒13)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――









ENo.761
イザイア・クライスト



プロフ絵はメイン2種、サブ1種。
置きレスの民です。どうぞよしなに。
―――――――――――――――
名前:Isaiah Kleist
年齢:24歳
性別:男
身長:176cm
職場:http://lisge.com/ib/talk.php?s=99
ツクナミ区に居を構える雑貨屋《宙(ソラ)の仔猫堂》の仕入れ担当。
普段は店のバックヤードにいたり、店内ディスプレイを弄ったり、街中をぶらついて買い付けや委託作家との交流をしていたりする。
レジに立っていることもあるが、人相が悪く胡散臭い。
顔面の凶悪さに反し、誰に対してもフランクで面倒見のよいマゾ。
マゾはライフワーク。
生まれ持った異能の性質から、大抵の場合、応急手当セットとちょっとしたお菓子の類を持ち歩いている。
何やかんやで家出してイバラシティに流れ着いた為、使っている名称は偽名。
御祖神社で譲り受けた紅い鋏をお守りにしている。
異能:受罰快楽《ペインホリック》
他者の【痛み】を自身に移し替えることができる異能。
発動の際には対象者を『視界の範囲内』に入れる必要があるが、発動後は『認識の範囲内』にいる限り効果を維持できる。
同一箇所に【痛み】のみを譲り受けるため、治癒とは異なる。
最大捕捉人数は一度につき一人。
複数の相手から一度に移し替えることはできないが、順にであれば、異能者が耐え続けられる限り、際限なく痛みを蓄積できる。
要するにリアル「痛いの痛いの飛んでいけ」。やりすぎると当然ショック死する。
ハザマ内で異能が強くなると、任意の相手に【痛み】を譲渡することが可能となる。
また、感覚が鋭敏になる為、視認含め、『認識できる範囲』が格段に広くなる。
最大捕捉人数に変わりはない為、より強い【痛み】を与えようとすると、一旦自身に蓄積しなければならない。痛覚ルンバ。
――それが、彼の有する記憶。
しかし、家を飛び出した彼が実際に辿り着いたのはイバラシティではない。
それはサイハテ、何者にもなれなかった男が迷い込んだ奈落。
《否定の世界》アンジニティ。
総ては泡沫の夢幻。
―――――――――――――――
サブキャラクター
伊勢守 殊代(いせかみ ことしろ)
伊勢守 咲耶(いせかみ さくや)
双子の兄妹。
相良伊橋高校1-2に所属。
兄の異能は【奴隷遣い(サディスティック・オーダー)】、他者にごく簡単な命令を実行させることができる。
少し強い暗示のようなもので、人によってかかりやすさはまちまち。
妹の異能は【木花開耶比売(コノハナノサクヤヒメ)】、生物の生命活動を活性化させることができる。
傷の治癒を早めたり、植物を素早く成長させたり。
置きレスの民です。どうぞよしなに。
―――――――――――――――
名前:Isaiah Kleist
年齢:24歳
性別:男
身長:176cm
職場:http://lisge.com/ib/talk.php?s=99
ツクナミ区に居を構える雑貨屋《宙(ソラ)の仔猫堂》の仕入れ担当。
普段は店のバックヤードにいたり、店内ディスプレイを弄ったり、街中をぶらついて買い付けや委託作家との交流をしていたりする。
レジに立っていることもあるが、人相が悪く胡散臭い。
顔面の凶悪さに反し、誰に対してもフランクで面倒見のよいマゾ。
マゾはライフワーク。
生まれ持った異能の性質から、大抵の場合、応急手当セットとちょっとしたお菓子の類を持ち歩いている。
何やかんやで家出してイバラシティに流れ着いた為、使っている名称は偽名。
御祖神社で譲り受けた紅い鋏をお守りにしている。
異能:受罰快楽《ペインホリック》
他者の【痛み】を自身に移し替えることができる異能。
発動の際には対象者を『視界の範囲内』に入れる必要があるが、発動後は『認識の範囲内』にいる限り効果を維持できる。
同一箇所に【痛み】のみを譲り受けるため、治癒とは異なる。
最大捕捉人数は一度につき一人。
複数の相手から一度に移し替えることはできないが、順にであれば、異能者が耐え続けられる限り、際限なく痛みを蓄積できる。
要するにリアル「痛いの痛いの飛んでいけ」。やりすぎると当然ショック死する。
ハザマ内で異能が強くなると、任意の相手に【痛み】を譲渡することが可能となる。
また、感覚が鋭敏になる為、視認含め、『認識できる範囲』が格段に広くなる。
最大捕捉人数に変わりはない為、より強い【痛み】を与えようとすると、一旦自身に蓄積しなければならない。痛覚ルンバ。
――それが、彼の有する記憶。
しかし、家を飛び出した彼が実際に辿り着いたのはイバラシティではない。
それはサイハテ、何者にもなれなかった男が迷い込んだ奈落。
《否定の世界》アンジニティ。
総ては泡沫の夢幻。
―――――――――――――――
サブキャラクター
伊勢守 殊代(いせかみ ことしろ)
伊勢守 咲耶(いせかみ さくや)
双子の兄妹。
相良伊橋高校1-2に所属。
兄の異能は【奴隷遣い(サディスティック・オーダー)】、他者にごく簡単な命令を実行させることができる。
少し強い暗示のようなもので、人によってかかりやすさはまちまち。
妹の異能は【木花開耶比売(コノハナノサクヤヒメ)】、生物の生命活動を活性化させることができる。
傷の治癒を早めたり、植物を素早く成長させたり。
13 / 30
173 PS
チナミ区
J-15
J-15








| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | 敏捷10 | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 赤いピアス | 装飾 | 25 | 器用10 | - | - | |
| 5 | 火炎瓶 | 武器 | 36 | 炎上10 | 束縛10 | - | 【射程5】 |
| 6 | 普通の鋏 | 装飾 | 58 | 貫通10 | - | - | |
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | |||||||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 幻術 | 4 | 夢幻/精神/光 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 29 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| 応急手当 (ヒール) | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練2 | エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| AllegRo (ヘイスト) | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| hAlo effect (シャイン) | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
| 練1 | tRAnquIlAIze (ヒールポーション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 |
| sonIc AegIs (プロテクション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| sonIc buRst (エアシュート) | 5 | 0 | 80 | 敵:風撃&連続減 | |
| pAin hOLiC_im. (リフレクション) | 5 | 0 | 60 | 自:反射 | |
| スパイン | 5 | 0 | 110 | 自:反撃LV増 | |
| sCissOrs CrOss (ライトセイバー) | 6 | 0 | 110 | 敵貫:光痛撃 | |
| fAIlnAught (インシジョン) | 5 | 0 | 60 | 敵:風痛撃+領域値[風]3以上なら、更に風痛撃 | |
| pAin hOLiC_sA. (ブロック) | 6 | 0 | 60 | 味傷:HP増+護衛 | |
| puRgAtRIum cARol (ハルシネイト) | 5 | 0 | 90 | 敵列:光撃&混乱 | |
| プロビデンス | 5 | 0 | 120 | 味全:祝福 | |
| howlIng dIsAstAR (ウィルスゾーン) | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| stReAm scReAm (コロージョン) | 5 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 | |
| テリトリー | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |
| ヒールミスト | 5 | 2 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程4以上ならAT減(1T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 医学の心得 (回復) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 痛覚麻痺 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 被虐の怪物 (鎮痛) | 6 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
狐のおまじない (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
怠惰なる破壊神 (ブラックリリィ) |
0 | 140 | 自:闇特性・朦朧LV増 | |
|
断線 (テリトリー) |
0 | 160 | 味列:DX増 | |
|
デリシャス上海は毎日営業中!! (インパクト) |
0 | 120 | 敵:攻撃&DX・AG減(1T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ヒールポーション | [ 3 ]エアスラスト |

PL / 紅緒