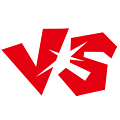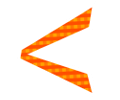<< 3:00>> 5:00




====
こがら行商日記 四日目
ハト、いるじゃないですか。どこにでもいるしどこでも生きていけるとどこぞの歌でもあったような気がしますが、あれ。
本当にどこにでもいます。昨今スズメさんなんかは減少が著しいとされている反面ハトだけは昨今の移りゆく都市型生息域にも即座に適応。
むしろソーラパネルやら公共敷設の橋梁やら高層ビルの構造部に至るまで全力で営巣、増殖の一途を辿っているという報告もあります。
その適応力、繁殖の頻度と雛の成長の異様なまでの速さ、群体行動から個体行動まで容易にこなす特化された社会性など挙げてみたらキリがない意味で危険きわまりない21世紀世界におけるウィナーというか、某獰猛縞尾の外来種と並んで今後人類世界にとって確実に脅威になるであろう生物の一種なんですが。
彼らの天敵とも言えるのって現状ノネコくらいでしょうか。郊外に行けばイタチやら蛇やらもいるんでしょうけどそれも都市部では期待しにくいとなるとますます無双、もといふてぶてしさも強化されていくようで、昨今人が近づこうが犬がいようが明らかに至近距離でも呑気に鎮座してるような個体が割と多い、そんな印象ですね。
そんなわけで御多分に洩れずここイバラシティ、チナミ区の街角のベンチで、周囲にわらわら時間とともに集ってくるハトたちの姿を力なく見つめている我々なわけですが。
「もういっそよその国の文化のようにハト肉解禁まで行ければいいんでしょうかねー」
「味は悪くはないらしいが、衛生面の問題があるだろ?変な細菌やら病気持ってたら厄介だ」
「あんだけ都合よく使っといて、自分で言うんですね、それ」
数を増していくハトにだんだん居心地を悪くしつつも、チナミ公園前にあった某コンビニチェーンで買ってきた助六寿司をがさごそ開きます。
経緯はともあれ、私たち人間も補給は欠かせないのです。
「もうちょっといいもん買ってこれなかったのかよ」マッケンジー氏が渋い顔で割り箸を割りつつ毒づきました。
「助六侮っちゃいけませんよ、これは割とどこでも売っていて、味は濃いですが炎天下の屋外で食べても食中毒の危険性が低い上に比較的消化もいい理想的な」
「あーはいはい。御託はいいから飲み物もくれよ」
「緑茶とほうじ茶がありますよ」
「おい今西暦何年なんだよ…」
もりもりもさもさ。しばらく無言でコンビニ弁当を頬張る二人の周囲をハトが集ります。ここで怖いのはこのハトたち、決して物を食べてる私たちには見向きもしないところです。まあ、食べてる物が助六寿司ですから、ハト的に興味の対象外なのかもしれません。
それに食べてるのが成人男女、その辺のカップルというわけでも子供連れというわけでもない実務的な出で立ちの2名ですから、おこぼれのちょうだいなど最初っから期待していないのでしょう。つまり、こいつらはあきらかに人を見ているということにもなるわけですが。
「せめて集まってくるのがカラスとかだったら、まだ格好もついたんでしょうけどねー」
行きがかり上行動を共にすることになってしまったマッケンジー氏の『異能』の説明を受けたわたしは、そう言ってため息を吐きました。
「言ってくれるな、それはオレも思った」
なんでもこのマッケンジー氏、現職業は探偵で、このイバラシティに自分と同じような事情で『連れてこられた』類の人物だということ。
そしてこのイバラシティで扱うことができる『異能』に類する物が、この周辺にたかるハトに関わる、一種異様な、にわかには信じ難く、そこはかとなく薄気味悪いもろもろの能力だったのです。
「ハトが増えてって、増えたハトのぶんだけ相手や自分たちにに影響が出て、割と周辺のどこにでも生やすことができる…」
と、聞いた話を指折順番に数えて言って、眉をひそめました。「特に最後、何?」
「としか説明できねえしなあ」
「…」
まあ、お互い説明しあった身としては、自分の『ふろしきから様々なアイテムを不如意に出す』という異能も大概気味悪いんですけど。
何が出るかわからないわたしの異能と、出る物は確実にハトだけど何が起こるかは未知数、というマッケンジー氏の異能。
どっちがマシかといったらどっちも『使いにくい』の一択で、お互い途方に暮れているというのが正直なところではないでしょうか。
「いずれにせよ巻き込まれちまったもんはしかたねえ。あのサカキとかいうスーツ野郎の言うことは一応覚えとくべきだろな」
「でも、なんでしょうねアンジニティって。この街が脅かされてるのは、あの駅前にいた草とかとはまた違うんでしょうか?」
「って話だな、侵略しようとする勢力、ってだけしか説明されてねーけど、それがどっから来て何が目的かってのはまだわかんねえ。もしくは、教えたくねえんだろ」
「うーん、アンジニティ。単語だけ聞くとなんかこー、ネガティブななんか、って感じですけど。
よくある異世界からやってきた魔物とか、外宇宙からの侵略生物とか、SCPシリーズとか、深淵の混沌とかそういう類なんでしょうかね」
「…それ、『よくある』のか?」マッケンジー氏は首をひねりつつ太巻きにかぶりつきます。
「まあ、わかりませんけど」
イバラシティが異変に襲われている。それは、冒頭電車の中で襲われたナレハテやら、歩く草、凶暴な猫らしきもの、といった相手をしてきて嫌でも実感しました。ですがアンジニティ、というのは、それとはまた別に存在するなにかなのでしょうか。
そもそも異変とは、アンジニティが起こしているのか、するとアンジニティという連中の手下として、今まで出会ってきたおかしな怪物が位置付けられているのでしょうか。ですが聞いた話では、そんな単純な話ではないようです。
「異変、というものがまずありきで、そのせいで『アンジニティ』って連中が介入してきてる?って可能性もあるんでしょうかね」
「それはまだ、わかんねえな。いずれにせよアンジニティってのがどんな連中なのか、まだオレらには知る術がねえ。会ったこともねえしな」
「…むしろ、そういうことなんじゃないでしょうかね」お茶を飲みつつ、ふとつぶやきます。
「あ?」
「『誰がアンジニティかわからない』ってのが、あるんじゃないですか?
だって、わたし達今までいろんな局面で怪物と戦ってましたけど、そこには同じように戦ってる他の人たちもちらほらいましたよね?
あの人たちが全員『アンジニティじゃない』って、どうやって分かるんですか?そんな簡単なことじゃない気がするんですよ」
そこまで言ったところで、ふと我に帰ります。「あ、あくまで、なんとなくの話ですけど」
マッケンジー氏は少し考え込んでから、少し足元に視線を下げました。「だとしたら、厄介だな」
「まあ、そうですよね。今はいいですけど、また『ハザマ世界』ってやつが現れたら、いずれは出てくるかもしれないってことですよね」
お互い顔を見合わせてから、二人同時に口を開きかけて、同時に何かに思い当たったように、視線を助六寿司に戻しました。
「まあ、いずれにせよ『あんたはどうなんだ』って聞こうとしてる時点でアレだよな」
「ですよね」
ただ、コンビニ弁当を食べているだけの時間、たった一時間にも満たないそのやり取りで、なんとなく。
なんかよくわからないけれど、まあ、そういうことだろうな、で納得してしまえる経緯というのは確かにあるようだなあという思いに、自分なりに苦笑をかみ殺している、そんなひと時なのでした。
====



ItemNo.7 紅はるか を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










H-1092(1092) とカードを交換しました!
試験データ04 (ファイアボール)


ジェイド を研究しました!(深度2⇒3)
ロックスティング を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度1⇒2)



マッケンジー(1249) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK.



====
こがら行商日記 四日目
ハト、いるじゃないですか。どこにでもいるしどこでも生きていけるとどこぞの歌でもあったような気がしますが、あれ。
本当にどこにでもいます。昨今スズメさんなんかは減少が著しいとされている反面ハトだけは昨今の移りゆく都市型生息域にも即座に適応。
むしろソーラパネルやら公共敷設の橋梁やら高層ビルの構造部に至るまで全力で営巣、増殖の一途を辿っているという報告もあります。
その適応力、繁殖の頻度と雛の成長の異様なまでの速さ、群体行動から個体行動まで容易にこなす特化された社会性など挙げてみたらキリがない意味で危険きわまりない21世紀世界におけるウィナーというか、某獰猛縞尾の外来種と並んで今後人類世界にとって確実に脅威になるであろう生物の一種なんですが。
彼らの天敵とも言えるのって現状ノネコくらいでしょうか。郊外に行けばイタチやら蛇やらもいるんでしょうけどそれも都市部では期待しにくいとなるとますます無双、もといふてぶてしさも強化されていくようで、昨今人が近づこうが犬がいようが明らかに至近距離でも呑気に鎮座してるような個体が割と多い、そんな印象ですね。
そんなわけで御多分に洩れずここイバラシティ、チナミ区の街角のベンチで、周囲にわらわら時間とともに集ってくるハトたちの姿を力なく見つめている我々なわけですが。
「もういっそよその国の文化のようにハト肉解禁まで行ければいいんでしょうかねー」
「味は悪くはないらしいが、衛生面の問題があるだろ?変な細菌やら病気持ってたら厄介だ」
「あんだけ都合よく使っといて、自分で言うんですね、それ」
数を増していくハトにだんだん居心地を悪くしつつも、チナミ公園前にあった某コンビニチェーンで買ってきた助六寿司をがさごそ開きます。
経緯はともあれ、私たち人間も補給は欠かせないのです。
「もうちょっといいもん買ってこれなかったのかよ」マッケンジー氏が渋い顔で割り箸を割りつつ毒づきました。
「助六侮っちゃいけませんよ、これは割とどこでも売っていて、味は濃いですが炎天下の屋外で食べても食中毒の危険性が低い上に比較的消化もいい理想的な」
「あーはいはい。御託はいいから飲み物もくれよ」
「緑茶とほうじ茶がありますよ」
「おい今西暦何年なんだよ…」
もりもりもさもさ。しばらく無言でコンビニ弁当を頬張る二人の周囲をハトが集ります。ここで怖いのはこのハトたち、決して物を食べてる私たちには見向きもしないところです。まあ、食べてる物が助六寿司ですから、ハト的に興味の対象外なのかもしれません。
それに食べてるのが成人男女、その辺のカップルというわけでも子供連れというわけでもない実務的な出で立ちの2名ですから、おこぼれのちょうだいなど最初っから期待していないのでしょう。つまり、こいつらはあきらかに人を見ているということにもなるわけですが。
「せめて集まってくるのがカラスとかだったら、まだ格好もついたんでしょうけどねー」
行きがかり上行動を共にすることになってしまったマッケンジー氏の『異能』の説明を受けたわたしは、そう言ってため息を吐きました。
「言ってくれるな、それはオレも思った」
なんでもこのマッケンジー氏、現職業は探偵で、このイバラシティに自分と同じような事情で『連れてこられた』類の人物だということ。
そしてこのイバラシティで扱うことができる『異能』に類する物が、この周辺にたかるハトに関わる、一種異様な、にわかには信じ難く、そこはかとなく薄気味悪いもろもろの能力だったのです。
「ハトが増えてって、増えたハトのぶんだけ相手や自分たちにに影響が出て、割と周辺のどこにでも生やすことができる…」
と、聞いた話を指折順番に数えて言って、眉をひそめました。「特に最後、何?」
「としか説明できねえしなあ」
「…」
まあ、お互い説明しあった身としては、自分の『ふろしきから様々なアイテムを不如意に出す』という異能も大概気味悪いんですけど。
何が出るかわからないわたしの異能と、出る物は確実にハトだけど何が起こるかは未知数、というマッケンジー氏の異能。
どっちがマシかといったらどっちも『使いにくい』の一択で、お互い途方に暮れているというのが正直なところではないでしょうか。
「いずれにせよ巻き込まれちまったもんはしかたねえ。あのサカキとかいうスーツ野郎の言うことは一応覚えとくべきだろな」
「でも、なんでしょうねアンジニティって。この街が脅かされてるのは、あの駅前にいた草とかとはまた違うんでしょうか?」
「って話だな、侵略しようとする勢力、ってだけしか説明されてねーけど、それがどっから来て何が目的かってのはまだわかんねえ。もしくは、教えたくねえんだろ」
「うーん、アンジニティ。単語だけ聞くとなんかこー、ネガティブななんか、って感じですけど。
よくある異世界からやってきた魔物とか、外宇宙からの侵略生物とか、SCPシリーズとか、深淵の混沌とかそういう類なんでしょうかね」
「…それ、『よくある』のか?」マッケンジー氏は首をひねりつつ太巻きにかぶりつきます。
「まあ、わかりませんけど」
イバラシティが異変に襲われている。それは、冒頭電車の中で襲われたナレハテやら、歩く草、凶暴な猫らしきもの、といった相手をしてきて嫌でも実感しました。ですがアンジニティ、というのは、それとはまた別に存在するなにかなのでしょうか。
そもそも異変とは、アンジニティが起こしているのか、するとアンジニティという連中の手下として、今まで出会ってきたおかしな怪物が位置付けられているのでしょうか。ですが聞いた話では、そんな単純な話ではないようです。
「異変、というものがまずありきで、そのせいで『アンジニティ』って連中が介入してきてる?って可能性もあるんでしょうかね」
「それはまだ、わかんねえな。いずれにせよアンジニティってのがどんな連中なのか、まだオレらには知る術がねえ。会ったこともねえしな」
「…むしろ、そういうことなんじゃないでしょうかね」お茶を飲みつつ、ふとつぶやきます。
「あ?」
「『誰がアンジニティかわからない』ってのが、あるんじゃないですか?
だって、わたし達今までいろんな局面で怪物と戦ってましたけど、そこには同じように戦ってる他の人たちもちらほらいましたよね?
あの人たちが全員『アンジニティじゃない』って、どうやって分かるんですか?そんな簡単なことじゃない気がするんですよ」
そこまで言ったところで、ふと我に帰ります。「あ、あくまで、なんとなくの話ですけど」
マッケンジー氏は少し考え込んでから、少し足元に視線を下げました。「だとしたら、厄介だな」
「まあ、そうですよね。今はいいですけど、また『ハザマ世界』ってやつが現れたら、いずれは出てくるかもしれないってことですよね」
お互い顔を見合わせてから、二人同時に口を開きかけて、同時に何かに思い当たったように、視線を助六寿司に戻しました。
「まあ、いずれにせよ『あんたはどうなんだ』って聞こうとしてる時点でアレだよな」
「ですよね」
ただ、コンビニ弁当を食べているだけの時間、たった一時間にも満たないそのやり取りで、なんとなく。
なんかよくわからないけれど、まあ、そういうことだろうな、で納得してしまえる経緯というのは確かにあるようだなあという思いに、自分なりに苦笑をかみ殺している、そんなひと時なのでした。
====



ItemNo.7 紅はるか を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









H-1092(1092) とカードを交換しました!
試験データ04 (ファイアボール)


ジェイド を研究しました!(深度2⇒3)
ロックスティング を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度1⇒2)



マッケンジー(1249) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――







ENo.1583
橋部渡 こがら



ジョーバンラインに乗ってはるばる遠方からやってきた、風呂敷包みをかかえた年代不詳の人。一応仕事は『行商』だと説明するものの包みの中身は自分でもよくわかっていない雑多かつ様々な商売道具に満ちているらしい。
イバラシティの異変に巻き込まれる形で里帰りの途中で下車した。
イバラシティの異変に巻き込まれる形で里帰りの途中で下車した。
16 / 30
182 PS
チナミ区
K-14
K-14




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 黄色いレプユニNo.7 | 防具 | 25 | 防御10 | - | - | |
| 5 | 染め抜きのふろしき | 武器 | 20 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | 紅あずま | 料理 | 15 | 治癒10 | - | - | |
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 武器 | 10 | 武器作製に影響 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| ロックスティング | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃 | |
| クラック | 5 | 0 | 160 | 敵全:地撃&次与ダメ減 | |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 | |
| ジェイド | 6 | 0 | 150 | 自:鎮痛LV・LK増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 6 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】[スキル使用設定不要]生産行動『効果付加』時、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
輝く1 (ヒールポーション) |
0 | 60 | 味傷:HP増 | |
|
テッポウウオ (リップル) |
0 | 150 | 敵全:水痛撃(対象の領域値[水]が高いほど威力増) | |
|
試験データ04 (ファイアボール) |
0 | 180 | 敵全:火撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ストーンブラスト | [ 1 ]ストレングス | [ 2 ]ロックスティング |
| [ 1 ]ストライキング | [ 3 ]ジェイド |

PL / あな