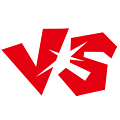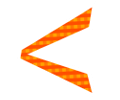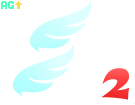<< 3:00>> 5:00




ハトとハードボイルド 第四回
でーでーぼっぽぽーというハトの声がこだますると右から左から聞こえてくる。街道に沿って東に少しく足を向けると、周囲は鬱蒼とした木々や峻険な岩々、ぬかるんだ湿地があちこちにあって、このイバラシティという町が一都六県の一画というよりもラヴクラフトが望んだドリームランドに近しい場所であることが分かる。マッケンジーが暮らしているマッドシティはもっと世紀末然とした、朽ちた荒野に傾いた廃ビルや高架が行く手を遮るような世界だが、ここには退廃した文明と獰猛な自然が共存して夢見る訪問者に牙を向けていた。
肩を大きく動かして息を吐く。このようなとき、一般的な探偵であればマール・ボロを抜いたりマイルドセブンにチルチルミチルで火をつけたり、あるいはシケモクをつまんだりするのだろうが、彼は嫌煙家だから吸いたいならママのハネオツパイでもしゃぶってなベイビーとでも悪態をつくところだがあるいはホソオツパイかもしれない。このような場所にいるのだから、ハトも木の枝や岩棚にでもいればいいだろうに沿道の地面を呑気に歩いていて人間に対する警戒心のかけらも見せてはいなかった。
「ハトなんてものはどこにでもいるもんだ」
夢を見ている人間は自分が夢を見ていることに疑問を持たない。マッケンジーに限らず、この町にいる者は自分が置かれている境遇に疑問を持っていないか、持っていてもそれをごく当然に受け入れている。ハザマと呼ばれている、このふざけた世界を訪れた者たちは、誰でも不可思議な力を使うことができてそれはマッケンジーも例外ではなかった。まるで出来の悪い漫画(マンファ)のような話だが、実際にその能力とやらを目の当たりにしてそれを否定することもできない。生まれてからこの方、彼の人生には家族も親戚も友人も知り合いも、立ち飲み屋でくだをまいていた見知らぬおっさんも含めてスプーンの一本すら曲げることができる能力者など見たことも聞いたこともなかった。
行く手を遮って避けるそぶりすらないハトに悪態をつくと、大儀そうに道脇を歩いていく。ふざけた世界に呼び出されて不可思議な能力を使うことができる、まるで中学生向けのテレビアニメの主人公のようではないか、などとマッケンジーは考えたりはしない。彼と同じような境遇にある者は数十人どころか百人も千人もいるらしく、ならば彼らはよほどタチの悪い輩に目を着けられた挙句、厄介ごとに巻き込まれた「運の悪すぎるエキストラたち」に他ならない。例えるなら、なかまになりたそうにこちらをみてもいなかったのに、モンスターおじさんに拐かされて闘技場に放り込まれてしまったとつげきへいの気分とでもいうべきだろうか。黒スーツ姿で、にやけた笑みを浮かべていた男の言葉を思い出す。
「この世界はアンジニティの侵攻を受けているのです。このイバラシティを守らなければならないのです(棒)!」
サカイだかサカキだか、名前を忘れてしまったので、とりあえず黒スーツと呼ぶことにする。黒スーツは自分の白々しい言葉が、胡散臭く思われていることなど承知の上で、どうせマッケンジーたちに選択肢はないのだということを言外に仄めかしていた。しょせんゲームの開発者を前にして、プレイを拒否することはできないし、ゲームの能力で襲いかかるなどできよう筈もないのだ。想定された挙動をしないプログラムなどデバッグされてしまうのが関の山だろう。
「なにをブツブツ言ってるんですか?」
「屈折した大人は独り言が多くなるもんでな」
横合いからかけられた、物売りの娘の呑気な声にテキトウな冗談を返しておく。コガラだかハシブトガラだかシジュウカラガンだかいったか、彼女も奇天烈な名前をした娘だが、マッケンジーと似た境遇でこの町に呼びつけられたらしい。いまどきの若いモンは順応性が高いのか、このふざけた状況にも動じた様子はなく、駅前に徘徊していた大黒猫なる怪しげな生き物たちを先んじてぼこぼこと殴り倒してくれていた。同じ境遇で、頼りになりそうな「性格」をしているなら協力するに如くはない。
上り電車で売り荷をさばいた帰り道だったのだろう。大きな風呂敷を振り回したシジュウカラガンは大立ち回りを演じると大黒猫たちを脳天から平たくつぶしてしまい、便利ですねーなどと自分の能力に自分で感心している。風呂敷を自在に操っているのかとも思ったが、どうやら風呂敷からなんでも取り出すことができる能力らしく「石」を包んで殴り倒していたのだという。
「何が出てくるか自分でも分からないんですけどね」
などと笑っているが、もしもそんなことができたらそれこそなんでもありの能力になるだろう。心中で舌を巻いていたがいろいろと条件があるのかもしれず、そこまで物事は都合よくいくとも限らない。
ぽつねんとそびえている、背の高い街灯のてっぺんに何羽ものハトが集まっている。自分の能力がどのようなものであるかは、誰に説明されずともなんとなく理解できるが細やかな条件や使い方は自分で調べなければならない。駅前で襲われたときも、逃げ回りながら革靴で蹴り倒すくらいしかできずにいたマッケンジーのことを、シジュウカラガンは心配なり疑いなりの目で見ていたが、実のところ彼も能力を使いながら戦ってはいたのである。正直よく分からない力だし、役に立つのかどうかさえ疑問だが、ようやくコツのようなものは呑み込めてきたように思う。
ハト。それはこの世界のどこにでもあるものだ。ハトは人間がいるところどこにでも見かけることができて、彼の能力はこのハトの存在を自由に操ることができる。例えば草木に含まれているハトを取り出して一羽のハトにすることができるし、生き物から直接ハトを取り出すこともできる。当たり前だが、ハトを失った生き物はそれだけ力を奪われて弱ってしまう。能力には射程距離のようなものがあって、数メートル程度の間合いにいるものからでなければハトを取り出すことはできないが、よほど近づいて直接触れれば急速にハトを奪うことができた。
「なんかきみわるいです」
「奇遇だな。オレもそう思う」
そんなことよりも、黒スーツの言葉を正直に信じるならば、アンジニティとか呼ばれている輩がこの町を訪れていて自分たちは彼らから町を守らなければいけないらしい。こんなわざとらしい大義名分を頭から信じるわけにはいかないが、少なくともアンジニティの連中が自分たちと同じような不可思議な能力を持っていることと、その彼らに自分たちがぶつけられる可能性は高いとしかいえない。つまりそれまでにこのふざけた世界と不可思議な能力について少しでも理解しておく必要がある。今はそこらを徘徊する化け物?が相手だからよいが、いずれ自分の能力で自分が襲われたらと思えばあまり気分がよくはなれない。
ひとかたまりのハトがひとかたまりに飛び立つと、向こうにある別の街灯に移動してゆく。同じことは皆が考えているらしく、沿道を歩きながら言葉を交わしている幾人かや、実際に互いの能力を確かめるように撃ち合っている数人の姿を見ることができる。いわゆる練習試合というやつで、真面目だねえと悪意もなく感心するマッケンジーに、自分たちはああいう練習試合はしなくていいんですかとシジュウカラガンが尋ねてきた。
「だっておじさんあまり役に立ってないですよ」
「人間の価値は役に立つか役に立たないかで決まるもんじゃないんだぜ?」
もっともらしいことをうそぶいてみせるが、大した根拠のある言葉でもない。だが彼には彼なりの理由もあって、ハト魔法と呼ぶことにしたこの能力で、もう少し、試してみたいことがあった。まずは駅前に徘徊するチリメン雑魚くんを相手にするつもりでいたが、黒スーツが急かしていたように先に進めという無言の要求はあるらしく、いつまでも居座ればペナルティを食らいかねない。
「まーよくわからないのはお互い様ですけどね。しばらくお手伝いします」
「悪ぃな。お礼にハトだったらいくらでもくれてやるぜ」
「お断りします」
いいですとか結構ですとか中途半端な回答をせず、はっきりノーと言ってみせることは重要だと思う。とりあえずは彼女の助けを借りているあいだに試したいことは試してしまうがよさそうだ。
彼のハト魔法は近くにいる生き物だけではなく、木々や地面の中に少しずつ存在しているハトを集めて一羽のハトにすることもできる。もしもこの力をもっと集めて、それを大きなハトにして取り出すことはできないだろうか。実は一度試してみようとしたのだが、そのときは周囲から集めることができた力が足りずに何も起こらなかった。だが駅前で見かけた数人の連中から、「カード」と称する奇妙な力を融通してもらったり、幾つかの能力を組み合わせればもう少し大きな力を集めることはできそうだった。
鬼が出るか蛇が出るか。だがどうせ出てくるのはハトに違いないのだ。
***
そんなわけで日記の4回目。わりと正直にスキルやら成長やらに頭を悩ませていますのでそれをそのまま書いてます。今回はサモンレッサーデーモンが使えるのではないかと思いましたので、このあとの結果でうまいこと使えたらいいなーと思いますがわりとルールを覚えずに失敗することがままあるので楽しみにしているのです!



特に何もしませんでした。










百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ペロリーメイト』をつくりました!
⇒ ペロリーメイト/料理:強さ15/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ヨケト(1052) とカードを交換しました!
回避風撃 (スカイディバイド)

クリエイト:タライ を研究しました!(深度2⇒3)
エナジードレイン を研究しました!(深度2⇒3)
サモン:レッサーデーモン を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を習得!
ヴェノム を習得!
クリエイト:シリンジ を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



ハトとハードボイルド 第四回
でーでーぼっぽぽーというハトの声がこだますると右から左から聞こえてくる。街道に沿って東に少しく足を向けると、周囲は鬱蒼とした木々や峻険な岩々、ぬかるんだ湿地があちこちにあって、このイバラシティという町が一都六県の一画というよりもラヴクラフトが望んだドリームランドに近しい場所であることが分かる。マッケンジーが暮らしているマッドシティはもっと世紀末然とした、朽ちた荒野に傾いた廃ビルや高架が行く手を遮るような世界だが、ここには退廃した文明と獰猛な自然が共存して夢見る訪問者に牙を向けていた。
肩を大きく動かして息を吐く。このようなとき、一般的な探偵であればマール・ボロを抜いたりマイルドセブンにチルチルミチルで火をつけたり、あるいはシケモクをつまんだりするのだろうが、彼は嫌煙家だから吸いたいならママのハネオツパイでもしゃぶってなベイビーとでも悪態をつくところだがあるいはホソオツパイかもしれない。このような場所にいるのだから、ハトも木の枝や岩棚にでもいればいいだろうに沿道の地面を呑気に歩いていて人間に対する警戒心のかけらも見せてはいなかった。
「ハトなんてものはどこにでもいるもんだ」
夢を見ている人間は自分が夢を見ていることに疑問を持たない。マッケンジーに限らず、この町にいる者は自分が置かれている境遇に疑問を持っていないか、持っていてもそれをごく当然に受け入れている。ハザマと呼ばれている、このふざけた世界を訪れた者たちは、誰でも不可思議な力を使うことができてそれはマッケンジーも例外ではなかった。まるで出来の悪い漫画(マンファ)のような話だが、実際にその能力とやらを目の当たりにしてそれを否定することもできない。生まれてからこの方、彼の人生には家族も親戚も友人も知り合いも、立ち飲み屋でくだをまいていた見知らぬおっさんも含めてスプーンの一本すら曲げることができる能力者など見たことも聞いたこともなかった。
行く手を遮って避けるそぶりすらないハトに悪態をつくと、大儀そうに道脇を歩いていく。ふざけた世界に呼び出されて不可思議な能力を使うことができる、まるで中学生向けのテレビアニメの主人公のようではないか、などとマッケンジーは考えたりはしない。彼と同じような境遇にある者は数十人どころか百人も千人もいるらしく、ならば彼らはよほどタチの悪い輩に目を着けられた挙句、厄介ごとに巻き込まれた「運の悪すぎるエキストラたち」に他ならない。例えるなら、なかまになりたそうにこちらをみてもいなかったのに、モンスターおじさんに拐かされて闘技場に放り込まれてしまったとつげきへいの気分とでもいうべきだろうか。黒スーツ姿で、にやけた笑みを浮かべていた男の言葉を思い出す。
「この世界はアンジニティの侵攻を受けているのです。このイバラシティを守らなければならないのです(棒)!」
サカイだかサカキだか、名前を忘れてしまったので、とりあえず黒スーツと呼ぶことにする。黒スーツは自分の白々しい言葉が、胡散臭く思われていることなど承知の上で、どうせマッケンジーたちに選択肢はないのだということを言外に仄めかしていた。しょせんゲームの開発者を前にして、プレイを拒否することはできないし、ゲームの能力で襲いかかるなどできよう筈もないのだ。想定された挙動をしないプログラムなどデバッグされてしまうのが関の山だろう。
「なにをブツブツ言ってるんですか?」
「屈折した大人は独り言が多くなるもんでな」
横合いからかけられた、物売りの娘の呑気な声にテキトウな冗談を返しておく。コガラだかハシブトガラだかシジュウカラガンだかいったか、彼女も奇天烈な名前をした娘だが、マッケンジーと似た境遇でこの町に呼びつけられたらしい。いまどきの若いモンは順応性が高いのか、このふざけた状況にも動じた様子はなく、駅前に徘徊していた大黒猫なる怪しげな生き物たちを先んじてぼこぼこと殴り倒してくれていた。同じ境遇で、頼りになりそうな「性格」をしているなら協力するに如くはない。
上り電車で売り荷をさばいた帰り道だったのだろう。大きな風呂敷を振り回したシジュウカラガンは大立ち回りを演じると大黒猫たちを脳天から平たくつぶしてしまい、便利ですねーなどと自分の能力に自分で感心している。風呂敷を自在に操っているのかとも思ったが、どうやら風呂敷からなんでも取り出すことができる能力らしく「石」を包んで殴り倒していたのだという。
「何が出てくるか自分でも分からないんですけどね」
などと笑っているが、もしもそんなことができたらそれこそなんでもありの能力になるだろう。心中で舌を巻いていたがいろいろと条件があるのかもしれず、そこまで物事は都合よくいくとも限らない。
ぽつねんとそびえている、背の高い街灯のてっぺんに何羽ものハトが集まっている。自分の能力がどのようなものであるかは、誰に説明されずともなんとなく理解できるが細やかな条件や使い方は自分で調べなければならない。駅前で襲われたときも、逃げ回りながら革靴で蹴り倒すくらいしかできずにいたマッケンジーのことを、シジュウカラガンは心配なり疑いなりの目で見ていたが、実のところ彼も能力を使いながら戦ってはいたのである。正直よく分からない力だし、役に立つのかどうかさえ疑問だが、ようやくコツのようなものは呑み込めてきたように思う。
ハト。それはこの世界のどこにでもあるものだ。ハトは人間がいるところどこにでも見かけることができて、彼の能力はこのハトの存在を自由に操ることができる。例えば草木に含まれているハトを取り出して一羽のハトにすることができるし、生き物から直接ハトを取り出すこともできる。当たり前だが、ハトを失った生き物はそれだけ力を奪われて弱ってしまう。能力には射程距離のようなものがあって、数メートル程度の間合いにいるものからでなければハトを取り出すことはできないが、よほど近づいて直接触れれば急速にハトを奪うことができた。
「なんかきみわるいです」
「奇遇だな。オレもそう思う」
そんなことよりも、黒スーツの言葉を正直に信じるならば、アンジニティとか呼ばれている輩がこの町を訪れていて自分たちは彼らから町を守らなければいけないらしい。こんなわざとらしい大義名分を頭から信じるわけにはいかないが、少なくともアンジニティの連中が自分たちと同じような不可思議な能力を持っていることと、その彼らに自分たちがぶつけられる可能性は高いとしかいえない。つまりそれまでにこのふざけた世界と不可思議な能力について少しでも理解しておく必要がある。今はそこらを徘徊する化け物?が相手だからよいが、いずれ自分の能力で自分が襲われたらと思えばあまり気分がよくはなれない。
ひとかたまりのハトがひとかたまりに飛び立つと、向こうにある別の街灯に移動してゆく。同じことは皆が考えているらしく、沿道を歩きながら言葉を交わしている幾人かや、実際に互いの能力を確かめるように撃ち合っている数人の姿を見ることができる。いわゆる練習試合というやつで、真面目だねえと悪意もなく感心するマッケンジーに、自分たちはああいう練習試合はしなくていいんですかとシジュウカラガンが尋ねてきた。
「だっておじさんあまり役に立ってないですよ」
「人間の価値は役に立つか役に立たないかで決まるもんじゃないんだぜ?」
もっともらしいことをうそぶいてみせるが、大した根拠のある言葉でもない。だが彼には彼なりの理由もあって、ハト魔法と呼ぶことにしたこの能力で、もう少し、試してみたいことがあった。まずは駅前に徘徊するチリメン雑魚くんを相手にするつもりでいたが、黒スーツが急かしていたように先に進めという無言の要求はあるらしく、いつまでも居座ればペナルティを食らいかねない。
「まーよくわからないのはお互い様ですけどね。しばらくお手伝いします」
「悪ぃな。お礼にハトだったらいくらでもくれてやるぜ」
「お断りします」
いいですとか結構ですとか中途半端な回答をせず、はっきりノーと言ってみせることは重要だと思う。とりあえずは彼女の助けを借りているあいだに試したいことは試してしまうがよさそうだ。
彼のハト魔法は近くにいる生き物だけではなく、木々や地面の中に少しずつ存在しているハトを集めて一羽のハトにすることもできる。もしもこの力をもっと集めて、それを大きなハトにして取り出すことはできないだろうか。実は一度試してみようとしたのだが、そのときは周囲から集めることができた力が足りずに何も起こらなかった。だが駅前で見かけた数人の連中から、「カード」と称する奇妙な力を融通してもらったり、幾つかの能力を組み合わせればもう少し大きな力を集めることはできそうだった。
鬼が出るか蛇が出るか。だがどうせ出てくるのはハトに違いないのだ。
***
そんなわけで日記の4回目。わりと正直にスキルやら成長やらに頭を悩ませていますのでそれをそのまま書いてます。今回はサモンレッサーデーモンが使えるのではないかと思いましたので、このあとの結果でうまいこと使えたらいいなーと思いますがわりとルールを覚えずに失敗することがままあるので楽しみにしているのです!



特に何もしませんでした。









百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ペロリーメイト』をつくりました!
⇒ ペロリーメイト/料理:強さ15/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
マッケンジー 「やっぱこれだろ。」 |
ヨケト(1052) とカードを交換しました!
回避風撃 (スカイディバイド)

クリエイト:タライ を研究しました!(深度2⇒3)
エナジードレイン を研究しました!(深度2⇒3)
サモン:レッサーデーモン を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を習得!
ヴェノム を習得!
クリエイト:シリンジ を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――







ENo.1249
新沼ケンジ



本名はシンヌマ・ケンジ。
チバ県マッドシティ出身の探偵。
ジョーバンアーバンラインに乗ってイバラシティにやって来た。
どこからでもハトが出てくるハト魔法を使いこなす。
ハトは出てくる場所の周囲にある生き物から生成されるので、
ハトが増えれば増えるほど近くにいるものは消耗していく。
チバ県マッドシティ出身の探偵。
ジョーバンアーバンラインに乗ってイバラシティにやって来た。
どこからでもハトが出てくるハト魔法を使いこなす。
ハトは出てくる場所の周囲にある生き物から生成されるので、
ハトが増えれば増えるほど近くにいるものは消耗していく。
16 / 30
182 PS
チナミ区
K-14
K-14




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 微動だにしないドバト(1) | 武器 | 20 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 黄色いレプユニNo.17 | 防具 | 25 | 敏捷10 | - | - | |
| 6 | ペロリーメイト | 料理 | 15 | 治癒10 | - | - | |
| 7 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 8 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 12 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]敏捷10(LV10)[効果2]復活10(LV10)[効果3]体力15(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 10 | 呪詛/邪気/闇 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
| 料理 | 5 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ハトブレイク (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ハトピンポイント (ピンポイント) | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| ハトクイック (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ハトブラスト (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ハトヒール (ヒール) | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ハトダークネス (ダークネス) | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 | |
| クリエイトハト (クリエイト:タライ) | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| ハトファントム (クリエイト:ファントム) | 5 | 0 | 140 | 自:衰弱LV増 | |
| ヴェノム | 5 | 0 | 50 | 敵:猛毒・麻痺・衰弱 | |
| クリエイト:シリンジ | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&自:HP増 | |
| ハトドレイン (エナジードレイン) | 5 | 0 | 160 | 敵:闇撃&DF奪取 | |
| サモンハト (サモン:レッサーデーモン) | 5 | 0 | 400 | 自:レッサーデーモン召喚+HP減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| ハトハトハト (召喚強化) | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
黑い巨神 (ブレイク) |
0 | 20 | 敵:攻撃 | |
|
空間衝突 (レックレスチャージ) |
0 | 80 | 自:HP減+敵全:風痛撃 | |
|
『お狐さま』 (エネルジコ) |
0 | 80 | 自:MHP・MSP増 | |
|
回避風撃 (スカイディバイド) |
0 | 200 | 敵貫:風撃&風耐性減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]クリエイト:タライ | [ 3 ]エナジードレイン | [ 3 ]サモン:レッサーデーモン |

PL / TOSHIKI