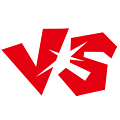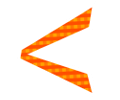<< 3:00>> 5:00




周辺の地図を『Cross+Rose』で簡単に確認をして、すぐに閉じる。意識を集中させるという事ひとつとっても、今の玲瓏にとってみれば重労働だ。
それに加えて、いつもの記憶の流入もある。これにはだいぶ慣れてきた、というか所詮は自分を元に作られた存在が、似たようなコンプレックスで悩んでいる姿が多いのでそれについてどうこう思うのを、極力やめることにした。
これについては思考を放棄すればいいだけなので簡単にできる。もとより、考えようとしなければ考えられないのだから。
「……」
ばくり。白米にかじりついて噛み締める。噛めば噛むほど甘味が出るとかそんな事はわからないが、いつもより余計に動ける世界では普段ほとんど必要無く、取りすぎてしまえば逆に体に負荷がかかる食事も必要な事にかわるらしい。味は、ほんのうっすら感じる程度だ。
不思議な食材と名付けられているそれは本当によくわからないものだったが、さらにわからないのはそれがいじくりまわすとおにぎりになることだ。
とはいえ、どのみち歩き通しであれば歩きながら食べられるこの選択は間違いではなかったと思うのだが。もう一度かじりつきながら、ふと違和感を覚えて足を止めた。
「……おい」
自分の隣を歩いていた巨体が気付けば自分の後ろにいた。3メートルまでいかないものの2メートルはゆうに超えている、隣に並べば自分がまるで子供になったかと思うほどに見上げる相手が歩速で玲瓏より劣る事は無いだろうし実際玲瓏は彼に置いていかれないように気をつけてはいた。
その巨躯は振り返って声をかけると顔をあげてこちらを見てくる。いつものニヤケ顔……もとい、笑みをたたえた表情に、どことなく興味の色が混じっているような気がした。
「玲瓏、これはなんだ」
「なんだって……おにぎり、だよ」
巨躯――4(よん)とかⅣ(フォー)とか、玲瓏からしてみればそれは単なる識別番号なのでは、と思わなくもないがそう名乗ってきたので4と読んでいる――は、ものの数歩で玲瓏との間を詰めてきては手にしたもの玲瓏の眼前に差し出してきた。
自分のよりは大きめに作ったつもりだが、その大きな手に収まってしまえば全くそんな事はなかったらしいおにぎりは、米を三角に握って持ち手になるように海苔をシンプルに巻いたものだ。
が、どうやらこの4という存在(そもそも人間でないようにも見えるし、男に見えているが男なのかも定かではない)は、それを知らないらしい。世界や国が違えば当たり前なのでそれに驚きはしないので説明をしようか、と口を開きかけてふと気付いた。死んでいる自分にしてはとても冴えていたと思う。
「……イバラの方で、見たこと、ねえのか?」
「おにぎり、という呼称をしていた記憶は確かにあったが、我の記憶ではこのような形ではなかったな」
「……なるほど、な。確かに、色々形はあるけど、コメが握られてて、ノリが巻いてりゃ全部おにぎりだ」
言ってから、それだと巻き寿司もおにぎりに含まれてしまいそうな気がしたがそんな事はどうでもよかった。
4は玲瓏の言葉に納得がいったようで、なるほど、と呟きつつもう一度おにぎりをまじまじと見てから、手の中に収まっていたそれを一気に口の中に放り込んた。
一応咀嚼しているらしく、口の中がもごもごと動いているのが見える。しかし、その動きがぴくりと一瞬止まった……かと思えば再び何事もなかったように動き出し、しばらくして飲み込んだらしく、喉が大きくうねった。
「……不思議な味だ。中に酸味の刺激があるものがはいっていたが、コメ、とやらの味と混ざるとちょうどいい風味となる。この、ノリというのは海藻か? これもよい。」
「……、……」
飲み込んだ4がすらすらとおにぎりの感想を並べていく。この相手が今までどんな食事を取ってきたかは知らないが、アンジニティで何度か見たときはそのへんの草とか花も食べていたような気がしたので、味に頓着がないと思っていた玲瓏にとっては意外すぎた返答に言葉も出せずにぽかん、としてしまった。
すると、それに気付いた4が瞳を細めて玲瓏を眺める。
「ふむ、玲瓏は面白い顔もできるのだな」
「……、うるせえ、もう食ったなら、いくぞ」
明らかにからかってきた言葉を聞いて我に返った玲瓏はわざとらしく大きな舌打ちをすると、踵を返して歩き始めた。
背中から楽しげにくくく、と笑う声が聞こえて若干イラっときたがいちいち言い返したところであの巨躯は楽しそうにするだけなので何も言わずに歩をすすめる。しばらくして、隣についてくる気配を感じたのでそれでよかったのだろう。
ただ、自分の料理(という程でもないが)が褒められた事に対しては悪い気はしない。そうなると現金なのは生きてても死んでても変わらないらしく、このとりあえず共に行動しているだけという同行者に多少の興味がわいてしまった。
アンジニティでも別段深い交流があったワケでもなく、今だって成り行きではあるのだがそれでももう少し相手を知ってもいいのかも、しれない。
ただ、そんな気持ちもふと視線があった瞬間に浮かべられた笑みで、とりあえず今すぐそれを聞くのはやめようとなってしまうのだった。



ENo.909 スカリム とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 おにぎり を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(16⇒17)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










ItemNo.9 美味しい果実 から料理『うさちゃんりんご』をつくりました!
⇒ うさちゃんりんご/料理:強さ54/[効果1]敏捷10 [効果2]復活10 [効果3]体力15
タウラシアス(570) とカードを交換しました!
アル・ナスル (イレイザー)





Ⅳ(416) に移動を委ねました。
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 H-16(森林)に移動!(体調13⇒12)






―― ハザマ時間が紡がれる。

エディアンが早足で湖岸に駆け寄る。
そこでは、白鳥たち黒鳥たちがのんびりと寛いでいる。
エディアンが何かを出そうとすると、後方にランニングおじさん。
そうつぶやき、走り去っていく。
チャットが閉じられる――







棒のような何かが釣りを楽しんでいる。

元気なエビをもらったが、元気すぎて空高くジャンプして見えなくなる。
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK.



周辺の地図を『Cross+Rose』で簡単に確認をして、すぐに閉じる。意識を集中させるという事ひとつとっても、今の玲瓏にとってみれば重労働だ。
それに加えて、いつもの記憶の流入もある。これにはだいぶ慣れてきた、というか所詮は自分を元に作られた存在が、似たようなコンプレックスで悩んでいる姿が多いのでそれについてどうこう思うのを、極力やめることにした。
これについては思考を放棄すればいいだけなので簡単にできる。もとより、考えようとしなければ考えられないのだから。
「……」
ばくり。白米にかじりついて噛み締める。噛めば噛むほど甘味が出るとかそんな事はわからないが、いつもより余計に動ける世界では普段ほとんど必要無く、取りすぎてしまえば逆に体に負荷がかかる食事も必要な事にかわるらしい。味は、ほんのうっすら感じる程度だ。
不思議な食材と名付けられているそれは本当によくわからないものだったが、さらにわからないのはそれがいじくりまわすとおにぎりになることだ。
とはいえ、どのみち歩き通しであれば歩きながら食べられるこの選択は間違いではなかったと思うのだが。もう一度かじりつきながら、ふと違和感を覚えて足を止めた。
「……おい」
自分の隣を歩いていた巨体が気付けば自分の後ろにいた。3メートルまでいかないものの2メートルはゆうに超えている、隣に並べば自分がまるで子供になったかと思うほどに見上げる相手が歩速で玲瓏より劣る事は無いだろうし実際玲瓏は彼に置いていかれないように気をつけてはいた。
その巨躯は振り返って声をかけると顔をあげてこちらを見てくる。いつものニヤケ顔……もとい、笑みをたたえた表情に、どことなく興味の色が混じっているような気がした。
「玲瓏、これはなんだ」
「なんだって……おにぎり、だよ」
巨躯――4(よん)とかⅣ(フォー)とか、玲瓏からしてみればそれは単なる識別番号なのでは、と思わなくもないがそう名乗ってきたので4と読んでいる――は、ものの数歩で玲瓏との間を詰めてきては手にしたもの玲瓏の眼前に差し出してきた。
自分のよりは大きめに作ったつもりだが、その大きな手に収まってしまえば全くそんな事はなかったらしいおにぎりは、米を三角に握って持ち手になるように海苔をシンプルに巻いたものだ。
が、どうやらこの4という存在(そもそも人間でないようにも見えるし、男に見えているが男なのかも定かではない)は、それを知らないらしい。世界や国が違えば当たり前なのでそれに驚きはしないので説明をしようか、と口を開きかけてふと気付いた。死んでいる自分にしてはとても冴えていたと思う。
「……イバラの方で、見たこと、ねえのか?」
「おにぎり、という呼称をしていた記憶は確かにあったが、我の記憶ではこのような形ではなかったな」
「……なるほど、な。確かに、色々形はあるけど、コメが握られてて、ノリが巻いてりゃ全部おにぎりだ」
言ってから、それだと巻き寿司もおにぎりに含まれてしまいそうな気がしたがそんな事はどうでもよかった。
4は玲瓏の言葉に納得がいったようで、なるほど、と呟きつつもう一度おにぎりをまじまじと見てから、手の中に収まっていたそれを一気に口の中に放り込んた。
一応咀嚼しているらしく、口の中がもごもごと動いているのが見える。しかし、その動きがぴくりと一瞬止まった……かと思えば再び何事もなかったように動き出し、しばらくして飲み込んだらしく、喉が大きくうねった。
「……不思議な味だ。中に酸味の刺激があるものがはいっていたが、コメ、とやらの味と混ざるとちょうどいい風味となる。この、ノリというのは海藻か? これもよい。」
「……、……」
飲み込んだ4がすらすらとおにぎりの感想を並べていく。この相手が今までどんな食事を取ってきたかは知らないが、アンジニティで何度か見たときはそのへんの草とか花も食べていたような気がしたので、味に頓着がないと思っていた玲瓏にとっては意外すぎた返答に言葉も出せずにぽかん、としてしまった。
すると、それに気付いた4が瞳を細めて玲瓏を眺める。
「ふむ、玲瓏は面白い顔もできるのだな」
「……、うるせえ、もう食ったなら、いくぞ」
明らかにからかってきた言葉を聞いて我に返った玲瓏はわざとらしく大きな舌打ちをすると、踵を返して歩き始めた。
背中から楽しげにくくく、と笑う声が聞こえて若干イラっときたがいちいち言い返したところであの巨躯は楽しそうにするだけなので何も言わずに歩をすすめる。しばらくして、隣についてくる気配を感じたのでそれでよかったのだろう。
ただ、自分の料理(という程でもないが)が褒められた事に対しては悪い気はしない。そうなると現金なのは生きてても死んでても変わらないらしく、このとりあえず共に行動しているだけという同行者に多少の興味がわいてしまった。
アンジニティでも別段深い交流があったワケでもなく、今だって成り行きではあるのだがそれでももう少し相手を知ってもいいのかも、しれない。
ただ、そんな気持ちもふと視線があった瞬間に浮かべられた笑みで、とりあえず今すぐそれを聞くのはやめようとなってしまうのだった。



ENo.909 スカリム とのやりとり
| ▲ |
| ||||
| |||
| |||
| |||||
以下の相手に送信しました



 |
Ⅳ 「我にも生命としての摂理があるが。玲瓏のその体、何で動いているのかよくよくおもしろい。さていつまで動くものであろうか。 一度じっくり…(Ⅳは玲瓏を上から下まで嘗め回すように見ている」 |
| 玲瓏 「……石壁、か。俺が知ってるのは、もっと可愛げが、あるんだがな」 |
ItemNo.7 おにぎり を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(16⇒17)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









ItemNo.9 美味しい果実 から料理『うさちゃんりんご』をつくりました!
⇒ うさちゃんりんご/料理:強さ54/[効果1]敏捷10 [効果2]復活10 [効果3]体力15
| 玲瓏 「(りんごを上手に切っている)」 |
タウラシアス(570) とカードを交換しました!
アル・ナスル (イレイザー)





Ⅳ(416) に移動を委ねました。
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 H-16(森林)に移動!(体調13⇒12)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「わぁぁ・・・・・ 結構大きいんですねぇ。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
エディアン 「あ、ごきげんよう皆さん!いまチナミ湖の周りを歩いてるんですよー!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・? あれは・・・??」 |
エディアンが早足で湖岸に駆け寄る。
そこでは、白鳥たち黒鳥たちがのんびりと寛いでいる。
 |
エディアン 「・・・・・かわいいいいッ!!!! かわいくないですか!!?これッ!!このこたちッ!!!!」 |
 |
エディアン 「ごはん?ごはんが欲しいのかなー?? えっと、でしたら・・・ えーっと・・・・・」 |
エディアンが何かを出そうとすると、後方にランニングおじさん。
 |
ランニングおじさん 「売ってるエサ買え。変なの食わすな。」 |
そうつぶやき、走り去っていく。
 |
エディアン 「あ・・・ ・・・えぇ!えぇ!!そうですよぉー!! エサは変なのあげちゃダメですからね!ダメですよー!?」 |
チャットが閉じられる――






 |
マイケル 「あ、ようこそチェックポイントへ。 いまエビが釣れそうなので少々お待ちを……。」 |
棒のような何かが釣りを楽しんでいる。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「よくぞここまで。私はマイケルといいます。 出会いの記念にこちらをどうぞ。」 |
元気なエビをもらったが、元気すぎて空高くジャンプして見えなくなる。
 |
マイケル 「……戻ってきませんねぇ、エビさん。」 |
 |
マイケル 「まぁいいです。始めるとしましょうか。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんので、そちらも本気でどうぞ。」 |
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.1132
古瀬圭一郎



[イラスト右側]
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
異能は無いがゾンビになる前にうけた多数の人体実験等の影響により、常人以上の身体能力を発揮することが可能。これにより生前の頃のような血の気の多い姿も見られるとか。
ただし、それ相応に反動がありひどい時はロクに動くことすらできなくなる。
ハザマ世界では元の世界やアンジニティよりその能力が使いやすいらしい。
古瀬圭一郎は本名だが、今人に名乗る場合は玲瓏と名乗っている。
......................................................
[イラスト左側]
舘和男 たち かずお
37歳 173cm
イバラシティでカフェバー【白詰草】を営む。
物静かで店を営むにしては少々愛想が無いようにも思えるが、特に性格的に冷たいとかではなくどちらかといえば優しく柔和な雰囲気を持つ。
世界の侵略については自分ひとりの力でどうこうできる問題ではないので、特段それを意識して生活している事はない。どちらにしても自分の異能では侵略者に対抗するのは難しいとも思っている。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
「こんな力で痛みを感じてたらショック死してしまうからではないか」と冗談めかしていうのが常套句となっている。
幼い頃はこの異能の力を見たがる同級生等に過度に暴力を振るわれた事もあった。
スポット:カフェバー《白詰草》
http://lisge.com/ib/talk.php?s=457
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
異能は無いがゾンビになる前にうけた多数の人体実験等の影響により、常人以上の身体能力を発揮することが可能。これにより生前の頃のような血の気の多い姿も見られるとか。
ただし、それ相応に反動がありひどい時はロクに動くことすらできなくなる。
ハザマ世界では元の世界やアンジニティよりその能力が使いやすいらしい。
古瀬圭一郎は本名だが、今人に名乗る場合は玲瓏と名乗っている。
......................................................
[イラスト左側]
舘和男 たち かずお
37歳 173cm
イバラシティでカフェバー【白詰草】を営む。
物静かで店を営むにしては少々愛想が無いようにも思えるが、特に性格的に冷たいとかではなくどちらかといえば優しく柔和な雰囲気を持つ。
世界の侵略については自分ひとりの力でどうこうできる問題ではないので、特段それを意識して生活している事はない。どちらにしても自分の異能では侵略者に対抗するのは難しいとも思っている。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
「こんな力で痛みを感じてたらショック死してしまうからではないか」と冗談めかしていうのが常套句となっている。
幼い頃はこの異能の力を見たがる同級生等に過度に暴力を振るわれた事もあった。
スポット:カフェバー《白詰草》
http://lisge.com/ib/talk.php?s=457
12 / 30
150 PS
チナミ区
H-16
H-16

















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 鈍色の沈丁花 | 装飾 | 30 | 器用10 | - | - | |
| 5 | 無骨な石斧 | 武器 | 33 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 7 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 9 | うさちゃんりんご | 料理 | 54 | 敏捷10 | 復活10 | 体力15 | |
| 10 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 26 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練3 | エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ヒールポーション | 6 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| アドレナリン | 5 | 0 | 80 | 自:AT増(4T)+麻痺か衰弱状態なら、連続増+麻痺・衰弱減 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]イレイザー |

PL / カミヤキサラ