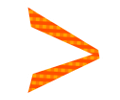<< 2:00>> 4:00




襲いかかってくる、魔物、と呼んでいいのかすらよくわからない相手を殴り飛ばしてすこしは気分がすっきりした。かといって、急激に状況が変わる事はなく廃墟を進んでいるうちに一時間が経過する。
「……ッ」
突然やってくる記憶と感情の奔流。一時間毎にやってくる“イバラシティ”での、そこにいる自分ではない自分の記憶や感情が一気に流れ込んでくる。
無遠慮に流し込まれるそれに慣れる事はおそらく無いだろう。歩く足を止めて、地面に座り込んで頭を押さえながら忌々しく歯噛みする。
しばらくして記憶の流れが落ち着けば、はあ、と大きく息を吐き出す。
「このシステム、いらねえん、じゃ、ねえか……」
よろよろと立ち上がり、ズボンの砂をはらいながら愚痴めいたつぶやきをこぼす。この、イバラシティの記憶を自分が得る事になんの意味があるのかという疑問に答えてくれる相手はいない。舘和夫、という男は自分とは完全に切り離せる存在ではないのだろうか。
ここ最近の彼は、どうやら今までの自分の行いに疑問を持ち始めたらしい。それもそうだろう。何せ作られ、あてがわれた記憶と記録だ。今まで欠片も疑問を持たなかったのはその直前まで彼が存在していなかった何よりの証拠になる。
当の本人はそんな事実を知らないので、今までの空白を埋めるかの如く自分自身の為の時間、というものを作り始めたらしい。まだ、行き先は少ない。
「……」
口を僅かに開いて、すぐに閉じた。ここで呟いたところで聞こえはしない。
“お前は、何がしたいんだ?”
口の中にとどめた言葉を頭の中で呟いた。舘、という男の中では自らに対するコンプレックスが渦巻いている。異能のある世界の中でも彼の異能(という体なだけで、ゾンビである自分の体の特製なのだが)は奇特に写るらしい。
(……だが、)
彼のこの作られた記憶もおそらくは自分が今の状態をよしと思っていない事が反映されているのだと思うと、なんとも言えない気持ちになる。
死んだ人間から生み出された、いびつな人間。それが今、自分の預かり知らぬ所で生きていく事にもがいている。
羨ましいような妬ましいような、複雑な感情に再び大きく息を吐いた。
この身体に対して大きすぎる記憶も感情も毒のようなものだ。蝕まれた先、まるで自分が生きている人間だなんて錯覚しようものなら笑い話にもならない。
じっと自らの手をみる。包帯を巻いてごまかしてはいるが隙間から見えるのは生気の無い土気色の肌。擦れた場所から血が滲み塞がる事はない。いつか、いつかは動きを止める、中途半端な存在。
「……」
頭を左右に振って、思考を振り切ると歩く速度を速めた。
万が一にも考えてはいけない。俺の代わりに生きてくれ、などと、そんなことは。
もう、終わっているのだ。自分も、イバラシティのあの男も。なにも、はじまらない。
そう、なにも。



ENo.116 雲谷 煙次/ケムルス とのやりとり

ENo.167 卯島渉/因幡うさ子 とのやりとり

ENo.1495 鹿瀬 満月 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 おにぎり を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












チナミ区 J-11(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。

エディアンが香りの元へと振り向くと――

満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
鬼の口へと放り込まれる。
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
屋台の前ではしゃぐエディアン。
チャットが閉じられる――














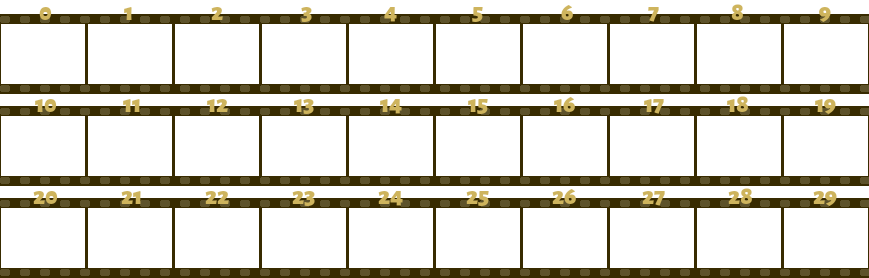





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



襲いかかってくる、魔物、と呼んでいいのかすらよくわからない相手を殴り飛ばしてすこしは気分がすっきりした。かといって、急激に状況が変わる事はなく廃墟を進んでいるうちに一時間が経過する。
「……ッ」
突然やってくる記憶と感情の奔流。一時間毎にやってくる“イバラシティ”での、そこにいる自分ではない自分の記憶や感情が一気に流れ込んでくる。
無遠慮に流し込まれるそれに慣れる事はおそらく無いだろう。歩く足を止めて、地面に座り込んで頭を押さえながら忌々しく歯噛みする。
しばらくして記憶の流れが落ち着けば、はあ、と大きく息を吐き出す。
「このシステム、いらねえん、じゃ、ねえか……」
よろよろと立ち上がり、ズボンの砂をはらいながら愚痴めいたつぶやきをこぼす。この、イバラシティの記憶を自分が得る事になんの意味があるのかという疑問に答えてくれる相手はいない。舘和夫、という男は自分とは完全に切り離せる存在ではないのだろうか。
ここ最近の彼は、どうやら今までの自分の行いに疑問を持ち始めたらしい。それもそうだろう。何せ作られ、あてがわれた記憶と記録だ。今まで欠片も疑問を持たなかったのはその直前まで彼が存在していなかった何よりの証拠になる。
当の本人はそんな事実を知らないので、今までの空白を埋めるかの如く自分自身の為の時間、というものを作り始めたらしい。まだ、行き先は少ない。
「……」
口を僅かに開いて、すぐに閉じた。ここで呟いたところで聞こえはしない。
“お前は、何がしたいんだ?”
口の中にとどめた言葉を頭の中で呟いた。舘、という男の中では自らに対するコンプレックスが渦巻いている。異能のある世界の中でも彼の異能(という体なだけで、ゾンビである自分の体の特製なのだが)は奇特に写るらしい。
(……だが、)
彼のこの作られた記憶もおそらくは自分が今の状態をよしと思っていない事が反映されているのだと思うと、なんとも言えない気持ちになる。
死んだ人間から生み出された、いびつな人間。それが今、自分の預かり知らぬ所で生きていく事にもがいている。
羨ましいような妬ましいような、複雑な感情に再び大きく息を吐いた。
この身体に対して大きすぎる記憶も感情も毒のようなものだ。蝕まれた先、まるで自分が生きている人間だなんて錯覚しようものなら笑い話にもならない。
じっと自らの手をみる。包帯を巻いてごまかしてはいるが隙間から見えるのは生気の無い土気色の肌。擦れた場所から血が滲み塞がる事はない。いつか、いつかは動きを止める、中途半端な存在。
「……」
頭を左右に振って、思考を振り切ると歩く速度を速めた。
万が一にも考えてはいけない。俺の代わりに生きてくれ、などと、そんなことは。
もう、終わっているのだ。自分も、イバラシティのあの男も。なにも、はじまらない。
そう、なにも。



ENo.116 雲谷 煙次/ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.167 卯島渉/因幡うさ子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1495 鹿瀬 満月 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
Ⅳ 「そうか、くっくっ。玲瓏のその面白くない顔は見ていて実に面白い。 愛着すら湧いてくるが、自分で見れぬのが残念なことよ。 さてさて、また面白い生き物が来る。 どれ叩きのめして憂さでも晴らすか。おいしい所はくれてやろう。 そのうちそれが病みつきになるかもしれんぞ。 趣味の一つにでもなればしめたものではないか。」 |
| 玲瓏 「……不良と猫、か。ワケのわからん奴らよりは、殴りがいがありそう、だな」 |
ItemNo.6 おにぎり を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!











チナミ区 J-11(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。
 |
エディアン 「皆さんこんにちはー!! 私はいま、梅楽園に来ていまーす!」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
エディアン 「・・・・・何か匂いますね。(くんくん・・・) ・・・これは!・・・パンケーキの香りッ」 |
エディアンが香りの元へと振り向くと――

ベニ
二本の角を持つ体格の良い赤い大鬼。怖い顔。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
 |
ベニ 「残念、こいつはベビーカステラだ。」 |
満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
 |
エディアン 「ベビーカステラ!?私も食べてみ――」 |
 |
ベニ 「残念、品切れだよ。」 |
鬼の口へと放り込まれる。
 |
エディアン 「・・・・・。・・・何なんですか? ただ美味しいものを見せつけたい人ですか?」 |
 |
ベニ 「ああそうさ、羨ましいだろ。」 |
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
 |
エディアン 「・・・どうしてこんなところでこんなことを?」 |
 |
ベニ 「あー、あんたエディ・・・アン?だったな。俺はベニだ。イバラじゃアカツカという名だった。 あちらの生活がクセになっちまったようで、同じように梅楽園でこれを焼いちまってる。」 |
 |
エディアン 「そうですか・・・ それにしても、よく道具や素材がありましたねぇ。」 |
 |
ベニ 「残骸を根気強く漁ってみろ。イバラシティの物が深く埋もれていたりする。 何故か新鮮な食い物だったりな。アンジニティに比べりゃここハザマすら天国だ。」 |
 |
ベニ 「俺の住処ら辺にも食材が在ったようで、いま仲間に運ばせている。 届いたらどんどん焼いてやる。飢えてっだろ、アンジニティ連中は。」 |
 |
エディアン 「本当ですか!?それは楽しみですっ!! 準備ができたらまたこうして連絡してくださいね!絶対行きますッ!!」 |
屋台の前ではしゃぐエディアン。
 |
ベニ 「・・・あいよ、よろしくよろしく。あー、有料だから金は用意しとけよ。」 |
 |
エディアン 「はい!皆さんもぜひぜひ訪れてみてくださいねぇ!! それでは、また来週・・・じゃなくって―― また1時間後っ!!」 |
チャットが閉じられる――





ENo.1132
古瀬圭一郎



[イラスト右側]
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
異能は無いがゾンビになる前にうけた多数の人体実験等の影響により、常人以上の身体能力を発揮することが可能。これにより生前の頃のような血の気の多い姿も見られるとか。
ただし、それ相応に反動がありひどい時はロクに動くことすらできなくなる。
ハザマ世界では元の世界やアンジニティよりその能力が使いやすいらしい。
古瀬圭一郎は本名だが、今人に名乗る場合は玲瓏と名乗っている。
......................................................
[イラスト左側]
舘和男 たち かずお
37歳 173cm
イバラシティでカフェバー【白詰草】を営む。
物静かで店を営むにしては少々愛想が無いようにも思えるが、特に性格的に冷たいとかではなくどちらかといえば優しく柔和な雰囲気を持つ。
世界の侵略については自分ひとりの力でどうこうできる問題ではないので、特段それを意識して生活している事はない。どちらにしても自分の異能では侵略者に対抗するのは難しいとも思っている。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
「こんな力で痛みを感じてたらショック死してしまうからではないか」と冗談めかしていうのが常套句となっている。
幼い頃はこの異能の力を見たがる同級生等に過度に暴力を振るわれた事もあった。
スポット:カフェバー《白詰草》
http://lisge.com/ib/talk.php?s=457
古瀬圭一郎 ふるせ けいいちろう
享年32歳 173cm
元々いた世界で紆余曲折の末に生ける屍(ゾンビ)となった男。
世界の片隅に誰にも迷惑をかけないよう、そして静かに朽ちていける事を望んでいたがその思いも叶わず、気が付けば 《否定の世界》へと飛ばされていた。
生前はどちらかといえば短気だったが、死んでからは自分の処理能力の遅さにイラつく事すら疲れてしまったの、静かで地味。
異能は無いがゾンビになる前にうけた多数の人体実験等の影響により、常人以上の身体能力を発揮することが可能。これにより生前の頃のような血の気の多い姿も見られるとか。
ただし、それ相応に反動がありひどい時はロクに動くことすらできなくなる。
ハザマ世界では元の世界やアンジニティよりその能力が使いやすいらしい。
古瀬圭一郎は本名だが、今人に名乗る場合は玲瓏と名乗っている。
......................................................
[イラスト左側]
舘和男 たち かずお
37歳 173cm
イバラシティでカフェバー【白詰草】を営む。
物静かで店を営むにしては少々愛想が無いようにも思えるが、特に性格的に冷たいとかではなくどちらかといえば優しく柔和な雰囲気を持つ。
世界の侵略については自分ひとりの力でどうこうできる問題ではないので、特段それを意識して生活している事はない。どちらにしても自分の異能では侵略者に対抗するのは難しいとも思っている。
【不死体――しなずのからだ】
端的に言ってしまえば驚異的な回復力を持っている異能。ただし、不死と名はついているが回復力以上にダメージを与えるか、一撃で死に追いやってしまえば死亡する。
失ってしまった部分が再生する事はないが、体から離れてしまった部位はくっつけてしばらく置いておくと融合して元通りになる。頭と首が切り離されていたとしても心臓が動いているうちに合わせてしまえば元に戻る。らしい。試した事は流石にない。
異能の代償なのか、痛覚がない。
「こんな力で痛みを感じてたらショック死してしまうからではないか」と冗談めかしていうのが常套句となっている。
幼い頃はこの異能の力を見たがる同級生等に過度に暴力を振るわれた事もあった。
スポット:カフェバー《白詰草》
http://lisge.com/ib/talk.php?s=457
16 / 30
120 PS
チナミ区
K-14
K-14

















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 鈍色の沈丁花 | 装飾 | 30 | 器用10 | - | - | |
| 5 | 無骨な石斧 | 武器 | 33 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 7 | おにぎり | 料理 | 30 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 9 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]敏捷10(LV10)[効果2]復活10(LV10)[効果3]体力15(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 26 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| アドレナリン | 5 | 0 | 80 | 自:AT増(4T)+麻痺か衰弱状態なら、連続増+麻痺・衰弱減 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]イレイザー |

PL / カミヤキサラ