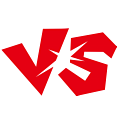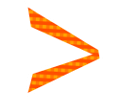<< 8:00~9:00




ぶっちゃけた話、憂鬱なのだった。
小学生は気楽なモンだと会う大人たちはみんな言うけれど、絶対に嘘だと思う。小学生には小学生なりの悩みってもんがあるのだ。
「俺さ。何して生きていくんだろう」などと早熟気取って垂れる憂いも、中学受験がある世の中では必ずしも的外れとは言えない。小学生だって現実を考えたりするのだ。
俺の場合、来月の母親の命日に合わせてナイーブの入ってる父親(本当に気が早い)とか、アホほど出された宿題(やったことは過去五年ほどない)とか、あと何より世界がぶっ壊れたのかと思うくらいの熱帯夜(寝れない)とか、さっきに外れた自転車のチェーン(現在進行形で直している)とか。
「ねーねー。ありがとうくらい言ってもよくない? 恩人だよー、ボク」
中でも極めつけは、うざったく纏わりついてくるセーラー服の女子高生だ。
事の発端と言えば、夏休み初日の解放感に任せて、人生初の夜遊びに繰り出したことだった。
もっと辿るなら親父が仕事で家を空けていたことにも起因するし、さらに辿るならテレビで夏の星座特集をやっていたこともあるし、まだまだ辿れば何もかも世の中が悪い。俺は悪くない。
ともあれ。俺は慣れない夜の街で、迂闊にも薄暗い細路地に自転車で突っ込んで、こともあろうにガラの悪そうな兄ちゃんにぶつかってしまったのだ。
今後見辛いところを曲がるときはちゃんと減速する癖をつけようと固く思いました。
いや、まあその後俺は大人しく転がった自転車を立て直し、呆けた兄ちゃんを置き去りに、何もなかったことにして颯爽と立ち去ろうとしたのだが、その後の展開が非常に好ましくなかった。
「……なあなあ、正義の味方さん。恩人ってのはさ、幼気な小学生を喧嘩の口実に使って、挙句にその子の愛車を武器としてぶん回したうえで主張してる?」
そういうことだ。
もう少しくらい中身の解像度を上げよう。
俺が不良に絡まれていると勘違いしたこいつが、迷惑にも『その子を離せ』的に蹴り込んできて、俺の自転車で不良をボコボコにした。俺の自転車で。
お蔭でチェーンは外れるわ車体は気持ち歪んでるわで散々だ。
半袖のパーカーを羽織った女子高生は、少しばつが悪そうに黒髪の毛先を弄って視線を逸らした。暗闇の中でも、鮮やかな緋色だから分かりやすい。
「いやあ……だってほら、素手で殴るといたそうだったし。っていうか駄目だよ、こんな時間にこんなところに来ちゃあ。ああいうのいるんだし」
「うわすっげブーメラン。つーかあの人そこまで悪くないんじゃ……」
彼女が白く長い指で示したのは、肌がゴツゴツと無機質に隆起した姿になった、可哀そうな被害者。たとえ女子供が相手とは言え、強襲されて異能と暴力に訴えた彼を誰が責められようか。
そもそも、この街では性別なんか暴力指数の当てにならない。這い蹲っているのが彼で、呑気にコンビニの袋をがさがさやっているのが彼女というのがその証左だ。
そのくらいのこと、一二年足らずの人生でだってとっくに知っていた。
「身体強化の異能って、手とか硬くなったりすぐ治ったりしないのかよ」
「いやあ、そんな都合よくないよ。あれ、買ってなかったっけ──ん? 見ただけで分かるの?」
「片手で自転車ぶんぶん振り回してたら誰だってそう思うよ。融通の利かない異能だな、くそ」
お陰様でしなくていい作業をさせられている。未だ噛み合わないチェーンを前に、思わずため息が零れた。つーか何で壊したアイツじゃなくて壊された俺が直してるのか。
ああくそ、何かもうめんどくさくなってきたな。
投げ出すように立ち上がり、背筋を伸ばすついでにビルに切り取られた細長い空を見上げる。七夕の過ぎた濃紺の夜空には、今も天の川が滔々と流れて世界の明度を上げている。もう少し開けた大通りに出れば、月だってさぞ綺麗に見えるだろう。
そういう景色を見に来たっていうのに、どうして俺の指先は潤滑油まみれになっているのか。言うまでもない、後ろのお節介のせいだ。
改めて文句を言ってやる。そう決めて振り返ったところ、目の前にシュークリームがあった。抹茶の粉とかまぶしてある、コンビニスイーツにしてはそこそこの値段がしそうな奴だ。
「……いや、なにこれ」
「シュークリームって美味しいんだよ。知らなかったかな」
「そこじゃねえよ。あと俺手汚れてるんだけど」
気にするなとでも言いたげに、ずいとシュークリームが近づいた。
「自分用だったんだけど、あげるからさ。機嫌直しなよ?」
「誰の所為だと思ってんだ!? ──もが!?」
思わず声を荒げて突っ込んだ瞬間、そこを逃さず勢いよく突っ込まれた。小麦の香ばしさと抹茶の芳しさが口腔から鼻腔にかけてを蹂躙していく。美味い不味い以前に普通に息苦しい。
どうにかクリームを零さないよう気を遣って噛み千切り、もちゃもちゃと咀嚼の傍ら睨み付ける。何かもう全体的に無茶苦茶だこの女。
「どう、美味しいでしょ? その上女子高生の『あーん』だよ?」
「たぶん本来の味の半分も理解できなかったし、後半どうでもいいし……」
「どうでもッ……」
息苦しさと合わせて収支過不足なく差し引きゼロという感じだった。女子高生、そんな有難がるような紋所なのだろうか。小学生にはちょっと分からない理屈だ。
指先をシャツで拭い、心なしか肩が落ち込んでいる女子高生の手から残ったシュークリームをひったくる。落ち着いて食べてみれば、成る程確かに美味しい。ただ、結構クリームが甘くて喉が渇くこと。
「飲み物とかないの?」
「……あるけど。可愛げないな、キミ。ほら、お茶だ」
あるのか。そしてくれるのか。強請ってみるものだ。出て来たのは緑茶のペットボトルだったが、この際文句は言うまい。
意外に思いながら差し出した手に、しかしいつまで立ってもペットボトルはおろか、缶や紙パックすらも置かれない。
代わりに、頭の上でどむんと鈍い音がした。
「いってェ──!?」
こいつ、人の頭をペットボトルで殴りやがった……ッ!?
「……あ、間違えたな。ラベルの銘柄をちゃんと向けるべきだった。マナー違反だコレ」
「そ、そこじゃねえよ……くぅ……何すんだ急に」
涙目で見上げる。打撲部を抱えて蹲った上にそもそもの身長差が相まって、凄く見下されている気分だ。何で年下を殴ってああも勝ち誇ったような表情になれるのか、俺にはとんと理解できなかった。
どうでもいいけど、結構女子高生には胸があるらしい。この視点だとパースとかが凄い。
「無礼だったから」
マジで見下されてた。しかもどの口がほざくのかという罪状だった。
一撃加えて満足したのか、ぱきぱきとキャップを開ける気の利かせようまで披露して、今度こそ俺に手渡されるペットボトル。『よく振ってからお飲みください』の注釈は無視してもよさそうだ。
……我ながら、だいぶ不用心な。人からもらったものをホイホイ口にするとは。
そんな自戒が浮かばないでもなかったが、あんまりにも馬鹿らしいので気にしないことにした。湿らす程度の一口を含む。抹茶と緑茶、味は結構違うみたいだ。
緩やかな風が吹いて、路地裏の陰気な空気を緩慢に入れ替えていく。女子高生の黒髪が、翼のように広がった。
「で、こんな夜更けに何しに出て来たのさ、悪ガキ」
「……。星が綺麗だったから。それだけ」
言って、何だか自分がロマンチストみたいに思えて顔を顰める。『ぶってる』みたいで受け付けない。
案の定というか、茶化すような口笛が聞こえた。気恥ずかしくなって、それ以上を遮るように質問を返した。
「そっちは何」
「コンビニ帰りさ。夜食を買いにね」
ぷらぷら、がさがさ。夜闇に浮かぶクラゲみたいなビニール袋が揺れた。薄く覗く中身は、カップラーメンとかポテトチップスとかそう言うのばかり。
「太るぞ」
「ふふん、全部胸に行くから大丈夫──あ、今見たでしょ」
図星だった。思わず固まり、血流だけが加速する。気温が二度ほど上がったような気がした。
「すけべ」
「ッ、ば、仕方ないだろいまの! 言われたら見るじゃんだってさあ!」
不用意だった。
泡を食ってばたばたする俺を見て、けたけた女子高生が笑う。どうしようもなく完全に玩具扱いだ。
もう何を言っても逆効果な気がして、俺には小さく唸ることしかできない。それもまた、単なる敗北宣言にしか過ぎないけど。
「いやぁー、可愛げがないとか言ったけどそうでもないね。ちゃんとあるじゃん」
「うるさい、うるさい」
熱を冷ますため、中身が半分ほどになってしまったペットボトルを傾ける。
早くこの場から逃げ出したい。だが無情にも自転車のチェーンは外れたまま。修理を終えるまで、この関係性を享受するしかない。
未だ小さく聞こえる笑い声に歯噛みしながら、再度チェーンと格闘を始める。相も変わらず俺を縫い留めるように、頑としてチェーンは元の位置に収まらない。千切ってやろうかもう。
「力技じゃハマんないよー。指挟まないように気を付けて、ある程度嵌め直したら普通にペダル回してごらん」
やってみた。すぐに直った。
「……いや先言えよ」
何だったんだ、今までの時間。
ともあれ、自転車が直ったならここに居座る理由もない。そそくさとスタンドを蹴り、サドルに跨る。
「何だ、もう行っちゃうの。自己紹介もしてないのに」
「いいよ。会わないでしょたぶん」
「えー……じゃあボクの名前だけ教えさせてよ」
「別に。あとででいい。じゃあバイバイ、シュークリームとお茶御馳走さまでした」
物惜しげな声を出されても名乗らないものは名乗らないし聞かないものは聞かない。残った緑茶だけ丁重に返して、若干噛み合いの悪くなったペダルを踏み込む。
踏み込もうとして。
「待ちなって。──ちょっと、ボクと勝負してみない?」
あんまりにも唐突な誘いに、何故かその足が止まった。
振り返った先、俺が両の瞳で見たものは、唇を吊り上げ静かに笑んだ彼女と、その頭上に輝くやけに大きな月だった。



ENo.612 チホ とのやりとり

ENo.658 天弖 とのやりとり

ENo.1257 アルマ とのやりとり

ENo.1443 三波 とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。






六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



すごい石材(400 PS)を購入しました。
自然LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
合成LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
防具LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
オーディオル(1039) とカードを交換しました!
怪人カード「バイオリングモ」 (ラプチャー)
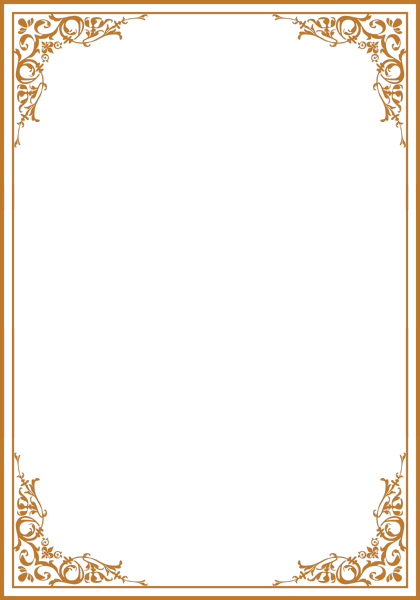
グラインドコア を研究しました!(深度2⇒3)
サモン:ヴァンパイア を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:キャノン を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
レッドショック を習得!
アリア を習得!
ファイアボルト を習得!
デストロイ を習得!
ボムトラップ を習得!
火の祝福 を習得!
獄炎陣 を習得!
フレアトラップ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!





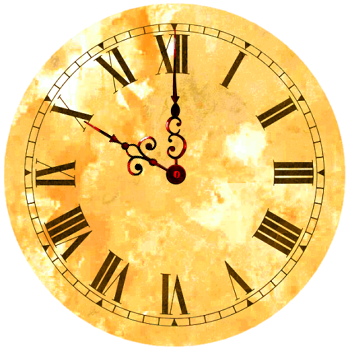
[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。




チャット画面に映る、4人の姿。
少しの間、無音となる。
くんくんと匂いを嗅ぐふたり。
3人の様子を遠目に眺める白南海。
チャットが閉じられる――






梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・





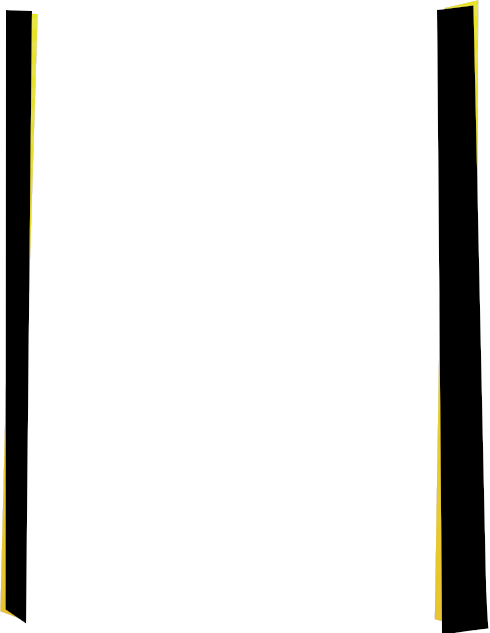
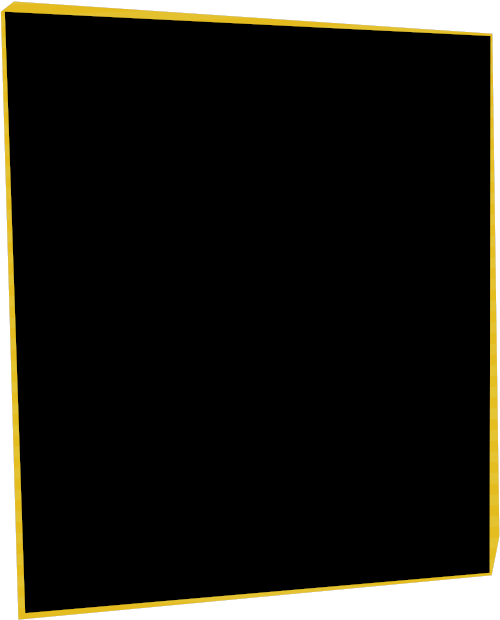





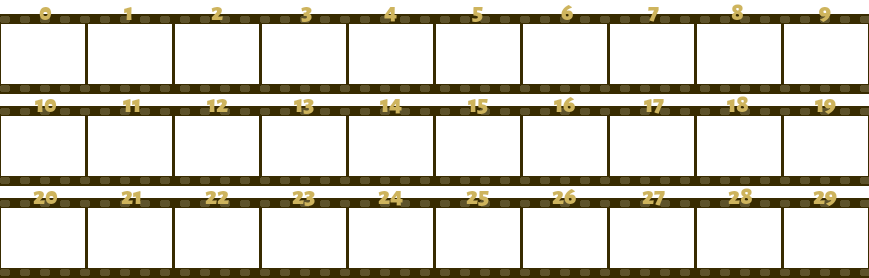







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「ちょっと、ボクと勝負してみない?」
夏休み最大の厄ネタは、そう言って怪しく笑った。
LOG:8⇔0/Wednesday, 13 July 2014/PM10:43
Repeat
ぶっちゃけた話、憂鬱なのだった。
小学生は気楽なモンだと会う大人たちはみんな言うけれど、絶対に嘘だと思う。小学生には小学生なりの悩みってもんがあるのだ。
「俺さ。何して生きていくんだろう」などと早熟気取って垂れる憂いも、中学受験がある世の中では必ずしも的外れとは言えない。小学生だって現実を考えたりするのだ。
俺の場合、来月の母親の命日に合わせてナイーブの入ってる父親(本当に気が早い)とか、アホほど出された宿題(やったことは過去五年ほどない)とか、あと何より世界がぶっ壊れたのかと思うくらいの熱帯夜(寝れない)とか、さっきに外れた自転車のチェーン(現在進行形で直している)とか。
「ねーねー。ありがとうくらい言ってもよくない? 恩人だよー、ボク」
中でも極めつけは、うざったく纏わりついてくるセーラー服の女子高生だ。
事の発端と言えば、夏休み初日の解放感に任せて、人生初の夜遊びに繰り出したことだった。
もっと辿るなら親父が仕事で家を空けていたことにも起因するし、さらに辿るならテレビで夏の星座特集をやっていたこともあるし、まだまだ辿れば何もかも世の中が悪い。俺は悪くない。
ともあれ。俺は慣れない夜の街で、迂闊にも薄暗い細路地に自転車で突っ込んで、こともあろうにガラの悪そうな兄ちゃんにぶつかってしまったのだ。
今後見辛いところを曲がるときはちゃんと減速する癖をつけようと固く思いました。
いや、まあその後俺は大人しく転がった自転車を立て直し、呆けた兄ちゃんを置き去りに、何もなかったことにして颯爽と立ち去ろうとしたのだが、その後の展開が非常に好ましくなかった。
「……なあなあ、正義の味方さん。恩人ってのはさ、幼気な小学生を喧嘩の口実に使って、挙句にその子の愛車を武器としてぶん回したうえで主張してる?」
そういうことだ。
もう少しくらい中身の解像度を上げよう。
俺が不良に絡まれていると勘違いしたこいつが、迷惑にも『その子を離せ』的に蹴り込んできて、俺の自転車で不良をボコボコにした。俺の自転車で。
お蔭でチェーンは外れるわ車体は気持ち歪んでるわで散々だ。
半袖のパーカーを羽織った女子高生は、少しばつが悪そうに黒髪の毛先を弄って視線を逸らした。暗闇の中でも、鮮やかな緋色だから分かりやすい。
「いやあ……だってほら、素手で殴るといたそうだったし。っていうか駄目だよ、こんな時間にこんなところに来ちゃあ。ああいうのいるんだし」
「うわすっげブーメラン。つーかあの人そこまで悪くないんじゃ……」
彼女が白く長い指で示したのは、肌がゴツゴツと無機質に隆起した姿になった、可哀そうな被害者。たとえ女子供が相手とは言え、強襲されて異能と暴力に訴えた彼を誰が責められようか。
そもそも、この街では性別なんか暴力指数の当てにならない。這い蹲っているのが彼で、呑気にコンビニの袋をがさがさやっているのが彼女というのがその証左だ。
そのくらいのこと、一二年足らずの人生でだってとっくに知っていた。
「身体強化の異能って、手とか硬くなったりすぐ治ったりしないのかよ」
「いやあ、そんな都合よくないよ。あれ、買ってなかったっけ──ん? 見ただけで分かるの?」
「片手で自転車ぶんぶん振り回してたら誰だってそう思うよ。融通の利かない異能だな、くそ」
お陰様でしなくていい作業をさせられている。未だ噛み合わないチェーンを前に、思わずため息が零れた。つーか何で壊したアイツじゃなくて壊された俺が直してるのか。
ああくそ、何かもうめんどくさくなってきたな。
投げ出すように立ち上がり、背筋を伸ばすついでにビルに切り取られた細長い空を見上げる。七夕の過ぎた濃紺の夜空には、今も天の川が滔々と流れて世界の明度を上げている。もう少し開けた大通りに出れば、月だってさぞ綺麗に見えるだろう。
そういう景色を見に来たっていうのに、どうして俺の指先は潤滑油まみれになっているのか。言うまでもない、後ろのお節介のせいだ。
改めて文句を言ってやる。そう決めて振り返ったところ、目の前にシュークリームがあった。抹茶の粉とかまぶしてある、コンビニスイーツにしてはそこそこの値段がしそうな奴だ。
「……いや、なにこれ」
「シュークリームって美味しいんだよ。知らなかったかな」
「そこじゃねえよ。あと俺手汚れてるんだけど」
気にするなとでも言いたげに、ずいとシュークリームが近づいた。
「自分用だったんだけど、あげるからさ。機嫌直しなよ?」
「誰の所為だと思ってんだ!? ──もが!?」
思わず声を荒げて突っ込んだ瞬間、そこを逃さず勢いよく突っ込まれた。小麦の香ばしさと抹茶の芳しさが口腔から鼻腔にかけてを蹂躙していく。美味い不味い以前に普通に息苦しい。
どうにかクリームを零さないよう気を遣って噛み千切り、もちゃもちゃと咀嚼の傍ら睨み付ける。何かもう全体的に無茶苦茶だこの女。
「どう、美味しいでしょ? その上女子高生の『あーん』だよ?」
「たぶん本来の味の半分も理解できなかったし、後半どうでもいいし……」
「どうでもッ……」
息苦しさと合わせて収支過不足なく差し引きゼロという感じだった。女子高生、そんな有難がるような紋所なのだろうか。小学生にはちょっと分からない理屈だ。
指先をシャツで拭い、心なしか肩が落ち込んでいる女子高生の手から残ったシュークリームをひったくる。落ち着いて食べてみれば、成る程確かに美味しい。ただ、結構クリームが甘くて喉が渇くこと。
「飲み物とかないの?」
「……あるけど。可愛げないな、キミ。ほら、お茶だ」
あるのか。そしてくれるのか。強請ってみるものだ。出て来たのは緑茶のペットボトルだったが、この際文句は言うまい。
意外に思いながら差し出した手に、しかしいつまで立ってもペットボトルはおろか、缶や紙パックすらも置かれない。
代わりに、頭の上でどむんと鈍い音がした。
「いってェ──!?」
こいつ、人の頭をペットボトルで殴りやがった……ッ!?
「……あ、間違えたな。ラベルの銘柄をちゃんと向けるべきだった。マナー違反だコレ」
「そ、そこじゃねえよ……くぅ……何すんだ急に」
涙目で見上げる。打撲部を抱えて蹲った上にそもそもの身長差が相まって、凄く見下されている気分だ。何で年下を殴ってああも勝ち誇ったような表情になれるのか、俺にはとんと理解できなかった。
どうでもいいけど、結構女子高生には胸があるらしい。この視点だとパースとかが凄い。
「無礼だったから」
マジで見下されてた。しかもどの口がほざくのかという罪状だった。
一撃加えて満足したのか、ぱきぱきとキャップを開ける気の利かせようまで披露して、今度こそ俺に手渡されるペットボトル。『よく振ってからお飲みください』の注釈は無視してもよさそうだ。
……我ながら、だいぶ不用心な。人からもらったものをホイホイ口にするとは。
そんな自戒が浮かばないでもなかったが、あんまりにも馬鹿らしいので気にしないことにした。湿らす程度の一口を含む。抹茶と緑茶、味は結構違うみたいだ。
緩やかな風が吹いて、路地裏の陰気な空気を緩慢に入れ替えていく。女子高生の黒髪が、翼のように広がった。
「で、こんな夜更けに何しに出て来たのさ、悪ガキ」
「……。星が綺麗だったから。それだけ」
言って、何だか自分がロマンチストみたいに思えて顔を顰める。『ぶってる』みたいで受け付けない。
案の定というか、茶化すような口笛が聞こえた。気恥ずかしくなって、それ以上を遮るように質問を返した。
「そっちは何」
「コンビニ帰りさ。夜食を買いにね」
ぷらぷら、がさがさ。夜闇に浮かぶクラゲみたいなビニール袋が揺れた。薄く覗く中身は、カップラーメンとかポテトチップスとかそう言うのばかり。
「太るぞ」
「ふふん、全部胸に行くから大丈夫──あ、今見たでしょ」
図星だった。思わず固まり、血流だけが加速する。気温が二度ほど上がったような気がした。
「すけべ」
「ッ、ば、仕方ないだろいまの! 言われたら見るじゃんだってさあ!」
不用意だった。
泡を食ってばたばたする俺を見て、けたけた女子高生が笑う。どうしようもなく完全に玩具扱いだ。
もう何を言っても逆効果な気がして、俺には小さく唸ることしかできない。それもまた、単なる敗北宣言にしか過ぎないけど。
「いやぁー、可愛げがないとか言ったけどそうでもないね。ちゃんとあるじゃん」
「うるさい、うるさい」
熱を冷ますため、中身が半分ほどになってしまったペットボトルを傾ける。
早くこの場から逃げ出したい。だが無情にも自転車のチェーンは外れたまま。修理を終えるまで、この関係性を享受するしかない。
未だ小さく聞こえる笑い声に歯噛みしながら、再度チェーンと格闘を始める。相も変わらず俺を縫い留めるように、頑としてチェーンは元の位置に収まらない。千切ってやろうかもう。
「力技じゃハマんないよー。指挟まないように気を付けて、ある程度嵌め直したら普通にペダル回してごらん」
やってみた。すぐに直った。
「……いや先言えよ」
何だったんだ、今までの時間。
ともあれ、自転車が直ったならここに居座る理由もない。そそくさとスタンドを蹴り、サドルに跨る。
「何だ、もう行っちゃうの。自己紹介もしてないのに」
「いいよ。会わないでしょたぶん」
「えー……じゃあボクの名前だけ教えさせてよ」
「別に。あとででいい。じゃあバイバイ、シュークリームとお茶御馳走さまでした」
物惜しげな声を出されても名乗らないものは名乗らないし聞かないものは聞かない。残った緑茶だけ丁重に返して、若干噛み合いの悪くなったペダルを踏み込む。
踏み込もうとして。
「待ちなって。──ちょっと、ボクと勝負してみない?」
あんまりにも唐突な誘いに、何故かその足が止まった。
振り返った先、俺が両の瞳で見たものは、唇を吊り上げ静かに笑んだ彼女と、その頭上に輝くやけに大きな月だった。
語るのが遅れたが、これは、きっとなかった話。
あってはいけない物語だ。



ENo.612 チホ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.658 天弖 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.1257 アルマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1443 三波 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。





ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



すごい石材(400 PS)を購入しました。
自然LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
合成LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
防具LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
オーディオル(1039) とカードを交換しました!
怪人カード「バイオリングモ」 (ラプチャー)
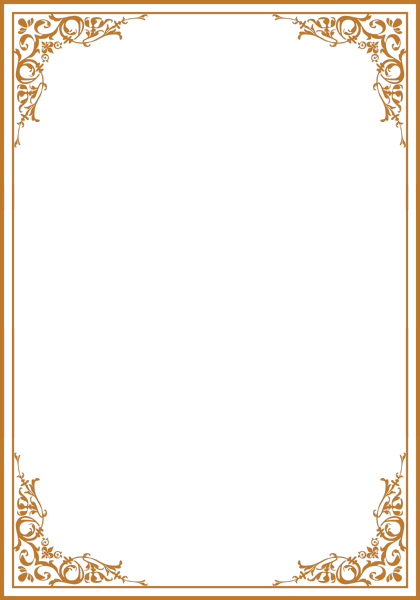
グラインドコア を研究しました!(深度2⇒3)
サモン:ヴァンパイア を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:キャノン を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
レッドショック を習得!
アリア を習得!
ファイアボルト を習得!
デストロイ を習得!
ボムトラップ を習得!
火の祝福 を習得!
獄炎陣 を習得!
フレアトラップ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!





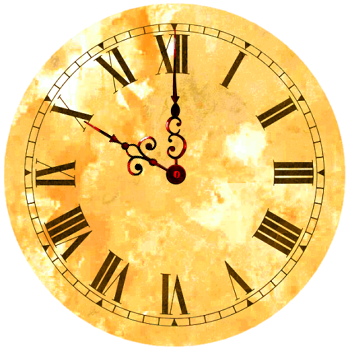
[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
 |
アンドリュウ 「ヘーイ!皆さんオゲンキですかー!!」 |
 |
ロジエッタ 「チャット・・・・・できた。・・・ん、あれ・・・?」 |
 |
エディアン 「あらあら賑やかですねぇ!!」 |
 |
白南海 「・・・ンだこりゃ。既に退室してぇんだが、おい。」 |
チャット画面に映る、4人の姿。
 |
ロジエッタ 「ぁ・・・ぅ・・・・・初めまして。」 |
 |
アンドリュウ 「はーじめまして!!アンドウリュウいいまーすっ!!」 |
 |
エディアン 「はーじめまして!エディアンカーグいいまーすっ!!」 |
 |
白南海 「ロストのおふたりですか。いきなり何用です?」 |
 |
アンドリュウ 「用・・・用・・・・・そうですねー・・・」 |
 |
アンドリュウ 「・・・特にないでーす!!」 |
 |
ロジエッタ 「私も別に・・・・・ ・・・ ・・・暇だったから。」 |
少しの間、無音となる。
 |
エディアン 「えぇえぇ!暇ですよねー!!いいんですよーそれでー。」 |
 |
ロジエッタ 「・・・・・なんか、いい匂いする。」 |
 |
エディアン 「ん・・・?そういえばほんのりと甘い香りがしますねぇ。」 |
くんくんと匂いを嗅ぐふたり。
 |
アンドリュウ 「それはわたくしでございますなぁ! さっきまで少しCookingしていたのです!」 |
 |
エディアン 「・・・!!もしかして甘いものですかーっ!!?」 |
 |
アンドリュウ 「Yes!ほおぼねとろけるスイーツ!!」 |
 |
ロジエッタ 「貴方が・・・?美味しく作れるのかしら。」 |
 |
アンドリュウ 「自信はございまーす!お店、出したいくらいですよー?」 |
 |
ロジエッタ 「プロじゃないのね・・・素人の作るものなんて自己満足レベルでしょう?」 |
 |
アンドリュウ 「ムムム・・・・・厳しいおじょーさん。」 |
 |
アンドリュウ 「でしたら勝負でーすっ!! わたくしのスイーツ、食べ残せるものなら食べ残してごらんなさーい!」 |
 |
エディアン 「・・・・・!!」 |
 |
エディアン 「た、確かに疑わしい!素人ですものね!!!! それは私も審査しますよぉー!!・・・審査しないとですよッ!!」 |
 |
アンドリュウ 「かかってこいでーす! ・・・ともあれ材料集まんないとでーすねー!!」 |
 |
ロジエッタ 「大した自信ですね。私の舌を満足させるのは難しいですわよ。 何せ私の家で出されるデザートといえば――」 |
 |
エディアン 「皆さん急務ですよこれは!急務ですッ!! ハザマはスイーツ提供がやたらと期待できちゃいますねぇ!!」 |
3人の様子を遠目に眺める白南海。
 |
白南海 「まぁ甘いもんの話ばっか、飽きないっすねぇ。 ・・・そもそも毎時強制のわりに、案内することなんてそんな無ぇっつぅ・・・な。」 |
 |
白南海 「・・・・・物騒な情報はノーセンキューですがね。ほんと。」 |
チャットが閉じられる――





チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・



ENo.46
一栄斗

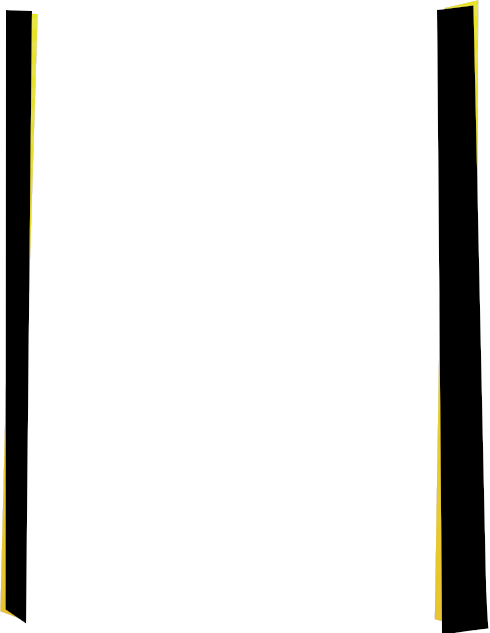
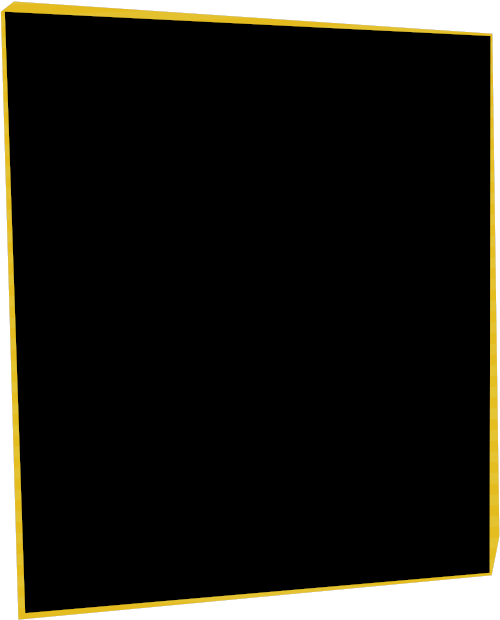
【名前】一 栄斗(ニノマエ・エイト)
【年齢】17 【性別】男
【身長/体重】179cm/87kg
【学校】相良伊橋高校3年特進科・民俗文化研究部部長・生徒会執行部副会長
「やっべ、良いこと思い付いた……やっぱ俺天才だわ」
余裕綽綽泰然自若、ヒトを食ったような軽薄な態度で常を過ごす悪ガキ。
ブレザーの代わりに黒いパーカーを羽織っている。
大抵のことは努力せずとも熟せる天才肌で、そのため特進科にいるのに授業を聞き流しがち。恐らく先生がたからの心証はあまりよくない。
彼が立ち上げた民俗文化研究部は、『学校に勝手出来る部屋が欲しいから』立ち上げられており、名前の通りの活動を行うことはごく稀。
【年齢】17 【性別】男
【身長/体重】179cm/87kg
【学校】相良伊橋高校3年特進科・民俗文化研究部部長・生徒会執行部副会長
「やっべ、良いこと思い付いた……やっぱ俺天才だわ」
余裕綽綽泰然自若、ヒトを食ったような軽薄な態度で常を過ごす悪ガキ。
ブレザーの代わりに黒いパーカーを羽織っている。
大抵のことは努力せずとも熟せる天才肌で、そのため特進科にいるのに授業を聞き流しがち。恐らく先生がたからの心証はあまりよくない。
彼が立ち上げた民俗文化研究部は、『学校に勝手出来る部屋が欲しいから』立ち上げられており、名前の通りの活動を行うことはごく稀。
30 / 30
518 PS
チナミ区
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 鉄芯 | 武器 | 35 | 治癒10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 古雑誌 | 素材 | 20 | [武器]心酔15(LV30)[防具]鎮痛15(LV30)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
| 6 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 7 | 孔雀石 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV25)[防具]耐狂15(LV25)[装飾]放毒10(LV20) | |||
| 8 | ファイナル法衣 | 法衣 | 20 | 体力10 | - | 幸運6 | |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 星柄の眼帯 | 装飾 | 67 | 舞乱10 | - | - | |
| 11 | 何か固い物体 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20) | |||
| 12 | 藍鉄鉱 | 素材 | 20 | [武器]放凍15(LV25)[防具]反凍10(LV20)[装飾]舞凍15(LV25) | |||
| 13 | ニードル | 武器 | 45 | 致命15 | - | - | 【射程1】 |
| 14 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 15 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 16 | 血色の鋼線 | 武器 | 80 | 獄炎15 | - | - | 【射程1】 |
| 17 | 毛皮 | 素材 | 15 | [武器]道連10(LV20)[防具]鎮痛10(LV30)[装飾]耐災10(LV25) | |||
| 18 | 黒い貝 | 素材 | 20 | [武器]水撃15(LV25)[防具]反闇15(LV30)[装飾]闇纏15(LV25) | |||
| 19 | 何かの骨 | 素材 | 20 | [武器]闇撃10(LV25)[防具]活力15(LV30)[装飾]強靭10(LV20) | |||
| 20 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||
| 21 | 触手 | 素材 | 20 | [武器]器用20(LV30)[防具]迫撃20(LV40)[装飾]舞縛20(LV35) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 25 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 制約 | 25 | 拘束/罠/リスク |
| 武器 | 35 | 武器作製に影響 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ストーンブラスト | 6 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| アサルト | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| アイアンナックル | 6 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| フラワリング | 5 | 0 | 50 | 敵列:魅了+領域値[地]3以上なら束縛 | |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| プチメテオカード | 6 | 0 | 40 | 敵:粗雑地撃 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| デストロイ | 5 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
| ブランチ | 6 | 0 | 100 | 敵:地痛撃&領域値[地]3以上なら、敵傷:地領痛撃 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| フェイタルポイント | 5 | 0 | 80 | 敵:精確痛撃 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| トラストラップ | 5 | 0 | 150 | 敵:罠《稲妻》LV増+敵従全:罠《稲妻》LV増 | |
| ジャックポット | 6 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| サモン:サーヴァント | 7 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| フレアトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵列:罠《猛火》LV増 | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 | |
| デスペラート | 7 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 | |
| フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| マイントラップ | 5 | 0 | 250 | 敵:罠《地雷》LV増 | |
| インファイト | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&隊列1なら更に4連撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 獄炎陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど獄炎LV増 | |
| 阿修羅 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 応酬 | 5 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】対:精確攻撃 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 | |
| 駄物発生 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『合成』で、合成成功時に自分にアイテム「駄物」が手に入る。(実験除く、1更新1つまで) |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ヒールLv.1 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
モアイと先生 (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
|
妙に頭が冴えるFOXコーヒー (ラッシュ) |
0 | 100 | 味全:連続増 | |
|
守護の壁 (ガードフォーム) |
0 | 100 | 自:DF増 | |
|
みんながんばれ~ (ディベスト) |
0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
|
ありがたさ120% (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
|
使いきり乾電池 (マスフレイム) |
0 | 230 | 敵:火撃&炎上+敵全:精確光撃&盲目+自:炎上・盲目 | |
|
ソールアッパー (ブレイドフォーム) |
0 | 160 | 自:AT増 | |
|
フォックスコーヒー (エアスラッシュ) |
0 | 110 | 敵:5連風撃 | |
|
怪人カード「バイオリングモ」 (ラプチャー) |
2 | 200 | 敵傷:風痛撃&HP・DF減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]クリエイト:キャノン | [ 3 ]バーニングチューン | [ 1 ]ジャックポット |
| [ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]電光石火 | [ 1 ]ブランチ |
| [ 1 ]オーバーウェルム | [ 2 ]オートヒール | [ 1 ]チャージ |
| [ 1 ]星火燎原 | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]ストーンブラスト |
| [ 1 ]レーヴァテイン | [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]スポイル |
| [ 1 ]ソルプレーザ | [ 1 ]サモン:ヴァンパイア | [ 3 ]グラインドコア |
| [ 1 ]キュアブリーズ | [ 1 ]ナース |

PL / 空気頭の蛞蝓