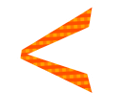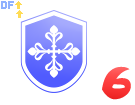<< 7:00~8:00




濡れたアスファルトの独特な臭いが鼻を突く。
生憎の夕立に見舞われて、愛車と一緒にびしょ濡れになってしまった。
通り雨の類だったから、既に晴れているものの、既に夕日が落ちかけている時間帯だ。
ライダーズジャケットも着ずに飛び出してきたせいで、吹き抜ける秋風を余計に冷たく感じる。
それでもただ無心に飛ばしていた。あの時の記憶を振り切るように、アクセルを回す。
────夜の帳を照らしていた事故現場の炎。未だこの鼻腔に、焼けるガソリンの臭いが残っている。
あの時の光景がずっとずっと、脳裏にこびりついて離れない。
あれから半月近くたった今でも、ずっと夢に出てくる。
こうしてバイクに跨って、風を感じていれば気も紛れた。
皮肉な事に、自分から大切なものを奪ったものは、そのトラウマを遠ざけるのに一番の相棒だった。
それに気づくとまた、胸の内が酷く焦げるような不快感に襲われた。
それすらも振り切ろうと、ひたすらにアクセルを回した。
安全運転など、今はクソ食らえだ。
とにかくスピードを出し続けた。
人通りのない山道だからまだ良かったものの、警察でもいたら即切符ものだ。
勿論そんな事を考える余裕も、今の自分には当然なかった。
ただ、脳裏にこびりついた悪夢を振り払いたい。
正直、振り払えれば何でもよかったんだと思う。
何処まで走らせたかも、覚えていない。それだけ目的地もなく飛ばし続けた。
人が通らないような山道で、ふと愛車にブレーキを掛けた。
自分でも何故気づけたかはわからない。
鬱蒼とした雑木林に囲まれた景色の中、誰かの視線を感じた。
フルフェイスヘルメットを取り、周囲を見渡した。
既に日は落ち、辺りは暗い。バイクのライトが非常に目立つ程に。
それほどまでに暗い空間なのに、"それ"はすぐに目つく程、強い存在感を放っていた。
紺色の和装姿の老人だ。ほっそりとした長身で、白髪となっても尚艶やかな髪は男性でありながら美しさを感じる。
枯れた老人だからか、存在感というか、覇気、生気。そう言った類を感じさせない。
如何にも寂しい雰囲気を醸し出していた。ただ、その目だけはまるで刃のように鋭かった。
しかし、そのような老人が何故、こんな人気のない場所にいるのだろうか。
不思議と不気味さは感じないし、幽霊の類ではなさそうだ。
「─────何故、其の様な哀しい目をしている?」
自分が何かを言う前に、しゃがれた声が問いかける。
「─────逃げたいのだな。過去から。」
腹の底を見透かされている。
その視線は、老人とは思えないような透き通った目だ。
逆上するほど気力もなかったが、その穏やかな声音に怒りも沸かない。
「浮世離れして久しいが、此処で出会ったのも何かの縁。」
「少しだけ、話をしよう。御前の気を紛らわすかは分からないが……」
「驟雨に汗水漬、濡れ鼠では風邪を引こう。付いてこい。」
老人は踵を返し、雑木林の暗がりへと消えていく。
初めてであったはずなのに、何故そこまでわかるのだろう。
分かりやすい表情でもしていたのか。疑問は尽きない。
だが、老人についていくことにした。
そう、何でも良かったんだ。
本当に気が紛れるかもわからないけど、この脳裏にこびり付いたトラウマを払えるなら、何だってよかったんだ。
バイクを置き去りにし、見向きもせずに自らも雑木林の暗がりへと消えていく────。
老人の背中を見失わないように、雨で抜かるんだ地面を踏み抜いてついていく。
整備されていないような、道とも言えないような道だ。歩きづらい。
それでも老人はすいすいと進んでいく。
非常に歩きなれているのか。体幹の通った姿勢は、老人ながら凛々しさを感じさせる。
「付いたぞ。」
老人の言葉に、足を止めた。
雑木林の奥、開けた場所にはあばら家が建っていた。
随分と古い建物だ。こんな場所に住んでいるのか。
浮世離れ、本当に言葉通りのようだ。
老人に続くように、中へと入っていく。
古い木材が敷き詰められた空間だ。
汚れや湿っぽさ、埃っぽさを感じないが何処か殺風景としている。
棚に箪笥、中央の囲炉裏に壁に立てかけられた刀以外に目立つものは見えない。
老人は座敷を上がり、囲炉裏の前に腰を下ろした。凛とした居住まいだ。
「来なさい。」
老人に言われるままに、対面へと腰を下ろした。
知り合いでもない手前、妙に落ち着かない。
そんな様子を老人は静かに見ていた。
「…………。」
静かな眼差しが見据えている。
「……酷い隈だ。寝れんのか?」
老人の言葉に、徐に自身の目元に触れた。
確かに寝ていない。寝れるわけない。
寝るだけでまた、あの光景を思い出してしまうから。
そんな事を考えると、また臭いが鼻腔に充満してきた。
吐き気ごと押し込めるように、口元を強く手で覆った。
なんて無様なんだろう。嫌気が差してくる。
そんな自分の姿を、老人は─────。
「──────……。」
憐れむわけもなく、ただ静かに、穏やかに自分を見ていた。
同情されたかは、表情からは読み取れない。
だけど、悪い気はしなかった。
老人は何も言わない。視線に居た堪れなくなったわけでもない。
けど、自然にぽつり、ぽつりと口から洩れた。
あの日の夜の事も。
自分が犯した過ちも。
盆水から何もかもが、零れていく。
「──────……。」
聞いてる間も、最後まで聞いても老人は何も言わなかった。
パチパチと音を立てて燃える囲炉裏の炎の音だけが、大きく響く。
ただ、憐れみも同情も口にしない。静かに老人は、立ち上がる。
「来し方行く末、暗れ惑うか。名も知らぬ若人。」
老人はあばら家の戸を開く。
「私は然のみ情深く御前を激励する事は出来ない。」
「然るに、御前の悪夢を振り払うに事足りるかは分からない。」
「さやかに言えるのは、私なりに御前に気を遣おうと思う。」
それもそうか。突然こんなことを聞かせれても、普通は戸惑う。
この人は不器用なんだ。不器用なりに優しくて、自分を気遣おうとしているんだ。
「深々とした夜更けではあるが、少しだけ体を動かそう。」
「何、すずろうよりは良いだろう。来なさい。」
だから、この人の言葉に従おう。
藁にもすがる思いなのは、間違いではないから。
それからだ。老人、紫陽花 剱菊(あじばな こんぎく)の下で稽古が始まったのは。
彼は自分の事を多くは語らなかった。
だが、とても強い人物だということを身を以て知った。
この島で喧嘩に明け暮れていた。
異能を使った戦いは、命のやり取りに相違ない部分が多いと思っている。
だから、腕っぷしには自信があった。
忌々しい異名ではあるが、人々に恐れる程には強かったはずだ。
だが、老人剱菊の前では手も足も出なかった。
その技術も、力も、人間性も、何もかも自分は及ばなかった。
彼との運動──率直に言えば手合わせだが、何度やっても一本取る事も出来なかった。
倒れ伏す自分を嘲ることなく、あの夜と同じ静かな目で見下ろしてくる。
────まだやれるはずだ。
そう言ってきているような気がした。
悔しいと言えば悔しいが、それ以上に自分の中で燃えるような何かが、憧れが芽吹き始めた。
しっかりと前を向いて、目の前の老人を見据えて何度も立ち向かった。
及ばずとも何度も、何度も立ち上がって、倒されては立ち上がる。
諦めの悪く、無様な姿だったかもしれない。
だが、老人剱菊は笑う事はなかった。
「其処迄。やはり御前は、技を盗むのが上手いな。」
稽古が終われば、褒めてくれた。
「怪我は無いか?」
不器用ながら、気遣いもしてくれた。
「……私の余命も後僅かだ。其れまでに、御前に全てを教える事はきっと叶わないだろう。」
そして、何処が寂しそうだった。
剱菊との稽古は数ヵ月続いた。
おかげで、あの悪夢に悩むことはなくなっていた。
後ろを振り返らずに、前を向くことの強さを教えられた。
優しさとは何か、という事を教わった。
それらは全て、言葉で伝えられたわけではない。
本当に短い数ヵ月の間に、心で、体で教えられた。
それでも尚、別れと言うものはやってくる。
剱菊と出会う前と同じ、雨の降る夕暮れ。
自分があばら家に訪れた時、老人は静かに息絶えていた。
言葉を発する事はなく、静かに囲炉裏に向かって、何も言わない。
まだ教わりたい事は幾らでもあった。
まだ彼と共に過ごしたかった。
剱菊自信が言ったように、それはもう叶わない。
だが、また失ったとは思わない。彼の教えてくれた強さが、自分の心には残っている。
それはきっと、中途半端なものなのかもしれない。
だけど、自分なりにやってみよう。
時には間違いを起こすかもしれない。
貴方の優しさも強さも、教わった全てを引き継いで前を向いて歩こう。
強く決心した表情を浮かべ、綺麗な目元を強引に腕で拭った。
「……また来るよ、爺さン。」
────夕立晒しの悲しみを、拾うものなどいない。



ENo.55 ゆい とのやりとり

ENo.81 葵 とのやりとり

ENo.117 ユーリウス とのやりとり

ENo.122 よつね とのやりとり

ENo.273 闇 とのやりとり

ENo.360 瑞稀 とのやりとり

ENo.380 "ofLOSE" とのやりとり

ENo.658 天弖 とのやりとり

ENo.668 パドメ とのやりとり

ENo.779 ハルトとリリス とのやりとり

ENo.950 仏の男 とのやりとり

ENo.1000 空 とのやりとり

ENo.1191 音々子 とのやりとり

ENo.1249 シオガマ とのやりとり

ENo.1257 アルマ とのやりとり

ENo.1278 レイジ とのやりとり

ENo.1288 裏葉 とのやりとり

ENo.1289 サク とのやりとり

ENo.1355 アキ とのやりとり

ENo.1364 絶えず流るる泡沫 とのやりとり

ENo.1553 ルミニア とのやりとり

以下の相手に送信しました




えびぴらふ(1506) に ItemNo.21 禁断じゃない果実 を手渡ししました。
ItemNo.15 サイコロステーキ を食べました!
体調が 1 回復!(16⇒17)
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 増幅10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










自然LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
武器LV を 7 UP!(LV55⇒62、-7CP)
えびぴらふ(1506) により ItemNo.17 翌檜 から防具『グリーンのパーカー』を作製してもらいました!
⇒ グリーンのパーカー/防具:強さ180/[効果1]回復25 [効果2]- [効果3]-
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『メリケンサック』を作製しました!
⇒ メリケンサック/武器:強さ72/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ツバキ(1559) により ItemNo.20 禁断じゃない果実 から料理『りんごとクリームチーズのケーキ』をつくってもらいました!
⇒ りんごとクリームチーズのケーキ/料理:強さ20/[効果1]攻撃5 [効果2]防御5 [効果3]器用5
絶えず流るる泡沫(1364) により ItemNo.14 蛇モチーフのシルバーピアス に ItemNo.10 毛 を付加してもらいました!
⇒ 蛇モチーフのシルバーピアス/装飾:強さ150/[効果1]守護20 [効果2]回復10 [効果3]-
チュイ(1519) とカードを交換しました!
ザ・ガーディアン (ノクターン)

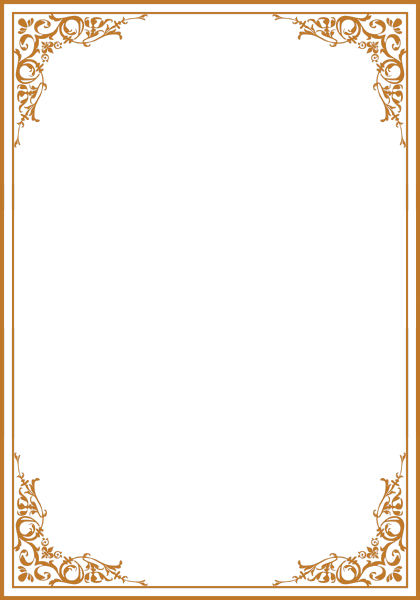
リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
リザレクション を研究しました!(深度1⇒2)
リザレクション を研究しました!(深度2⇒3)
グランドクラッシャー を習得!
珊瑚樹 を習得!
草根木皮 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



えびぴらふ(1506) は 燐灰石 を入手!
エリカ(1530) は 毒鉄鉱 を入手!
ルミニア(1553) は 燐灰石 を入手!
ツバキ(1559) は 猫目石 を入手!
えびぴらふ(1506) は 不思議な雫 を入手!
エリカ(1530) は 毛 を入手!
ルミニア(1553) は 牙 を入手!
えびぴらふ(1506) は 爪 を入手!



えびぴらふ(1506) に移動を委ねました。
カミセイ区 Q-1(山岳)に移動!(体調17⇒16)
カミセイ区 Q-2(山岳)に移動!(体調16⇒15)
カミセイ区 R-2(山岳)に移動!(体調15⇒14)
カミセイ区 S-2(山岳)に移動!(体調14⇒13)
カミセイ区 T-2(山岳)に移動!(体調13⇒12)





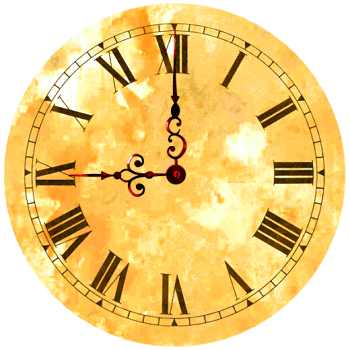
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
ザザッ――
ザザッ――
ザザッ――
チャットが閉じられる――










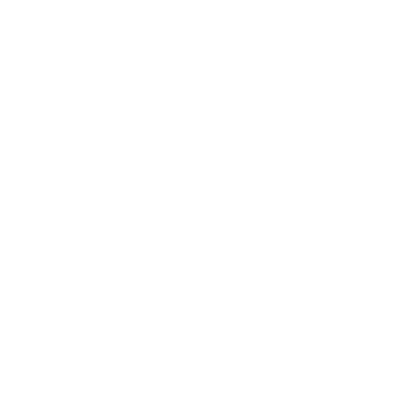
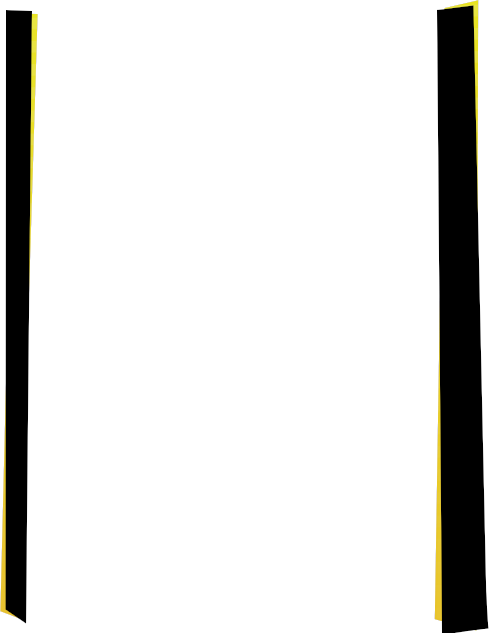
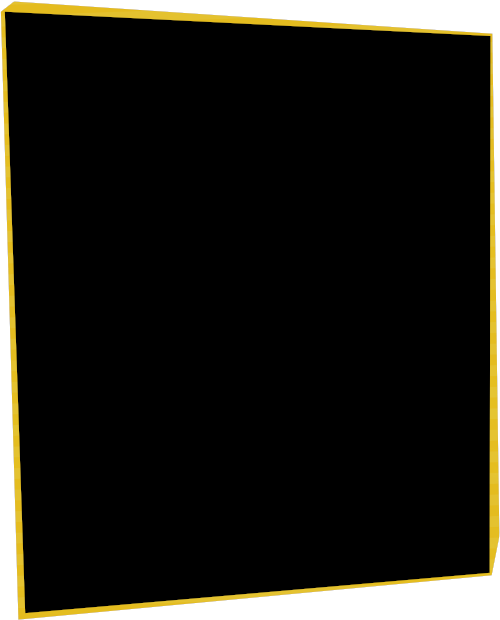





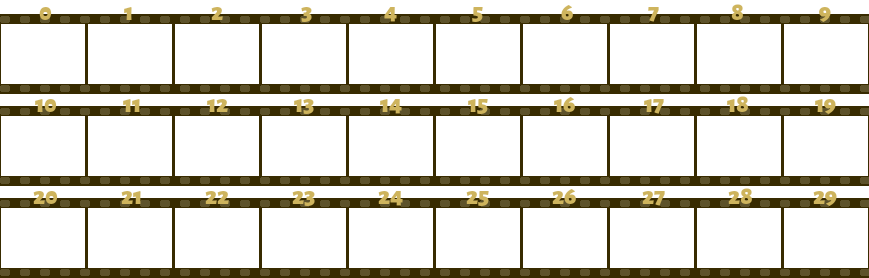









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



濡れたアスファルトの独特な臭いが鼻を突く。
生憎の夕立に見舞われて、愛車と一緒にびしょ濡れになってしまった。
通り雨の類だったから、既に晴れているものの、既に夕日が落ちかけている時間帯だ。
ライダーズジャケットも着ずに飛び出してきたせいで、吹き抜ける秋風を余計に冷たく感じる。
それでもただ無心に飛ばしていた。あの時の記憶を振り切るように、アクセルを回す。
────夜の帳を照らしていた事故現場の炎。未だこの鼻腔に、焼けるガソリンの臭いが残っている。
あの時の光景がずっとずっと、脳裏にこびりついて離れない。
あれから半月近くたった今でも、ずっと夢に出てくる。
こうしてバイクに跨って、風を感じていれば気も紛れた。
皮肉な事に、自分から大切なものを奪ったものは、そのトラウマを遠ざけるのに一番の相棒だった。
それに気づくとまた、胸の内が酷く焦げるような不快感に襲われた。
それすらも振り切ろうと、ひたすらにアクセルを回した。
安全運転など、今はクソ食らえだ。
とにかくスピードを出し続けた。
人通りのない山道だからまだ良かったものの、警察でもいたら即切符ものだ。
勿論そんな事を考える余裕も、今の自分には当然なかった。
ただ、脳裏にこびりついた悪夢を振り払いたい。
正直、振り払えれば何でもよかったんだと思う。
何処まで走らせたかも、覚えていない。それだけ目的地もなく飛ばし続けた。
人が通らないような山道で、ふと愛車にブレーキを掛けた。
自分でも何故気づけたかはわからない。
鬱蒼とした雑木林に囲まれた景色の中、誰かの視線を感じた。
フルフェイスヘルメットを取り、周囲を見渡した。
既に日は落ち、辺りは暗い。バイクのライトが非常に目立つ程に。
それほどまでに暗い空間なのに、"それ"はすぐに目つく程、強い存在感を放っていた。
紺色の和装姿の老人だ。ほっそりとした長身で、白髪となっても尚艶やかな髪は男性でありながら美しさを感じる。
枯れた老人だからか、存在感というか、覇気、生気。そう言った類を感じさせない。
如何にも寂しい雰囲気を醸し出していた。ただ、その目だけはまるで刃のように鋭かった。
しかし、そのような老人が何故、こんな人気のない場所にいるのだろうか。
不思議と不気味さは感じないし、幽霊の類ではなさそうだ。
「─────何故、其の様な哀しい目をしている?」
自分が何かを言う前に、しゃがれた声が問いかける。
「─────逃げたいのだな。過去から。」
腹の底を見透かされている。
その視線は、老人とは思えないような透き通った目だ。
逆上するほど気力もなかったが、その穏やかな声音に怒りも沸かない。
「浮世離れして久しいが、此処で出会ったのも何かの縁。」
「少しだけ、話をしよう。御前の気を紛らわすかは分からないが……」
「驟雨に汗水漬、濡れ鼠では風邪を引こう。付いてこい。」
老人は踵を返し、雑木林の暗がりへと消えていく。
初めてであったはずなのに、何故そこまでわかるのだろう。
分かりやすい表情でもしていたのか。疑問は尽きない。
だが、老人についていくことにした。
そう、何でも良かったんだ。
本当に気が紛れるかもわからないけど、この脳裏にこびり付いたトラウマを払えるなら、何だってよかったんだ。
バイクを置き去りにし、見向きもせずに自らも雑木林の暗がりへと消えていく────。
老人の背中を見失わないように、雨で抜かるんだ地面を踏み抜いてついていく。
整備されていないような、道とも言えないような道だ。歩きづらい。
それでも老人はすいすいと進んでいく。
非常に歩きなれているのか。体幹の通った姿勢は、老人ながら凛々しさを感じさせる。
「付いたぞ。」
老人の言葉に、足を止めた。
雑木林の奥、開けた場所にはあばら家が建っていた。
随分と古い建物だ。こんな場所に住んでいるのか。
浮世離れ、本当に言葉通りのようだ。
老人に続くように、中へと入っていく。
古い木材が敷き詰められた空間だ。
汚れや湿っぽさ、埃っぽさを感じないが何処か殺風景としている。
棚に箪笥、中央の囲炉裏に壁に立てかけられた刀以外に目立つものは見えない。
老人は座敷を上がり、囲炉裏の前に腰を下ろした。凛とした居住まいだ。
「来なさい。」
老人に言われるままに、対面へと腰を下ろした。
知り合いでもない手前、妙に落ち着かない。
そんな様子を老人は静かに見ていた。
「…………。」
静かな眼差しが見据えている。
「……酷い隈だ。寝れんのか?」
老人の言葉に、徐に自身の目元に触れた。
確かに寝ていない。寝れるわけない。
寝るだけでまた、あの光景を思い出してしまうから。
そんな事を考えると、また臭いが鼻腔に充満してきた。
吐き気ごと押し込めるように、口元を強く手で覆った。
なんて無様なんだろう。嫌気が差してくる。
そんな自分の姿を、老人は─────。
「──────……。」
憐れむわけもなく、ただ静かに、穏やかに自分を見ていた。
同情されたかは、表情からは読み取れない。
だけど、悪い気はしなかった。
老人は何も言わない。視線に居た堪れなくなったわけでもない。
けど、自然にぽつり、ぽつりと口から洩れた。
あの日の夜の事も。
自分が犯した過ちも。
盆水から何もかもが、零れていく。
「──────……。」
聞いてる間も、最後まで聞いても老人は何も言わなかった。
パチパチと音を立てて燃える囲炉裏の炎の音だけが、大きく響く。
ただ、憐れみも同情も口にしない。静かに老人は、立ち上がる。
「来し方行く末、暗れ惑うか。名も知らぬ若人。」
老人はあばら家の戸を開く。
「私は然のみ情深く御前を激励する事は出来ない。」
「然るに、御前の悪夢を振り払うに事足りるかは分からない。」
「さやかに言えるのは、私なりに御前に気を遣おうと思う。」
それもそうか。突然こんなことを聞かせれても、普通は戸惑う。
この人は不器用なんだ。不器用なりに優しくて、自分を気遣おうとしているんだ。
「深々とした夜更けではあるが、少しだけ体を動かそう。」
「何、すずろうよりは良いだろう。来なさい。」
だから、この人の言葉に従おう。
藁にもすがる思いなのは、間違いではないから。
それからだ。老人、紫陽花 剱菊(あじばな こんぎく)の下で稽古が始まったのは。
彼は自分の事を多くは語らなかった。
だが、とても強い人物だということを身を以て知った。
この島で喧嘩に明け暮れていた。
異能を使った戦いは、命のやり取りに相違ない部分が多いと思っている。
だから、腕っぷしには自信があった。
忌々しい異名ではあるが、人々に恐れる程には強かったはずだ。
だが、老人剱菊の前では手も足も出なかった。
その技術も、力も、人間性も、何もかも自分は及ばなかった。
彼との運動──率直に言えば手合わせだが、何度やっても一本取る事も出来なかった。
倒れ伏す自分を嘲ることなく、あの夜と同じ静かな目で見下ろしてくる。
────まだやれるはずだ。
そう言ってきているような気がした。
悔しいと言えば悔しいが、それ以上に自分の中で燃えるような何かが、憧れが芽吹き始めた。
しっかりと前を向いて、目の前の老人を見据えて何度も立ち向かった。
及ばずとも何度も、何度も立ち上がって、倒されては立ち上がる。
諦めの悪く、無様な姿だったかもしれない。
だが、老人剱菊は笑う事はなかった。
「其処迄。やはり御前は、技を盗むのが上手いな。」
稽古が終われば、褒めてくれた。
「怪我は無いか?」
不器用ながら、気遣いもしてくれた。
「……私の余命も後僅かだ。其れまでに、御前に全てを教える事はきっと叶わないだろう。」
そして、何処が寂しそうだった。
剱菊との稽古は数ヵ月続いた。
おかげで、あの悪夢に悩むことはなくなっていた。
後ろを振り返らずに、前を向くことの強さを教えられた。
優しさとは何か、という事を教わった。
それらは全て、言葉で伝えられたわけではない。
本当に短い数ヵ月の間に、心で、体で教えられた。
それでも尚、別れと言うものはやってくる。
剱菊と出会う前と同じ、雨の降る夕暮れ。
自分があばら家に訪れた時、老人は静かに息絶えていた。
言葉を発する事はなく、静かに囲炉裏に向かって、何も言わない。
まだ教わりたい事は幾らでもあった。
まだ彼と共に過ごしたかった。
剱菊自信が言ったように、それはもう叶わない。
だが、また失ったとは思わない。彼の教えてくれた強さが、自分の心には残っている。
それはきっと、中途半端なものなのかもしれない。
だけど、自分なりにやってみよう。
時には間違いを起こすかもしれない。
貴方の優しさも強さも、教わった全てを引き継いで前を向いて歩こう。
強く決心した表情を浮かべ、綺麗な目元を強引に腕で拭った。
「……また来るよ、爺さン。」
────夕立晒しの悲しみを、拾うものなどいない。



ENo.55 ゆい とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.81 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.117 ユーリウス とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.122 よつね とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||
ENo.273 闇 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.360 瑞稀 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.380 "ofLOSE" とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.658 天弖 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.668 パドメ とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.779 ハルトとリリス とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.950 仏の男 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1000 空 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1191 音々子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1249 シオガマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1257 アルマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1278 レイジ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.1288 裏葉 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1289 サク とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1355 アキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1364 絶えず流るる泡沫 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1553 ルミニア とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
キリエ 「……吾輩、登山するなら恐山がいいですぞぉ~ (そんな事言いながら着ぐるみキリエは山を登る)」 |
 |
エリカ 「いや、恐山ッて……。や、でも……ハァー……ッ。山、しンど……!爺さンのようにはいかねェなァ……。」 |
 |
エリカ 「……え?まだ続くの?オイオイオイ……勘弁してくれ……!」 |
 |
ツバキ 「ハザマだからいいものの、本当の登山なら怒られそうな服装ですよね。」 |
 |
ツバキ 「ところでお話してる最中なんですがナレハテ…えっ足長…」 |
えびぴらふ(1506) に ItemNo.21 禁断じゃない果実 を手渡ししました。
ItemNo.15 サイコロステーキ を食べました!
 |
矢車エリカ 「ンー、やッぱ肉ッて男の子の味だよなァ!」 |
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 増幅10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!



Strayeders
|
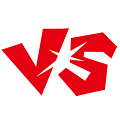 |
ハザマに生きるもの
|



なかよし動物園❤
|
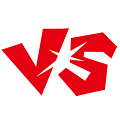 |
Strayeders
|



自然LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
武器LV を 7 UP!(LV55⇒62、-7CP)
えびぴらふ(1506) により ItemNo.17 翌檜 から防具『グリーンのパーカー』を作製してもらいました!
⇒ グリーンのパーカー/防具:強さ180/[効果1]回復25 [効果2]- [効果3]-
 |
えびぴらふ 「……一応なんか解れてたんで補修しときましたよ?……あとで料金請求しますのでよろです」 |
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『メリケンサック』を作製しました!
⇒ メリケンサック/武器:強さ72/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
矢車エリカ 「こンなモンかな……。」 |
ツバキ(1559) により ItemNo.20 禁断じゃない果実 から料理『りんごとクリームチーズのケーキ』をつくってもらいました!
⇒ りんごとクリームチーズのケーキ/料理:強さ20/[効果1]攻撃5 [効果2]防御5 [効果3]器用5
 |
…はい。どうぞ。毒は入ってませんよ |
絶えず流るる泡沫(1364) により ItemNo.14 蛇モチーフのシルバーピアス に ItemNo.10 毛 を付加してもらいました!
⇒ 蛇モチーフのシルバーピアス/装飾:強さ150/[効果1]守護20 [効果2]回復10 [効果3]-
 |
灰闇 眩 「お、会えた。元気?これ差し入れです。…つって、弄るだけだけど。ま、お互い頑張ろうぜ。」 |
チュイ(1519) とカードを交換しました!
ザ・ガーディアン (ノクターン)

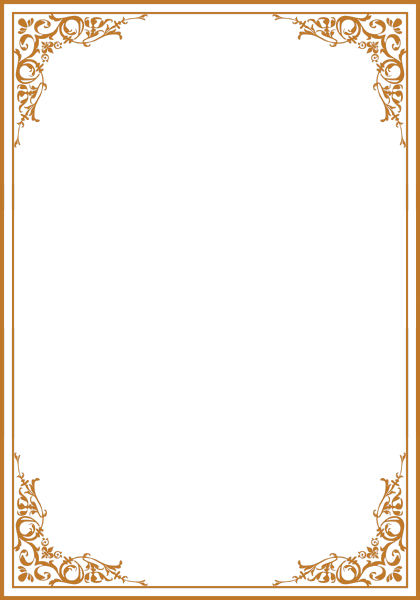
リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
リザレクション を研究しました!(深度1⇒2)
リザレクション を研究しました!(深度2⇒3)
グランドクラッシャー を習得!
珊瑚樹 を習得!
草根木皮 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



えびぴらふ(1506) は 燐灰石 を入手!
エリカ(1530) は 毒鉄鉱 を入手!
ルミニア(1553) は 燐灰石 を入手!
ツバキ(1559) は 猫目石 を入手!
えびぴらふ(1506) は 不思議な雫 を入手!
エリカ(1530) は 毛 を入手!
ルミニア(1553) は 牙 を入手!
えびぴらふ(1506) は 爪 を入手!



えびぴらふ(1506) に移動を委ねました。
カミセイ区 Q-1(山岳)に移動!(体調17⇒16)
カミセイ区 Q-2(山岳)に移動!(体調16⇒15)
カミセイ区 R-2(山岳)に移動!(体調15⇒14)
カミセイ区 S-2(山岳)に移動!(体調14⇒13)
カミセイ区 T-2(山岳)に移動!(体調13⇒12)





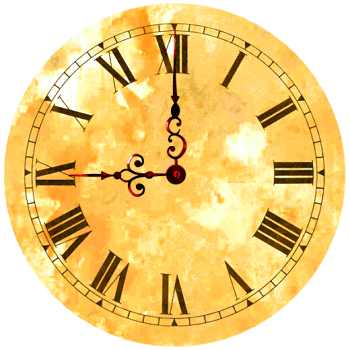
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・怖いだろうがよ。」 |
 |
エディアン 「・・・勘弁してくれませんか。」 |
 |
白南海 「ナレハテってあの!アレだろォッ!!?ドッロドロしてんじゃねーっすか!! なんすかあれキッモいのッ!!うげぇぇぇぇうげえええぇぇぇ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「私だって嫌ですよあんなの・・・・・ ・・・え、案内役って影響力どういう扱いに・・・??私達は関係ないですよね・・・????」 |
 |
白南海 「あんたアンジニティならそーゆーの平気じゃねーんすか? 何かアンジニティってそういう、変な、キモいの多いんじゃ?」 |
 |
エディアン 「こんな麗しき乙女を前に、ド偏見を撒き散らさないでくれます? 貴方こそ、アレな業界の人間なら似たようなの見慣れてるでしょうに。」 |
 |
白南海 「あいにくウチはキレイなお仕事しかしてないもんで。えぇ、本当にキレイなもんで。」 |
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
 |
白南海 「・・・っつーか、あれ本当にドライバーのオヤジっすか?何か雰囲気違くねぇ・・・??」 |
 |
エディアン 「まぁ別の何か、でしょうね。 雰囲気も言ってることも別人みたいでしたし。普通に、スワップ発動者さん?・・・うーん。」 |
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
 |
エディアン 「・・・・・?なんでしょう、何か変な雑音が。」 |
ザザッ――
 |
白南海 「ただの故障じゃねーっすか。」 |
ザザッ――
 |
声 「――・・・レーション、ヒノデコーポレーション。 襲撃に・・・・・・・・いる・・・ 大量・・・・・こ・・・・・・死体・・・・・・ゾ・・・・・・」 |
 |
声 「・・・・・ゾンビだッ!!!!助け――」 |
ザザッ――
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「ホラーはぁぁ――ッ!!!! やぁぁめろォォ―――ッ!!!!」 |
 |
エディアン 「勘弁してください勘弁してくださいマジ勘弁してください。 ホラーはプレイしないんですコメ付き実況でしか見れないんですやめてください。」 |
チャットが閉じられる――







Strayeders
|
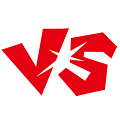 |
なかよし動物園❤
|


ENo.1530
矢車エリカ
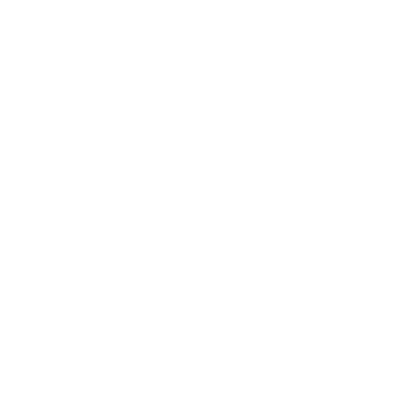
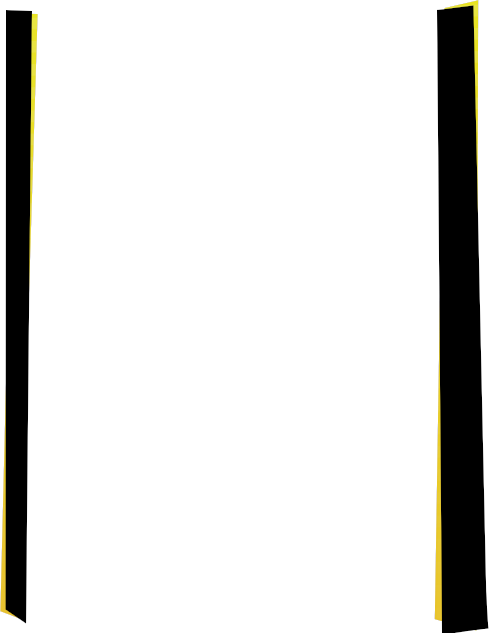
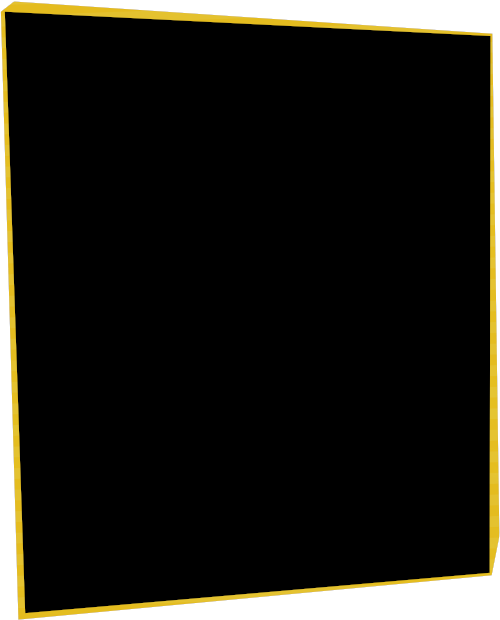
【プロフィール】
やぐるまエリカ。身長193cm 22歳 男性。誕生日11/30
イバラシティの個人バイクショップ「矢車バイカー」の店主。
相良伊橋高校卒業生で、在学中は"ソラコーの蛇"と呼ばれていた凶悪な不良だった。
卒業後、片思いをしていたバイカー仲間が両親に事故を起こし両者ともに死亡。
心に大きな傷を残し、自らの行いを悔いた彼は両親の店を継ぎ、真っ当に生きる事を決意。
社会の爪弾きものを自覚しながらも、"スジ"を通し、愚直とまで言える真っ直ぐなヤンキーになった。
尚、両親から店は継いだものの、大きな負い目を感じているらしく
旅好きな性格も相まって様々な事に手広く手を出しているようだ。
趣味はツーリング。愛車はCBR450SR。一応大型バイク免許も取得済み。
瀬能 楽子(ENo.1295)とは幼馴染であり親友の間柄。
現在は矢車バイカー店主、ブランブル女学院の守衛、天弖探偵事務所の手伝いを行っている。
【過去】
通称"ソラコーの蛇"と呼ばれていた不良学生。
きっかけは、顔も名前も知らない生徒が不良に絡まれていた所を助けた事が始まり。
彼は『自分が同じ社会の爪弾きものをシメれば学校やダチが助かる』と考え
それからは同じ不良所か極道や犯罪者など、同じ日陰者達に喧嘩三昧。
時に流行りすぎて"停学処分"を受ける程だったが、それでも彼は自分の正義を疑わなかった。
なんとか卒業こそ出来たものの、自身が思いを寄せていたバイク仲間が
両親相手に人身事故を起こして死亡。両親も病院搬送前に死亡してしまう。
連絡を受けて現場に駆け付けた彼は、その凄惨な光景を見て自らの行いを後悔する。
暴走した正義による天罰。そう捉えた彼は、大きなトラウマを抱えながら
死んでしまった両親と仲間に恥じないように生きる事を決意した。
尚、卒業から数年たっている今、当時の事は眉唾ものとなっており
彼が本当にそう呼ばれていたかも、そんな生徒だったかも真偽は不明。当時の歴史のみが語る。
少なくとも、彼の行いは大きく事を動かさなかったことを見れば、結果的に過ちだったのだろう。
(それが後悔に大きく拍車をかけている。)
【異能】
『再気-ウロボロス-』
再生力の異能。自己再生、身体強化等の肉体を強化する異能。
ハザマにおいては、エリカとは真逆の狡猾な人格をした蛇が出現する。
蛇とはまったくもってソリが合わないが、コンビネーションは抜群。
・再生と崩壊
再生能力。
如何なる傷を受けても再生する不死の力。
但し、再生の前には傷口が広がる、ダメージが大きくなる制約があり、大きく体力を持っていかれる為
意識を保ったまま再生し続けるのは限度がある。(意識を手放しても再生はするが、当然戦闘行動等は出来ない。)
また、病気などは回復できるが、毒物の解毒は不可能なため、延々と苦しむ羽目になる。
再生能力は他者に使用する事も可能だが、その場合傷口の崩壊は起きないが、治せる範囲に限度がある。
・身体強化
文字通り身体能力を強化する能力。
発動すると全身にオーラを纏う為、視覚的にわかりやすい能力になっている。
オーラの色によって様々な効果を発揮し、それぞれ長所短所が存在する。
最近はオーラのコントロールが上手くなったようで、二つまで能力を合わせる手段を身に着けた。
(但し持続力はなく、すぐ片方の能力は消える。)
緑:基本形態。全体的な能力が向上するバランスタイプ。
赤:スピード特化。空中機動すら可能だが、一切パワーは上がらない。
赤紫:スピード&柔軟性。体中の関節が非常に柔らかくなるが、赤ほど速くならず一切パワーは上がらない。
灰色:パワー特化。破壊力に特化した形態。見た目こそ変わらないが、筋肉が非常に重くなるため全体的な機動力が犠牲になる。
黄色:適正強化。装備した獲物の扱いが全て"達人級"に変わる武器強化。身体能力はさほど強化されない。
白:天弖探偵事務所所長の動きの模倣。圧倒的戦闘力を誇るが、体がついていかず強い反動がある。
黒:"ソラコーの蛇"として活動していた時の色。詳細は不明。本人が語りたがらない。
青:詳細不明。
・矢車流喧嘩殺法
異能ではないが此処に記載。
我流の喧嘩殺法。喧嘩に勝つ為に"使えそう"と思ったものを片っ端から取り入れ
それを戦闘スタイルに組み込んだ戦法。オーラに合わせた戦闘スタイルを分けており
見た目とは裏腹に技巧よりの喧嘩を得意としている。
また、相手の技を模倣をするのが得意であり、相手の事を観察する事にもたけている。
・紫陽花流武術
異能ではないが此処に記載。
とあるツーリング先で、さびれた田舎村にひっそりと住んでいた『紫陽花 剱菊(あじばな こんぎく)』と名乗る老人から一部伝授された武術。
合気道と日本刀を組み合わせた変則的な武術であり、喧嘩殺法を自ら捨てたエリカはその技の一部を伝授される。
今は戦いとなると主にこの技を主流に戦っていくが、何かと型にはまった動きをエリカ自身が苦手とし
全てを伝授される前に、剱菊が老衰で亡くなったため、残りの部分を補うために
上記の喧嘩殺法の荒々しい戦い方を組み込んで戦う。
----------------------------------------------
サブ置き場↓
https://www.evernote.com/shard/s357/sh/b1128a48-9ecf-dd68-6828-8bac70b03e32/f88c43810d08cbf8cd480508234e3f2b
基本的にかなりマイペースにやっていきます。大体置きレスです。一日34時間欲しい。
この手のゲームはあまりやったことないので
至らない部分も多々あるかもしれませんがよろしくお願い致します!基本的に関係性もろもろは色々フリーです。宜しくお願いします。
アイコン、イラストは星野 薫様に描いていただきました
やぐるまエリカ。身長193cm 22歳 男性。誕生日11/30
イバラシティの個人バイクショップ「矢車バイカー」の店主。
相良伊橋高校卒業生で、在学中は"ソラコーの蛇"と呼ばれていた凶悪な不良だった。
卒業後、片思いをしていたバイカー仲間が両親に事故を起こし両者ともに死亡。
心に大きな傷を残し、自らの行いを悔いた彼は両親の店を継ぎ、真っ当に生きる事を決意。
社会の爪弾きものを自覚しながらも、"スジ"を通し、愚直とまで言える真っ直ぐなヤンキーになった。
尚、両親から店は継いだものの、大きな負い目を感じているらしく
旅好きな性格も相まって様々な事に手広く手を出しているようだ。
趣味はツーリング。愛車はCBR450SR。一応大型バイク免許も取得済み。
瀬能 楽子(ENo.1295)とは幼馴染であり親友の間柄。
現在は矢車バイカー店主、ブランブル女学院の守衛、天弖探偵事務所の手伝いを行っている。
【過去】
通称"ソラコーの蛇"と呼ばれていた不良学生。
きっかけは、顔も名前も知らない生徒が不良に絡まれていた所を助けた事が始まり。
彼は『自分が同じ社会の爪弾きものをシメれば学校やダチが助かる』と考え
それからは同じ不良所か極道や犯罪者など、同じ日陰者達に喧嘩三昧。
時に流行りすぎて"停学処分"を受ける程だったが、それでも彼は自分の正義を疑わなかった。
なんとか卒業こそ出来たものの、自身が思いを寄せていたバイク仲間が
両親相手に人身事故を起こして死亡。両親も病院搬送前に死亡してしまう。
連絡を受けて現場に駆け付けた彼は、その凄惨な光景を見て自らの行いを後悔する。
暴走した正義による天罰。そう捉えた彼は、大きなトラウマを抱えながら
死んでしまった両親と仲間に恥じないように生きる事を決意した。
尚、卒業から数年たっている今、当時の事は眉唾ものとなっており
彼が本当にそう呼ばれていたかも、そんな生徒だったかも真偽は不明。当時の歴史のみが語る。
少なくとも、彼の行いは大きく事を動かさなかったことを見れば、結果的に過ちだったのだろう。
(それが後悔に大きく拍車をかけている。)
【異能】
『再気-ウロボロス-』
再生力の異能。自己再生、身体強化等の肉体を強化する異能。
ハザマにおいては、エリカとは真逆の狡猾な人格をした蛇が出現する。
蛇とはまったくもってソリが合わないが、コンビネーションは抜群。
・再生と崩壊
再生能力。
如何なる傷を受けても再生する不死の力。
但し、再生の前には傷口が広がる、ダメージが大きくなる制約があり、大きく体力を持っていかれる為
意識を保ったまま再生し続けるのは限度がある。(意識を手放しても再生はするが、当然戦闘行動等は出来ない。)
また、病気などは回復できるが、毒物の解毒は不可能なため、延々と苦しむ羽目になる。
再生能力は他者に使用する事も可能だが、その場合傷口の崩壊は起きないが、治せる範囲に限度がある。
・身体強化
文字通り身体能力を強化する能力。
発動すると全身にオーラを纏う為、視覚的にわかりやすい能力になっている。
オーラの色によって様々な効果を発揮し、それぞれ長所短所が存在する。
最近はオーラのコントロールが上手くなったようで、二つまで能力を合わせる手段を身に着けた。
(但し持続力はなく、すぐ片方の能力は消える。)
緑:基本形態。全体的な能力が向上するバランスタイプ。
赤:スピード特化。空中機動すら可能だが、一切パワーは上がらない。
赤紫:スピード&柔軟性。体中の関節が非常に柔らかくなるが、赤ほど速くならず一切パワーは上がらない。
灰色:パワー特化。破壊力に特化した形態。見た目こそ変わらないが、筋肉が非常に重くなるため全体的な機動力が犠牲になる。
黄色:適正強化。装備した獲物の扱いが全て"達人級"に変わる武器強化。身体能力はさほど強化されない。
白:天弖探偵事務所所長の動きの模倣。圧倒的戦闘力を誇るが、体がついていかず強い反動がある。
黒:"ソラコーの蛇"として活動していた時の色。詳細は不明。本人が語りたがらない。
青:詳細不明。
・矢車流喧嘩殺法
異能ではないが此処に記載。
我流の喧嘩殺法。喧嘩に勝つ為に"使えそう"と思ったものを片っ端から取り入れ
それを戦闘スタイルに組み込んだ戦法。オーラに合わせた戦闘スタイルを分けており
見た目とは裏腹に技巧よりの喧嘩を得意としている。
また、相手の技を模倣をするのが得意であり、相手の事を観察する事にもたけている。
・紫陽花流武術
異能ではないが此処に記載。
とあるツーリング先で、さびれた田舎村にひっそりと住んでいた『紫陽花 剱菊(あじばな こんぎく)』と名乗る老人から一部伝授された武術。
合気道と日本刀を組み合わせた変則的な武術であり、喧嘩殺法を自ら捨てたエリカはその技の一部を伝授される。
今は戦いとなると主にこの技を主流に戦っていくが、何かと型にはまった動きをエリカ自身が苦手とし
全てを伝授される前に、剱菊が老衰で亡くなったため、残りの部分を補うために
上記の喧嘩殺法の荒々しい戦い方を組み込んで戦う。
----------------------------------------------
サブ置き場↓
https://www.evernote.com/shard/s357/sh/b1128a48-9ecf-dd68-6828-8bac70b03e32/f88c43810d08cbf8cd480508234e3f2b
基本的にかなりマイペースにやっていきます。大体置きレスです。一日34時間欲しい。
この手のゲームはあまりやったことないので
至らない部分も多々あるかもしれませんがよろしくお願い致します!基本的に関係性もろもろは色々フリーです。宜しくお願いします。
アイコン、イラストは星野 薫様に描いていただきました
12 / 30
683 PS
カミセイ区
T-2
T-2




























【うちの子】貸し借りOKコミュ
2
相良伊橋高校
2
死なない。
対岸の情緒火事を眺める者の会
1
#交流歓迎
1
両陣営の和平を真面目に考える会
10
ログまとめられフリーの会
長文大好きクラブ
侵略対策・戦術勉強会
6



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | メリケンサック | 武器 | 72 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 漢のサラシ | 防具 | 15 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 7 | パリピなサングラス | 防具 | 90 | 反護15 | - | - | |
| 8 | 緑の恐竜着ぐるみ | 防具 | 55 | 体力10 | - | - | |
| 9 | バンテージ | 武器 | 65 | 水纏10 | - | - | 【射程1】 |
| 10 | 毒鉄鉱 | 素材 | 25 | [武器]疫病15(LV25)[防具]反腐20(LV30)[装飾]壊裂15(LV30) | |||
| 11 | ラベンダー | 素材 | 15 | [武器]魅了15(LV25)[防具]気合10(LV25)[装飾]魔力15(LV30) | |||
| 12 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 13 | シルバーチェーン | 装飾 | 70 | 守護15 | - | - | |
| 14 | 蛇モチーフのシルバーピアス | 装飾 | 150 | 守護20 | 回復10 | - | |
| 15 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 16 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 17 | グリーンのパーカー | 防具 | 180 | 回復25 | - | - | |
| 18 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 19 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 20 | りんごとクリームチーズのケーキ | 料理 | 20 | 攻撃5 | 防御5 | 器用5 | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 20 | 植物/鉱物/地 |
| 百薬 | 20 | 化学/病毒/医術 |
| 武器 | 62 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ヘッドクラッシュ (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| バッククラッシュ (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| チンピラの極み (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブン投げ (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 初鱗・回気 (ヒール) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| フォースイーター (ドレイン) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ハートブレイクショット (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 追い打ちの極み (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決3 | 重撃の極み (ストライク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 決3 | 巨岩潰し (ストーンブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 |
| 牙穿衝 (ライトニング) | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| タライの極み (クリエイト:タライ) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| 決3 | エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) |
| 決3 | 壱鱗・回気 (ヒールポーション) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| 紫陽花流『無手返し』 (リフレクション) | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 紫陽花流『葵摘み』 (コンテイン) | 6 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| 決2 | アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |
| 地鱗・回気 (ヒールハーブ) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| 決2 | 好転滅気 (クリエイト:グレイル) | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
| 決2 | 光鱗・回気 (ホーリーポーション) | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| トランス | 5 | 0 | 100 | 自:混乱+自:AT・HL増+魅了を祝福化 | |
| 決2 | 弐鱗・回気 (クイックレメディ) | 7 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 |
| 旋回放華の極み (チャージ) | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 決3 | 水鱗・回気 (アクアヒール) | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 決2 | ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 |
| 決2 | 参鱗・回気 (ファーマシー) | 7 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| 甲羅砕き (ガーディアン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| 紫陽花流『椿祈』 (カウンター) | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| レジスト | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+肉体精神変調防御 | |
| 喧嘩神の心得 (エネルジコ) | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・MSP増 | |
| 毒蛇の吐息 (ウィルスゾーン) | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| 大蛇落とし (ツインブラスト) | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 決2 | 正邪毒滅 (パワフルヒール) | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| 平穏の霧 (ヒールミスト) | 5 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) | |
| 地砕きの極み (フラワーバラッド) | 5 | 0 | 150 | 敵列2:地撃&魅了+味傷3:HP増 | |
| 地天鱗・回気 (ハーバルメディスン) | 5 | 0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) | |
| 毒気 (パーガティブ) | 5 | 0 | 200 | 敵全:攻撃&食事による付加効果のLV減 | |
| 鱗界・天気 (ディスインフェクト) | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 氷柱の極み (アイシクルランス) | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| 決2 | グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
| 決2 | 終鱗・回気 (インフェクシャスキュア) | 6 | 0 | 140 | 味列:HP増 |
| スネークスイック (インヴァージョン) | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 生命転機 (クライオセラピー) | 5 | 0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 | |
| 決2 | 廻天-ウロボロス- (ポーションラッシュ) | 6 | 0 | 240 | 味傷6:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛虎の気位 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 玄武の気位 (堅守) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 朱雀の気位 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 青龍の気位 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 静気の構え (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 黄龍の気位 (太陽) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 麒麟の気位 (隠者) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 不死身の肉体 (肉体変調耐性) | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |
| 水龍の構え (水の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地龍の構え (地の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 気合上等 (薬師) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 珊瑚樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・領域値[水][地]増+守護+連続減 | |
| 草根木皮 | 5 | 5 | 0 | 【HP回復後】対:領域値[地]2以上なら、HP増 | |
| なンかわからンけど大砲作れる (大砲作製) | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
びりびりけだま (カレイドスコープ) |
0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
| 決2 |
狐の霊薬(缶) (リザレクション) |
0 | 150 | 味傷:HP増+瀕死ならHP増 |
|
残像 (ヴィジランス) |
0 | 30 | 自:AG増(2T)+次受ダメ減 | |
|
悪夢:終わらない暴風 (ツインブラスト) |
0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 決2 |
癒符 (インフェクシャスキュア) |
0 | 140 | 味列:HP増 |
|
とぎすませ (キーンフォーム) |
0 | 150 | 自:DX・貫撃LV増 | |
|
ザ・ガーディアン (ノクターン) |
0 | 180 | 敵5:魅了 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]デアデビル | [ 3 ]サモン:サーヴァント | [ 3 ]リザレクション |
| [ 1 ]チャージ | [ 3 ]ヒールポーション | [ 1 ]ファーマシー |
| [ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 3 ]アクアブランド | [ 3 ]チャクラグラント |

PL / エトワール川島