<< 5:00~6:00




夜花は"特別"だった。
当代の幻月は…正真正銘、本物の巫。
かつての白月にもそれが存在したのかどうか断言はできない。
存在したという記録が無かったから。
それらが残っていれば、あるいはすべてを解明できたのかもしれない。
「亡骸の海が見えました。」
「抽象的…ね。何かわかった?」
「いいえ……はっきりとは。」
─── 夜花の力を借りても待宵の伝承の全ては解明できなかった。
許しをもらって直接待宵窟の調査もしてみた。
さすがに底の見えない深淵までは調べられなかったけど──。
中にある社の周辺には何かが居たような痕跡も見つかった。
ただ人のものとするにはやはり少々噛み合わない。
数多ある他の伝承と同じく──諸説あり、と結ぶしかなさそうなのは残念。
こういった本物の怪異に纏わる民間信仰や伝承を読み解くのが、本来の仕事なのにね。
ただ、わかったこともあった。
人は夜と月の神の怒りに触れた。
待宵窟を穢したからなのだろう。
遺体を投げ込んだとする伝承…これは、史実だ。
─── 夜花が視たのだから。
流行り病のせいで遺体を投げ込むようになったのか。
遺体を投げ込むようになった後発生した病を呪いとしたのか。
本当に死者が甦ったのか…あるいは何かをそう表現しただけなのか。
真実は、未だ深淵の闇の中だ。
だから、アタシは生きた伝承を観察することにした───
夜花たちは人とほぼ変わらない姿をしているけれど、いくつか大きく違うところがある。
まず驚いたのは、老いがわかりにくいこと。
違う種族の年齢を外見で判断しづらいことと同じ理屈なのかしらん、と最初は思った。
そして、白月はみな夭折であったこと。
それは人と比較して…ではなく、彼らの天寿と比べて。
本来、神に近い彼らは人と比べれば大幅に長寿だということは辛うじて判明した。
だが、それもどのくらいかはっきりとはわからない。
彼らは老若男女関係なく自滅しうる力を持ち、それが原因で命を落としていく。
天寿を全うした者がいるのかどうかも残っていない。
調べれば調べるほど記録など残すはずもないと思い知らされた。
白月の信奉した神は、かつて人に交わった己の神性を除こうとしている。
あの姿も力も奇跡などではなく、そのための呪いである──そう結論がついた。
これは、彼らにとって絶望の引金になるだろう。
信奉する神は、人どころか自分の子らすらとっくに見限っていたのだ。
「そうすれば勝手に後始末ができるってわかってるのね。
………神様って本当に意地が悪いわ。」
「だからこそ、残せなかったんでしょう……。
でも、もう私達は例外が存在しないくらい血が濃くなってしまいました…。
いくら自分達で身を守っても、人の心までは止められませんから。」
「そうね…。」
とにかく白月には記録というものが異様に少なかった。
それなのに力の根源である黒狼の存在は理解している。
そして慣習として一族を守ろうとする行動も染み付いている。
つまり、意図的に真相は隠されていた…ということだ。
恐らくかつての幻月たちによって。
神に与えられた力でその真意を知り、それが自分達を否定する…。
なんという皮肉なのだろう。
幻月といえば………
「夜花、アナタの妹にはその力は無いの?」
「…………。
真理、どうか私の願いを聞いて下さいませんか…。」
「なぁに?改まっちゃって。アナタのお願いなら最大限頑張っちゃうわよ。」
夜花は、妹を預けたいと言った。
あの子は一番絶望に近いところに居る。
"私"を捨て"ヨナ"という生き方を選んだあの子──
このままこの地に留まり真の幻月になってしまえば
白月という柱を失ったヨナはきっと黒狼に喰われてしまう…と。
それを視たのだと。
未来視に映ったということは、近い将来そうなるということだ。
過去視も未来視も決して万能の千里眼ではない。
絶望を塗り替えることができれば、この未来は覆すことができる。
アタシは観察の延長として、その頼みを引き受けることにした。
連れて行ってあげればいいのよ、もっと明るくて暖かな世界に。

あの子は自分達の他に、もっと外の世界を好きになってくれるだろう。
── それに、これで何か…糸口が見つかれば、夜花たちだって。
東の方には異能が発現し使い手の集まる島があると聞く。
そこなら、夜菜はきっと…もっと人らしく生きることができるだろう。
黒狼の存在を"異能"として。
「…珍しいね、マリがタバコを吸うなんて。」
「…………たまーに、ね。」
その先に待つのが希望なのか、それとも更なる絶望なのか…それはまだわからない。



ENo.260 貴登子 とのやりとり

ENo.326 セシリア とのやりとり

ENo.362 レーカ とのやりとり

ENo.624 キャロ とのやりとり













兎角杏子(381) から エナジー棒 を受け取りました。
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ウォン(99) により ItemNo.11 ド根性雑草 から魔晶『ラリマーピアス』を作製してもらいました!
⇒ ラリマーピアス/魔晶:強さ45/[効果1]復活10 [効果2]- [効果3]充填10
兎角杏子(381) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から法衣『黒咢のパーカー』を作製しました!
サキ(768) とカードを交換しました!
そよ風の呼び声 (サモン:シルフ)
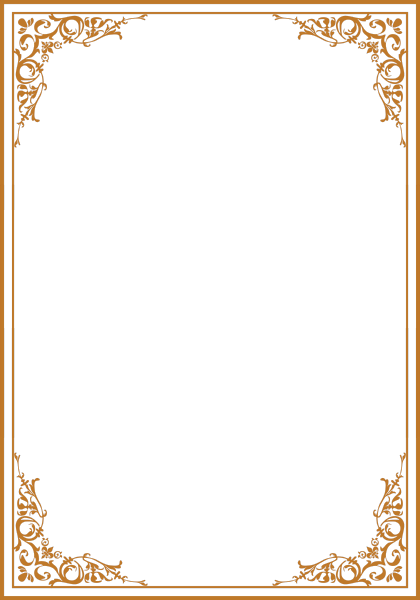
リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
リザレクション を研究しました!(深度1⇒2)
リザレクション を研究しました!(深度2⇒3)
ガードフォーム を習得!
コントラスト を習得!
アンダークーリング を習得!
ビューティーフォーム を習得!
ローバスト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ウォン(99) は 雑木 を入手!
ヨナ(354) は 鉄板 を入手!
兎角杏子(381) は 雑木 を入手!
銀子(455) は 石英 を入手!
兎角杏子(381) は 毛 を入手!
兎角杏子(381) は 花びら を入手!
銀子(455) は 毛 を入手!
銀子(455) は 毛 を入手!



ウォン(99) に移動を委ねました。
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)





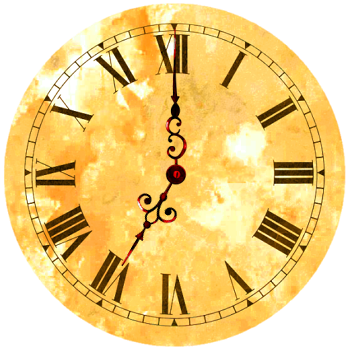
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映し出されるふたり。
チャットから消えるふたり。
チャットが閉じられる――











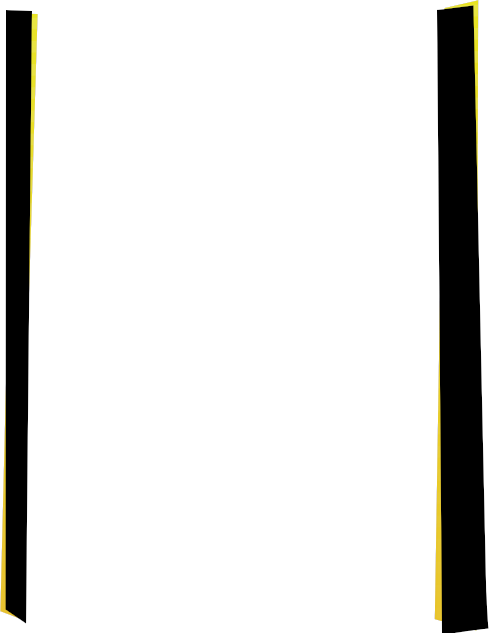
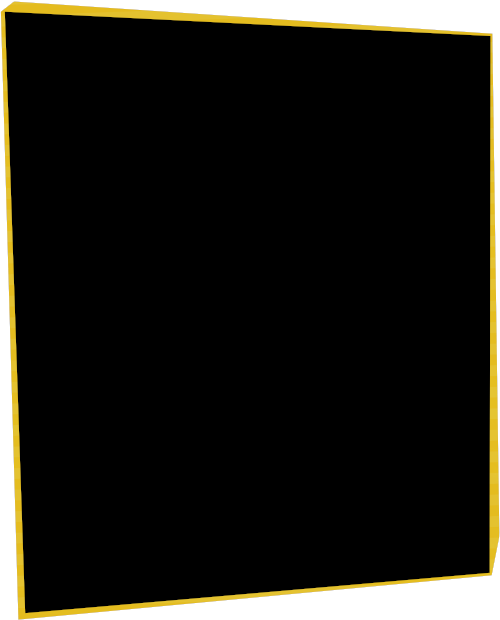





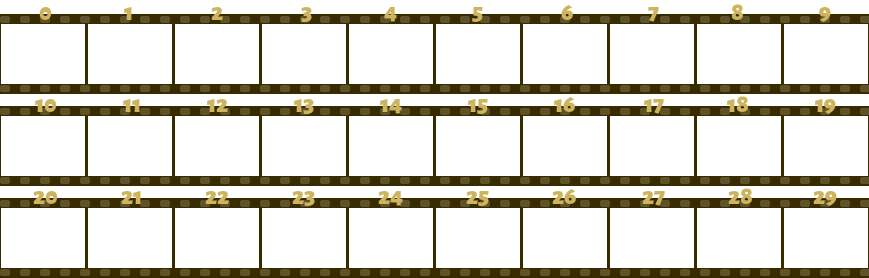







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



夜花は"特別"だった。
当代の幻月は…正真正銘、本物の巫。
かつての白月にもそれが存在したのかどうか断言はできない。
存在したという記録が無かったから。
それらが残っていれば、あるいはすべてを解明できたのかもしれない。
「亡骸の海が見えました。」
「抽象的…ね。何かわかった?」
「いいえ……はっきりとは。」
─── 夜花の力を借りても待宵の伝承の全ては解明できなかった。
許しをもらって直接待宵窟の調査もしてみた。
さすがに底の見えない深淵までは調べられなかったけど──。
中にある社の周辺には何かが居たような痕跡も見つかった。
ただ人のものとするにはやはり少々噛み合わない。
数多ある他の伝承と同じく──諸説あり、と結ぶしかなさそうなのは残念。
こういった本物の怪異に纏わる民間信仰や伝承を読み解くのが、本来の仕事なのにね。
ただ、わかったこともあった。
人は夜と月の神の怒りに触れた。
待宵窟を穢したからなのだろう。
遺体を投げ込んだとする伝承…これは、史実だ。
─── 夜花が視たのだから。
流行り病のせいで遺体を投げ込むようになったのか。
遺体を投げ込むようになった後発生した病を呪いとしたのか。
本当に死者が甦ったのか…あるいは何かをそう表現しただけなのか。
真実は、未だ深淵の闇の中だ。
だから、アタシは生きた伝承を観察することにした───
夜花たちは人とほぼ変わらない姿をしているけれど、いくつか大きく違うところがある。
まず驚いたのは、老いがわかりにくいこと。
違う種族の年齢を外見で判断しづらいことと同じ理屈なのかしらん、と最初は思った。
そして、白月はみな夭折であったこと。
それは人と比較して…ではなく、彼らの天寿と比べて。
本来、神に近い彼らは人と比べれば大幅に長寿だということは辛うじて判明した。
だが、それもどのくらいかはっきりとはわからない。
彼らは老若男女関係なく自滅しうる力を持ち、それが原因で命を落としていく。
天寿を全うした者がいるのかどうかも残っていない。
調べれば調べるほど記録など残すはずもないと思い知らされた。
白月の信奉した神は、かつて人に交わった己の神性を除こうとしている。
あの姿も力も奇跡などではなく、そのための呪いである──そう結論がついた。
これは、彼らにとって絶望の引金になるだろう。
信奉する神は、人どころか自分の子らすらとっくに見限っていたのだ。
「そうすれば勝手に後始末ができるってわかってるのね。
………神様って本当に意地が悪いわ。」
「だからこそ、残せなかったんでしょう……。
でも、もう私達は例外が存在しないくらい血が濃くなってしまいました…。
いくら自分達で身を守っても、人の心までは止められませんから。」
「そうね…。」
とにかく白月には記録というものが異様に少なかった。
それなのに力の根源である黒狼の存在は理解している。
そして慣習として一族を守ろうとする行動も染み付いている。
つまり、意図的に真相は隠されていた…ということだ。
恐らくかつての幻月たちによって。
神に与えられた力でその真意を知り、それが自分達を否定する…。
なんという皮肉なのだろう。
幻月といえば………
「夜花、アナタの妹にはその力は無いの?」
「…………。
真理、どうか私の願いを聞いて下さいませんか…。」
「なぁに?改まっちゃって。アナタのお願いなら最大限頑張っちゃうわよ。」
夜花は、妹を預けたいと言った。
あの子は一番絶望に近いところに居る。
"私"を捨て"ヨナ"という生き方を選んだあの子──
このままこの地に留まり真の幻月になってしまえば
白月という柱を失ったヨナはきっと黒狼に喰われてしまう…と。
それを視たのだと。
未来視に映ったということは、近い将来そうなるということだ。
過去視も未来視も決して万能の千里眼ではない。
絶望を塗り替えることができれば、この未来は覆すことができる。
アタシは観察の延長として、その頼みを引き受けることにした。
連れて行ってあげればいいのよ、もっと明るくて暖かな世界に。

あの子は自分達の他に、もっと外の世界を好きになってくれるだろう。
── それに、これで何か…糸口が見つかれば、夜花たちだって。
東の方には異能が発現し使い手の集まる島があると聞く。
そこなら、夜菜はきっと…もっと人らしく生きることができるだろう。
黒狼の存在を"異能"として。
「…珍しいね、マリがタバコを吸うなんて。」
「…………たまーに、ね。」
その先に待つのが希望なのか、それとも更なる絶望なのか…それはまだわからない。



ENo.260 貴登子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.326 セシリア とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.362 レーカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.624 キャロ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||



| どこまでも――どこまでも――澄んだ声が響いていく。そうそれは――コレの価値と居場所を示す…… |
 |
兎角杏子 「兎角が支えます! がんばりましょう!」 |
| 銀子 「よし、頑張っていこう。よろしくねー。」 |





ハイエース便輪廻ショートカットコース
|
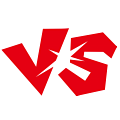 |
TRIQ SHOT
|



兎角杏子(381) から エナジー棒 を受け取りました。
 |
兎角杏子 「腹ごしらえは大事っすよ!」 |
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ウォン(99) により ItemNo.11 ド根性雑草 から魔晶『ラリマーピアス』を作製してもらいました!
⇒ ラリマーピアス/魔晶:強さ45/[効果1]復活10 [効果2]- [効果3]充填10
 |
右鞠 「――ほい、これ。言われてたやつね」 |
兎角杏子(381) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から法衣『黒咢のパーカー』を作製しました!
サキ(768) とカードを交換しました!
そよ風の呼び声 (サモン:シルフ)
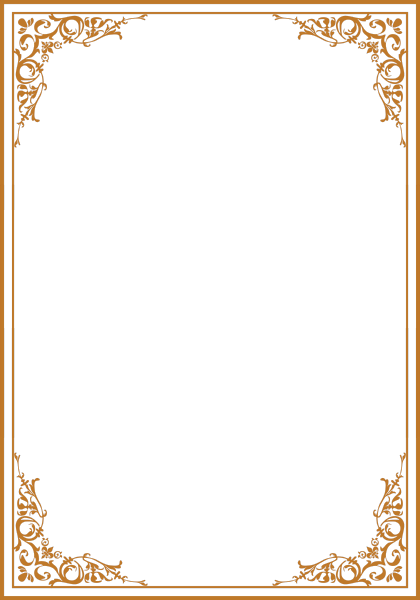
リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
リザレクション を研究しました!(深度1⇒2)
リザレクション を研究しました!(深度2⇒3)
ガードフォーム を習得!
コントラスト を習得!
アンダークーリング を習得!
ビューティーフォーム を習得!
ローバスト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ウォン(99) は 雑木 を入手!
ヨナ(354) は 鉄板 を入手!
兎角杏子(381) は 雑木 を入手!
銀子(455) は 石英 を入手!
兎角杏子(381) は 毛 を入手!
兎角杏子(381) は 花びら を入手!
銀子(455) は 毛 を入手!
銀子(455) は 毛 を入手!



ウォン(99) に移動を委ねました。
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)





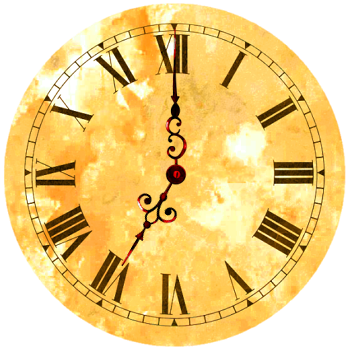
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「うんうん、順調じゃねーっすか。 あとやっぱうるせーのは居ねぇほうが断然いいっすね。」 |
 |
白南海 「いいから早くこれ終わって若に会いたいっすねぇまったく。 もう世界がどうなろうと一緒に歩んでいきやしょうワカァァ――」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カグハ 「・・・わ、変なひとだ。」 |
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
白南海 「――ん、んんッ・・・・・ ・・・なんすか。 お前らは・・・あぁ、梅楽園の団子むすめっこか。」 |
 |
カオリ 「チャットにいたからお邪魔してみようかなって!ごあいさつ!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
 |
白南海 「勝手に人の部屋に入るもんじゃねぇぞ、ガキンチョ。」 |
 |
カオリ 「勝手って、みんなに発信してるじゃんこのチャット。」 |
 |
カグハ 「・・・寂しがりや?」 |
 |
白南海 「・・・そ、操作ミスってたのか。クソ。・・・クソ。」 |
 |
白南海 「そういや、お前らは・・・・・ロストじゃねぇんよなぁ?」 |
 |
カグハ 「違うよー。」 |
 |
カオリ 「私はイバラシティ生まれのイバラシティ育ち!」 |
 |
白南海 「・・・・・は?なんだこっち側かよ。 だったらアンジニティ側に団子渡すなっての。イバラシティがどうなってもいいのか?」 |
 |
カオリ 「あ、・・・・・んー、・・・それがそれが。カグハちゃんは、アンジニティ側なの。」 |
 |
カグハ 「・・・・・」 |
 |
白南海 「なんだそりゃ。ガキのくせに、破滅願望でもあんのか?」 |
 |
カグハ 「・・・・・その・・・」 |
 |
カオリ 「うーあーやめやめ!帰ろうカグハちゃん!!」 |
 |
カオリ 「とにかく私たちは能力を使ってお団子を作ることにしたの! ロストのことは偶然そうなっただけだしっ!!」 |
 |
カグハ 「・・・カオリちゃん、やっぱり私――」 |
 |
カオリ 「そ、それじゃーね!バイビーン!!」 |
チャットから消えるふたり。
 |
白南海 「・・・・・ま、別にいいんすけどね。事情はそれぞれ、あるわな。」 |
 |
白南海 「でも何も、あんな子供を巻き込むことぁねぇだろ。なぁ主催者さんよ・・・」 |
チャットが閉じられる――







ハイエース便輪廻ショートカットコース
|
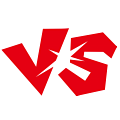 |
トレイターズ
|


ENo.354
白月 夜菜

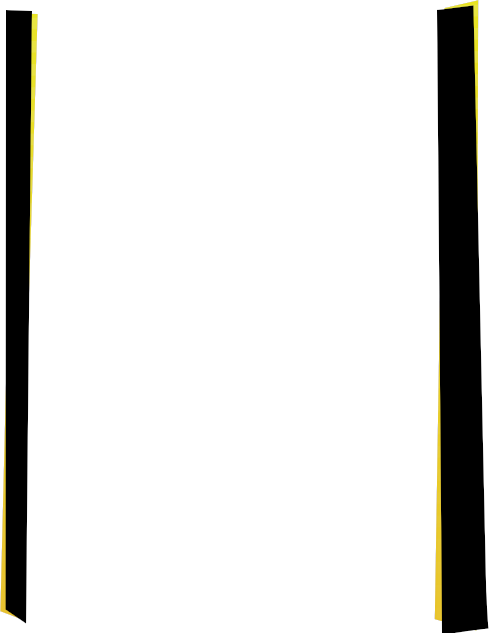
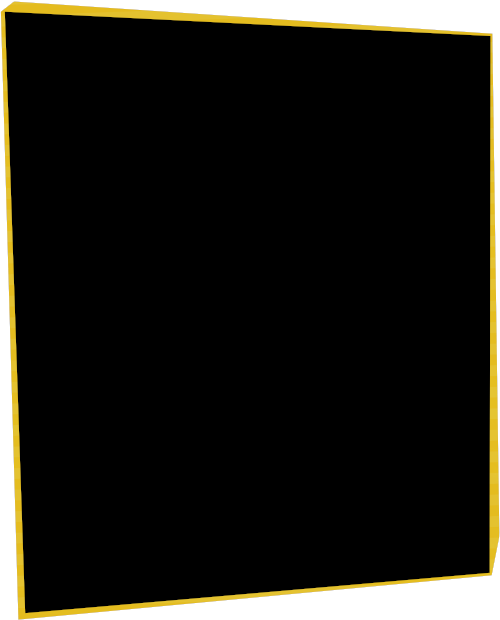
白月 夜菜 -シラツキ ヨナ-
17歳/2月15日生/152cm44kg
相良伊橋高校3年3組 水泳部
白髪金瞳、狐のような耳と尻尾、泣きぼくろのある少女。
月神信仰を持つ地域の出身。実家は神社で元巫女。
極度の人見知りで将来に対しても悲観的。
恋愛含め人との関わりにかなり疎く、積極的に関われるほどではないが最近は人に笑顔を見せることも増えてきた。
片想い中。悪い意味で吹っ切れた。
落ち着かないと顔周りの髪を弄る。尻尾に感情が出がち。
食べることとぬいぐるみが好き。
常にお菓子や栄養調整食品を持ち歩く。
ぬいぐるみ作りと射撃が趣味。怖いものは苦手。
《異能》 暴食 ─ ケルベロスアギト
食べることにより身体能力を飛躍的に引き上げる。
…と公式の書類等に記されているが、実際は食事を代償にしなくても使用が可能。
その一方で体への負担が大きく、場合によっては死に至ることが言及された。
【主な出現場所】
人材派遣 [スタッフサービス](マガサ区 P-8)
相良伊橋高校 2年3組(ツクナミ区 F-6)
シューティングカフェ モーゼル(ミナト区 I-2)
──────────────────────────
真理/カフェモーゼルの主人
ヨナの保護者。謎だらけで女性的な喋り方をする男。
格好はシンプル。ラブリーなもの(生き物含む)が好き。
服作りが趣味でハザマでは防具を作る。
トバリ/赤いスカーフの黒猫
ヨナに拾われてきた。イガサビルで飼われている。
人懐こいが猫なのでだいぶ気まぐれ。
──────────────────────────
置きレス気味ゆっくり交流です。既知はしていません。
基本何でもありの感覚でRPしています。
何かございましたら連絡もしくは@xiao_exe_まで
17歳/2月15日生/152cm44kg
相良伊橋高校3年3組 水泳部
白髪金瞳、狐のような耳と尻尾、泣きぼくろのある少女。
月神信仰を持つ地域の出身。実家は神社で元巫女。
極度の人見知りで将来に対しても悲観的。
恋愛含め人との関わりにかなり疎く、積極的に関われるほどではないが最近は人に笑顔を見せることも増えてきた。
片想い中。悪い意味で吹っ切れた。
落ち着かないと顔周りの髪を弄る。尻尾に感情が出がち。
食べることとぬいぐるみが好き。
常にお菓子や栄養調整食品を持ち歩く。
ぬいぐるみ作りと射撃が趣味。怖いものは苦手。
《異能》 暴食 ─ ケルベロスアギト
食べることにより身体能力を飛躍的に引き上げる。
…と公式の書類等に記されているが、実際は食事を代償にしなくても使用が可能。
その一方で体への負担が大きく、場合によっては死に至ることが言及された。
【主な出現場所】
人材派遣 [スタッフサービス](マガサ区 P-8)
相良伊橋高校 2年3組(ツクナミ区 F-6)
シューティングカフェ モーゼル(ミナト区 I-2)
──────────────────────────
真理/カフェモーゼルの主人
ヨナの保護者。謎だらけで女性的な喋り方をする男。
格好はシンプル。ラブリーなもの(生き物含む)が好き。
服作りが趣味でハザマでは防具を作る。
トバリ/赤いスカーフの黒猫
ヨナに拾われてきた。イガサビルで飼われている。
人懐こいが猫なのでだいぶ気まぐれ。
──────────────────────────
置きレス気味ゆっくり交流です。既知はしていません。
基本何でもありの感覚でRPしています。
何かございましたら連絡もしくは@xiao_exe_まで
20 / 30
115 PS
チナミ区
N-6
N-6






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ミリタリーコート | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 赤い首輪 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 黄鉄鉱 | 素材 | 15 | [武器]麻痺10(LV20)[防具]反光10(LV25)[装飾]光纏10(LV20) | |||
| 7 | チキンナゲット(5個入り) | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 9 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV25)[防具]強靭10(LV20)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
| 10 | スコルソール | 武器 | 45 | 炎上10 | - | - | 【射程3】 |
| 11 | ラリマーピアス | 魔晶 | 45 | 復活10 | - | 充填10 | |
| 12 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 13 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 防具 | 50 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 6 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 6 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| サンダーボルト | 6 | 0 | 80 | 敵痺:光痛撃&麻痺 | |
| クリエイト:ダイナマイト | 5 | 0 | 120 | 自:道連LV増 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| 練3 | クリエイト:グレイル | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
| ビューティーフォーム | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| マインドボム | 5 | 1 | 100 | 敵:SP火撃 | |
| クリエイト:ファイアウェポン | 5 | 0 | 200 | 味:炎上LV・反火LV増 | |
| ラディウス | 5 | 0 | 150 | 敵全:光撃+自:HP増&祝福消費で次与ダメ増 | |
| ブレイクダウン | 5 | 0 | 140 | 自:連続減+敵:光撃&敵全:火撃 | |
| 練3 | イグニス | 6 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| カレイドスコープ | 5 | 0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 練3 | 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
| 鏡像 | 5 | 3 | 0 | 【被HP回復後】自:反射 | |
| 火の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 光の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
| 法衣作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で防具「法衣」を選択できる。法衣は効果3に幸運LVが付加される。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
美味しい干し肉 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
喧嘩上等 (ブレイドフォーム) |
0 | 160 | 自:AT増 | |
|
朝焼けのカード (ツインブラスト) |
0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 練3 |
神無月 (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
|
矛盾した力 (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
|
フラワリングストーム (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
そよ風の呼び声 (サモン:シルフ) |
5 | 400 | 自:シルフ召喚 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ファーマシー | [ 3 ]パワフルヒール | [ 3 ]マナポーション |
| [ 3 ]アクアヒール | [ 3 ]リザレクション | [ 3 ]ヒールポーション |
| [ 3 ]クリエイト:グレイル |

PL / xiao






































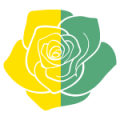




.png)