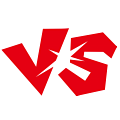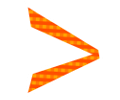<< 5:00~6:00




黒い霧。
あるいはそのようなもの。
ふいにわき出したそれに包まれ、一瞬、ポカンとしたような表情を浮かべる。
そこに視えるものに、あるいは見えてしまうものに。
その頬から血の気が引いていく、みるみるうちに青褪める。
壁際に身体をもたれさせていた両脚が不恰好にぐらつく、もつれる。
横倒しになった身体のとなりに、ごとりと頭を打つ重い音。
地面の上に髪が散らばる――気絶。
あまりに呆気のない。
***
そこに視えるもの。
それは具現と召喚の技の歪な混淆によって動かされているだけの『死人』には、いくらか荷がかち過ぎるものだった。
もはやとうの昔に殺され、ただ『主人』にとって都合よく歩き回るしかない《残り滓》の身には。
この死者の皮の主人こそは、ありとあるときに口を開く無痛の深淵、絶望そのものであったゆえに。

「なぜ?」

“『彼』の罪は、”

“かつて求められた問いに答えられなかったこと。”
必要なことばかりがあった。
求められることばかりが。
これまで、彼はいくつもの姿を借りてきた。
人、獣、鳥、魚、虫、光、石――いくつもの、何匹も何頭ものそれらに宿り、何人もの彼らとして生きてきた。
(そしてあるいは死者の皮、その亡骸の外面を)
“たすける”という、それだけのために。
どれほどの断片と断章のさなかにあっても、彼は応え続けた。
それぞれに固有の記憶はずたずたにほころび、もはや瞬間としてしか残っていない。
ただ。
ただ、ただ!
裳裾をつかむ手と手。祈りと言葉。ひれ伏す影。老いも若きも。微笑みと涙が混ざり合い、死後の約束におびえながら――彼は辛抱強く応え続けた。
どれも無下にすることなどできなかった。
押し寄せる願いと祈りを、彼は力の及ぶ限りに叶え続けた。
彼はしだいに希薄になっていった。もともとあった『彼』というものは。
寄せられる願望に応えるために、むしろ自我は邪魔でさえあった。
祈りへの応答が恣意的なものであってはならない。
彼は選び取りたくなかった。優劣をつけるなどという残酷を、彼は己に許したくなかった。
いつの間にか、彼は己というものを放棄していた――自身である、ということを。
押し寄せる祈りと願いが彼の魂を洗い流し、すっかり漂白してしまったのだった。
もはや祈りと願いこそが、彼というものの力の源でさえあったゆえに。
《彼》は忘我の果てへと、汚泥のように追いやられた。むなしく透明な悦びと共に。
どれほど惨めであっても、どれほど汚れ、醜くなろうと、彼はそんなことは一向に構わないのだった。
満たせないこと。
それは恐怖であった。
けれど物は風化し、人は、命はついに死ぬ。
こぼれていくものがある。
取り落してしまうものが。
どれほど手を差し伸べても、彼はそれらに間に合うことができなかった。
昨日助けた子供が今日は死に、今日救った娘が翌月に死ぬ。
明日の男も死ぬだろう。
翌日、翌月、翌年。もしかすると五年後。十年後、百年、千年ののち。
彼が自身をくべ、削ぎ砕いて施すだけでは、人々の渇きは癒せなかった。
それでも彼は彼というものを擲ち続けた。
ほかに取る術とてなく。
祈りの声が届いただけ、その願いが彼を満たしただけ、それらと骨がらみになった怒りと憎悪が呪いの声とともに降りかかる。
稲妻のように叩きつける罵倒、恨みつらみ。
そのたびごとに彼は小さくなっていった。
細かくすり減り、より本来性を失って。
それでも、「どうか」と。
たった一言縋られることは、あまりに甘美なことだった。
もはや何もかも手遅れとなった絶望の底から呼びかけられ、求められ、“語りかけられる”ことは。
そのとき、彼は石の像としてそこにあった。周囲を覆う、薄暗い天幕に守られて。
いつからそうしていたかは知れない。
目を覚ましたときにはもう、そこに『あった』のだった。
珍しいことではなかった。あるときは獣、あるときはこうした像のなかにいることにふと“気づく”。
いつの間にかそこに宿っている――彼はただ、示される祈りと願いに引き寄せられるものであるゆえに。
彼のいたそこは、《崇拝の地》と呼ばれていた。
あちこちに垂れた華やかな縫い取りの布地に、床の上に並べて点されたいくつもの火。
その輝きの向こうにひれ伏す、人々の姿。その声。
“祈り”。
人々はよく彼の名を呼んだ。
この土地の誰かが唱え始めたその名と、甘い祈りの響きに彼は酔った。もはやこれといってひとつの名を持たない彼ではあったが。
数々の言葉とうやうやしい儀礼を通して、像に侍る人々の期待と信頼が、温かく放射されているのを彼は感じた。
人々は誰も身ぎれいで、灰色の瞳に豊かな赤い髪を垂らし、孔雀の羽のように軽やかな衣を身に着けていた。
多くの人間が黄金に惹かれるのに反して、ここではみな銅や銀でその肌を飾っていた。飾りはどれものたうつ蛇を模したもの。
人々はこまやかに彼の世話を焼いた。もとい、彼がその内に宿っている像に対して。
そして”祈った”。
彼は応えた。これまでと変わらず、持つものは惜しみなくすべて差し出して。
人々は穏やかだった。彼が間に合いきらずとも、彼を責めなかった。彼は幸福だった、これほど長く求められることはかつてなかったために。
だから打ち寄せる祈りの裏側も、そこに覗いていたはずの意味についても、考えもしなかった。もとより、思うこと、考えることを果たすための『彼』は、彼のなかにもうほとんど残されていなかった。
――あるとき。
ひとりの小柄な背が、天幕をくぐって入ってきた。
ふと、彼はあたりの静けさに気づいた。いつもまめまめしく出入りする人々も、今日ばかりは姿を見せない。
目の前に立った人間は、ふだん天幕に出入りする者たちと明らかに違っていた。
少年、あるいは青年。としのころは十代か二十代そこらだろう。
丸く結い上げた金の髪に、真っ青な目。
こうした色はしばらく目にしていなかった。
ここへ出入りする人々はみな、赤毛に灰の目を持っていたから。
細い身体に不釣り合いな鎖帷子を着け、海豹の皮で作ったとおぼしき靴を履いている。飾り気はない。いつも見かける蛇はどこにもいない。その背には、長い柄の剣まで負っている。いや、剣ばかりではない。弓の影さえ見えている。腰には矢筒と、いかにも重たげな手斧。
そして腕には一本の長槍を持っている。

少年は彼に何も求めなかった。
祈りはなかった。
どころか、これは、
相対した少年の口から、雲一つない透きとおった空のような声がこぼれる。
「”なぜ”?」
そしておそるべき素早さで槍を振り上げ、彼を打ち据えた。
とっさに身をよじる。
彼は、台座から少し離れたところへごとりと落ちた。落下による衝撃で、石像は半ば地面にめりこむ。
彼はぼんやりと、土にまみれたまま少年を見上げた。
その手のかざす槍の穂先のひらめきを。
ひどく滑らかで優雅な腕のしなり。
今度の一撃には、先ほどのような甘さはなかった――憐みにも似たものは。
硬く強張った音をたて、像が割れる。
彼は、するりとそこから剥離した。
ほとんど反射的に宙へ逃れる。
身体を失うことには慣れていた。
けっきょくのところ、肉体というものは彼にとって仮宿に過ぎない。この石像もそれは同じことだった。
彼は空中に伸びあがってそのまま、いつものように立ち去ろうとした。ここではないどこか、何者かに祈る誰かを求めて。
身体を持たない間、彼の力は目減りしていくが、それとてもささいなことだった。彼はこの地で大きく肥え太っていた。人々の祈りと願いによって。
少年の足音がする。
それをぼんやりと聞き取って、少年が彼を追ってきていることに気づく。
もはや透明、“あってなきもの”である彼を、少年はどうしてか『視て』追うことができるようだった。
しかし追えたところで、その手に掲げる槍も、剣も手斧も弓も、彼とその本性を害することはできない。石に過ぎないかりそめの身体を壊すことはできたにせよ。
やがて彼はゆるやかに、漂う煙のように天幕の外へ出た。
そしてそこで、前に進むことをやめた。
そこには、
夥しい量の血と命とが流されていた。
そこに倒れていたのは、彼がいる天幕に出入りしていたあの人々では“なかった”。
物のように投げ出され、積み上げられたいくつもの亡骸は、
“金の髪に青い瞳”をして、
殺されていた。
ことごとく。
みな同じやり方で、短剣で首を裂かれて。
よく見れば、山と転がった死体のところどころに、見知った顔が倒れている。
赤い髪に灰色の目。蛇を飾った人々。
彼に祈っていた人々が。
その手に『血に濡れた短剣』を握ったまま、死んでいた。
とうに忘れたはずの恐れとともに振り返る。
血が、
――引きずり出されたはらわたが。
彼が置かれていた天幕のなかに続いていた。
その向こう、垂れた布の間に覗いて見える、割れて砕けた石の像もまた。
天幕のなかには、殺された人々の血と臓物が半ばどす黒く腐りながら、累々と積み上げられている。
ほかでもない、それこそは彼に捧げられた生贄の供物なのだった。
(なぜ)
彼は震えた。
恐ろしかった。
いまや、何もかも。
背後に足音。
逃れようもなくあの少年の声が、
「なぜ?」
彼は叫び声をあげた――言葉にならない言葉、声にならない声で。身体を失ったために上げることの叶わなかった、それは断末魔のごとき悲鳴だった。
そして彼は崩れ始めた。
端から、粉に。乾いた泥の、容易く水に溶かされ洗われるように。
“彼の罪は、かつて求められた問いに答えられなかったこと”。
神である彼は愚かだった。
痛みがあった。
彼は応えるべきではなかった。求められるべきではなかった。
憎まれ恨まれ、呪われて当然のものに過ぎなかったのだった。そうと知らずに彼が犠牲にしてきた、見棄てた、見放してきたすべての者たちから。
彼の前にはもう何も残されていなかった。
ただ、その絶望にふさわしいだけの痛みばかりが、
***
ぴくりとも動かない――いくらか不自然なほど、倒れたまま。
胸が上下している様子もなく、指先がゆれることもない。
見開いたままの目。
散らばった髪の下、地面には、緑色のどろりとした何か。
青リンゴを砕いたような。
緑色の液体は、頭のあたりから拡がっている。
しかしそうして何一つ動かないまま、横倒しになった身体の内側から声がもれる。
聞こえてきた足音に『応える』ように。
ぎこちない動きで腕が伸びる、息の止まったまま。
焦点の合わない両目が、この場にやってきた助けに『応じて』回り出す。
ようやく深々と息を吐き出す、そうすることを思い出したというように――あるいは『人目を気にする』ように。
”応えること、応えようとすることが、彼を動かす主人の本質的な働きであるゆえに”。
ぼうっとした顔で駆けつけた相手の顔を見つめる、差し出されたその腕を。



ENo.1232 ダーシャ とのやりとり

ENo.1352 マタル とのやりとり

ENo.1353 アッシュ とのやりとり




ItemNo.11 チキンステーキ(合成) を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 活力7 体力7 防御7 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








マタル(1352) から 剛毛 を受け取りました。
アッシュ(1353) から エクリチュール《suture》 を受け取りました。
アッシュ(1353) に ItemNo.9 爪 を送付しました。
アッシュ(1353) に ItemNo.15 パリュール『rainure』 を送付しました。
具現LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
料理LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
百薬LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV40⇒50、-10CP)
マタル(1352) により ItemNo.11 剛毛 に ItemNo.13 エクリチュール《suture》 を合成してもらい、白い塊 に変化させました!
⇒ 白い塊/素材:強さ20/[武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20)
マタル(1352) により ItemNo.2 古雑誌 に ItemNo.14 水盆『複写される月』 を合成してもらい、何か固い物体 に変化させました!
⇒ 何か固い物体/素材:強さ15/[武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20)
狐嵐華丸(16) により ItemNo.2 何か固い物体 から防具『踵』を作製してもらいました!
⇒ 踵/防具:強さ90/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-
アッシュ(1353) により ItemNo.11 白い塊 から装飾『左の爪先』を作製してもらいました!
⇒ 左の爪先/装飾:強さ120/[効果1]気合10 [効果2]- [効果3]-
マタル(1352) の持つ ItemNo.2 更紗『第三の黄昏』 に ItemNo.3 柳 を付加しました!
アッシュ(1353) の持つ ItemNo.9 パリュール『rainure』 に ItemNo.8 爪 を付加しました!
ItemNo.11 左の爪先 に ItemNo.1 駄物 を付加しました!
⇒ 左の爪先/装飾:強さ120/[効果1]気合10 [効果2]体力10 [効果3]-
サラタ(1522) とカードを交換しました!
ブルータス (アイシング)
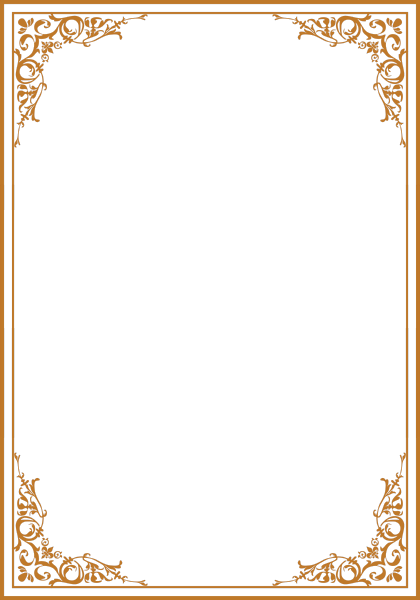
ケイオティックチェイス を研究しました!(深度0⇒1)
ケイオティックチェイス を研究しました!(深度1⇒2)
ケイオティックチェイス を研究しました!(深度2⇒3)
薬師 を習得!
ハオマ を習得!
インフェクシャスキュア を習得!
百薬之長 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



マタル(1352) は ラベンダー を入手!
アッシュ(1353) は 山査子 を入手!
ルーシー(1354) は 大蒜 を入手!
マタル(1352) は 毛皮 を入手!
ルーシー(1354) は ビーフ を入手!
ルーシー(1354) は 不思議な牙 を入手!
アッシュ(1353) は ビーフ を入手!
マタル(1352) は 不思議な牙 を入手!
アッシュ(1353) は ビーフ を入手!



マタル(1352) に移動を委ねました。
ヒノデ区 F-10(道路)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 G-10(道路)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 H-10(道路)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 I-10(沼地)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 J-10(沼地)に移動!(体調18⇒17)





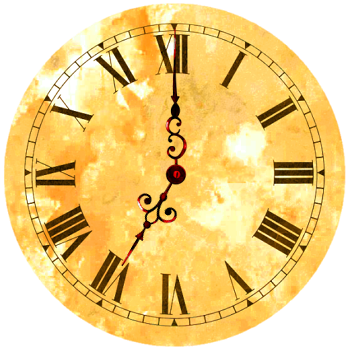
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
映し出される言葉を見て、腕を組む。


チャット画面に映し出されるふたり。
少し照れ臭そうにするエディアン。
チャットが閉じられる――











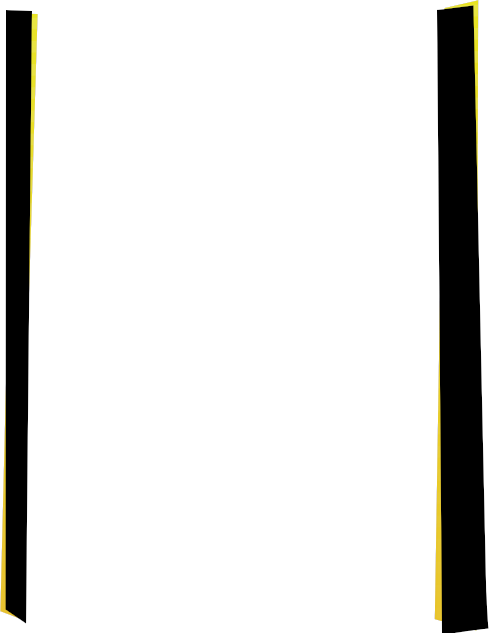
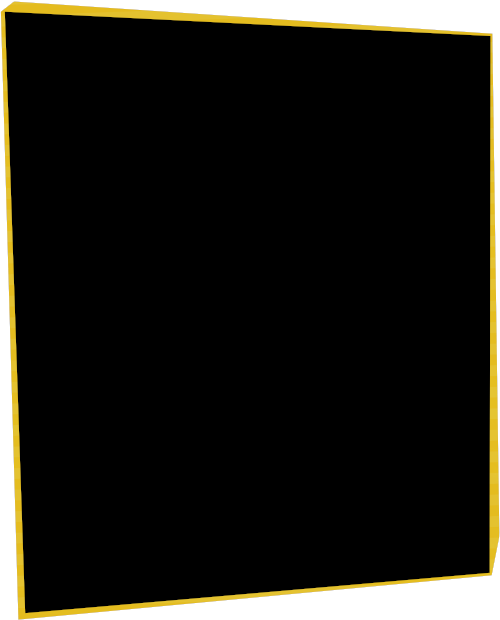





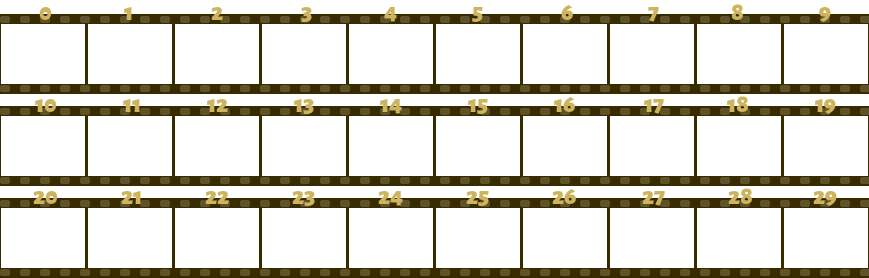







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



黒い霧。
あるいはそのようなもの。
ふいにわき出したそれに包まれ、一瞬、ポカンとしたような表情を浮かべる。
そこに視えるものに、あるいは見えてしまうものに。
「あ、……」 |
その頬から血の気が引いていく、みるみるうちに青褪める。
壁際に身体をもたれさせていた両脚が不恰好にぐらつく、もつれる。
横倒しになった身体のとなりに、ごとりと頭を打つ重い音。
地面の上に髪が散らばる――気絶。
あまりに呆気のない。
***
そこに視えるもの。
それは具現と召喚の技の歪な混淆によって動かされているだけの『死人』には、いくらか荷がかち過ぎるものだった。
もはやとうの昔に殺され、ただ『主人』にとって都合よく歩き回るしかない《残り滓》の身には。
この死者の皮の主人こそは、ありとあるときに口を開く無痛の深淵、絶望そのものであったゆえに。

「なぜ?」

“『彼』の罪は、”

“かつて求められた問いに答えられなかったこと。”
必要なことばかりがあった。
求められることばかりが。
これまで、彼はいくつもの姿を借りてきた。
人、獣、鳥、魚、虫、光、石――いくつもの、何匹も何頭ものそれらに宿り、何人もの彼らとして生きてきた。
(そしてあるいは死者の皮、その亡骸の外面を)
“たすける”という、それだけのために。
どれほどの断片と断章のさなかにあっても、彼は応え続けた。
それぞれに固有の記憶はずたずたにほころび、もはや瞬間としてしか残っていない。
ただ。
ただ、ただ!
裳裾をつかむ手と手。祈りと言葉。ひれ伏す影。老いも若きも。微笑みと涙が混ざり合い、死後の約束におびえながら――彼は辛抱強く応え続けた。
どれも無下にすることなどできなかった。
押し寄せる願いと祈りを、彼は力の及ぶ限りに叶え続けた。
彼はしだいに希薄になっていった。もともとあった『彼』というものは。
寄せられる願望に応えるために、むしろ自我は邪魔でさえあった。
祈りへの応答が恣意的なものであってはならない。
彼は選び取りたくなかった。優劣をつけるなどという残酷を、彼は己に許したくなかった。
いつの間にか、彼は己というものを放棄していた――自身である、ということを。
押し寄せる祈りと願いが彼の魂を洗い流し、すっかり漂白してしまったのだった。
もはや祈りと願いこそが、彼というものの力の源でさえあったゆえに。
《彼》は忘我の果てへと、汚泥のように追いやられた。むなしく透明な悦びと共に。
どれほど惨めであっても、どれほど汚れ、醜くなろうと、彼はそんなことは一向に構わないのだった。
満たせないこと。
それは恐怖であった。
けれど物は風化し、人は、命はついに死ぬ。
こぼれていくものがある。
取り落してしまうものが。
どれほど手を差し伸べても、彼はそれらに間に合うことができなかった。
昨日助けた子供が今日は死に、今日救った娘が翌月に死ぬ。
明日の男も死ぬだろう。
翌日、翌月、翌年。もしかすると五年後。十年後、百年、千年ののち。
彼が自身をくべ、削ぎ砕いて施すだけでは、人々の渇きは癒せなかった。
それでも彼は彼というものを擲ち続けた。
ほかに取る術とてなく。
祈りの声が届いただけ、その願いが彼を満たしただけ、それらと骨がらみになった怒りと憎悪が呪いの声とともに降りかかる。
稲妻のように叩きつける罵倒、恨みつらみ。
そのたびごとに彼は小さくなっていった。
細かくすり減り、より本来性を失って。
それでも、「どうか」と。
たった一言縋られることは、あまりに甘美なことだった。
もはや何もかも手遅れとなった絶望の底から呼びかけられ、求められ、“語りかけられる”ことは。
そのとき、彼は石の像としてそこにあった。周囲を覆う、薄暗い天幕に守られて。
いつからそうしていたかは知れない。
目を覚ましたときにはもう、そこに『あった』のだった。
珍しいことではなかった。あるときは獣、あるときはこうした像のなかにいることにふと“気づく”。
いつの間にかそこに宿っている――彼はただ、示される祈りと願いに引き寄せられるものであるゆえに。
彼のいたそこは、《崇拝の地》と呼ばれていた。
あちこちに垂れた華やかな縫い取りの布地に、床の上に並べて点されたいくつもの火。
その輝きの向こうにひれ伏す、人々の姿。その声。
“祈り”。
人々はよく彼の名を呼んだ。
この土地の誰かが唱え始めたその名と、甘い祈りの響きに彼は酔った。もはやこれといってひとつの名を持たない彼ではあったが。
数々の言葉とうやうやしい儀礼を通して、像に侍る人々の期待と信頼が、温かく放射されているのを彼は感じた。
人々は誰も身ぎれいで、灰色の瞳に豊かな赤い髪を垂らし、孔雀の羽のように軽やかな衣を身に着けていた。
多くの人間が黄金に惹かれるのに反して、ここではみな銅や銀でその肌を飾っていた。飾りはどれものたうつ蛇を模したもの。
人々はこまやかに彼の世話を焼いた。もとい、彼がその内に宿っている像に対して。
そして”祈った”。
彼は応えた。これまでと変わらず、持つものは惜しみなくすべて差し出して。
人々は穏やかだった。彼が間に合いきらずとも、彼を責めなかった。彼は幸福だった、これほど長く求められることはかつてなかったために。
だから打ち寄せる祈りの裏側も、そこに覗いていたはずの意味についても、考えもしなかった。もとより、思うこと、考えることを果たすための『彼』は、彼のなかにもうほとんど残されていなかった。
――あるとき。
ひとりの小柄な背が、天幕をくぐって入ってきた。
ふと、彼はあたりの静けさに気づいた。いつもまめまめしく出入りする人々も、今日ばかりは姿を見せない。
目の前に立った人間は、ふだん天幕に出入りする者たちと明らかに違っていた。
少年、あるいは青年。としのころは十代か二十代そこらだろう。
丸く結い上げた金の髪に、真っ青な目。
こうした色はしばらく目にしていなかった。
ここへ出入りする人々はみな、赤毛に灰の目を持っていたから。
細い身体に不釣り合いな鎖帷子を着け、海豹の皮で作ったとおぼしき靴を履いている。飾り気はない。いつも見かける蛇はどこにもいない。その背には、長い柄の剣まで負っている。いや、剣ばかりではない。弓の影さえ見えている。腰には矢筒と、いかにも重たげな手斧。
そして腕には一本の長槍を持っている。

少年は彼に何も求めなかった。
祈りはなかった。
どころか、これは、
相対した少年の口から、雲一つない透きとおった空のような声がこぼれる。
「”なぜ”?」
そしておそるべき素早さで槍を振り上げ、彼を打ち据えた。
とっさに身をよじる。
彼は、台座から少し離れたところへごとりと落ちた。落下による衝撃で、石像は半ば地面にめりこむ。
彼はぼんやりと、土にまみれたまま少年を見上げた。
その手のかざす槍の穂先のひらめきを。
ひどく滑らかで優雅な腕のしなり。
今度の一撃には、先ほどのような甘さはなかった――憐みにも似たものは。
硬く強張った音をたて、像が割れる。
彼は、するりとそこから剥離した。
ほとんど反射的に宙へ逃れる。
身体を失うことには慣れていた。
けっきょくのところ、肉体というものは彼にとって仮宿に過ぎない。この石像もそれは同じことだった。
彼は空中に伸びあがってそのまま、いつものように立ち去ろうとした。ここではないどこか、何者かに祈る誰かを求めて。
身体を持たない間、彼の力は目減りしていくが、それとてもささいなことだった。彼はこの地で大きく肥え太っていた。人々の祈りと願いによって。
少年の足音がする。
それをぼんやりと聞き取って、少年が彼を追ってきていることに気づく。
もはや透明、“あってなきもの”である彼を、少年はどうしてか『視て』追うことができるようだった。
しかし追えたところで、その手に掲げる槍も、剣も手斧も弓も、彼とその本性を害することはできない。石に過ぎないかりそめの身体を壊すことはできたにせよ。
やがて彼はゆるやかに、漂う煙のように天幕の外へ出た。
そしてそこで、前に進むことをやめた。
そこには、
夥しい量の血と命とが流されていた。
そこに倒れていたのは、彼がいる天幕に出入りしていたあの人々では“なかった”。
物のように投げ出され、積み上げられたいくつもの亡骸は、
“金の髪に青い瞳”をして、
殺されていた。
ことごとく。
みな同じやり方で、短剣で首を裂かれて。
よく見れば、山と転がった死体のところどころに、見知った顔が倒れている。
赤い髪に灰色の目。蛇を飾った人々。
彼に祈っていた人々が。
その手に『血に濡れた短剣』を握ったまま、死んでいた。
とうに忘れたはずの恐れとともに振り返る。
血が、
――引きずり出されたはらわたが。
彼が置かれていた天幕のなかに続いていた。
その向こう、垂れた布の間に覗いて見える、割れて砕けた石の像もまた。
天幕のなかには、殺された人々の血と臓物が半ばどす黒く腐りながら、累々と積み上げられている。
ほかでもない、それこそは彼に捧げられた生贄の供物なのだった。
(なぜ)
彼は震えた。
恐ろしかった。
いまや、何もかも。
背後に足音。
逃れようもなくあの少年の声が、
「なぜ?」
彼は叫び声をあげた――言葉にならない言葉、声にならない声で。身体を失ったために上げることの叶わなかった、それは断末魔のごとき悲鳴だった。
そして彼は崩れ始めた。
端から、粉に。乾いた泥の、容易く水に溶かされ洗われるように。
“彼の罪は、かつて求められた問いに答えられなかったこと”。
神である彼は愚かだった。
痛みがあった。
彼は応えるべきではなかった。求められるべきではなかった。
憎まれ恨まれ、呪われて当然のものに過ぎなかったのだった。そうと知らずに彼が犠牲にしてきた、見棄てた、見放してきたすべての者たちから。
彼の前にはもう何も残されていなかった。
ただ、その絶望にふさわしいだけの痛みばかりが、
***
ぴくりとも動かない――いくらか不自然なほど、倒れたまま。
胸が上下している様子もなく、指先がゆれることもない。
見開いたままの目。
散らばった髪の下、地面には、緑色のどろりとした何か。
青リンゴを砕いたような。
緑色の液体は、頭のあたりから拡がっている。
「う、」 |
しかしそうして何一つ動かないまま、横倒しになった身体の内側から声がもれる。
聞こえてきた足音に『応える』ように。
ぎこちない動きで腕が伸びる、息の止まったまま。
焦点の合わない両目が、この場にやってきた助けに『応じて』回り出す。
ようやく深々と息を吐き出す、そうすることを思い出したというように――あるいは『人目を気にする』ように。
”応えること、応えようとすることが、彼を動かす主人の本質的な働きであるゆえに”。
ぼうっとした顔で駆けつけた相手の顔を見つめる、差し出されたその腕を。
| 「……。 これは、……『ほんとのこと』ですか?」 |



ENo.1232 ダーシャ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1352 マタル とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1353 アッシュ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||



 |
「お探しものはゲーセン、ねぇ……。あっても廃墟なんじゃねぇの?」 |
| 「ヒノデ区もずいぶん様変わりしたが…… この『チェックポイント』てのは、たしか駅があったところだよな。 意図を感じるような感じないような、妙な構造だ」 |
| ルーシー 「……守護者。 ……」 |
ItemNo.11 チキンステーキ(合成) を食べました!
| 焼かれたあとの肉を持ち上げ、いぶかしげに首を傾げる。 |
今回の全戦闘において 活力7 体力7 防御7 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







マタル(1352) から 剛毛 を受け取りました。
 |
「ほらよ。……これ、なんの毛だ?」 |
アッシュ(1353) から エクリチュール《suture》 を受け取りました。
| 「こいつはマタルが広げてくれるはずだ」 |
アッシュ(1353) に ItemNo.9 爪 を送付しました。
アッシュ(1353) に ItemNo.15 パリュール『rainure』 を送付しました。
具現LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
料理LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
百薬LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV40⇒50、-10CP)
マタル(1352) により ItemNo.11 剛毛 に ItemNo.13 エクリチュール《suture》 を合成してもらい、白い塊 に変化させました!
⇒ 白い塊/素材:強さ20/[武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20)
マタル(1352) により ItemNo.2 古雑誌 に ItemNo.14 水盆『複写される月』 を合成してもらい、何か固い物体 に変化させました!
⇒ 何か固い物体/素材:強さ15/[武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20)
 |
「あー、新しい水盆用意しねーとだな……」 |
狐嵐華丸(16) により ItemNo.2 何か固い物体 から防具『踵』を作製してもらいました!
⇒ 踵/防具:強さ90/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-
 |
狐嵐華丸 「(踵…かかと!?雑誌から かかとって作れるの!?)」 |
 |
狐嵐華丸 「(う、うーん…こんな感じかな…こうかな…?自信ないよう)」 |
 |
狐嵐華丸 「お待たせしました。ご注文の品です。 未使用なのでつるつる、すべすべですよ!」 |
 |
アッシュ(1353) により ItemNo.11 白い塊 から装飾『左の爪先』を作製してもらいました!
⇒ 左の爪先/装飾:強さ120/[効果1]気合10 [効果2]- [効果3]-
足を手に取り、指先に文字を書き入れる。 |
マタル(1352) の持つ ItemNo.2 更紗『第三の黄昏』 に ItemNo.3 柳 を付加しました!
アッシュ(1353) の持つ ItemNo.9 パリュール『rainure』 に ItemNo.8 爪 を付加しました!
ItemNo.11 左の爪先 に ItemNo.1 駄物 を付加しました!
⇒ 左の爪先/装飾:強さ120/[効果1]気合10 [効果2]体力10 [効果3]-
| ため息。 |
サラタ(1522) とカードを交換しました!
ブルータス (アイシング)
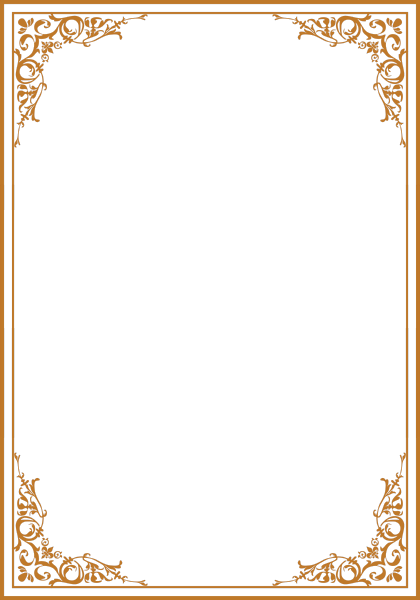
ケイオティックチェイス を研究しました!(深度0⇒1)
ケイオティックチェイス を研究しました!(深度1⇒2)
ケイオティックチェイス を研究しました!(深度2⇒3)
薬師 を習得!
ハオマ を習得!
インフェクシャスキュア を習得!
百薬之長 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



マタル(1352) は ラベンダー を入手!
アッシュ(1353) は 山査子 を入手!
ルーシー(1354) は 大蒜 を入手!
マタル(1352) は 毛皮 を入手!
ルーシー(1354) は ビーフ を入手!
ルーシー(1354) は 不思議な牙 を入手!
アッシュ(1353) は ビーフ を入手!
マタル(1352) は 不思議な牙 を入手!
アッシュ(1353) は ビーフ を入手!



マタル(1352) に移動を委ねました。
ヒノデ区 F-10(道路)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 G-10(道路)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 H-10(道路)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 I-10(沼地)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 J-10(沼地)に移動!(体調18⇒17)





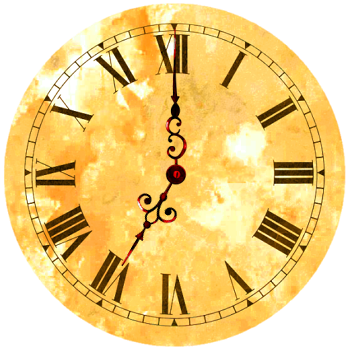
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
エディアン 「・・・おや。チェックポイントによる新たな影響があるようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「今度のは・・・・・割と分かりやすい?そういうことよね、多分。」 |
映し出される言葉を見て、腕を組む。

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
エディアン 「あら!梅楽園の、カオリちゃんとカグハちゃん?いらっしゃい!」 |
 |
カグハ 「おじゃまさまー。」 |
 |
カオリ 「へぇー、アンジニティの案内人さんやっぱり美人さん!」 |
 |
エディアン 「あ、ありがとー。褒めても何も出ませんよー?」 |
少し照れ臭そうにするエディアン。
 |
エディアン 「間接的だけど、お団子見ましたよ。美味しそうねぇあれ!」 |
 |
カオリ 「あー、チャットじゃなくて持ってくれば良かったー!」 |
 |
カグハ 「でも、危ないから・・・」 |
 |
エディアン 「えぇ、危ないからいいですよ。私が今度お邪魔しますから!」 |
 |
エディアン 「お団子、どうやって作ってるんです?」 |
 |
カオリ 「異能だよー!!私があれをこうすると具を作れてー。」 |
 |
カグハ 「お団子は私。」 |
 |
カオリ 「サイキョーコンビなのですっ!!」 |
 |
カグハ 「なのです。」 |
 |
エディアン 「すごーい・・・・・料理系の異能って便利そうねぇ。」 |
 |
カオリ 「お姉さんはどんな能力なの?」 |
 |
エディアン 「私は・・・アンジニティにいるだけあって、結構危ない能力・・・・・かなー。」 |
 |
カグハ 「危ない・・・・・」 |
 |
カオリ 「そっか、お姉さんアンジニティだもんね。なんか、そんな感じしないけど。」 |
 |
エディアン 「こう見えて凶悪なんですよぉー??ゲヘヘヘヘ・・・」 |
 |
カオリ 「それじゃ!梅楽園で待ってるねー!!」 |
 |
カグハ 「お姉さん用のスペシャルお団子、用意しとく。」 |
 |
エディアン 「わぁうれしい!!絶対行きますねーっ!!!!」 |
 |
エディアン 「ここじゃ甘いものなんて滅多に食べれなさそうだものねっ」 |
チャットが閉じられる――









ENo.1354
ルスヴン・ロー

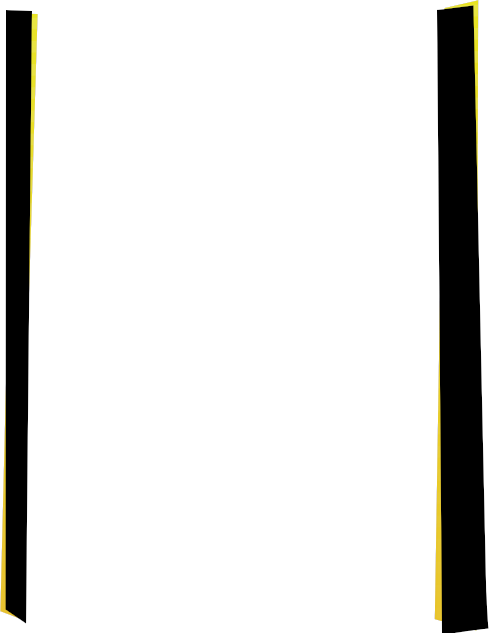
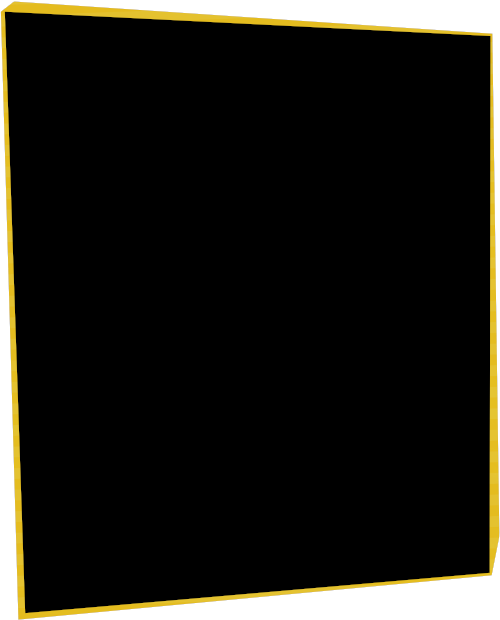
イバラシティでは、犬狩光(いぬかり・こう)。
8月1日生まれ。獅子座。
21歳。O型。
168cm、身軽。
何枚かある黒いツナギを着まわし続けて生きている。
イバラシティの外にある美大に通っていたが、いまは休学中。
基本的に金がない。
異能は「出血した血が緑色に変色すること」。
それ以外に効果らしい効果はない。
だいぶどうしようもない内容なので、特に名前はつけていない。
出てくる血の色は青林檎に似ている。
じっさいは世界最速のスポーツであるハーリングの恐るべき才能を秘めているが、本人がまだハーリングという競技に出会っていないため自覚はない。
ただ棒状のものとボール状(最大卵サイズ)のものを手に持つと身体能力がすごくよくなる。
喧嘩も強くなる。
むしろこっちが本来の異能なのでは???
ものを捨てられない。
捨てられそうなものを見かけると、つい引き受けてきてしまう。
乗っている自転車タクシーも昔のバイト先からもらったもの、飼っている蛇も解散した職場から引き取ったもの。
ほかにもあれこれの品をリスのように蓄えている。
異能を持つ黒い蛇を飼っている。
この蛇は、ネズミや鶏といった肉ではなく果物を食べる。
体長は1mほど。
皮の青い葡萄が好き。
その場でかけられた人語をオウムのように鳴き返すが、覚えることはできないように見える。
温かいところが好き。
名前は特にない。
よく脱走して日向で寝ている。
遠國静、雨宮綴に部屋を貸して暮らしている。
それがイバラシティでの姿。
――――――――――――――
癖のある乱れた黒髪に炎を映した緑の眼。
少年のような姿をしている。
石のように滑らかで冷たい、色のない肌。
極端に受動的。
誰かの言葉や行動を受けてはじめて何かをすることができる。
自分から、誰かに話しかけることはない。
磨り減った信仰心と共に力を失い、逃げるように隠れた神のようなもの。
自分以外の何かに存在を認められていなければ、形を保つことができない。
他者に己を認識させることで力を取り戻す。
これまで通りすぎ、横切ってきたさまざまの分割世界に、残滓や残響のようなものを点々と残している。
それらの《残り滓》は、彼がこれまで殺し、あるいは犠牲にしてきた者たちの《皮》をかぶり、各地をうつろに歩き回る。
これらはあくまで結果的に残ったもので、本体とのつながりを持ってはいない。
《残り滓》たちはほとんど自動的に、生きているかのように振る舞いながら、「彼に信仰心を集め力を取り戻させようとする」。
石に似て、火のなかに置けば熱を帯び、寒気のなかに置けばひやりと冷える。
傷口は罅の割れた目のように見え、時の経つと共にゆっくりと消える。
血は流れない。
アッシュ・サフ、マタル・ユイ、二人の命じるところを忠実に聞き、従う。
道中はただ黙然と、彼らの後を追って歩く。
しかし、彼ら二人の存在が、格別であるわけではないようだ。
求められると相手を問わず、それが何ものでも与えてしまう。
誰の味方とも、敵ともなり得る。
彼の罪は、かつて求められた問いに答えられなかったこと。
------------------------------------------
定期更新用フリーアイコン群、十conを作りつつ使用しています。
詳しくはこちら↓
https://twitter.com/palir_o/status/1216367486641135616
8月1日生まれ。獅子座。
21歳。O型。
168cm、身軽。
何枚かある黒いツナギを着まわし続けて生きている。
イバラシティの外にある美大に通っていたが、いまは休学中。
基本的に金がない。
異能は「出血した血が緑色に変色すること」。
それ以外に効果らしい効果はない。
だいぶどうしようもない内容なので、特に名前はつけていない。
出てくる血の色は青林檎に似ている。
じっさいは世界最速のスポーツであるハーリングの恐るべき才能を秘めているが、本人がまだハーリングという競技に出会っていないため自覚はない。
ただ棒状のものとボール状(最大卵サイズ)のものを手に持つと身体能力がすごくよくなる。
喧嘩も強くなる。
むしろこっちが本来の異能なのでは???
ものを捨てられない。
捨てられそうなものを見かけると、つい引き受けてきてしまう。
乗っている自転車タクシーも昔のバイト先からもらったもの、飼っている蛇も解散した職場から引き取ったもの。
ほかにもあれこれの品をリスのように蓄えている。
異能を持つ黒い蛇を飼っている。
この蛇は、ネズミや鶏といった肉ではなく果物を食べる。
体長は1mほど。
皮の青い葡萄が好き。
その場でかけられた人語をオウムのように鳴き返すが、覚えることはできないように見える。
温かいところが好き。
名前は特にない。
よく脱走して日向で寝ている。
遠國静、雨宮綴に部屋を貸して暮らしている。
それがイバラシティでの姿。
――――――――――――――
癖のある乱れた黒髪に炎を映した緑の眼。
少年のような姿をしている。
石のように滑らかで冷たい、色のない肌。
極端に受動的。
誰かの言葉や行動を受けてはじめて何かをすることができる。
自分から、誰かに話しかけることはない。
磨り減った信仰心と共に力を失い、逃げるように隠れた神のようなもの。
自分以外の何かに存在を認められていなければ、形を保つことができない。
他者に己を認識させることで力を取り戻す。
これまで通りすぎ、横切ってきたさまざまの分割世界に、残滓や残響のようなものを点々と残している。
それらの《残り滓》は、彼がこれまで殺し、あるいは犠牲にしてきた者たちの《皮》をかぶり、各地をうつろに歩き回る。
これらはあくまで結果的に残ったもので、本体とのつながりを持ってはいない。
《残り滓》たちはほとんど自動的に、生きているかのように振る舞いながら、「彼に信仰心を集め力を取り戻させようとする」。
石に似て、火のなかに置けば熱を帯び、寒気のなかに置けばひやりと冷える。
傷口は罅の割れた目のように見え、時の経つと共にゆっくりと消える。
血は流れない。
アッシュ・サフ、マタル・ユイ、二人の命じるところを忠実に聞き、従う。
道中はただ黙然と、彼らの後を追って歩く。
しかし、彼ら二人の存在が、格別であるわけではないようだ。
求められると相手を問わず、それが何ものでも与えてしまう。
誰の味方とも、敵ともなり得る。
彼の罪は、かつて求められた問いに答えられなかったこと。
------------------------------------------
定期更新用フリーアイコン群、十conを作りつつ使用しています。
詳しくはこちら↓
https://twitter.com/palir_o/status/1216367486641135616
17 / 30
305 PS
ヒノデ区
J-10
J-10









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 大蒜 | 素材 | 20 | [武器]体力15(LV30)[防具]体力15(LV30)[装飾]体力15(LV30) | |||
| 2 | 踵 | 防具 | 90 | 防御10 | - | - | |
| 3 | 右腕 | 武器 | 50 | 体力10 | 体力10 | - | 【射程1】 |
| 4 | カフヴァール | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | ガーウ・ラテウォン | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | 左腕 | 武器 | 50 | 体力10 | 体力10 | - | 【射程2】 |
| 7 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 8 | 《残り滓》 | 防具 | 40 | 体力10 | 命脈10 | - | |
| 9 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 10 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 11 | 左の爪先 | 装飾 | 120 | 気合10 | 体力10 | - | |
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 13 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 変化 | 20 | 強化/弱化/変身 |
| 百薬 | 20 | 化学/病毒/医術 |
| 付加 | 50 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| 決2 | クリエイト:グレイル | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
| ビューティーフォーム | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| 決1 | アクアヒール | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ダークネス | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| 決1 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| 決3 | クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) |
| サモン:スライム | 5 | 2 | 300 | 自:スライム召喚 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| 決1 | アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| ハオマ | 5 | 0 | 80 | 自:HP増+AG増(3T)+魅了・混乱 | |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 | |
| 決3 | ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 | |
| サモン:エンチャンター | 5 | 5 | 300 | 自:エンチャンター召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 決1 | 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
| 決2 | 五月雨 | 6 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
| 敗柳残花 | 6 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 肉体変調特性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 百薬之長 | 5 | 3 | 0 | 【自分行動前】自:精神変調をDF化 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
練乳の練乳あえ (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
ヒール (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 決3 |
イレイザー (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| 決1 |
暗黒脱力法 (アブソーブ) |
0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |
|
ブリ大根 (ホーリーポーション) |
0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 | |
|
菊に盃 (ディベスト) |
0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
|
ブルータス (アイシング) |
0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ダウンフォール | [ 3 ]ワールウィンド | [ 3 ]ヒールハーブ |
| [ 3 ]ケイオティックチェイス | [ 3 ]アンダークーリング | [ 3 ]リザレクション |
| [ 3 ]ダークネス |

PL / 十戸