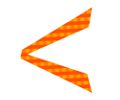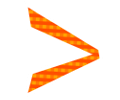<< 4:00~5:00




――とある昔話
どうして、私たちはこうなんだろう。
初めて私に意識というものが芽生えた時。
目の前には、笑みを浮かべる白衣の人物たちとたくさんの機械があった。
私たちは『調整』をされて生まれてきた。
目的は、最初はわからなかったけれど。
周りの白衣たちが、私たちを『かみさまのいれもの』と言っていたことを覚えていた。
きっとそれは、白衣たちが欲しいモノ。
―――それが手に入れば、こんな日々は要らなくなる。
私たちのまっさらな頭に与えられたものはほとんどなかった。
後は、能力の検査と強化。
薬を打たれ、頭が痛くなる。
私たちは、言葉もわからないまま痛みに泣き叫ぶ。
それを見て白衣が嗤う
重たい機械が頭に乗ってきた。
すぐに、真っ白な頭の中がかき回されるような感覚に泣き叫ぶ。
それを見て白衣が嗤う
変な模様が書いてある床の上に縛り付けられる。
裸の胸に、怖い鋭い機械が突きつけられて。
私たちの胸に入り込んでくる。
その激烈な痛みに、泣き叫ぶ
それを見て白衣が嗤う
白衣たちは、何かする度に忙しなく指と目を動かしていた。
怖い、怖い。けれど、どうしようもない。
一人、私の隣にいた『私たち』が白衣に指を向けられる。
私たちが入れられている水が赤くなり。泡で覆われ。
引き裂く様な叫びと共に、見えなくなる。
後に残るのは、長い筒に入れられた、水だけ。
ああ、あの指を向けられれば。
これは終わる。
もう、かみさまなんて要らない。
そう、思っていたのに。
私たちに言葉は与えられず、自由な時間もほとんどない。
けれど、筒に入れられてから、試験と検査が始まるまでの僅かな時間。
隣の『私たち』が、私の方を向いて。
少しだけ、口角をあげた。
思えばそれは、単なる偶然だったのかもしれない。
けれど、その…表情、というものが目新しく。
意識は芽生えていた私たちは、僅かな時間を利用して、表情で遊んだ。
後に嫌な事が待っていると、本能でわかっていたから。
壊れる前に、自己を保とうとしたのかもしれない。
そのやりとりは、少しの間、続いた。
言葉としてはわかっていなかったけれど。
初めて得られた、苦痛以外の感覚に私は夢中になった。
それは、相手も同じだったようで、何度も、何度もそれで遊んだ。
そうしているうちに、白衣たちの目的に…私は近づいてきたのか。
ある程度の教育が与えられる事になった。
この意図は、今でもよくわからない。
後で教育するのが面倒な年齢になったからか、あるいは最初からここまで耐えられたら教育を施すという決まりだったのか。
ともかく、筒に入る以外の時間に少し、本というものを読める時間が生まれた。
字は最初に教えられ、絵本へと。
表情と同じく、新しい事であるそれに、私はまた、夢中になった。
勇敢な王子様がお姫様を助けて愛を見つけるお話。
一人きりだった詩人が、たくさん詩を考えて森の動物たちと友達になるお話。
嘘をついた村人が、みんなから虐められて、正直に生きようと叫び、思い直すお話。
悪い竜を倒すために、ほのおに焼かれながら戦って、みんなのために犠牲になった人のお話
のんびりとした、日々かみさまに祈りを捧げながら生きている人たちの話。
他にも、色々。
どんな基準で選ばれた本なのかはわからない。
けれど、どれもその時の私には新鮮で。
どういうことかわからなければ…既に『最終段階』に入っていた私の質問に、白衣は答えた。
言葉の発音も、その時に覚えることができた。
少し広い部屋で本を読む時間は、私にとってはとても心地よい時間だった。
…けれどそこに、私と遊んだ『わたしたち』は居なかった。
私だけしか、そこには呼ばれなかった。
いつもの、筒の中。
隣の『わたしたち』と、表情で遊ぶ。
言葉は、いくつか…本から覚えた単語を教えて、二人で言い合った。
そもそも目の前の『わたしたち』は、あの本を見てはいないはずだから。
あの部屋に行ったのは、私だけだと白衣たちが話していたから。
けれど。
二人で見つけた色々な表情を、見せ合いながら。
新しい遊び…稚拙ないくつかの単語を筒の中に響かせて少しだけ届け合うことはできた。
『うた』
『こい』
『おうじさま』
『おひめさま』
『いえ』
『ともだち』
『あなた』
『わたし』
『いぬ』
『ひつじ』
…そんな、他愛ない、意味すらも薄い、やりとり。
けれど、楽しかった。
でも―――
「――――え」
…ワタシノ、トナリニ。…ユビガ、ムケラレタ
その時、私の胸に浮かんだものは何だったのだろう。
喪失感、悲しみ、怒り…、本を読んだからこそ。
知識を得たからこそ…それが感情であることが理解できた。
理解、できてしまった。
こんなことなら、本なんて要らなかった。
隣で消えていく初めての『ともだち』が消えていくのを、こんな…理解できる感情を抱えたまま、見ていたくなかった。
けれど、またどうしようもない。
紅い泡に包まれて、叫びを上げながら『ともだち』が消えていく。
このままここに居ては、私も消えるかもしれない。
けれどそれはいい。でも、でも。
私と関わってくれた…あるいは、私が関わった相手が…消えることに、耐えられない。
だから私は『泣き』ながら『叫び』『祈った』
「…わたし、は、どうなっても、いい。なんでも、します」
「でも、わたしいがいが、しんじゃうのは、いや」
「となりの、なかよくはなしたひとが、かえってこないのは、もう、いや」
「となりの…へんなつつにいれられていたひとが、とけてなくなるのをみるのは、もう、いや」
「わたしがさけばないのをみて、わらうひとたちをみるのは、もう、いや」
「だから、――さま、おねがいです」
「おりてきて、ください」
「…わたしから、なにをうばってもかまいません」
「わたしが、しあわせになれなくても、かまいません」
「こいや、あいなんて、…あこがれるけど、いりません」
「だから、おねがいです」
「みんなを、たすけるために、『私』を殺してください」
ああ、それが終わりだった。
私という存在の。
私は、純粋な私ではなくなった。
そしてまた、決断を迫られていく。



ENo.35 一深 とのやりとり

ENo.101 イクコ とのやりとり

ENo.102 安里杏莉? とのやりとり

ENo.161 ミツフネ とのやりとり

ENo.296 枢木 とのやりとり

ENo.298 避役 とのやりとり

ENo.851 まがいものども とのやりとり

ENo.917 ? とのやりとり

以下の相手に送信しました















ミツフネ(161) から 右天黒月・改 を受け取りました。
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ItemNo.14 美味しい果実 から料理『デリシャスアンノウンタワー』をつくりました!
⇒ デリシャスアンノウンタワー/料理:強さ82/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
クリス(169) とカードを交換しました!
フォックスコーヒー (エアスラッシュ)


チェインリアクト を研究しました!(深度2⇒3)
サルベイション を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:グレイル を研究しました!(深度1⇒2)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ミツフネ(161) は ド根性雑草 を入手!
詩穂乃(191) は ド根性雑草 を入手!
闇(273) は ド根性雑草 を入手!
ミツフネ(161) は 美味しい草 を入手!
詩穂乃(191) は 花びら を入手!
闇(273) は 美味しい草 を入手!



闇(273) に移動を委ねました。
カミセイ区 J-4(草原)に移動!(体調6⇒5)
カミセイ区 I-4(草原)に移動!(体調5⇒4)
カミセイ区 H-4(チェックポイント)に移動!(体調4⇒3)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ミツフネ(161) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 闇(273) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 が発生!
- ミツフネ(161) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
- 詩穂乃(191) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
- 闇(273) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














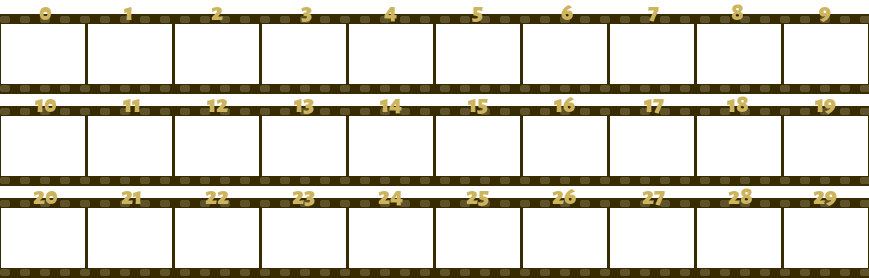


































No.1 キラービー (種族:キラービー)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [戦闘:エイド2]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



――とある昔話
どうして、私たちはこうなんだろう。
初めて私に意識というものが芽生えた時。
目の前には、笑みを浮かべる白衣の人物たちとたくさんの機械があった。
私たちは『調整』をされて生まれてきた。
目的は、最初はわからなかったけれど。
周りの白衣たちが、私たちを『かみさまのいれもの』と言っていたことを覚えていた。
きっとそれは、白衣たちが欲しいモノ。
―――それが手に入れば、こんな日々は要らなくなる。
私たちのまっさらな頭に与えられたものはほとんどなかった。
後は、能力の検査と強化。
薬を打たれ、頭が痛くなる。
私たちは、言葉もわからないまま痛みに泣き叫ぶ。
それを見て白衣が嗤う
重たい機械が頭に乗ってきた。
すぐに、真っ白な頭の中がかき回されるような感覚に泣き叫ぶ。
それを見て白衣が嗤う
変な模様が書いてある床の上に縛り付けられる。
裸の胸に、怖い鋭い機械が突きつけられて。
私たちの胸に入り込んでくる。
その激烈な痛みに、泣き叫ぶ
それを見て白衣が嗤う
白衣たちは、何かする度に忙しなく指と目を動かしていた。
怖い、怖い。けれど、どうしようもない。
一人、私の隣にいた『私たち』が白衣に指を向けられる。
私たちが入れられている水が赤くなり。泡で覆われ。
引き裂く様な叫びと共に、見えなくなる。
後に残るのは、長い筒に入れられた、水だけ。
ああ、あの指を向けられれば。
これは終わる。
もう、かみさまなんて要らない。
そう、思っていたのに。
私たちに言葉は与えられず、自由な時間もほとんどない。
けれど、筒に入れられてから、試験と検査が始まるまでの僅かな時間。
隣の『私たち』が、私の方を向いて。
少しだけ、口角をあげた。
思えばそれは、単なる偶然だったのかもしれない。
けれど、その…表情、というものが目新しく。
意識は芽生えていた私たちは、僅かな時間を利用して、表情で遊んだ。
後に嫌な事が待っていると、本能でわかっていたから。
壊れる前に、自己を保とうとしたのかもしれない。
そのやりとりは、少しの間、続いた。
言葉としてはわかっていなかったけれど。
初めて得られた、苦痛以外の感覚に私は夢中になった。
それは、相手も同じだったようで、何度も、何度もそれで遊んだ。
そうしているうちに、白衣たちの目的に…私は近づいてきたのか。
ある程度の教育が与えられる事になった。
この意図は、今でもよくわからない。
後で教育するのが面倒な年齢になったからか、あるいは最初からここまで耐えられたら教育を施すという決まりだったのか。
ともかく、筒に入る以外の時間に少し、本というものを読める時間が生まれた。
字は最初に教えられ、絵本へと。
表情と同じく、新しい事であるそれに、私はまた、夢中になった。
勇敢な王子様がお姫様を助けて愛を見つけるお話。
一人きりだった詩人が、たくさん詩を考えて森の動物たちと友達になるお話。
嘘をついた村人が、みんなから虐められて、正直に生きようと叫び、思い直すお話。
悪い竜を倒すために、ほのおに焼かれながら戦って、みんなのために犠牲になった人のお話
のんびりとした、日々かみさまに祈りを捧げながら生きている人たちの話。
他にも、色々。
どんな基準で選ばれた本なのかはわからない。
けれど、どれもその時の私には新鮮で。
どういうことかわからなければ…既に『最終段階』に入っていた私の質問に、白衣は答えた。
言葉の発音も、その時に覚えることができた。
少し広い部屋で本を読む時間は、私にとってはとても心地よい時間だった。
…けれどそこに、私と遊んだ『わたしたち』は居なかった。
私だけしか、そこには呼ばれなかった。
いつもの、筒の中。
隣の『わたしたち』と、表情で遊ぶ。
言葉は、いくつか…本から覚えた単語を教えて、二人で言い合った。
そもそも目の前の『わたしたち』は、あの本を見てはいないはずだから。
あの部屋に行ったのは、私だけだと白衣たちが話していたから。
けれど。
二人で見つけた色々な表情を、見せ合いながら。
新しい遊び…稚拙ないくつかの単語を筒の中に響かせて少しだけ届け合うことはできた。
『うた』
『こい』
『おうじさま』
『おひめさま』
『いえ』
『ともだち』
『あなた』
『わたし』
『いぬ』
『ひつじ』
…そんな、他愛ない、意味すらも薄い、やりとり。
けれど、楽しかった。
でも―――
「――――え」
…ワタシノ、トナリニ。…ユビガ、ムケラレタ
その時、私の胸に浮かんだものは何だったのだろう。
喪失感、悲しみ、怒り…、本を読んだからこそ。
知識を得たからこそ…それが感情であることが理解できた。
理解、できてしまった。
こんなことなら、本なんて要らなかった。
隣で消えていく初めての『ともだち』が消えていくのを、こんな…理解できる感情を抱えたまま、見ていたくなかった。
けれど、またどうしようもない。
紅い泡に包まれて、叫びを上げながら『ともだち』が消えていく。
このままここに居ては、私も消えるかもしれない。
けれどそれはいい。でも、でも。
私と関わってくれた…あるいは、私が関わった相手が…消えることに、耐えられない。
だから私は『泣き』ながら『叫び』『祈った』
「…わたし、は、どうなっても、いい。なんでも、します」
「でも、わたしいがいが、しんじゃうのは、いや」
「となりの、なかよくはなしたひとが、かえってこないのは、もう、いや」
「となりの…へんなつつにいれられていたひとが、とけてなくなるのをみるのは、もう、いや」
「わたしがさけばないのをみて、わらうひとたちをみるのは、もう、いや」
「だから、――さま、おねがいです」
「おりてきて、ください」
「…わたしから、なにをうばってもかまいません」
「わたしが、しあわせになれなくても、かまいません」
「こいや、あいなんて、…あこがれるけど、いりません」
「だから、おねがいです」
「みんなを、たすけるために、『私』を殺してください」
ああ、それが終わりだった。
私という存在の。
私は、純粋な私ではなくなった。
そしてまた、決断を迫られていく。



ENo.35 一深 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.101 イクコ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.102 安里杏莉? とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.161 ミツフネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.296 枢木 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.298 避役 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.851 まがいものども とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.917 ? とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ミトリヤ 「ヤーさん、詩穂乃さん、がんばれ~~!! あっもちろんおにいも、程々にがんばれ~!」 |
| 「……斯様に歩き詰めでは…… 此処に愛車があれば……と、此れ程に思うことも、そうはないな……」 |







対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 5 増加!
影響力が 5 増加!



ミツフネ(161) から 右天黒月・改 を受け取りました。
 |
ミツフネ 「これ使いな、咲崎。……頼りにしてるぜ」 |
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ItemNo.14 美味しい果実 から料理『デリシャスアンノウンタワー』をつくりました!
⇒ デリシャスアンノウンタワー/料理:強さ82/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
 |
詩穂乃 「も、盛り過ぎた…ちょっとかじってみたら美味しい果物だったから多分大丈夫…」 |
クリス(169) とカードを交換しました!
フォックスコーヒー (エアスラッシュ)


チェインリアクト を研究しました!(深度2⇒3)
サルベイション を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:グレイル を研究しました!(深度1⇒2)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ミツフネ(161) は ド根性雑草 を入手!
詩穂乃(191) は ド根性雑草 を入手!
闇(273) は ド根性雑草 を入手!
ミツフネ(161) は 美味しい草 を入手!
詩穂乃(191) は 花びら を入手!
闇(273) は 美味しい草 を入手!



闇(273) に移動を委ねました。
カミセイ区 J-4(草原)に移動!(体調6⇒5)
カミセイ区 I-4(草原)に移動!(体調5⇒4)
カミセイ区 H-4(チェックポイント)に移動!(体調4⇒3)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ミツフネ(161) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 闇(273) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 が発生!
- ミツフネ(161) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
- 詩穂乃(191) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
- 闇(273) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――











カミセイ区 H-4
チェックポイント《森の学舎》
チェックポイント。チェックポイント《森の学舎》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《SNAKE》
黒闇に包まれた巨大なヘビのようなもの。
 |
守護者《SNAKE》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.191
天使と監視対象



メインPC
咲崎詩穂乃(サキザキ シホノ)
age:17
height:166
weight:56
birth day:5月15日
黒色の瞳と灰色に近い黒の髪
校章なしのどこかの制服を着た少女
余程の事が無い限り天真爛漫な性格で誰とでも仲良くなろうとする。
普段外に居るときは、長く伸びた髪をポニーテールにしている。
滞在先に居るときやリラックスしている時は解いていることが多い。
ローカル的なアイドルであり、稀にではあるがテレビやラジオにも徐々に顔を出すようになってきた。
人を立てつつも自己主張の強い(精神的にも肉体的にも)ため、コアなファンが付いている様子。
なかなかキャッチーなタイトルの曲もネット発売している。
彼女が所属するグループ、Angel gunner詳細↓
暇な方はどうぞ
https://www.evernote.com/shard/s444/sh/5b1d200e-3b86-4d47-a53d-74708ea56358/840ada49b6730e3130564d76072dfcac
以前にもこの街で生活していたが、少しの間、街を離れていたようで、最近戻ってきた。
――――――――――
ここまでが、表向きの情報。
本来は世界を守るある組織の一員。
その身に宿すのは、光を物質として固着し、実在的な破壊力や空を飛ぶ推進力などの様々な力として利用できる。
黙示録を告げる天使の如き威容を放つ力。
裏世界での彼女は、単騎で戦略兵器扱いされる存在。
本来人の身で制御できる力ではなく、使い続ければ必ず彼女の自我はいつか力に乗っ取られる。
けれど、そんな強大な力を曲がりなりにも制御できるのは彼女がその力を受け入れるために作られた存在だから。
体組成全てに人の手が入っており、天使の力をその身に堕とすデザインチャイルドとして産み出された。
それ故に両親と呼べる存在は居らず、人の情や愛に飢えている面がある。
余程の事が無い限り誰とでも仲良くしようとするのはそのため。
今までは力を少しでも開放すると白髪金目となっていたが、これまでの人生と、イバラシティに来てからの度重なる戦闘によって更に体に能力が馴染み。
多少の力であれば平時の姿のまま放出できるようになった。
普段は怒り狂うことはないが、自身の親しい人に危害が加わりそうになった際には本来の力を十全に発揮し、戦う。
―――――ただし、この情報には欺瞞が含まれている。
現在、彼女は"どちらの世界であろうとも"能力を十全に使えない。
原因は彼女だけが知っており、解決方法も不明であるため、実際に問い詰めなければ明かすことはない。
カモフラージュとして、弱い力で強い攻撃であるかのように振舞い。
叶うのならば肉弾戦闘で済ませようとする。
以前、とある研究所で現出した現象が関係しているようだ。
服装には気を付けていたものの装飾品などの飾り気は無かった彼女だが、少し前から紫の宝石が嵌まったペンダントを身に着けている。
サブPC
アレグリス・E・M・A
優し気な青年医者。
人を尊重する話し方をしつつ、できないことはきっちりとノーと言えるはっきりした性格。
医療技術は目を見張るものがあり、異世界から持ってきたのではないかと噂される器具や技術を使う。
彼の異能とされているのは空間移動。
一度訪れた場所、強固にイメージできる場所にノータイムに繋がる空間の穴を開けることができる。
ただ、移動できるのは1度に付き1人という制限がある。
サブPC
咲崎 陽乃 (サキザキ ヒノ)
age 14
height 150cm
weight 44kg
造られし子供の片割れ
黒髪と、紫の瞳に黄色の眼鏡をかけた少女。
ブランブル女学院に時季外れに転入してきた。
普段はどちらかというと大人しく周りの空気に合わせる。
しかし、『姉』のこととなると過激になり、年齢相応の残酷さを見せる。
勉学の成績は上の上。
要領も良く、授業を受け、軽く参考書をなぞるだけで優秀な成績を取る。
また、普段着は和装だが運動面も優秀。
運動すること自体も好きなのか、体育の授業が楽しみのようだ。
人見知りしない性格であり、あっさりとした細かい事を気にしない性格で場に馴染みやすい。
礼儀も弁えており、年上と見た人や、立場が上だと判断した相手には丁寧に敬語を使おうとする。
趣味は『姉』の音楽を聴くこと、『姉』の活躍を聞くこと。
『姉』に対しては、あまりに積極的すぎるため、若干引かれることもあるようだ。
異能:デウス・デクスター
発動すると、機械と人の目が混じった、グロテスクな右腕が現出する。
直接攻撃もできるほか、現在の異能としての能力は、人間以外の生きているモノ限定の命令権の行使。
草花や動物、昆虫などが対象となり、その生き物たちの命に関わらない範囲なら、簡易な命令に従わせることができる。
ここに多様性があり、ただ単に道路を走っている車の前に飛び込め、なら命令されたモノは従わないが、あの道路に進め、と命令すれば有効になる可能性が高い。
従わせる数に限度は無く、行おうと思えば意図的に昆虫や動物の群れを操れる。
ただし、この異能は発展段階であり、未だ先があることを『姉』は知っている。
咲崎 結羽月(サキザキ ユウキ)
age 12
height 142cm
weight 40kg
造られし子供の片割れ
金髪オールバック。前髪を逆立てた勝気そうな少年。
私立星しろつめ学園に時季外れに転入してきた。
性格はリーダー気質で生意気。
年上にも気に入らなければ、年齢相応に感情で食って掛かる。
しかし、一番上の『姉』を引き合いに出されると弱く、あっさりと引き下がる。
勉学は少し苦手。
特に社会が絶望的。
代わりに算数が得意。
全体としての平均点は高いものの、苦手な教科が足を引っ張っているため、中の上付近の成績に収まっている。
運動については…決まった形の運動、例えばダンスなどは得意ではないが、自分で動きやペースを考えられる喧嘩や、単純なマラソンなどは得意。
体力にも自信があり、よく陽乃と競っている。
言葉遣いなどはまだまだで、敬語を使おうとしてもたどたどしくなることが多く、それを陽乃によく弄られている。
異能:デウス・シニスター
発動すると、機械と人間の口が合わさった異様な腕が現出する。
こちらは直接攻撃能力は持たないものの、霊体など、非実体のモノに対して干渉することができる。
異能としての能力は、死者や生きていないものへの簡易な命令権。
守護霊や地縛霊のように誰かに憑いているモノには効かないが、意思が薄弱な浮遊霊などを操れる。
霊感の無い相手には少し寒気がする程度だが、もしそういったモノに敏感な相手なら、即座に不調をきたすこともある。
無機物に対しても有効であり、小石や水などをテレキネシスのようにぶつけることもできる。
家などの人間の手によって組まれたモノは命令できない。
ただし、異能は発展段階であり、未だ先があることを『姉』は知っている。
――――――――――――――――――――
立ち絵は自作です。
詩穂乃のアイコンはヒトさんにいただきました。感謝!!
アレグリス、陽乃、結羽月のアイコンは自作です!
咲崎詩穂乃(サキザキ シホノ)
age:17
height:166
weight:56
birth day:5月15日
黒色の瞳と灰色に近い黒の髪
校章なしのどこかの制服を着た少女
余程の事が無い限り天真爛漫な性格で誰とでも仲良くなろうとする。
普段外に居るときは、長く伸びた髪をポニーテールにしている。
滞在先に居るときやリラックスしている時は解いていることが多い。
ローカル的なアイドルであり、稀にではあるがテレビやラジオにも徐々に顔を出すようになってきた。
人を立てつつも自己主張の強い(精神的にも肉体的にも)ため、コアなファンが付いている様子。
なかなかキャッチーなタイトルの曲もネット発売している。
彼女が所属するグループ、Angel gunner詳細↓
暇な方はどうぞ
https://www.evernote.com/shard/s444/sh/5b1d200e-3b86-4d47-a53d-74708ea56358/840ada49b6730e3130564d76072dfcac
以前にもこの街で生活していたが、少しの間、街を離れていたようで、最近戻ってきた。
――――――――――
ここまでが、表向きの情報。
本来は世界を守るある組織の一員。
その身に宿すのは、光を物質として固着し、実在的な破壊力や空を飛ぶ推進力などの様々な力として利用できる。
黙示録を告げる天使の如き威容を放つ力。
裏世界での彼女は、単騎で戦略兵器扱いされる存在。
本来人の身で制御できる力ではなく、使い続ければ必ず彼女の自我はいつか力に乗っ取られる。
けれど、そんな強大な力を曲がりなりにも制御できるのは彼女がその力を受け入れるために作られた存在だから。
体組成全てに人の手が入っており、天使の力をその身に堕とすデザインチャイルドとして産み出された。
それ故に両親と呼べる存在は居らず、人の情や愛に飢えている面がある。
余程の事が無い限り誰とでも仲良くしようとするのはそのため。
今までは力を少しでも開放すると白髪金目となっていたが、これまでの人生と、イバラシティに来てからの度重なる戦闘によって更に体に能力が馴染み。
多少の力であれば平時の姿のまま放出できるようになった。
普段は怒り狂うことはないが、自身の親しい人に危害が加わりそうになった際には本来の力を十全に発揮し、戦う。
―――――ただし、この情報には欺瞞が含まれている。
現在、彼女は"どちらの世界であろうとも"能力を十全に使えない。
原因は彼女だけが知っており、解決方法も不明であるため、実際に問い詰めなければ明かすことはない。
カモフラージュとして、弱い力で強い攻撃であるかのように振舞い。
叶うのならば肉弾戦闘で済ませようとする。
以前、とある研究所で現出した現象が関係しているようだ。
服装には気を付けていたものの装飾品などの飾り気は無かった彼女だが、少し前から紫の宝石が嵌まったペンダントを身に着けている。
サブPC
アレグリス・E・M・A
優し気な青年医者。
人を尊重する話し方をしつつ、できないことはきっちりとノーと言えるはっきりした性格。
医療技術は目を見張るものがあり、異世界から持ってきたのではないかと噂される器具や技術を使う。
彼の異能とされているのは空間移動。
一度訪れた場所、強固にイメージできる場所にノータイムに繋がる空間の穴を開けることができる。
ただ、移動できるのは1度に付き1人という制限がある。
サブPC
咲崎 陽乃 (サキザキ ヒノ)
age 14
height 150cm
weight 44kg
造られし子供の片割れ
黒髪と、紫の瞳に黄色の眼鏡をかけた少女。
ブランブル女学院に時季外れに転入してきた。
普段はどちらかというと大人しく周りの空気に合わせる。
しかし、『姉』のこととなると過激になり、年齢相応の残酷さを見せる。
勉学の成績は上の上。
要領も良く、授業を受け、軽く参考書をなぞるだけで優秀な成績を取る。
また、普段着は和装だが運動面も優秀。
運動すること自体も好きなのか、体育の授業が楽しみのようだ。
人見知りしない性格であり、あっさりとした細かい事を気にしない性格で場に馴染みやすい。
礼儀も弁えており、年上と見た人や、立場が上だと判断した相手には丁寧に敬語を使おうとする。
趣味は『姉』の音楽を聴くこと、『姉』の活躍を聞くこと。
『姉』に対しては、あまりに積極的すぎるため、若干引かれることもあるようだ。
異能:デウス・デクスター
発動すると、機械と人の目が混じった、グロテスクな右腕が現出する。
直接攻撃もできるほか、現在の異能としての能力は、人間以外の生きているモノ限定の命令権の行使。
草花や動物、昆虫などが対象となり、その生き物たちの命に関わらない範囲なら、簡易な命令に従わせることができる。
ここに多様性があり、ただ単に道路を走っている車の前に飛び込め、なら命令されたモノは従わないが、あの道路に進め、と命令すれば有効になる可能性が高い。
従わせる数に限度は無く、行おうと思えば意図的に昆虫や動物の群れを操れる。
ただし、この異能は発展段階であり、未だ先があることを『姉』は知っている。
咲崎 結羽月(サキザキ ユウキ)
age 12
height 142cm
weight 40kg
造られし子供の片割れ
金髪オールバック。前髪を逆立てた勝気そうな少年。
私立星しろつめ学園に時季外れに転入してきた。
性格はリーダー気質で生意気。
年上にも気に入らなければ、年齢相応に感情で食って掛かる。
しかし、一番上の『姉』を引き合いに出されると弱く、あっさりと引き下がる。
勉学は少し苦手。
特に社会が絶望的。
代わりに算数が得意。
全体としての平均点は高いものの、苦手な教科が足を引っ張っているため、中の上付近の成績に収まっている。
運動については…決まった形の運動、例えばダンスなどは得意ではないが、自分で動きやペースを考えられる喧嘩や、単純なマラソンなどは得意。
体力にも自信があり、よく陽乃と競っている。
言葉遣いなどはまだまだで、敬語を使おうとしてもたどたどしくなることが多く、それを陽乃によく弄られている。
異能:デウス・シニスター
発動すると、機械と人間の口が合わさった異様な腕が現出する。
こちらは直接攻撃能力は持たないものの、霊体など、非実体のモノに対して干渉することができる。
異能としての能力は、死者や生きていないものへの簡易な命令権。
守護霊や地縛霊のように誰かに憑いているモノには効かないが、意思が薄弱な浮遊霊などを操れる。
霊感の無い相手には少し寒気がする程度だが、もしそういったモノに敏感な相手なら、即座に不調をきたすこともある。
無機物に対しても有効であり、小石や水などをテレキネシスのようにぶつけることもできる。
家などの人間の手によって組まれたモノは命令できない。
ただし、異能は発展段階であり、未だ先があることを『姉』は知っている。
――――――――――――――――――――
立ち絵は自作です。
詩穂乃のアイコンはヒトさんにいただきました。感謝!!
アレグリス、陽乃、結羽月のアイコンは自作です!
30 / 30
405 PS
チナミ区
D-2
D-2




































No.1 キラービー (種族:キラービー)
 |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| 練3 | デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 幸星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:祝福 | |
| 快進撃 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど復活LV増 | |
| 猛毒陣 | 5 | 4 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど猛毒LV増 | |
| 肉体変調特性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |
| 巧技 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX・LK増 |
最大EP[20]
No.2 歩行石壁 (種族:歩行石壁) |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| 火炎避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:火耐性・炎上耐性増+他者から炎上を移される確率減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |
| 瑠璃樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP・精神変調防御・領域値[地][闇]増+守護+連続減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ナイフ | 武器 | 40 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | イヤリング | 装飾 | 40 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | べたつくプロテクター | 防具 | 45 | 舞反10 | - | - | |
| 7 | さらだ(?) | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 9 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV10)[効果2]充填10(LV20)[効果3]増幅10(LV30) | |||
| 10 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 11 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 12 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]地纏10(LV20)[防具]防御10(LV15)[装飾]反射10(LV25) | |||
| 13 | 杉 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV30)[防具]放盲15(LV25)[装飾]舞盲10(LV20) | |||
| 14 | デリシャスアンノウンタワー | 料理 | 82 | 攻撃10 | 防御10 | 強靭15 | |
| 15 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 16 | 右天黒月・改 | 武器 | 75 | 器用10 | - | - | 【射程3】 |
| 17 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 18 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 20 | 身体/武器/物理 |
| 使役 | 5 | エイド/援護 |
| 響鳴 | 20 | 歌唱/音楽/振動 |
| 料理 | 45 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 6 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヴィジランス | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+次受ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| シュリーク | 5 | 0 | 50 | 敵貫:朦朧+自:混乱 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ユニティ | 5 | 0 | 120 | 自:応報LV増+自従全:護衛 | |
| ブレイブハート | 5 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| 練1 | ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| 練1 | チェインリアクト | 5 | 1 | 150 | 敵:5連鎖撃 |
| 練3 | ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
| エファヴェセント | 6 | 0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 狂歌乱舞 | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:混乱+自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増(2T) | |
| 巧技 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX・LK増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
coup droit (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
腹パン×パンチ (ツインブラスト) |
0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
|
Windowlicker (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
ノイズ (ビブラート) |
0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
|
退廃的衝動 (アースリボルト) |
0 | 150 | 敵:X連地領撃+自:弱化ターン効果を短縮 ※X=自分の弱化ターン効果の数+1 | |
|
フォックスコーヒー (エアスラッシュ) |
0 | 110 | 敵:5連風撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]カラミティゲイル | [ 1 ]ディメンションブレイク |
| [ 1 ]コンテイン | [ 3 ]デアデビル | [ 1 ]マジックミサイル |
| [ 2 ]サルベイション | [ 2 ]サモン:サーヴァント | [ 1 ]イグニス |
| [ 3 ]チェインリアクト | [ 1 ]ハードブレイク |

PL / なかえむ