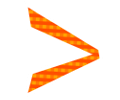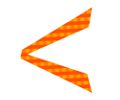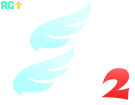<< 4:00~5:00




六日目(Quicksilva)
まるで不吉なカラスのように、瓦礫の山の上にずらりととまっているハトたちを背景にして、オレたちは黒っぽい鹿どもと対峙する。視界を広げると、あちらこちらでオレたちと同じように集まっては、シカだかウマだかと退治している連中の姿がある。守護者とか自称していたか、こいつらを倒せというのがオレたちに与えられた課題ということなのだろう。
「よ~し、かかってきなさい!」
「四辻霜夜の名において、メリさんに命じる。わが血を対価に、その身を守れ」
「まあいっちょう、やりますかね」
「・・・おめ・・・あぐ・・・」
オレたちの相手をするウマシカは四頭、こちらはうつろな目をしたヤンキーを加えて五人とメリさん一頭だから、人数では優っている。「守護者」と称する、この瓦礫の山で主導権を手にしている連中との戦い。挑もうとするオレたちの作戦はソーヤが提案して曰く「全員で横一列に並んでみんなでバンザイ特攻」だった。別に乱暴でもナンでもなく、ソーヤなりに考えた上での作戦だ。
「あの様子なら、あちらはまっすぐ特攻して来そうです。それなら、こちらも正面から迎え撃ったほうが人数の差で有利ですよ。たぶん」
「なるほどねえ。マトを散らそうってことか」
果たして鹿どもはイバラの赤い猛者どもではなく、頭の悪いディアーマンだったから、ソーヤの予想通り全員が盲滅法にバンザイ特攻を仕掛けてきた。これまでこの世界の侵入者、アンジニティの連中にさんざんヒドイ目に遭わされてきたオレたちだが、何度もほうほうのていで逃げ延びてきたことで覚えたコトも少なくない。例えば相手をブッ56してやるよりも、まずは我が身かわいさを優先するというコトだ。
「ちょっと待って待ってよもー!」
「あぶねえなあ!」
ウマシカのくせに、ウシのように突進して来る鹿どもを、フミや楽タローが必死こいて避けている。オレはといえば、最初からこんな発情したウマみてーな奴らとマトモにやりあう気なんてねーから、正面に立ちはだかるフリをして避けるタイミングばかり考えていた。どうやらオレの能力、ハト魔法には距離は関係あるが触れるかどーかは関係ないらしいから、ヤツらのように反撃するつもりで避けるといったむつかしい芸当は必要ないのだ。
「テメーの後ろにハトがいるぜ!?」
オレがそう言って、ウマの後ろを見るとそこには本当にハトがいる。何も考えていない目をしているハトだが、さすがに目の前をウマだかウシだかが通り過ぎていくと、億劫そうにばたばたと一羽が飛び去って行って、ハトが一羽いなくなると力の抜けたシカは肩を落とす。ハトはソーヤの方に飛んで行くが、他のハトどもに混じってしまったのか姿がない。そしてソーヤの体力がほんの少しだけ回復する。それがハト魔法。この世界のどこにでもある、ハトの存在をほんのちょっとだけ動かす能力だ。
突進して通り過ぎて、体勢を立て直すとまた突進する。ウマシカどもの戦い方は迫力があるが単純で、何度か繰り返されるとオレたちも慣れてきて落ち着いて迎え撃てるようになる。フミはアメリカン・コミックのヒーローよろしく合わせた手のひらから光を放ち、楽タローはどこからか現れた石のかたまりを投げつけている。ソーヤの連れているメリさんが突進して、あのふかふかした体でどうやってかワカラネーがシカどもを軽々と弾き飛ばしてみせる。そして、ふらふらと歩きながら、うつろな目をしたヤンキーがシカどもに近づいていく。
「くなや・・・ざこ・・・」
ぶつぶつと呟くと、明らかに不自然な力で地面ごと叩きつけるようなパンチを振り下ろす。漫画か特撮映画のような衝撃が広がり、一発でシカどもの全員が弾かれるように後じさった。これもコイツの異能なんだろうが、殴りつけた腕がぷらんとぶら下がってるがオイオイオイオイ大丈夫かテメー。
だが、この一撃でシカの一頭が消え去ると、数が減って一気にやりやすくなった。メリさんが二頭目のシカを、楽タローが三頭目を、最後の一頭をフミが殴り倒してみせるとチリメンザコくんどもはすべて消え去って後には瓦礫の山が残されただけだった。
「ハッハァ!キスマイアァス」
もっと苦戦するかと思っていたが、思わぬ快勝に気を良くしたハイタッチが宙に打ち合わされる。実はオレだけが戦果を上げていないのは内緒だが、ヤンキーくんの手柄はオレの手柄のようなモノだから構わない。守護者がいなくなった瓦礫の山に、静寂とハトの群れが戻ってくる。
シカどもの姿が消えると、空に向けてナニやら縁起の悪そうな真っ赤な光の柱がそびえ立った。これで次元タクシーとやらが使えるようになって、好きなときにベースキャンプとここを行き来できるようになったらしい。
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
唐突に、オレの古臭い携帯端末が振動すると、画面にこんな文字が映された。他の連中を見ると、どうやら同じメッセージが流されているようだ。当然これにも意味はあるのだろう。数字はここにいる人数だとして、オレたちのいる瓦礫の山には600人を超えるヒマ人どもがいるということか。
すると同じ数だけ守護者とかいうウマシカどもがいたハズで、ホンモノの鹿が何百頭も放されていたとは思えないから、消えちまったところを見ても、オレたちが相手をしたのは目に見える力のよーなモンだったんだろうかとテキトーに考えておく。探偵というモノは好奇心で生きているが、不要なことに労力を使わない、怠惰という名の割り切りも必要だ。オレは仲間たちに声をかける。
「とにかく、いったん帰るか。この趣味の悪い光で、飛ばされたらハエ人間になってましたとかじゃなければいいがね」
「そんな例えを出すオッサンの方が、趣味が悪いぞ」
楽タローの感想をオレはいつものように聞き流すと、真っ赤な光の柱に飛び込んだ。戦いのリスクは他の連中に任せるが、こういうときに真っ先に飛び込んじまうのは単なる好奇心だ。後ろに続いて、他の連中も光に飛び込んできたのがわかる。
でーでーぼっぽぽーと、呑気に鳴いているハトの声が耳に届く。すぐに視界が開けて、覚えのある駅舎とバスターミナルの前に自分が立っていることに気づく。振り向くと後ろには見知った顔がいて、誰も欠けた様子はない。これでオレたちの全員がベースキャンプに戻ってきたというワケだ。駅前にある、大時計の針が指している「4」の数字が午前四時であることに、思わず頭をかいてため息を漏らす。
「やれやれ。いつものコトだがミョーな感じだねえ」
「一時間ごとにいつもの生活に戻って、ハザマにいたことを忘れてるんだよな。こっちにいると覚えてるんだけど、慣れないっちゃ慣れないよなあ」
南高梅だったかいう男に呼び出されて、イバラシティのために戦えとか言われて、チェックポイントとやらを目指して、無事に帰って来ることができた。報酬もハザマ世界で渡されるとはいえ、仕事であるからにはマジメに進めているつもりだし、ここまでの結果もまあ悪くない。
まさしく昔の怪奇小説で読んだドリームランド、趣味の悪い悪夢の世界そのものだ。聞いた話では、アンジニティの連中は戻ってもハザマの記憶を覚えているということだが、それを聞いたオレはむしろ気の毒にねえと思ってしまった。夢の中身なんざ覚えてもロクなことはない。そしてロクでもないからこそ、オレたちがいまいるハザマの世界が夢であると思えば安堵することができる。
「それにしてもさ、オッサン。あれ、なんとかなんねーのかよ」
楽タローが背中越しに指差した後ろ、オレたちから少し離れたところに、うつろな目をして開いた口からはごぽごぽと音を立てているヤンキーと、うつろな目をして瞳孔も口も開きっ放しの歩行軍手がぼんやりとした様子で立っている。連中の足元にはハト。
どーやらオレのハト魔法は、ヤンキーだけではなく歩行軍手みたいな生き物ともつかないモノにも効果があるのは間違いない。なんとかいうゲームに例えるなら、悪魔召喚士とか魔物使いとかいう能力なのかもしれないが、以前フミが言っていたようにこれはファンタジーではなくてホラーだと思う。
「ぐぐぅ・・・」
もういっぺん言っておこう。ロクでもないからこそ、オレたちがいまいるハザマの世界が夢であると思えばいっそ安堵することができるのだ。




ENo.157 ケイ とのやりとり

ENo.1285 楽タロー とのやりとり










ダンデライオン をエイドとして招き入れました!
良い石材(200 PS)を購入しました。
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ヨツジ(1231) の持つ ItemNo.13 良い石材 から防具『石の護符』を作製しました!
星を背負う影(890) とカードを交換しました!
憤怒 (ブレイブハート)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度0⇒1)
インフェクシャスキュア を研究しました!(深度1⇒2)
インフェクシャスキュア を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ヨツジ(1231) は 花びら を入手!
マッケンジー(1144) は 花びら を入手!
楽タロー(1285) は ボロ布 を入手!
ヨツジ(1231) は 大軽石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マッケンジー(1144) のもとに ダンデライオン がスキップしながら近づいてきます。
マッケンジー(1144) のもとに 歩行軍手 がスキップしながら近づいてきます。
マッケンジー(1144) のもとに 歩行小岩 が軽快なステップで近づいてきます。



ヨツジ(1231) がパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――








梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・














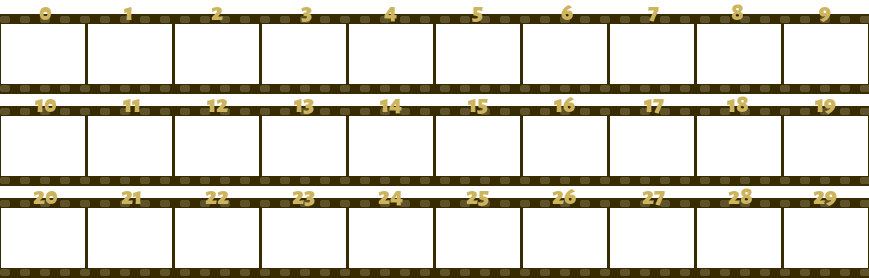


































No.1 うつろな目をしたヤンキー (種族:ヤンキー)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [戦闘:エイド2]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



六日目(Quicksilva)
まるで不吉なカラスのように、瓦礫の山の上にずらりととまっているハトたちを背景にして、オレたちは黒っぽい鹿どもと対峙する。視界を広げると、あちらこちらでオレたちと同じように集まっては、シカだかウマだかと退治している連中の姿がある。守護者とか自称していたか、こいつらを倒せというのがオレたちに与えられた課題ということなのだろう。
「よ~し、かかってきなさい!」
「四辻霜夜の名において、メリさんに命じる。わが血を対価に、その身を守れ」
「まあいっちょう、やりますかね」
「・・・おめ・・・あぐ・・・」
オレたちの相手をするウマシカは四頭、こちらはうつろな目をしたヤンキーを加えて五人とメリさん一頭だから、人数では優っている。「守護者」と称する、この瓦礫の山で主導権を手にしている連中との戦い。挑もうとするオレたちの作戦はソーヤが提案して曰く「全員で横一列に並んでみんなでバンザイ特攻」だった。別に乱暴でもナンでもなく、ソーヤなりに考えた上での作戦だ。
「あの様子なら、あちらはまっすぐ特攻して来そうです。それなら、こちらも正面から迎え撃ったほうが人数の差で有利ですよ。たぶん」
「なるほどねえ。マトを散らそうってことか」
果たして鹿どもはイバラの赤い猛者どもではなく、頭の悪いディアーマンだったから、ソーヤの予想通り全員が盲滅法にバンザイ特攻を仕掛けてきた。これまでこの世界の侵入者、アンジニティの連中にさんざんヒドイ目に遭わされてきたオレたちだが、何度もほうほうのていで逃げ延びてきたことで覚えたコトも少なくない。例えば相手をブッ56してやるよりも、まずは我が身かわいさを優先するというコトだ。
「ちょっと待って待ってよもー!」
「あぶねえなあ!」
ウマシカのくせに、ウシのように突進して来る鹿どもを、フミや楽タローが必死こいて避けている。オレはといえば、最初からこんな発情したウマみてーな奴らとマトモにやりあう気なんてねーから、正面に立ちはだかるフリをして避けるタイミングばかり考えていた。どうやらオレの能力、ハト魔法には距離は関係あるが触れるかどーかは関係ないらしいから、ヤツらのように反撃するつもりで避けるといったむつかしい芸当は必要ないのだ。
「テメーの後ろにハトがいるぜ!?」
オレがそう言って、ウマの後ろを見るとそこには本当にハトがいる。何も考えていない目をしているハトだが、さすがに目の前をウマだかウシだかが通り過ぎていくと、億劫そうにばたばたと一羽が飛び去って行って、ハトが一羽いなくなると力の抜けたシカは肩を落とす。ハトはソーヤの方に飛んで行くが、他のハトどもに混じってしまったのか姿がない。そしてソーヤの体力がほんの少しだけ回復する。それがハト魔法。この世界のどこにでもある、ハトの存在をほんのちょっとだけ動かす能力だ。
突進して通り過ぎて、体勢を立て直すとまた突進する。ウマシカどもの戦い方は迫力があるが単純で、何度か繰り返されるとオレたちも慣れてきて落ち着いて迎え撃てるようになる。フミはアメリカン・コミックのヒーローよろしく合わせた手のひらから光を放ち、楽タローはどこからか現れた石のかたまりを投げつけている。ソーヤの連れているメリさんが突進して、あのふかふかした体でどうやってかワカラネーがシカどもを軽々と弾き飛ばしてみせる。そして、ふらふらと歩きながら、うつろな目をしたヤンキーがシカどもに近づいていく。
「くなや・・・ざこ・・・」
ぶつぶつと呟くと、明らかに不自然な力で地面ごと叩きつけるようなパンチを振り下ろす。漫画か特撮映画のような衝撃が広がり、一発でシカどもの全員が弾かれるように後じさった。これもコイツの異能なんだろうが、殴りつけた腕がぷらんとぶら下がってるがオイオイオイオイ大丈夫かテメー。
だが、この一撃でシカの一頭が消え去ると、数が減って一気にやりやすくなった。メリさんが二頭目のシカを、楽タローが三頭目を、最後の一頭をフミが殴り倒してみせるとチリメンザコくんどもはすべて消え去って後には瓦礫の山が残されただけだった。
「ハッハァ!キスマイアァス」
もっと苦戦するかと思っていたが、思わぬ快勝に気を良くしたハイタッチが宙に打ち合わされる。実はオレだけが戦果を上げていないのは内緒だが、ヤンキーくんの手柄はオレの手柄のようなモノだから構わない。守護者がいなくなった瓦礫の山に、静寂とハトの群れが戻ってくる。
シカどもの姿が消えると、空に向けてナニやら縁起の悪そうな真っ赤な光の柱がそびえ立った。これで次元タクシーとやらが使えるようになって、好きなときにベースキャンプとここを行き来できるようになったらしい。
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
唐突に、オレの古臭い携帯端末が振動すると、画面にこんな文字が映された。他の連中を見ると、どうやら同じメッセージが流されているようだ。当然これにも意味はあるのだろう。数字はここにいる人数だとして、オレたちのいる瓦礫の山には600人を超えるヒマ人どもがいるということか。
すると同じ数だけ守護者とかいうウマシカどもがいたハズで、ホンモノの鹿が何百頭も放されていたとは思えないから、消えちまったところを見ても、オレたちが相手をしたのは目に見える力のよーなモンだったんだろうかとテキトーに考えておく。探偵というモノは好奇心で生きているが、不要なことに労力を使わない、怠惰という名の割り切りも必要だ。オレは仲間たちに声をかける。
「とにかく、いったん帰るか。この趣味の悪い光で、飛ばされたらハエ人間になってましたとかじゃなければいいがね」
「そんな例えを出すオッサンの方が、趣味が悪いぞ」
楽タローの感想をオレはいつものように聞き流すと、真っ赤な光の柱に飛び込んだ。戦いのリスクは他の連中に任せるが、こういうときに真っ先に飛び込んじまうのは単なる好奇心だ。後ろに続いて、他の連中も光に飛び込んできたのがわかる。
でーでーぼっぽぽーと、呑気に鳴いているハトの声が耳に届く。すぐに視界が開けて、覚えのある駅舎とバスターミナルの前に自分が立っていることに気づく。振り向くと後ろには見知った顔がいて、誰も欠けた様子はない。これでオレたちの全員がベースキャンプに戻ってきたというワケだ。駅前にある、大時計の針が指している「4」の数字が午前四時であることに、思わず頭をかいてため息を漏らす。
「やれやれ。いつものコトだがミョーな感じだねえ」
「一時間ごとにいつもの生活に戻って、ハザマにいたことを忘れてるんだよな。こっちにいると覚えてるんだけど、慣れないっちゃ慣れないよなあ」
南高梅だったかいう男に呼び出されて、イバラシティのために戦えとか言われて、チェックポイントとやらを目指して、無事に帰って来ることができた。報酬もハザマ世界で渡されるとはいえ、仕事であるからにはマジメに進めているつもりだし、ここまでの結果もまあ悪くない。
まさしく昔の怪奇小説で読んだドリームランド、趣味の悪い悪夢の世界そのものだ。聞いた話では、アンジニティの連中は戻ってもハザマの記憶を覚えているということだが、それを聞いたオレはむしろ気の毒にねえと思ってしまった。夢の中身なんざ覚えてもロクなことはない。そしてロクでもないからこそ、オレたちがいまいるハザマの世界が夢であると思えば安堵することができる。
「それにしてもさ、オッサン。あれ、なんとかなんねーのかよ」
楽タローが背中越しに指差した後ろ、オレたちから少し離れたところに、うつろな目をして開いた口からはごぽごぽと音を立てているヤンキーと、うつろな目をして瞳孔も口も開きっ放しの歩行軍手がぼんやりとした様子で立っている。連中の足元にはハト。
どーやらオレのハト魔法は、ヤンキーだけではなく歩行軍手みたいな生き物ともつかないモノにも効果があるのは間違いない。なんとかいうゲームに例えるなら、悪魔召喚士とか魔物使いとかいう能力なのかもしれないが、以前フミが言っていたようにこれはファンタジーではなくてホラーだと思う。
「ぐぐぅ・・・」
もういっぺん言っておこう。ロクでもないからこそ、オレたちがいまいるハザマの世界が夢であると思えばいっそ安堵することができるのだ。




ENo.157 ケイ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1285 楽タロー とのやりとり
| ▲ |
| ||||||



 |
うつろな目をしたヤンキー 「・・・おめ。」 |
 |
うつろな目をした歩行軍手 「・・・ぐぅ。」 |
 |
マッケンジー 「・・・なんかオレの能力は問題があると思う。」 |
 |
ヨツジ 「DEERには勝てましたが、あんな賭けは二度とやりたくないですね」 |
 |
メリさん 「めえー」 皆の周りをぽんぽん跳ねている。 |
 |
ヨツジ 「ウラというか、開示されていないルールはまだありそうですね。 ああ、そうだ。 次は少し別行動しますね」 |
| 楽タロー 「…お。またハザマ時間ってやつか。 こう言うのも妙な話だけど、なんか慣れて来たな。」 |
| 楽タロー 「ああ、ヨツジさんとこはそんな感じなのか。住所はミナト区…と(メモを取ろうとして) って、せっかく書いてもそれすら覚えてられないんじゃ、訪ねようがねえのか?」 |
| 楽タロー 「(少し考えて)…フミちゃんも言ってたけど、どうにか『ここでの記憶』を持って帰れたらなあ。 あ、ちょっとメリさん触ってもいいか?(わしわしと愛でつつ)」 |
| 楽タロー 「…俺達、なんとかイバラシティのほうでも接点持てりゃそれに越したことはないよな。 いろいろ相談できることもあるだろうし、俺の異能のことも… まあ正直ハトのおっさんとはあっちじゃ関わりたくねえ気もするけど。」 |
| 楽タロー 「 (ハトとヤンキーを交互に見つつ)明らかにカタギじゃないもんな。」 |





ダンデライオン をエイドとして招き入れました!
良い石材(200 PS)を購入しました。
領域LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ヨツジ(1231) の持つ ItemNo.13 良い石材 から防具『石の護符』を作製しました!
星を背負う影(890) とカードを交換しました!
憤怒 (ブレイブハート)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度0⇒1)
インフェクシャスキュア を研究しました!(深度1⇒2)
インフェクシャスキュア を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ヨツジ(1231) は 花びら を入手!
マッケンジー(1144) は 花びら を入手!
楽タロー(1285) は ボロ布 を入手!
ヨツジ(1231) は 大軽石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マッケンジー(1144) のもとに ダンデライオン がスキップしながら近づいてきます。
マッケンジー(1144) のもとに 歩行軍手 がスキップしながら近づいてきます。
マッケンジー(1144) のもとに 歩行小岩 が軽快なステップで近づいてきます。



ヨツジ(1231) がパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――







チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・





ENo.1144
新沼ケンジ(しんぬま・けんじ)



チバ県マッドシティで開業している探偵。
差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。
能力は「ハト魔法使い」。
差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。
能力は「ハト魔法使い」。
30 / 30
147 PS
チナミ区
D-2
D-2



































No.1 うつろな目をしたヤンキー (種族:ヤンキー)
 |
|
マッケンジーの従者をしているヤンキー。 うつろな目をして、どこも見ていないように見える。 近くにはハトがうろついている。 |
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 | |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
| 先制 | 5 | 6 | 0 | 【戦闘開始時】自:連続増 |
最大EP[20]
No.2 うつろな目をした歩行軍手 (種族:歩行軍手) |
|
マッケンジーの従者をしている軍手。 うつろな目をして、どこも見ていないように見える。 近くにはハトがうろついている。 |
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| マナ | 5 | 0 | 10 | 自:消費SP減 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 背水 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど被攻撃ダメージ減 | |
| 強打 | 5 | 4 | 0 | 【自分行動前】自:次与ダメ増 |
最大EP[20]
No.3 ダンデライオン (種族:ダンデライオン) |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| カタルシス | 5 | 0 | 60 | 敵強:SP光撃&強化を腐食化 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| パージ | 5 | 0 | 120 | 敵列:粗雑SP光撃 | |
| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
| 集気 | 5 | 4 | 0 | 【通常攻撃後】自:次与ダメ増 | |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 光の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 5 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 6 | ラトルスネーク | 装飾 | 50 | 防御10 | - | - | |
| 7 | イグナイター | 武器 | 50 | 炎上10 | - | - | 【射程1】 |
| 8 | トーテンコップ | 防具 | 45 | 体力10 | - | - | |
| 9 | 美味しいブルーチーズ | 料理 | 20 | 治癒10 | - | - | |
| 10 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 11 | デモンズ・スキン | 防具 | 50 | 敏捷10 | - | - | |
| 12 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 13 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 14 | 良い石材 | 素材 | 20 | [武器]体力15(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]幸運15(LV30) | |||
| 15 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 使役 | 20 | エイド/援護 |
| 百薬 | 20 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 45 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ヒールポーション | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| クイックレメディ | 6 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ファーマシー | 6 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| タクシックゾーン | 6 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| パワーブリンガー | 5 | 0 | 100 | 自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増+猛毒 | |
| チャームダンス | 5 | 0 | 140 | 敵全:魅了 | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| スタンピート | 5 | 0 | 50 | 自従:AT・DX・AG増(3T) | |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 | |
| スペシャルポーション | 5 | 0 | 120 | 味傷:HP増+従者ならAT増(1T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 救済 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、味全:HP増&自:救済消滅 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
いましめ (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
|
鎖の巨人 (サモン:ウォリアー) |
5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
|
深層水 (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
|
おまじないカード (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
|
憤怒 (ブレイブハート) |
0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ヒールポーション | [ 3 ]クイックレメディ | [ 3 ]インフェクシャスキュア |
| [ 3 ]ウィルスゾーン | [ 3 ]ファーマシー |

PL / TOSHIKI