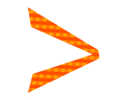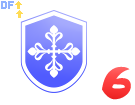<< 3:00~4:00




休憩を許可され、久しぶりに一人になった。
「やっほー、結城さん。この間ぶりだね。……大丈夫だった?」
石を集めながら、考え事に没頭しようか。
そう思っていたところに、そんな声がかかる。
振り返ると、つなぐ先輩がいた。あの男──オニキスとの戦いが、まだ記憶に新しい。
「……ええ。あの男の指示で、何とか戦えて、生きてもいます。
自分のやりたい事に正直な点では、信用できる人ですよ、彼は」
──本当にいいのか。
以前の別れ際、そう聞かれていたことを思い出し。その点の心配は無いと伝えたくて、そう言った。
安心した声で良かった、と口にする先輩は、普通の良い人だ。けれど、
「先輩の方こそ、大丈夫ですか?
……あの男との戦いぶりを見ていたから、あまり、心配はしていなかったんですけど」
あの男との戦いで生まれた疑念は、私の中で燻ぶったままだ。だからつい、探るような言葉を口にしてしまう。
「んー、こっちはちょっと厳しいかな。
ちょっと異能が使えても、やっぱりただの学生だって自覚させられたよ。強いね、アンジニティの人……」
カラスとかは大丈夫だったよ。
と続ける先輩の言葉を聞きながら、浮かんだのは、無事でよかった。という思いだった。
疑っているけれど、以前と変わらず、親しくも思っている。
今の兄への思いと重なって、少し、胸が苦しくなる。
「……信用できる人、か。結城さんはどうしてそう思ったのか聞いても良いかな」
少し間をおいて、先輩はそう問いかけてきた。
「……信用、と言っても、彼の全てを、ではないのですが」
どう言葉にしたものか。迷うように一度言葉を切る。
「彼の目的を聞いた訳ではないんですけど、どうも、侵略には興味がないように感じるんです。
戦いに不得手な私たちを導くのにも、
……こう、この戦いの決着を、一方的に終わらせたくないような意図を感じて」
「だから少なくとも、わたし達が十分に戦えるようになるまでは、その可能性がある限りは、大丈夫だと。
……これも、勝手な希望と推測ではあるんですけどね。
イバラでの彼の記憶のように、また全てが嘘だった……という可能性も捨てきれません」
確りとあった筈のものが、全くの虚ろだった。その事実が、こんなに自分を揺るがすものだとは思わなかったから。
どうしても声や表情に、苦みが滲んでしまうのを、抑えられない。
「それは……信用して、いいのか?」
まあ、今の所は手助けしてくれてるってことかぁ、と取り敢えずと言う納得を見せてくれる先輩。
もっともな反応に、つい小さく笑ってしまう。
利用価値があると思われている内は、この首も飛ぶことは無いという部分にだけは、信用を置ける。
というのは、果たして信用と言って良いものなのか。
けれど、今はそれに縋るのが最良だと、判断したのは自分だ。
「正直なところ何を信じれば良いのやら、という状態です。
これもまた正直に言うと、つなぐ先輩達のこともわたし、疑っていましたから……」
「あー……そうだよね、助けられてたーなんて分からないまま戦っちゃったし。
あの時はごめん。もう少しちゃんと見るべきだった……」
「……いいえ。ただそもそも、この世界に来たばかりの先輩達が戦えていた事自体に、違和を感じていたというか。
騎士になれるふたば先輩以外は本当に、ただの学生だと思っていたので」
先程の彼の言葉を拾いながら。
ふたば先輩の為に、つなぐ先輩が攻撃を凌いだ事。駆け付けたばかりのリリィ先輩が、するりと参戦していた事。
共に戦うことに慣れていると思って。予想外のそれに疑念が生まれてしまったのだと、伝える。
疑っている相手にここまで素直に言葉を紡いだのは、
頭に流れ込んできた、イバラでもハザマでも変わらない先輩の笑顔を見たからか、
嘘でも本当でも、彼自身の言葉で答えが欲しかったからなのか、自分でもわからなかった。
「あ……、そっか。……あいつ約束守りすぎだろ」
控えめな、でも聞こえる程度の声で、先輩は言った。
「あー、ごめん、バツから聞いてると思ってた。
えっと、剣道とかそういうのやってるのは確かにフタバだけなんだけど、
何かと戦うのってあれが初めてじゃないんだよね。……うちの学校さ、なんかたまに変なこと起きない?」
遭遇したことはある。失せ物だとか、幻が見えただとか。不思議な音が聞こえたとか。
嘘かまことかわからないおかしな事が、学園では時折起こり、生徒たちの間で噂になる。
警察や、先生が騒ぐ程のものではない、というのが自分の認識だったけれど。
話の続きを促すと、先輩は話し始めた。
天文部の別の活動。先生や、他の何人かのサポートを受けて、厄介なそれらを退治していた事。
その過程で、戦闘の経験を積んでいた事。
そして、『バツから聞いてる』という言葉で思い出した。
「……一時期、兄が放送室でCDが無くなったって騒いでいた事があって」
やたら遅い時間に帰って来るし、DJ帰りにしては妙に疲れ切ってるし、理由を聞いても歯切れ悪い。
そんな日が、確かにあった。
それがもし、彼らの手伝いをしていたのだとすれば。
私の予想に頷きを見せながら、先輩は話を続ける。
放送室で起きたこと、物の紛失、
先輩たちの異能の事、敵の異能が先輩たちには手に負えなかったこと、
そしてバツ兄の異能によって、それを切り抜けられたこと。
「ホント助かったよ。俺たちああいうのどうにもできないから……。
でも、一応ってバツに口止めはしたけど、結城さんには言ってると思ってたよ」
「兄は案外、そういう所は律儀なので」
兄は、結んだ約束に嘘はつかない。そういう人だから。
「……だから全然知らなかったとは言え、疑ってしまって申し訳なかったです。
兄と合流できたのも、先輩方のおかげですし。ありがとうございます」
小さく頭を下げる。それから、
「……ちなみに、なんですけど。ハザマで兄と会ったときに、何か変わった様子とかはありませんでしたか?
いえ。……率直に聞くと、兄の事、どう『見え』ましたか」
この問いをするのには、少しの勇気が必要だった。
言葉にすると同時に、達成感よりも、罪悪感に苛まれる。けれど、一度吐いた言葉はもう、飲み込めはしない。
「普段学校で会うのとは、やっぱり全然違ったよ。体調も悪そうだし……。
まあ、聞きたいことはこういう事じゃないんだろうね」
先輩はすぐに、質問の意図をくみ取ってくれた。
「俺がバツと合流したのは、バツの方から連絡が来たからなんだ。
急に飛ばされて、味方とか敵とか全然わからないし、全然見た目も見慣れない人も多い中で……。
あいつは『巳羽を無事に帰したい』っていつも通りに妹を心配してたよ。
絶不調って感じだったし、自分がまず危ないのにね」
「まーなに、俺が異能で観れることって結局表面的っていうか……。
さっき結城さんがあの……名前しらないな。あいつを信用できるって感じたのとそう変わらないんじゃないかな。
俺はバツの言葉を信じてるよ」
言葉を選ぶような間の後に、
『異能』ではなく、その『目』で見て感じたことを、思いを答えてくれる。
真実を示される事よりも曖昧な筈なのに、わたしはそこに、彼の誠実さを感じた。
「……こんな質問をしてしまったから、ばればれだと思うし、酷い話だと思われるかもしれないんですけど。
わたし、兄の事も少しだけ、疑ってしまっていたんです」
その理由を、話す。
『結城伐都を信じるな。結城伐都は裏切り者だ。結城伐都に心を許すな』
ハザマに来て間もなく送られてきた、匿名のメッセージの話を。
「何かの冗談だって笑い飛ばしたい自分も、
別の知り合いがアンジニティとわかって、不安を払拭しきれない自分もいて。
だから、誰かの後押しが、欲しくなってしまって」
『解析』の異能を持つ彼ならば、全てわかるかもしれないと。
寄り掛かってしまおうとした自分を、弱くて未熟だと、思う。
誰かに全てを委ねてしまうことは楽だけれど、後々後悔することになるのは、わかり切っているのに。
「でも、もっと単純に考えて良いんだって、気付けました。
わたしが兄の事をどう見たくて、どうしたいか。それだけで良いって」
真っ先に自分の心配をしてくれたという兄の話と、
彼の言葉を信じてる、という先輩の思いを聞いて、そう思った。
ありがとうございます、と。
吹っ切れたようにつなぐ先輩を見上げると、彼は視線を外し口元を手で押さえていた。
くぐもった呟きが、聞こえる。
「なんか、俺も、結城さんと一緒だったのかも。人に偉そうに言っといてだけど……。
自覚なかったけど友達と家族ってまたちょっと違うね」
言葉の断片から、何となく、彼は彼のお姉さんの話をしているのでは、と思うけれど。
つなぐ先輩から話さない限りは、と、触れずにおくことにした。
「ありがとう、結城さん話せて良かったよ」
「わたしも、つなぐ先輩と話せて良かったです」
互いに、再会したその時よりも、雰囲気が明るくなったように感じた。
少なくとも自分は、なんだか道が開けたような気がしている。
兄の事も、あの男の言う、『己の定義』の事も。
この手ごたえを離したくなくて、刻みつけるように、わたしは手元の石を握りしめていた。
++++++++++++++++++++++++++++
「……つなぐ先輩は、もし自分の知り合いがアンジニティだとしたら、それを知りたいと思いますか」
それは先輩との会話の中で。ザクロ先生がオニキスだったことを告げて良いものか。迷っての問いだった。
打ち明けること。それはつまり、イバラシティでのその人との繋がりが、偽りだったと知る事になる。
だからこそ、その事実を伝えることに、躊躇いがあって。反応を伺うように先輩を見上げた。
「どう……なのかな。……いろいろ言い訳しちゃうんだよ。
こっちの記憶が向こうで意味ないとか、会わなければどちらでもとか……。
結局ビビッて自分から連絡とりに行かなかったりしちゃってたりね」
「まあ、俺の場合解っちゃうから言える我儘かもしれないけど……知りたくなかったなって思うことはあると思うよ」
先輩の言葉に、は。と、息が漏れた。抑える前に、唇が『同じだ』と形を作ってしまう。
「……そう、ですよね。現実に立ち向かえって、ある人は言うんですけど、
自ら進んで知ってまで、立ち向かいに行く必要はないんじゃないかって、わたしは思います。
自衛や、アンジニティと渡り合う為に、積極的に情報を得ようとする人もいるかもしれませんが」
少なくとも自分はまだ、そこまで割り切れそうにない。
今近くにいる、たった一人の存在から思い知らされた現実さえ、未だに飲み込み切れていないのだから。
「そうだね。まー俺もそこまで余裕ないから、今はフタバとリリィと、あと友達の範囲で精いっぱいって感じ」
見えてしまう。見ざるを得ない状況にいるつなぐ先輩なら、尚の事だろうと思う。
だからわたしは、今は先生の事は伏せていようと、そう思った。
「……話繰り返しちゃうけど、さ。
アンジニティでもイバラシティでも、それだけで信用できるできないってことにはならないと思うし、
それだけで警戒する必要があることだとは思う。……気を付けてね」
「……ありがとうございます」
進んで知ろうとしなくても良いと思う。けれど、一度知ってしまった現実には、向き合わなくてはいけないとも思う。
自分で見つめて、考えて、信じたい相手を、心を傾ける度合いを、選んで行く。
それがこのハザマで、この先にある未来で、少しでも、悔いのないように生きるために必要な事なのだろうと。
なんとなく、わかり始めていた。













六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



オニキス(301) に 90 PS 送付しました。
イデオローグ(474) に 90 PS 送付しました。
さき(911) に 90 PS 送付しました。
さき(911) に ItemNo.13 平石 を送付しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
幻術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
リリィ(494) により ItemNo.10 何か固い物体 から防具『新たな祈り』を作製してもらいました!
⇒ 新たな祈り/防具:強さ75/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-
オニキス(301) の持つ ItemNo.11 Apfel に ItemNo.9 針 を付加しました!
さき(911) の持つ ItemNo.12 フリーリィ・スカイシー・ダイブ に ItemNo.11 平石 を付加しました!
ItemNo.10 新たな祈り に ItemNo.14 何か固い物体 を付加しました!
⇒ 新たな祈り/防具:強さ75/[効果1]防御10 [効果2]防御10 [効果3]-
つぼみ(901) とカードを交換しました!
芽吹つぼみのカード (アクアヒール)

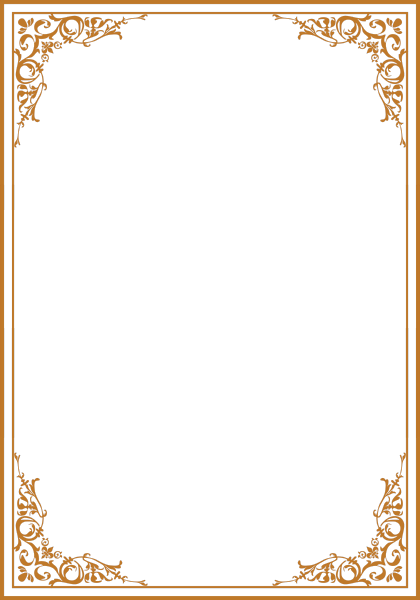
ヘイルカード を研究しました!(深度0⇒1)
ヘイルカード を研究しました!(深度1⇒2)
ヘイルカード を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
ガードフォーム を習得!
リフレッシュ を習得!
アクアシェル を習得!
アンダークーリング を習得!
アクアリカバー を習得!
ヘイルカード を習得!
環境変調耐性 を習得!
ローバスト を習得!
ウィークネス を習得!
プロテクション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



巳羽(473) は 毛 を入手!
イデオローグ(474) は ボロ布 を入手!
オニキス(301) は 毛 を入手!
イデオローグ(474) は ボロ布 を入手!
イデオローグ(474) は 毛 を入手!
オニキス(301) は 毛 を入手!
オニキス(301) は 毛 を入手!
さき(911) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
イデオローグ(474) のもとに 大黒猫 が微笑を浮かべて近づいてきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 に転送されました!
イデオローグ(474) に移動を委ねました。
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 S-8(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 T-8(山岳)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 A-8(山岳)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 B-8(森林)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- オニキス(301) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- イデオローグ(474) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- オニキス(301) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- イデオローグ(474) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)





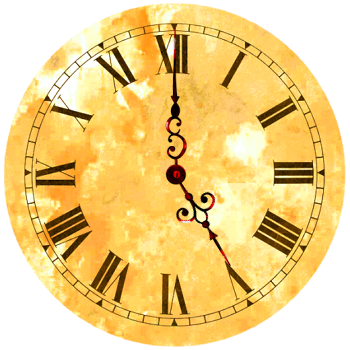
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。

ノウレットから遠く離れる白南海。
遠く離れた白南海を手招く。
チャットが閉じられる――














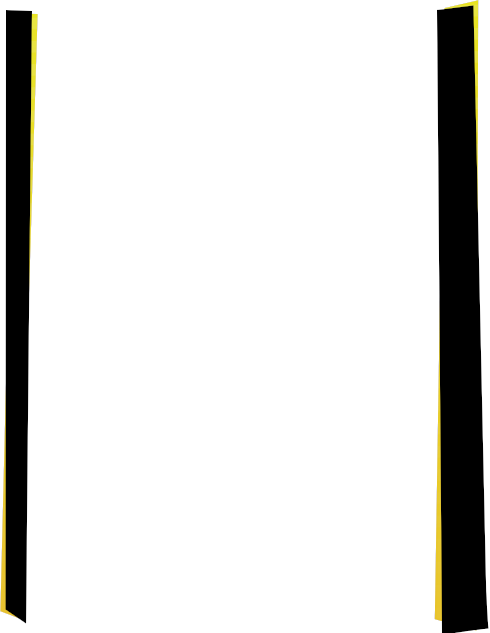
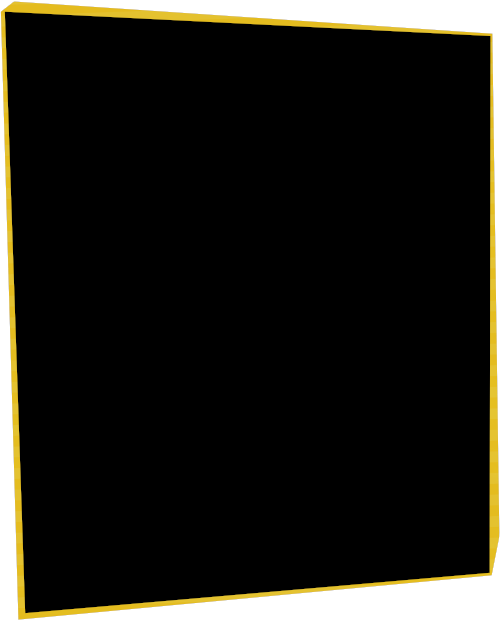





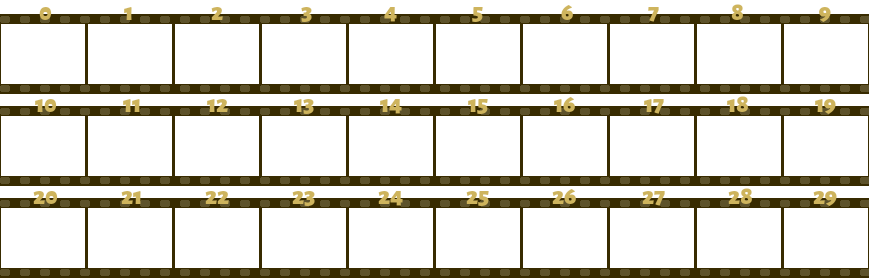





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



休憩を許可され、久しぶりに一人になった。
「やっほー、結城さん。この間ぶりだね。……大丈夫だった?」
石を集めながら、考え事に没頭しようか。
そう思っていたところに、そんな声がかかる。
振り返ると、つなぐ先輩がいた。あの男──オニキスとの戦いが、まだ記憶に新しい。
「……ええ。あの男の指示で、何とか戦えて、生きてもいます。
自分のやりたい事に正直な点では、信用できる人ですよ、彼は」
──本当にいいのか。
以前の別れ際、そう聞かれていたことを思い出し。その点の心配は無いと伝えたくて、そう言った。
安心した声で良かった、と口にする先輩は、普通の良い人だ。けれど、
「先輩の方こそ、大丈夫ですか?
……あの男との戦いぶりを見ていたから、あまり、心配はしていなかったんですけど」
あの男との戦いで生まれた疑念は、私の中で燻ぶったままだ。だからつい、探るような言葉を口にしてしまう。
「んー、こっちはちょっと厳しいかな。
ちょっと異能が使えても、やっぱりただの学生だって自覚させられたよ。強いね、アンジニティの人……」
カラスとかは大丈夫だったよ。
と続ける先輩の言葉を聞きながら、浮かんだのは、無事でよかった。という思いだった。
疑っているけれど、以前と変わらず、親しくも思っている。
今の兄への思いと重なって、少し、胸が苦しくなる。
「……信用できる人、か。結城さんはどうしてそう思ったのか聞いても良いかな」
少し間をおいて、先輩はそう問いかけてきた。
「……信用、と言っても、彼の全てを、ではないのですが」
どう言葉にしたものか。迷うように一度言葉を切る。
「彼の目的を聞いた訳ではないんですけど、どうも、侵略には興味がないように感じるんです。
戦いに不得手な私たちを導くのにも、
……こう、この戦いの決着を、一方的に終わらせたくないような意図を感じて」
「だから少なくとも、わたし達が十分に戦えるようになるまでは、その可能性がある限りは、大丈夫だと。
……これも、勝手な希望と推測ではあるんですけどね。
イバラでの彼の記憶のように、また全てが嘘だった……という可能性も捨てきれません」
確りとあった筈のものが、全くの虚ろだった。その事実が、こんなに自分を揺るがすものだとは思わなかったから。
どうしても声や表情に、苦みが滲んでしまうのを、抑えられない。
「それは……信用して、いいのか?」
まあ、今の所は手助けしてくれてるってことかぁ、と取り敢えずと言う納得を見せてくれる先輩。
もっともな反応に、つい小さく笑ってしまう。
利用価値があると思われている内は、この首も飛ぶことは無いという部分にだけは、信用を置ける。
というのは、果たして信用と言って良いものなのか。
けれど、今はそれに縋るのが最良だと、判断したのは自分だ。
「正直なところ何を信じれば良いのやら、という状態です。
これもまた正直に言うと、つなぐ先輩達のこともわたし、疑っていましたから……」
「あー……そうだよね、助けられてたーなんて分からないまま戦っちゃったし。
あの時はごめん。もう少しちゃんと見るべきだった……」
「……いいえ。ただそもそも、この世界に来たばかりの先輩達が戦えていた事自体に、違和を感じていたというか。
騎士になれるふたば先輩以外は本当に、ただの学生だと思っていたので」
先程の彼の言葉を拾いながら。
ふたば先輩の為に、つなぐ先輩が攻撃を凌いだ事。駆け付けたばかりのリリィ先輩が、するりと参戦していた事。
共に戦うことに慣れていると思って。予想外のそれに疑念が生まれてしまったのだと、伝える。
疑っている相手にここまで素直に言葉を紡いだのは、
頭に流れ込んできた、イバラでもハザマでも変わらない先輩の笑顔を見たからか、
嘘でも本当でも、彼自身の言葉で答えが欲しかったからなのか、自分でもわからなかった。
「あ……、そっか。……あいつ約束守りすぎだろ」
控えめな、でも聞こえる程度の声で、先輩は言った。
「あー、ごめん、バツから聞いてると思ってた。
えっと、剣道とかそういうのやってるのは確かにフタバだけなんだけど、
何かと戦うのってあれが初めてじゃないんだよね。……うちの学校さ、なんかたまに変なこと起きない?」
遭遇したことはある。失せ物だとか、幻が見えただとか。不思議な音が聞こえたとか。
嘘かまことかわからないおかしな事が、学園では時折起こり、生徒たちの間で噂になる。
警察や、先生が騒ぐ程のものではない、というのが自分の認識だったけれど。
話の続きを促すと、先輩は話し始めた。
天文部の別の活動。先生や、他の何人かのサポートを受けて、厄介なそれらを退治していた事。
その過程で、戦闘の経験を積んでいた事。
そして、『バツから聞いてる』という言葉で思い出した。
「……一時期、兄が放送室でCDが無くなったって騒いでいた事があって」
やたら遅い時間に帰って来るし、DJ帰りにしては妙に疲れ切ってるし、理由を聞いても歯切れ悪い。
そんな日が、確かにあった。
それがもし、彼らの手伝いをしていたのだとすれば。
私の予想に頷きを見せながら、先輩は話を続ける。
放送室で起きたこと、物の紛失、
先輩たちの異能の事、敵の異能が先輩たちには手に負えなかったこと、
そしてバツ兄の異能によって、それを切り抜けられたこと。
「ホント助かったよ。俺たちああいうのどうにもできないから……。
でも、一応ってバツに口止めはしたけど、結城さんには言ってると思ってたよ」
「兄は案外、そういう所は律儀なので」
兄は、結んだ約束に嘘はつかない。そういう人だから。
「……だから全然知らなかったとは言え、疑ってしまって申し訳なかったです。
兄と合流できたのも、先輩方のおかげですし。ありがとうございます」
小さく頭を下げる。それから、
「……ちなみに、なんですけど。ハザマで兄と会ったときに、何か変わった様子とかはありませんでしたか?
いえ。……率直に聞くと、兄の事、どう『見え』ましたか」
この問いをするのには、少しの勇気が必要だった。
言葉にすると同時に、達成感よりも、罪悪感に苛まれる。けれど、一度吐いた言葉はもう、飲み込めはしない。
「普段学校で会うのとは、やっぱり全然違ったよ。体調も悪そうだし……。
まあ、聞きたいことはこういう事じゃないんだろうね」
先輩はすぐに、質問の意図をくみ取ってくれた。
「俺がバツと合流したのは、バツの方から連絡が来たからなんだ。
急に飛ばされて、味方とか敵とか全然わからないし、全然見た目も見慣れない人も多い中で……。
あいつは『巳羽を無事に帰したい』っていつも通りに妹を心配してたよ。
絶不調って感じだったし、自分がまず危ないのにね」
「まーなに、俺が異能で観れることって結局表面的っていうか……。
さっき結城さんがあの……名前しらないな。あいつを信用できるって感じたのとそう変わらないんじゃないかな。
俺はバツの言葉を信じてるよ」
言葉を選ぶような間の後に、
『異能』ではなく、その『目』で見て感じたことを、思いを答えてくれる。
真実を示される事よりも曖昧な筈なのに、わたしはそこに、彼の誠実さを感じた。
「……こんな質問をしてしまったから、ばればれだと思うし、酷い話だと思われるかもしれないんですけど。
わたし、兄の事も少しだけ、疑ってしまっていたんです」
その理由を、話す。
『結城伐都を信じるな。結城伐都は裏切り者だ。結城伐都に心を許すな』
ハザマに来て間もなく送られてきた、匿名のメッセージの話を。
「何かの冗談だって笑い飛ばしたい自分も、
別の知り合いがアンジニティとわかって、不安を払拭しきれない自分もいて。
だから、誰かの後押しが、欲しくなってしまって」
『解析』の異能を持つ彼ならば、全てわかるかもしれないと。
寄り掛かってしまおうとした自分を、弱くて未熟だと、思う。
誰かに全てを委ねてしまうことは楽だけれど、後々後悔することになるのは、わかり切っているのに。
「でも、もっと単純に考えて良いんだって、気付けました。
わたしが兄の事をどう見たくて、どうしたいか。それだけで良いって」
真っ先に自分の心配をしてくれたという兄の話と、
彼の言葉を信じてる、という先輩の思いを聞いて、そう思った。
ありがとうございます、と。
吹っ切れたようにつなぐ先輩を見上げると、彼は視線を外し口元を手で押さえていた。
くぐもった呟きが、聞こえる。
「なんか、俺も、結城さんと一緒だったのかも。人に偉そうに言っといてだけど……。
自覚なかったけど友達と家族ってまたちょっと違うね」
言葉の断片から、何となく、彼は彼のお姉さんの話をしているのでは、と思うけれど。
つなぐ先輩から話さない限りは、と、触れずにおくことにした。
「ありがとう、結城さん話せて良かったよ」
「わたしも、つなぐ先輩と話せて良かったです」
互いに、再会したその時よりも、雰囲気が明るくなったように感じた。
少なくとも自分は、なんだか道が開けたような気がしている。
兄の事も、あの男の言う、『己の定義』の事も。
この手ごたえを離したくなくて、刻みつけるように、わたしは手元の石を握りしめていた。
++++++++++++++++++++++++++++
「……つなぐ先輩は、もし自分の知り合いがアンジニティだとしたら、それを知りたいと思いますか」
それは先輩との会話の中で。ザクロ先生がオニキスだったことを告げて良いものか。迷っての問いだった。
打ち明けること。それはつまり、イバラシティでのその人との繋がりが、偽りだったと知る事になる。
だからこそ、その事実を伝えることに、躊躇いがあって。反応を伺うように先輩を見上げた。
「どう……なのかな。……いろいろ言い訳しちゃうんだよ。
こっちの記憶が向こうで意味ないとか、会わなければどちらでもとか……。
結局ビビッて自分から連絡とりに行かなかったりしちゃってたりね」
「まあ、俺の場合解っちゃうから言える我儘かもしれないけど……知りたくなかったなって思うことはあると思うよ」
先輩の言葉に、は。と、息が漏れた。抑える前に、唇が『同じだ』と形を作ってしまう。
「……そう、ですよね。現実に立ち向かえって、ある人は言うんですけど、
自ら進んで知ってまで、立ち向かいに行く必要はないんじゃないかって、わたしは思います。
自衛や、アンジニティと渡り合う為に、積極的に情報を得ようとする人もいるかもしれませんが」
少なくとも自分はまだ、そこまで割り切れそうにない。
今近くにいる、たった一人の存在から思い知らされた現実さえ、未だに飲み込み切れていないのだから。
「そうだね。まー俺もそこまで余裕ないから、今はフタバとリリィと、あと友達の範囲で精いっぱいって感じ」
見えてしまう。見ざるを得ない状況にいるつなぐ先輩なら、尚の事だろうと思う。
だからわたしは、今は先生の事は伏せていようと、そう思った。
「……話繰り返しちゃうけど、さ。
アンジニティでもイバラシティでも、それだけで信用できるできないってことにはならないと思うし、
それだけで警戒する必要があることだとは思う。……気を付けてね」
「……ありがとうございます」
進んで知ろうとしなくても良いと思う。けれど、一度知ってしまった現実には、向き合わなくてはいけないとも思う。
自分で見つめて、考えて、信じたい相手を、心を傾ける度合いを、選んで行く。
それがこのハザマで、この先にある未来で、少しでも、悔いのないように生きるために必要な事なのだろうと。
なんとなく、わかり始めていた。







熾す魂火、絶えぬ火光
|
 |
【Stairwell】ご飯おいしいは正義
|



チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
熾す魂火、絶えぬ火光
|
 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



オニキス(301) に 90 PS 送付しました。
イデオローグ(474) に 90 PS 送付しました。
さき(911) に 90 PS 送付しました。
さき(911) に ItemNo.13 平石 を送付しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
幻術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
リリィ(494) により ItemNo.10 何か固い物体 から防具『新たな祈り』を作製してもらいました!
⇒ 新たな祈り/防具:強さ75/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-
| リリィ 「……少し、雰囲気かわった?」 |
オニキス(301) の持つ ItemNo.11 Apfel に ItemNo.9 針 を付加しました!
さき(911) の持つ ItemNo.12 フリーリィ・スカイシー・ダイブ に ItemNo.11 平石 を付加しました!
ItemNo.10 新たな祈り に ItemNo.14 何か固い物体 を付加しました!
⇒ 新たな祈り/防具:強さ75/[効果1]防御10 [効果2]防御10 [効果3]-
つぼみ(901) とカードを交換しました!
芽吹つぼみのカード (アクアヒール)

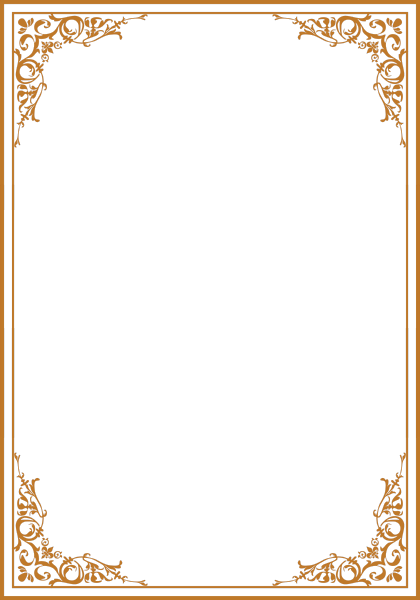
ヘイルカード を研究しました!(深度0⇒1)
ヘイルカード を研究しました!(深度1⇒2)
ヘイルカード を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
ガードフォーム を習得!
リフレッシュ を習得!
アクアシェル を習得!
アンダークーリング を習得!
アクアリカバー を習得!
ヘイルカード を習得!
環境変調耐性 を習得!
ローバスト を習得!
ウィークネス を習得!
プロテクション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



巳羽(473) は 毛 を入手!
イデオローグ(474) は ボロ布 を入手!
オニキス(301) は 毛 を入手!
イデオローグ(474) は ボロ布 を入手!
イデオローグ(474) は 毛 を入手!
オニキス(301) は 毛 を入手!
オニキス(301) は 毛 を入手!
さき(911) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
イデオローグ(474) のもとに 大黒猫 が微笑を浮かべて近づいてきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ほら降りた降りた。次の客が待ってんだわ。」 |
イデオローグ(474) に移動を委ねました。
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 S-8(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 T-8(山岳)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 A-8(山岳)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 B-8(森林)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- オニキス(301) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- イデオローグ(474) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- オニキス(301) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- イデオローグ(474) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)





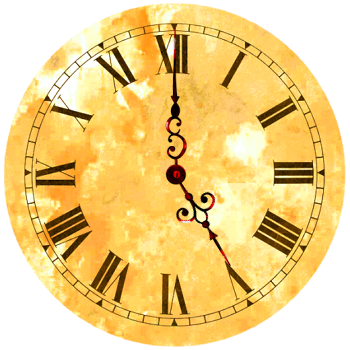
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「ん・・・・・」 |
 |
エディアン 「これは・・・・・」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「なんでしょうこれ!変な情報が映し出されてますねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・つーか何でまた一緒の部屋入ってるんですかね。」 |
 |
エディアン 「いいじゃないですかぁ!案外ヒマじゃないですか?案内役。」 |
 |
白南海 「私はひとりがいいんです、が、ね。」 |
 |
エディアン 「くッッらいですねぇ・・・・・クール気取りですか一匹狼気取りですか、まったく。」 |
 |
白南海 「うっせーオンナが嫌いなだけです。」 |
 |
エディアン 「・・・そういう発言、嫌われますよぉ?」 |
 |
白南海 「貴方も、ね。」 |
 |
エディアン 「――さて、まぁいいとしてこのログ?は何なんですかねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・・・仕方ねぇですね。・・・おーい、クソ妖精ー。」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!ノウレットはいつでも貴方の背後から―――ッ!!」 |
 |
エディアン 「あぁなるほどノウレットちゃん!」 |
 |
エディアン 「・・・っていうかクソ妖精って――」 |
 |
ノウレット 「あだ名をいただいちゃいました☆」 |
 |
白南海 「――ほれ、Cross+Roseに変な情報出てんぞ説明しろ。」 |
 |
ノウレット 「うおおぉぉぉ頼られてます!?もしかして頼られてますッ!!?」 |
ノウレットから遠く離れる白南海。
 |
ノウレット 「どうして離れていくんですッ!!!?」 |
 |
ノウレット 「これはですねぇ!チェックポイント開放者数の情報ですっ!!」 |
 |
エディアン 「えぇえぇ、それはまぁそうかなーとは。右側の1000って数字はなんでしょう? もしかして開放できる人数が限られてる・・・とか?」 |
 |
ノウレット 「いえいえー!開放は皆さんできますよーっ!! これはハザマにいる全員に新たな力を与えるという情報です!!」 |
 |
エディアン 「新たな力・・・?」 |
 |
ノウレット 「そうでぇっす!!各チェックポイントの開放者数が増えるほど、対応する力が強く与えられます! 1000というのは1000人より上は1000人として扱うってことです!!」 |
 |
エディアン 「なるほどなるほど。これ・・・・・敵も味方も、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!全部が全部、ハザマの全員でーす!!」 |
 |
エディアン 「具体的に、どんな力が与えられるんです?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・はーい、大丈夫ですよー。」 |
 |
エディアン 「これは言葉からイメージして実感してみるしかないですかね。 出てくる敵にも力が・・・・・気をつけないといけませんね。」 |
 |
エディアン 「・・・・・白南海さーん!聞きましたよー。」 |
遠く離れた白南海を手招く。
 |
白南海 「――まぁ聞こえていたわけですが。離れても音量変わらなかったわけですが。」 |
 |
エディアン 「・・・ノウレットちゃんの音量調整できますよ?コンフィグで。」 |
 |
白南海 「・・・・・ぁー、よくわかんねぇめんどくせぇ。」 |
 |
エディアン 「まったく、こういうのダメな人ですか。右上のここから・・・ほら、音量設定。あるでしょ。 それから・・・・・あぁ違いますって!それだとチャッ――」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。





ENo.473
結城 巳羽

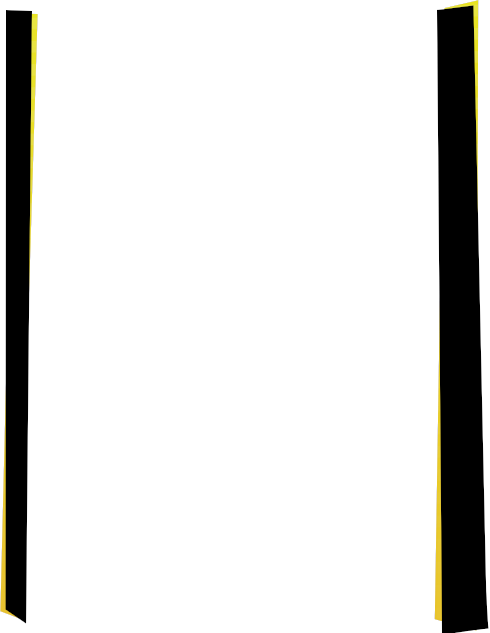
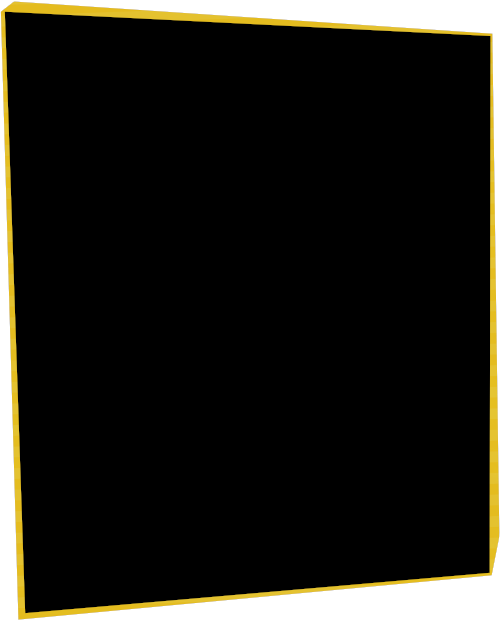
結城 巳羽 ゆうきみう
熾盛天晴学園中等部2年5組に在籍。
身長は155cm。普段から気怠げに目を細めている少女。
制服は規定通り。
鞄も髪型も飾り気がないのは、
溺愛してくる両親から買い与えられる
愛らしいお洋服、小物からの反動。
高等部になったら直ぐにバイトを始め、
自分のお金で服を揃えたいと思っている。
みう、という己の名前も気に入ってはおらず、
学園外では名字を名乗ることが多い。
結城伐都との兄妹仲は良好。呼び方はバツ兄(ばつにい)。
趣味は石集め。
++++++++++++++++++++++++++++
巳羽の異能メモ。
【石に花咲く】
豪腕、鋭敏、跳躍などなど。
石に役割を込め身に付ける事で力を発揮する。
思い入れの深さに依存するため
巳羽がピンときた石にしか効力を発揮しない。
一番のお気に入りの石は、
毎日健康の祈りを込めて、兄に持たせている。
++++++++++++++++++++++++++++++
石拾いのキャラクターイラスト、カード絵は、鴉瓜様に描いて頂きました。
素敵なイラストをありがとうございます。
熾盛天晴学園中等部2年5組に在籍。
身長は155cm。普段から気怠げに目を細めている少女。
制服は規定通り。
鞄も髪型も飾り気がないのは、
溺愛してくる両親から買い与えられる
愛らしいお洋服、小物からの反動。
高等部になったら直ぐにバイトを始め、
自分のお金で服を揃えたいと思っている。
みう、という己の名前も気に入ってはおらず、
学園外では名字を名乗ることが多い。
結城伐都との兄妹仲は良好。呼び方はバツ兄(ばつにい)。
趣味は石集め。
++++++++++++++++++++++++++++
巳羽の異能メモ。
【石に花咲く】
豪腕、鋭敏、跳躍などなど。
石に役割を込め身に付ける事で力を発揮する。
思い入れの深さに依存するため
巳羽がピンときた石にしか効力を発揮しない。
一番のお気に入りの石は、
毎日健康の祈りを込めて、兄に持たせている。
++++++++++++++++++++++++++++++
石拾いのキャラクターイラスト、カード絵は、鴉瓜様に描いて頂きました。
素敵なイラストをありがとうございます。
25 / 30
120 PS
ヒノデ区
B-8
B-8





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 守りの石 | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 最初に拾った石 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | ソーダキャンディ | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | ほしがたちょこ | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 9 | 鉄パイプ | 武器 | 67 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 10 | 新たな祈り | 防具 | 75 | 防御10 | 防御10 | - | |
| 11 | Priere | 装飾 | 40 | 回復10 | - | - | |
| 12 | ブックカバー | 装飾 | 45 | 強靭15 | - | - | |
| 13 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 14 | |||||||
| 15 | 針 | 素材 | 15 | [武器]致命15(LV20)[防具]舞撃15(LV30)[装飾]器用15(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 40 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 6 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| タービュレントブルーム | 5 | 0 | 60 | 敵全:地撃+3D6が15以上ならAT減(2T) | |
| ヒールハーブ | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| クリエイト:グレイル | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 | |
| ホーリーポーション | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 | |
| ピュリフィケーション | 5 | 0 | 50 | 敵味腐:SP増+腐食状態なら、精確光撃&腐食を猛毒化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 薬師 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ビラッディホルン (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
クリエイト:フライング亀 (クリエイト:タライ) |
0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
|
石に花咲く (ヒールハーブ) |
0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
|
沃懸甕 (アクアブランド) |
1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
|
芽吹つぼみのカード (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]デアデビル | [ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 3 ]ヘイルカード |
| [ 3 ]イレイザー | [ 3 ]ストライク |

PL / なっき