<< 3:00~4:00




----------------------
[3rd Trigger ON]
----------------------
――親友に恋人ができた。
僕の親友はそれはもう酷い朴念仁で、誰に対しても悪気なしに口説き落とすとんでもない人だ。
相手となった人も例に漏れず、彼の無自覚な爆弾発言に心を揺さぶられた一人。
そう考えるとついに彼も年貢の納め時を迎えたのだろう。……その人に言われなければ一生自覚しなかったのかもしれないところが恐ろしいけど。
嬉しかった。
親友に幸せが訪れたことが。
自分なんていなくなればいいといつも言っていた彼をここに繋ぎ止めてくれる人が、できたことが。
きっとこれは彼にとって良い方向に働くだろう、そう確信した。
必要としてくれる人が身近にいることで、きっと彼の心を覆った氷は溶けていくだろう。
……そう、思っている。
それに間違いはない。この気持ちは嘘なんかじゃ決してない。
なのに。
なのに何で、こんなに胸が苦しいんだろう。
喜ばしいことなのに。
大事な親友のことなんだ、僕も自分のことのように嬉しい、それは確かなのに。
――何で、彼が別の人と結ばれたことが羨ましいのか、妬ましいのか。
何故そこにいるのが僕でないことが悔しいのだろう。
そんな感情を抱いてはいけないハズなのに。
……胸が苦しい。痛い。
然程の痛みではないのに、じわじわと脈打つように広がっていく。
これなら"蠱毒"の代償で血を吐いた方が遥かにマシだ。何でこんな気持ちが僕の中にあるのだろう……?
自問したところでわかっている。
僕が異常なんだ。彼に隣にいるのは僕だけでいいなんてバカげたことを考えて。
彼の笑顔も、優しさも、全て独り占めしたい――なんて傲慢な考えだろうか。
きっとこれだけならただの嫉妬深いだけの人間で済んだのだろう。
でもそうじゃない。
僕はこのような感情を、僕に接してくれる全ての人に等しく抱いている。
おかしい、気が狂っている以上の相応しい表現は見つからない。
親友にも。
彼の恋人にも。
兄のような人にも。
具現使いのあの子にも。
夕焼けのような暖かい彼にも――
僕を見て欲しい。ずっと、ずうっと……
僕から目を離して欲しくない。その為ならどんなことだっていとわない。
そう、例えば痛みで支配することだって――
そんなことを考えている、どうしようもない外道が僕だ。
本当は親友の隣などふさわしくも何ともない。むしろ日の目すら浴びるべきではない。ああ、なんて浅ましく汚らわしい存在か。
心の中で声がする。
また一人、感情の首を刎ねる。
二人。
三人。
四人。
五人。
<LEFT>――――違わないよ。散々殺してきたんだもの。今更血を拭えるなんて思ってないよね?
――――ねえ?
足を何かが掴む。
今まで僕が殺してきた感情の群れが、沼に引きずり込もうと笑っている。
目のえぐれた顔が、頬の削れた顔が、一斉ににたりと笑って血まみれの手で引っ張って――
「ああああああああああぁああああああああああああああああッッ!!!!!!!!!!!!!!!!!」
蒼い稲妻がそれらを消し去り、声が止む。
「はあっ……はっ……は、あ……っう」
激しい痛みと共に血が喉を駆け上がる。
地面に落ちた紅い雫が滴る度、先程の感情の死体たちを見せつけるような気がして少し寒気がする。
「……違う、僕は……僕は……」
僕は、人だ。人でなくてはいけないんだ。
でなければ、僕に課せられた任を果たすことが――
「……釣れないじゃないか。せっかく可愛い甥が悩んでいるのを何とかしてあげようと思ったのに」
背後から女性の声が聞こえた瞬間、先程から感じていた寒気がより明確に感じられる。
その声はかつての面影を残しながらも酷く狂気的で……自分を保っていなければすぐにどうにかなってしまいそうな程の"圧"があった。
恐る恐る後ろを振り向く。
そこには僕と同じ、夜の帳のような色の髪をした女性が。
……僕が、今までずっと追いかけてきた人物。彼女が、そこ に
「……旭日、伯母さん」
「久しぶりだね日明。随分と大きくなったじゃないか」
【To be Continued.】



ENo.9 タマキ とのやりとり

ENo.19 翠眼の怪物 とのやりとり

ENo.180 ちわわ とのやりとり

ENo.271 八生 とのやりとり

ENo.284 フェル とのやりとり

ENo.290 玲 とのやりとり

ENo.546 不幸喰らい とのやりとり

ENo.562 スグル とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。












六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



甲斐中(221) に 15 PS 送付しました。
幻術LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
甲斐中(221) により ItemNo.1 ネジ から射程3の武器『マグネート・クリンゲ』を作製してもらいました!
⇒ マグネート・クリンゲ/武器:強さ75/[効果1]貫撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
菫(450) とカードを交換しました!
守護天使 (チャージ)

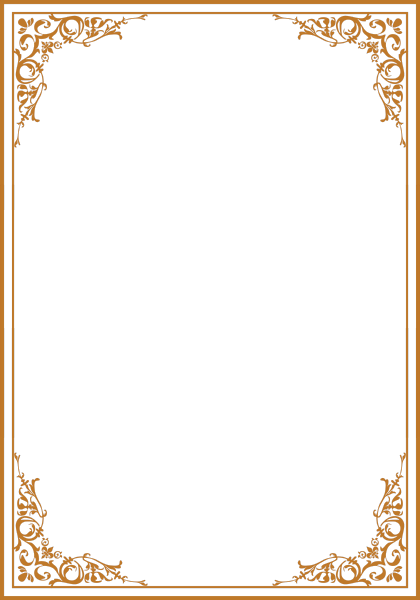
☆レーザービーム を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



リカルド(28) は ド根性雑草 を入手!
八生(271) は ド根性雑草 を入手!
日明と月夜(285) は ド根性雑草 を入手!
冷泉といちか(533) は 雑木 を入手!
八生(271) は 毛 を入手!
八生(271) は 毛 を入手!
日明と月夜(285) は 毛 を入手!
八生(271) は 花びら を入手!
日明と月夜(285) は 皮 を入手!
冷泉といちか(533) は 皮 を入手!
日明と月夜(285) は 皮 を入手!
冷泉といちか(533) は 皮 を入手!



チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- リカルド(28) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 日明と月夜(285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 冷泉といちか(533) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION - 未発生:
- 日明と月夜(285) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(同行者が達成済み)
- 冷泉といちか(533) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(同行者が達成済み)





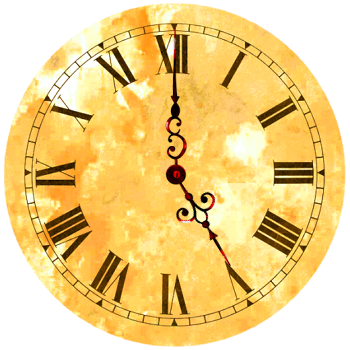
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。

ノウレットから遠く離れる白南海。
遠く離れた白南海を手招く。
チャットが閉じられる――







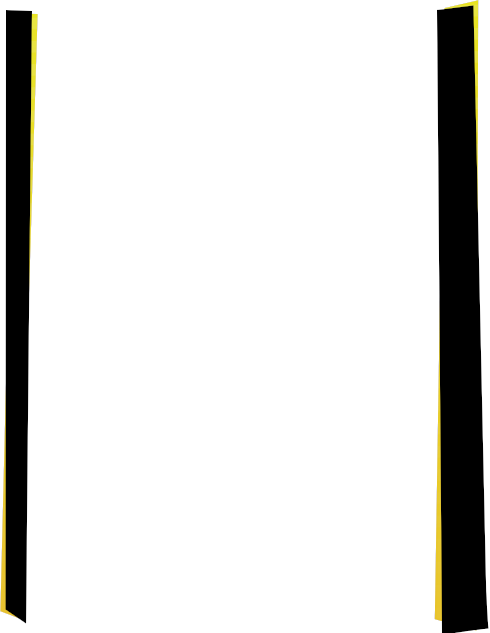
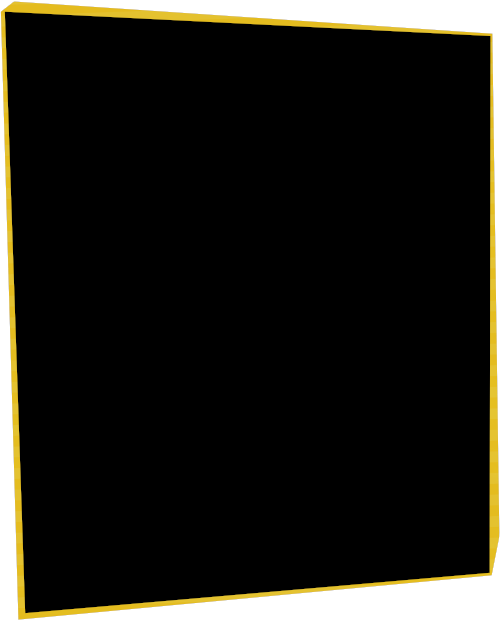





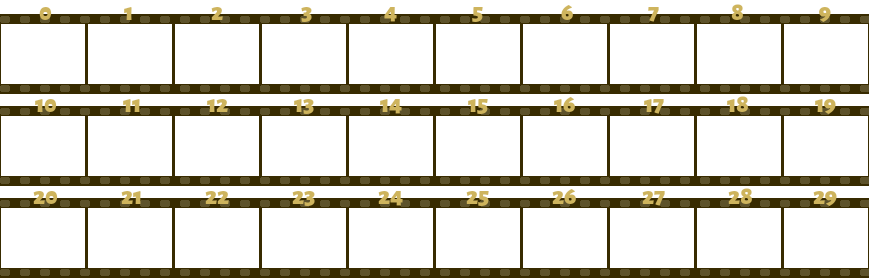







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



----------------------
[3rd Trigger ON]
----------------------
――親友に恋人ができた。
僕の親友はそれはもう酷い朴念仁で、誰に対しても悪気なしに口説き落とすとんでもない人だ。
相手となった人も例に漏れず、彼の無自覚な爆弾発言に心を揺さぶられた一人。
そう考えるとついに彼も年貢の納め時を迎えたのだろう。……その人に言われなければ一生自覚しなかったのかもしれないところが恐ろしいけど。
嬉しかった。
親友に幸せが訪れたことが。
自分なんていなくなればいいといつも言っていた彼をここに繋ぎ止めてくれる人が、できたことが。
きっとこれは彼にとって良い方向に働くだろう、そう確信した。
必要としてくれる人が身近にいることで、きっと彼の心を覆った氷は溶けていくだろう。
……そう、思っている。
それに間違いはない。この気持ちは嘘なんかじゃ決してない。
なのに。
なのに何で、こんなに胸が苦しいんだろう。
喜ばしいことなのに。
大事な親友のことなんだ、僕も自分のことのように嬉しい、それは確かなのに。
――何で、彼が別の人と結ばれたことが羨ましいのか、妬ましいのか。
何故そこにいるのが僕でないことが悔しいのだろう。
そんな感情を抱いてはいけないハズなのに。
……胸が苦しい。痛い。
然程の痛みではないのに、じわじわと脈打つように広がっていく。
これなら"蠱毒"の代償で血を吐いた方が遥かにマシだ。何でこんな気持ちが僕の中にあるのだろう……?
自問したところでわかっている。
僕が異常なんだ。彼に隣にいるのは僕だけでいいなんてバカげたことを考えて。
彼の笑顔も、優しさも、全て独り占めしたい――なんて傲慢な考えだろうか。
きっとこれだけならただの嫉妬深いだけの人間で済んだのだろう。
でもそうじゃない。
僕はこのような感情を、僕に接してくれる全ての人に等しく抱いている。
おかしい、気が狂っている以上の相応しい表現は見つからない。
親友にも。
彼の恋人にも。
兄のような人にも。
具現使いのあの子にも。
夕焼けのような暖かい彼にも――
僕を見て欲しい。ずっと、ずうっと……
僕から目を離して欲しくない。その為ならどんなことだっていとわない。
そう、例えば痛みで支配することだって――
そんなことを考えている、どうしようもない外道が僕だ。
本当は親友の隣などふさわしくも何ともない。むしろ日の目すら浴びるべきではない。ああ、なんて浅ましく汚らわしい存在か。
――――いいじゃない。一つぐらいわがままを言ったって。
心の中で声がする。
…………黙れ。
また一人、感情の首を刎ねる。
――――何でさ。今まで我慢したじゃない。
…………それが当たり前だからだ。
二人。
――――今までロクに見てもらえなかったんだからこれぐらいいいじゃないか。
…………それならこんなに人に恵まれてはいないんだ。
三人。
――――でも足りないんでしょう?
…………彼らは僕の所有物じゃない。
四人。
――――いっそのこと奪ってしまおうよ。そうしたら悩まなくて済む。
…………そんなこと許されるワケがないだろう?
五人。
――――奪って、閉じ込めて、僕だけしか見えないようにしてしまえばきっと満足できるよ。
…………黙れと言っているだろう。
――――ホントはそれを一番望んでいる癖に。
…………違う。
――――あの人たちが見てくれるなら、何だってできるのにね。殺しだって自殺だって、それこそ足開くのだって喜んでさ。
違う!
――――何が違うの?今更綺麗な顔装ったって無駄だよ。これが本当の僕じゃないか。
違う!!
<LEFT>――――違わないよ。散々殺してきたんだもの。今更血を拭えるなんて思ってないよね?
違う!!!!
――――ねえ?
足を何かが掴む。
今まで僕が殺してきた感情の群れが、沼に引きずり込もうと笑っている。
イ マ サ ラ ニ ン ゲ ン ヅ ラ デ キ ル ト オ モ ウ ナ ヨ ?
目のえぐれた顔が、頬の削れた顔が、一斉ににたりと笑って血まみれの手で引っ張って――
「ああああああああああぁああああああああああああああああッッ!!!!!!!!!!!!!!!!!」
蒼い稲妻がそれらを消し去り、声が止む。
「はあっ……はっ……は、あ……っう」
激しい痛みと共に血が喉を駆け上がる。
地面に落ちた紅い雫が滴る度、先程の感情の死体たちを見せつけるような気がして少し寒気がする。
「……違う、僕は……僕は……」
僕は、人だ。人でなくてはいけないんだ。
でなければ、僕に課せられた任を果たすことが――
「……釣れないじゃないか。せっかく可愛い甥が悩んでいるのを何とかしてあげようと思ったのに」
背後から女性の声が聞こえた瞬間、先程から感じていた寒気がより明確に感じられる。
その声はかつての面影を残しながらも酷く狂気的で……自分を保っていなければすぐにどうにかなってしまいそうな程の"圧"があった。
恐る恐る後ろを振り向く。
そこには僕と同じ、夜の帳のような色の髪をした女性が。
……僕が、今までずっと追いかけてきた人物。彼女が、そこ に
「……旭日、伯母さん」
「久しぶりだね日明。随分と大きくなったじゃないか」
【To be Continued.】



ENo.9 タマキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.19 翠眼の怪物 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.180 ちわわ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.271 八生 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.284 フェル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.290 玲 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.546 不幸喰らい とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.562 スグル とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。





立ちはだかるもの
|
 |
少女と青年と愉快な同行者たち
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
少女と青年と愉快な同行者たち
|
 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



甲斐中(221) に 15 PS 送付しました。
幻術LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
甲斐中(221) により ItemNo.1 ネジ から射程3の武器『マグネート・クリンゲ』を作製してもらいました!
⇒ マグネート・クリンゲ/武器:強さ75/[効果1]貫撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
 |
甲斐中 「ご注文の品、お届けにきましたーーーー!!!」 |
菫(450) とカードを交換しました!
守護天使 (チャージ)

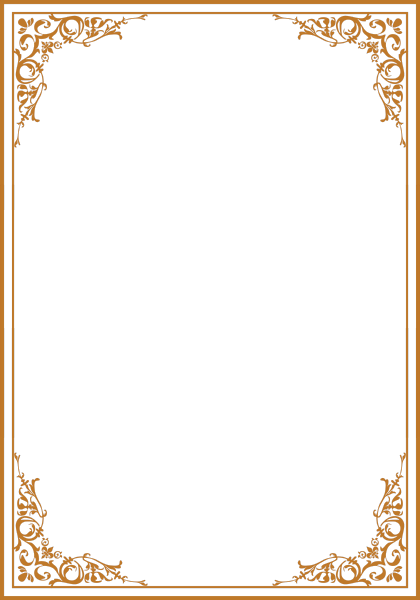
☆レーザービーム を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



リカルド(28) は ド根性雑草 を入手!
八生(271) は ド根性雑草 を入手!
日明と月夜(285) は ド根性雑草 を入手!
冷泉といちか(533) は 雑木 を入手!
八生(271) は 毛 を入手!
八生(271) は 毛 を入手!
日明と月夜(285) は 毛 を入手!
八生(271) は 花びら を入手!
日明と月夜(285) は 皮 を入手!
冷泉といちか(533) は 皮 を入手!
日明と月夜(285) は 皮 を入手!
冷泉といちか(533) は 皮 を入手!



チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- リカルド(28) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 日明と月夜(285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 冷泉といちか(533) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION - 未発生:
- 日明と月夜(285) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(同行者が達成済み)
- 冷泉といちか(533) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(同行者が達成済み)





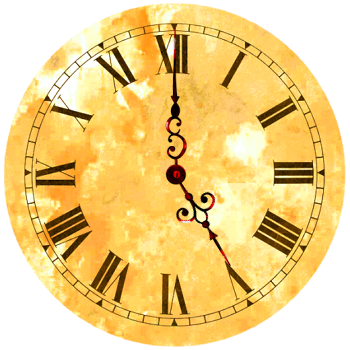
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「ん・・・・・」 |
 |
エディアン 「これは・・・・・」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「なんでしょうこれ!変な情報が映し出されてますねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・つーか何でまた一緒の部屋入ってるんですかね。」 |
 |
エディアン 「いいじゃないですかぁ!案外ヒマじゃないですか?案内役。」 |
 |
白南海 「私はひとりがいいんです、が、ね。」 |
 |
エディアン 「くッッらいですねぇ・・・・・クール気取りですか一匹狼気取りですか、まったく。」 |
 |
白南海 「うっせーオンナが嫌いなだけです。」 |
 |
エディアン 「・・・そういう発言、嫌われますよぉ?」 |
 |
白南海 「貴方も、ね。」 |
 |
エディアン 「――さて、まぁいいとしてこのログ?は何なんですかねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・・・仕方ねぇですね。・・・おーい、クソ妖精ー。」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!ノウレットはいつでも貴方の背後から―――ッ!!」 |
 |
エディアン 「あぁなるほどノウレットちゃん!」 |
 |
エディアン 「・・・っていうかクソ妖精って――」 |
 |
ノウレット 「あだ名をいただいちゃいました☆」 |
 |
白南海 「――ほれ、Cross+Roseに変な情報出てんぞ説明しろ。」 |
 |
ノウレット 「うおおぉぉぉ頼られてます!?もしかして頼られてますッ!!?」 |
ノウレットから遠く離れる白南海。
 |
ノウレット 「どうして離れていくんですッ!!!?」 |
 |
ノウレット 「これはですねぇ!チェックポイント開放者数の情報ですっ!!」 |
 |
エディアン 「えぇえぇ、それはまぁそうかなーとは。右側の1000って数字はなんでしょう? もしかして開放できる人数が限られてる・・・とか?」 |
 |
ノウレット 「いえいえー!開放は皆さんできますよーっ!! これはハザマにいる全員に新たな力を与えるという情報です!!」 |
 |
エディアン 「新たな力・・・?」 |
 |
ノウレット 「そうでぇっす!!各チェックポイントの開放者数が増えるほど、対応する力が強く与えられます! 1000というのは1000人より上は1000人として扱うってことです!!」 |
 |
エディアン 「なるほどなるほど。これ・・・・・敵も味方も、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!全部が全部、ハザマの全員でーす!!」 |
 |
エディアン 「具体的に、どんな力が与えられるんです?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・はーい、大丈夫ですよー。」 |
 |
エディアン 「これは言葉からイメージして実感してみるしかないですかね。 出てくる敵にも力が・・・・・気をつけないといけませんね。」 |
 |
エディアン 「・・・・・白南海さーん!聞きましたよー。」 |
遠く離れた白南海を手招く。
 |
白南海 「――まぁ聞こえていたわけですが。離れても音量変わらなかったわけですが。」 |
 |
エディアン 「・・・ノウレットちゃんの音量調整できますよ?コンフィグで。」 |
 |
白南海 「・・・・・ぁー、よくわかんねぇめんどくせぇ。」 |
 |
エディアン 「まったく、こういうのダメな人ですか。右上のここから・・・ほら、音量設定。あるでしょ。 それから・・・・・あぁ違いますって!それだとチャッ――」 |
チャットが閉じられる――



裏切り者は狭間の夢を見るか
|
 |
ハザマに生きるもの
|


ENo.285
《夜明け》と《黄昏》

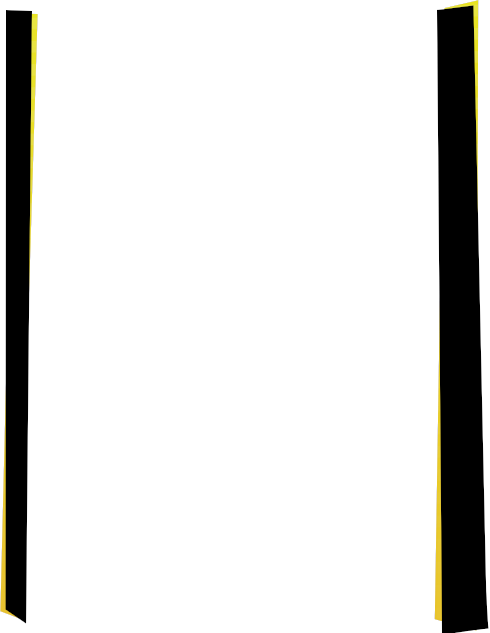
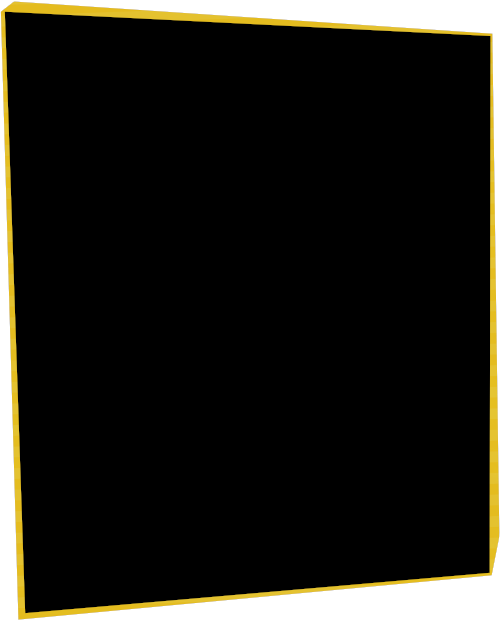
※前期と"全く同じ過程を経ている"という設定なので前期で交流のあった人には割と軽率に絡みにいく可能性がございます。
ダメな人は先に言うてね!!!!!!※
※ほんのりどころではないBL表現があります。苦手な人は回れ右してBACK推奨。※
「あんたらに恨みは一切ないが――」
「人々の日常を脅かす者は、我らが組織の名の下に制裁します」
一般の学生(とフリーター)を装う異能力者野郎二人組。
幼少の頃に「"異物"が混ざる」ことで人ならざる力に目覚め、
組織に保護されコントロール方法や戦闘訓練を徹底的に
施された「チルドレン」と呼ばれる少年兵、あるいは工作員。
組織については基本秘匿事項のため知らない人には話さない。
……同業相手なら話は別だけど。尚人体実験とかそういう
非人道的物騒な教育背景はこの二人に限っては存在しない。
戦闘、探索ではコードネームを用いる。
ツクナミ区中心に活動中、任務の為にイバラシティにやってきたらしくとある女性を探しているのだとか。
○《夜明けの裁断者(オルトロス)》終夜日明(よすがら-あきら)
18歳/170cm 一人称「僕」
青髪の方。物静かで物腰柔らか、誰にでも親切で温厚な性格。
常に相手と一定の距離を置き感情をあまり表に出さないため
よそよそしい印象を与えがち。しかして別に人見知りだったり
人嫌いだったりとかそんなことは全くなく、昔の経験から
"繋がりを自分から作ること"においては半ば諦めているだけ、
早い話がめちゃくちゃ受動的。仲良くしようと距離を詰めて
くる人は拒絶しないし話を聞くのは大好き、人付き合いは
かなり良い方。何だかんだ年相応の少年。
月夜は数少ない友人であり一番の親友でありかつ一番の相棒。
強い信頼を置いているが、何かと無茶しがちな彼をかなり心配している。
普段は現役高校生として相良伊橋高校に通っている。2年4組
放課後は異能総合格闘部での部活動か「Tea&Pub ティールマイト(http://lisge.com/ib/talk.php?p=245)」であるバイトをしている。
【異能】
《猛り立つ霹靂(ジヴェルス・イウルドス)》
雷を操る能力。電磁力による金属引き寄せや反発作用による引き剥がしはたまたイオンクラフト効果による飛行やら割と何でもできる。
副次効果で機械系や電子情報系にめっちゃ強い。
《蠱毒》
異物特効能力、同族殺しの特性。対異物混じりでの異能攻撃の殺傷力が極めて高くなる。
代償として自身も■■の対象として体内を食い荒らされる為長くは生きられない(延命手段は存在する)。
●《黄昏の射手(クレピュスキュール》終日月夜(ひすがら-つきや)
19歳/180cm 一人称「俺」
赤髪の方。明るく人懐こい性格で良く言えば困っている人を
見れば手を差しのべたがるお人好し、
悪く言えば死に急ぎレベルの自己犠牲精神の持ち主。
思ったことはすぐ口に出すし嘘が全くつけない上に口を滑らし
やすいという良くも悪くも自分に正直な性分でそっちの適正はゼロ。工作員の癖に。
反面戦闘及び索敵能力は非常に高く大人顔負けの実力の
持ち主。サーチ&デストロイを地で行くスタイルで足も速い。
考えるより先に動きがちで先走って諌められることも多いが、
その明るさと力で日明を支える良き相棒である。
見た目に反して家事炊事が得意。
普段は「Tea&Pub ティールマイト」でアルバイトをしている。
Eno.19の方と恋仲になりました。
【異能】
《陽炎輪舞(ロンド・オブ・ミラージュ)》
光を操る能力。目眩ましやレーザー攻撃以外にも屈折率を弄って姿を消したりもできる。副次効果として五感が常人の何倍も鋭くなる。
《我想錬成(アルケミー・イズ・マイン)》
物質錬成能力。元あるものを作り変えることもできれば無から有を生み出すこともできる。食べ物も作れるよ。ドッグフードも出せる。
基本的にこれで手持ちのサバイバルナイフを銃に錬成して戦う。
《贄》
月夜に混ざっている異物の特性。「月夜が攻撃、あるいは危害を加えると認識した行動」に対して因果レベルで干渉し対象を全て自分に移し替えることができる。
あくまでターゲットを移し替えるだけでありそこから防いだり回避したりは本人の度量に左右される。
【サブキャラクター】
○《求道者(エア)》ルキュリヤ・カナリヤ (Lkyria Canaria)
女性/見た目20代後半/169cm 一人称「私」
雲林園荘の管理人兼組織の研究班及び医療班兼任エージェント。
研究者の割にはさっぱりとした性格で面倒くさがりな傾向があるが何だかんだで面倒見の良い大人の女性。
【異能】
《次元干渉者(ディメンジョナル・シンギュラリティ》
時空間操作能力。四次元ポケットとかどこでもドアとか。重力や斥力の操作も可能。
《変毒為薬/変薬為毒(ギフト・オア・ギフト)》
化学物質精製能力。文字通り薬にもできるし毒にもでき精神干渉も行うことが可能。どっちかっていうと支援型の異能。
●プレイスとか
雲林園荘:203号室 http://lisge.com/ib/talk.php?p=691
雲林園荘:000号室 http://lisge.com/ib/talk.php?p=692
○各著作権
虚無アイコンはEno.180PL様作。あとは自作。
※RPについての注意事項
メタだろうがなんだろうが軽率に喋ります。
なのでよっぽどのことじゃなけりゃ何でも許容します。
プレイスRPにつきましては背後が不定休職につき置きレス遅レスが大量発生しますのでお早めの返信をご希望の方は
お手数ですが@UtA_kAtA_sA_yAまでリプライお願いします。
【RPイベント:END OF ENDLESS NIGHT】
――終夜に終止符を。
彼ら二人の探している者とは"異物混じり"の成れの果てであり、その中でも最も危険性の高いと言われる対象。
その討伐が彼らに与えられた任務である。現在標的はイバラシティに潜伏しておりあらゆる手を使って情報を洗っているが、
未だその足取りは掴めていない……
RPイベントを第一回更新後から開始するよ!テストプレイ時から進行値は継続です。
進行値は更新日の末尾と別途プレイス(http://lisge.com/ib/talk.php?p=701)でのダイス判定に対応した出目によって1~3、更新される毎に加算されます。
現在進行値:83 【トリガー起動したので遠くないうちにイベント開始します】
ダメな人は先に言うてね!!!!!!※
※ほんのりどころではないBL表現があります。苦手な人は回れ右してBACK推奨。※
「あんたらに恨みは一切ないが――」
「人々の日常を脅かす者は、我らが組織の名の下に制裁します」
一般の学生(とフリーター)を装う異能力者野郎二人組。
幼少の頃に「"異物"が混ざる」ことで人ならざる力に目覚め、
組織に保護されコントロール方法や戦闘訓練を徹底的に
施された「チルドレン」と呼ばれる少年兵、あるいは工作員。
組織については基本秘匿事項のため知らない人には話さない。
……同業相手なら話は別だけど。尚人体実験とかそういう
非人道的物騒な教育背景はこの二人に限っては存在しない。
戦闘、探索ではコードネームを用いる。
ツクナミ区中心に活動中、任務の為にイバラシティにやってきたらしくとある女性を探しているのだとか。
○《夜明けの裁断者(オルトロス)》終夜日明(よすがら-あきら)
18歳/170cm 一人称「僕」
青髪の方。物静かで物腰柔らか、誰にでも親切で温厚な性格。
常に相手と一定の距離を置き感情をあまり表に出さないため
よそよそしい印象を与えがち。しかして別に人見知りだったり
人嫌いだったりとかそんなことは全くなく、昔の経験から
"繋がりを自分から作ること"においては半ば諦めているだけ、
早い話がめちゃくちゃ受動的。仲良くしようと距離を詰めて
くる人は拒絶しないし話を聞くのは大好き、人付き合いは
かなり良い方。何だかんだ年相応の少年。
月夜は数少ない友人であり一番の親友でありかつ一番の相棒。
強い信頼を置いているが、何かと無茶しがちな彼をかなり心配している。
普段は現役高校生として相良伊橋高校に通っている。2年4組
放課後は異能総合格闘部での部活動か「Tea&Pub ティールマイト(http://lisge.com/ib/talk.php?p=245)」であるバイトをしている。
【異能】
《猛り立つ霹靂(ジヴェルス・イウルドス)》
雷を操る能力。電磁力による金属引き寄せや反発作用による引き剥がしはたまたイオンクラフト効果による飛行やら割と何でもできる。
副次効果で機械系や電子情報系にめっちゃ強い。
《蠱毒》
異物特効能力、同族殺しの特性。対異物混じりでの異能攻撃の殺傷力が極めて高くなる。
代償として自身も■■の対象として体内を食い荒らされる為長くは生きられない(延命手段は存在する)。
●《黄昏の射手(クレピュスキュール》終日月夜(ひすがら-つきや)
19歳/180cm 一人称「俺」
赤髪の方。明るく人懐こい性格で良く言えば困っている人を
見れば手を差しのべたがるお人好し、
悪く言えば死に急ぎレベルの自己犠牲精神の持ち主。
思ったことはすぐ口に出すし嘘が全くつけない上に口を滑らし
やすいという良くも悪くも自分に正直な性分でそっちの適正はゼロ。工作員の癖に。
反面戦闘及び索敵能力は非常に高く大人顔負けの実力の
持ち主。サーチ&デストロイを地で行くスタイルで足も速い。
考えるより先に動きがちで先走って諌められることも多いが、
その明るさと力で日明を支える良き相棒である。
見た目に反して家事炊事が得意。
普段は「Tea&Pub ティールマイト」でアルバイトをしている。
Eno.19の方と恋仲になりました。
【異能】
《陽炎輪舞(ロンド・オブ・ミラージュ)》
光を操る能力。目眩ましやレーザー攻撃以外にも屈折率を弄って姿を消したりもできる。副次効果として五感が常人の何倍も鋭くなる。
《我想錬成(アルケミー・イズ・マイン)》
物質錬成能力。元あるものを作り変えることもできれば無から有を生み出すこともできる。食べ物も作れるよ。ドッグフードも出せる。
基本的にこれで手持ちのサバイバルナイフを銃に錬成して戦う。
《贄》
月夜に混ざっている異物の特性。「月夜が攻撃、あるいは危害を加えると認識した行動」に対して因果レベルで干渉し対象を全て自分に移し替えることができる。
あくまでターゲットを移し替えるだけでありそこから防いだり回避したりは本人の度量に左右される。
【サブキャラクター】
○《求道者(エア)》ルキュリヤ・カナリヤ (Lkyria Canaria)
女性/見た目20代後半/169cm 一人称「私」
雲林園荘の管理人兼組織の研究班及び医療班兼任エージェント。
研究者の割にはさっぱりとした性格で面倒くさがりな傾向があるが何だかんだで面倒見の良い大人の女性。
【異能】
《次元干渉者(ディメンジョナル・シンギュラリティ》
時空間操作能力。四次元ポケットとかどこでもドアとか。重力や斥力の操作も可能。
《変毒為薬/変薬為毒(ギフト・オア・ギフト)》
化学物質精製能力。文字通り薬にもできるし毒にもでき精神干渉も行うことが可能。どっちかっていうと支援型の異能。
●プレイスとか
雲林園荘:203号室 http://lisge.com/ib/talk.php?p=691
雲林園荘:000号室 http://lisge.com/ib/talk.php?p=692
○各著作権
虚無アイコンはEno.180PL様作。あとは自作。
※RPについての注意事項
メタだろうがなんだろうが軽率に喋ります。
なのでよっぽどのことじゃなけりゃ何でも許容します。
プレイスRPにつきましては背後が不定休職につき置きレス遅レスが大量発生しますのでお早めの返信をご希望の方は
お手数ですが@UtA_kAtA_sA_yAまでリプライお願いします。
【RPイベント:END OF ENDLESS NIGHT】
――終夜に終止符を。
彼ら二人の探している者とは"異物混じり"の成れの果てであり、その中でも最も危険性の高いと言われる対象。
その討伐が彼らに与えられた任務である。現在標的はイバラシティに潜伏しておりあらゆる手を使って情報を洗っているが、
未だその足取りは掴めていない……
RPイベントを第一回更新後から開始するよ!テストプレイ時から進行値は継続です。
進行値は更新日の末尾と別途プレイス(http://lisge.com/ib/talk.php?p=701)でのダイス判定に対応した出目によって1~3、更新される毎に加算されます。
現在進行値:83 【トリガー起動したので遠くないうちにイベント開始します】
30 / 30
257 PS
チナミ区
D-2
D-2






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | マグネート・クリンゲ | 武器 | 75 | 貫撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 4 | 百の手銃 | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | ヘアピン | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV10)[効果2]充填10(LV20)[効果3]増幅10(LV30) | |||
| 9 | クリームカラージャケット | 法衣 | 20 | 敏捷10 | 体力10 | 幸運6 | |
| 10 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 11 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 20 | 夢幻/精神/光 |
| 解析 | 20 | 精確/対策/装置 |
| 防具 | 40 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| プレスト・エギーユ (クイック) | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| エクレール・プファイル (ライトニング) | 6 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| CrCODE:ホークビジョン (エチュード) | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| アトラクト | 5 | 0 | 50 | 自:HATE・連続増 | |
| ブリュム・ドゥ・シャルール (レイ) | 5 | 0 | 30 | 敵貫:盲目 | |
| ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ブリッツ・ロンギヌス (ライトジャベリン) | 6 | 0 | 150 | 敵貫3:光痛撃 | |
| インディグネイトディスチャージ (リンクブレイク) | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| CuCODE:ハルシネイトレイ (カレイドスコープ) | 6 | 0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
| ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |
| レーザービーム | 5 | 0 | 300 | 敵貫:光領撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| インストーリング (猛攻) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| CrCODE:デルタイーグル (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| スタンバイ・ステップ (隠者) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 光の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
| CrCODE:イーグルビジョン (白虹貫日) | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:発動する「敵貫」を強化 | |
| 法衣作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で防具「法衣」を選択できる。法衣は効果3に幸運LVが付加される。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
癒しの力 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
慈悲の天輪 (マナポーション) |
0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
|
癒やしの願い (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
猟犬の一撃 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
守護天使 (チャージ) |
0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]グランドクラッシャー |

PL / 御巫咲絢





























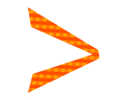














.png)

