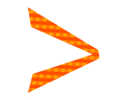<< 3:00~4:00




「──得体の知れないあやかし?」
復唱して訊き返す、稲穂の女。
無言で頷く黒髪の童女。その主張を補うように、背後に控えた大蛇が言葉を発する。
「イバラシティの者もアンジニティの者も見境なしに、弱いものから順に襲われ喰われているようだ。 旧きもののにおいはするが、我らにも一切心当たりが無い。
厭な気配だ。葛の君の判断を仰ぐと、さとりが申しておる。」
「葛子さま。あさなたちは、葛子さまの命に随います。」
縁あるモノたち。“街”では家族も同然の、あやかしたち。
「そなたらは、それでよいのか? そちらの陣営での立場は悪くならんか?」
「ふん。もとより群れだって行動するような輩の集まりではない。
秩序などというものがあるなら、初めからアンジニティなんぞには堕とされん。誰がどう勝手に動こうが、頓着はすまい。
そも我らはだな、葛の君よ。そなたが現世(そちら)に残ったからこそ、安心してこの大平の世からの三行半を甘んじて受けたのだ。ならば我らあやかし、そなたの手足となって動くのが道理であろうが。」
心配げな葛子の言葉をにべもなく一蹴し、そんなことより、とおろちは続ける。
「先も言ったが、件のあやかしからは厭なにおいがする。あれらの痕跡を辿れば、いつかはそなたの宿敵に行き着くやもしれんぞ。」
同胞の言葉。アンジニティでありながら葛子にしたがおうとする彼らの意思は、堅いものである。
「……みんな、同じ思いです。葛子さま。 あさなたちはあやかし。他者の決めた彼我の区切りに付き合うつもりも、イバラシティを欲するつもりもありません。」
幼い姿の、真っ直ぐなまなざし。
葛子は迷わず、頷いた。迷えるはずもない。
「分かった。そなたらの助け、遠慮無く借りるぞ。」
それは、滅ぶものたちからの餞別でもあるのだから。
▲▼
チナミ区、J-16番地。
首を回せば湖がすぐ近くに見え、軽く寄せる波の音がする。
水は濁った鈍色で、湖岸の砂利には暗緑色のヘドロがこびりついている。普段のチナミ湖からは想像もできない景色。
湖の向こうには梅楽園が見える。明かりは点いており、荒廃し薄暗いハザマの中で奇妙なほどに華やかであった。
それはまるで、宵闇に倦み疲れたものを引き寄せる、誘蛾灯のように。
「よかったのか、あの者らに事のあらましを伝えずして。」
おろちの言葉に、葛子は頷く。
「タマーニ殿に、うさもり殿たちのことかえ? それならば、うむ。
なにも知らぬ彼女らを、この怨嗟と呪いの只中へと引き込むことはできぬ。」
葛子とおろち、それにあさなは、湖畔に敷設された道路を歩いていた。
アスファルトは長い間整備されていないかのようにひび割れ、至る所から雑草が暗緑色の葉を伸ばしている。
あやかし達が感じたにおいのうち、最も近場であったのが此処、チナミ湖であった。
葛子の返答に、おろちは鼻を鳴らした。
「それはそなたのやり方ではなかろう。ヒトを繋ぎ、ヒトと繋がり、頼り頼られ生きるのがそなたであるぞ。仔を想うばかりに、庇護の仕方を間違えるのは──」
「葛子さま、おろちさま。あそこ……!」
発されたあさなの声に、二人は言葉を止める。
湖の一角に渡された、小さな木造の橋。その中央に、人影があったのだ。
「臭うな。どうやらたどり着いたようだぞ。」
「うっ……。」
あさなが鼻を押さえ、眉をしかめる。強烈な死臭と怨嗟のにおい。
橋の上の影が、その口を三日月の形に曲げて嗤った。
「──あは、あは、あは。」
腕を上げ、指をさす。葛子に向けられたそれとの間に、あさなが立ち塞がる。
「たすけて、きつねのかみ。」
か細い女の声とともに、ごぼり、と水の詰まるような音が鳴った。ぺたりと頬に張り付いた黒髪。ぐっしょりと濡れそぼった衣服から、ぽたぽたと落ちる水のしずく。
おろちが鎌首をもたげ、「同情を引ける相手と思っているのか?」と唸る。
「たすけて、たすけ──」
ごぼり、ごぼ、ごぼ。ばしゃばしゃと水音。
女は水を吐く。薄緑色の水がさばさばと橋の傾斜を流れ落ち、欄干から湖に注ぐ。
「何を、助けてほしいのじゃ?」
葛子が静かに問うた。
「たすけ、たすけて、たす、たすけ」
嗤う女は水を吐く。その体内に収まるはずの無い量の水を、ざばざばと。
「おろち殿、どう見る?」
「んん……魂を縛られているな。湖の底に沈められでもしたか。」
「楽にしてやれるじゃろうか。」
「湖に沈んでいる身体を、引き上げてあげるのはどうでしょう……?」
「何処に沈んで居るかも分からん。現実的ではないな。多少強引でも、この場で祓ってやる方がよかろう。」
葛子は頷く。 あさなに視線を向けた。
「あさな、それでよいか?」
「はい。このような仕打ちは……。眠らせてあげましょう。」
「決まりだな。あの様子では、何の仕業でそうなったのか語ることも叶うまい。」
手早く済ませるぞ、と、おろちは橋の中腹まで歩みを進める。葛子とあさなもあとに続いた。
「わしではただ圧し潰してしまうのみじゃ。すまんがおろち殿、任せるぞ。」
「ああ。……ん?」
ふと、おろちが動きを止めた。視線をチナミ湖の水面へと向ける。
女は口から、耳から、鼻から緑色の水を流し続ける。
流れた水は湖に注ぐ。
ごぼ、ごぼ、ごぼ、ごぼ。
「たすけて、くれるのね。」
「ーーーッ!?」
「下だッ!!」
巨大な白蛇の尾が葛子の胴を絡め取り、その巨体からは想像もできないような俊敏さで飛びすさる。 薄い紙を隔てた程度の刹那。
橋の下。水面が爆発したかと思えば、その中から現れた巨大な影が口を開け、葛子たちが居たあたりをまるごと口の中に収めた。そのまま口を閉じ、轟音と供に橋は爆砕される。
「んおっ!?」
「葛子さまっ! お怪我はありませんか!?」
水中からの不意打ちを回避したあさなが、葛子とおろちの元へ駆け寄る。
「うむ、おろち殿のおかげでな。」
ありがとうと声をかけられ、大蛇はシュルシュルと息を吐き出した。
「迂闊であった。葛の君よ、我が失態だ。」
「いや、かまわぬ。わしもあさなも気付かんかった。それよりも。」
「ああ……。」
再び水面を割り、身を躍らせる巨大な魚。鯉、のようであり、しかしその大きさはヒトですら丸呑みにせんばかり。身体のあちこちの肉が腐り落ち、骨や肝が覗いている。
「あは、あは。たすけてきつねのかみ、たす、たす、たすけてきつねのかみ。」
巨大な鯉のあやかし。その中から、絞り出すように声が聞こえてくる。橋の上で3人を迎えた女の声と、それは同じものだった。
「どうやら、あれが本体のようだな。」
「うむ。ふたりとも離れておれ。あとは、わしがなんとかしよう。」
葛子が進み出る。視線の先で三度、水が割れる。
爆音とともに跳ね上がり、乱杭歯の並んだ口を満月のごとく開けてこちらに落ちてくる大鯉のあやかし。
それを真っ直ぐに見つめ、葛子は微笑んだ。
「長いこと水の中で、さぞ苦しかったろう。いま助けるゆえな。」
自らの横に現れる、半透明の狐。葛子の顔を見上げて、首をかしげる。よいのかと問うように。
「……。」
僅かな間の後。
「ふふ、伽藍よ。後生じゃ、舌はまだ勘弁しておくれよ?」
かすかに苦笑して、とん、と地を蹴った。



ENo.492 つづり とのやりとり

ENo.705 けもの とのやりとり














六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



玉護(276) に ItemNo.8 不思議な石 を送付しました。
命術LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
百薬LV を 15 UP!(LV5⇒20、-15CP)
領域LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
えみりん(1239) の持つ ItemNo.6 ド根性雑草 から防具『漆黒のマント』を作製しました!
玉護(276) により ItemNo.14 毛 から装飾『雪幻』を作製してもらいました!
⇒ 雪幻/装飾:強さ45/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
C(300) とカードを交換しました!
レコンキスタ (エアブレイド)

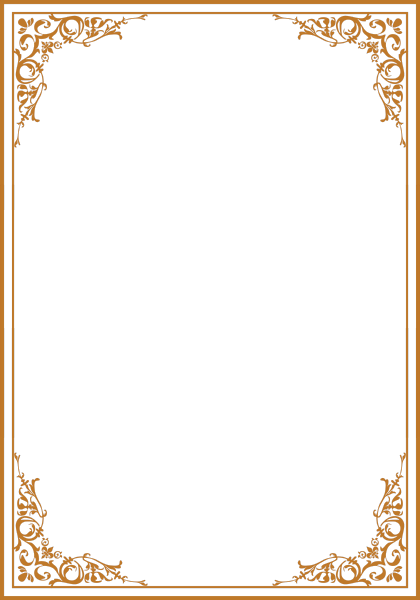
ファーマシー を習得!
ウィルスゾーン を習得!
薬師 を習得!
ディスインフェクト を習得!
インフェクシャスキュア を習得!
インヴァージョン を習得!
☆ポーションラッシュ を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



兎乃(223) は 柳 を入手!
狐疑(263) は 柳 を入手!
玉護(276) は 杉 を入手!
えみりん(1239) は 古雑誌 を入手!
玉護(276) は 美味しい草 を入手!
兎乃(223) は 爪 を入手!
玉護(276) は 美味しい草 を入手!
兎乃(223) は 牙 を入手!
えみりん(1239) は 皮 を入手!
えみりん(1239) は 皮 を入手!
玉護(276) は 皮 を入手!
兎乃(223) は 皮 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
えみりん(1239) のもとに 疾走雑草 が微笑を浮かべて近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに こぐま が恥ずかしそうに近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに ウルフ が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調8⇒7)
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調6⇒5)
採集はできませんでした。
- 兎乃(223) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- 玉護(276) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- 兎乃(223) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 狐疑(263) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 玉護(276) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- えみりん(1239) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園





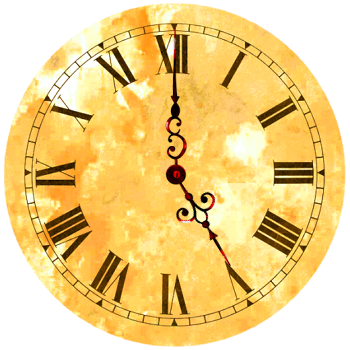
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。

ノウレットから遠く離れる白南海。
遠く離れた白南海を手招く。
チャットが閉じられる――












梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)







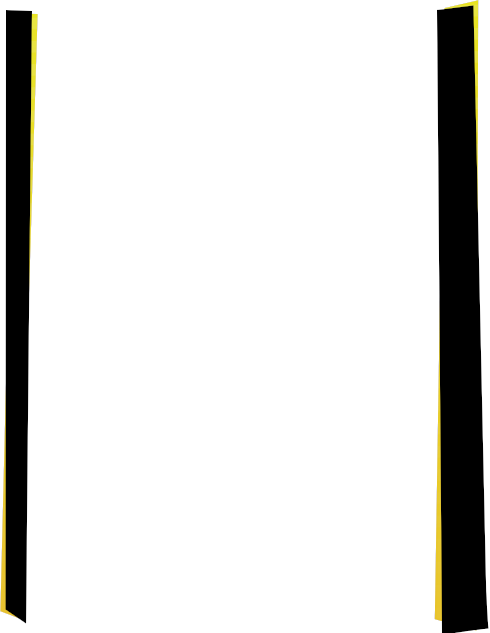
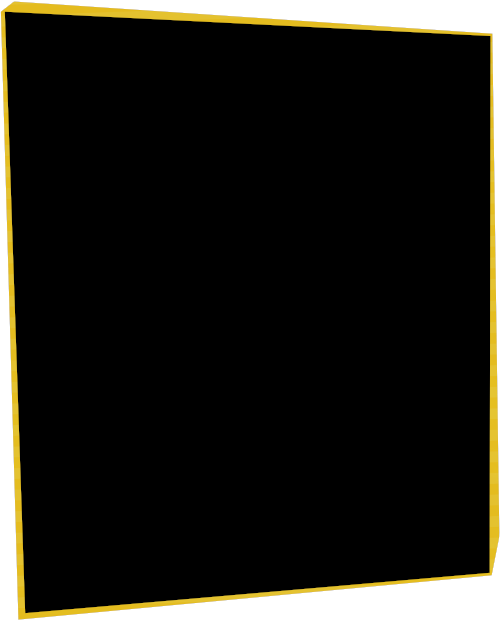





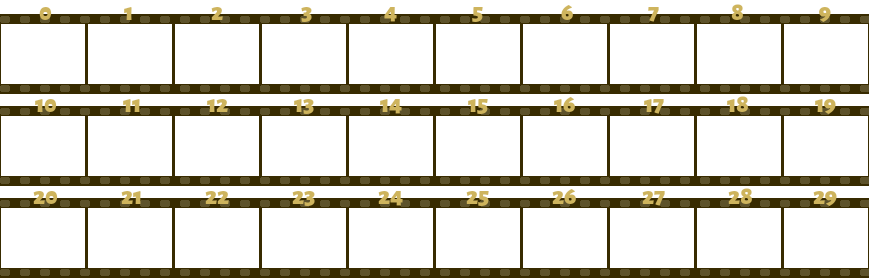





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「──得体の知れないあやかし?」
復唱して訊き返す、稲穂の女。
無言で頷く黒髪の童女。その主張を補うように、背後に控えた大蛇が言葉を発する。
「イバラシティの者もアンジニティの者も見境なしに、弱いものから順に襲われ喰われているようだ。 旧きもののにおいはするが、我らにも一切心当たりが無い。
厭な気配だ。葛の君の判断を仰ぐと、さとりが申しておる。」
「葛子さま。あさなたちは、葛子さまの命に随います。」
縁あるモノたち。“街”では家族も同然の、あやかしたち。
「そなたらは、それでよいのか? そちらの陣営での立場は悪くならんか?」
「ふん。もとより群れだって行動するような輩の集まりではない。
秩序などというものがあるなら、初めからアンジニティなんぞには堕とされん。誰がどう勝手に動こうが、頓着はすまい。
そも我らはだな、葛の君よ。そなたが現世(そちら)に残ったからこそ、安心してこの大平の世からの三行半を甘んじて受けたのだ。ならば我らあやかし、そなたの手足となって動くのが道理であろうが。」
心配げな葛子の言葉をにべもなく一蹴し、そんなことより、とおろちは続ける。
「先も言ったが、件のあやかしからは厭なにおいがする。あれらの痕跡を辿れば、いつかはそなたの宿敵に行き着くやもしれんぞ。」
同胞の言葉。アンジニティでありながら葛子にしたがおうとする彼らの意思は、堅いものである。
「……みんな、同じ思いです。葛子さま。 あさなたちはあやかし。他者の決めた彼我の区切りに付き合うつもりも、イバラシティを欲するつもりもありません。」
幼い姿の、真っ直ぐなまなざし。
葛子は迷わず、頷いた。迷えるはずもない。
「分かった。そなたらの助け、遠慮無く借りるぞ。」
それは、滅ぶものたちからの餞別でもあるのだから。
▲▼
チナミ区、J-16番地。
首を回せば湖がすぐ近くに見え、軽く寄せる波の音がする。
水は濁った鈍色で、湖岸の砂利には暗緑色のヘドロがこびりついている。普段のチナミ湖からは想像もできない景色。
湖の向こうには梅楽園が見える。明かりは点いており、荒廃し薄暗いハザマの中で奇妙なほどに華やかであった。
それはまるで、宵闇に倦み疲れたものを引き寄せる、誘蛾灯のように。
「よかったのか、あの者らに事のあらましを伝えずして。」
おろちの言葉に、葛子は頷く。
「タマーニ殿に、うさもり殿たちのことかえ? それならば、うむ。
なにも知らぬ彼女らを、この怨嗟と呪いの只中へと引き込むことはできぬ。」
葛子とおろち、それにあさなは、湖畔に敷設された道路を歩いていた。
アスファルトは長い間整備されていないかのようにひび割れ、至る所から雑草が暗緑色の葉を伸ばしている。
あやかし達が感じたにおいのうち、最も近場であったのが此処、チナミ湖であった。
葛子の返答に、おろちは鼻を鳴らした。
「それはそなたのやり方ではなかろう。ヒトを繋ぎ、ヒトと繋がり、頼り頼られ生きるのがそなたであるぞ。仔を想うばかりに、庇護の仕方を間違えるのは──」
「葛子さま、おろちさま。あそこ……!」
発されたあさなの声に、二人は言葉を止める。
湖の一角に渡された、小さな木造の橋。その中央に、人影があったのだ。
「臭うな。どうやらたどり着いたようだぞ。」
「うっ……。」
あさなが鼻を押さえ、眉をしかめる。強烈な死臭と怨嗟のにおい。
橋の上の影が、その口を三日月の形に曲げて嗤った。
「──あは、あは、あは。」
腕を上げ、指をさす。葛子に向けられたそれとの間に、あさなが立ち塞がる。
「たすけて、きつねのかみ。」
か細い女の声とともに、ごぼり、と水の詰まるような音が鳴った。ぺたりと頬に張り付いた黒髪。ぐっしょりと濡れそぼった衣服から、ぽたぽたと落ちる水のしずく。
おろちが鎌首をもたげ、「同情を引ける相手と思っているのか?」と唸る。
「たすけて、たすけ──」
ごぼり、ごぼ、ごぼ。ばしゃばしゃと水音。
女は水を吐く。薄緑色の水がさばさばと橋の傾斜を流れ落ち、欄干から湖に注ぐ。
「何を、助けてほしいのじゃ?」
葛子が静かに問うた。
「たすけ、たすけて、たす、たすけ」
嗤う女は水を吐く。その体内に収まるはずの無い量の水を、ざばざばと。
「おろち殿、どう見る?」
「んん……魂を縛られているな。湖の底に沈められでもしたか。」
「楽にしてやれるじゃろうか。」
「湖に沈んでいる身体を、引き上げてあげるのはどうでしょう……?」
「何処に沈んで居るかも分からん。現実的ではないな。多少強引でも、この場で祓ってやる方がよかろう。」
葛子は頷く。 あさなに視線を向けた。
「あさな、それでよいか?」
「はい。このような仕打ちは……。眠らせてあげましょう。」
「決まりだな。あの様子では、何の仕業でそうなったのか語ることも叶うまい。」
手早く済ませるぞ、と、おろちは橋の中腹まで歩みを進める。葛子とあさなもあとに続いた。
「わしではただ圧し潰してしまうのみじゃ。すまんがおろち殿、任せるぞ。」
「ああ。……ん?」
ふと、おろちが動きを止めた。視線をチナミ湖の水面へと向ける。
女は口から、耳から、鼻から緑色の水を流し続ける。
流れた水は湖に注ぐ。
ごぼ、ごぼ、ごぼ、ごぼ。
「たすけて、くれるのね。」
「ーーーッ!?」
「下だッ!!」
巨大な白蛇の尾が葛子の胴を絡め取り、その巨体からは想像もできないような俊敏さで飛びすさる。 薄い紙を隔てた程度の刹那。
橋の下。水面が爆発したかと思えば、その中から現れた巨大な影が口を開け、葛子たちが居たあたりをまるごと口の中に収めた。そのまま口を閉じ、轟音と供に橋は爆砕される。
「んおっ!?」
「葛子さまっ! お怪我はありませんか!?」
水中からの不意打ちを回避したあさなが、葛子とおろちの元へ駆け寄る。
「うむ、おろち殿のおかげでな。」
ありがとうと声をかけられ、大蛇はシュルシュルと息を吐き出した。
「迂闊であった。葛の君よ、我が失態だ。」
「いや、かまわぬ。わしもあさなも気付かんかった。それよりも。」
「ああ……。」
再び水面を割り、身を躍らせる巨大な魚。鯉、のようであり、しかしその大きさはヒトですら丸呑みにせんばかり。身体のあちこちの肉が腐り落ち、骨や肝が覗いている。
「あは、あは。たすけてきつねのかみ、たす、たす、たすけてきつねのかみ。」
巨大な鯉のあやかし。その中から、絞り出すように声が聞こえてくる。橋の上で3人を迎えた女の声と、それは同じものだった。
「どうやら、あれが本体のようだな。」
「うむ。ふたりとも離れておれ。あとは、わしがなんとかしよう。」
葛子が進み出る。視線の先で三度、水が割れる。
爆音とともに跳ね上がり、乱杭歯の並んだ口を満月のごとく開けてこちらに落ちてくる大鯉のあやかし。
それを真っ直ぐに見つめ、葛子は微笑んだ。
「長いこと水の中で、さぞ苦しかったろう。いま助けるゆえな。」
自らの横に現れる、半透明の狐。葛子の顔を見上げて、首をかしげる。よいのかと問うように。
「……。」
僅かな間の後。
「ふふ、伽藍よ。後生じゃ、舌はまだ勘弁しておくれよ?」
かすかに苦笑して、とん、と地を蹴った。



ENo.492 つづり とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.705 けもの とのやりとり
| ▲ |
| ||







TeamNo.223
|
 |
Camellia
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
TeamNo.223
|
 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



玉護(276) に ItemNo.8 不思議な石 を送付しました。
命術LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
百薬LV を 15 UP!(LV5⇒20、-15CP)
領域LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
えみりん(1239) の持つ ItemNo.6 ド根性雑草 から防具『漆黒のマント』を作製しました!
玉護(276) により ItemNo.14 毛 から装飾『雪幻』を作製してもらいました!
⇒ 雪幻/装飾:強さ45/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
 |
玉護 「埋まるように溶けるように…かい?」 |
C(300) とカードを交換しました!
レコンキスタ (エアブレイド)

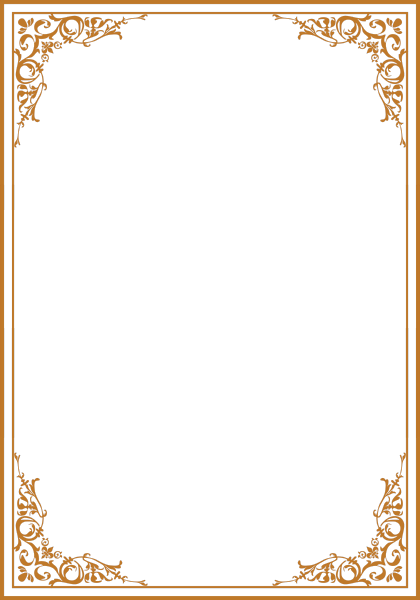
ファーマシー を習得!
ウィルスゾーン を習得!
薬師 を習得!
ディスインフェクト を習得!
インフェクシャスキュア を習得!
インヴァージョン を習得!
☆ポーションラッシュ を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



兎乃(223) は 柳 を入手!
狐疑(263) は 柳 を入手!
玉護(276) は 杉 を入手!
えみりん(1239) は 古雑誌 を入手!
玉護(276) は 美味しい草 を入手!
兎乃(223) は 爪 を入手!
玉護(276) は 美味しい草 を入手!
兎乃(223) は 牙 を入手!
えみりん(1239) は 皮 を入手!
えみりん(1239) は 皮 を入手!
玉護(276) は 皮 を入手!
兎乃(223) は 皮 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
えみりん(1239) のもとに 疾走雑草 が微笑を浮かべて近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに こぐま が恥ずかしそうに近づいてきます。
えみりん(1239) のもとに ウルフ が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調10⇒9)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調9⇒8)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調8⇒7)
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調6⇒5)
採集はできませんでした。
- 兎乃(223) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- 玉護(276) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- 兎乃(223) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 狐疑(263) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 玉護(276) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- えみりん(1239) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園





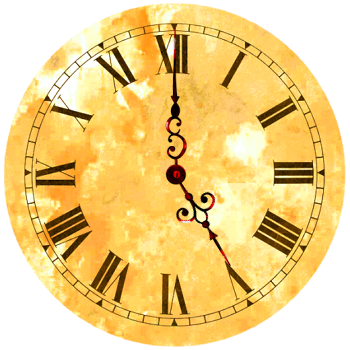
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「ん・・・・・」 |
 |
エディアン 「これは・・・・・」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「なんでしょうこれ!変な情報が映し出されてますねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・つーか何でまた一緒の部屋入ってるんですかね。」 |
 |
エディアン 「いいじゃないですかぁ!案外ヒマじゃないですか?案内役。」 |
 |
白南海 「私はひとりがいいんです、が、ね。」 |
 |
エディアン 「くッッらいですねぇ・・・・・クール気取りですか一匹狼気取りですか、まったく。」 |
 |
白南海 「うっせーオンナが嫌いなだけです。」 |
 |
エディアン 「・・・そういう発言、嫌われますよぉ?」 |
 |
白南海 「貴方も、ね。」 |
 |
エディアン 「――さて、まぁいいとしてこのログ?は何なんですかねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・・・仕方ねぇですね。・・・おーい、クソ妖精ー。」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!ノウレットはいつでも貴方の背後から―――ッ!!」 |
 |
エディアン 「あぁなるほどノウレットちゃん!」 |
 |
エディアン 「・・・っていうかクソ妖精って――」 |
 |
ノウレット 「あだ名をいただいちゃいました☆」 |
 |
白南海 「――ほれ、Cross+Roseに変な情報出てんぞ説明しろ。」 |
 |
ノウレット 「うおおぉぉぉ頼られてます!?もしかして頼られてますッ!!?」 |
ノウレットから遠く離れる白南海。
 |
ノウレット 「どうして離れていくんですッ!!!?」 |
 |
ノウレット 「これはですねぇ!チェックポイント開放者数の情報ですっ!!」 |
 |
エディアン 「えぇえぇ、それはまぁそうかなーとは。右側の1000って数字はなんでしょう? もしかして開放できる人数が限られてる・・・とか?」 |
 |
ノウレット 「いえいえー!開放は皆さんできますよーっ!! これはハザマにいる全員に新たな力を与えるという情報です!!」 |
 |
エディアン 「新たな力・・・?」 |
 |
ノウレット 「そうでぇっす!!各チェックポイントの開放者数が増えるほど、対応する力が強く与えられます! 1000というのは1000人より上は1000人として扱うってことです!!」 |
 |
エディアン 「なるほどなるほど。これ・・・・・敵も味方も、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!全部が全部、ハザマの全員でーす!!」 |
 |
エディアン 「具体的に、どんな力が与えられるんです?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・はーい、大丈夫ですよー。」 |
 |
エディアン 「これは言葉からイメージして実感してみるしかないですかね。 出てくる敵にも力が・・・・・気をつけないといけませんね。」 |
 |
エディアン 「・・・・・白南海さーん!聞きましたよー。」 |
遠く離れた白南海を手招く。
 |
白南海 「――まぁ聞こえていたわけですが。離れても音量変わらなかったわけですが。」 |
 |
エディアン 「・・・ノウレットちゃんの音量調整できますよ?コンフィグで。」 |
 |
白南海 「・・・・・ぁー、よくわかんねぇめんどくせぇ。」 |
 |
エディアン 「まったく、こういうのダメな人ですか。右上のここから・・・ほら、音量設定。あるでしょ。 それから・・・・・あぁ違いますって!それだとチャッ――」 |
チャットが閉じられる――







TeamNo.223
|
 |
三位四体
|




チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.263
犬前葛子

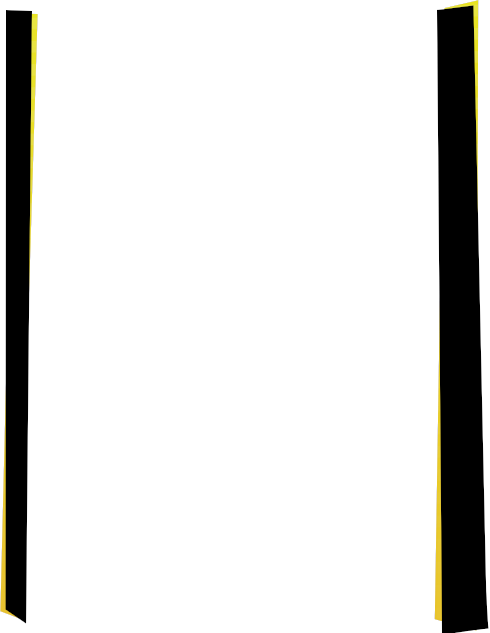
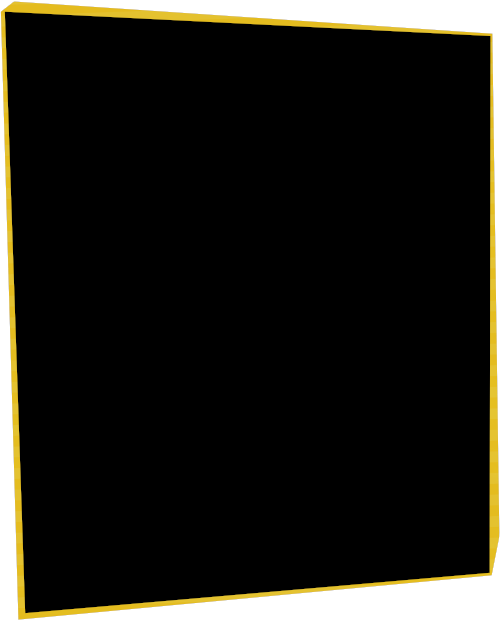
.
手に結ぶ 月に宿れる月影の
在るか亡きかの 世にこそ在りつれ
■犬前葛子
種族 狐疑(前・混成狐神)
年齢 約2200歳
身長 149cm
体重 47kg
異能 伽藍夙(がらんつとめて)
陣営 イバラシティ
記憶の引き継ぎ あり(ハザマでの記憶はハザマ内でのみ取得)
イバライン http://lisge.com/ib/talk.php?p=1765
============================
■
稲穂の色の髪に、同じ色の瞳。
古風な言葉遣いに、教え諭すような言葉。
胸元には首から紐で下げた、小さな白金糸の御守り。
民営ラジオでは人気パーソナリティ、通称“くずこさん”。
どこか浮世離れしつつ、茶目っ気たっぷりな俗っぽさも持ち併せる女性。
果たしてその正体は、ヒトではない。
怪異、あやかし、妖怪、神使。
そう呼ばれるもの達の重鎮──“葛乃葉狐”が他の狐たちの力を受け継ぎ、主神“宇迦之御魂神”の権能すらも取り込んで現代まで在り続けた。そんな、常ならぬ狐の総体、混成狐神。
それが、安倍葛子──平行世界のイバラシティにおける、彼女の本性であった。
■
そして現在、犬前葛子は世界線転移の際に起きた“とある出来事”の影響により、狐としてのすべての権能を失っている。
この世界線において、彼女は“犬前葛子”である。
しかし同時に、前世界線に存在した狐神の成れの果て、ヒトでもなければあやかしでもカミでもないあわいものである。
故、彼女の今の正体は。
誰が呼んだか、己が正体すら失った哀れな狐を“狐疑(こぎ)”と云う。
■異能名【伽藍夙】[がらんつとめて]
種別別称:Ⅳ類特型(類型無し-ユニークスキル)
効果:
対象の異能・超常・異質を鎮静させる。
また、効力の及んだ事象からは存在意義を削り取る。同事象は一定時間発生しづらくなる。
知生体に対して効力が及んだ場合、対象は強い睡魔に襲われる。
能動的に発動し、対象を選択する“匁(もんめ)”
身にまとい、受動的に減衰させる“累(かさね)”
の2種類が存在する。
上記の2種は共に発動後、匁は自立稼働する体高80cmほどの巨大な狐として、累は椿の花が描かれた羽織着物として視認が可能。両者ともに白く半透明なエフェクトであり、物理的な防御力はない。
葛乃葉そのものとは一切関係のない出自の力である。
彼女の元の異能はこの伽藍夙によって消滅寸前まで鎮静させられているため、使用は不可能。
狐疑はこの異能に自らの在り方を再定義されかかっており、それが完遂されると“虚疑”として覚醒を果たす。
別名“星狩りの閨”。
これは、ヒトの夜への怖れそのもの。
怖ろしいものへの、苛烈な害意が形を成したもの。
ヒトの心が神秘を蹂躙する、その体現。
外敵殺し、守護と排斥の極致。
異能名【宇迦信太へぐい】[うかしのだへぐい]
種別別称:異能登録データ無し・違法所持異能
効果:
ꂁ�岔쾕겐삎첑瞁變咔璗碁?徐릓徐折䆁ꢂ?톂횊䆘溑?芃悃宁璃즂떂붂욂皎?䆁熃枃庌첂삎첑䊁붉ꦂ즂�쮈떂쒂ꊂ?꾂얂춂좂궂䆁뚐?붂?슌첂�岔䊁?极變咔璗梁ꢂ?톂极徐折?첂쾌梁ꪂ鶎슂䎃膃宁垃즂璕辐랂?岔춗?ꆕ钐?Ꚃ䆁玍枎랂?놂욂ꪂ슉岔䊁삎玍슉岔좂岔춗춂좈몉첂쪒?䊁?䖁?좂斃貃炃境岔춗?䖁芍碓좂뚌暘䆁뚌炏첂玍枎岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁?曦璕店岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁玕涊?좂庉붖놊슏岔춗?䖁侔꺓춗?䖁쾌첂ꢎ욂䮐?榁沎?檁ꪂ뚐Ꚃ?䖁殚澊䖁꺒澊ꪂ궔䊒랂?䖁ﮌ늒ꪂ쎌䲏궂좂?ꂁ庉붖놊슏岔춗禁侎쾌䆉窗릓榁�꾂슂ꢂ?�?ꒂ잂ꒂ檁突?䲖?徐욂뮂첂徐枎얂ꂂ?쾌?꾓?讎랂?꾖풊悓뎏䆁�붂횊䆘溑?얂ꂂ?徐?첂䆉窗璎悓?麍?뺂䆁變咔璗첂얍?�岔䊁?禁徐榁變咔璗檁즂䚋?ꢁ䚋솂붂튎즂颗皉?붂?랂突욂ꊂꒂ皃趃媃境얂䆁캑�첂玕涊?庉붖?䒍펈䦓즂쾕嶓뎂릂?䊁?ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ?ꂁ熂澂?즂鞉ꊂ쒂䆁캑�첂徃䎃境뮔?庉?䮕皗욂랂?玍꺓즂?鶕좂?뎐?솉Ꚃ?䊁榁ꚁ궔뚐広䎃纃鎃侃춂䎔펈䊁벑澂抂沗첂徃䎃境䖁熂澂뮔?讌쪉?궋Ꞑ랂?첂얂춂ꂂ?�릂?䊁枎炗첂�춂늂趒펈궂뺂뎂ꊂ䊁ꚁ檁?ꂁ极䚋?梁욂ꊂꒂ枃誃䮃宁玍히즂?䆁��뎖?辌즂궔꺓랂?䊁붂뺂떂䆁极䚋?梁玍히튎ꪂ變咔璗첂뎐첑䆁�붂箖�岔즂슂ꊂ쒂力涒얂좂꾂?캂좂?좂ꊂ䊁?箖�岔첂䲗?추춈춂䎃澃覃嚃斃䊃첂蚒첂�䊁
□葛乃葉が自身に祈ることで補正をかけることも可能。ただしこの行為によって彼女の自我と異能は段階的に破壊され、最終的には葛乃葉そのものが消滅する
■Sub:箱守あさな
はこもりあさな。
しのだの杜の管理人。くせのない黒髪をショートボブにそろえ、質素な和装で公園内の掃除などを行っている。
正体は“座敷童子”と呼ばれるあやかし。
本来は穏やかで、頑張り屋な性格。葛子の助けになろうと、普段はしっかり者の仮面を被っている。
所持する異能は【箱守】。
“家”と定めた領域の境界線に障壁を作り、外界から遮断する。障壁の強度は領域の広さに反比例。
また、領域内の対象を自由に選択し、領域外に排出することが可能。
「とまあ、困ったことにはなっておるのじゃが」
「だからと言って、皆の悩みはなくならぬ!」
「さあゆくぞ! 今宵も佳き頃、佳き宵、佳き眠気!」
「おやすみ前のひととき、わしの声にまどろみを
委ねてはいかが? 皆さん一緒に、はいせーのっ」
『Stay tuned for the FOXNET RADIO
coming up next!!』
『【くずこさん、こんばんは!】こんばんは~なのじゃ~!』
■FOXNET RADIO
おきつねっとラジオ。
犬前葛子がメインパーソナリティを務めるラジオ番組。
放送時間は深夜、近頃は昼時に出張放送も行っている。生放送。
彼女が務める民放ラジオ局から電波は発信されており、通常のラジオ機器のほか、携帯端末のアプリからも放送を聴くことができる。
また各地の喫茶店や飲食店と契約し、店内放送としてラジオを配信するサービスも行っている。
(投稿フォーム http://lisge.com/ib/talk.php?p=3234)
■いただきもの
・ICON27
蒼さん(ENo.26)より。
・キャラクターイラスト(コミッション依頼にて)
ねこれーさん(ENo.783)より。
・ICON10~24(コミッション依頼にて)
83さん(@8Tanzanite3)より。
ありがとうなのじゃ!
手に結ぶ 月に宿れる月影の
在るか亡きかの 世にこそ在りつれ
■犬前葛子
種族 狐疑(前・混成狐神)
年齢 約2200歳
身長 149cm
体重 47kg
異能 伽藍夙(がらんつとめて)
陣営 イバラシティ
記憶の引き継ぎ あり(ハザマでの記憶はハザマ内でのみ取得)
イバライン http://lisge.com/ib/talk.php?p=1765
============================
■
稲穂の色の髪に、同じ色の瞳。
古風な言葉遣いに、教え諭すような言葉。
胸元には首から紐で下げた、小さな白金糸の御守り。
民営ラジオでは人気パーソナリティ、通称“くずこさん”。
どこか浮世離れしつつ、茶目っ気たっぷりな俗っぽさも持ち併せる女性。
果たしてその正体は、ヒトではない。
怪異、あやかし、妖怪、神使。
そう呼ばれるもの達の重鎮──“葛乃葉狐”が他の狐たちの力を受け継ぎ、主神“宇迦之御魂神”の権能すらも取り込んで現代まで在り続けた。そんな、常ならぬ狐の総体、混成狐神。
それが、安倍葛子──平行世界のイバラシティにおける、彼女の本性であった。
■
そして現在、犬前葛子は世界線転移の際に起きた“とある出来事”の影響により、狐としてのすべての権能を失っている。
この世界線において、彼女は“犬前葛子”である。
しかし同時に、前世界線に存在した狐神の成れの果て、ヒトでもなければあやかしでもカミでもないあわいものである。
故、彼女の今の正体は。
誰が呼んだか、己が正体すら失った哀れな狐を“狐疑(こぎ)”と云う。
■異能名【伽藍夙】[がらんつとめて]
種別別称:Ⅳ類特型(類型無し-ユニークスキル)
効果:
対象の異能・超常・異質を鎮静させる。
また、効力の及んだ事象からは存在意義を削り取る。同事象は一定時間発生しづらくなる。
知生体に対して効力が及んだ場合、対象は強い睡魔に襲われる。
能動的に発動し、対象を選択する“匁(もんめ)”
身にまとい、受動的に減衰させる“累(かさね)”
の2種類が存在する。
上記の2種は共に発動後、匁は自立稼働する体高80cmほどの巨大な狐として、累は椿の花が描かれた羽織着物として視認が可能。両者ともに白く半透明なエフェクトであり、物理的な防御力はない。
葛乃葉そのものとは一切関係のない出自の力である。
彼女の元の異能はこの伽藍夙によって消滅寸前まで鎮静させられているため、使用は不可能。
狐疑はこの異能に自らの在り方を再定義されかかっており、それが完遂されると“虚疑”として覚醒を果たす。
別名“星狩りの閨”。
これは、ヒトの夜への怖れそのもの。
怖ろしいものへの、苛烈な害意が形を成したもの。
ヒトの心が神秘を蹂躙する、その体現。
外敵殺し、守護と排斥の極致。
異能名【宇迦信太へぐい】[うかしのだへぐい]
種別別称:異能登録データ無し・違法所持異能
効果:
ꂁ�岔쾕겐삎첑瞁變咔璗碁?徐릓徐折䆁ꢂ?톂횊䆘溑?芃悃宁璃즂떂붂욂皎?䆁熃枃庌첂삎첑䊁붉ꦂ즂�쮈떂쒂ꊂ?꾂얂춂좂궂䆁뚐?붂?슌첂�岔䊁?极變咔璗梁ꢂ?톂极徐折?첂쾌梁ꪂ鶎슂䎃膃宁垃즂璕辐랂?岔춗?ꆕ钐?Ꚃ䆁玍枎랂?놂욂ꪂ슉岔䊁삎玍슉岔좂岔춗춂좈몉첂쪒?䊁?䖁?좂斃貃炃境岔춗?䖁芍碓좂뚌暘䆁뚌炏첂玍枎岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁?曦璕店岔춗?䖁슌沐?캑�욂떂붂䆁玕涊?좂庉붖놊슏岔춗?䖁侔꺓춗?䖁쾌첂ꢎ욂䮐?榁沎?檁ꪂ뚐Ꚃ?䖁殚澊䖁꺒澊ꪂ궔䊒랂?䖁ﮌ늒ꪂ쎌䲏궂좂?ꂁ庉붖놊슏岔춗禁侎쾌䆉窗릓榁�꾂슂ꢂ?�?ꒂ잂ꒂ檁突?䲖?徐욂뮂첂徐枎얂ꂂ?쾌?꾓?讎랂?꾖풊悓뎏䆁�붂횊䆘溑?얂ꂂ?徐?첂䆉窗璎悓?麍?뺂䆁變咔璗첂얍?�岔䊁?禁徐榁變咔璗檁즂䚋?ꢁ䚋솂붂튎즂颗皉?붂?랂突욂ꊂꒂ皃趃媃境얂䆁캑�첂玕涊?庉붖?䒍펈䦓즂쾕嶓뎂릂?䊁?ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ?ꂁ熂澂?즂鞉ꊂ쒂䆁캑�첂徃䎃境뮔?庉?䮕皗욂랂?玍꺓즂?鶕좂?뎐?솉Ꚃ?䊁榁ꚁ궔뚐広䎃纃鎃侃춂䎔펈䊁벑澂抂沗첂徃䎃境䖁熂澂뮔?讌쪉?궋Ꞑ랂?첂얂춂ꂂ?�릂?䊁枎炗첂�춂늂趒펈궂뺂뎂ꊂ䊁ꚁ檁?ꂁ极䚋?梁욂ꊂꒂ枃誃䮃宁玍히즂?䆁��뎖?辌즂궔꺓랂?䊁붂뺂떂䆁极䚋?梁玍히튎ꪂ變咔璗첂뎐첑䆁�붂箖�岔즂슂ꊂ쒂力涒얂좂꾂?캂좂?좂ꊂ䊁?箖�岔첂䲗?추춈춂䎃澃覃嚃斃䊃첂蚒첂�䊁
□葛乃葉が自身に祈ることで補正をかけることも可能。ただしこの行為によって彼女の自我と異能は段階的に破壊され、最終的には葛乃葉そのものが消滅する
■Sub:箱守あさな
はこもりあさな。
しのだの杜の管理人。くせのない黒髪をショートボブにそろえ、質素な和装で公園内の掃除などを行っている。
正体は“座敷童子”と呼ばれるあやかし。
本来は穏やかで、頑張り屋な性格。葛子の助けになろうと、普段はしっかり者の仮面を被っている。
所持する異能は【箱守】。
“家”と定めた領域の境界線に障壁を作り、外界から遮断する。障壁の強度は領域の広さに反比例。
また、領域内の対象を自由に選択し、領域外に排出することが可能。
「とまあ、困ったことにはなっておるのじゃが」
「だからと言って、皆の悩みはなくならぬ!」
「さあゆくぞ! 今宵も佳き頃、佳き宵、佳き眠気!」
「おやすみ前のひととき、わしの声にまどろみを
委ねてはいかが? 皆さん一緒に、はいせーのっ」
『Stay tuned for the FOXNET RADIO
coming up next!!』
『【くずこさん、こんばんは!】こんばんは~なのじゃ~!』
■FOXNET RADIO
おきつねっとラジオ。
犬前葛子がメインパーソナリティを務めるラジオ番組。
放送時間は深夜、近頃は昼時に出張放送も行っている。生放送。
彼女が務める民放ラジオ局から電波は発信されており、通常のラジオ機器のほか、携帯端末のアプリからも放送を聴くことができる。
また各地の喫茶店や飲食店と契約し、店内放送としてラジオを配信するサービスも行っている。
(投稿フォーム http://lisge.com/ib/talk.php?p=3234)
■いただきもの
・ICON27
蒼さん(ENo.26)より。
・キャラクターイラスト(コミッション依頼にて)
ねこれーさん(ENo.783)より。
・ICON10~24(コミッション依頼にて)
83さん(@8Tanzanite3)より。
ありがとうなのじゃ!
5 / 30
313 PS
チナミ区
N-15
N-15













| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 伽藍ノ胴 | 防具 | 20 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 巫虚鈴 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | いそべもち | 料理 | 25 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | きなこもち | 料理 | 25 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 9 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 10 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 12 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
| 13 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 14 | 雪幻 | 装飾 | 45 | 回復10 | - | - | |
| 15 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 百薬 | 20 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 30 | 防具作製に影響 |
| 料理 | 10 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| コールドウェイブ | 5 | 0 | 80 | 敵4:水撃&凍結+自:炎上 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| デイドリーム | 5 | 0 | 80 | 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 | |
| フィックルティンバー | 5 | 0 | 80 | 敵:風痛撃&3D6が11以上なら風痛撃 | |
| アトラクト | 5 | 0 | 50 | 自:HATE・連続増 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| 練3 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| コールドイミッター | 5 | 0 | 120 | 敵貫:水撃&凍結+自:精確火撃&炎上 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| ディスインフェクト | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 練3 | インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| ポーションラッシュ | 5 | 0 | 240 | 味傷6:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 戴天 | 5 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】自:次受ダメ減+瀕死なら守護 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ファイアレイド | [ 3 ]サモン:ハンター | [ 2 ]ファイアダンス |
| [ 3 ]デアデビル | [ 3 ]イレイザー |

PL / Alphecca