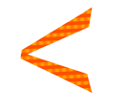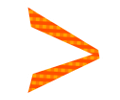<< 2:00~3:00




====
荊街備忘録
4
怪しい奴、というのはざらにいる。
本当に怪しい奴ってのは大抵の場合そう見られないよう気を使うくらいの知能は備えてるもんだと思ってたけど、
そういうことすら敢えてせず、あからさまに隠し立てなく怪しさを常に爆発させている奴がいる。
むしろ怪しいと本人はまったく自覚しておらずそれが普通と思ってる類いの怪しいやつの場合は『真性』で片付くとして、
一番厄介なのは本人が自覚して、周囲への影響も理解した上で敢えて、それでも悪びれず堂々と振舞っている『確信犯』の類いだろう。
「つまりどう考えても怪しいんだよなあ…」
おれの呟きをしっかり聞き咎めて、数歩先を歩いていた男が足を止めた。「あ?なんだコゾー」
黒いシャツにスラックス、やけに浮いたネクタイとどう考えてもカタギに見えないその男は、なし崩し的にこのハザマ世界で同行することになった男の一人だ。
もうひとりがの男性が白っぽいコートで品行方正な雰囲気を漂わせてるぶん、なおさらもう片方の怪しさが際立っているといってもいい。
猫背気味で歩く黒ずくめ。かたや居住まい正しい白コート。この一見するとまるで対照的な二人には、共通する点がいくつかあった。
ひとつは、このイバラシティおよびハザマ世界をめぐる戦いの仲間であるということ。
そしてもうひとつは、この二人とも、自称『魔法使い』であるということだったーーー
*
『異能』が普通に受け入れられている今日日この街の、しかも不思議が当然とばかりに混沌としたこのハザマ世界において、いまさら魔法だ超能力だ言われたって正直たいていのことは受け入れる用意はおれにはある。てか、この異界でバケモノや侵略的異邦人と戦うというなんでもありの非常時に、そんな覚悟はなんとなく決めておかないと色々しんどいよなって気もしている。
だからこそ、この対照的な二人の扱うものが異能という扱いとも微妙に違う『魔法』ということに共通して拘っているというのも不思議な偶然ではあった。
最初になし崩し的にチナミ区の駅前で共闘したときから、彼らの戦いぶりは見ていたから、それがどんなものかもだいたいわかる。
白いコートの男性〜ヨツジと名乗った青年は、いかにも『魔法』としか言いようのない、古式ゆかしい呪文や術式を使って、従えている羊〜(メリさんというらしい)を戦わせるという形を取っていた。一種の使い魔的な存在といえば、おれにもなんとなく理解できる。うん、魔術っぽい。
だが対して黒ずくめの男〜新沼ケンジというらしいそいつは、単にガラの悪い蹴りを放っているだけのそのスジの怖い人にしか見えないのだが、そいつの周囲に確実に現れる『何か』が常にそこにいる。そしてそれがとにかくヤバいのだ。
それは、どこにでもいる見慣れた街の生き物にして誰一人疑問に思わないオブジェクト、そのへんにいる、ごく普通の、『鳩』だった。
その鳩が、戦いの場において、どこからか確実に現れる。相手を攻撃するわけでも邪魔するわけでもない。ついでに言うと俺たちに何かしてくれるわけでもない。だが、確実に、鳩が数を増やしていくごとに相手の行動は鈍っていくし、なにがしかの影響を受けていくようだった。つまり、集まる鳩の数に応じて相手が弱っていくのだ。
…これは『異能』というより呪いみたいなやつなんじゃないかとか思うんだけどどうだろうか。
「まじないなんて生易しいもんじゃねえんだが」
「いや、呪い(のろ)いの方な。カース」
苦笑した新沼という男〜当人はマッケンジーを自称しているあたりその時点で『知れる』のだが〜のつぶやきにすかさず突っ込む。
「まあ否定はしねえけど、この街じゃみんな一緒くたに『異能』扱いでカタがつくんだからガタガタ抜かすのも不毛だろ」
「身も蓋もない言い方すんなよな、おれは個人的にそういうの気になるんだよ」
「なんでだよ」
そう尋ねられ、ちょっと口ごもる。ちょっと考えてから息を吸い込んだ。「…おれ、『異能』について自分でもまだよくわかってねえからさ」
「どういうこった」
おれは大雑把に、この街にやってきた経緯をかいつまんで説明した。隣県住まいだった頃、子供の頃から頻繁に経験していた一種の不思議な体験が、どうやら超常現象でも悪霊でも病気の症状の類でもなく『異能がらみ』だったとわかったこと。その謎を解くために、知り合ったフミちゃんの伝手でこの街にやってきたということ。
「つまり自分がどんな異能なのか本人もわかってねえってことか」いぶかしげにマッケンジーは眉をひそめる。「なんか面倒くせえな」
「いや、だいたいは分かるんだ。なんつーか、基本『そこにあったもの』の力を借りるみたいな…あれ、これからできるもの、だっけ?」
「場当たり的だなー。大丈夫かてめー」
苦笑まじりに頭を小突かれる。「まあ、さっきの立ち回りなら問題ねえだろうけどよ」
「とにかく、おれとしてはもう少しこう『異能』ってのはそもそもどんなもんなのか情報を集めたいんだよ!いきなり実地教習みたいなもんなんだから」
「そんな畏るもんじゃねえだろー、皆テキトーに受け入れてよろしくやってるじゃねえか」
肩をすくめて、前を歩くフミちゃんやヨツジさんの後ろ姿に視線を投げる。「だいたいざっくり分かってりゃいいんだよ」
「いやヨツジさんの『魔法』ってのは由緒正しい本物の魔法ってのはなんかわかるんだよ、見てれば。だけど、あんたの、何?」
「ハト『と』魔法なんだよ、わっかんねーやつだな」
「2回転くらいしてわかんねえから聞いてるんだよ…」
会話が堂々巡りになってしまっていることに気づいて、おれはため息を吐いてしまった。「おれの方が変なのかな…」
前方の二人を見ると、おれたちの話を聞いてたんだろう、沈黙の合間に二人の会話が聞こえてきた。
「ヨツジさん、『魔法』ってそんなのもあるの?あの例の、ハトみたいな」
「…あるのかもしれないですね。魔法と一言で言っても大変も歴史があるものですから。様々な可能性があります」
「そ、そうなんだ…」
「私の知る限りでも、鳩を使い魔として用いる類いの術は聞いたことがありますし。その派生のようなものかもしれません」
フミちゃんもなんか半信半疑って感じだったけど、納得したようだった。
「ま、まあ、私が個人的に気になったのは、それって魔法というよりその…」
「…手品?」
「そう!」しばらく間を置いて返ってきたヨツジさんのセリフに、フミちゃんとおれはほぼ同時に返答し、マッケンジーは飄々と一同から視線を逸らしていた。
====



ENo.1144 マッケンジー とのやりとり

ENo.1231 ヨツジ とのやりとり

以下の相手に送信しました













自然LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
フミ(961) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
マッケンジー(1144) の持つ ItemNo.6 不思議なブルーチーズ に ItemNo.7 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
ItemNo.5 肩チュンバード に ItemNo.6 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
フミ(961) により ItemNo.8 花びら から射程1の武器『レガーロ』を作製してもらいました!
⇒ レガーロ/武器:強さ45/[効果1]混乱10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
マッケンジー(1144) により ItemNo.9 不思議な雫 から防具『スズメット』を作製してもらいました!
⇒ スズメット/防具:強さ45/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
ヨツジ(1231) により ItemNo.10 不思議な雫 から装飾『肩チュンバード・改』を作製してもらいました!
⇒ 肩チュンバード・改/装飾:強さ45/[効果1]耐水10 [効果2]- [効果3]-
ウィンドカッター を研究しました!(深度1⇒2)
ライトニング を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度2⇒3)
グランドクラッシャー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フミ(961) は 吸い殻 を入手!
マッケンジー(1144) は 吸い殻 を入手!
ヨツジ(1231) は ネジ を入手!
楽タロー(1285) は ネジ を入手!
ヨツジ(1231) は ボロ布 を入手!
マッケンジー(1144) は ボロ布 を入手!
楽タロー(1285) は 美味しい果実 を入手!
フミ(961) は ボロ布 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マッケンジー(1144) のもとに 歩行軍手 が空を見上げなから近づいてきます。
マッケンジー(1144) のもとに チェリーさん が微笑を浮かべて近づいてきます。



ヨツジ(1231) に移動を委ねました。
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)
採集はできませんでした。
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- フミ(961) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- マッケンジー(1144) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ヨツジ(1231) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 楽タロー(1285) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――















仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














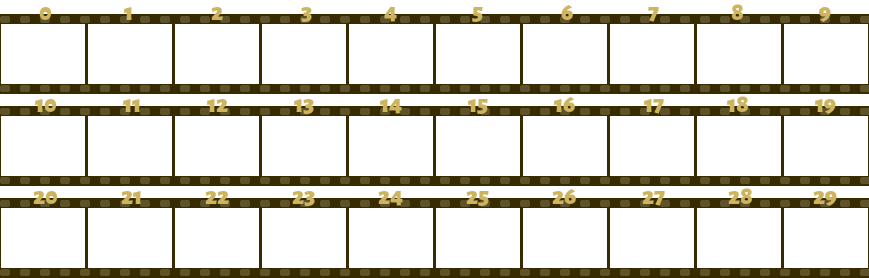





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



====
荊街備忘録
4
怪しい奴、というのはざらにいる。
本当に怪しい奴ってのは大抵の場合そう見られないよう気を使うくらいの知能は備えてるもんだと思ってたけど、
そういうことすら敢えてせず、あからさまに隠し立てなく怪しさを常に爆発させている奴がいる。
むしろ怪しいと本人はまったく自覚しておらずそれが普通と思ってる類いの怪しいやつの場合は『真性』で片付くとして、
一番厄介なのは本人が自覚して、周囲への影響も理解した上で敢えて、それでも悪びれず堂々と振舞っている『確信犯』の類いだろう。
「つまりどう考えても怪しいんだよなあ…」
おれの呟きをしっかり聞き咎めて、数歩先を歩いていた男が足を止めた。「あ?なんだコゾー」
黒いシャツにスラックス、やけに浮いたネクタイとどう考えてもカタギに見えないその男は、なし崩し的にこのハザマ世界で同行することになった男の一人だ。
もうひとりがの男性が白っぽいコートで品行方正な雰囲気を漂わせてるぶん、なおさらもう片方の怪しさが際立っているといってもいい。
猫背気味で歩く黒ずくめ。かたや居住まい正しい白コート。この一見するとまるで対照的な二人には、共通する点がいくつかあった。
ひとつは、このイバラシティおよびハザマ世界をめぐる戦いの仲間であるということ。
そしてもうひとつは、この二人とも、自称『魔法使い』であるということだったーーー
*
『異能』が普通に受け入れられている今日日この街の、しかも不思議が当然とばかりに混沌としたこのハザマ世界において、いまさら魔法だ超能力だ言われたって正直たいていのことは受け入れる用意はおれにはある。てか、この異界でバケモノや侵略的異邦人と戦うというなんでもありの非常時に、そんな覚悟はなんとなく決めておかないと色々しんどいよなって気もしている。
だからこそ、この対照的な二人の扱うものが異能という扱いとも微妙に違う『魔法』ということに共通して拘っているというのも不思議な偶然ではあった。
最初になし崩し的にチナミ区の駅前で共闘したときから、彼らの戦いぶりは見ていたから、それがどんなものかもだいたいわかる。
白いコートの男性〜ヨツジと名乗った青年は、いかにも『魔法』としか言いようのない、古式ゆかしい呪文や術式を使って、従えている羊〜(メリさんというらしい)を戦わせるという形を取っていた。一種の使い魔的な存在といえば、おれにもなんとなく理解できる。うん、魔術っぽい。
だが対して黒ずくめの男〜新沼ケンジというらしいそいつは、単にガラの悪い蹴りを放っているだけのそのスジの怖い人にしか見えないのだが、そいつの周囲に確実に現れる『何か』が常にそこにいる。そしてそれがとにかくヤバいのだ。
それは、どこにでもいる見慣れた街の生き物にして誰一人疑問に思わないオブジェクト、そのへんにいる、ごく普通の、『鳩』だった。
その鳩が、戦いの場において、どこからか確実に現れる。相手を攻撃するわけでも邪魔するわけでもない。ついでに言うと俺たちに何かしてくれるわけでもない。だが、確実に、鳩が数を増やしていくごとに相手の行動は鈍っていくし、なにがしかの影響を受けていくようだった。つまり、集まる鳩の数に応じて相手が弱っていくのだ。
…これは『異能』というより呪いみたいなやつなんじゃないかとか思うんだけどどうだろうか。
「まじないなんて生易しいもんじゃねえんだが」
「いや、呪い(のろ)いの方な。カース」
苦笑した新沼という男〜当人はマッケンジーを自称しているあたりその時点で『知れる』のだが〜のつぶやきにすかさず突っ込む。
「まあ否定はしねえけど、この街じゃみんな一緒くたに『異能』扱いでカタがつくんだからガタガタ抜かすのも不毛だろ」
「身も蓋もない言い方すんなよな、おれは個人的にそういうの気になるんだよ」
「なんでだよ」
そう尋ねられ、ちょっと口ごもる。ちょっと考えてから息を吸い込んだ。「…おれ、『異能』について自分でもまだよくわかってねえからさ」
「どういうこった」
おれは大雑把に、この街にやってきた経緯をかいつまんで説明した。隣県住まいだった頃、子供の頃から頻繁に経験していた一種の不思議な体験が、どうやら超常現象でも悪霊でも病気の症状の類でもなく『異能がらみ』だったとわかったこと。その謎を解くために、知り合ったフミちゃんの伝手でこの街にやってきたということ。
「つまり自分がどんな異能なのか本人もわかってねえってことか」いぶかしげにマッケンジーは眉をひそめる。「なんか面倒くせえな」
「いや、だいたいは分かるんだ。なんつーか、基本『そこにあったもの』の力を借りるみたいな…あれ、これからできるもの、だっけ?」
「場当たり的だなー。大丈夫かてめー」
苦笑まじりに頭を小突かれる。「まあ、さっきの立ち回りなら問題ねえだろうけどよ」
「とにかく、おれとしてはもう少しこう『異能』ってのはそもそもどんなもんなのか情報を集めたいんだよ!いきなり実地教習みたいなもんなんだから」
「そんな畏るもんじゃねえだろー、皆テキトーに受け入れてよろしくやってるじゃねえか」
肩をすくめて、前を歩くフミちゃんやヨツジさんの後ろ姿に視線を投げる。「だいたいざっくり分かってりゃいいんだよ」
「いやヨツジさんの『魔法』ってのは由緒正しい本物の魔法ってのはなんかわかるんだよ、見てれば。だけど、あんたの、何?」
「ハト『と』魔法なんだよ、わっかんねーやつだな」
「2回転くらいしてわかんねえから聞いてるんだよ…」
会話が堂々巡りになってしまっていることに気づいて、おれはため息を吐いてしまった。「おれの方が変なのかな…」
前方の二人を見ると、おれたちの話を聞いてたんだろう、沈黙の合間に二人の会話が聞こえてきた。
「ヨツジさん、『魔法』ってそんなのもあるの?あの例の、ハトみたいな」
「…あるのかもしれないですね。魔法と一言で言っても大変も歴史があるものですから。様々な可能性があります」
「そ、そうなんだ…」
「私の知る限りでも、鳩を使い魔として用いる類いの術は聞いたことがありますし。その派生のようなものかもしれません」
フミちゃんもなんか半信半疑って感じだったけど、納得したようだった。
「ま、まあ、私が個人的に気になったのは、それって魔法というよりその…」
「…手品?」
「そう!」しばらく間を置いて返ってきたヨツジさんのセリフに、フミちゃんとおれはほぼ同時に返答し、マッケンジーは飄々と一同から視線を逸らしていた。
====



ENo.1144 マッケンジー とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1231 ヨツジ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
フミ 「みんなまた会ったね~! 元気だった?」 |
 |
フミ 「もうあたし大学の授業ついてくの大変! こんなことが起きてたら集中出来ないわ いつまで続くのかしら、ブツブツ…」 |
 |
フミ 「あ、ごめん、ごめん!」 |
 |
フミ 「ま、それはさておき 今回もよろしくね」 |
 |
マッケンジー 「どーもココに来ると時間の感覚が狂うな。いま何時だ?」 |
 |
ヨツジ 「ええと、お久しぶりです。なかなか慣れませんね、これ。 もう少し行くとチェックポイントですから、頑張りましょうね。適度に」 |
 |
ヨツジ 「『むこう』の私が知覚している限りでは、ハザマにいる間、時間は経過していないと思います。 そもそも『むこう』では、ここの…ハザマの記憶も全くありませんし。 皆さんは違うんですか?」 |
 |
メリさん 「めー?」 ヨツジのまわりでふわふわ漂っている |
| 楽タロー 「うーん、ハザマ時間ってのには慣れてきたけど、やっぱ妙な感じだなこりゃ」 |
| 楽タロー 「でもまあ、ハザマに移動する時が来たら無事皆合流した状態で再開って感じになるみたいだし …あんま気にすることじゃないのかもな。」 |
| 楽タロー 「そういやなんか突然『ロスト』だなんだの情報も降ってきたけど、 ハザマ世界ではそいつらを探すって目的もできたってことか?」 |
| 楽タロー 「アンジニティの連中とも違うってんなら、戦う必要がなけりゃいいんだけど… この調子じゃどうだか…えらい強いとかそういうのは勘弁だよな。」 |
| 楽タロー 「…おれまだ、自分の異能も全然使いこなせてないしなあ…」 |





ひつじふかふか
|
 |
蛇ノ目堂古書店住民組合
|



自然LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
フミ(961) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
マッケンジー(1144) の持つ ItemNo.6 不思議なブルーチーズ に ItemNo.7 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
ItemNo.5 肩チュンバード に ItemNo.6 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
| 楽タロー 「今までありがとうな、肩チュン…」 |
フミ(961) により ItemNo.8 花びら から射程1の武器『レガーロ』を作製してもらいました!
⇒ レガーロ/武器:強さ45/[効果1]混乱10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
 |
フミ 「Present for U !」 |
マッケンジー(1144) により ItemNo.9 不思議な雫 から防具『スズメット』を作製してもらいました!
⇒ スズメット/防具:強さ45/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
 |
マッケンジー 「似合うぜ?似合うぜ?」 |
ヨツジ(1231) により ItemNo.10 不思議な雫 から装飾『肩チュンバード・改』を作製してもらいました!
⇒ 肩チュンバード・改/装飾:強さ45/[効果1]耐水10 [効果2]- [効果3]-
 |
ヨツジ 「鳥がお好きなんですか?あ、今ならメリさんに触れるのでは?」 |
 |
メリさん 「めえ!」 |
ウィンドカッター を研究しました!(深度1⇒2)
ライトニング を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度2⇒3)
グランドクラッシャー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フミ(961) は 吸い殻 を入手!
マッケンジー(1144) は 吸い殻 を入手!
ヨツジ(1231) は ネジ を入手!
楽タロー(1285) は ネジ を入手!
ヨツジ(1231) は ボロ布 を入手!
マッケンジー(1144) は ボロ布 を入手!
楽タロー(1285) は 美味しい果実 を入手!
フミ(961) は ボロ布 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マッケンジー(1144) のもとに 歩行軍手 が空を見上げなから近づいてきます。
マッケンジー(1144) のもとに チェリーさん が微笑を浮かべて近づいてきます。



ヨツジ(1231) に移動を委ねました。
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)
採集はできませんでした。
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- フミ(961) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- マッケンジー(1144) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ヨツジ(1231) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 楽タロー(1285) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



キマエラ
|
 |
ひつじふかふか
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



ひつじふかふか
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.1285
設楽楽太郎



致命的な方向音痴であり結果的に失踪癖(当人は不本意)のある青年。基本真面目で勤勉だが生来からの物覚えの悪さと離れ癖(※)を何かの病気と勘違いされ、ことあるごとに入退院を繰り返してきた経緯を持つ。
イバラシティの某施設に転院した折それが異能の一種と判明したため、可能性を買われそのまま研究生として所属。実際はていのいいテスター。
PTMの女学生、フミのツテをたよってイバラシティへやってきたが、
彼女の所属する某組織の研究に微妙に巻き込まれる形でハザマの戦いに参加。
本人的にはフミを心配してのことらしいが、真偽は不明。
※のちに異能とされた特異体質。まだまだ謎が多いのだが、無茶振りに対しての生還率だけは確か。
よくことりがたかる。
イバラシティの某施設に転院した折それが異能の一種と判明したため、可能性を買われそのまま研究生として所属。実際はていのいいテスター。
PTMの女学生、フミのツテをたよってイバラシティへやってきたが、
彼女の所属する某組織の研究に微妙に巻き込まれる形でハザマの戦いに参加。
本人的にはフミを心配してのことらしいが、真偽は不明。
※のちに異能とされた特異体質。まだまだ謎が多いのだが、無茶振りに対しての生還率だけは確か。
よくことりがたかる。
12 / 30
139 PS
チナミ区
H-16
H-16




















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 土産の木刀 | 武器 | 15 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 6 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 7 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 8 | レガーロ | 武器 | 45 | 混乱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | スズメット | 防具 | 45 | 敏捷10 | - | - | |
| 10 | 肩チュンバード・改 | 装飾 | 45 | 耐水10 | - | - | |
| 11 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 10 | 空間/時間/風 |
| 自然 | 20 | 植物/鉱物/地 |
| 幻術 | 5 | 夢幻/精神/光 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 合成 | 25 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| スキューア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:地痛撃&次受ダメ増 | |
| デイドリーム | 5 | 0 | 80 | 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| アースリボルト | 5 | 0 | 150 | 敵:X連地領撃+自:弱化ターン効果を短縮 ※X=自分の弱化ターン効果の数+1 | |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ウィンドカッター | [ 1 ]ブルーム | [ 1 ]スキューア |
| [ 2 ]ライトニング | [ 3 ]ストーンブラスト |

PL / あな(穴)