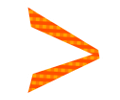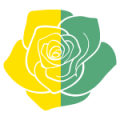<< 2:00~3:00




白い鍵盤を押せば、心地のよい音が部屋に広がった。
おれはこの楽器が奏でる音が好きだ。
始めたのはここで暮らすようになってからだけれど、用事がある時以外は大体毎日触れている気がする。
あとはそう、先生に大事な"お客さん"が来ているとき。
決して話し声の聞こえない防音室で、その人が帰るまでおれはここに居ないといけない。
それがおれと先生が交わした、約束の1つ。
Ⅳ. 二人の失くし物
初めてこのピアノの存在を知ったのは、家に来て部屋の場所を教えてもらって数日後。他の部屋のものよりもちょっと重たそうな扉があったけれど、先生はその先を教えてくれなかったから、子供なりの興味本意である日勝手に扉を開けたのだ。
すればその先、向こうに待ち構えていたのは、大きくて立派なグランドピアノが一台。
十分な広さのある部屋の真ん中に佇む姿はある種美しさもあって、おれはその瞬間確かにこの楽器に見惚れていた。
勝手に部屋に入っていることはすぐにバレてしまったので怒られるかと思ったけれど、先生は眉を落として笑うだけだった。そうして叱ることもなく、優しく頭を撫でてくれたことを覚えている。
『弾きたい?』
たった一言尋ねられて、迷わず頷いてしまったことも、また。
その日を機に先生は、暇があれば楽譜の読み方や弾き方をおれに教えてくれている。先生はおれにとって料理の先生でもあるけれど、ピアノの先生でもあるのだ。
けれど一つだけ、不思議なことがある。
共に暮らし始めて5年間、先生が鍵盤に触れているところをおれは一度も見たことがない。
この家にあるということは、ピアノの持ち主が先生であることは間違いないだろう。なのに先生は絶対にピアノを弾きたがらない。
否。
『──ねえ、どうして先生はピアノ、ひかないんですか?』
『んー? 気になっちゃう? そうだなぁ……命、私はね?』
弾かない、のではなくて。
弾けない、のだとそう言う。
繰り返すが変な話だ。おれに色んなことを教えてくれていて、そんなわけはないだろうに。
でも、少しぐらいは予測がついている。なぜ彼がそう言ったのか。
おれがピアノを弾くとき、決まって一人足を運ぶ観客がいた。
今日もまた、彼女はそこで笑っている。
慈しむように、ピアノを弾くおれを、音色を響かせるピアノを見ている。
或いはおれが席を離れたとき、彼女が一人でそこに座っていることがあるのも知っている。
鍵盤から指先を離して、彼女を見上げた。
全部予測で推測にしか過ぎない。でもきっとこのピアノは、先生と彼女を繋げる何かだ。
だからこそ先生は弾けない。だって彼は恐らく、ずっと。
そう考えるとつい溜め息が零れて、視線も落ちてしまう。先生のそういう一面を見る度に、どうしたって感じていたこと。引け目、とでも呼ぶのだろうか。
絶対に先生に声の届かない場所で、今日ばかりは言葉が漏れてしまった。
5年前、突然いなくなってしまったおれの家族。
母と父の間には、子供が産まれにくかった。
そんな中漸く産まれたおれのことを、二人はそりゃもう随分と可愛がってくれていたと思う。
寝るときはいつも川の字だった。おやすみ前の挨拶は決まって同じだった。
『愛してるよ、命。
かわいくて大切な、私たちの宝物』
眠れなくて、自分を大切にできなくて、きっと大好きなんだろうピアノにも触れない先生。
彼はきっと、死者に囚われている。おれを見下ろして頬笑む彼女に囚われている。
大切だったからだ。彼にとっても彼女にとっても、お互いが大切だから。失くしたことが受け入れられなくて、その穴がずっと埋まらない。
おれも確かに大切なものを失くしたはずなのに、けれど先生と違って、二人の思い出に触れることは怖くない。
それとこれとはまた別問題というか。対人関係が苦手なのはまた別種のトラウマだとか元々の気質もあるだろうし、そもそも人には得意不得意があるし。なんて言い訳はしてしまう。いやいつか克服したいとはちゃんと思っているけれども。
なんだかなあと思ってまた息を吐きながらも改めて彼女を見上げれば、思いもよらぬ光景が飛び込んできたものだから目を瞠った。
ぽたりと頬を伝う滴は、流れ落ちて、それでも床を濡らすことはなかったけれど。
でも、紛れもなく、泣いていた。
いつも笑っていた彼女が、泣いていた。
彼女と共に過ごすようになっても5年は経つのだが、これまでの間に泣いている姿は一度も見たことがない。やってしまった、泣かせてしまった。この状況、喋っていたのは自分だけ、と考えると紛れもなく悪いのはおれだ。
慰めるにもどうすればいいのかわからなくて、とりあえずおれは慌てて立ち上がって、本当にとりあえず、失礼かもしれないけれど彼女の頭を撫でた。かける言葉がわからない今、おれにできるのは泣かないでと、涙が止まるようにと触れることしか。
どうしようもないことを言ってもどうしようもないのだけど、ただただ涙を溢す彼女を見ているとそう思わずにはいられなかった。どうしてなのか分かれば、もう少しマシな言動が出来そうなのに。
なんにもわからない自分が、酷く情けない。
結局その後おれは何度か彼女に謝ったけれど、涙の理由はやっぱり分からず仕舞いで。
先生がおれを呼びに来たことで二人の時間は終わりを告げて、申し訳なさだけがずっと胸の中に渦巻いていたのだった。



ENo.147 ヨシノ とのやりとり

ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり

ENo.585 イザヤ とのやりとり

以下の相手に送信しました




一海(853) に ItemNo.11 甲殻 を手渡ししました。






一海(853) に ItemNo.8 松 を送付しました。
ヒシュ(1202) の持つ ItemNo.9 松 から防具『スカーレット』を作製しました!
万智花(1159) の持つ ItemNo.9 松 から防具『デニムのエプロン』を作製しました!
一海(853) の持つ ItemNo.7 松 から防具『鎧かけ松』を作製しました!
万智花(1159) により ItemNo.10 甲殻 から装飾『赤いネクタイ』を作製してもらいました!
⇒ 赤いネクタイ/装飾:強さ67/[効果1]反射10 [効果2]- [効果3]-
サステイン を研究しました!(深度0⇒1)
サステイン を研究しました!(深度1⇒2)
サステイン を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



一海(853) は ド根性雑草 を入手!
斎(1033) は ド根性雑草 を入手!
万智花(1159) は 吸い殻 を入手!
ヒシュ(1202) は ネジ を入手!
斎(1033) は ボロ布 を入手!
ヒシュ(1202) は 花びら を入手!
斎(1033) は 毛 を入手!
万智花(1159) は 毛 を入手!



万智花(1159) に移動を委ねました。
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 G-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 F-16(山岳)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 E-16(山岳)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 一海(853) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 万智花(1159) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 一海(853) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 斎(1033) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 万智花(1159) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ヒシュ(1202) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――








仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














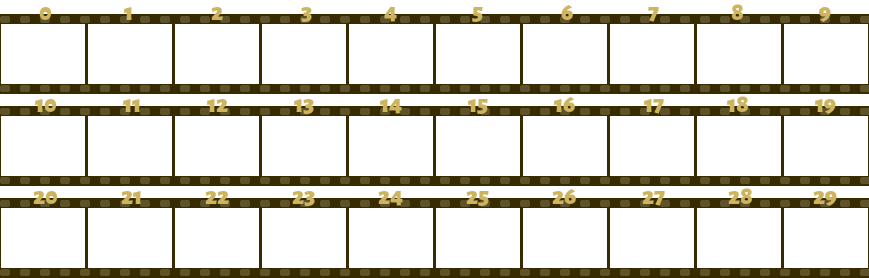







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK.



白い鍵盤を押せば、心地のよい音が部屋に広がった。
おれはこの楽器が奏でる音が好きだ。
始めたのはここで暮らすようになってからだけれど、用事がある時以外は大体毎日触れている気がする。
あとはそう、先生に大事な"お客さん"が来ているとき。
決して話し声の聞こえない防音室で、その人が帰るまでおれはここに居ないといけない。
それがおれと先生が交わした、約束の1つ。
Ⅳ. 二人の失くし物
初めてこのピアノの存在を知ったのは、家に来て部屋の場所を教えてもらって数日後。他の部屋のものよりもちょっと重たそうな扉があったけれど、先生はその先を教えてくれなかったから、子供なりの興味本意である日勝手に扉を開けたのだ。
すればその先、向こうに待ち構えていたのは、大きくて立派なグランドピアノが一台。
十分な広さのある部屋の真ん中に佇む姿はある種美しさもあって、おれはその瞬間確かにこの楽器に見惚れていた。
勝手に部屋に入っていることはすぐにバレてしまったので怒られるかと思ったけれど、先生は眉を落として笑うだけだった。そうして叱ることもなく、優しく頭を撫でてくれたことを覚えている。
『弾きたい?』
たった一言尋ねられて、迷わず頷いてしまったことも、また。
その日を機に先生は、暇があれば楽譜の読み方や弾き方をおれに教えてくれている。先生はおれにとって料理の先生でもあるけれど、ピアノの先生でもあるのだ。
けれど一つだけ、不思議なことがある。
共に暮らし始めて5年間、先生が鍵盤に触れているところをおれは一度も見たことがない。
 |
「……変だよな」 |
この家にあるということは、ピアノの持ち主が先生であることは間違いないだろう。なのに先生は絶対にピアノを弾きたがらない。
否。
『──ねえ、どうして先生はピアノ、ひかないんですか?』
『んー? 気になっちゃう? そうだなぁ……命、私はね?』
弾かない、のではなくて。
弾けない、のだとそう言う。
繰り返すが変な話だ。おれに色んなことを教えてくれていて、そんなわけはないだろうに。
でも、少しぐらいは予測がついている。なぜ彼がそう言ったのか。
 |
「 」 |
おれがピアノを弾くとき、決まって一人足を運ぶ観客がいた。
今日もまた、彼女はそこで笑っている。
慈しむように、ピアノを弾くおれを、音色を響かせるピアノを見ている。
或いはおれが席を離れたとき、彼女が一人でそこに座っていることがあるのも知っている。
 |
「…………」 |
鍵盤から指先を離して、彼女を見上げた。
全部予測で推測にしか過ぎない。でもきっとこのピアノは、先生と彼女を繋げる何かだ。
だからこそ先生は弾けない。だって彼は恐らく、ずっと。
そう考えるとつい溜め息が零れて、視線も落ちてしまう。先生のそういう一面を見る度に、どうしたって感じていたこと。引け目、とでも呼ぶのだろうか。
絶対に先生に声の届かない場所で、今日ばかりは言葉が漏れてしまった。
 |
「……おれって、薄情なんですかね」 |
5年前、突然いなくなってしまったおれの家族。
母と父の間には、子供が産まれにくかった。
そんな中漸く産まれたおれのことを、二人はそりゃもう随分と可愛がってくれていたと思う。
寝るときはいつも川の字だった。おやすみ前の挨拶は決まって同じだった。
『愛してるよ、命。
かわいくて大切な、私たちの宝物』
 |
「二人が傍に居ないこと、寂しいなって思います。悲しいなって。 ……でも、だからっておれ、そこまでなんです」 |
眠れなくて、自分を大切にできなくて、きっと大好きなんだろうピアノにも触れない先生。
彼はきっと、死者に囚われている。おれを見下ろして頬笑む彼女に囚われている。
大切だったからだ。彼にとっても彼女にとっても、お互いが大切だから。失くしたことが受け入れられなくて、その穴がずっと埋まらない。
おれも確かに大切なものを失くしたはずなのに、けれど先生と違って、二人の思い出に触れることは怖くない。
 |
「だって、……二人が居なくなっても、与えてくれた愛情が嘘になるわけじゃない。 きっと二人は今もおれの幸せを望んでいてくれている。 居なくなってもおれを、ずっと、……愛してくれているんだろうなって」 |
 |
「……だから、それさえあれば、おれはこわいものなんてないんです。 今日も明日も明後日も、前を向いて頑張ろうって思うんです。 ああいや、人と喋るのとか学校とかは苦手で、情けない感じですけど……」 |
それとこれとはまた別問題というか。対人関係が苦手なのはまた別種のトラウマだとか元々の気質もあるだろうし、そもそも人には得意不得意があるし。なんて言い訳はしてしまう。いやいつか克服したいとはちゃんと思っているけれども。
なんだかなあと思ってまた息を吐きながらも改めて彼女を見上げれば、思いもよらぬ光景が飛び込んできたものだから目を瞠った。
 |
 |
「……え?」 |
ぽたりと頬を伝う滴は、流れ落ちて、それでも床を濡らすことはなかったけれど。
でも、紛れもなく、泣いていた。
いつも笑っていた彼女が、泣いていた。
 |
「ッ、す、すみません! 嫌なこと言いました? ごめんなさい……!」 |
彼女と共に過ごすようになっても5年は経つのだが、これまでの間に泣いている姿は一度も見たことがない。やってしまった、泣かせてしまった。この状況、喋っていたのは自分だけ、と考えると紛れもなく悪いのはおれだ。
慰めるにもどうすればいいのかわからなくて、とりあえずおれは慌てて立ち上がって、本当にとりあえず、失礼かもしれないけれど彼女の頭を撫でた。かける言葉がわからない今、おれにできるのは泣かないでと、涙が止まるようにと触れることしか。
 |
「ああクソ……おれにあなたの言葉がちゃんと分かればな……」 |
どうしようもないことを言ってもどうしようもないのだけど、ただただ涙を溢す彼女を見ているとそう思わずにはいられなかった。どうしてなのか分かれば、もう少しマシな言動が出来そうなのに。
なんにもわからない自分が、酷く情けない。
結局その後おれは何度か彼女に謝ったけれど、涙の理由はやっぱり分からず仕舞いで。
先生がおれを呼びに来たことで二人の時間は終わりを告げて、申し訳なさだけがずっと胸の中に渦巻いていたのだった。



ENo.147 ヨシノ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.585 イザヤ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
一海 「穏やかな道、というと……。望み薄ですかね、これは。」 |
 |
斎 「ロスト? だっけ? なんだか少年漫画にでもありそうな展開になってきたね!」 |
 |
万智花 「7人のロスト……何だか一気にゲームめいてきましたねえ。 ほんとにゲームなら良かったのになあ、なんて」 |
 |
ヒシュ 「どいつもこいつも歯ごたえ無ェんなあ……。」 |
 |
ヒシュ 「(――もっとも、この前みたいに通りすがりにボコられるのは勘弁だけど。)」 |
一海(853) に ItemNo.11 甲殻 を手渡ししました。





一海(853) に ItemNo.8 松 を送付しました。
ヒシュ(1202) の持つ ItemNo.9 松 から防具『スカーレット』を作製しました!
万智花(1159) の持つ ItemNo.9 松 から防具『デニムのエプロン』を作製しました!
一海(853) の持つ ItemNo.7 松 から防具『鎧かけ松』を作製しました!
万智花(1159) により ItemNo.10 甲殻 から装飾『赤いネクタイ』を作製してもらいました!
⇒ 赤いネクタイ/装飾:強さ67/[効果1]反射10 [効果2]- [効果3]-
サステイン を研究しました!(深度0⇒1)
サステイン を研究しました!(深度1⇒2)
サステイン を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



一海(853) は ド根性雑草 を入手!
斎(1033) は ド根性雑草 を入手!
万智花(1159) は 吸い殻 を入手!
ヒシュ(1202) は ネジ を入手!
斎(1033) は ボロ布 を入手!
ヒシュ(1202) は 花びら を入手!
斎(1033) は 毛 を入手!
万智花(1159) は 毛 を入手!



万智花(1159) に移動を委ねました。
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 G-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 F-16(山岳)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 E-16(山岳)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 一海(853) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 万智花(1159) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 一海(853) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 斎(1033) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 万智花(1159) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ヒシュ(1202) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



スイーツ☆パラダイス
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.1033
神園 斎



◇神園 斎(かみぞの いつき)
183cm / 30歳 / 男性
数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。
典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。
ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。
金銭感覚がずれているところが少々。
好きなものは酒とタバコとネットゲーム。
MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。
古参&重課金勢&ネカマ。
異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。
日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。
◆月守 命(つきもり みこと)
156cm / 15歳 / 男性
5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。
引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。
友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。
基本的な家事や買い物は彼が行っている。
好きなものは苺、それから駄菓子。
異能:人や動物でない存在を認識する。
常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。
他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。
--------------------
〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。
〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。
〇プロフ絵二種
183cm / 30歳 / 男性
数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。
典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。
ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。
金銭感覚がずれているところが少々。
好きなものは酒とタバコとネットゲーム。
MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。
古参&重課金勢&ネカマ。
異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。
日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。
◆月守 命(つきもり みこと)
156cm / 15歳 / 男性
5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。
引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。
友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。
基本的な家事や買い物は彼が行っている。
好きなものは苺、それから駄菓子。
異能:人や動物でない存在を認識する。
常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。
他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。
--------------------
〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。
〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。
〇プロフ絵二種
30 / 30
199 PS
チナミ区
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | チェスターコート | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 聴診器 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 9 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 10 | 赤いネクタイ | 装飾 | 67 | 反射10 | - | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 防具 | 30 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ライフリンク | 5 | 0 | 50 | 自従傷:HP増+HP譲渡 | |
| アクアヒール | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 氷水避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水耐性・凍結耐性増+凍結によるHP・SP減少量減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ケア (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
渇望のカード (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
|
ささやかなる祈り (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ウォーターフォール | [ 3 ]アイシクルランス | [ 3 ]チャージ |
| [ 3 ]サステイン |

PL / 蒸しパン