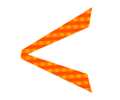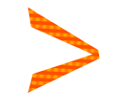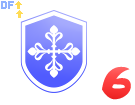<< 1:00~2:00




三日目(LEBEN PRO)
今日も退屈な一日が過ぎる。チバ県マッドシティで、オレはしがない探偵業を営んでいるが、探偵の仕事なんてモノはたいていはヒトか会社の信用調査がほとんどで、散文的でなければ、まったく逆に愛憎溢れる修羅場にご招待という依頼が多く正直げんなりしてしまう。だがおかげさまでというべきか、オレは人間を観る癖がしぜんに身につくようになって、そして人間には二種類が存在することを知ることができた。
人間はわずかの善人と多くの小悪党によって構成される。
気がつくと、行き先にそびえている壁のような断崖が目に入る。端末機の画面には、わざわざアナログ表示にした時計の針が動いていて、時刻は零時を過ぎている。あれから十日ほどが過ぎたはずだが、時計の針はあれから一時間ほどしか進んでいない。午後ではなく、午前の零時。本来なら真夜中なのだろうが、ハザマ世界と呼ばれる時間にある、イバラシティの空はよどんでいて明るいとも暗いともいえず、もちろん太陽も星も雲も見ることはできない。ガキのじぶん、何かの怪奇小説で読んだドリームランドとかいう世界を思い浮かべる。
「やれやれ。ひでー目にあったぜ、皆んな大丈夫か?」
「あれがアンジニティの方々ですか。さすがに、お強かったですね」
オレはそれが当然であるかのように、仲間になったばかりの連中に視線を向けると、ソーヤもここまでくれば大丈夫だろうかといった様子で、傍に浮いているメリさんの腹のあたりをふかふかと叩いている。たぶん、あまり意識していない行動だ。
イバラシティの駅前に広がる荒野、莫迦げて聞こえるが、ハザマ世界と呼ばれるこの「時間」の街は本当に悪夢のような荒野が広がっている、に、足を踏み出したオレたちは、さっそくこのハザマに生きている奇妙な存在に襲われた。ゴリラめいた雑草やら、妖精やら、何のコトを言ってるのかわかんねーと思うがそういう奇怪な生き物に襲われた。
「Mary had a little lamb Its fleece was white as snow...」
すかさずソーヤが、動揺したそぶりもなく呟くと、彼の傍に浮いているメリさんに呼びかける。魔法使いと称するソーヤが本当に魔法使いであることをオレたちは知っている。それが異能というもので、フミと楽タローも、もちろんオレもこのチリメン雑魚くんたちを蹴散らそうと身構えた。
「よ〜し、かかってきなさい!」
「出し惜しみはナシだ!」
結果から言えば、オレたちは大した苦労もなくそいつらを蹴散らすことができた。知り合ったばかりでチームワークもクソもないし、オレも自分の異能を理解するには程遠いなりに、とりあえず長い脚で蹴りをくれてやる。
「ハッハァ!キスマイアァス」
簡単に蹴散らすと、妖精と雑草の残骸がごろごろと地面に転がっている。緑色の、ゴリラの頭めいたモノが転がっている姿に思うところもあるが、コイツはオレたちを襲ってきた植物のナレノハテだぜ?と自分を説得する。何より、この程度のチャンバラに手間取っているオレたちは、本当にヤバい連中が様子を見ていたことにもまるで気がつけずにいたのだから。
「茜の空に 君は何を見るのか 旅立つ風に 君は何を聞くのか
少年のままで生きているなら その手で明日を掴めるはずさ
チャンバラ チャンバラ 魂よ 魂よ 今燃えろよ
チャンバラ チャンバラ そいつが男達の生きざま」

「いや、私たちそんなの歌ってないから!歌ってないから!」
大事なコトなので二度言われてしまったが、ハザマ世界を通じてこのイバラシティを訪れている連中、アンジニティの連中にいよいよ遭遇してしまったというワケだ。
一人はピンクの髪に砂糖菓子のような甘い匂いをさせている女、一人は頭にネコの耳みたいなヘッドホンを載せている女、一人は右と左の瞳の色が違う小柄な女、そしてもう一人は、どこかのほほんとして見えるメガネの男。一見するとライブハウスあたりにいそうな、ちょっと派手好きな連中にしか見えないが、どいつも身にまとっているふいんき(漢字変換できねーな)がヤバい。わざわざ刃物を持ったナントカに近寄ろうとするのはマヌケのするコトだ。
「なんかさっきから散々言ってくれてるねー。こいつらヤッちゃっていいんだよね?」
「ふーん。じゃあ、どこまで減じられるか、試してみようか」
ピンク髪の女の言葉に、小柄な女が妙な構えをする。コツは心得ている、オレがタイミングを合わせてソイツを「見る」と、小柄な女がわずかに表情を歪める。
「やられたっ」
「ヒャッハー!テメーの技は見切ったぜ!」
異能は封じることができる。もちろん半ばは運だよりだが、この時はうまくいった。だがそれでこの連中に勝てるとは最初から思っていない。ハッキリ言って逃げるために時間稼ぎのつもりだったが、正面から莫迦にされてノンキに逃してくれるほど先方も甘くない。砂糖みたいに甘い匂いをさせていても残念ながら甘くない。
「アマさにトロけて...!」
次の瞬間には、オレたちめがけて火やら稲妻やらが飛んでくる。
* * *
「いや、ひでー目にあったぜ」
「なんかマッケンジーさん、我先に逃げてませんでした?」
フミが不審なモノを見る目を向けている。危なくなったら逃げる、オレがソイツを身をもって実践したからこそ全員が逃げ遅れずに済んだ。戦略的撤退というヤツだとテキトーなことを言ってごまかしておくが、納得しないなりに納得はしてくれたらしい(どっちだよ)。
あれがアンジニティ。このイバラシティに侵略とやらを試みている連中だ。そしてオレたちは連中からこの世界を守るために、ハザマ世界で連中を待ち構えて迎え撃つために集められた。異能とはその資格を持つ者たちに与えられた力。ソイツがこの世界の事情というワケだ。
「いやしかし連中強ぇーだろ」
「強かったですねえ」
のほほんとした口調でソーヤも同意してくれているが、考えてみればコイツは問題だ。アンジニティの連中は、たいていはイバラシティに自分の居場所を探して訪れる。多くがそのつもりでやってきている。対するイバラシティの連中にも、アンジニティからこの世界を守るんだと息巻いてるヤツもいるが、オレたちのように異能があるからという理由で、ワケも分からないままここにやってきた者が少なくない。つまりモチベーションが違う。
「まあ、みんな無事ならヨシとしないとな」
「その通りだぜ。楽タローはモノノドーリというやつが分かっている」
オレの偉そうな言葉に、楽タローも胡散臭げな視線を向けている。オレたちはヤル気マンマンなアンジニティの連中を相手にして、まずは無事に生き残ることを考えながら、少しずつ力をつけていかなければならないらしい。負けて当然、引き分ければ御の字が今のところの方針だ。
だが、やはりそんなこすっからいことを考えているオレこそが呑気なのだ。オレたちが知りもしない場所で、端末に映りもしない場所で、あの南高梅とかいうヤローたちが不穏な会話を交わしている。DAZNサーバがクルクルまわるみてーな不安定な通信の上で、断片的なやりとりだけを拾うことができる。
「おっくれましてーーーッ!!」
「どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな」
「招かれた方々全員がーー」
「周期的に発動する、能力というより・・・」
「制御不能な・・・ザザッ・・・己の世界のために、争え」
こいつがオレたちの置かれている状況というワケだ。襲いかかってくるアンジニティの連中に勝つどころではない。まずは、無事に生き残ることを考えながら、少しずつ力をつけていかなければならない。



ENo.1285 楽タロー とのやりとり




フミ(961) に ItemNo.8 韮 を手渡ししました。









呪術LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
料理LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
使役LV を 9 UP!(LV1⇒10、-9CP)
百薬LV を 1 UP!(LV4⇒5、-1CP)
武器LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
フミ(961) の持つ ItemNo.10 韮 から防具『韮の道着』を作製しました!
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なブルーチーズ』をつくりました!
⇒ 不思議なブルーチーズ/料理:強さ20/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]-/特殊アイテム
ItemNo.9 美味しい草 から料理『美味しいブルーチーズ』をつくりました!
⇒ 美味しいブルーチーズ/料理:強さ20/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-
九々之助(154) とカードを交換しました!
鎖の巨人 (サモン:ウォリアー)

ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ファーマシー を研究しました!(深度0⇒1)
ファーマシー を研究しました!(深度1⇒2)
サステイン を習得!
ペレル を習得!
ポイズン を習得!
スコーピオン を習得!
クレイジーチューン を習得!
魅惑 を習得!
チャームダンス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フミ(961) は 花びら を入手!
マッケンジー(1144) は 韮 を入手!
ヨツジ(1231) は 韮 を入手!
楽タロー(1285) は 花びら を入手!
フミ(961) は 毛 を入手!
ヨツジ(1231) は ネジ を入手!
楽タロー(1285) は 不思議な雫 を入手!
ヨツジ(1231) は ネジ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マッケンジー(1144) のもとに ヤンキー が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調16⇒15)
採集はできませんでした。
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



三日目(LEBEN PRO)
今日も退屈な一日が過ぎる。チバ県マッドシティで、オレはしがない探偵業を営んでいるが、探偵の仕事なんてモノはたいていはヒトか会社の信用調査がほとんどで、散文的でなければ、まったく逆に愛憎溢れる修羅場にご招待という依頼が多く正直げんなりしてしまう。だがおかげさまでというべきか、オレは人間を観る癖がしぜんに身につくようになって、そして人間には二種類が存在することを知ることができた。
人間はわずかの善人と多くの小悪党によって構成される。
気がつくと、行き先にそびえている壁のような断崖が目に入る。端末機の画面には、わざわざアナログ表示にした時計の針が動いていて、時刻は零時を過ぎている。あれから十日ほどが過ぎたはずだが、時計の針はあれから一時間ほどしか進んでいない。午後ではなく、午前の零時。本来なら真夜中なのだろうが、ハザマ世界と呼ばれる時間にある、イバラシティの空はよどんでいて明るいとも暗いともいえず、もちろん太陽も星も雲も見ることはできない。ガキのじぶん、何かの怪奇小説で読んだドリームランドとかいう世界を思い浮かべる。
「やれやれ。ひでー目にあったぜ、皆んな大丈夫か?」
「あれがアンジニティの方々ですか。さすがに、お強かったですね」
オレはそれが当然であるかのように、仲間になったばかりの連中に視線を向けると、ソーヤもここまでくれば大丈夫だろうかといった様子で、傍に浮いているメリさんの腹のあたりをふかふかと叩いている。たぶん、あまり意識していない行動だ。
イバラシティの駅前に広がる荒野、莫迦げて聞こえるが、ハザマ世界と呼ばれるこの「時間」の街は本当に悪夢のような荒野が広がっている、に、足を踏み出したオレたちは、さっそくこのハザマに生きている奇妙な存在に襲われた。ゴリラめいた雑草やら、妖精やら、何のコトを言ってるのかわかんねーと思うがそういう奇怪な生き物に襲われた。
「Mary had a little lamb Its fleece was white as snow...」
すかさずソーヤが、動揺したそぶりもなく呟くと、彼の傍に浮いているメリさんに呼びかける。魔法使いと称するソーヤが本当に魔法使いであることをオレたちは知っている。それが異能というもので、フミと楽タローも、もちろんオレもこのチリメン雑魚くんたちを蹴散らそうと身構えた。
「よ〜し、かかってきなさい!」
「出し惜しみはナシだ!」
結果から言えば、オレたちは大した苦労もなくそいつらを蹴散らすことができた。知り合ったばかりでチームワークもクソもないし、オレも自分の異能を理解するには程遠いなりに、とりあえず長い脚で蹴りをくれてやる。
「ハッハァ!キスマイアァス」
簡単に蹴散らすと、妖精と雑草の残骸がごろごろと地面に転がっている。緑色の、ゴリラの頭めいたモノが転がっている姿に思うところもあるが、コイツはオレたちを襲ってきた植物のナレノハテだぜ?と自分を説得する。何より、この程度のチャンバラに手間取っているオレたちは、本当にヤバい連中が様子を見ていたことにもまるで気がつけずにいたのだから。
「茜の空に 君は何を見るのか 旅立つ風に 君は何を聞くのか
少年のままで生きているなら その手で明日を掴めるはずさ
チャンバラ チャンバラ 魂よ 魂よ 今燃えろよ
チャンバラ チャンバラ そいつが男達の生きざま」

「いや、私たちそんなの歌ってないから!歌ってないから!」
大事なコトなので二度言われてしまったが、ハザマ世界を通じてこのイバラシティを訪れている連中、アンジニティの連中にいよいよ遭遇してしまったというワケだ。
一人はピンクの髪に砂糖菓子のような甘い匂いをさせている女、一人は頭にネコの耳みたいなヘッドホンを載せている女、一人は右と左の瞳の色が違う小柄な女、そしてもう一人は、どこかのほほんとして見えるメガネの男。一見するとライブハウスあたりにいそうな、ちょっと派手好きな連中にしか見えないが、どいつも身にまとっているふいんき(漢字変換できねーな)がヤバい。わざわざ刃物を持ったナントカに近寄ろうとするのはマヌケのするコトだ。
「なんかさっきから散々言ってくれてるねー。こいつらヤッちゃっていいんだよね?」
「ふーん。じゃあ、どこまで減じられるか、試してみようか」
ピンク髪の女の言葉に、小柄な女が妙な構えをする。コツは心得ている、オレがタイミングを合わせてソイツを「見る」と、小柄な女がわずかに表情を歪める。
「やられたっ」
「ヒャッハー!テメーの技は見切ったぜ!」
異能は封じることができる。もちろん半ばは運だよりだが、この時はうまくいった。だがそれでこの連中に勝てるとは最初から思っていない。ハッキリ言って逃げるために時間稼ぎのつもりだったが、正面から莫迦にされてノンキに逃してくれるほど先方も甘くない。砂糖みたいに甘い匂いをさせていても残念ながら甘くない。
「アマさにトロけて...!」
次の瞬間には、オレたちめがけて火やら稲妻やらが飛んでくる。
* * *
「いや、ひでー目にあったぜ」
「なんかマッケンジーさん、我先に逃げてませんでした?」
フミが不審なモノを見る目を向けている。危なくなったら逃げる、オレがソイツを身をもって実践したからこそ全員が逃げ遅れずに済んだ。戦略的撤退というヤツだとテキトーなことを言ってごまかしておくが、納得しないなりに納得はしてくれたらしい(どっちだよ)。
あれがアンジニティ。このイバラシティに侵略とやらを試みている連中だ。そしてオレたちは連中からこの世界を守るために、ハザマ世界で連中を待ち構えて迎え撃つために集められた。異能とはその資格を持つ者たちに与えられた力。ソイツがこの世界の事情というワケだ。
「いやしかし連中強ぇーだろ」
「強かったですねえ」
のほほんとした口調でソーヤも同意してくれているが、考えてみればコイツは問題だ。アンジニティの連中は、たいていはイバラシティに自分の居場所を探して訪れる。多くがそのつもりでやってきている。対するイバラシティの連中にも、アンジニティからこの世界を守るんだと息巻いてるヤツもいるが、オレたちのように異能があるからという理由で、ワケも分からないままここにやってきた者が少なくない。つまりモチベーションが違う。
「まあ、みんな無事ならヨシとしないとな」
「その通りだぜ。楽タローはモノノドーリというやつが分かっている」
オレの偉そうな言葉に、楽タローも胡散臭げな視線を向けている。オレたちはヤル気マンマンなアンジニティの連中を相手にして、まずは無事に生き残ることを考えながら、少しずつ力をつけていかなければならないらしい。負けて当然、引き分ければ御の字が今のところの方針だ。
だが、やはりそんなこすっからいことを考えているオレこそが呑気なのだ。オレたちが知りもしない場所で、端末に映りもしない場所で、あの南高梅とかいうヤローたちが不穏な会話を交わしている。DAZNサーバがクルクルまわるみてーな不安定な通信の上で、断片的なやりとりだけを拾うことができる。
「おっくれましてーーーッ!!」
「どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな」
「招かれた方々全員がーー」
「周期的に発動する、能力というより・・・」
「制御不能な・・・ザザッ・・・己の世界のために、争え」
こいつがオレたちの置かれている状況というワケだ。襲いかかってくるアンジニティの連中に勝つどころではない。まずは、無事に生き残ることを考えながら、少しずつ力をつけていかなければならない。



ENo.1285 楽タロー とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||



 |
フミ 「みんな、よろしくね!適度にがんばろ~!」 |
 |
マッケンジー 「いや、ヒデー目に遭ったがみんな無事で何よりだ(自分が逃げたことは言わない)」 |
 |
ヨツジ 「お久しぶりです。 ええと、20日ぶりくらいですね。 負けたらもう呼ばれないかと思っていたのですが、そうでもなかったですね」 |
 |
メリさん 「めえ」 今は四辻に抱きかかえられている。 |
 |
ヨツジ 「地元民からすると異能があるのは普通ですが…… いや、ここまで大規模な異能はあまり聞かないですし、ここまで治安は悪くないですけども」 |
 |
ヨツジ 「『魔法使い』は異能名ですね。 名前を付けると、イメージして使いやすくなるので。自分でつけたり、つけてもらったりします。 ……もしかしたら、ローカルルールかもしれませんね」 |
| 楽タロー 「…」 |
| 楽タロー 「またこの場所に放り込まれたけどさ、このハザマって場所、一体どうなってんだ?」 |
| 楽タロー 「異能持ちが普通にいる街ってことは、それがらみの事件も普通にあるんだろーなとは思ってたけど…」 |
| 楽タロー 「こういう場所にしょっちゅう引っ張られて、そんで元の街のほうに戻って…」 |
| 楽タロー 「…その間、元の街の時間ってどうなっちまってるんだろうな?」 |
| 楽タロー 「時間の流れが違うって事は、来るたんびにだんだんズレてったりとかしたら、怖くねえ?」 |
フミ(961) に ItemNo.8 韮 を手渡ししました。





ナツメグ
|
 |
ひつじふかふか
|



呪術LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
料理LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
使役LV を 9 UP!(LV1⇒10、-9CP)
百薬LV を 1 UP!(LV4⇒5、-1CP)
武器LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
フミ(961) の持つ ItemNo.10 韮 から防具『韮の道着』を作製しました!
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『不思議なブルーチーズ』をつくりました!
⇒ 不思議なブルーチーズ/料理:強さ20/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]-/特殊アイテム
 |
マッケンジー 「臭うぜ。」 |
ItemNo.9 美味しい草 から料理『美味しいブルーチーズ』をつくりました!
⇒ 美味しいブルーチーズ/料理:強さ20/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-
 |
マッケンジー 「臭うぜ?」 |
九々之助(154) とカードを交換しました!
鎖の巨人 (サモン:ウォリアー)

ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ファーマシー を研究しました!(深度0⇒1)
ファーマシー を研究しました!(深度1⇒2)
サステイン を習得!
ペレル を習得!
ポイズン を習得!
スコーピオン を習得!
クレイジーチューン を習得!
魅惑 を習得!
チャームダンス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フミ(961) は 花びら を入手!
マッケンジー(1144) は 韮 を入手!
ヨツジ(1231) は 韮 を入手!
楽タロー(1285) は 花びら を入手!
フミ(961) は 毛 を入手!
ヨツジ(1231) は ネジ を入手!
楽タロー(1285) は 不思議な雫 を入手!
ヨツジ(1231) は ネジ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
マッケンジー(1144) のもとに ヤンキー が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調16⇒15)
採集はできませんでした。
- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







ひつじふかふか
|
 |
蛇ノ目堂古書店住民組合
|


ENo.1144
新沼ケンジ(しんぬま・けんじ)



チバ県マッドシティで開業している探偵。
差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。
能力は「ハト魔法使い」。
差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。
能力は「ハト魔法使い」。
15 / 30
87 PS
チナミ区
I-14
I-14




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ジャミングアーム | 魔晶 | 17 | 体力10 | - | 充填5 | |
| 5 | ケブラーベスト | 防具 | 15 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議なブルーチーズ | 料理 | 20 | 器用10 | 敏捷10 | - | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]体力10(LV10)[装飾]増勢10(LV25) | |||
| 9 | 美味しいブルーチーズ | 料理 | 20 | 治癒10 | - | - | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 10 | 武器作製に影響 |
| 防具 | 10 | 防具作製に影響 |
| 料理 | 10 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| 決3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| チャームダンス | 5 | 0 | 140 | 敵全:魅了 | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 2 ]ファーマシー | [ 3 ]ウィルスゾーン |

PL / TOSHIKI