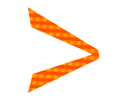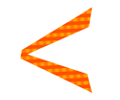<< 0:00~1:00





『ある兵士の手記』 兎斬雫
3020年6月5日 初版発行
訳者 日月 敦
いまのわたしのじかんは、みなのためのものだから、みなのことをにっきにかいていこうとおもう。
ぜんいんは、とてもかききれないから、とくにきおくにのこっているひとだけを、かいていこうとおもう……
訳者はしがき
「兎斬雫手記」が発見されてから既に10年以上の歳月が流れた。
その手記は、帝歴225年(2263年)頃という終末戦争真っただ中における戦地の状況を知るための資料として、学者に広まった。私は手記について研究を重ねてきたが、手記を単なる研究材料とするには惜しいように思われた。そこで以前より懇意にさせていただいている編集のアレクシス・トマス氏に現代語訳版を出版する話を持ち掛けたところ、幸いにも賛同が得られ、氏の尽力によってこの度本書を皆さまの手にお届けできるに至った。トマス氏には重ねて感謝申し上げる次第である。
本書については、「兎斬雫手記」の内容を分かりやすくお伝えすることを心掛けた。もし分かりづらいところがあれば、それはひとえに私の責任である。
また、「兎斬雫手記」は正式な名称ではなく、学者の中でのみ通用している便宜上の名前である。手記には、当然のことながら題名が付されていない。そのため、本書を出版するにあたり題を何とするかは頭を悩ませたところである。これについては作家のミルヤミ・サミドリ氏よりアイディアをいただいた。お忙しい中相談に乗っていただいたサミドリ氏には心より感謝申し上げる。
3020年1月 雪降るタウティカの研究室にて

アイリス姉……アイリスと初めて出会ったのは、帝歴225年の9月頃で、わたしは12歳だった(ということになっていた。※1)。わたしが隊長※2の部隊に参加して初めての戦場が終わった後だった。アイリスは補充人員のうちの一人だった。もとは東方の半妖※3部隊にいたらしいが、アイリスとほか数人とを除いてみな戦死するか退役するかしてしまったため、元の部隊と同じくほぼ半妖しかいないこの部隊に回されてきたらしかった。着任のあいさつで、寒いところは不慣れで、と笑っていたことをよく覚えている。
彼女には元々名前がなく、アイリスという名前は軍隊に入った後で隊の仲間に付けてもらった名前だと聞いた※4。4月5日に入隊したから、その日の誕生花から取って、アイリス。部隊の皆も彼女自身も、そこまで考えていなかったし、知らなかったようだけど、アイリスの花言葉は「吉報」というもので、衛生兵の彼女にはぴったりのものだった。
アイリスは、わたしと同じく、半妖としてはまだマシな方……見た目が人間に近い方だった。人間との違いは、右目が石のように硬く視力がないことと、両手の上腕から先の部分が異常に膨らんでいて、人間の何倍もの大きさがあり、大きさに違わず力持ちなことだった。どのくらい大きいかというと、普通の人間が両手で他の人間の顔を挟むと、せいぜいがほっぺたを押しつぶすことができるくらいだが、アイリスは頭をすっかり包んで握ることができ、しかもそのまま握りつぶしてしまえるほどだった。しかし、その膨らんだ両手のせいで武器を扱うことができず、戦闘要員ではなく衛生兵に回されたらしかった。
アイリスは部隊の中では年上の方で、優しく、穏やかで、そして勇敢だった。銃弾がひっきりなしに飛び交い続ける戦場の中で、負傷して動けなくなっている兵を見つけては、銃弾の合間を縫うようにして塹壕から飛び出して救助しに行った。それも何度もだ。ときどき、自分も重傷を負って帰ってくることはあったが、彼女が帰ってくるときは決まって一人以上を連れて帰ってきていた。それも、その人が担いでいた装備も込みで、だ。彼女に戦場から助けられた子は多くいて、その子たちが彼女のことを「アイリス姉」と呼んで慕うものだから、その呼び方が隊の中でも定着した。わたしもそう呼んでいた。アイリスはわたしたちの中隊に加わったとき、既に曹長だったけど、わたしたちの隊の中では階級なんて関係がなかったし、彼女もアイリス姉という呼び方を受け入れていた。
実際に、アイリスは皆の姉のようだった。新兵が恐怖でパニックに陥って、彼女が抱きしめて落ち着かせたことは一度や二度ではなかった。彼女は体も、心も温かかった。その温かさに触れると、不安が和らいでくる……
わたしも、彼女に助けられた一人だ。帝歴226年の1月頃、わたしはチュプト防衛戦※5で敵の一斉射撃に遭って、退却中に運悪く銃弾を左足の膝下のあたりに一発食って動けなくなってしまった。仲間は後方の塹壕に退却してしまって、そこまでは結構な距離があった。
足からは大量の血が流れだしていた。わたしは、左足の付け根に止血帯を付けて、偶然近くにあったコンクリート壁(おそらく、建物の一部ではないかと思う。)の後ろに転がり込んで遮蔽を取った。服を切って傷口を見ると、わたしの左足には表と裏に穴が開いていて、銃弾は貫通したようだったが骨は無事ではなさそうだった。後で教えてもらったことだけれど、その銃弾のせいでわたしの左足の骨は砕けていたらしい。わたしは止血方法をバンテージに切り替えて、それでうまく血が止まってくれたので、止血帯を緩めることができた。
相変わらず銃弾は飛び交っていて、後方の塹壕まで手で這っていけば、その間にもう何発かとびきりの銃弾をプレゼントされるであろうことは目に見えていた。足が一本使えないと、とにかくスピードが出ないし、白一色の景色の中でわたしの血の色は目立ってしまう。かといって、ここでいつまでもじっとしているわけにはいかなかった。わたしの足は銃弾で歪な穴が空いていて感染症の危険もあった。溢れた血と漏れたおしっこですっかり湿ったズボンは、外気に冷やされ凍ってわたしの肌をひどく突き刺していて、凍傷も放っておくわけにはいかなかった。もし相手の前線が上がってくれば、逃げることのできないわたしは上手く死体のフリができなければ死ぬしかなかった。
わたしが、可能性にかけて味方の塹壕まで這っていこうと決意したとき、目指すべき方向から一人の兵が身を低くして、四足歩行でこちらに向かってきているのが見えた。アイリスだった。彼女はわたしのところまで銃弾の中をやってきてくれて、血を失って苦しそうにしているわたしを「もう大丈夫」と言って抱きしめてくれた。この時ほど彼女の大きな手が頼もしく見えたことはなかった。彼女はわたしの左足を手早く固定すると、その大きな左手で汚くなっていたわたしを抱きかかえて、身を低くして走り出した。左手はわたしを支えるのに使っているから右手と両足の三足歩行になっていたが、彼女の大きな大きな手は一本しか使えなくてもその体のバランスを失うことはなかった。
わたしはアイリスに運んでもらって、仲間のところへたどり着いた。仲間の顔に囲まれて、わたしは泣いた……
わたしは、アイリスに救われた351人目の兵になったと、後方移送の前に彼女から教えてもらった。彼女は自分が助けた兵を全て記憶していた。どうして、と尋ねると、彼女は恥ずかしそうに笑って「生きていてくれたことが嬉しいから」と答えた。幸いわたしの傷は軽く、砕けた骨片を取り除けば後は何とかなる程度だった。わたしはそう時間が経たないうちに戦線に復帰した。しかし、わたしが復帰したときには既にアイリスはいなくなっていた。彼女はわたしの後にさらに2人を助け、そして354人目を救おうと戦場に飛び出していったが、それきり帰ってこなかった……彼女の救助記録は353人から永久に動かなくなってしまった。そして、わたしたちは、アイリスがいないまま戦線を離れることになった……
後から聞いた話では、わたしたちの後続部隊が反撃に転じ敵の拠点を攻め落としたとき、アイリスの死体が見つかったそうだ。両方の目玉はくりぬかれ、綺麗な石のような右目は砕かれていた。胸は切り落とされ、色々な暴行の後があった。そして、なにより彼女の大きな両腕が切り落とされていたようだった。彼女のあの優しく温かくたくましい両手を切り落とすなんて、こんなむごい仕打ちがあるだろうか。たくさんの仲間の命と心を救ってきたあの大きな手を。
わたしは今でも鮮明に思い出すことができる。彼女の手の大きさを、温かさを。彼女の手に包まれたときのあの安心感を……アイリス姉……
※1
当時、遺伝子変異が起きた者については戸籍届出がなされないことが一般的であった。兎斬雫は、軍の記録上1月3日生まれの除隊時14歳となっているが、正確な記録ではないと思われる。
※2
Francisca Neves Silva(2248~2265)のこと。兎斬雫はいくつかの隊に所属していたが、帝歴225年9月頃に所属していたのはFrancisnaが隊長を務める北方第1341独立歩兵中隊であった。この中隊は遺伝子変異が起きた者のみを集めた、当時の言葉で言うところの「半妖部隊」であった。独立となっているのもそのためであろう。
※3
遺伝子変異が起きた者の蔑称。当時は、様々な面において通常人とは異なる扱いを受けていた。
※4
当時、遺伝子変異が起きた者については、名前がなく番号などで呼ばれることが珍しいことではなかったようである。
※5
第四次チュプト防衛戦(2263年12月~2264年2月)。この時期のチュプトは平均気温がマイナス20度程度で、極寒の中での戦いであった。

「……もう大丈夫。戻りましょう、みんなのところへ……」



ENo.26 ラプリナ とのやりとり

ENo.55 ゆい とのやりとり

ENo.70 金鵄 とのやりとり

ENo.141 れーこ とのやりとり

ENo.334 ひまわり&ナナシ とのやりとり

ENo.448 スターシャ とのやりとり

以下の相手に送信しました












リミュ(411) に 5 PS 送付しました。
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
アーテル(126) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
リミュ(411) により ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
ゆい(55) により ItemNo.1 駄物 から装飾『ティアーズオブシルキークォーツ』を作製してもらいました!
⇒ ティアーズオブシルキークォーツ/装飾:強さ35/[効果1]- [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
リュジアプローシ(1224) の持つ ItemNo.1 駄物 から射程1の武器『虚像のカノプス』を作製しました!
こぐさ(40) の持つ ItemNo.1 駄物 から射程2の武器『鎮守の勾玉』を作製しました!
ゆい(55) の持つ ItemNo.1 駄物 から射程1の武器『短刀『赤糸』』を作製しました!
エネ&ギイ(336) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『軍隊ブーツ』を作製してもらいました!
⇒ 軍隊ブーツ/武器:強さ35/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
無名(789) により ItemNo.5 不思議な石 から防具『防寒服』を作製してもらいました!
⇒ 防寒服/防具:強さ35/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
▒▜▮▒▓▝(530) とカードを交換しました!
【泥寧の夢】 (クリエイト:シールド)


ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
ハードブレイク を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
ボロウライフ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



こぐさ(40) は 吸い殻 を入手!
ゆい(55) は 吸い殻 を入手!
雫(134) は 美味しくない草 を入手!
マナカナ(145) は 美味しくない草 を入手!
マナカナ(145) は ねばねば を入手!
マナカナ(145) は 不思議な石 を入手!
ゆい(55) は 不思議な石 を入手!
こぐさ(40) は ねばねば を入手!



ゆい(55) に移動を委ねました。
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-7(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 K-7(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 L-7(森林)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




『ある兵士の手記』 兎斬雫
3020年6月5日 初版発行
訳者 日月 敦
いまのわたしのじかんは、みなのためのものだから、みなのことをにっきにかいていこうとおもう。
ぜんいんは、とてもかききれないから、とくにきおくにのこっているひとだけを、かいていこうとおもう……
訳者はしがき
「兎斬雫手記」が発見されてから既に10年以上の歳月が流れた。
その手記は、帝歴225年(2263年)頃という終末戦争真っただ中における戦地の状況を知るための資料として、学者に広まった。私は手記について研究を重ねてきたが、手記を単なる研究材料とするには惜しいように思われた。そこで以前より懇意にさせていただいている編集のアレクシス・トマス氏に現代語訳版を出版する話を持ち掛けたところ、幸いにも賛同が得られ、氏の尽力によってこの度本書を皆さまの手にお届けできるに至った。トマス氏には重ねて感謝申し上げる次第である。
本書については、「兎斬雫手記」の内容を分かりやすくお伝えすることを心掛けた。もし分かりづらいところがあれば、それはひとえに私の責任である。
また、「兎斬雫手記」は正式な名称ではなく、学者の中でのみ通用している便宜上の名前である。手記には、当然のことながら題名が付されていない。そのため、本書を出版するにあたり題を何とするかは頭を悩ませたところである。これについては作家のミルヤミ・サミドリ氏よりアイディアをいただいた。お忙しい中相談に乗っていただいたサミドリ氏には心より感謝申し上げる。
3020年1月 雪降るタウティカの研究室にて

アイリス
衛生准尉
多数の軍人生命を守りたる功績により功六級勲章授与
第四次チュプト防衛戦において戦死
多数の軍人生命を守りたる功績により功六級勲章授与
第四次チュプト防衛戦において戦死
アイリス姉……アイリスと初めて出会ったのは、帝歴225年の9月頃で、わたしは12歳だった(ということになっていた。※1)。わたしが隊長※2の部隊に参加して初めての戦場が終わった後だった。アイリスは補充人員のうちの一人だった。もとは東方の半妖※3部隊にいたらしいが、アイリスとほか数人とを除いてみな戦死するか退役するかしてしまったため、元の部隊と同じくほぼ半妖しかいないこの部隊に回されてきたらしかった。着任のあいさつで、寒いところは不慣れで、と笑っていたことをよく覚えている。
彼女には元々名前がなく、アイリスという名前は軍隊に入った後で隊の仲間に付けてもらった名前だと聞いた※4。4月5日に入隊したから、その日の誕生花から取って、アイリス。部隊の皆も彼女自身も、そこまで考えていなかったし、知らなかったようだけど、アイリスの花言葉は「吉報」というもので、衛生兵の彼女にはぴったりのものだった。
アイリスは、わたしと同じく、半妖としてはまだマシな方……見た目が人間に近い方だった。人間との違いは、右目が石のように硬く視力がないことと、両手の上腕から先の部分が異常に膨らんでいて、人間の何倍もの大きさがあり、大きさに違わず力持ちなことだった。どのくらい大きいかというと、普通の人間が両手で他の人間の顔を挟むと、せいぜいがほっぺたを押しつぶすことができるくらいだが、アイリスは頭をすっかり包んで握ることができ、しかもそのまま握りつぶしてしまえるほどだった。しかし、その膨らんだ両手のせいで武器を扱うことができず、戦闘要員ではなく衛生兵に回されたらしかった。
アイリスは部隊の中では年上の方で、優しく、穏やかで、そして勇敢だった。銃弾がひっきりなしに飛び交い続ける戦場の中で、負傷して動けなくなっている兵を見つけては、銃弾の合間を縫うようにして塹壕から飛び出して救助しに行った。それも何度もだ。ときどき、自分も重傷を負って帰ってくることはあったが、彼女が帰ってくるときは決まって一人以上を連れて帰ってきていた。それも、その人が担いでいた装備も込みで、だ。彼女に戦場から助けられた子は多くいて、その子たちが彼女のことを「アイリス姉」と呼んで慕うものだから、その呼び方が隊の中でも定着した。わたしもそう呼んでいた。アイリスはわたしたちの中隊に加わったとき、既に曹長だったけど、わたしたちの隊の中では階級なんて関係がなかったし、彼女もアイリス姉という呼び方を受け入れていた。
実際に、アイリスは皆の姉のようだった。新兵が恐怖でパニックに陥って、彼女が抱きしめて落ち着かせたことは一度や二度ではなかった。彼女は体も、心も温かかった。その温かさに触れると、不安が和らいでくる……
わたしも、彼女に助けられた一人だ。帝歴226年の1月頃、わたしはチュプト防衛戦※5で敵の一斉射撃に遭って、退却中に運悪く銃弾を左足の膝下のあたりに一発食って動けなくなってしまった。仲間は後方の塹壕に退却してしまって、そこまでは結構な距離があった。
足からは大量の血が流れだしていた。わたしは、左足の付け根に止血帯を付けて、偶然近くにあったコンクリート壁(おそらく、建物の一部ではないかと思う。)の後ろに転がり込んで遮蔽を取った。服を切って傷口を見ると、わたしの左足には表と裏に穴が開いていて、銃弾は貫通したようだったが骨は無事ではなさそうだった。後で教えてもらったことだけれど、その銃弾のせいでわたしの左足の骨は砕けていたらしい。わたしは止血方法をバンテージに切り替えて、それでうまく血が止まってくれたので、止血帯を緩めることができた。
相変わらず銃弾は飛び交っていて、後方の塹壕まで手で這っていけば、その間にもう何発かとびきりの銃弾をプレゼントされるであろうことは目に見えていた。足が一本使えないと、とにかくスピードが出ないし、白一色の景色の中でわたしの血の色は目立ってしまう。かといって、ここでいつまでもじっとしているわけにはいかなかった。わたしの足は銃弾で歪な穴が空いていて感染症の危険もあった。溢れた血と漏れたおしっこですっかり湿ったズボンは、外気に冷やされ凍ってわたしの肌をひどく突き刺していて、凍傷も放っておくわけにはいかなかった。もし相手の前線が上がってくれば、逃げることのできないわたしは上手く死体のフリができなければ死ぬしかなかった。
わたしが、可能性にかけて味方の塹壕まで這っていこうと決意したとき、目指すべき方向から一人の兵が身を低くして、四足歩行でこちらに向かってきているのが見えた。アイリスだった。彼女はわたしのところまで銃弾の中をやってきてくれて、血を失って苦しそうにしているわたしを「もう大丈夫」と言って抱きしめてくれた。この時ほど彼女の大きな手が頼もしく見えたことはなかった。彼女はわたしの左足を手早く固定すると、その大きな左手で汚くなっていたわたしを抱きかかえて、身を低くして走り出した。左手はわたしを支えるのに使っているから右手と両足の三足歩行になっていたが、彼女の大きな大きな手は一本しか使えなくてもその体のバランスを失うことはなかった。
わたしはアイリスに運んでもらって、仲間のところへたどり着いた。仲間の顔に囲まれて、わたしは泣いた……
わたしは、アイリスに救われた351人目の兵になったと、後方移送の前に彼女から教えてもらった。彼女は自分が助けた兵を全て記憶していた。どうして、と尋ねると、彼女は恥ずかしそうに笑って「生きていてくれたことが嬉しいから」と答えた。幸いわたしの傷は軽く、砕けた骨片を取り除けば後は何とかなる程度だった。わたしはそう時間が経たないうちに戦線に復帰した。しかし、わたしが復帰したときには既にアイリスはいなくなっていた。彼女はわたしの後にさらに2人を助け、そして354人目を救おうと戦場に飛び出していったが、それきり帰ってこなかった……彼女の救助記録は353人から永久に動かなくなってしまった。そして、わたしたちは、アイリスがいないまま戦線を離れることになった……
後から聞いた話では、わたしたちの後続部隊が反撃に転じ敵の拠点を攻め落としたとき、アイリスの死体が見つかったそうだ。両方の目玉はくりぬかれ、綺麗な石のような右目は砕かれていた。胸は切り落とされ、色々な暴行の後があった。そして、なにより彼女の大きな両腕が切り落とされていたようだった。彼女のあの優しく温かくたくましい両手を切り落とすなんて、こんなむごい仕打ちがあるだろうか。たくさんの仲間の命と心を救ってきたあの大きな手を。
わたしは今でも鮮明に思い出すことができる。彼女の手の大きさを、温かさを。彼女の手に包まれたときのあの安心感を……アイリス姉……
※1
当時、遺伝子変異が起きた者については戸籍届出がなされないことが一般的であった。兎斬雫は、軍の記録上1月3日生まれの除隊時14歳となっているが、正確な記録ではないと思われる。
※2
Francisca Neves Silva(2248~2265)のこと。兎斬雫はいくつかの隊に所属していたが、帝歴225年9月頃に所属していたのはFrancisnaが隊長を務める北方第1341独立歩兵中隊であった。この中隊は遺伝子変異が起きた者のみを集めた、当時の言葉で言うところの「半妖部隊」であった。独立となっているのもそのためであろう。
※3
遺伝子変異が起きた者の蔑称。当時は、様々な面において通常人とは異なる扱いを受けていた。
※4
当時、遺伝子変異が起きた者については、名前がなく番号などで呼ばれることが珍しいことではなかったようである。
※5
第四次チュプト防衛戦(2263年12月~2264年2月)。この時期のチュプトは平均気温がマイナス20度程度で、極寒の中での戦いであった。

「……もう大丈夫。戻りましょう、みんなのところへ……」



ENo.26 ラプリナ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.55 ゆい とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.70 金鵄 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.141 れーこ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.334 ひまわり&ナナシ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.448 スターシャ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



| ゆい 「これだけ人数いればきっと大丈夫、さ、すすも。」 |
| 雫 「征きましょう、戦いへ。駆けましょう、戦いを」 |
 |
カナ 「……行こうか、皆」 |







リミュ(411) に 5 PS 送付しました。
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
アーテル(126) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
 |
アーテル 「纏めて一つにしちまおうな。」 |
リミュ(411) により ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
| リミュ 「こねこねはぼくにおまかせ!」 |
ゆい(55) により ItemNo.1 駄物 から装飾『ティアーズオブシルキークォーツ』を作製してもらいました!
⇒ ティアーズオブシルキークォーツ/装飾:強さ35/[効果1]- [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
| ゆい 「これから、一緒に頑張ろうね。 少しでも癒しになりますよーに。」 |
リュジアプローシ(1224) の持つ ItemNo.1 駄物 から射程1の武器『虚像のカノプス』を作製しました!
こぐさ(40) の持つ ItemNo.1 駄物 から射程2の武器『鎮守の勾玉』を作製しました!
ゆい(55) の持つ ItemNo.1 駄物 から射程1の武器『短刀『赤糸』』を作製しました!
エネ&ギイ(336) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『軍隊ブーツ』を作製してもらいました!
⇒ 軍隊ブーツ/武器:強さ35/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
| ギイ 「コレモ、武器トイエバ武器デスカ。」 |
無名(789) により ItemNo.5 不思議な石 から防具『防寒服』を作製してもらいました!
⇒ 防寒服/防具:強さ35/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
八百城/満月 「無いよりはマシだろう。よければ使うといい。」 |
▒▜▮▒▓▝(530) とカードを交換しました!
【泥寧の夢】 (クリエイト:シールド)


ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
ハードブレイク を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
ボロウライフ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



こぐさ(40) は 吸い殻 を入手!
ゆい(55) は 吸い殻 を入手!
雫(134) は 美味しくない草 を入手!
マナカナ(145) は 美味しくない草 を入手!
マナカナ(145) は ねばねば を入手!
マナカナ(145) は 不思議な石 を入手!
ゆい(55) は 不思議な石 を入手!
こぐさ(40) は ねばねば を入手!



ゆい(55) に移動を委ねました。
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-7(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 K-7(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 L-7(森林)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――









ENo.134
鷺内雫



----------《ハザマSide》----------
名前:兎斬 雫(うさぎり しずく) 性別:女性
年齢:推定14歳 誕生日:不明(名目上は1月3日)
身長:156cm 体重:52kg
イバラシティの出身でもなく、
アンジニティに堕ちた存在でもない。
遺伝子変異により人ならざる姿と能力を得た「半妖」。
彼女の世界で、半妖には人権がなくひどく差別されていた。
彼女は身体能力と感覚に優れ、体の動作の制御に優れる。
彼女が人権と引き換えに得た能力はそれだけであった。
人間であっても鍛錬次第でほぼ到達可能な域であった。
魔法やPSIといった人間離れした能力は、彼女にはない。
彼女は、元々の世界では軍人をしていた。
半妖は軍隊でも一部を除いて使いつぶされる存在だった。
年齢の割には多くの戦場を渡り歩き、そして衰弱死した。
死出の旅路の途中、彼女は侵略の影響に巻き込まれ、
ハザマで再び肉体を得て、侵略に参加することとなった。
侵略の成否にこだわりはない。
こだわったところでどうにもならないということを知っている。
彼女は、戦場において果たすべき役割を果たすだけだ。
----------《イバラシティSide》----------
【メインキャラ】(アイコン:0~9)
名前:鷺内 雫(さぎうち しずく) 性別:女性
年齢:14歳 誕生日:1月3日
身長:156cm 体重:52kg
所属:イバラ創藍高校中等部二年生
好き:肉、甘味、炭酸水、歌 嫌い:孤独、雪
異能:《獣憑き》
獣耳や尻尾など、変異が生じる代わりに身体能力が向上する。
異能者の意志にかかわらず常時発動する。
性格:穏やかで優しい。比較的常識人寄り。
小学校時代を私立星しろつめ学園で過ごす。
亡くなった母親がイバラ創藍高校OGであるため、
イバラ創藍高校中等部へ進学、現在に至る。
成績はとても良くない。運動はとても得意。しかし泳げない。
歌は好きだが、特定の歌以外の歌を覚えられない。
異常な大食いで、六人分くらいはぺろりと食べる。
家業の手伝いをしている。
※家業→まんぷく精肉鷺内
(http://lisge.com/ib/talk.php?s=367)
(補足)
・テストプレイ時の出来事は基本的に覚えています。
ですが自分の苗字や住所が変わっていることに
違和感は覚えていません。
・既知設定歓迎。それっぽく話しかけてください。
_____________________
【サブキャラ】(アイコン:10~19)
名前:六徳堂 慈(りっとくどう いつき) 性別:男性
年齢:12歳 誕生日:6月10日
身長:140cm 体重:35kg
所属:イバラ創藍高校初等部六年生
好き:味噌汁、楽しいこと 嫌い:悲しいこと
異能:《時の檻》
自分以外の時間を止める。
性格:まっすぐで明るい。元気でへこたれない。
イバラシティ外で生まれ育った異能持ち。
祖父の寺に住み異能を制御する訓練をしている。
※住居→譱穰寺
(http://lisge.com/ib/talk.php?s=504)
_____________________
【その他サブキャラ】(アイコン:20~29)
メインキャラのソロール用が主です。
_____________________
交流歓迎ですが、置きレスが多めになると思います。
それでもよろしければお付き合いいただけるとありがたいです。
名前:兎斬 雫(うさぎり しずく) 性別:女性
年齢:推定14歳 誕生日:不明(名目上は1月3日)
身長:156cm 体重:52kg
イバラシティの出身でもなく、
アンジニティに堕ちた存在でもない。
遺伝子変異により人ならざる姿と能力を得た「半妖」。
彼女の世界で、半妖には人権がなくひどく差別されていた。
彼女は身体能力と感覚に優れ、体の動作の制御に優れる。
彼女が人権と引き換えに得た能力はそれだけであった。
人間であっても鍛錬次第でほぼ到達可能な域であった。
魔法やPSIといった人間離れした能力は、彼女にはない。
彼女は、元々の世界では軍人をしていた。
半妖は軍隊でも一部を除いて使いつぶされる存在だった。
年齢の割には多くの戦場を渡り歩き、そして衰弱死した。
死出の旅路の途中、彼女は侵略の影響に巻き込まれ、
ハザマで再び肉体を得て、侵略に参加することとなった。
侵略の成否にこだわりはない。
こだわったところでどうにもならないということを知っている。
彼女は、戦場において果たすべき役割を果たすだけだ。
----------《イバラシティSide》----------
【メインキャラ】(アイコン:0~9)
名前:鷺内 雫(さぎうち しずく) 性別:女性
年齢:14歳 誕生日:1月3日
身長:156cm 体重:52kg
所属:イバラ創藍高校中等部二年生
好き:肉、甘味、炭酸水、歌 嫌い:孤独、雪
異能:《獣憑き》
獣耳や尻尾など、変異が生じる代わりに身体能力が向上する。
異能者の意志にかかわらず常時発動する。
性格:穏やかで優しい。比較的常識人寄り。
小学校時代を私立星しろつめ学園で過ごす。
亡くなった母親がイバラ創藍高校OGであるため、
イバラ創藍高校中等部へ進学、現在に至る。
成績はとても良くない。運動はとても得意。しかし泳げない。
歌は好きだが、特定の歌以外の歌を覚えられない。
異常な大食いで、六人分くらいはぺろりと食べる。
家業の手伝いをしている。
※家業→まんぷく精肉鷺内
(http://lisge.com/ib/talk.php?s=367)
(補足)
・テストプレイ時の出来事は基本的に覚えています。
ですが自分の苗字や住所が変わっていることに
違和感は覚えていません。
・既知設定歓迎。それっぽく話しかけてください。
_____________________
【サブキャラ】(アイコン:10~19)
名前:六徳堂 慈(りっとくどう いつき) 性別:男性
年齢:12歳 誕生日:6月10日
身長:140cm 体重:35kg
所属:イバラ創藍高校初等部六年生
好き:味噌汁、楽しいこと 嫌い:悲しいこと
異能:《時の檻》
自分以外の時間を止める。
性格:まっすぐで明るい。元気でへこたれない。
イバラシティ外で生まれ育った異能持ち。
祖父の寺に住み異能を制御する訓練をしている。
※住居→譱穰寺
(http://lisge.com/ib/talk.php?s=504)
_____________________
【その他サブキャラ】(アイコン:20~29)
メインキャラのソロール用が主です。
_____________________
交流歓迎ですが、置きレスが多めになると思います。
それでもよろしければお付き合いいただけるとありがたいです。
21 / 30
20 PS
チナミ区
L-7
L-7

















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | ティアーズオブシルキークォーツ | 装飾 | 35 | - | - | - | |
| 2 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]耐疫10(LV30)[防具]体力10(LV30)[装飾]強靭10(LV30) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 剣鉈 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 防寒服 | 防具 | 35 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 軍隊ブーツ | 武器 | 35 | 治癒10 | - | - | 【射程1】 |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 20 | 呪詛/邪気/闇 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 月虹 (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 白雪 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 花間 (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 飛英 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 空明 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 真椿 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 雪風 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 盈月 (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 灰雪 (カース) | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| 回雪 (ダークネス) | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| 白魔 (ダウンフォール) | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 挺身 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 狂風 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 散華 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 金剛 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 旗雲 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 剛毅 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 水影 (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 瑞雪霏霏 (闇の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]イレイザー | [ 3 ]ハードブレイク |

PL / そめいろ