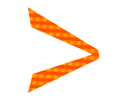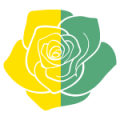<< 0:00~1:00




悲鳴にどよめき、響くサイレンの音、打ち付けられた体が痛くて、頬に触れるのは鉄臭くて生暖かい、
「──命、私の傍から決して離れないでね?」
「分かってますよ、……こんなところで迷子なんて、絶対嫌です」
目の前の荒れ果てた風景は、いやに昔の記憶を刺激して、気持ちが悪い。
Ⅱ.午後の微睡み
玄関の扉を開けばまず目の前に飛び込んできたのは人差し指を立てて口に当てている彼女の姿だった。
少し驚いてはしまうけれど、たまにあることなので大きな声は出さずに静かに扉を閉める。
声量は抑えていつもの挨拶を口にすれば、彼女は満足そうに頷いた。
それから靴を脱いで廊下を歩くときも物音はあまり立てないように気を付けて、リビングへと続く扉もまた静かに開けば。
見えたのはソファに横たわっているこの家の主の姿。毛布やブランケットをかけることもなくすやすやと寝息を立てては穏やかに眠っている。
先ほど自分を出迎えてくれた彼女はするりと横を抜けてゆっくりとソファに近づいては、しゃがみこんでその寝顔に微笑んでいた。
おんなじようにおれも歩み寄って、背凭れの側から寝顔を見下ろした。胸に沸いたのはよく寝ているな、という見たままの感想である。
安堵していることも、また事実なのだが。
──先生に病名をつけるなら色々と挙げられそうだが、まあまず不眠症であることには間違いなかった。
寝付きが悪い、眠りも浅い、かといって日中は睡眠不足であることを尾首にも出しやしない、ので質が悪い。
無理をしていても知る術がないので、たまに電源が切れたようにこうやって寝ているのだ。それもたまに。
リビングのテーブルの上にはオルゴールが一つ置いている。
何週間か前に、雑貨屋で買ってきたと機嫌良く報告されて、言われるがままに共に作ったもの。
余程気に入っているのか一人でも鳴らしていたらしい、それがよい子守唄になったようだ。
これでも、おれが来てからマシになったのだと本人は話していた。
三十にもなるくせに一人が嫌いな男は、寝るときも一人だとうまく眠れない。もう自分も高校生なのだし抱き枕にされる日々は少し恥ずかしさがあるというものだが、ちょっとの我慢で先生の健康が少しでも保たれるなら、と思ってしまうのは甘やかしてしまっているのだろうか。
なんというか、一回りも違うくせに、どっちが子供なのかたまに分からない。
ぼんやりと寝顔をそのまま見下ろしていたら、白くて細い指先が色の薄い髪を撫でていた。
何か、言っているのだと思う。というよりは口の動き的に、歌っている。
それでも彼女の声はおれには聞こえない。おれ自身の問題、というよりは、彼女自身の問題なのだろう。
見えるだけでなくて他のよくわからないものたちの声や音を拾うことは一応できるのだ。というか、否応なしに耳につくのが日常だ。
だから口を開いていても音が聞こえないのは、彼女に声が無いからだろう。生前からそうだったのか、死んでからなのかはわからないけれど。
傍から見てもわかるぐらい、彼女は先生のことをすごく気にかけていた。
それがおれだけに見えていて、本人には何も分からない、というのは少し胸が締め付けられるような心地がしてしまう。
だってこうやって彼女が届けたい歌も、先生には何も聞こえないのだ。撫でているというのだって、おれにしか分からない。
おれの視界にはどちらも間違いなく在るというのに、二人の間にはどうしたって埋まらない境界があるのだ。
こういう気持ちをもどかしいと表現すれば適切だろうか。何かしてあげたいような気もして、けれどできることなんて大して何もない。
今できることだって、物音を立てず覚醒させず、幸せそうな彼女の一時を守るぐらいだろうか。
あとはプラスアルファ。溜息を吐いて、こっそり心の中で悪態を吐く。
晩御飯の準備があるので彼女には申し訳ないが三十分も経てば作り始めよう、そんなことを考えながら。



ENo.147 ヨシノ とのやりとり

ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり

ENo.421 エインモーネ とのやりとり

ENo.1159 万智花 とのやりとり




ItemNo.6 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。









使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
アッシュ(283) とカードを交換しました!
惑わずの一撃 (イレイザー)

アイシクルランス を研究しました!(深度0⇒1)
アイシクルランス を研究しました!(深度1⇒2)
アイシクルランス を研究しました!(深度2⇒3)
サステイン を習得!
ライフリンク を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



一海(853) は 何かの殻 を入手!
斎(1033) は 何かの殻 を入手!
万智花(1159) は ボロ布 を入手!
ヒシュ(1202) は 何かの殻 を入手!
一海(853) は 甲殻 を入手!
斎(1033) は 羽 を入手!
斎(1033) は 甲殻 を入手!
万智花(1159) は 何か柔らかい物体 を入手!



万智花(1159) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 一海(853) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ヒシュ(1202) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



悲鳴にどよめき、響くサイレンの音、打ち付けられた体が痛くて、頬に触れるのは鉄臭くて生暖かい、
「──命、私の傍から決して離れないでね?」
「分かってますよ、……こんなところで迷子なんて、絶対嫌です」
目の前の荒れ果てた風景は、いやに昔の記憶を刺激して、気持ちが悪い。
Ⅱ.午後の微睡み
 |
「────」 |
玄関の扉を開けばまず目の前に飛び込んできたのは人差し指を立てて口に当てている彼女の姿だった。
少し驚いてはしまうけれど、たまにあることなので大きな声は出さずに静かに扉を閉める。
 |
「……ただいま」 |
声量は抑えていつもの挨拶を口にすれば、彼女は満足そうに頷いた。
それから靴を脱いで廊下を歩くときも物音はあまり立てないように気を付けて、リビングへと続く扉もまた静かに開けば。
 |
(──ああ、やっぱりか) |
見えたのはソファに横たわっているこの家の主の姿。毛布やブランケットをかけることもなくすやすやと寝息を立てては穏やかに眠っている。
先ほど自分を出迎えてくれた彼女はするりと横を抜けてゆっくりとソファに近づいては、しゃがみこんでその寝顔に微笑んでいた。
おんなじようにおれも歩み寄って、背凭れの側から寝顔を見下ろした。胸に沸いたのはよく寝ているな、という見たままの感想である。
安堵していることも、また事実なのだが。
──先生に病名をつけるなら色々と挙げられそうだが、まあまず不眠症であることには間違いなかった。
寝付きが悪い、眠りも浅い、かといって日中は睡眠不足であることを尾首にも出しやしない、ので質が悪い。
無理をしていても知る術がないので、たまに電源が切れたようにこうやって寝ているのだ。それもたまに。
リビングのテーブルの上にはオルゴールが一つ置いている。
何週間か前に、雑貨屋で買ってきたと機嫌良く報告されて、言われるがままに共に作ったもの。
余程気に入っているのか一人でも鳴らしていたらしい、それがよい子守唄になったようだ。
 |
「…………」 |
これでも、おれが来てからマシになったのだと本人は話していた。
三十にもなるくせに一人が嫌いな男は、寝るときも一人だとうまく眠れない。もう自分も高校生なのだし抱き枕にされる日々は少し恥ずかしさがあるというものだが、ちょっとの我慢で先生の健康が少しでも保たれるなら、と思ってしまうのは甘やかしてしまっているのだろうか。
なんというか、一回りも違うくせに、どっちが子供なのかたまに分からない。
ぼんやりと寝顔をそのまま見下ろしていたら、白くて細い指先が色の薄い髪を撫でていた。
 |
「 」 |
何か、言っているのだと思う。というよりは口の動き的に、歌っている。
それでも彼女の声はおれには聞こえない。おれ自身の問題、というよりは、彼女自身の問題なのだろう。
見えるだけでなくて他のよくわからないものたちの声や音を拾うことは一応できるのだ。というか、否応なしに耳につくのが日常だ。
だから口を開いていても音が聞こえないのは、彼女に声が無いからだろう。生前からそうだったのか、死んでからなのかはわからないけれど。
 |
(……愛されてるなあ) |
傍から見てもわかるぐらい、彼女は先生のことをすごく気にかけていた。
それがおれだけに見えていて、本人には何も分からない、というのは少し胸が締め付けられるような心地がしてしまう。
だってこうやって彼女が届けたい歌も、先生には何も聞こえないのだ。撫でているというのだって、おれにしか分からない。
おれの視界にはどちらも間違いなく在るというのに、二人の間にはどうしたって埋まらない境界があるのだ。
こういう気持ちをもどかしいと表現すれば適切だろうか。何かしてあげたいような気もして、けれどできることなんて大して何もない。
今できることだって、物音を立てず覚醒させず、幸せそうな彼女の一時を守るぐらいだろうか。
 |
(あんまり心配かけるなよ、だめなひと) |
あとはプラスアルファ。溜息を吐いて、こっそり心の中で悪態を吐く。
晩御飯の準備があるので彼女には申し訳ないが三十分も経てば作り始めよう、そんなことを考えながら。



ENo.147 ヨシノ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.421 エインモーネ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.1159 万智花 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||



 |
斎 「元気がいいのは何よりだね! ただでさえわけのわからない状況でうんざりしちゃうからね!」 |
 |
命 「物騒なのは勘弁なんですけど……」 |
 |
ヒシュ 「………」 |
 |
ヒシュ 「…足引っ張ンじゃねえぞ。」 |
 |
そう告げた狐面の彼女に、見覚えはあるだろうか。 少なくとも"アサヒ"を知るのであれば、その違和感や風貌の既視感に気付くことができるだろう。 |
ItemNo.6 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。





スイーツ☆パラダイス
|
 |
梟の住処
|



使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
アッシュ(283) とカードを交換しました!
惑わずの一撃 (イレイザー)

アイシクルランス を研究しました!(深度0⇒1)
アイシクルランス を研究しました!(深度1⇒2)
アイシクルランス を研究しました!(深度2⇒3)
サステイン を習得!
ライフリンク を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



一海(853) は 何かの殻 を入手!
斎(1033) は 何かの殻 を入手!
万智花(1159) は ボロ布 を入手!
ヒシュ(1202) は 何かの殻 を入手!
一海(853) は 甲殻 を入手!
斎(1033) は 羽 を入手!
斎(1033) は 甲殻 を入手!
万智花(1159) は 何か柔らかい物体 を入手!



万智花(1159) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 一海(853) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ヒシュ(1202) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.1033
神園 斎



◇神園 斎(かみぞの いつき)
183cm / 30歳 / 男性
数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。
典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。
ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。
金銭感覚がずれているところが少々。
好きなものは酒とタバコとネットゲーム。
MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。
古参&重課金勢&ネカマ。
異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。
日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。
◆月守 命(つきもり みこと)
156cm / 15歳 / 男性
斎の親戚。
5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。
引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。
友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。
基本的な家事や買い物は彼が行っている。
好きなものは苺、それから駄菓子。
異能:人や動物でない存在を認識する。
常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。
他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。
--------------------
〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。
〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。
〇プロフ絵二種
183cm / 30歳 / 男性
数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。
典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。
ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。
金銭感覚がずれているところが少々。
好きなものは酒とタバコとネットゲーム。
MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。
古参&重課金勢&ネカマ。
異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。
日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。
◆月守 命(つきもり みこと)
156cm / 15歳 / 男性
斎の親戚。
5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。
引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。
友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。
基本的な家事や買い物は彼が行っている。
好きなものは苺、それから駄菓子。
異能:人や動物でない存在を認識する。
常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。
他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。
--------------------
〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。
〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。
〇プロフ絵二種
21 / 30
61 PS
チナミ区
I-11
I-11







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | チェスターコート | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 聴診器 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]凍結10(LV20)[防具]反盲10(LV25)[装飾]防御15(LV25) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 9 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]地纏10(LV20)[防具]防御10(LV15)[装飾]反射10(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 使役 | 5 | エイド/援護 |
| 防具 | 25 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ライフリンク | 5 | 0 | 50 | 自従傷:HP増+HP譲渡 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]チャージ | [ 3 ]アイシクルランス |

PL / 蒸しパン