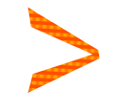<< 0:00~0:00




今日の朝御飯はお味噌汁にご飯と塩焼きにした鮭、それからほうれん草のお浸し。
全部並べ終えて、いつもの席に座る。そうしてしっかりと両手を合わせた。
おれと、向かいに先生。
それから、その隣に。
にこにこ笑う、女の人。
これが神園家の、毎朝の光景だ。
Ⅰ . 3人の食卓
五年前、おれは事故に遭った。
なんてことないよくある交通事故だ。車と車がぶつかった。交通事故に遭う確率が30%ぐらいは一生の内にあるみたいだから、珍しくはない。多分。
ただ運が悪いことにおれ以外の家族は皆そのときに死んでしまった。あんまり事故に遭った瞬間の記憶はないけれど、まあわりと勢いよくぶつかってしまったのだろう。
かくいうおれ自身、生死の境を彷徨った。こうやって生きているのは奇跡に近い、とはそのときの医者に話されたことだ。とりあえず全身がしばらく痛くてしょうがなかったので重症だったというのは本当だと思う。あんな痛みは産まれて初めてだったしもう味わいたくない。
そういうわけで皆の中運良く一人生き残ってしまったのだが、ならばそれはそれで仕方ない。助けてもらった命を無駄に放り投げるわけにもいかないので、とりあえず生きることにはしたし、まだ10歳だったから親戚にも引き取ってもらえて、幼いながらもなんとか第2の人生とやらを歩む心構えもした。
けれど、その生死の境を彷徨った、というのがきっとよくなかったのだろう。
それまで異能を持たなかったおれの瞳には、事故を境によくわからないものが映るようになってしまった。
見ただけで吐き気を及ぼすような化け物としか言えない何か。
人間離れした美しさを持ったお伽噺でしか見ないような妖精みたいな子。
生きている人間とそっくりの、この世にはもういない誰か。
ただの猫とそっくりなのに、よく見れば尻尾が二本あったりする猫。
最初は皆にも見えているものだと思って話を振ったりしたのが更にだめだった。
それはおれの瞳にしか映らないもの──幽霊とか、妖怪とか、空想上の存在だと思われているそれら──だったから、そりゃもう気味悪がられて仕方なかったのだ。そんな気持ちの悪い子供を引き受けたくないのは当然である、というのは転々と親戚間をたらい回しにされている内に嫌というほど理解できてしまった。ゆえに引っ込み思案だった性格には拍車がかかり、自分から何かを話すこともめっきり苦手になってしまった5年前、10歳の春。
まあ当然気持ち悪いよなとは思うので、相手方を責める気はない。浅慮だった子供の自分がきっと悪い。だが理解できても傷つかない、というわけにはいかないので、それなりに心が傷つきはした半年間ぐらいの日々は今もしっかり覚えている。嫌というほど。
それがどうしてかおかしなことに今は先生の家にいるのだから、人生と言うのは不思議なものだ。
まだ少し眠そうな眼を細めてふにゃりと笑う男の人は、ある日突然おれの前に現れて、ある日突然この家に自分を招き入れた。
誘拐か? と思ったがそうではなかったらしく、今日から君は私の家族だよなんて事もなさげに楽しそうに笑ってみせたことは、まだ鮮明に覚えている。そのとき先生はまだ二十五歳だったというのに、よく十歳の子供なんか引き取ろうと思ったものだ。その上血の繋がりもないときたら本当に気の迷いなのではとしか思えない。実際、気の迷いかもしれない。
──で。
家に招き入れてもらった初めての日、にこにことリビングで当然のように座っていたのが彼女だ。
『恋人さんですか?』と聞いたら『え、何の話?』と返されたので、あ、これはだめなやつだ、と思ってそれ以降先生に話を振ったことはない。
恐らく幽霊か何かの彼女はよく先生の近くにいるが、先生は全く気づいていない。今も隣に座っているし、美味しそうにお味噌汁を飲む先生をにこやかな笑顔を向けているというのに、やっぱり普通の人には見えないのだ。
妹か、姉か、といっても顔立ちはあまり似ていないので、昔の彼女か、何かか。確かめることはできていないし、する気も然程ないので、これからもずっと謎のままだろうが。ただ死んだあとも先生の傍にいるからには相当思い入れがあるのだと思う──もしかしたら、全くの知らない人に気に入られてるのかもしれないけれど。ストーカーとか?
常時おかしなものが見える瞳を気にした先生に、異能制御の専門医でも紹介しようか、と言われたこともあったが断った理由がこれだ。
もし全く見えなくなってしまったとき、同居人が見えなくなるのはちょっとだけ心苦しい。彼女はおれにもいつも笑ってくれるし、変なのが多い視界の中で害のないただのいい人なので。
そういうわけで、おれは奇妙な生活を送っている。
自分と、先生と、幽霊の彼女。
5年前から続く、とある高層マンションでの3人暮らしだ。









命術LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
一海(853) により ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『聴診器』を作製してもらいました!
⇒ 聴診器/武器:強さ30/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
万智花(1159) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『花柄のワンピース』を作製しました!
ItemNo.4 不思議な牙 から防具『チェスターコート』を作製しました!
⇒ チェスターコート/防具:強さ30/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
六華(8) とカードを交換しました!
ケア (ヒール)

チャージ を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を研究しました!(深度1⇒2)
チャージ を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
アクアヒール を習得!
☆水の祝福 を習得!
☆アイシクルランス を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが4増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調26⇒25)
万智花(1159) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 一海(853) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 斎(1033) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 万智花(1159) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- アサヒ?(1202) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――


















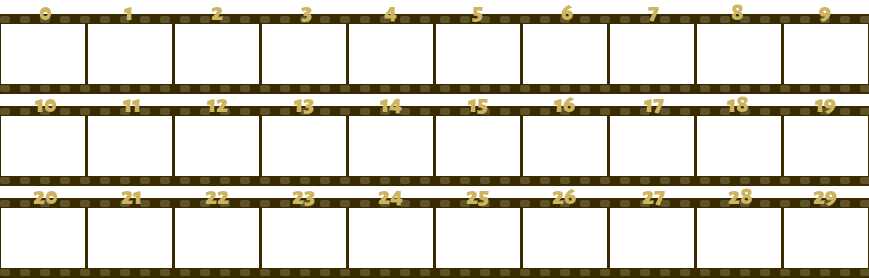





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



今日の朝御飯はお味噌汁にご飯と塩焼きにした鮭、それからほうれん草のお浸し。
全部並べ終えて、いつもの席に座る。そうしてしっかりと両手を合わせた。
 |
「いただきます」 |
 |
「いただきます」 |
おれと、向かいに先生。
それから、その隣に。
 |
「────」 |
にこにこ笑う、女の人。
これが神園家の、毎朝の光景だ。
Ⅰ . 3人の食卓
五年前、おれは事故に遭った。
なんてことないよくある交通事故だ。車と車がぶつかった。交通事故に遭う確率が30%ぐらいは一生の内にあるみたいだから、珍しくはない。多分。
ただ運が悪いことにおれ以外の家族は皆そのときに死んでしまった。あんまり事故に遭った瞬間の記憶はないけれど、まあわりと勢いよくぶつかってしまったのだろう。
かくいうおれ自身、生死の境を彷徨った。こうやって生きているのは奇跡に近い、とはそのときの医者に話されたことだ。とりあえず全身がしばらく痛くてしょうがなかったので重症だったというのは本当だと思う。あんな痛みは産まれて初めてだったしもう味わいたくない。
そういうわけで皆の中運良く一人生き残ってしまったのだが、ならばそれはそれで仕方ない。助けてもらった命を無駄に放り投げるわけにもいかないので、とりあえず生きることにはしたし、まだ10歳だったから親戚にも引き取ってもらえて、幼いながらもなんとか第2の人生とやらを歩む心構えもした。
けれど、その生死の境を彷徨った、というのがきっとよくなかったのだろう。
それまで異能を持たなかったおれの瞳には、事故を境によくわからないものが映るようになってしまった。
見ただけで吐き気を及ぼすような化け物としか言えない何か。
人間離れした美しさを持ったお伽噺でしか見ないような妖精みたいな子。
生きている人間とそっくりの、この世にはもういない誰か。
ただの猫とそっくりなのに、よく見れば尻尾が二本あったりする猫。
最初は皆にも見えているものだと思って話を振ったりしたのが更にだめだった。
それはおれの瞳にしか映らないもの──幽霊とか、妖怪とか、空想上の存在だと思われているそれら──だったから、そりゃもう気味悪がられて仕方なかったのだ。そんな気持ちの悪い子供を引き受けたくないのは当然である、というのは転々と親戚間をたらい回しにされている内に嫌というほど理解できてしまった。ゆえに引っ込み思案だった性格には拍車がかかり、自分から何かを話すこともめっきり苦手になってしまった5年前、10歳の春。
まあ当然気持ち悪いよなとは思うので、相手方を責める気はない。浅慮だった子供の自分がきっと悪い。だが理解できても傷つかない、というわけにはいかないので、それなりに心が傷つきはした半年間ぐらいの日々は今もしっかり覚えている。嫌というほど。
それがどうしてかおかしなことに今は先生の家にいるのだから、人生と言うのは不思議なものだ。
 |
「命が作ってくれる味噌汁は美味しいね、将来はいいお嫁さんになるよ」 |
 |
「なるなら旦那ですけど」 |
 |
「怒った? 冗談だよ? 命はそう見えて男前だものね」 |
まだ少し眠そうな眼を細めてふにゃりと笑う男の人は、ある日突然おれの前に現れて、ある日突然この家に自分を招き入れた。
誘拐か? と思ったがそうではなかったらしく、今日から君は私の家族だよなんて事もなさげに楽しそうに笑ってみせたことは、まだ鮮明に覚えている。そのとき先生はまだ二十五歳だったというのに、よく十歳の子供なんか引き取ろうと思ったものだ。その上血の繋がりもないときたら本当に気の迷いなのではとしか思えない。実際、気の迷いかもしれない。
 |
「……まあ、褒めてもらえるのは嬉しいです、ありがとう」 |
 |
「────」 |
──で。
家に招き入れてもらった初めての日、にこにことリビングで当然のように座っていたのが彼女だ。
『恋人さんですか?』と聞いたら『え、何の話?』と返されたので、あ、これはだめなやつだ、と思ってそれ以降先生に話を振ったことはない。
恐らく幽霊か何かの彼女はよく先生の近くにいるが、先生は全く気づいていない。今も隣に座っているし、美味しそうにお味噌汁を飲む先生をにこやかな笑顔を向けているというのに、やっぱり普通の人には見えないのだ。
妹か、姉か、といっても顔立ちはあまり似ていないので、昔の彼女か、何かか。確かめることはできていないし、する気も然程ないので、これからもずっと謎のままだろうが。ただ死んだあとも先生の傍にいるからには相当思い入れがあるのだと思う──もしかしたら、全くの知らない人に気に入られてるのかもしれないけれど。ストーカーとか?
常時おかしなものが見える瞳を気にした先生に、異能制御の専門医でも紹介しようか、と言われたこともあったが断った理由がこれだ。
もし全く見えなくなってしまったとき、同居人が見えなくなるのはちょっとだけ心苦しい。彼女はおれにもいつも笑ってくれるし、変なのが多い視界の中で害のないただのいい人なので。
 |
「今日は週明けだから患者が多いかなぁ、がんばらないとね」 |
 |
「はい、頑張ってください、おれも行くので」 |
 |
「ふふ、ありがと」 |
そういうわけで、おれは奇妙な生活を送っている。
自分と、先生と、幽霊の彼女。
5年前から続く、とある高層マンションでの3人暮らしだ。



 |
斎 「……ここが、ハザマというところかな? 命、私から離れないようにね」 |
 |
命 「は、はい…………」 |





命術LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
一海(853) により ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『聴診器』を作製してもらいました!
⇒ 聴診器/武器:強さ30/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
万智花(1159) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『花柄のワンピース』を作製しました!
ItemNo.4 不思議な牙 から防具『チェスターコート』を作製しました!
⇒ チェスターコート/防具:強さ30/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
斎 「とりあえずこんなものかな?」 |
六華(8) とカードを交換しました!
ケア (ヒール)

チャージ を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を研究しました!(深度1⇒2)
チャージ を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
アクアヒール を習得!
☆水の祝福 を習得!
☆アイシクルランス を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが4増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「はいお疲れさん。サービスの飴ちゃん持ってきな。」 |
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調26⇒25)
万智花(1159) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 一海(853) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 斎(1033) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 万智花(1159) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- アサヒ?(1202) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――







TeamNo.1159
|
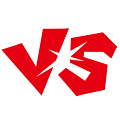 |
梟の住処
|


ENo.1033
神園 斎



◇神園 斎(かみぞの いつき)
183cm / 30歳 / 男性
数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。
典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。
ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。
金銭感覚がずれているところが少々。
好きなものは酒とタバコとネットゲーム。
MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。
古参&重課金勢&ネカマ。
異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。
日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。
◆月守 命(つきもり みこと)
156cm / 15歳 / 男性
斎の親戚。
5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。
引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。
友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。
基本的な家事や買い物は彼が行っている。
好きなものは苺、それから駄菓子。
異能:人や動物でない存在を認識する。
常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。
他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。
--------------------
〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。
〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。
〇プロフ絵二種
183cm / 30歳 / 男性
数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。
典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。
ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。
金銭感覚がずれているところが少々。
好きなものは酒とタバコとネットゲーム。
MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。
古参&重課金勢&ネカマ。
異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。
日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。
◆月守 命(つきもり みこと)
156cm / 15歳 / 男性
斎の親戚。
5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。
引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。
友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。
基本的な家事や買い物は彼が行っている。
好きなものは苺、それから駄菓子。
異能:人や動物でない存在を認識する。
常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。
他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。
--------------------
〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。
〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。
〇プロフ絵二種
25 / 30
5 PS
チナミ区
G-8
G-8





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | チェスターコート | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 聴診器 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]チャージ |

PL / 蒸しパン