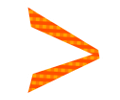<< 2:00>> 4:00




人は異常を恐れるものだ。
それは生き物ならば当然の感覚である。
本能的に生きる動物などでさえ危機感知能力から異質なものを避けるのが当たり前。
ましてや知恵ある者ならば、余計に注意して然るべきだろう。
……が、しかし例外は当然存在するものだ。
人と言うのは面白いもので、注意すべき異常にすら、場合によっては慣れてしまうのである。
それを柔軟な適応力の賜物と見るべきなのか。
それとも、単に自己への自信の高さから来る過信と見るべきなのか。
答えは誰も知らない。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
異界に赴くというのに普段の姿のままで行くと告げた時のウィルヘルムの顔を、ヴィーズィーはまるでさっき見た事の様にありありと思い出すことが出来る。いやはやあれは傑作だった。普段はクール系――まあ昨今は大分表情も和らぐようになってきたようで何よりなのだが――で通している彼が目を剥いて驚愕と混乱と困惑の入り混じる表情を浮かべる様は、見ている方としては愉快な絵面だったのは確かである。
クツクツと仮面の下で笑いながら、ヴィーズィーは手にしていた荷物を棚にしまいふぅと息を吐いた。数日前から行っていた荷解きは何とかこれで完了である。持ち込んだ荷は少なめにした筈だが、それでも予想以上に手間がかかってしまった。やはり、こういった作業は人手が必要だと改めて思いつつも、ヴィーズィーはやっと整った室内をぐるりと見回す。
少し狭く薄暗い部屋だった。壁際にはシックな棚が並び、古びた背表紙の本やら不思議な金属板やらカードやらといった諸々がしまい込まれている。部屋の中央には天鵞絨の布をかけられた大きな机が置かれ、その上には丸い水晶玉が豪奢な台座の上で仄かな照明を受けて煌めいていた。
酷く怪しい雰囲気のある部屋である。十中八九の人が、感想をきけば怪しいと答えることだろう。しかし、それは何一つ問題ではない。
ヴィーズィーは部屋の扉――これもまた重そうな鉄枠で飾られた中世風の扉である――を押し開けて歩み出た。外、ではなく室内だったが先程の小部屋とはうって変わって、こちらは酷く現代的である。接客用のものだろうカウンターに、壁にはポスター大の幾つかの張り紙、そして隅の方には置かれたテーブルや棚に小さな小物が無数に並べられ値札がそれぞれに取り付けられていた。ちょっとした店、といった様相である。
まあそれも当然だろう。何せココは紛れもなく『店』なのだから。それも、占い専門の。
「占い師なぞ、怪しくてなんぼじゃからな」
普段から外す事の少ない仮面に全身を覆い隠す白のローブ。これらを勿論、別のものに変える事は不可能ではなかった。いや、現状を考えれば本来は変更すべきなのだ。今、ヴィーズィーが暫くの住居を構える事になったこの世界は、今まで転々と旅をして回ったファンタジックな世界とは異なり科学技術が程々に進歩した世界なのだから。イバラシティと呼ばれるこの都市はその中でも変わり種――『異能』と呼ばれる不可思議な力を持つ住人が当たり前に闊歩しているのは、こういう傾向の世界ではレアケースかもしれない――とはいえ、この出で立ちは異質そのものと言っていい。
しかしこのスタイルをヴィーズィーは変えるつもりが無かった。それは、少々複雑な事情がからむのも理由の一つだが……それ以上に、この姿形こそ最も自分らしいものだという自負の為だ。ならばこそ、紛れ込むためには上手な嘘を用意してやらねばならない。
ヴィーズィーが今回、この世界に紛れ込むために用意した嘘は『占い師』という経歴だった。勿論、嘘は嘘だが完全な嘘ではない。実際に占いに関しては専門ではないが多少の知識があるからだ。今までそれで商売をしたこともある。そういった経験は確かな説得力となって、今のヴィーズィーを助けている。
何より、こんな非現代的な格好をしていても「これは商売着」と言い張れば多少訝られたり怪しがられたりしつつも受け入れられやすいこの職業は、ヴィーズィーにとってはちょうど良かった。
「怪し過ぎたとして、それに至極真っ当な理由が付けば、人は存外に納得するもんじゃからな」
人は異常を恐れるものだ。
その最たる理由は、理解が出来ないからである。
分からないものは恐怖を掻き立て不安を煽るのだ。
ならば、どうやって異常なものを上手く溶け込ませるのか。
簡単な話だ。
理解しやすい情報を与えてやればいい。
納得の出来る説明を聞かせてやればいい。
其処に存在する簡単な理由を教えてやればいい。
人は未知のものをこそ恐れるが、それが何か分かってしまえば安心する。
たとえそれが真っ赤なウソだったとしても、気付かなければ同じことだ。
「有り難いと言えば有り難い話じゃて」
それが良いのか悪いのかは別として。そんな呟きと共に口元に浮かぶ笑みは細い細い三日月のカタチをしていたが、仮面に隠され誰にも窺い知ることは出来ないのだった。





守屋弓弦(102) から 吸い殻 を手渡しされました。
守屋弓弦(102) に ItemNo.9 美味しくない草 を手渡ししました。








守屋弓弦(102) は ぬめぬめ を入手!
ヴィズ(163) は 何かの殻 を入手!
守屋弓弦(102) は ねばねば を入手!
ヴィズ(163) は 甲殻 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ヴィズ(163) のもとに 豆ゾンビ がゆっくりと近づいてきます。



大黒猫 をエイドとして招き入れました!
使役LV を 2 DOWN。(LV13⇒11、+2CP、-2FP)
制約LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 1 UP!(LV23⇒24、-1CP)
付加LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)
守屋弓弦(102) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
守屋弓弦(102) の持つ ItemNo.4 堅牢なコンバットナイフ に ItemNo.1 どうでもよさげな物体 を付加しました!
ItemNo.8 占い師のローブ に ItemNo.1 どうでもよさげな物体 を付加しました!
⇒ 占い師のローブ/防具:強さ33/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]-
守屋弓弦(102) の持つ ItemNo.11 小振りなダガー に ItemNo.2 どうでもよさげな物体 を付加しました!
ナルミ(1481) とカードを交換しました!
簡易式防御壁 (プロテクション)

エキサイト を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
リストリクト を習得!
ファイアダンス を習得!
アイシング を習得!
ラテントパワー を習得!



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――
















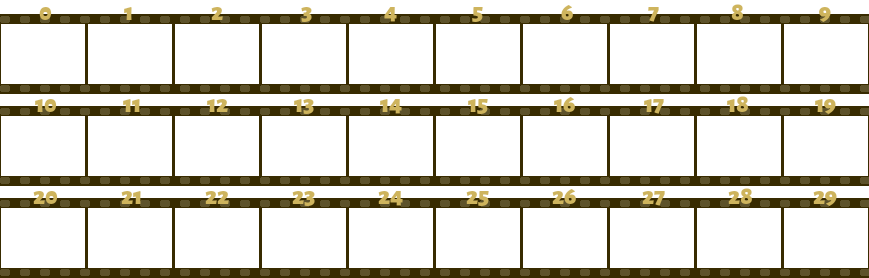


































No.1 大黒猫 (種族:大黒猫)






異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



人は異常を恐れるものだ。
それは生き物ならば当然の感覚である。
本能的に生きる動物などでさえ危機感知能力から異質なものを避けるのが当たり前。
ましてや知恵ある者ならば、余計に注意して然るべきだろう。
……が、しかし例外は当然存在するものだ。
人と言うのは面白いもので、注意すべき異常にすら、場合によっては慣れてしまうのである。
それを柔軟な適応力の賜物と見るべきなのか。
それとも、単に自己への自信の高さから来る過信と見るべきなのか。
答えは誰も知らない。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
異界に赴くというのに普段の姿のままで行くと告げた時のウィルヘルムの顔を、ヴィーズィーはまるでさっき見た事の様にありありと思い出すことが出来る。いやはやあれは傑作だった。普段はクール系――まあ昨今は大分表情も和らぐようになってきたようで何よりなのだが――で通している彼が目を剥いて驚愕と混乱と困惑の入り混じる表情を浮かべる様は、見ている方としては愉快な絵面だったのは確かである。
クツクツと仮面の下で笑いながら、ヴィーズィーは手にしていた荷物を棚にしまいふぅと息を吐いた。数日前から行っていた荷解きは何とかこれで完了である。持ち込んだ荷は少なめにした筈だが、それでも予想以上に手間がかかってしまった。やはり、こういった作業は人手が必要だと改めて思いつつも、ヴィーズィーはやっと整った室内をぐるりと見回す。
少し狭く薄暗い部屋だった。壁際にはシックな棚が並び、古びた背表紙の本やら不思議な金属板やらカードやらといった諸々がしまい込まれている。部屋の中央には天鵞絨の布をかけられた大きな机が置かれ、その上には丸い水晶玉が豪奢な台座の上で仄かな照明を受けて煌めいていた。
酷く怪しい雰囲気のある部屋である。十中八九の人が、感想をきけば怪しいと答えることだろう。しかし、それは何一つ問題ではない。
ヴィーズィーは部屋の扉――これもまた重そうな鉄枠で飾られた中世風の扉である――を押し開けて歩み出た。外、ではなく室内だったが先程の小部屋とはうって変わって、こちらは酷く現代的である。接客用のものだろうカウンターに、壁にはポスター大の幾つかの張り紙、そして隅の方には置かれたテーブルや棚に小さな小物が無数に並べられ値札がそれぞれに取り付けられていた。ちょっとした店、といった様相である。
まあそれも当然だろう。何せココは紛れもなく『店』なのだから。それも、占い専門の。
「占い師なぞ、怪しくてなんぼじゃからな」
普段から外す事の少ない仮面に全身を覆い隠す白のローブ。これらを勿論、別のものに変える事は不可能ではなかった。いや、現状を考えれば本来は変更すべきなのだ。今、ヴィーズィーが暫くの住居を構える事になったこの世界は、今まで転々と旅をして回ったファンタジックな世界とは異なり科学技術が程々に進歩した世界なのだから。イバラシティと呼ばれるこの都市はその中でも変わり種――『異能』と呼ばれる不可思議な力を持つ住人が当たり前に闊歩しているのは、こういう傾向の世界ではレアケースかもしれない――とはいえ、この出で立ちは異質そのものと言っていい。
しかしこのスタイルをヴィーズィーは変えるつもりが無かった。それは、少々複雑な事情がからむのも理由の一つだが……それ以上に、この姿形こそ最も自分らしいものだという自負の為だ。ならばこそ、紛れ込むためには上手な嘘を用意してやらねばならない。
ヴィーズィーが今回、この世界に紛れ込むために用意した嘘は『占い師』という経歴だった。勿論、嘘は嘘だが完全な嘘ではない。実際に占いに関しては専門ではないが多少の知識があるからだ。今までそれで商売をしたこともある。そういった経験は確かな説得力となって、今のヴィーズィーを助けている。
何より、こんな非現代的な格好をしていても「これは商売着」と言い張れば多少訝られたり怪しがられたりしつつも受け入れられやすいこの職業は、ヴィーズィーにとってはちょうど良かった。
「怪し過ぎたとして、それに至極真っ当な理由が付けば、人は存外に納得するもんじゃからな」
人は異常を恐れるものだ。
その最たる理由は、理解が出来ないからである。
分からないものは恐怖を掻き立て不安を煽るのだ。
ならば、どうやって異常なものを上手く溶け込ませるのか。
簡単な話だ。
理解しやすい情報を与えてやればいい。
納得の出来る説明を聞かせてやればいい。
其処に存在する簡単な理由を教えてやればいい。
人は未知のものをこそ恐れるが、それが何か分かってしまえば安心する。
たとえそれが真っ赤なウソだったとしても、気付かなければ同じことだ。
「有り難いと言えば有り難い話じゃて」
それが良いのか悪いのかは別として。そんな呟きと共に口元に浮かぶ笑みは細い細い三日月のカタチをしていたが、仮面に隠され誰にも窺い知ることは出来ないのだった。





 |
守屋弓弦 「さて、と。お互い命拾いしたな。」 |
 |
守屋弓弦 「俺は守屋弓弦。そっちも名前くらいは教えてくれないか?」 |
 |
ヴィズ 「いやはや、存外におぬしは頼りになるようじゃな。今後もしっかり頼っていく所存であるのでまあよろしゅう頼むわい。クフフ。」 |
守屋弓弦(102) から 吸い殻 を手渡しされました。
 |
守屋弓弦 「どう見てもゴミにしか見えねえけどなあ……。」 |
守屋弓弦(102) に ItemNo.9 美味しくない草 を手渡ししました。







守屋弓弦(102) は ぬめぬめ を入手!
ヴィズ(163) は 何かの殻 を入手!
守屋弓弦(102) は ねばねば を入手!
ヴィズ(163) は 甲殻 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ヴィズ(163) のもとに 豆ゾンビ がゆっくりと近づいてきます。



大黒猫 をエイドとして招き入れました!
使役LV を 2 DOWN。(LV13⇒11、+2CP、-2FP)
制約LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 1 UP!(LV23⇒24、-1CP)
付加LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)
守屋弓弦(102) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
 |
守屋弓弦 「はい、出来たぜ。名前の割には優秀な素材みたいだな。」 |
守屋弓弦(102) の持つ ItemNo.4 堅牢なコンバットナイフ に ItemNo.1 どうでもよさげな物体 を付加しました!
ItemNo.8 占い師のローブ に ItemNo.1 どうでもよさげな物体 を付加しました!
⇒ 占い師のローブ/防具:強さ33/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]-
 |
ヴィズ 「ま、こんなもんじゃろ。」 |
守屋弓弦(102) の持つ ItemNo.11 小振りなダガー に ItemNo.2 どうでもよさげな物体 を付加しました!
ナルミ(1481) とカードを交換しました!
簡易式防御壁 (プロテクション)

エキサイト を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
リストリクト を習得!
ファイアダンス を習得!
アイシング を習得!
ラテントパワー を習得!



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――







ENo.163
ヴィーズィー



「おぉ、そこな御仁。暇ならばちと占っていかんかぇ?」
仮面の占い師。
何時頃からか、イバモールに程近い路地裏にひっそりと店を構えている。
不思議なローブと仮面を身に着けているが、
当人曰く「コレは営業モード」であるとの事。
そのくせしてこの姿以外を見かけた者が居ないと言う噂もあるらしい。
占いの的中率はそこそこ。
「当たるも八卦当たらぬも八卦」とは当人談だが……それで良いのか?
※ ※ ※
テストプレイ用キャラクターです。
既知設定などはご自由に。
PL:九十九(@tukumo_fast)
仮面の占い師。
何時頃からか、イバモールに程近い路地裏にひっそりと店を構えている。
不思議なローブと仮面を身に着けているが、
当人曰く「コレは営業モード」であるとの事。
そのくせしてこの姿以外を見かけた者が居ないと言う噂もあるらしい。
占いの的中率はそこそこ。
「当たるも八卦当たらぬも八卦」とは当人談だが……それで良いのか?
※ ※ ※
テストプレイ用キャラクターです。
既知設定などはご自由に。
PL:九十九(@tukumo_fast)
15 / 30
79 PS
チナミ区
K-14
K-14


































No.1 大黒猫 (種族:大黒猫)
 |
|
|
||||||||||||



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | |||||||
| 2 | 仕込み刀『幽世』 | 武器 | 33 | 器用10 | - | - | 【射程1】 |
| 3 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 4 | 蝶の錫杖 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 紫紺の勾玉 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | フォーチュンクッキー | 料理 | 33 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | |||||||
| 8 | 占い師のローブ | 防具 | 33 | 防御10 | 治癒10 | - | |
| 9 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]加速10(LV15)[防具]幸運10(LV5)[装飾]水纏15(LV25) | |||
| 10 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]活力10(LV15) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 使役 | 11 | エイド/援護 |
| 装飾 | 24 | 装飾作製に影響 |
| 付加 | 2 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| 練2 | アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 | |
| ボロウライフ | 6 | 0 | 60 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火撃&炎上、領域値[火]3以上なら、更に火撃&炎上 | |
| レッドゾーン | 5 | 0 | 80 | 敵:火撃&火耐性減 | |
| アイシング | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増&強制凍結 | |
| ライフリンク | 5 | 0 | 30 | エ傷:HP増&自:HP減 | |
| ラテントパワー | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護+重傷ならAT・DX増(1T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【常時】異能『使役』のLVに応じて、戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率が上昇 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]エキサイト | [ 2 ]アクアヒール | [ 2 ]ヒールポーション |
| [ 1 ]ボロウライフ | [ 1 ]ドレイン | [ 1 ]アレグロ |

PL / 九十九