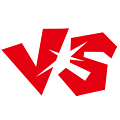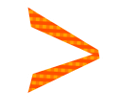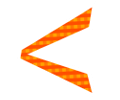<< 3:00>> 5:00




ほんの少しの目眩に近い気配と同時、世界が切り替わる感覚。
慣れたものだ。
それは今まで散々得てきた感覚では在る。
「が、しかし……他者に強引に切り替えられておるというのはどうにも落ち着かんな」
既に数度のハザマ世界への来訪を経た上で、そんな感想をヴィーズィーは呟く。実際、イバラシティと異なり荒れ果て淀みどこか退廃的な気配の蔓延るこの異世界は。決して長居したいと思える場所では無かった。そこへ、自らの意思ではなく誰か──本当に一体どこの誰がこれだけの規模の力を行使しているのか、現状では予想すら出来ない──の力によって跳ばされている訳である。落ち着く方がおかしい。
とはいえ、問題はその程度だ。衣擦れの音を立てて袖の中からズルリとヴィーズィーは長物を引きずり出した。身の丈ほどもある、それは錫杖である。宝石で飾られた先端で、金属のリングが涼し気な音をたてる。
「こういった事がアチラではし難いでな。その点だけは、ハザマの方が気楽じゃわい。……まあ手品と言っても限界もあるしの」
ただの占い師を標榜している身だ。行動に程度制限がかけられてしまうのが、科学文明の程々に進んだ世界に生きる際の面倒な所である。が、それも納得済みでの来訪だ。あまり文句も言えまい。くるりと手の中で錫杖を回せばヴィーズィーは軽く首を鳴らした。
「……? 何をしようとしてるんだ? お前」
訝しげな声が後ろからかけられる。
「〝お前〟ではない。ヴィーズィー、じゃよ」
肩越しに名乗りつつ振り返れば、一人の少年が険しい顔でヴィーズィーを見ていた。彼は、初めてハザマ世界に飛ばされた時から行動を共にしている連れである。お互いに見知らぬ同士──と言っても、彼はヴィーズィーを見たことがあるようだったが──ではあったが、敵を前にすれば共闘するのが最善と判断し一緒に行動する事になったのがほんの少し前の事だ。とは言え、それはこのハザマ世界での経過時間だけを数えた場合であって、実際はその合間にかなりの日数がたっているのだが。
何にせよ、怪訝げな少年へとヴィーズィーは口を開いた。
「わしらだけでは、ちぃと心許無いでな。助力になりそうな者を招こうと思うての」
「助力になりそうな者……? 何だ、近場に協力者でもいるのか」
「居ないわけでも無いが、今回はちと違う」
シャンッ、と錫杖が音を立てて荒れ果てた地を打つ。そこを起点として、瞬時に輝く魔法陣が展開された。大きさにして半径3m程のそれはほんのりと輝きながら明滅している。
「なっ!? 何だこれは!?」
「魔法陣じゃよ。見たことは無いかのぅ? ……ま、イバラシティの様な環境ともなればさもありなん、といった所じゃが」
目を瞬かせる少年をよそに、ヴィーズィーは離れた所で待機していた別の影を手招いた。とてて、と軽い足音を立てて駆け寄ってくるのは普通よりも明らかに大柄な黒猫である。このハザマの生き物の様で普通の黒猫よりもぎょろりとした目つきが少々心臓に悪い、そんな猫だった。性質も好戦的で、実際に二人は戦ったこともある。が、こうしてヴィーズィーの眼前にまで走ってきた大黒猫はというと、すっかり懐いた飼い猫のように大人しいものだった。
それもその筈、この大黒猫はヴィーズィーの操る『使役』の力で無力化されてしまったのだ。
異能。
それは、《響奏の世界》イバラシティに生きる人々が当たり前の様に持つ、異質な力である。中身も人それぞれ。自分の内面だけの変化に留まる者もいれば、自分の周囲に多少の影響力を与える様な異能の持ち主も居る。一概に「こういうものだ!」と定義しにくい固有の才能のようなもの。それが異能だった。
ヴィーズィーは勿論、外界からの来訪者である。異能なんてものは──それに近いものを持っている事を否定はできないが──持っていない。が、世界にあふれる異能の原点や理を密かに解析し、再現する事ぐらいは出来ていた。異質な外界の力は、ただでさえ不安定なイバラシティとハザマ世界に余計な歪みを生みかねない。ならば、元より世界に存在していた力を真似たほうが安全だろう。そう判断したからだ。
大黒猫を支配下に置けたのも再現された異能の力によるものである。『使役』と一般的に言われるその力は、一度打倒したハザマの原生生物を支配下におけるというものだった。もっとも、力が及ぶかどうかは運次第なところもあるので、確実性は薄いのだが。
そんな訳で、無事に自らの下僕──俗に、『エイド』と呼ばれているようである──と化し足元にすり寄ってくる大黒猫をわしゃわしゃと撫でた。これから行おうとしている事は、ヴィーズィーですら少々骨が折れる作業である。この猫の存在があればそれも多少は楽になるのだが。
魔法陣の中心に大黒猫を座らせて、ヴィーズィーは錫杖に手をそれた。遠方から幾分不安げな眼差しを送ってくる気配を感じつつ、詠唱する。
「界隔て、在りし其の身を請い招く。天を天に、地を地に。等価の巡りの元、一を一に」
魔法陣の輝きが強くなる。
その輝きの中に大黒猫の姿が溶け込んでいき──…
光が消え失せた時、そこには別の黒猫の姿があった。
「めにゃーん!」
元気よく個性的な鳴き声を上げるのは、大黒猫よりももう少しスマートな普通の猫程の体格の黒猫だった。首には鈴のついたリボンを付け、どこか誇らしげな顔で見上げてくるのを指差し少年が困惑の声を上げる。
「め、めにゃ……!?」
「おお、メラン。無事にこの世界に喚べた様じゃな。善哉善哉」
「さっきの猫が消えて、コイツが現れた……一体何を?」
「んむ。擬似的な召喚術じゃ」
「擬似的な……召喚術? 異能の『召喚』とは何が違うんだ」
警戒の色の濃い表情の少年へとヴィーズィーは続けた。
「異能の『召喚』は、あくまでこの世界や関連性の在る場所からの喚び出しに過ぎん。今行ったのは、全く異なる異界のリソースを追加で持ち込む、というヤツじゃよ。これをゼロからするのは中々に難儀での。故に、大熊猫を触媒とした訳じゃ」
「触媒……?」
「命というものは、どれほど世界が変わっても価値の変わらぬリソースじゃ。虫も、獣も、人も、それ以上の何かですら、付随する多種多様な情報を剥ぎ取れば結局『命』という一単位のものでしかない。あらゆるものの間に上下はなく、全てが全て、等しくなってしまう。……それを利用し、同じリソースを持つ者同士に繋がりを擬似的にもたせ、それを伝って異なる世界の情報をダウンロードしインストールする……と。まぁ、そんな感じじゃな」
「???」
「……何となくは分かるが今ひとつ理解できん、という顔をしておるな」
魔術などという世界とは縁遠いのだから、明確なイメージが湧きにくいのも仕方ないのだろう。
「つまりじゃな……わしのターン、ドロー! わしはフィールド上に存在する『大熊猫』をリリースする事で手札の『使い魔メラン』を守備表示で特殊召喚する! ……という事じゃ」
「何でかわからないがよくわかった」
疲れた顔で呟く少年。
「でも、大熊猫のままじゃ駄目だったのか? 別に戦力としては……対して変わらないんだろう?」
「まあのぅ」
うむ、とメランを抱き上げつつ頷いてみせるヴィーズィー。
「じゃが、ちとわしとしては此奴にしてもらわねばならん仕事があるでな。その為の労力じゃよ。……ともあれ、よろしく頼むわい」
そう言って、少年へとヴィーズィーが頭を下げれば、腕の中の黒猫もまた「めにゃーん!」と鳴いてみせるのだった。



ENo.1353 コウ とのやりとり




守屋弓弦(102) から 小振りなダガー を手渡しされました。
守屋弓弦(102) に ItemNo.3 吸い殻 を手渡ししました。








守屋弓弦(102) は ネジ を入手!
ヴィーズィー(163) は ネジ を入手!
守屋弓弦(102) は 不思議な石 を入手!
ヴィーズィー(163) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ヴィーズィー(163) のもとに 歩行石壁 が微笑を浮かべて近づいてきます。



豆ゾンビ をエイドとして招き入れました!
守屋弓弦(102) から ぬめぬめ を受け取りました。
守屋弓弦(102) から ねばねば を受け取りました。
魔術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
付加LV を 2 DOWN。(LV2⇒0、+2CP、-2FP)
命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
使役LV を 3 UP!(LV11⇒14、-3CP)
装飾LV を 5 UP!(LV24⇒29、-5CP)
佐藤(179) により ItemNo.2 仕込み刀『幽世』 に ItemNo.4 蝶の錫杖 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
守屋弓弦(102) により ItemNo.10 甲殻 から射程3の武器『違法改造ハンドガン』を作製してもらいました!
⇒ 違法改造ハンドガン/武器:強さ58/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
叶原(738) の持つ ItemNo.5 どうでもよさげな物体 から装飾『香袋』を作製しました!
ItemNo.9 何かの殻 から装飾『潮騒の貝飾り』を作製しました!
⇒ 潮騒の貝飾り/装飾:強さ58/[効果1]水纏15 [効果2]- [効果3]-
ラノザ(1071) の持つ ItemNo.10 不思議な雫 から装飾『大きなゴーグル』を作製しました!
此乃夏(81) により ItemNo.10 違法改造ハンドガン に ItemNo.2 どうでもよさげな物体 を付加してもらいました!
⇒ 違法改造ハンドガン/武器:強さ58/[効果1]攻撃10 [効果2]器用10 [効果3]-【射程3】
ドッペルくん(718) とカードを交換しました!
Lack Only (イバラ)
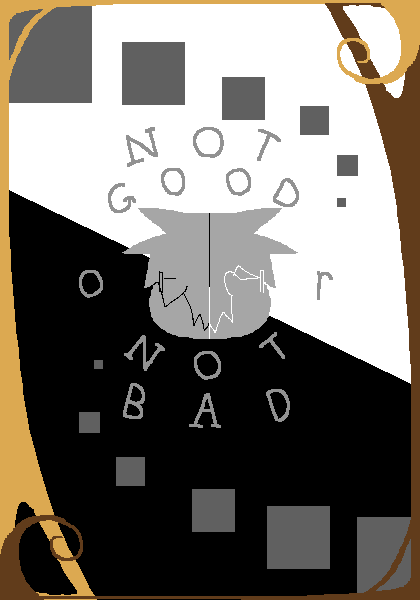

エキサイト を研究しました!(深度2⇒3)
アクアヒール を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を研究しました!(深度2⇒3)
水特性回復 を習得!
ブレッシングレイン を習得!



守屋弓弦(102) に移動を委ねました。
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 I-15(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 H-16(森林)に移動!(体調11⇒10)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――









棒のような何かが釣りを楽しんでいる。

元気なエビをもらったが、元気すぎて空高くジャンプして見えなくなる。
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)

















































No.1 メラン (種族:大黒猫)
No.2 豆ゾンビ (種族:豆ゾンビ)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



ほんの少しの目眩に近い気配と同時、世界が切り替わる感覚。
慣れたものだ。
それは今まで散々得てきた感覚では在る。
「が、しかし……他者に強引に切り替えられておるというのはどうにも落ち着かんな」
既に数度のハザマ世界への来訪を経た上で、そんな感想をヴィーズィーは呟く。実際、イバラシティと異なり荒れ果て淀みどこか退廃的な気配の蔓延るこの異世界は。決して長居したいと思える場所では無かった。そこへ、自らの意思ではなく誰か──本当に一体どこの誰がこれだけの規模の力を行使しているのか、現状では予想すら出来ない──の力によって跳ばされている訳である。落ち着く方がおかしい。
とはいえ、問題はその程度だ。衣擦れの音を立てて袖の中からズルリとヴィーズィーは長物を引きずり出した。身の丈ほどもある、それは錫杖である。宝石で飾られた先端で、金属のリングが涼し気な音をたてる。
「こういった事がアチラではし難いでな。その点だけは、ハザマの方が気楽じゃわい。……まあ手品と言っても限界もあるしの」
ただの占い師を標榜している身だ。行動に程度制限がかけられてしまうのが、科学文明の程々に進んだ世界に生きる際の面倒な所である。が、それも納得済みでの来訪だ。あまり文句も言えまい。くるりと手の中で錫杖を回せばヴィーズィーは軽く首を鳴らした。
「……? 何をしようとしてるんだ? お前」
訝しげな声が後ろからかけられる。
「〝お前〟ではない。ヴィーズィー、じゃよ」
肩越しに名乗りつつ振り返れば、一人の少年が険しい顔でヴィーズィーを見ていた。彼は、初めてハザマ世界に飛ばされた時から行動を共にしている連れである。お互いに見知らぬ同士──と言っても、彼はヴィーズィーを見たことがあるようだったが──ではあったが、敵を前にすれば共闘するのが最善と判断し一緒に行動する事になったのがほんの少し前の事だ。とは言え、それはこのハザマ世界での経過時間だけを数えた場合であって、実際はその合間にかなりの日数がたっているのだが。
何にせよ、怪訝げな少年へとヴィーズィーは口を開いた。
「わしらだけでは、ちぃと心許無いでな。助力になりそうな者を招こうと思うての」
「助力になりそうな者……? 何だ、近場に協力者でもいるのか」
「居ないわけでも無いが、今回はちと違う」
シャンッ、と錫杖が音を立てて荒れ果てた地を打つ。そこを起点として、瞬時に輝く魔法陣が展開された。大きさにして半径3m程のそれはほんのりと輝きながら明滅している。
「なっ!? 何だこれは!?」
「魔法陣じゃよ。見たことは無いかのぅ? ……ま、イバラシティの様な環境ともなればさもありなん、といった所じゃが」
目を瞬かせる少年をよそに、ヴィーズィーは離れた所で待機していた別の影を手招いた。とてて、と軽い足音を立てて駆け寄ってくるのは普通よりも明らかに大柄な黒猫である。このハザマの生き物の様で普通の黒猫よりもぎょろりとした目つきが少々心臓に悪い、そんな猫だった。性質も好戦的で、実際に二人は戦ったこともある。が、こうしてヴィーズィーの眼前にまで走ってきた大黒猫はというと、すっかり懐いた飼い猫のように大人しいものだった。
それもその筈、この大黒猫はヴィーズィーの操る『使役』の力で無力化されてしまったのだ。
異能。
それは、《響奏の世界》イバラシティに生きる人々が当たり前の様に持つ、異質な力である。中身も人それぞれ。自分の内面だけの変化に留まる者もいれば、自分の周囲に多少の影響力を与える様な異能の持ち主も居る。一概に「こういうものだ!」と定義しにくい固有の才能のようなもの。それが異能だった。
ヴィーズィーは勿論、外界からの来訪者である。異能なんてものは──それに近いものを持っている事を否定はできないが──持っていない。が、世界にあふれる異能の原点や理を密かに解析し、再現する事ぐらいは出来ていた。異質な外界の力は、ただでさえ不安定なイバラシティとハザマ世界に余計な歪みを生みかねない。ならば、元より世界に存在していた力を真似たほうが安全だろう。そう判断したからだ。
大黒猫を支配下に置けたのも再現された異能の力によるものである。『使役』と一般的に言われるその力は、一度打倒したハザマの原生生物を支配下におけるというものだった。もっとも、力が及ぶかどうかは運次第なところもあるので、確実性は薄いのだが。
そんな訳で、無事に自らの下僕──俗に、『エイド』と呼ばれているようである──と化し足元にすり寄ってくる大黒猫をわしゃわしゃと撫でた。これから行おうとしている事は、ヴィーズィーですら少々骨が折れる作業である。この猫の存在があればそれも多少は楽になるのだが。
魔法陣の中心に大黒猫を座らせて、ヴィーズィーは錫杖に手をそれた。遠方から幾分不安げな眼差しを送ってくる気配を感じつつ、詠唱する。
「界隔て、在りし其の身を請い招く。天を天に、地を地に。等価の巡りの元、一を一に」
魔法陣の輝きが強くなる。
その輝きの中に大黒猫の姿が溶け込んでいき──…
光が消え失せた時、そこには別の黒猫の姿があった。
「めにゃーん!」
元気よく個性的な鳴き声を上げるのは、大黒猫よりももう少しスマートな普通の猫程の体格の黒猫だった。首には鈴のついたリボンを付け、どこか誇らしげな顔で見上げてくるのを指差し少年が困惑の声を上げる。
「め、めにゃ……!?」
「おお、メラン。無事にこの世界に喚べた様じゃな。善哉善哉」
「さっきの猫が消えて、コイツが現れた……一体何を?」
「んむ。擬似的な召喚術じゃ」
「擬似的な……召喚術? 異能の『召喚』とは何が違うんだ」
警戒の色の濃い表情の少年へとヴィーズィーは続けた。
「異能の『召喚』は、あくまでこの世界や関連性の在る場所からの喚び出しに過ぎん。今行ったのは、全く異なる異界のリソースを追加で持ち込む、というヤツじゃよ。これをゼロからするのは中々に難儀での。故に、大熊猫を触媒とした訳じゃ」
「触媒……?」
「命というものは、どれほど世界が変わっても価値の変わらぬリソースじゃ。虫も、獣も、人も、それ以上の何かですら、付随する多種多様な情報を剥ぎ取れば結局『命』という一単位のものでしかない。あらゆるものの間に上下はなく、全てが全て、等しくなってしまう。……それを利用し、同じリソースを持つ者同士に繋がりを擬似的にもたせ、それを伝って異なる世界の情報をダウンロードしインストールする……と。まぁ、そんな感じじゃな」
「???」
「……何となくは分かるが今ひとつ理解できん、という顔をしておるな」
魔術などという世界とは縁遠いのだから、明確なイメージが湧きにくいのも仕方ないのだろう。
「つまりじゃな……わしのターン、ドロー! わしはフィールド上に存在する『大熊猫』をリリースする事で手札の『使い魔メラン』を守備表示で特殊召喚する! ……という事じゃ」
「何でかわからないがよくわかった」
疲れた顔で呟く少年。
「でも、大熊猫のままじゃ駄目だったのか? 別に戦力としては……対して変わらないんだろう?」
「まあのぅ」
うむ、とメランを抱き上げつつ頷いてみせるヴィーズィー。
「じゃが、ちとわしとしては此奴にしてもらわねばならん仕事があるでな。その為の労力じゃよ。……ともあれ、よろしく頼むわい」
そう言って、少年へとヴィーズィーが頭を下げれば、腕の中の黒猫もまた「めにゃーん!」と鳴いてみせるのだった。



ENo.1353 コウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||



 |
ヴィズ 「此度からは使い魔が増えたぞ! くふふ!!」 |
守屋弓弦(102) から 小振りなダガー を手渡しされました。
 |
守屋弓弦 「たぶん、あんたが使った方が良い。」 |
守屋弓弦(102) に ItemNo.3 吸い殻 を手渡ししました。







守屋弓弦(102) は ネジ を入手!
ヴィーズィー(163) は ネジ を入手!
守屋弓弦(102) は 不思議な石 を入手!
ヴィーズィー(163) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ヴィーズィー(163) のもとに 歩行石壁 が微笑を浮かべて近づいてきます。



豆ゾンビ をエイドとして招き入れました!
守屋弓弦(102) から ぬめぬめ を受け取りました。
 |
守屋弓弦 「あんまり、触りたくねえな……。」 |
 |
ビニール袋に入れられたぬめぬめを差し出した! |
守屋弓弦(102) から ねばねば を受け取りました。
 |
守屋弓弦 「さっきのと混ぜないでくれよ?」 |
 |
同じくビニール袋に入れられたねばねばを差し出した! |
魔術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
付加LV を 2 DOWN。(LV2⇒0、+2CP、-2FP)
命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
使役LV を 3 UP!(LV11⇒14、-3CP)
装飾LV を 5 UP!(LV24⇒29、-5CP)
佐藤(179) により ItemNo.2 仕込み刀『幽世』 に ItemNo.4 蝶の錫杖 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
 |
佐藤 「はい、お待たせしました。これでいいっすかね?」 |
守屋弓弦(102) により ItemNo.10 甲殻 から射程3の武器『違法改造ハンドガン』を作製してもらいました!
⇒ 違法改造ハンドガン/武器:強さ58/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
 |
守屋弓弦 「射程は短いが威力はあるぜ。」 |
叶原(738) の持つ ItemNo.5 どうでもよさげな物体 から装飾『香袋』を作製しました!
ItemNo.9 何かの殻 から装飾『潮騒の貝飾り』を作製しました!
⇒ 潮騒の貝飾り/装飾:強さ58/[効果1]水纏15 [効果2]- [効果3]-
 |
ヴィズ 「……うむ、懐かしい香りじゃの……。」 |
ラノザ(1071) の持つ ItemNo.10 不思議な雫 から装飾『大きなゴーグル』を作製しました!
此乃夏(81) により ItemNo.10 違法改造ハンドガン に ItemNo.2 どうでもよさげな物体 を付加してもらいました!
⇒ 違法改造ハンドガン/武器:強さ58/[効果1]攻撃10 [効果2]器用10 [効果3]-【射程3】
ドッペルくん(718) とカードを交換しました!
Lack Only (イバラ)
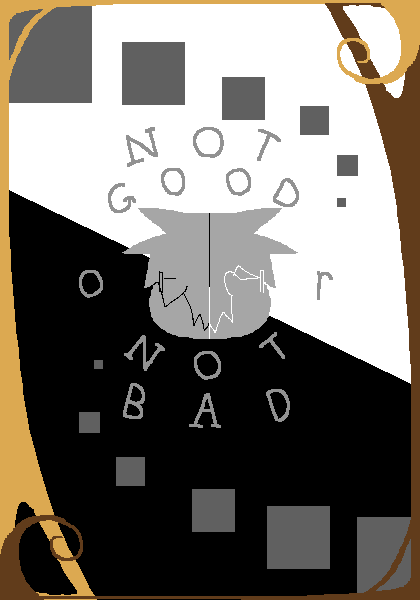

エキサイト を研究しました!(深度2⇒3)
アクアヒール を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を研究しました!(深度2⇒3)
水特性回復 を習得!
ブレッシングレイン を習得!



守屋弓弦(102) に移動を委ねました。
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 I-15(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 H-16(森林)に移動!(体調11⇒10)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――








 |
マイケル 「あ、ようこそチェックポイントへ。 いまエビが釣れそうなので少々お待ちを……。」 |
棒のような何かが釣りを楽しんでいる。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「よくぞここまで。私はマイケルといいます。 出会いの記念にこちらをどうぞ。」 |
元気なエビをもらったが、元気すぎて空高くジャンプして見えなくなる。
 |
マイケル 「……戻ってきませんねぇ、エビさん。」 |
 |
マイケル 「まぁいいです。始めるとしましょうか。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんので、そちらも本気でどうぞ。」 |
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.163
ヴィーズィー



「おぉ、そこな御仁。暇ならばちと占っていかんかぇ?」
仮面の占い師。
何時頃からか、イバモールに程近い路地裏にひっそりと店を構えている。
不思議なローブと仮面を身に着けているが、
当人曰く「コレは営業モード」であるとの事。
そのくせしてこの姿以外を見かけた者が居ないと言う噂もあるらしい。
占いの的中率はそこそこ。
「当たるも八卦当たらぬも八卦」とは当人談だが……それで良いのか?
※ ※ ※
テストプレイ用キャラクターです。
既知設定などはご自由に。
PL:九十九(@tukumo_fast)
仮面の占い師。
何時頃からか、イバモールに程近い路地裏にひっそりと店を構えている。
不思議なローブと仮面を身に着けているが、
当人曰く「コレは営業モード」であるとの事。
そのくせしてこの姿以外を見かけた者が居ないと言う噂もあるらしい。
占いの的中率はそこそこ。
「当たるも八卦当たらぬも八卦」とは当人談だが……それで良いのか?
※ ※ ※
テストプレイ用キャラクターです。
既知設定などはご自由に。
PL:九十九(@tukumo_fast)
10 / 30
109 PS
チナミ区
H-16
H-16


































No.1 メラン (種族:大黒猫)
 |
|
異界に置いてきた家族の一人が生み出した使い魔。<BR>……そのうちの一匹を、借りてきたもの。<BR>全身が魔力の籠もったインクで出来ている擬似生物。<BR>自分を可愛がってくれる相手には懐きやすい現金な性格の持ち主。
|
||||||||||||
 |
|
|
||||||||||||



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 小振りなダガー | 武器 | 31 | 攻撃10 | 器用10 | - | 【射程1】 |
| 2 | |||||||
| 3 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 4 | |||||||
| 5 | 紫紺の勾玉 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | フォーチュンクッキー | 料理 | 33 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 8 | 占い師のローブ | 防具 | 33 | 防御10 | 治癒10 | - | |
| 9 | 潮騒の貝飾り | 装飾 | 58 | 水纏15 | - | - | |
| 10 | 違法改造ハンドガン | 武器 | 58 | 攻撃10 | 器用10 | - | 【射程3】 |
| 11 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) | |||
| 12 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 使役 | 14 | エイド/援護 |
| 装飾 | 29 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| 練1 | アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| 練1 | リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) |
| ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 | |
| ボロウライフ | 6 | 0 | 60 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火撃&炎上、領域値[火]3以上なら、更に火撃&炎上 | |
| レッドゾーン | 5 | 0 | 80 | 敵:火撃&火耐性減 | |
| アイシング | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増&強制凍結 | |
| ライフリンク | 5 | 0 | 30 | エ傷:HP増&自:HP減 | |
| ラテントパワー | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護+重傷ならAT・DX増(1T) | |
| ブレッシングレイン | 5 | 0 | 150 | 味全:HP増+祝福 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【常時】異能『使役』のLVに応じて、戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率が上昇 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
アタック (ブレイク) |
0 | 20 | 敵:攻撃 | |
|
無名のカード (クイック) |
0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
|
簡易式防御壁 (プロテクション) |
0 | 60 | 味傷:守護 | |
|
Lack Only (イバラ) |
0 | 120 | 敵3:精確地痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]エキサイト | [ 3 ]アクアヒール | [ 3 ]ヒールポーション |
| [ 1 ]ボロウライフ | [ 1 ]ドレイン | [ 1 ]アレグロ |

PL / 九十九