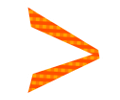<< 2:00>> 4:00




「……ねえ、どう思う?舞」
「そこ、私に振るところですか!?」
顔見知りの――しかし、少し様相が違っていた女性とのやり取りを踏まえて、翔華は舞華に振る。
イバラシティ、チナミ区にできていた飴専門店の店主。翔華の好みどストライクのフレーバーを出し、その種類も様々で非常に好みの店だったが。
ついつい、多めに買い込んでしまい、消費しきるまでは再びの来店もできないと思っていて、再度の来店はしていなかったのだが。
「いや……姉さんの顔見知り、なんでしょう?私に振られてもわかりませんって。」
「そうだよねえ……。赤ちゃんの頃なんて覚えてないし。」
「流石にそういうことでは無いと思いますけど。
……でも」
なにかに思い当たったのか、舞華は首をかしげながら、考え込む。
「こっちの私は覚えている。つまり、向こうの飴屋さんは知らないってことですよね?」
「え?え、ああ、うん。そうなるのかな。」
「それって、つまり――――」
言おうとして、口を噤む。
言ってしまえば、姉は彼女とどう相対すれば良いのか分からなくなるだろう。しかし、相手にしてみれば、そんな事は知ったことではなく、いつか明らかになるだろうという事柄ではある。
だけど、だけれども、運が良ければ、コレきり会うことは無く、知らないままでいられるかもしれない。
しかし、遅かった。
正面には、姉の顔があった。
青ざめて、眉を潜めて、口の端を震えさせている姉の顔が。
「あの人が、侵略者、ってこと……?」
「それは、あの胡散臭い男の話を信用すればという話に、いやでも、姉さん、それはまだ……!」
「……いや、そう、かもしれない。でも、あの雰囲気が変わって、それに、嘘を付く理由があんまり見当たらなくて。」
姉は、やさしい。
それは、妹である自分が、一番良く分かっている。
だから、あの仕組みを聞いたとき、姉は、向こうで顔見知りとなった侵略者と、戦えないのではないか。戦えたとしても、心をボロ布のように裂かれながら茨の道を進むことになるのではないか。
そう、思ったのだ。
「どうして……っていうのは、違うんだよね。あっちが、偽物で、あれが、ここにいる方が本当なんだよね。」
「姉さん……。」
「聞かなきゃ。」
「え?」
「私の、拙い飴細工。褒めてくれたんだ。あれが、あれは、本心なのか。
あれは、あの人は、変わったのか、変わってないのか。そんなに知ってるわけじゃないけど、戻ったら忘れてしまうけど。」
「姉さん、それは……」
ただ辛くなるだけだ、と、侵略者は倒さなきゃいけないと、舞華は言う。
多分、それは「納得」に必要なことだ、と、翔華は結論付ける。
それがこれから、どれだけ自らの首を締めることになるのだろうか。知ってか知らずか、彼女は茨の道を歩き続けるのだろう。



ENo.1312 隼 志駁 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 不思議な何か。 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










魔術LV を 2 UP!(LV13⇒15、-2CP)
自然LV を 1 UP!(LV10⇒11、-1CP)
料理LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ItemNo.8 パンの耳 から料理『パンがゆ』をつくりました!
⇒ パンがゆ/料理:強さ36/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]-
フォーティーツー(411) の持つ ItemNo.8 パンの耳 から料理『揚げパン』をつくりました!
鋭川(159) とカードを交換しました!
その行進を止めよ (ガードフォーム)


ティンダー を研究しました!(深度2⇒3)
イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアボール を研究しました!(深度1⇒2)



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――


















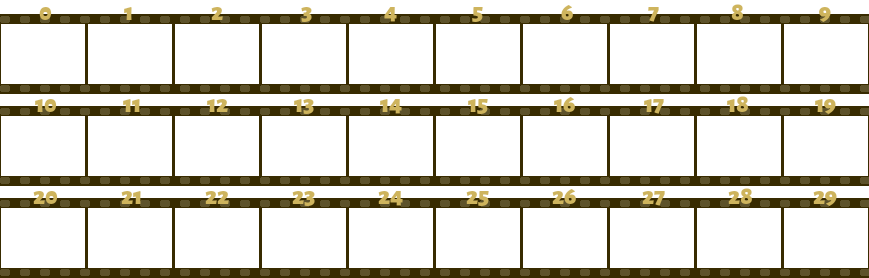





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「……ねえ、どう思う?舞」
「そこ、私に振るところですか!?」
顔見知りの――しかし、少し様相が違っていた女性とのやり取りを踏まえて、翔華は舞華に振る。
イバラシティ、チナミ区にできていた飴専門店の店主。翔華の好みどストライクのフレーバーを出し、その種類も様々で非常に好みの店だったが。
ついつい、多めに買い込んでしまい、消費しきるまでは再びの来店もできないと思っていて、再度の来店はしていなかったのだが。
「いや……姉さんの顔見知り、なんでしょう?私に振られてもわかりませんって。」
「そうだよねえ……。赤ちゃんの頃なんて覚えてないし。」
「流石にそういうことでは無いと思いますけど。
……でも」
なにかに思い当たったのか、舞華は首をかしげながら、考え込む。
「こっちの私は覚えている。つまり、向こうの飴屋さんは知らないってことですよね?」
「え?え、ああ、うん。そうなるのかな。」
「それって、つまり――――」
言おうとして、口を噤む。
言ってしまえば、姉は彼女とどう相対すれば良いのか分からなくなるだろう。しかし、相手にしてみれば、そんな事は知ったことではなく、いつか明らかになるだろうという事柄ではある。
だけど、だけれども、運が良ければ、コレきり会うことは無く、知らないままでいられるかもしれない。
しかし、遅かった。
正面には、姉の顔があった。
青ざめて、眉を潜めて、口の端を震えさせている姉の顔が。
「あの人が、侵略者、ってこと……?」
「それは、あの胡散臭い男の話を信用すればという話に、いやでも、姉さん、それはまだ……!」
「……いや、そう、かもしれない。でも、あの雰囲気が変わって、それに、嘘を付く理由があんまり見当たらなくて。」
姉は、やさしい。
それは、妹である自分が、一番良く分かっている。
だから、あの仕組みを聞いたとき、姉は、向こうで顔見知りとなった侵略者と、戦えないのではないか。戦えたとしても、心をボロ布のように裂かれながら茨の道を進むことになるのではないか。
そう、思ったのだ。
「どうして……っていうのは、違うんだよね。あっちが、偽物で、あれが、ここにいる方が本当なんだよね。」
「姉さん……。」
「聞かなきゃ。」
「え?」
「私の、拙い飴細工。褒めてくれたんだ。あれが、あれは、本心なのか。
あれは、あの人は、変わったのか、変わってないのか。そんなに知ってるわけじゃないけど、戻ったら忘れてしまうけど。」
「姉さん、それは……」
ただ辛くなるだけだ、と、侵略者は倒さなきゃいけないと、舞華は言う。
多分、それは「納得」に必要なことだ、と、翔華は結論付ける。
それがこれから、どれだけ自らの首を締めることになるのだろうか。知ってか知らずか、彼女は茨の道を歩き続けるのだろう。



ENo.1312 隼 志駁 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
以下の相手に送信しました



ItemNo.7 不思議な何か。 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









魔術LV を 2 UP!(LV13⇒15、-2CP)
自然LV を 1 UP!(LV10⇒11、-1CP)
料理LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ItemNo.8 パンの耳 から料理『パンがゆ』をつくりました!
⇒ パンがゆ/料理:強さ36/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]-
 |
翔華 「これ、風邪引いたときに良くたべたんですよね。」 |
フォーティーツー(411) の持つ ItemNo.8 パンの耳 から料理『揚げパン』をつくりました!
鋭川(159) とカードを交換しました!
その行進を止めよ (ガードフォーム)


ティンダー を研究しました!(深度2⇒3)
イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアボール を研究しました!(深度1⇒2)



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――









ENo.144
鳳翔華



19歳
162cm
59kg
イバラシティ南部のツクナミに実家(http://lisge.com/ib/talk.php?s=558)を持つ大学生。
妹と弟が一人ずついるが、妹の方が姉っぽいとは母親談。
虫嫌い。特にカマキリが嫌。嫌いというより恐怖。理由は不明。
異能は「素肌で触れている物質の熱量を熱に変換、貯蔵し、放出できる」能力。
変換できるのは「燃えるもの」。燃えやすい程変換させやすく、変換された物質は炭化を経て灰となる。
炭化させるのは肩から下の肌に触れた時で、自分の身体は影響を受けにくい。
うっかりすると着ているものが灰になるため、不燃繊維の下着と、難燃繊維のアンダーは手放せない。
熱は放出点からゆっくりと放出され、やがて物体へ至ると、放出した分が全て接点へ殺到する。
放出点は指の先、そして眼。眼の放出量は多く、勢いもあり、遠くまで届く。しかし、放出するほど、その部分も熱を持つ。
幼少期、発現し始めた頃にコントロールが効かず大やけどを負う。
上記の虫嫌いと熱に対する潜在的な恐怖から、水辺を好み、それが転じて生物学の道へ進む。
……しかしそんな事言ったらエビとかシャコとか、水辺にも虫っぽい奴はいくらでもいるのだが、水族館で魚ばかり見ていた彼女は、まだ気がついていない。
////////////////////////////////////////
鳳舞華
5つ違いの翔華の妹。中二病真っ最中。
姉よりしっかりしていると評判。だけどクールぶっているだけだったりする。
姉以上に、恐怖に近いレベルで虫が嫌い。道場で大きなムカデを見て暴走して以来、道場には何となく近づきがたいらしい。
異能は「物の熱量を爆発物に変える」
蓄えるまでは姉と一緒だが、放出するのが熱のリボンでなく、目に見える光の玉で、接触すると破裂する。基本的に花火程度のもの。
162cm
59kg
イバラシティ南部のツクナミに実家(http://lisge.com/ib/talk.php?s=558)を持つ大学生。
妹と弟が一人ずついるが、妹の方が姉っぽいとは母親談。
虫嫌い。特にカマキリが嫌。嫌いというより恐怖。理由は不明。
異能は「素肌で触れている物質の熱量を熱に変換、貯蔵し、放出できる」能力。
変換できるのは「燃えるもの」。燃えやすい程変換させやすく、変換された物質は炭化を経て灰となる。
炭化させるのは肩から下の肌に触れた時で、自分の身体は影響を受けにくい。
うっかりすると着ているものが灰になるため、不燃繊維の下着と、難燃繊維のアンダーは手放せない。
熱は放出点からゆっくりと放出され、やがて物体へ至ると、放出した分が全て接点へ殺到する。
放出点は指の先、そして眼。眼の放出量は多く、勢いもあり、遠くまで届く。しかし、放出するほど、その部分も熱を持つ。
幼少期、発現し始めた頃にコントロールが効かず大やけどを負う。
上記の虫嫌いと熱に対する潜在的な恐怖から、水辺を好み、それが転じて生物学の道へ進む。
……しかしそんな事言ったらエビとかシャコとか、水辺にも虫っぽい奴はいくらでもいるのだが、水族館で魚ばかり見ていた彼女は、まだ気がついていない。
////////////////////////////////////////
鳳舞華
5つ違いの翔華の妹。中二病真っ最中。
姉よりしっかりしていると評判。だけどクールぶっているだけだったりする。
姉以上に、恐怖に近いレベルで虫が嫌い。道場で大きなムカデを見て暴走して以来、道場には何となく近づきがたいらしい。
異能は「物の熱量を爆発物に変える」
蓄えるまでは姉と一緒だが、放出するのが熱のリボンでなく、目に見える光の玉で、接触すると破裂する。基本的に花火程度のもの。
16 / 30
172 PS
チナミ区
K-14
K-14





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 藍鉄鉱 | 素材 | 20 | [武器]器用15(LV25)[防具]防御15(LV25)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 8 | パンがゆ | 料理 | 36 | 防御10 | 治癒10 | - | |
| 9 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
| 10 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]器用10(LV15)[装飾]反撃10(LV25) | |||
| 11 | 何か固い物体 | 素材 | 15 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]活力10(LV20)[装飾]反護10(LV20) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 自然 | 11 | 植物/鉱物/地 |
| 料理 | 26 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ティンダー | 6 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| ストーンブラスト | 6 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| フラワリング | 5 | 0 | 90 | 敵列:魅了+領域値[地]3以上なら束縛 | |
| ファイアボール | 5 | 0 | 180 | 敵全:火撃 | |
| クラック | 5 | 0 | 160 | 敵全:地撃&次与ダメ減 | |
| アグリローズ | 6 | 0 | 180 | 敵:地痛撃&猛毒+火痛撃&炎上 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 6 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ティンダー | [ 1 ]イレイザー | [ 2 ]ファイアボール |

PL / やすかけ