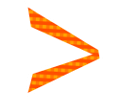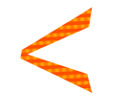<< 1:00>> 3:00




「……あれ?」
「姉さん。」
「おかしいな、鍋を食べてた気がするのに。」
「え、なんですかソレずるい。」
ふと、再びあのハザマと呼ばれる場に立っていることに気がつく。
一度、イバラシティに戻った後に、前回のハザマでの行動直後の時間へとワープしたのだろう。
つまり、数日間の記憶を定期的に突っ込まれつつ、ハザマで行動していくことになるわけだ。
「うわ……ずーっと荒れ果ててる。」
榊と名乗る、怪しさがスーツを着た男が呼び寄せたタクシーに乗って、着いた先からしばらく歩く。
道路はひび割れたアスファルトに覆われていて、森や草むらを歩くよりは歩きやすい、といった程度。
マップを見る限り、ここはチナミ区だという。自宅のあるツクナミとは、ほぼ反対側だ。様子も見たかったが、歩いて到達するのは難しいだろう。
チナミといえば、例のキャンディ屋がここにあるのだったか。行っても、この様子では何があるとも思えないが。
「なんか、こうしてると思い出すねえ。」
「何をですか?」
「小さい頃、カスミのキャンプ場に行ったときにさ、舞と二人で探検に出たらいつの間にか暗くなって、ひんひん半べそかきながら戻ったことあったじゃない。」
「あー……。いや、あれ半べそかいてたの姉さんでしたよね?」
「いや流石に小学校入るか入らないかの頃の舞華の前で……泣いてたっけ?」
「泣いてました。……私も泣いていた覚えがありますけど。」
「舞が泣いてて、なんとかしなきゃなあ、って思ってた記憶はあるけど……そうかぁ、私も泣いてたかあ。」
情けない姉だねえ、とつぶやく声が、響かずに瓦礫の中へ吸い込まれていく。
記憶。
そう、記憶だ。あの胡散臭い榊という男が言うには、ワールドスワップという力により、記憶は補填されているという。
イバラシティの、今に繋がるまでの記憶が。
どこまでだろう?
……彼女に、記憶はあるだろうか。
私が思い出しているという事は、彼女も、"私が本当はいない"ということを思い出しているかもしれない。
必死に話題をつなぐ。違和を感じさせないように。彼女に、自分はアンジニティではないと、証明するために。隠し続けるために。
だってそうしなければ、彼女はきっと迷ってしまう。守るのをためらってしまう。余計な悩みを抱えさせてしまう。彼女は、ただまっすぐ、行ってくれればいい。
恐らく、侵略が失敗し、ワールドスワップの効果が無くなれば、私がいたという記憶も、痕跡も、全てが消えて失せる。
だから、今だけだ。今だけ、ごまかせれば良い。
壊したくないのだ。だって、この関係性が、家族という形態が、私が何度も失って、ようやく手に入れた望みなのだから。
たとえコレが手に入らないとしても、渇望した物を、私が壊して手に入れることをしてはいけないのだから――――。



ENo.746 千歳 佐久間 とのやりとり














魔術LV を 3 UP!(LV10⇒13、-3CP)
料理LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議な何か。』をつくりました!
⇒ 不思議な何か。/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
フォーティーツー(411) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議ななにか。』をつくりました!
ジョウ(1244) とカードを交換しました!
[泥にはまり込んだ車輪:停滞] (クイックアナライズ)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボール を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 J-6(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-7(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 J-8(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 J-9(沼地)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 J-10(山岳)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















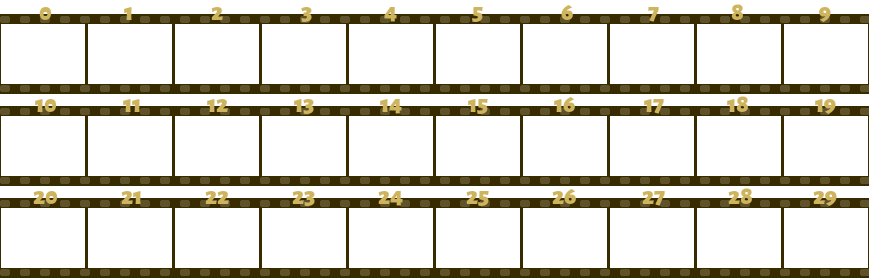





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「……あれ?」
「姉さん。」
「おかしいな、鍋を食べてた気がするのに。」
「え、なんですかソレずるい。」
ふと、再びあのハザマと呼ばれる場に立っていることに気がつく。
一度、イバラシティに戻った後に、前回のハザマでの行動直後の時間へとワープしたのだろう。
つまり、数日間の記憶を定期的に突っ込まれつつ、ハザマで行動していくことになるわけだ。
「うわ……ずーっと荒れ果ててる。」
榊と名乗る、怪しさがスーツを着た男が呼び寄せたタクシーに乗って、着いた先からしばらく歩く。
道路はひび割れたアスファルトに覆われていて、森や草むらを歩くよりは歩きやすい、といった程度。
マップを見る限り、ここはチナミ区だという。自宅のあるツクナミとは、ほぼ反対側だ。様子も見たかったが、歩いて到達するのは難しいだろう。
チナミといえば、例のキャンディ屋がここにあるのだったか。行っても、この様子では何があるとも思えないが。
「なんか、こうしてると思い出すねえ。」
「何をですか?」
「小さい頃、カスミのキャンプ場に行ったときにさ、舞と二人で探検に出たらいつの間にか暗くなって、ひんひん半べそかきながら戻ったことあったじゃない。」
「あー……。いや、あれ半べそかいてたの姉さんでしたよね?」
「いや流石に小学校入るか入らないかの頃の舞華の前で……泣いてたっけ?」
「泣いてました。……私も泣いていた覚えがありますけど。」
「舞が泣いてて、なんとかしなきゃなあ、って思ってた記憶はあるけど……そうかぁ、私も泣いてたかあ。」
情けない姉だねえ、とつぶやく声が、響かずに瓦礫の中へ吸い込まれていく。
記憶。
そう、記憶だ。あの胡散臭い榊という男が言うには、ワールドスワップという力により、記憶は補填されているという。
イバラシティの、今に繋がるまでの記憶が。
どこまでだろう?
……彼女に、記憶はあるだろうか。
私が思い出しているという事は、彼女も、"私が本当はいない"ということを思い出しているかもしれない。
必死に話題をつなぐ。違和を感じさせないように。彼女に、自分はアンジニティではないと、証明するために。隠し続けるために。
だってそうしなければ、彼女はきっと迷ってしまう。守るのをためらってしまう。余計な悩みを抱えさせてしまう。彼女は、ただまっすぐ、行ってくれればいい。
恐らく、侵略が失敗し、ワールドスワップの効果が無くなれば、私がいたという記憶も、痕跡も、全てが消えて失せる。
だから、今だけだ。今だけ、ごまかせれば良い。
壊したくないのだ。だって、この関係性が、家族という形態が、私が何度も失って、ようやく手に入れた望みなのだから。
たとえコレが手に入らないとしても、渇望した物を、私が壊して手に入れることをしてはいけないのだから――――。



ENo.746 千歳 佐久間 とのやりとり
| ▲ |
| ||



 |
翔華 「よろしくおねがいしまーす!」 |
 |
フォーティーツー 「一緒にがんばろうね。」 |









魔術LV を 3 UP!(LV10⇒13、-3CP)
料理LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議な何か。』をつくりました!
⇒ 不思議な何か。/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
翔華 「不思議な食材……ってなんでしょう、これ。」 |
フォーティーツー(411) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議ななにか。』をつくりました!
ジョウ(1244) とカードを交換しました!
[泥にはまり込んだ車輪:停滞] (クイックアナライズ)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボール を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 J-6(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-7(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 J-8(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 J-9(沼地)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 J-10(山岳)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――









ENo.144
鳳翔華



19歳
162cm
59kg
イバラシティ南部のツクナミに実家を持つ大学生。
妹と弟が一人ずついるが、妹の方が姉っぽいとは母親談。
虫嫌い。特にカマキリが嫌。嫌いというより恐怖。理由は不明。
異能は「素肌で触れている物質の熱量を熱に変換、貯蔵し、放出できる」能力。
変換できるのは「燃えるもの」。燃えやすい程変換させやすく、変換された物質は炭化を経て灰となる。
炭化させるのは肩から下の肌に触れた時で、自分の身体は影響を受けにくい。
うっかりすると着ているものが灰になるため、不燃繊維の下着と、難燃繊維のアンダーは手放せない。
熱は放出点からゆっくりと放出され、やがて物体へ至ると、放出した分が全て接点へ殺到する。
放出点は指の先、そして眼。眼の放出量は多く、勢いもあり、遠くまで届く。しかし、放出するほど、その部分も熱を持つ。
幼少期、発現し始めた頃にコントロールが効かず大やけどを負う。
上記の虫嫌いと熱に対する潜在的な恐怖から、水辺を好み、それが転じて生物学の道へ進む。
……しかしそんな事言ったらエビとかシャコとか、水辺にも虫っぽい奴はいくらでもいるのだが、水族館で魚ばかり見ていた彼女は、まだ気がついていない。
////////////////////////////////////////
鳳舞華
5つ違いの翔華の妹。中二病真っ最中。
姉よりしっかりしていると評判。だけどクールぶっているだけだったりする。
姉以上に、恐怖に近いレベルで虫が嫌い。道場で大きなムカデを見て暴走して以来、道場には何となく近づきがたいらしい。
異能は「物の熱量を爆発物に変える」
蓄えるまでは姉と一緒だが、放出するのが熱のリボンでなく、目に見える光の玉で、接触すると破裂する。基本的に花火程度のもの。
162cm
59kg
イバラシティ南部のツクナミに実家を持つ大学生。
妹と弟が一人ずついるが、妹の方が姉っぽいとは母親談。
虫嫌い。特にカマキリが嫌。嫌いというより恐怖。理由は不明。
異能は「素肌で触れている物質の熱量を熱に変換、貯蔵し、放出できる」能力。
変換できるのは「燃えるもの」。燃えやすい程変換させやすく、変換された物質は炭化を経て灰となる。
炭化させるのは肩から下の肌に触れた時で、自分の身体は影響を受けにくい。
うっかりすると着ているものが灰になるため、不燃繊維の下着と、難燃繊維のアンダーは手放せない。
熱は放出点からゆっくりと放出され、やがて物体へ至ると、放出した分が全て接点へ殺到する。
放出点は指の先、そして眼。眼の放出量は多く、勢いもあり、遠くまで届く。しかし、放出するほど、その部分も熱を持つ。
幼少期、発現し始めた頃にコントロールが効かず大やけどを負う。
上記の虫嫌いと熱に対する潜在的な恐怖から、水辺を好み、それが転じて生物学の道へ進む。
……しかしそんな事言ったらエビとかシャコとか、水辺にも虫っぽい奴はいくらでもいるのだが、水族館で魚ばかり見ていた彼女は、まだ気がついていない。
////////////////////////////////////////
鳳舞華
5つ違いの翔華の妹。中二病真っ最中。
姉よりしっかりしていると評判。だけどクールぶっているだけだったりする。
姉以上に、恐怖に近いレベルで虫が嫌い。道場で大きなムカデを見て暴走して以来、道場には何となく近づきがたいらしい。
異能は「物の熱量を爆発物に変える」
蓄えるまでは姉と一緒だが、放出するのが熱のリボンでなく、目に見える光の玉で、接触すると破裂する。基本的に花火程度のもの。
20 / 30
60 PS
チナミ区
J-10
J-10





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な何か。 | 料理 | 33 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) |
| 9 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 13 | 破壊/詠唱/火 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 料理 | 23 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| フラワリング | 5 | 0 | 90 | 敵列:魅了+領域値[地]3以上なら束縛 | |
| 決3 | ファイアボール | 5 | 0 | 180 | 敵全:火撃 |
| 決2 | クラック | 5 | 0 | 160 | 敵全:地撃&次与ダメ減 |
| アグリローズ | 5 | 0 | 180 | 敵:地痛撃&猛毒+火痛撃&炎上 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ティンダー | [ 1 ]ファイアボール |

PL / やすかけ