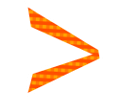<< 1:00>> 3:00




「いとはさんのところに持っていったチョコ、喜んでもらえてよかったわね。
いとはさんのお友達とも知り合いになれたし」
「ごんになった私が、ちゃんとバレンタインやクリスマスを楽しめていてよかった。
あのひとが言っていた、『一時的に記憶・姿がイバラシティに適応したものに置換される』ってこのことなのね、きっと。
私、ごんにバレンタインのことなんて教えてないし」
「私は……イバラシティにいるごんは、確かに『妖狐』であって、『人ではない』けれど、もう何にも化けることはできない」
「ごんが……本物のごんが、私になると言ってくれたから。
もう一緒に遊ぶことのできない、もう布団から出ることのできない、もう後はしんでいくだけの私の代わりに、世界を見てくれると言ったから。
広い世界で、私の代わりに友達をたくさん作ってくれると言ってくれたから。
私の姿をしていれば、二度と私のことを忘れることはないからって。
私の顔で、私の姿で友達を作れば、友達の心の中にも私が生きてくれるからって」
「今も、ここではないどこかにいる本物のごんが、最後にそう言ってくれたから」
「その言葉がうれしかったから。
そんなことを言える、そんなことを言ってくれるあの子がまぶしかったから」
「羨ましかったから。
だから私はあの子に――」
「ほんとうに?」
「ほんとうよ」
「でもいいの。ほんとうのことは」
「ほんとうのことより、侵略しないといけないの。
ほんとうにするために、侵略しないといけないの」
「戦える。侵略できる。倒せる。
排除できる。退けられる。拒絶する」
「ああ、ああ、こんなにたくさんの言葉があるのね。
誰かを倒すためにこんなにもたくさんの言葉があるのね。
地獄に来て、新しい言葉を覚えることになるなんて思わなかったけれど。
地獄に来て成長できるなんて思わなかったけれど」
「これは成長と呼ぶのかしら。
これをせいちょうと読んでいいのかしら」
「ええ、そうね、ここは地獄ではなかった。
ここはもう地獄ではなかった。
イバラシティとアンジニティのあいだの世界。はざまにある世界」
「あのひとたちと戦えばいいのね。
あのひとたちが、イバラシティ側なのね。
ええ、わかる。わかるわ。
大丈夫。だいじょうぶよ。戦える。
私の力で。私の寿命を奪ったこの力で、戦える」
「焼くことができる。
ああ、そうなのね。焼くということも戦うための言葉になり得るのね。
私の体を焼いていたように、あのひとたちを焼けばいいのね」
「私は戦っていたのね」
「ずっと」
「ウミネコさんは探偵なのね。
まだ子供なのに探偵しているなんてすごいわ。
探偵さんが出てくる本、よく読んだっけ。
楽しかったなあ」
「探偵さんが事件を解決してくれるのがすきだったわ。
見えないものを形にしてくれるのが好きだったわ。
私には何も見えなかったから。
目が見えないわけじゃないけど、この赤い目には見たいものは何も見えなかったから」
「ううん、ごめんなさい。
違うわね。
何も見えなかったわけじゃなかった。
ごん。あなたが見えたもの。
妖狐になったばかりのあなたが見えた。
何も持っていないけれど、何にでもなれるあなたが見えた」
「何にでもなれる!」
「何にでも! 誰にでも……!」
「私は何かに……」
「侵略する」
「そうね、そのための侵略だものね。
そのために焼けばいいのね」
「ウミネコさんは、強いひとだなって思ったわ。
やさしくて、強いひと。
きっとあのひとなら、この場所……ええと、そう、『ハザマ』でも、自分が探偵であることを忘れずに探偵業を始めるんだとおもう。
いえ、きっと、もう始めているわよね、きっと」
「おじいさまはここにいらしてるのかしら。
いとこの……そう、キャロルさんはいらしてるのかしら。
3人で来ていたら、きっとみんなで助け合っているわね。
だって、3人は家族ですもの」
「助け合う家族ですもの」
「おじいさま。私のおじいさま。ウミネコさんのおじいさまと、顔は似ていないけれど、でも、どこか似ている気がする」
「ううん、そう思っているだけなのかもしれない」
「私が思い込んでいるだけなのかもしれない」
「憧れていたから。
憧れの関係だから」
「おじいさまの仕事を、孫娘が手伝う」
「私にはできなかった。
私はおじいさまの期待に応えられなかった。
お母さんもお父さんも、そんなことはないと言ってくれたけど。
踊りも、神事のお手伝いも、元気になってからがんばればいいと言ってくれたけど」
「あたたかいほうじ茶」
「その機会は失われてしまった。
心配と期待をいっぱいいっぱい注いでもらったけれど、その全ては焼き尽くされてしまった。
私が焼き尽くしてしまった。私が」
「ほうじ茶の湯気みたいにじんわりあたたかいウミネコさんとおじいさんの声」
「もう叱られながら踊る必要はない。
傷みをこらえて正座をする必要はない。
大好きなおじいさまに心配かけることもない。
大好きなおじいさまを失望させることもない」
「香ばしくてふんわりとしたサンドイッチ。
一口食べるだけで、レタスやきゅうり、エビや貝のおいしさが広がっていく。
一口ごとに食感が変わる感じがして、ときどきぴりっと胡椒が主張したりして。
食べることって、こんなに楽しかったかしら」
「けれど、その記憶は私の中に残っている。
全て焼き尽くされてしまったはずなのに、それが燃えたということだけは残っている」
「だから、だから、戦える」
「まあるいタルト。ベリーとクリームがたっぷり乗っている。
食べてしまうのがもったいないくらい。
甘くて、酸っぱくて、甘酸っぱくて、やさしくて、おいしさが弾ける」
「もし相手がウミネコさんでも、戦えるわ」
「隣にはあなたがいる。
おいしそうにタルトを頬張るあなたがいる。
カウンターの奥にはおじいさんがいる」
「おじいさんがいても、戦えるわ」
「ウミネコさん。あなたは私の憧れだから。
あなたと友達になれるから。
あなたを見ていると、胸がいっぱいになるから。
あなたがすてきだから、『すてきだ』と思う私を思い出してしまうから。
私が『期待に応えられなかった私』なのだということを、思い出してしまうから」
「ああ。あなたはどちらなのかしら。
あなたたちもアンジニティの人間であってほしい」
「また、あの喫茶店に食事をしにいきたいもの。
おじいさんも、また来ていいっておっしゃってくださったし。
ウミネコさんとも話したいし」
「ごんも妖怪退治をがんばりたいって言ってたわね。
ただあの子、妖怪探しが得意じゃないのよね」
「ウミネコさんは探偵だから、きっと探すのは得意よね。
妖怪を探すのも得意だったりするかしら。
妖怪はさすがに探偵が探すものじゃないと思うけれど、ウミネコさんが探して、ごんがやっつけて、みたいなこともできたりするかしら」
「どちらかしら、ウミネコさん」
「わからなかったら聞けばいいのよね。
わからなかったら調べればいいのよね」
「ウミネコさんがイバラシティの人間だったら、戦わないといけないもの」
「戦えるけれど、戦うなら早いほうがいい。
時間が経って、決意が『鈍らない』ことが怖いから。
どれだけ友達と仲良くなっても、どれだけ同じ時間を過ごしても、『戦えない』と思えなかったら」
「決意が変わらなかったら……」
「……」



ENo.643 蚕霊いとは とのやりとり

ENo.733 ウミネコ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 こんぺいとう を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









ごん(419) は 美味しい草 を入手!
アイリ(428) は 美味しい草 を入手!
クレハ(675) は 花びら を入手!
ナナキ(1016) は 花びら を入手!
ナナキ(1016) は 毛 を入手!
クレハ(675) は 毛 を入手!
クレハ(675) は 美味しい草 を入手!
ナナキ(1016) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
クレハ(675) のもとに ちわわ が軽快なステップで近づいてきます。
クレハ(675) のもとに 大黒猫 が恥ずかしそうに近づいてきます。
クレハ(675) のもとに 歩行石壁 が恥ずかしそうに近づいてきます。



付加LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ナナキ(1016) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『南天燭』を作製してもらいました!
⇒ 南天燭/武器:強さ33/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ハナコ(1542) により ItemNo.5 不思議な石 から防具『陽炎』を作製してもらいました!
⇒ 陽炎/防具:強さ33/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
錫也(1018) とカードを交換しました!
飢餓蝦蟇の呪詛 (ストライキング)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
アグリローズ を研究しました!(深度0⇒1)
デッドリィトクシン を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
そう言ってフロントダブルバイセップス。
賞品について何だか盛り上がっているふたり。
チャットが閉じられる――


















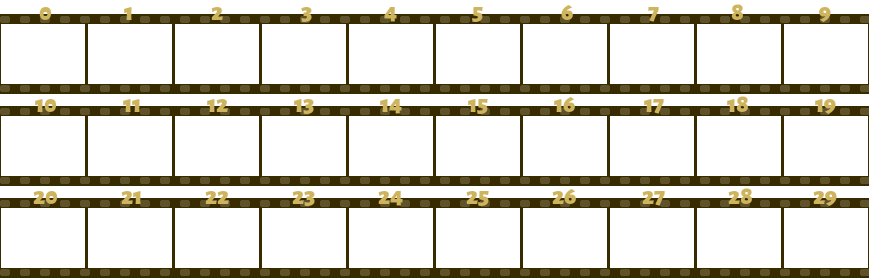





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「いとはさんのところに持っていったチョコ、喜んでもらえてよかったわね。
いとはさんのお友達とも知り合いになれたし」
「ごんになった私が、ちゃんとバレンタインやクリスマスを楽しめていてよかった。
あのひとが言っていた、『一時的に記憶・姿がイバラシティに適応したものに置換される』ってこのことなのね、きっと。
私、ごんにバレンタインのことなんて教えてないし」
「私は……イバラシティにいるごんは、確かに『妖狐』であって、『人ではない』けれど、もう何にも化けることはできない」
「ごんが……本物のごんが、私になると言ってくれたから。
もう一緒に遊ぶことのできない、もう布団から出ることのできない、もう後はしんでいくだけの私の代わりに、世界を見てくれると言ったから。
広い世界で、私の代わりに友達をたくさん作ってくれると言ってくれたから。
私の姿をしていれば、二度と私のことを忘れることはないからって。
私の顔で、私の姿で友達を作れば、友達の心の中にも私が生きてくれるからって」
「今も、ここではないどこかにいる本物のごんが、最後にそう言ってくれたから」
「その言葉がうれしかったから。
そんなことを言える、そんなことを言ってくれるあの子がまぶしかったから」
「羨ましかったから。
だから私はあの子に――」
「ほんとうに?」
「ほんとうよ」
「でもいいの。ほんとうのことは」
「ほんとうのことより、侵略しないといけないの。
ほんとうにするために、侵略しないといけないの」
「戦える。侵略できる。倒せる。
排除できる。退けられる。拒絶する」
「ああ、ああ、こんなにたくさんの言葉があるのね。
誰かを倒すためにこんなにもたくさんの言葉があるのね。
地獄に来て、新しい言葉を覚えることになるなんて思わなかったけれど。
地獄に来て成長できるなんて思わなかったけれど」
「これは成長と呼ぶのかしら。
これをせいちょうと読んでいいのかしら」
「ええ、そうね、ここは地獄ではなかった。
ここはもう地獄ではなかった。
イバラシティとアンジニティのあいだの世界。はざまにある世界」
「あのひとたちと戦えばいいのね。
あのひとたちが、イバラシティ側なのね。
ええ、わかる。わかるわ。
大丈夫。だいじょうぶよ。戦える。
私の力で。私の寿命を奪ったこの力で、戦える」
「焼くことができる。
ああ、そうなのね。焼くということも戦うための言葉になり得るのね。
私の体を焼いていたように、あのひとたちを焼けばいいのね」
「私は戦っていたのね」
「ずっと」
「ウミネコさんは探偵なのね。
まだ子供なのに探偵しているなんてすごいわ。
探偵さんが出てくる本、よく読んだっけ。
楽しかったなあ」
「探偵さんが事件を解決してくれるのがすきだったわ。
見えないものを形にしてくれるのが好きだったわ。
私には何も見えなかったから。
目が見えないわけじゃないけど、この赤い目には見たいものは何も見えなかったから」
「ううん、ごめんなさい。
違うわね。
何も見えなかったわけじゃなかった。
ごん。あなたが見えたもの。
妖狐になったばかりのあなたが見えた。
何も持っていないけれど、何にでもなれるあなたが見えた」
「何にでもなれる!」
「何にでも! 誰にでも……!」
「私は何かに……」
「侵略する」
「そうね、そのための侵略だものね。
そのために焼けばいいのね」
「ウミネコさんは、強いひとだなって思ったわ。
やさしくて、強いひと。
きっとあのひとなら、この場所……ええと、そう、『ハザマ』でも、自分が探偵であることを忘れずに探偵業を始めるんだとおもう。
いえ、きっと、もう始めているわよね、きっと」
「おじいさまはここにいらしてるのかしら。
いとこの……そう、キャロルさんはいらしてるのかしら。
3人で来ていたら、きっとみんなで助け合っているわね。
だって、3人は家族ですもの」
「助け合う家族ですもの」
「おじいさま。私のおじいさま。ウミネコさんのおじいさまと、顔は似ていないけれど、でも、どこか似ている気がする」
「ううん、そう思っているだけなのかもしれない」
「私が思い込んでいるだけなのかもしれない」
「憧れていたから。
憧れの関係だから」
「おじいさまの仕事を、孫娘が手伝う」
「私にはできなかった。
私はおじいさまの期待に応えられなかった。
お母さんもお父さんも、そんなことはないと言ってくれたけど。
踊りも、神事のお手伝いも、元気になってからがんばればいいと言ってくれたけど」
「あたたかいほうじ茶」
「その機会は失われてしまった。
心配と期待をいっぱいいっぱい注いでもらったけれど、その全ては焼き尽くされてしまった。
私が焼き尽くしてしまった。私が」
「ほうじ茶の湯気みたいにじんわりあたたかいウミネコさんとおじいさんの声」
「もう叱られながら踊る必要はない。
傷みをこらえて正座をする必要はない。
大好きなおじいさまに心配かけることもない。
大好きなおじいさまを失望させることもない」
「香ばしくてふんわりとしたサンドイッチ。
一口食べるだけで、レタスやきゅうり、エビや貝のおいしさが広がっていく。
一口ごとに食感が変わる感じがして、ときどきぴりっと胡椒が主張したりして。
食べることって、こんなに楽しかったかしら」
「けれど、その記憶は私の中に残っている。
全て焼き尽くされてしまったはずなのに、それが燃えたということだけは残っている」
「だから、だから、戦える」
「まあるいタルト。ベリーとクリームがたっぷり乗っている。
食べてしまうのがもったいないくらい。
甘くて、酸っぱくて、甘酸っぱくて、やさしくて、おいしさが弾ける」
「もし相手がウミネコさんでも、戦えるわ」
「隣にはあなたがいる。
おいしそうにタルトを頬張るあなたがいる。
カウンターの奥にはおじいさんがいる」
「おじいさんがいても、戦えるわ」
「ウミネコさん。あなたは私の憧れだから。
あなたと友達になれるから。
あなたを見ていると、胸がいっぱいになるから。
あなたがすてきだから、『すてきだ』と思う私を思い出してしまうから。
私が『期待に応えられなかった私』なのだということを、思い出してしまうから」
「ああ。あなたはどちらなのかしら。
あなたたちもアンジニティの人間であってほしい」
「また、あの喫茶店に食事をしにいきたいもの。
おじいさんも、また来ていいっておっしゃってくださったし。
ウミネコさんとも話したいし」
「ごんも妖怪退治をがんばりたいって言ってたわね。
ただあの子、妖怪探しが得意じゃないのよね」
「ウミネコさんは探偵だから、きっと探すのは得意よね。
妖怪を探すのも得意だったりするかしら。
妖怪はさすがに探偵が探すものじゃないと思うけれど、ウミネコさんが探して、ごんがやっつけて、みたいなこともできたりするかしら」
「どちらかしら、ウミネコさん」
「わからなかったら聞けばいいのよね。
わからなかったら調べればいいのよね」
「ウミネコさんがイバラシティの人間だったら、戦わないといけないもの」
「戦えるけれど、戦うなら早いほうがいい。
時間が経って、決意が『鈍らない』ことが怖いから。
どれだけ友達と仲良くなっても、どれだけ同じ時間を過ごしても、『戦えない』と思えなかったら」
「決意が変わらなかったら……」
「……」



ENo.643 蚕霊いとは とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.733 ウミネコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



| アイリ 「まあ、まあ。こんなにかわいらしい子たちが、これまでずっと苦労して……ぐすん」 |
| アイリ 「でもきっともう大丈夫よ~。イバラシティはいいところよ、頑張っていきましょうねぇ」 |
 |
クレハ 「…今回から合流であったか。ややこしい摂理よな。」 |
 |
クレハ 「…まぁ良い。」 |
 |
クレハ 「我が名クレハ。北東の角の偉大なる王…の麗しき美姫である!」 |
 |
クレハ 「麗しいと美しい、合わさったら最強に見えるだろう。最強だからな。仕方無いね!」 |
| ナナキ 「荒廃せし夢の跡…ここが世界と世界の狭間。フフ、さぁ皆の者、宴が始まるようだぞ、遅れるわけにはいかないな」 |
| ナナキ 「…?む?前回も似たようなことを言っていたようだと?きのせい!きのせいなのじゃ!!!あれはただの練習!!!今回が本番!!!!!」 |
ItemNo.6 こんぺいとう を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





TriQ Shots
|
 |
TeamNo.428
|



ごん(419) は 美味しい草 を入手!
アイリ(428) は 美味しい草 を入手!
クレハ(675) は 花びら を入手!
ナナキ(1016) は 花びら を入手!
ナナキ(1016) は 毛 を入手!
クレハ(675) は 毛 を入手!
クレハ(675) は 美味しい草 を入手!
ナナキ(1016) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
クレハ(675) のもとに ちわわ が軽快なステップで近づいてきます。
クレハ(675) のもとに 大黒猫 が恥ずかしそうに近づいてきます。
クレハ(675) のもとに 歩行石壁 が恥ずかしそうに近づいてきます。



付加LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ナナキ(1016) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『南天燭』を作製してもらいました!
⇒ 南天燭/武器:強さ33/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ハナコ(1542) により ItemNo.5 不思議な石 から防具『陽炎』を作製してもらいました!
⇒ 陽炎/防具:強さ33/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
ハナコ 「揺らめきを纏う、か……いいね、実にいい。我々はそれくらい、自分のルールを世界に押し付けなくてはね」 |
錫也(1018) とカードを交換しました!
飢餓蝦蟇の呪詛 (ストライキング)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
アグリローズ を研究しました!(深度0⇒1)
デッドリィトクシン を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「わぁぁ!!なんですなんですぅ!!!?」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「告知?なんでしょう??」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「ハチャメチャトーナメントバトル!楽しそうですねぇ!!」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
エディアン 「そうですよねぇ。息抜きって大事だと思います。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!豪華賞品も考えてるんですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「賞品はあると燃えますね!豪華賞品・・・・・ホールケーキとか。」 |
 |
ノウレット 「ホールケーキ!!1人1個用意しちゃいますっ!!?」 |
 |
エディアン 「夢のようですね!食べきれるか怪しいですけど。」 |
賞品について何だか盛り上がっているふたり。
 |
ノウレット 「・・・・・あ!でも開催はすぐじゃなくてまだ先なんです!! 賞品の準備とかもありますしぃー!!」 |
 |
エディアン 「わかりました、楽しみにしていますね。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
チャットが閉じられる――







JC/DK/保護者/保護柱(大)
|
 |
TeamNo.419
|


ENo.419
『ごん』



操術にして装術にして葬術使い。
外見は小学生ぐらいに見える。
身長は130cmくらい。
この姿は可能性。
『夢』を見ず、自らを否定した彼女の可能性。
この姿は可能性。
幼い彼女が目を落とす直前に託した願いの姿。
――託したはずのそれを彼女はねだった。
あの子になりたいと強請ってしまった。
そして彼女はあの子になった。
未来を対価にあの子になった。
あの子として彼女は生きる。
その虚しさに気づくときまで。
あの子として彼女は生きる。
それにさえ意味があるのだと気づくときまで。
……いやだ、気づきたくない。
虚しさも意味も知りたくない。
……いやよ、忘れたいの。
おれがほんとうは『私』だなんて、忘れてしまいたい。
だから、彼女は『侵略』する。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記憶力判定に成功すれば、あなたは彼女(『ごん』)の姿が、とある塔で見かけた「銀髪青目の妖狐」と同じ姿であることに気づいてもいい
(その上で洞察力判定に成功すれば、あなたは彼女が「塔にいた銀髪青目の妖狐」とは別人であることに気づいてもいい)。
また、「ハザマ」内で現れる黒髪の少女が、『ごん』と同じ顔をしており、外見年齢的にもほぼ同じであるとあなたは気づいてもいい。
※キャラクターイラストとアイコンNo0~8はすまちー様(@sumachi)に、No.9、26~29はけそ様(@kso_)に、それぞれコミッションにて描いていただきました。
※十card使用させていただいております(http://rainpark.sub.jp/palir/jucard.html)。
※メッセージ等はお気軽にどうぞ。
外見は小学生ぐらいに見える。
身長は130cmくらい。
この姿は可能性。
『夢』を見ず、自らを否定した彼女の可能性。
この姿は可能性。
幼い彼女が目を落とす直前に託した願いの姿。
――託したはずのそれを彼女はねだった。
あの子になりたいと強請ってしまった。
そして彼女はあの子になった。
未来を対価にあの子になった。
あの子として彼女は生きる。
その虚しさに気づくときまで。
あの子として彼女は生きる。
それにさえ意味があるのだと気づくときまで。
……いやだ、気づきたくない。
虚しさも意味も知りたくない。
……いやよ、忘れたいの。
おれがほんとうは『私』だなんて、忘れてしまいたい。
だから、彼女は『侵略』する。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記憶力判定に成功すれば、あなたは彼女(『ごん』)の姿が、とある塔で見かけた「銀髪青目の妖狐」と同じ姿であることに気づいてもいい
(その上で洞察力判定に成功すれば、あなたは彼女が「塔にいた銀髪青目の妖狐」とは別人であることに気づいてもいい)。
また、「ハザマ」内で現れる黒髪の少女が、『ごん』と同じ顔をしており、外見年齢的にもほぼ同じであるとあなたは気づいてもいい。
※キャラクターイラストとアイコンNo0~8はすまちー様(@sumachi)に、No.9、26~29はけそ様(@kso_)に、それぞれコミッションにて描いていただきました。
※十card使用させていただいております(http://rainpark.sub.jp/palir/jucard.html)。
※メッセージ等はお気軽にどうぞ。
21 / 30
82 PS
チナミ区
I-11
I-11



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 南天燭 | 武器 | 33 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 5 | 陽炎 | 防具 | 33 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]防御10(LV20)[効果3]治癒10(LV30) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 付加 | 23 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 80 | 自:DF増(2T) | |
| 決1 | イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 | |
| チャージ | 5 | 0 | 60 | 敵:4連鎖撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】[スキル使用設定不要]生産行動『効果付加』時、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]アグリローズ | [ 1 ]デッドリィトクシン |

PL / bisnon