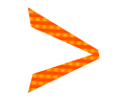<< 0:00>> 2:00




それは榊を名乗る人物が『イバラシティが侵略されている』と告げた、ある騒がしい日の夕刻のこと。
熾盛天晴学園の三年生である神実はふりは、ゲームセンターの待ち椅子に座り、スマートフォンの画面に視線を落としていた。
何か考え事でもしているような、神妙で、難しい表情を浮かべながら。
「……やれやれ~、やっぱりか。まあ、疑うようなことでもないかもしれないけど」
端末に映されていたのはメモ帳の画面だ。そこには箇条書きで何行かの文章が綴られていた。
たとえば、突然男の声が聞こえただとか。あるいは、侵略とかいう訳分からないことを言われただとか。
つまるところ、聞き取り調査の記録だった。本当にあの言葉が、全員に聞こえていたのかどうかの。
「ま、裏は取っておいて損はないからね~……私もずいぶんと動きを決めやすくなるってものだし」
そう言うと、はふりはくるくると手の中でスマートフォンを弄んでから、それをパーカーのポケットにしまった。
あと一人二人くらいに話を聞いておいてもいいだろう。特にまだ『こういう場所』にいる人からはあまり話を聞けていない。
そして、そういう人種からはどうすれば情報を聞き出しやすいかも、はふりはきちんと知っていた。
「……えーっと、それじゃあ……誰に行こうかな」
金色をした瞳で、ゲームセンターの中を行き交う客のことをぼんやりと、しかし注意を払いつつ眺める。
果たして誰であれば、すぐに話をしてくれるだろうか。こちらの『対応』次第で、もっと詳しい事を言ってくれそうな人は。
カモと言えば言い方は悪いのだが、ターゲットの属性をきちんと見分ける事は調査を行う上で必要なことだ、と。
そして、彼女の視線は——ひとりの少年に止まった。
「ん……?」
じいっと、じいっとその少年を眺めるはふり。その視線の先に居るのは、茶髪をした同年代前後の男子だった。
先程のはふりと同じようにスマートフォンを眺める彼は、何の事はない、ごくごく普通の少年にも思える。
おそらく話には応じてくれるであろう。世間話なら簡単そうだ。しかし、極端に『騙しやすい』ようには見えない。
その彼からはふりが視線を離すことができない理由が、ひとつあった。
「……似てる。たぶんだけど、私と。能力が」
騒がしいゲームの音に掻き消されてしまうような声で、彼女はそう独りごちた。
——神実はふりには、普通の人間が見えない物が見えてしまう。
それは彼女の情報分析能力だとかそういうことを抜きにした、もっと根本的で、かつスピリチュアルな物として。
すなわち、一般的に言うところの霊感がある。それでほとんど語弊はないはずだ。
彼女の目に、その少年はどう映っていたのだろう。同族であるのか、あるいは、普段彼女が『見ているもの』なのか。
しかし、少なくとも。彼女は彼を見た上で似ていると判断し、なおかつ倒すべきものではないと理解した。
つまり自身と似ていて、なおかつどうやら敵対的ではないらしく、それも年齢が近く、世間話には応じてくれそうな、少年。
はふりは薄く微笑む。ここに至って、彼女の次のターゲットは決まったと言ってよかった。
彼女はやおら待ち椅子から立ち上がる。そして人混みの中をするすると抜けて。
スマートフォンをじっと眺めている彼の後ろに忍び寄って、ぽんぽん、とその背中を叩くのだった。
「——やっほ~。今暇かな、少年?」
■ ■ ■
「嫌な場所だね」
あの男が言っていた場所——『ハザマ』に降りたはふりは、開口一番そう言った。
金の瞳をしかめて眺める大地は、普段の彼女が見ている世界よりもずっと暗い。
突然蔵の中にでも放り込まれてしまったかのような気分になるのも無理からぬことだ。
彼女はイバラシティの住民だった。否、本質的にはそうではないが、少なくとも今は。
アンジニティの人間でなく、イバラシティのために戦おうと彼女自身が決めている以上。
その心だけが、神実はふりという人間をイバラシティの存在であると規定するのだ。
「さ、て。この場所でこれが役に立つのか……分かんないけど」
スマートデバイスを取り出し、画面上で印を切るかのようにすいすいと指を動かす。
すると——彼女の手元に、漆黒の鞘に納められた一本の日本刀が姿を現した。
代行召喚術式の再生。『組織』の技術による、魔術が使えない彼女へのサポートである。
はふりはそれをしっかりと握りしめると、再度周囲を見渡した。
ここからは戦いだ。何が起こるか分からない以上、警戒だけはしておかなければならない。
彼女の視線は、イバラシティで見せた表情とは全く違う、厳しく鋭いものだった。
そう、異能機関のエージェントの一人としてのそれだ。
「……まずは信頼できる人を探さなきゃ。
うーん、ザクロ先生とか伐都君、結城ちゃん、あと……かぎ君とかいればいいんだけどね」
ひとりごちると、はふりはハザマでの第一歩目を踏み出した。



ENo.307 天河 ザクロ とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。








武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程3の武器『護身の霊刀・影打』を作製しました!
⇒ 護身の霊刀・影打/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
かぎ(912) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『お札』を作製しました!
楓&大地(158) とカードを交換しました!
珈琲の試供品 (ヒール)
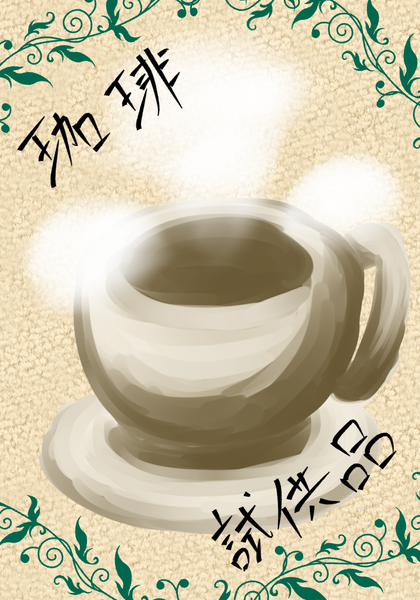

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)
エキサイト を習得!
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
イレイザー を習得!
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調26⇒25)
かぎ(912) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



それは榊を名乗る人物が『イバラシティが侵略されている』と告げた、ある騒がしい日の夕刻のこと。
熾盛天晴学園の三年生である神実はふりは、ゲームセンターの待ち椅子に座り、スマートフォンの画面に視線を落としていた。
何か考え事でもしているような、神妙で、難しい表情を浮かべながら。
「……やれやれ~、やっぱりか。まあ、疑うようなことでもないかもしれないけど」
端末に映されていたのはメモ帳の画面だ。そこには箇条書きで何行かの文章が綴られていた。
たとえば、突然男の声が聞こえただとか。あるいは、侵略とかいう訳分からないことを言われただとか。
つまるところ、聞き取り調査の記録だった。本当にあの言葉が、全員に聞こえていたのかどうかの。
「ま、裏は取っておいて損はないからね~……私もずいぶんと動きを決めやすくなるってものだし」
そう言うと、はふりはくるくると手の中でスマートフォンを弄んでから、それをパーカーのポケットにしまった。
あと一人二人くらいに話を聞いておいてもいいだろう。特にまだ『こういう場所』にいる人からはあまり話を聞けていない。
そして、そういう人種からはどうすれば情報を聞き出しやすいかも、はふりはきちんと知っていた。
「……えーっと、それじゃあ……誰に行こうかな」
金色をした瞳で、ゲームセンターの中を行き交う客のことをぼんやりと、しかし注意を払いつつ眺める。
果たして誰であれば、すぐに話をしてくれるだろうか。こちらの『対応』次第で、もっと詳しい事を言ってくれそうな人は。
カモと言えば言い方は悪いのだが、ターゲットの属性をきちんと見分ける事は調査を行う上で必要なことだ、と。
そして、彼女の視線は——ひとりの少年に止まった。
「ん……?」
じいっと、じいっとその少年を眺めるはふり。その視線の先に居るのは、茶髪をした同年代前後の男子だった。
先程のはふりと同じようにスマートフォンを眺める彼は、何の事はない、ごくごく普通の少年にも思える。
おそらく話には応じてくれるであろう。世間話なら簡単そうだ。しかし、極端に『騙しやすい』ようには見えない。
その彼からはふりが視線を離すことができない理由が、ひとつあった。
「……似てる。たぶんだけど、私と。能力が」
騒がしいゲームの音に掻き消されてしまうような声で、彼女はそう独りごちた。
——神実はふりには、普通の人間が見えない物が見えてしまう。
それは彼女の情報分析能力だとかそういうことを抜きにした、もっと根本的で、かつスピリチュアルな物として。
すなわち、一般的に言うところの霊感がある。それでほとんど語弊はないはずだ。
彼女の目に、その少年はどう映っていたのだろう。同族であるのか、あるいは、普段彼女が『見ているもの』なのか。
しかし、少なくとも。彼女は彼を見た上で似ていると判断し、なおかつ倒すべきものではないと理解した。
つまり自身と似ていて、なおかつどうやら敵対的ではないらしく、それも年齢が近く、世間話には応じてくれそうな、少年。
はふりは薄く微笑む。ここに至って、彼女の次のターゲットは決まったと言ってよかった。
彼女はやおら待ち椅子から立ち上がる。そして人混みの中をするすると抜けて。
スマートフォンをじっと眺めている彼の後ろに忍び寄って、ぽんぽん、とその背中を叩くのだった。
「——やっほ~。今暇かな、少年?」
■ ■ ■
「嫌な場所だね」
あの男が言っていた場所——『ハザマ』に降りたはふりは、開口一番そう言った。
金の瞳をしかめて眺める大地は、普段の彼女が見ている世界よりもずっと暗い。
突然蔵の中にでも放り込まれてしまったかのような気分になるのも無理からぬことだ。
彼女はイバラシティの住民だった。否、本質的にはそうではないが、少なくとも今は。
アンジニティの人間でなく、イバラシティのために戦おうと彼女自身が決めている以上。
その心だけが、神実はふりという人間をイバラシティの存在であると規定するのだ。
「さ、て。この場所でこれが役に立つのか……分かんないけど」
スマートデバイスを取り出し、画面上で印を切るかのようにすいすいと指を動かす。
すると——彼女の手元に、漆黒の鞘に納められた一本の日本刀が姿を現した。
代行召喚術式の再生。『組織』の技術による、魔術が使えない彼女へのサポートである。
はふりはそれをしっかりと握りしめると、再度周囲を見渡した。
ここからは戦いだ。何が起こるか分からない以上、警戒だけはしておかなければならない。
彼女の視線は、イバラシティで見せた表情とは全く違う、厳しく鋭いものだった。
そう、異能機関のエージェントの一人としてのそれだ。
「……まずは信頼できる人を探さなきゃ。
うーん、ザクロ先生とか伐都君、結城ちゃん、あと……かぎ君とかいればいいんだけどね」
ひとりごちると、はふりはハザマでの第一歩目を踏み出した。



ENo.307 天河 ザクロ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。







武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程3の武器『護身の霊刀・影打』を作製しました!
⇒ 護身の霊刀・影打/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
かぎ(912) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『お札』を作製しました!
楓&大地(158) とカードを交換しました!
珈琲の試供品 (ヒール)
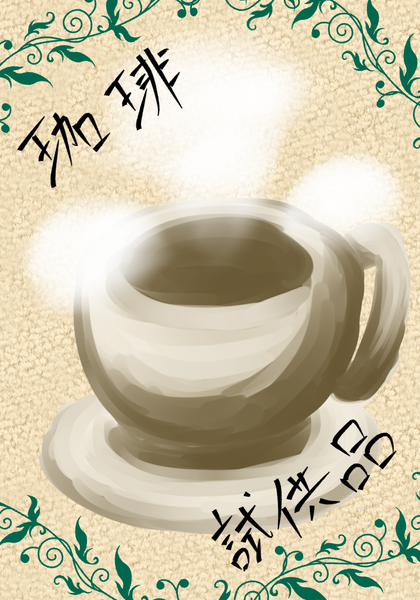

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)
エキサイト を習得!
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
イレイザー を習得!
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調26⇒25)
かぎ(912) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――







ENo.860
神実はふり



かんざね はふり。
ある日熾盛天晴学園に転校してきた高校三年生の女子。
リボン付きワイシャツの上からパーカー着用。ギンガムチェックのスカート、ニーソックス、ローファーを身に着けている。
身長は150cmあるかないか。細身で小さい。黒髪ストレート、金色をしたどことなく眠たげにも映る瞳。
普段の表情もなんとなくふわっとしているような印象。よく言えば浮世離れ、悪く言えば何を考えているか読み取りづらい。
とある『機関』のエージェントであり、何らかの使命を負ってイバラシティに潜入している。
熾盛天晴学園はその潜伏先である。だが、どうやら普通に高校生活を楽しんでいるようだ。
はふりの身の上を知るのは、彼女が信頼していると考えられるごくごく一部の人間に限られる。
学校での彼女はいたって普通の人間である。
平均的な学力、平均的な運動能力、誰かと深く仲良くなるわけでも、激しくいがみ合うわけでもない。
まさに絵に描いたような『一般的な』女子高生としてハレ高生活を過ごしている。
甘いものが好きであり、よくシュークリームなどを食べている。
またエナジードリンクを愛飲している。これは彼女が朝起きるのが苦手なことに起因しているらしい。
似たような理由で紙パック入りのカフェオレなども好んで買っている。
人の体温を感じることが好き。もっと言えば『生きていると分かること』が好き。
そのためよく男女を問わず他人にくっついたり手を握ったりなどのスキンシップを図る。
スマホ中毒のきらいがあり、人と話しているときにも時たま画面に目を落としていることがある。
異能は『神通力』。
武器や体に不可思議な力を纏わせることにより、それらを強化して戦うことができる。
また、彼女には他の人間には感知しづらい『悪いもの』が見えてしまう。
加えて、ほんの些細な力ではあるが物体移動能力の真似事のようなこともできる。
そのため普段の彼女はテレキネシストとして振る舞い、本来の能力を隠している。
武器として刀を扱うが、剣道部所属というわけではなく、振り方や扱い方は完全に我流。
というよりも、もはや結果的に斬れているだけでそのやり口は鈍器のそれに近くもある。
これに上記の『神通力』を組み合わせての近接戦闘がはふりの戦い方である。
(プロフィール画像、アイコンは渡部アクサ様より頂きました。
この場を借りてお礼を申し上げます)
ある日熾盛天晴学園に転校してきた高校三年生の女子。
リボン付きワイシャツの上からパーカー着用。ギンガムチェックのスカート、ニーソックス、ローファーを身に着けている。
身長は150cmあるかないか。細身で小さい。黒髪ストレート、金色をしたどことなく眠たげにも映る瞳。
普段の表情もなんとなくふわっとしているような印象。よく言えば浮世離れ、悪く言えば何を考えているか読み取りづらい。
とある『機関』のエージェントであり、何らかの使命を負ってイバラシティに潜入している。
熾盛天晴学園はその潜伏先である。だが、どうやら普通に高校生活を楽しんでいるようだ。
はふりの身の上を知るのは、彼女が信頼していると考えられるごくごく一部の人間に限られる。
学校での彼女はいたって普通の人間である。
平均的な学力、平均的な運動能力、誰かと深く仲良くなるわけでも、激しくいがみ合うわけでもない。
まさに絵に描いたような『一般的な』女子高生としてハレ高生活を過ごしている。
甘いものが好きであり、よくシュークリームなどを食べている。
またエナジードリンクを愛飲している。これは彼女が朝起きるのが苦手なことに起因しているらしい。
似たような理由で紙パック入りのカフェオレなども好んで買っている。
人の体温を感じることが好き。もっと言えば『生きていると分かること』が好き。
そのためよく男女を問わず他人にくっついたり手を握ったりなどのスキンシップを図る。
スマホ中毒のきらいがあり、人と話しているときにも時たま画面に目を落としていることがある。
異能は『神通力』。
武器や体に不可思議な力を纏わせることにより、それらを強化して戦うことができる。
また、彼女には他の人間には感知しづらい『悪いもの』が見えてしまう。
加えて、ほんの些細な力ではあるが物体移動能力の真似事のようなこともできる。
そのため普段の彼女はテレキネシストとして振る舞い、本来の能力を隠している。
武器として刀を扱うが、剣道部所属というわけではなく、振り方や扱い方は完全に我流。
というよりも、もはや結果的に斬れているだけでそのやり口は鈍器のそれに近くもある。
これに上記の『神通力』を組み合わせての近接戦闘がはふりの戦い方である。
(プロフィール画像、アイコンは渡部アクサ様より頂きました。
この場を借りてお礼を申し上げます)
25 / 30
50 PS
チナミ区
D-9
D-9




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 護身の霊刀・影打 | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 20 | 武器作製と、武器への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| クイックアナライズ | 5 | 0 | 200 | 敵全:AG減 |
| ウィークポイント | 5 | 0 | 140 | 敵:3連痛撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]イレイザー |

PL / タカミ