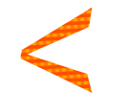<< 0:00>> 2:00




見晴らしのいい道を、白いミニバンが走っていく。
今は年末のシーズンで、周りの家々の中には電飾を取り付けられたものも少なくなかった。発光ダイオードの連なりでできたサンタクロースだのスノーマンだのは、視界の隅を通り過ぎるだけでもいくらかの注意を引く。
「っへ、みーんな年の暮れで浮かれてやがるぜ、座間さんよぉ」
運転手の男、ロシュ・ブーリアン―――日本人ではない。金髪で、青い目をしている―――は、助手席に座るふくよかな女性に声をかけた。
「いいんじゃないですかぁ、平和で。あたしらのお仕事って、普通の人たちが浮かれてられるようにがんばることでしょ?」
女、座間為知(ざま ししる)は、四十度ほどリクライニングをしている。
「……違えねェや」
ロシュは、行く手にそびえる富士山を見上げた。雪化粧が夕日を浴びて、オレンジに輝いている。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
ミニバンは富士山のふもと近く、人気のない場所にある四角い建物のそばに停まった。
ロシュは先に車を降りると豆腐の入口へ足早に向かい、ドアスコープを見つめた。それだけでひとりでに鍵が開き、暗闇がロシュを迎え入れる。
しばし灯りのスイッチを探り、ふと振り返ると、コウモリの翼を生やした悪魔の影がそこにいた。
「電気、こっちっすよ」
悪魔……もとい為知は、部屋を明るくした。つやつやの革でできた翼が、背中から顔を出している。
「ちゃちゃっと戻りましょ、お土産もあることですし」
為知は入口の反対側にあるテーブルへ歩き、ロシュを手招きする―――彼女はその背中に、青いドラゴンを一匹、背負っていた。
無論本物ではなく、そういうデザインの鞄である。かつて東京都心の店で見かけ、本人曰く『一目ぼれ』したらしい為知がその場で購入し、今日の日まで使い続けていた。ロシュの目から見てもなかなか格好いい代物だったが、あいにく為知がやたらと物を詰めこむせいでぶくぶくに太ってしまっている。ペットは飼い主に似るとはよく言ったものだ、イヤ違うか、とロシュはたまに思う。
さてそのロシュは、テーブルの引き出しの裏にあるボタンをトン、トト、トントと指で突っついた。するとテーブル下の床がスライドし、パネルが現れる。このパネルに今度は指をくっつけ声を当て、とどめに瞳を見せてやると、また横にずれてゆき、後には抜け穴が一つ残った。
そのまま穴に飛び込んで、滑るように梯子を下りる。
「うー、もうちっとこれ、別な仕組み考えらんなかったのかなぁ」
後から来る為知は、豊満なバストをコンクリート打ちっ放しの壁にこすりつけぬよう、ゆっくり降りざるを得ない。
「痩せとけ」
ロシュは相方が降りてくるのを待たずに先へ進んだ。
人に踏まれてはじめて動くリフトに乗りこみ、しばらく待てば、視界が開ける。彼らは巨大な球状の入れ物の中に入っていっているところだ。この球の中にはより小さな球や、四角い部屋がいくつも見える―――実際こんな風になっているわけではなく、いずれも土に埋もれてはいるのだが、その土を除いたらこうなるというのを映像で見せているのだった。
「もう、待ってよぉ、ロシュさんっ」
リフトのシャフトを滑り降りてきた為知に、ロシュは一言、おつかれと告げた。
彼の手には生もののお土産がある。あともういくつかセキュリティを通過しないといけないので、あまりのんびりはしていられない。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
少年がひとり、飾りっけのない部屋にいた。
屋内だというのに灰色のニット帽を被った少年、宮田一穂(みやた かずほ)は、壁際に備え付けられたデスクで海洋生物の図鑑を読んでいた。戻す本棚はこの部屋にはない。明日の朝にでも、元あった場所に返してもらうことになっている。
デスクの横には、作り物の空と太陽がしまわれた窓がある。生活リズムを狂わせないためのものだが、読書の邪魔になるのでカーテンで遮っておいてある。その上には壁掛け時計とエアコンがあり、反対の壁際にはパイプを溶接して造られたベッドが一つと、ウォーターサーバー。あとは電話もある。その傍にあるドアの向こうは、トイレもついたバスルーム。
これらが少年の住まいの全てで、後は本当に何もない。だけどそれでよかった。
チャイムが鳴った。少年は本にしおりを入れて閉じ、部屋の出入り口となるドアへ歩く。
「一穂、開けるぞー。糖分だ」
聞き慣れた声がして、ドアが開く。そこにはロシュがいた。遠くからは皿の触れ合う音もする。
「おーら、出てこい出てこい」
ロシュに肩を引かれて一穂は外に出る。
短い通路を抜けるとそこは円形の部屋で、一穂の部屋の何倍もの面積をもっているようだった。真ん中の十数人くらいで使えそうな丸テーブルに、為知がお皿とコップ、それからフォークを並べている。他にも四人ほど人がいて、もう椅子にかけていた。
「クリスマスケーキだってさ。私ら、もうンな歳でもないんじゃなくって」
水色の髪の少女が一穂に声をかける。
「美香さん、適度に糖分を摂取できることは望ましいと考えられます」
そう一穂が応えれば、尖った髪形をした茶髪の少年が思い切り呆れて、
「あーッたく……お前さァ、お祭りだぞ? レーションとか食おうってわけじゃねェンだぞ?」
「よせ、昭。一穂には一穂の感情があるんだと、ずっと言っているじゃないか。楽しいからって押し付けるのはよくない」
彼の隣にいたメガネの少年が、茶髪の子―――昭をなだめた。
四人の少年少女はみな同じくらいの年齢だが、何もかもが違っていた。一穂はずいぶん痩せているし、無機質だ。水色の子―――川野美香(かわの よしか)はそこそこ自慢できる程度に身体が引き締まっていて、眼光も鋭い。三島昭(みしま あきら)はぐんぐんと背を伸ばし、こんな地下施設にいなければスポーツ選手でも目指していたかもしれない。メガネをかけた村田実(むらた みのる)は白衣を普段着にしており、何かしらの実験の手伝いをさせてもらえる日を楽しみにしている。
彼らの他に、もう一人カール・ケンドという初老の男性がいた。だいぶおでこが広くなってはいるものの、背筋は張って歯並びもよく、くたびれた様子はない。彼は膝の上に猫を一匹乗せていた。白磁の様に滑らかで、毛が生えていない猫だった。それどころか異常に柔軟で、骨すら入っていないように見えるほどだ。
「お元気でしたか、一穂君?」
「はい」
カールの穏やかな挨拶を平坦極まる声で返し、一穂は席に着く。既にブッシュ・ド・ノエルがテーブルの上にその身を晒し、為知にカットされているところだった。美香、昭、実、それから為知がトッピングをほどほどに奪い合い、あとの三人は残ったものを皿へ運ぶ。
「おし、食う前に宣誓ッ! 来年のクリスマスも、ぜってェ、今ここにいる奴ら、みんな揃ってお祝いするぞォ!」
と、昭。
一穂にはわかっていた。確かに、去年も同じお祝いをした。ケーキはもう数ミリほど長く、為知は二キロばかり痩せていた。隣にいたのは自分ではなく美香で、青いスカートを履き、さっき昭が自分に言ったのと同じことを、その時は彼女が言っていた。実のメガネはあの後破壊されてしまったので、今年のとは違う―――
それはお祝いそのものの性質を変えてしまうような差異ではないが、確かな記憶である。何もかも、文字通り何もかもを、一穂は覚えていた。
去年の今頃、この部屋から三キロ離れた研究棟で、何が起ころうとしていたのかも。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
神はサイコロを振らないわけではない。けれど、そのサイコロは出来損ないなのかもしれない。
ブゥーッ! ブゥーッ! アラームが、穏やかな空気を引き裂いた。
「緊急事態発生、緊急事態発生。スフィア06第三研究棟、DE-615の実験にて事故発生。時空間安定プログラムを使用できる職員は、その場ですぐに行動されたし。繰り返す。スフィア06第三研究棟、DE-615の実験にて事故発生。時空間安定プログラムを使用できる職員は、その場ですぐに行動されたし……」
喋るものなど居ようはずもなかった。一同はわずかな時間凍り付き、すぐさま熱を取り戻した。
「は、ハチバン倉庫! 時空間のヤツってあっこじゃないと……ッ!」
為知が上ずった声を上げ、どたどたと部屋のロッカーへ駆けていく。中から分厚いコートを取り出して羽織った。ロシュ、カールもそれに続き、白磁の猫も何故だかついていく。
「悪ィな、留守番頼まァ!」
と、白い歯を見せ、同僚に上司、それから猫と一緒に部屋を去るロシュ。
あとの少年少女四人は、それぞれの部屋に戻るでもなく、その場に立ち尽くす。戻って、布団被って震えてでもいれば、そのうちどうにかなる類の問題ではない―――全員がわかっていた。
時計の音と、心臓の音と、アラームの周期。全部がうまく噛み合わなくて、余計に気持ちが悪かった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
―――それからすこし、時は流れて。
ふと目を開ければ目の前には柵。それから、黒い大地を満たす電気の灯たち。
異能者の世界の都市『イバラシティ』、その一画たる『ツクナミ区』は夜の帳の中で絢爛たる賑わいを見せていた。東の『マシカ区』、その反対の『ウラド区』、北方の『コヌマ区』と比較しても、ツクナミの街並みは異常に発展しているように思える。元々こんな場所だったのか、ここしばらくで急激に発展してしまったというのか、なぜかはっきりしない。
街を見下ろしているのは、宮田一穂である。
現実に立ち返った彼は、展望台に風を遮ってもらえる場所に寝袋を敷いた。枕はビニール袋を詰めたものだ。中に入ってしまえばそれなりに暖かいし、カイロも使えば凍死の可能性は減る。
この世界に戸籍を持たない以上は、とりあえずこうするしかなかった。
そう、なんとか、生きていかなくてはならないのだ。
自分は、失われるべきではないものなのだから。



特に何もしませんでした。








魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
影道 律(1247) とカードを交換しました!
ポッキー (ヒール)

ティンダー を習得!
ラッシュ を習得!
レッドゾーン を習得!
ファイアボール を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 H-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
結乃(233) をパーティに勧誘しました!
チホ(388) をパーティに勧誘しました!
恋文(400) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



見晴らしのいい道を、白いミニバンが走っていく。
今は年末のシーズンで、周りの家々の中には電飾を取り付けられたものも少なくなかった。発光ダイオードの連なりでできたサンタクロースだのスノーマンだのは、視界の隅を通り過ぎるだけでもいくらかの注意を引く。
「っへ、みーんな年の暮れで浮かれてやがるぜ、座間さんよぉ」
運転手の男、ロシュ・ブーリアン―――日本人ではない。金髪で、青い目をしている―――は、助手席に座るふくよかな女性に声をかけた。
「いいんじゃないですかぁ、平和で。あたしらのお仕事って、普通の人たちが浮かれてられるようにがんばることでしょ?」
女、座間為知(ざま ししる)は、四十度ほどリクライニングをしている。
「……違えねェや」
ロシュは、行く手にそびえる富士山を見上げた。雪化粧が夕日を浴びて、オレンジに輝いている。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
ミニバンは富士山のふもと近く、人気のない場所にある四角い建物のそばに停まった。
ロシュは先に車を降りると豆腐の入口へ足早に向かい、ドアスコープを見つめた。それだけでひとりでに鍵が開き、暗闇がロシュを迎え入れる。
しばし灯りのスイッチを探り、ふと振り返ると、コウモリの翼を生やした悪魔の影がそこにいた。
「電気、こっちっすよ」
悪魔……もとい為知は、部屋を明るくした。つやつやの革でできた翼が、背中から顔を出している。
「ちゃちゃっと戻りましょ、お土産もあることですし」
為知は入口の反対側にあるテーブルへ歩き、ロシュを手招きする―――彼女はその背中に、青いドラゴンを一匹、背負っていた。
無論本物ではなく、そういうデザインの鞄である。かつて東京都心の店で見かけ、本人曰く『一目ぼれ』したらしい為知がその場で購入し、今日の日まで使い続けていた。ロシュの目から見てもなかなか格好いい代物だったが、あいにく為知がやたらと物を詰めこむせいでぶくぶくに太ってしまっている。ペットは飼い主に似るとはよく言ったものだ、イヤ違うか、とロシュはたまに思う。
さてそのロシュは、テーブルの引き出しの裏にあるボタンをトン、トト、トントと指で突っついた。するとテーブル下の床がスライドし、パネルが現れる。このパネルに今度は指をくっつけ声を当て、とどめに瞳を見せてやると、また横にずれてゆき、後には抜け穴が一つ残った。
そのまま穴に飛び込んで、滑るように梯子を下りる。
「うー、もうちっとこれ、別な仕組み考えらんなかったのかなぁ」
後から来る為知は、豊満なバストをコンクリート打ちっ放しの壁にこすりつけぬよう、ゆっくり降りざるを得ない。
「痩せとけ」
ロシュは相方が降りてくるのを待たずに先へ進んだ。
人に踏まれてはじめて動くリフトに乗りこみ、しばらく待てば、視界が開ける。彼らは巨大な球状の入れ物の中に入っていっているところだ。この球の中にはより小さな球や、四角い部屋がいくつも見える―――実際こんな風になっているわけではなく、いずれも土に埋もれてはいるのだが、その土を除いたらこうなるというのを映像で見せているのだった。
「もう、待ってよぉ、ロシュさんっ」
リフトのシャフトを滑り降りてきた為知に、ロシュは一言、おつかれと告げた。
彼の手には生もののお土産がある。あともういくつかセキュリティを通過しないといけないので、あまりのんびりはしていられない。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
少年がひとり、飾りっけのない部屋にいた。
屋内だというのに灰色のニット帽を被った少年、宮田一穂(みやた かずほ)は、壁際に備え付けられたデスクで海洋生物の図鑑を読んでいた。戻す本棚はこの部屋にはない。明日の朝にでも、元あった場所に返してもらうことになっている。
デスクの横には、作り物の空と太陽がしまわれた窓がある。生活リズムを狂わせないためのものだが、読書の邪魔になるのでカーテンで遮っておいてある。その上には壁掛け時計とエアコンがあり、反対の壁際にはパイプを溶接して造られたベッドが一つと、ウォーターサーバー。あとは電話もある。その傍にあるドアの向こうは、トイレもついたバスルーム。
これらが少年の住まいの全てで、後は本当に何もない。だけどそれでよかった。
チャイムが鳴った。少年は本にしおりを入れて閉じ、部屋の出入り口となるドアへ歩く。
「一穂、開けるぞー。糖分だ」
聞き慣れた声がして、ドアが開く。そこにはロシュがいた。遠くからは皿の触れ合う音もする。
「おーら、出てこい出てこい」
ロシュに肩を引かれて一穂は外に出る。
短い通路を抜けるとそこは円形の部屋で、一穂の部屋の何倍もの面積をもっているようだった。真ん中の十数人くらいで使えそうな丸テーブルに、為知がお皿とコップ、それからフォークを並べている。他にも四人ほど人がいて、もう椅子にかけていた。
「クリスマスケーキだってさ。私ら、もうンな歳でもないんじゃなくって」
水色の髪の少女が一穂に声をかける。
「美香さん、適度に糖分を摂取できることは望ましいと考えられます」
そう一穂が応えれば、尖った髪形をした茶髪の少年が思い切り呆れて、
「あーッたく……お前さァ、お祭りだぞ? レーションとか食おうってわけじゃねェンだぞ?」
「よせ、昭。一穂には一穂の感情があるんだと、ずっと言っているじゃないか。楽しいからって押し付けるのはよくない」
彼の隣にいたメガネの少年が、茶髪の子―――昭をなだめた。
四人の少年少女はみな同じくらいの年齢だが、何もかもが違っていた。一穂はずいぶん痩せているし、無機質だ。水色の子―――川野美香(かわの よしか)はそこそこ自慢できる程度に身体が引き締まっていて、眼光も鋭い。三島昭(みしま あきら)はぐんぐんと背を伸ばし、こんな地下施設にいなければスポーツ選手でも目指していたかもしれない。メガネをかけた村田実(むらた みのる)は白衣を普段着にしており、何かしらの実験の手伝いをさせてもらえる日を楽しみにしている。
彼らの他に、もう一人カール・ケンドという初老の男性がいた。だいぶおでこが広くなってはいるものの、背筋は張って歯並びもよく、くたびれた様子はない。彼は膝の上に猫を一匹乗せていた。白磁の様に滑らかで、毛が生えていない猫だった。それどころか異常に柔軟で、骨すら入っていないように見えるほどだ。
「お元気でしたか、一穂君?」
「はい」
カールの穏やかな挨拶を平坦極まる声で返し、一穂は席に着く。既にブッシュ・ド・ノエルがテーブルの上にその身を晒し、為知にカットされているところだった。美香、昭、実、それから為知がトッピングをほどほどに奪い合い、あとの三人は残ったものを皿へ運ぶ。
「おし、食う前に宣誓ッ! 来年のクリスマスも、ぜってェ、今ここにいる奴ら、みんな揃ってお祝いするぞォ!」
と、昭。
一穂にはわかっていた。確かに、去年も同じお祝いをした。ケーキはもう数ミリほど長く、為知は二キロばかり痩せていた。隣にいたのは自分ではなく美香で、青いスカートを履き、さっき昭が自分に言ったのと同じことを、その時は彼女が言っていた。実のメガネはあの後破壊されてしまったので、今年のとは違う―――
それはお祝いそのものの性質を変えてしまうような差異ではないが、確かな記憶である。何もかも、文字通り何もかもを、一穂は覚えていた。
去年の今頃、この部屋から三キロ離れた研究棟で、何が起ころうとしていたのかも。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
神はサイコロを振らないわけではない。けれど、そのサイコロは出来損ないなのかもしれない。
ブゥーッ! ブゥーッ! アラームが、穏やかな空気を引き裂いた。
「緊急事態発生、緊急事態発生。スフィア06第三研究棟、DE-615の実験にて事故発生。時空間安定プログラムを使用できる職員は、その場ですぐに行動されたし。繰り返す。スフィア06第三研究棟、DE-615の実験にて事故発生。時空間安定プログラムを使用できる職員は、その場ですぐに行動されたし……」
喋るものなど居ようはずもなかった。一同はわずかな時間凍り付き、すぐさま熱を取り戻した。
「は、ハチバン倉庫! 時空間のヤツってあっこじゃないと……ッ!」
為知が上ずった声を上げ、どたどたと部屋のロッカーへ駆けていく。中から分厚いコートを取り出して羽織った。ロシュ、カールもそれに続き、白磁の猫も何故だかついていく。
「悪ィな、留守番頼まァ!」
と、白い歯を見せ、同僚に上司、それから猫と一緒に部屋を去るロシュ。
あとの少年少女四人は、それぞれの部屋に戻るでもなく、その場に立ち尽くす。戻って、布団被って震えてでもいれば、そのうちどうにかなる類の問題ではない―――全員がわかっていた。
時計の音と、心臓の音と、アラームの周期。全部がうまく噛み合わなくて、余計に気持ちが悪かった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
―――それからすこし、時は流れて。
ふと目を開ければ目の前には柵。それから、黒い大地を満たす電気の灯たち。
異能者の世界の都市『イバラシティ』、その一画たる『ツクナミ区』は夜の帳の中で絢爛たる賑わいを見せていた。東の『マシカ区』、その反対の『ウラド区』、北方の『コヌマ区』と比較しても、ツクナミの街並みは異常に発展しているように思える。元々こんな場所だったのか、ここしばらくで急激に発展してしまったというのか、なぜかはっきりしない。
街を見下ろしているのは、宮田一穂である。
現実に立ち返った彼は、展望台に風を遮ってもらえる場所に寝袋を敷いた。枕はビニール袋を詰めたものだ。中に入ってしまえばそれなりに暖かいし、カイロも使えば凍死の可能性は減る。
この世界に戸籍を持たない以上は、とりあえずこうするしかなかった。
そう、なんとか、生きていかなくてはならないのだ。
自分は、失われるべきではないものなのだから。



特に何もしませんでした。







魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
影道 律(1247) とカードを交換しました!
ポッキー (ヒール)

ティンダー を習得!
ラッシュ を習得!
レッドゾーン を習得!
ファイアボール を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 H-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
結乃(233) をパーティに勧誘しました!
チホ(388) をパーティに勧誘しました!
恋文(400) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――





ENo.8
宮田一穂



【留意事項】
後述する異能の特性により、「当PCが知覚した事象/感覚刺激」についてゲーム内の別な場面で活用させて頂く可能性があります。
活用を控えてほしい場合につきましてはご一報いただければ幸いです。
【人物】
14歳の少年。
154cm/41kg。
ニット帽がトレードマーク。
自我が薄く、刺激に対する反応もどこか鈍い。
生活環境へのこだわりもほぼ無いに等しい。
【異能】
自らの記憶を、生物/無生物に焼き付ける異能を持つ。
生物に焼き付ければ、相手はその記憶を自らのものであったかのように受け取る。無生物に焼き付ければひとりでに動き出し、その物の機能の範囲で記憶の内容を再現しようとする。また、ごく短い時間ではあるが触れた生物に記憶を伝染させる性質を得る。
異能を行使した後は元の記憶が消耗し、ぼやけてしまう。ものにもよるが基本的に一回きり、長持ちしても数回程度の焼き付けにしか耐えない。
また、生物への焼きつけは相手に強い精神的負担を与える為、乱用は不可。
異能とは別に驚異的な記憶力を持ち、音声、映像、文章、数字、その他あらゆる物事を完璧に覚えることができる。
反面、先述の異能を行使した場合を除き、何かを忘れることができない。
【経歴】
元々はイバラシティの住人ではなく、他の世界にいた。
そこでは『WSO』と呼ばれる組織の一員として育てられていたらしい。訓練の成果か、銃火器や応急処置用の医療器具をある程度扱うことができる。
後述する異能の特性により、「当PCが知覚した事象/感覚刺激」についてゲーム内の別な場面で活用させて頂く可能性があります。
活用を控えてほしい場合につきましてはご一報いただければ幸いです。
【人物】
14歳の少年。
154cm/41kg。
ニット帽がトレードマーク。
自我が薄く、刺激に対する反応もどこか鈍い。
生活環境へのこだわりもほぼ無いに等しい。
【異能】
自らの記憶を、生物/無生物に焼き付ける異能を持つ。
生物に焼き付ければ、相手はその記憶を自らのものであったかのように受け取る。無生物に焼き付ければひとりでに動き出し、その物の機能の範囲で記憶の内容を再現しようとする。また、ごく短い時間ではあるが触れた生物に記憶を伝染させる性質を得る。
異能を行使した後は元の記憶が消耗し、ぼやけてしまう。ものにもよるが基本的に一回きり、長持ちしても数回程度の焼き付けにしか耐えない。
また、生物への焼きつけは相手に強い精神的負担を与える為、乱用は不可。
異能とは別に驚異的な記憶力を持ち、音声、映像、文章、数字、その他あらゆる物事を完璧に覚えることができる。
反面、先述の異能を行使した場合を除き、何かを忘れることができない。
【経歴】
元々はイバラシティの住人ではなく、他の世界にいた。
そこでは『WSO』と呼ばれる組織の一員として育てられていたらしい。訓練の成果か、銃火器や応急処置用の医療器具をある程度扱うことができる。
25 / 30
50 PS
チナミ区
H-7
H-7





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 使役 | 5 | エイド/援護 |
| 防具 | 20 | 防具作製と、防具への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 |
| ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 |
| レッドゾーン | 5 | 0 | 80 | 敵:火撃&火耐性減 |
| ファイアボール | 5 | 0 | 180 | 敵全:火撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / 切り株