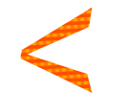<< 0:00>> 2:00




「これで、あなたは全てを識った。
黒薔薇卿の暴君としての歴史、
父親と慕った男の悪行と最期、
そして、あなたの本当の名前―――」
辺境の地グリムドール郊外、黒き森の木々に隠されるようにして、その洋館は建っていた。
休戦以来、国内において最多となる死者を出した『黒薔薇事件』、その舞台。
辺境伯ローゼンフェルド家に仕える黒薔薇騎士団と、王立騎士団による武力衝突。
この事件については、その発生の起因も含めて不可解な点が余りにも多い。
一説には時期を同じくして南方領域で発生していた、少女連続拉致殺害事件が遠因と言われるものの、
戦闘に参加した両軍の騎士達の尽くが戦死した上、領主であるレオン・ローゼンフェルド卿も、
事件以降に行方不明となっており、当事者からの聞き取りも出来ずに真相は闇の中である。
後に騎士団の行った実況見分によれば、最初こそ両軍による戦闘が行われたのは事実らしいが、
どうやら途中で別の勢力が介入したらしく、中には両軍による共闘の痕跡も見られたという。
騎士達の最期、その余りにも凄惨に変わり果てた姿から、様々な憶測が飛び交ったものの、
残された奇怪な謎の多くは、未だ完全には解明されていないのである。
そんな曰くだらけの洋館の中、そこに居たのは二つの人影。
一人は、淡い金髪にウサギのような赤い瞳の長耳少女。
もう一人は、色素の抜け落ちたような白い髪と肌、薄氷色の瞳の少女。
昼でも薄暗く鬱蒼とした中庭。
かつて、その場所で開かれていた気違いのお茶会の参列者達、
肉は腐り、骨さえ朽ちて、その痕跡は、もう何処にも無い。
「―――つまり、もうお父さまは、この世界の何処にも居ないのね」
「ええ、それにあなたの家門、ローゼンフェルド家も没落して、
……というよりも、事実上は滅亡したものとして扱われているわ。
南方領域の統治は、ブランテーゼ家が引き継いでね」
「家門とか、統治とか、どうでもいい。
私はただ、お父さまと一緒に居たかっただけ」
「あなたは気にしなくても、周りはそうもいかないのよね……」
「………?」
「さっきも話したけど、ローゼンフェルドは暴君の系譜。
この辺りでは、その名前を快く思わない人も多い」
「それなら、私はどうしたらいい……?」
「今までは、なんて名乗ってたの?」
「……ミオ」
「じゃあ、これからもそう名乗ったらいいんじゃない?
本当の名前は必要なときにだけ使うようにして。
……もちろん、あなたが嫌じゃなければ、だけれど」
「今までずっと、私はその名前で呼ばれていた。
そっちの方が、呼ばれて落ち着く、嫌なわけない」
「それなら、これからは私もミオって呼ぶことにするね。
……そろそろ帰ろっか、ミオ。
あなたの前で言うのもなんだけど、正直ここは居心地が悪い」
「むせ返るような血と薬の匂い、魔法陣……。
私が覚えていた場所は、きっとここ」
「それは、素敵な思い出?」
「……わからない。
お父さまは優しかったけれど、とても寂しかった。
―――それに、素敵な思い出は、今なら他にもたくさんある。
大切な思い出は、お父さまのことだけじゃない」
「それはよかった。
帰ったら、また一緒にクッキーでも焼きましょう」
「……ネアの作ったクッキーは、全然おいしくない」
「やかましいわ」
軽口を叩いて、笑い合いながら帰路につく、その後姿に怪物の面影はない。
様々な因果と運命に縛られた呪いから、彼女は解き放たれたのだ。
これからは、きっと、人として―――



特に何もしませんでした。








魔術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
呪術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ミロワール(791) とカードを交換しました!
練習用ヒール (ヒール)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
ダークネス を習得!
ブラックウェッジ を習得!
ファイアボール を習得!
エナジードレイン を習得!
エクスターペイト を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 H-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
ななな(1328) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「これで、あなたは全てを識った。
黒薔薇卿の暴君としての歴史、
父親と慕った男の悪行と最期、
そして、あなたの本当の名前―――」
辺境の地グリムドール郊外、黒き森の木々に隠されるようにして、その洋館は建っていた。
休戦以来、国内において最多となる死者を出した『黒薔薇事件』、その舞台。
辺境伯ローゼンフェルド家に仕える黒薔薇騎士団と、王立騎士団による武力衝突。
この事件については、その発生の起因も含めて不可解な点が余りにも多い。
一説には時期を同じくして南方領域で発生していた、少女連続拉致殺害事件が遠因と言われるものの、
戦闘に参加した両軍の騎士達の尽くが戦死した上、領主であるレオン・ローゼンフェルド卿も、
事件以降に行方不明となっており、当事者からの聞き取りも出来ずに真相は闇の中である。
後に騎士団の行った実況見分によれば、最初こそ両軍による戦闘が行われたのは事実らしいが、
どうやら途中で別の勢力が介入したらしく、中には両軍による共闘の痕跡も見られたという。
騎士達の最期、その余りにも凄惨に変わり果てた姿から、様々な憶測が飛び交ったものの、
残された奇怪な謎の多くは、未だ完全には解明されていないのである。
そんな曰くだらけの洋館の中、そこに居たのは二つの人影。
一人は、淡い金髪にウサギのような赤い瞳の長耳少女。
もう一人は、色素の抜け落ちたような白い髪と肌、薄氷色の瞳の少女。
昼でも薄暗く鬱蒼とした中庭。
かつて、その場所で開かれていた気違いのお茶会の参列者達、
肉は腐り、骨さえ朽ちて、その痕跡は、もう何処にも無い。
「―――つまり、もうお父さまは、この世界の何処にも居ないのね」
「ええ、それにあなたの家門、ローゼンフェルド家も没落して、
……というよりも、事実上は滅亡したものとして扱われているわ。
南方領域の統治は、ブランテーゼ家が引き継いでね」
「家門とか、統治とか、どうでもいい。
私はただ、お父さまと一緒に居たかっただけ」
「あなたは気にしなくても、周りはそうもいかないのよね……」
「………?」
「さっきも話したけど、ローゼンフェルドは暴君の系譜。
この辺りでは、その名前を快く思わない人も多い」
「それなら、私はどうしたらいい……?」
「今までは、なんて名乗ってたの?」
「……ミオ」
「じゃあ、これからもそう名乗ったらいいんじゃない?
本当の名前は必要なときにだけ使うようにして。
……もちろん、あなたが嫌じゃなければ、だけれど」
「今までずっと、私はその名前で呼ばれていた。
そっちの方が、呼ばれて落ち着く、嫌なわけない」
「それなら、これからは私もミオって呼ぶことにするね。
……そろそろ帰ろっか、ミオ。
あなたの前で言うのもなんだけど、正直ここは居心地が悪い」
「むせ返るような血と薬の匂い、魔法陣……。
私が覚えていた場所は、きっとここ」
「それは、素敵な思い出?」
「……わからない。
お父さまは優しかったけれど、とても寂しかった。
―――それに、素敵な思い出は、今なら他にもたくさんある。
大切な思い出は、お父さまのことだけじゃない」
「それはよかった。
帰ったら、また一緒にクッキーでも焼きましょう」
「……ネアの作ったクッキーは、全然おいしくない」
「やかましいわ」
軽口を叩いて、笑い合いながら帰路につく、その後姿に怪物の面影はない。
様々な因果と運命に縛られた呪いから、彼女は解き放たれたのだ。
これからは、きっと、人として―――



特に何もしませんでした。







魔術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
呪術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ミロワール(791) とカードを交換しました!
練習用ヒール (ヒール)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
ダークネス を習得!
ブラックウェッジ を習得!
ファイアボール を習得!
エナジードレイン を習得!
エクスターペイト を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 H-7(草原)に移動!(体調26⇒25)
ななな(1328) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――







✾✿❀❁
|
 |
おのれ破壊神!茨世界もお前によって破壊された!
|


ENo.1329
ミオン・ローゼンフェルド



Myon Rosenfeld
人として生きることを選んだ、とある怪物の残骸。
外見は10代前半位の少女の見た目をしている。
怪物だった頃の能力の殆どは捕食衝動と共に鳴りを潜めており、
現在は一般的な魔法使い程度の魔力しか残されていないが、
狭間等の異空間や、夜の間は本来の能力が戻る。
本来の能力を行使している間も、以前とは異なり凶暴性は無い。
怪物としての能力は、影を操り使役する程度の能力。
夜に比べたら弱いものの、昼間にも行使することは可能。
イバラシティにおいては、これが彼女の持つ異能とされている。
紆余曲折を経て自身の過去や本当の名前を知ることができたが、
本名ではなく、今まで通りに『ミオ』と名乗っている。
今でもやや世間知らずなところはあるものの、
以前のように一般常識が通用しないということはないようだ。
感情表現も豊かになり、良くも悪くも人間臭くなっている。
人として生きることを選んだ、とある怪物の残骸。
外見は10代前半位の少女の見た目をしている。
怪物だった頃の能力の殆どは捕食衝動と共に鳴りを潜めており、
現在は一般的な魔法使い程度の魔力しか残されていないが、
狭間等の異空間や、夜の間は本来の能力が戻る。
本来の能力を行使している間も、以前とは異なり凶暴性は無い。
怪物としての能力は、影を操り使役する程度の能力。
夜に比べたら弱いものの、昼間にも行使することは可能。
イバラシティにおいては、これが彼女の持つ異能とされている。
紆余曲折を経て自身の過去や本当の名前を知ることができたが、
本名ではなく、今まで通りに『ミオ』と名乗っている。
今でもやや世間知らずなところはあるものの、
以前のように一般常識が通用しないということはないようだ。
感情表現も豊かになり、良くも悪くも人間臭くなっている。
25 / 30
50 PS
チナミ区
H-7
H-7





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 呪術 | 10 | 呪詛/邪気/闇 |
| 付加 | 20 | 装備品への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 |
| ダークネス | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 |
| ブラックウェッジ | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃 |
| ファイアボール | 5 | 0 | 180 | 敵全:火撃 |
| エナジードレイン | 5 | 0 | 160 | 敵:闇撃&DF奪取 |
| エクスターペイト | 5 | 0 | 150 | 自:環境変調・肉体変調減+敵:闇撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]ダークネス |

PL / cuma