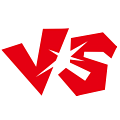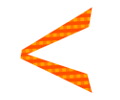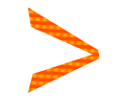<< 18:00~19:00




簡潔に言うとひどい目にあったが、所詮は通過点だった。そこにそれ以上いる義理はない。
我ながら運がいい、とも思った。力が馴染んでいるのを感じている。そして、それを律せていることも。故に立ち、故に思考し、故に焦がすことができる。
「ではデータを送るよ。俺たちはちょっとナメてたね」
『髪!』
「……」
『そうですね』

しばらく会っていない彼らは、自分たちの少し後ろを進んでいる――いや、いた。今はもうその気配はない。拠点に戻ったのだろう。もうすぐそこに見えているチェックポイントを踏んで自分たちも帰還する、それでこのちぐはぐな組み合わせも終わりだ。
『あと、しっぽと羽根と…耳!!』
「……」
それがただの子供ではなく、利己的に頭の切れる子供だという情報を、今更掴んでいた。
学校行事。そういうものにはまるで無縁の生活をしてきたから、向こうの俺が楽しそうにしているな、ということ以外の感想を持たなかった。なるほど従者と主人というのは的を得ていて、彼らはそういう挙動をしていた。高校生だと言う割に子供っぽく、知能を疑いたくなったことは数知れずだが、それも個体差なのだろう。子供っぽい主人だと思っていたが、それは単純に他の子供と触れ合う機会がなかったからなのかもしれない、だとすればまあ、納得できる範疇だ。
「お楽しみのトコ悪ぃんだけど、スズヒコで間違い探しすんのは後でな」
熱源が近づいてくる。
最近特に“熱い”。何があった、と問いかけるのは、もう少し後にさせてほしい、と勝手に思っていた。
吉野暁海の記憶が、不可思議なことを告げていた。到底ありえないことを告げていた。その処理を先にしなければ、と思っていた。
「っつーか、変わったっつーなら――」
視線の先。眼鏡を掛けた目付きの悪い男――従者、グノウ・スワロルド。
見ないうちに随分と“らしく”なったものだ。何時間か前の話、彼は頼みがあると言っていた。
『もし、傷が……この呪いが私を食い破って出てきたら、私を殺してくれると約束してください』
それは果たして、本当に彼の望みだろうか?聞き入れ、頷き、定期的に連絡を取り合いながら、ずっと思っていた。今ならもう少し真面目に取り合うことができて、そしてカマをかけることだってできる。そのくらいの余裕が生まれていた。
要するに一人だけ問題から一抜けし、自分の抱えている問題と言ったら、この世界から出られないこと以外に存在していない。ここで死ぬのではなく、何としてでも外に出なければならない。それ以外の問題は――脱ぎ捨て、すべて食わせてしまった。
「……まあ何にせよね、生憎暇と持ち合わせがなくてね。そちらで頑張ってくれ。俺たちはちょっと靴探しに行ってくるから」
『わかりました。では――』
ジャミングでもされたかのように通信が阻害され、そして切れた。
不快以外の何物でもない。切るタイミングというものがあるはずだ。
「……やれやれ……」
手を握り込むと、その動作だけで通信用のインターフェースが閉じられ、そして格納された。便利なものだ、と思う。同時に何となく危うさを感じてもいた。
言い残し、言い逃げ。あるいはログとしての再生。もし、最期の一言をこれに託されたら。それだけで自分は嫌だ、と感じる。最期に逃げた側のくせに何をとも思うが、だからこそ何も遺さずに死んだ。何も遺さないことが幸せかもしれないと、真剣に考えていたからだ。
それより今、何よりも気になることが一つあった。
流れ込んできた吉野暁海の記憶。その中に、あってはならないものがある。絶対にあってはならない、特異的なもの。絶対に排除したい異物。
(――吉野暁海……それを“何故”手に入れた……!!)
それこそ物語のような話だが、そこにはかつて本の世界があった。本の世界に集まった、もしくは集められた人々は、物語を読み進め、そこに発生している異変をひとつずつ解決していった。黎明期にあってはそのような物語をはいくつも生え、いわゆる本筋のみならず、様々な物語が様々な場所から集った。
――戯書。本の世界。死した自分が何らかの奇跡により呼び寄せられ、そして必然を成した場所。
吉野暁海が手にした本には、確かに覚えがあった。ずっと古く昔の話、特筆するほど特別なものではなく、プレゼントとして親が自分に与えた一般的な図鑑だ。そうして与えられた本の何冊かを、確かに自分の故郷から持ち出した記憶はある。自分にとって、それらは進むべき道を定めた大切なものだからだ。あまりに普遍的すぎて、別にどうでもいいものだと言えばそうなってしまう。けれどもそれはそうではなかった。
真っ白なページ。進まない物語。ページを捲る、捲る、物語は続いていく……
(何故それが……そうなっているんだ……!)
白紙の本。それは、本の世界の入り口だった。過去形なのはすでにあの世界は完全に閉じていて、どうやっても――少なくとも自分の思いつく限りの方法では、再び入り込むことはできなかった。それをわざわざご丁寧に、自分の知る装丁で渡したやつがいる。
「先生、随分と剣呑な顔だ。どうかした?」
「すっとぼけているといくらお前と言えど首を刎ねるよ。その程度で死んでくれればよかったのにね」
今のパライバトルマリンの持ち主は、どうしてか探究心が強く、自分の存在を理解しているような挙動をし、そしてそのように吉野暁海という端末に働きかける。例えばあの本もそうだ。間違いなく分かっていて、そしてわざと渡している。それ以外のことを見出すことができないくらい、意図的に。
「そうだね。だからここにいるんだろうけど」
「全くだ」
沼地を歩いて汚れたブーツの泥を払いながら、音も立てずについてくるその生き物を見た。
徹底的な不干渉、正確に言うのなら観察。その挙動を貫き続け、素知らぬ顔で危険があれば隠れ潜み、決して戦力になろうとはしない。言ってしまえば不愉快な距離感だった。尊大な態度であろうと、共闘して最低限役に立つのであれば気にしない。気にしている暇はない。だからこそ、余計に鼻につく。
「……それで……何が目的?お前の今の持ち主は」
「次に拠点に戻ったときに話すつもりでいたんだけど……」
「もうどこも変わらないさ。どこにいようと襲われる。どこにいようと逃げ場はない。一息ついた安息はどこにも保証されていない」
「そう。じゃあいっそ誰もいないほうが気楽?」
「それはそっくりそのまま返すよ」
人気はまるでない道だった。誰より早く通り抜けることを選択したのだから当然で、しばらくはこの沼地と友達だ。尻尾を半分ほど突っ込んで、沼の底を攫うように歩いていた。
思えば、どこへ行ってもそんな、泥臭い歩き方をしていたように思う。先が見えないなら、手探りで進むしかない、そんな日々をどこでもやっていた。探ることは苦ではなかった。身体に染み付いている。
だからこそ、探ってしまう。電気石の名を冠した不可思議の向こう側の人間のことを。
「先生……いや、」
「大日向深知」
「そう。……あ、そっか、先生には記憶が来るんだっけ?」
「そうだよ。そうでなきゃ何も知らずに歩いていただろうね。だからこそ腹立つというか、ムカつくんだけど」
こちらでの一時間ごとに、圧縮された記憶が流れ込んでくる。日付の間隔はまちまちで、随分と詰め込んできた時間もあれば、そうでない時間もあった。幸いにして自分はそういう記録を整理することには特化していて、一度本を閉じてから開けばそれでよかった。何の感傷もなく、客観的に、全てを受け入れられる。ただの記録にしか過ぎないからだ。
記録ではなく記憶として全てを受け入れている他の大勢が、どのような思いでいるか、まるで興味がなかった。昔からあまり他人には興味がなかったし、群れる気質でもなかったからだ。
その中に、唐突にねじ込まれた『本を受け取る記憶』が何より気持ち悪かったのだ。一体どうやって手にしたのか、どうしてそれを選んだのか。探られている、探されているという事実を突きつけられたにほぼ等しい。――まだ推測でしかないが。
「大日向先生は……何でだろう?そういえばぼくもあんまり知らないな。けどあの人たちは、はじめから先生のことを知っていたように見えた」
「……予め調べてあった?」
「さあ。ぼくはとにかく、“先生”を探して……コンタクトを取れと。それだけだった。咲良乃スズヒコ、じゃなくて……先生って言ったんだよ。だから信用していいかな、って」
眉根にシワが寄る。
良くも悪くもパライバトルマリンの種族は清廉であり、世間知らずだ。例えるなら天使のようなものが一番近い、と言っていたのは確か本人だ。
「……もう少し人を選ぶことを覚えろ」
「待って待って。これでもぼくの前の持ち主よりは全然マシだよ。ぼくを雑に放り出すんじゃなくて、必要な知識、もの、こと、全部揃えてくれた」
「前の持ち主。……前の持ち主はどうしてお前を手放した?」
「買われたからだよ」
なるほど、売り物にするには特に相応しい。他人事ながらにそう思った。どんな物好きが拾ったのか知らないが、いい商売をしている。相変わらず他人事のように思っているが、その商売の結果自分が探られているのだ。
「……そう。それで、お前を使って俺を探し始めた?」
「いや……たぶんもっと前から、調べてると思う。ぼくは最終兵器だって言われてたんだ。大日向先生は、ハザマのこと知ってるし、来たこともあるみたいだし……」
「……ああ、なるほど」
少しずつ繋がっていく。一度来たことがあるのなら、世界の存在を把握していても何もおかしくはない。しかし世界を移動する力は基本的に限られたものの手にあり、そう自由のできるものではなかった。かくいう自分もふらつくように世界を移動して彷徨っていたことがあるが、長きにわたる滞在で力を得るか、現地が強大な力に満ちているかでなければ、すぐに次の場所に向かうことはできなかった。もちろん今もそうだ。
パライバトルマリンたちはそうではない。そもそもが世界の隙間を住処としているから、移動ではなければ話にならない。
「それで……送り込んで。俺と対話をさせて。その意図は」
「ねえ先生。先生は別の可能性って信じる?」
彼に目はない。目に見える模様はあるが、感覚器官として存在しているのは触角だけだ。
それでも強く引き止めるような視線を感じた気がして、沼地を掻き分ける足を止めた。
「……どういう意味で言っているかにもよる。俺が死ななかった可能性は間違いなくないから、俺の別の可能性は信じないけれど」
「言葉通りに捉えてほしいと言ったら?」
「言葉通りか。……考慮に入れてもいい、くらいには」
そっか、という小さな声を、確かに耳が拾った。
「ユーエがここにいるんだ。……それは、幸せなユーエじゃなくて。一人ぼっちのユーエ。一人ぼっちのまま大人になって、誰とも会わなかったユーエ」
「……」

ざわめき。
その物語は、この手で変えた。この手で閉じた。“そして幸せに暮らしました”で終わる、幸せな物語にした。そのはずなのに。
「……根拠はどこに?」
気づいたときには距離を詰めて、その身体を覆う膜を掴み上げていた。



ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 キャンベルストライカー を破棄しました。
ItemNo.10 百科のエフェメラ を破棄しました。
ItemNo.12 零度の背表紙 を破棄しました。
ItemNo.13 ドリームパイルバンカー を破棄しました。
ItemNo.28 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(10⇒11)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!











フェデルタ(165) から チャート を受け取りました。
フェデルタ(165) に ItemNo.5 角閃石 を送付しました。
変化LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
領域LV を 10 UP!(LV20⇒30、-10CP)
解析LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
順(39) により ItemNo.16 装甲 から装飾『トートイズシェルスピン』を作製してもらいました!
⇒ トートイズシェルスピン/装飾:強さ381/[効果1]耐災30 [効果2]- [効果3]-
順(39) の持つ ItemNo.40 お魚 から料理『カレイのムニエル』をつくりました!
フェデルタ(165) により ItemNo.16 トートイズシェルスピン に ItemNo.26 装甲 を付加してもらいました!
⇒ トートイズシェルスピン/装飾:強さ381/[効果1]耐災30 [効果2]耐災30 [効果3]-
ItemNo.15 コンサーティナペンダント に ItemNo.1 駄物 を付加しました!
⇒ コンサーティナペンダント/装飾:強さ327/[効果1]攻撃30 [効果2]体力10 [効果3]-
キヤハ(682) とカードを交換しました!
使いきり乾電池 (トールハンマー)
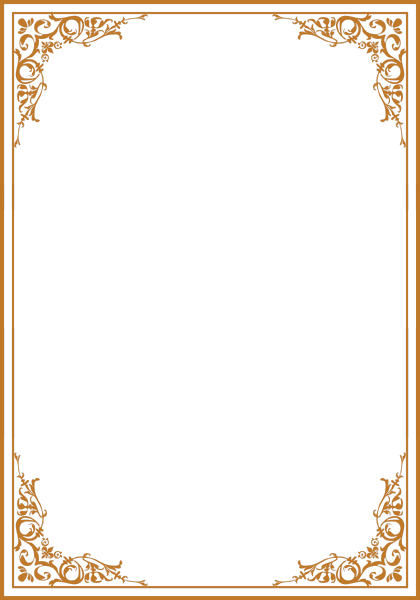
メテオ を研究しました!(深度0⇒1)
メテオ を研究しました!(深度1⇒2)
メテオ を研究しました!(深度2⇒3)
リンクブレイク を習得!
マナブースター を習得!
デスグラスプ を習得!
ワイドアナリシス を習得!
アルヒェ を習得!
オディウム を習得!
アジール を習得!
高速治癒 を習得!
ブラッドレイン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は 汚れた玩具+1 を入手!
フェデルタ(165) は イヌサフラン を入手!
スズヒコ(244) は イヌサフラン を入手!
フェデルタ(165) は 長い髪 を入手!
順(39) は おさかな+2 を入手!
スズヒコ(244) は 造花 を入手!



ミナト区 G-3(沼地)に移動!(体調11⇒10)
ミナト区 H-3(沼地)に移動!(体調10⇒9)
ミナト区 G-3(沼地)に移動!(体調9⇒8)
ミナト区 G-4(森林)に移動!(体調8⇒7)
ミナト区 G-5(森林)に移動!(体調7⇒6)





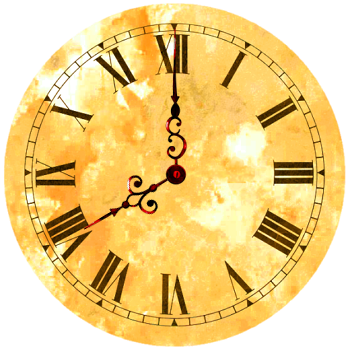
[861 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[444 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[193 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[397 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[305 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[216 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[156 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[79 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[134 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[128 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[182 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[28 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[48 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
[22 / 300] ―― 《渡し舟》蝶のように舞い
[49 / 200] ―― 《図書館》蜂のように刺し
[0 / 200] ―― 《赤い灯火》蟻のように喰う
―― Cross+Roseに映し出される。


チャットが閉じられる――













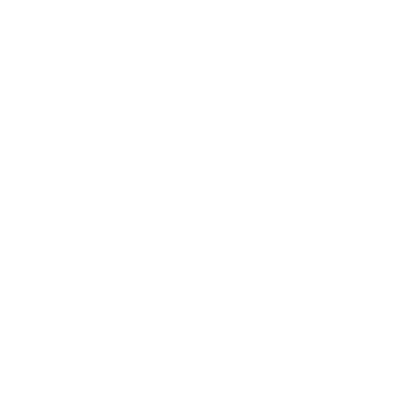
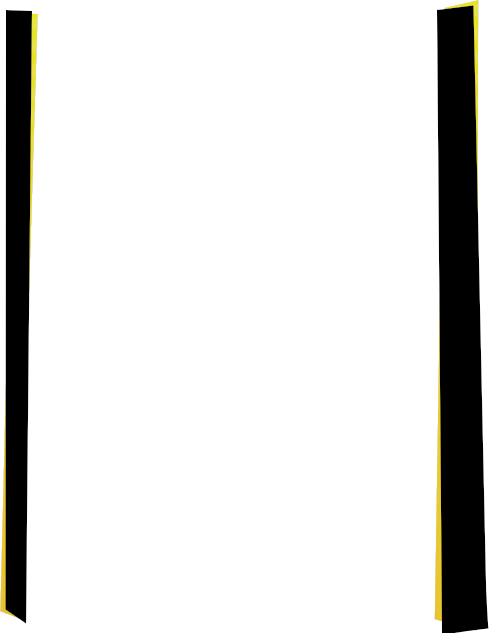
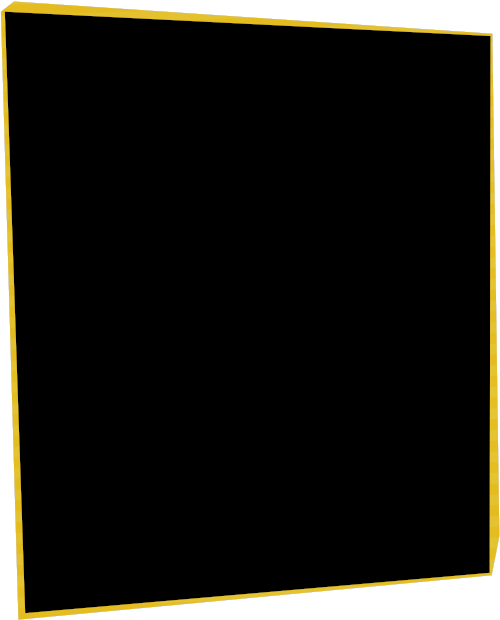





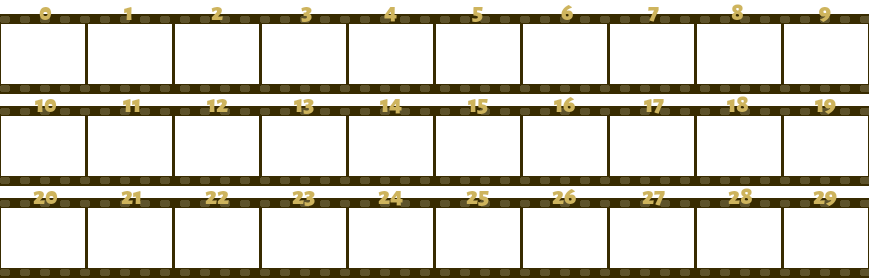









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



簡潔に言うとひどい目にあったが、所詮は通過点だった。そこにそれ以上いる義理はない。
我ながら運がいい、とも思った。力が馴染んでいるのを感じている。そして、それを律せていることも。故に立ち、故に思考し、故に焦がすことができる。
「ではデータを送るよ。俺たちはちょっとナメてたね」
『髪!』
「……」
『そうですね』

しばらく会っていない彼らは、自分たちの少し後ろを進んでいる――いや、いた。今はもうその気配はない。拠点に戻ったのだろう。もうすぐそこに見えているチェックポイントを踏んで自分たちも帰還する、それでこのちぐはぐな組み合わせも終わりだ。
『あと、しっぽと羽根と…耳!!』
「……」
それがただの子供ではなく、利己的に頭の切れる子供だという情報を、今更掴んでいた。
学校行事。そういうものにはまるで無縁の生活をしてきたから、向こうの俺が楽しそうにしているな、ということ以外の感想を持たなかった。なるほど従者と主人というのは的を得ていて、彼らはそういう挙動をしていた。高校生だと言う割に子供っぽく、知能を疑いたくなったことは数知れずだが、それも個体差なのだろう。子供っぽい主人だと思っていたが、それは単純に他の子供と触れ合う機会がなかったからなのかもしれない、だとすればまあ、納得できる範疇だ。
「お楽しみのトコ悪ぃんだけど、スズヒコで間違い探しすんのは後でな」
熱源が近づいてくる。
最近特に“熱い”。何があった、と問いかけるのは、もう少し後にさせてほしい、と勝手に思っていた。
吉野暁海の記憶が、不可思議なことを告げていた。到底ありえないことを告げていた。その処理を先にしなければ、と思っていた。
「っつーか、変わったっつーなら――」
視線の先。眼鏡を掛けた目付きの悪い男――従者、グノウ・スワロルド。
見ないうちに随分と“らしく”なったものだ。何時間か前の話、彼は頼みがあると言っていた。
『もし、傷が……この呪いが私を食い破って出てきたら、私を殺してくれると約束してください』
それは果たして、本当に彼の望みだろうか?聞き入れ、頷き、定期的に連絡を取り合いながら、ずっと思っていた。今ならもう少し真面目に取り合うことができて、そしてカマをかけることだってできる。そのくらいの余裕が生まれていた。
要するに一人だけ問題から一抜けし、自分の抱えている問題と言ったら、この世界から出られないこと以外に存在していない。ここで死ぬのではなく、何としてでも外に出なければならない。それ以外の問題は――脱ぎ捨て、すべて食わせてしまった。
「……まあ何にせよね、生憎暇と持ち合わせがなくてね。そちらで頑張ってくれ。俺たちはちょっと靴探しに行ってくるから」
『わかりました。では――』
ジャミングでもされたかのように通信が阻害され、そして切れた。
不快以外の何物でもない。切るタイミングというものがあるはずだ。
「……やれやれ……」
手を握り込むと、その動作だけで通信用のインターフェースが閉じられ、そして格納された。便利なものだ、と思う。同時に何となく危うさを感じてもいた。
言い残し、言い逃げ。あるいはログとしての再生。もし、最期の一言をこれに託されたら。それだけで自分は嫌だ、と感じる。最期に逃げた側のくせに何をとも思うが、だからこそ何も遺さずに死んだ。何も遺さないことが幸せかもしれないと、真剣に考えていたからだ。
それより今、何よりも気になることが一つあった。
流れ込んできた吉野暁海の記憶。その中に、あってはならないものがある。絶対にあってはならない、特異的なもの。絶対に排除したい異物。
(――吉野暁海……それを“何故”手に入れた……!!)
それこそ物語のような話だが、そこにはかつて本の世界があった。本の世界に集まった、もしくは集められた人々は、物語を読み進め、そこに発生している異変をひとつずつ解決していった。黎明期にあってはそのような物語をはいくつも生え、いわゆる本筋のみならず、様々な物語が様々な場所から集った。
――戯書。本の世界。死した自分が何らかの奇跡により呼び寄せられ、そして必然を成した場所。
吉野暁海が手にした本には、確かに覚えがあった。ずっと古く昔の話、特筆するほど特別なものではなく、プレゼントとして親が自分に与えた一般的な図鑑だ。そうして与えられた本の何冊かを、確かに自分の故郷から持ち出した記憶はある。自分にとって、それらは進むべき道を定めた大切なものだからだ。あまりに普遍的すぎて、別にどうでもいいものだと言えばそうなってしまう。けれどもそれはそうではなかった。
真っ白なページ。進まない物語。ページを捲る、捲る、物語は続いていく……
(何故それが……そうなっているんだ……!)
白紙の本。それは、本の世界の入り口だった。過去形なのはすでにあの世界は完全に閉じていて、どうやっても――少なくとも自分の思いつく限りの方法では、再び入り込むことはできなかった。それをわざわざご丁寧に、自分の知る装丁で渡したやつがいる。
「先生、随分と剣呑な顔だ。どうかした?」
「すっとぼけているといくらお前と言えど首を刎ねるよ。その程度で死んでくれればよかったのにね」
今のパライバトルマリンの持ち主は、どうしてか探究心が強く、自分の存在を理解しているような挙動をし、そしてそのように吉野暁海という端末に働きかける。例えばあの本もそうだ。間違いなく分かっていて、そしてわざと渡している。それ以外のことを見出すことができないくらい、意図的に。
「そうだね。だからここにいるんだろうけど」
「全くだ」
沼地を歩いて汚れたブーツの泥を払いながら、音も立てずについてくるその生き物を見た。
徹底的な不干渉、正確に言うのなら観察。その挙動を貫き続け、素知らぬ顔で危険があれば隠れ潜み、決して戦力になろうとはしない。言ってしまえば不愉快な距離感だった。尊大な態度であろうと、共闘して最低限役に立つのであれば気にしない。気にしている暇はない。だからこそ、余計に鼻につく。
「……それで……何が目的?お前の今の持ち主は」
「次に拠点に戻ったときに話すつもりでいたんだけど……」
「もうどこも変わらないさ。どこにいようと襲われる。どこにいようと逃げ場はない。一息ついた安息はどこにも保証されていない」
「そう。じゃあいっそ誰もいないほうが気楽?」
「それはそっくりそのまま返すよ」
人気はまるでない道だった。誰より早く通り抜けることを選択したのだから当然で、しばらくはこの沼地と友達だ。尻尾を半分ほど突っ込んで、沼の底を攫うように歩いていた。
思えば、どこへ行ってもそんな、泥臭い歩き方をしていたように思う。先が見えないなら、手探りで進むしかない、そんな日々をどこでもやっていた。探ることは苦ではなかった。身体に染み付いている。
だからこそ、探ってしまう。電気石の名を冠した不可思議の向こう側の人間のことを。
「先生……いや、」
「大日向深知」
「そう。……あ、そっか、先生には記憶が来るんだっけ?」
「そうだよ。そうでなきゃ何も知らずに歩いていただろうね。だからこそ腹立つというか、ムカつくんだけど」
こちらでの一時間ごとに、圧縮された記憶が流れ込んでくる。日付の間隔はまちまちで、随分と詰め込んできた時間もあれば、そうでない時間もあった。幸いにして自分はそういう記録を整理することには特化していて、一度本を閉じてから開けばそれでよかった。何の感傷もなく、客観的に、全てを受け入れられる。ただの記録にしか過ぎないからだ。
記録ではなく記憶として全てを受け入れている他の大勢が、どのような思いでいるか、まるで興味がなかった。昔からあまり他人には興味がなかったし、群れる気質でもなかったからだ。
その中に、唐突にねじ込まれた『本を受け取る記憶』が何より気持ち悪かったのだ。一体どうやって手にしたのか、どうしてそれを選んだのか。探られている、探されているという事実を突きつけられたにほぼ等しい。――まだ推測でしかないが。
「大日向先生は……何でだろう?そういえばぼくもあんまり知らないな。けどあの人たちは、はじめから先生のことを知っていたように見えた」
「……予め調べてあった?」
「さあ。ぼくはとにかく、“先生”を探して……コンタクトを取れと。それだけだった。咲良乃スズヒコ、じゃなくて……先生って言ったんだよ。だから信用していいかな、って」
眉根にシワが寄る。
良くも悪くもパライバトルマリンの種族は清廉であり、世間知らずだ。例えるなら天使のようなものが一番近い、と言っていたのは確か本人だ。
「……もう少し人を選ぶことを覚えろ」
「待って待って。これでもぼくの前の持ち主よりは全然マシだよ。ぼくを雑に放り出すんじゃなくて、必要な知識、もの、こと、全部揃えてくれた」
「前の持ち主。……前の持ち主はどうしてお前を手放した?」
「買われたからだよ」
なるほど、売り物にするには特に相応しい。他人事ながらにそう思った。どんな物好きが拾ったのか知らないが、いい商売をしている。相変わらず他人事のように思っているが、その商売の結果自分が探られているのだ。
「……そう。それで、お前を使って俺を探し始めた?」
「いや……たぶんもっと前から、調べてると思う。ぼくは最終兵器だって言われてたんだ。大日向先生は、ハザマのこと知ってるし、来たこともあるみたいだし……」
「……ああ、なるほど」
少しずつ繋がっていく。一度来たことがあるのなら、世界の存在を把握していても何もおかしくはない。しかし世界を移動する力は基本的に限られたものの手にあり、そう自由のできるものではなかった。かくいう自分もふらつくように世界を移動して彷徨っていたことがあるが、長きにわたる滞在で力を得るか、現地が強大な力に満ちているかでなければ、すぐに次の場所に向かうことはできなかった。もちろん今もそうだ。
パライバトルマリンたちはそうではない。そもそもが世界の隙間を住処としているから、移動ではなければ話にならない。
「それで……送り込んで。俺と対話をさせて。その意図は」
「ねえ先生。先生は別の可能性って信じる?」
彼に目はない。目に見える模様はあるが、感覚器官として存在しているのは触角だけだ。
それでも強く引き止めるような視線を感じた気がして、沼地を掻き分ける足を止めた。
「……どういう意味で言っているかにもよる。俺が死ななかった可能性は間違いなくないから、俺の別の可能性は信じないけれど」
「言葉通りに捉えてほしいと言ったら?」
「言葉通りか。……考慮に入れてもいい、くらいには」
そっか、という小さな声を、確かに耳が拾った。
「ユーエがここにいるんだ。……それは、幸せなユーエじゃなくて。一人ぼっちのユーエ。一人ぼっちのまま大人になって、誰とも会わなかったユーエ」
「……」

ざわめき。
その物語は、この手で変えた。この手で閉じた。“そして幸せに暮らしました”で終わる、幸せな物語にした。そのはずなのに。
「……根拠はどこに?」
気づいたときには距離を詰めて、その身体を覆う膜を掴み上げていた。



ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| 「……靴、加速する靴ってなんだよ……ローラースケートかよ……」 うわ言みたいに呟きながら沼をざぶざぶしている。 |
| スズヒコ 「……気持ちは分かるんだけどさ……」 尻尾で沼を浚っている…… |
ItemNo.6 キャンベルストライカー を破棄しました。
ItemNo.10 百科のエフェメラ を破棄しました。
ItemNo.12 零度の背表紙 を破棄しました。
ItemNo.13 ドリームパイルバンカー を破棄しました。
ItemNo.28 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(10⇒11)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 80 増加!
影響力が 80 増加!



フェデルタ(165) から チャート を受け取りました。
フェデルタ(165) に ItemNo.5 角閃石 を送付しました。
変化LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
領域LV を 10 UP!(LV20⇒30、-10CP)
解析LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
順(39) により ItemNo.16 装甲 から装飾『トートイズシェルスピン』を作製してもらいました!
⇒ トートイズシェルスピン/装飾:強さ381/[効果1]耐災30 [効果2]- [効果3]-
順(39) の持つ ItemNo.40 お魚 から料理『カレイのムニエル』をつくりました!
フェデルタ(165) により ItemNo.16 トートイズシェルスピン に ItemNo.26 装甲 を付加してもらいました!
⇒ トートイズシェルスピン/装飾:強さ381/[効果1]耐災30 [効果2]耐災30 [効果3]-
ItemNo.15 コンサーティナペンダント に ItemNo.1 駄物 を付加しました!
⇒ コンサーティナペンダント/装飾:強さ327/[効果1]攻撃30 [効果2]体力10 [効果3]-
キヤハ(682) とカードを交換しました!
使いきり乾電池 (トールハンマー)
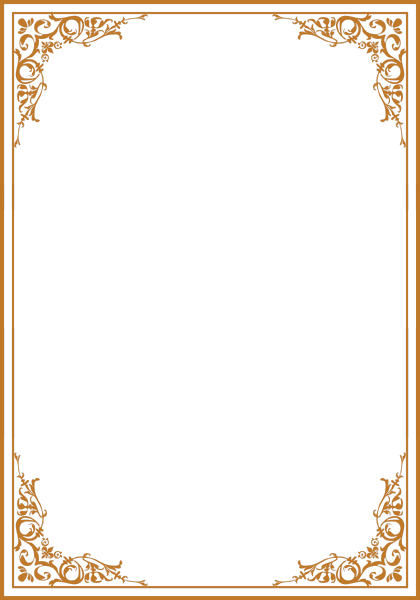
メテオ を研究しました!(深度0⇒1)
メテオ を研究しました!(深度1⇒2)
メテオ を研究しました!(深度2⇒3)
リンクブレイク を習得!
マナブースター を習得!
デスグラスプ を習得!
ワイドアナリシス を習得!
アルヒェ を習得!
オディウム を習得!
アジール を習得!
高速治癒 を習得!
ブラッドレイン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は 汚れた玩具+1 を入手!
フェデルタ(165) は イヌサフラン を入手!
スズヒコ(244) は イヌサフラン を入手!
フェデルタ(165) は 長い髪 を入手!
順(39) は おさかな+2 を入手!
スズヒコ(244) は 造花 を入手!



ミナト区 G-3(沼地)に移動!(体調11⇒10)
ミナト区 H-3(沼地)に移動!(体調10⇒9)
ミナト区 G-3(沼地)に移動!(体調9⇒8)
ミナト区 G-4(森林)に移動!(体調8⇒7)
ミナト区 G-5(森林)に移動!(体調7⇒6)





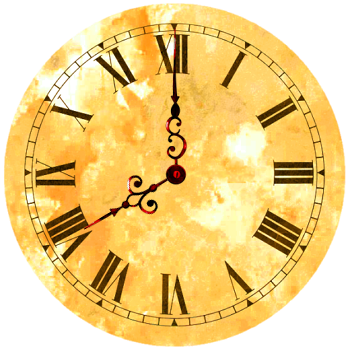
[861 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[444 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[193 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[397 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[305 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[216 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[156 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[79 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[134 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[128 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[182 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[28 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[48 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
[22 / 300] ―― 《渡し舟》蝶のように舞い
[49 / 200] ―― 《図書館》蜂のように刺し
[0 / 200] ―― 《赤い灯火》蟻のように喰う
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
カオリ 「ちぃーっす!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カオリ 「・・・・・あれぇ?誰もいなーい。」 |
 |
カグハ 「おといれ?」 |
 |
カオリ 「そうかもね!少し待ってみよっか?」 |
 |
カグハ 「長いのかな・・・」 |
 |
カオリ 「・・・・・・・・・あーもう!全然こなーいっ!!もう帰ろう!!!!」 |
 |
カグハ 「らじゃー。ざんねんむねん。」 |
 |
カオリ 「むー、私たちみたいにどこかドロドロになってないかなぁーって思ったんだけどなぁ。」 |
 |
カグハ 「ドロドロなかま。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。





ENo.244
鈴のなる夢
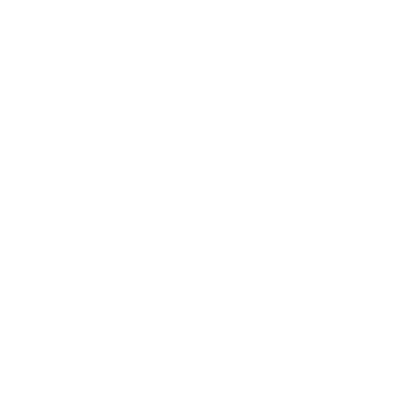
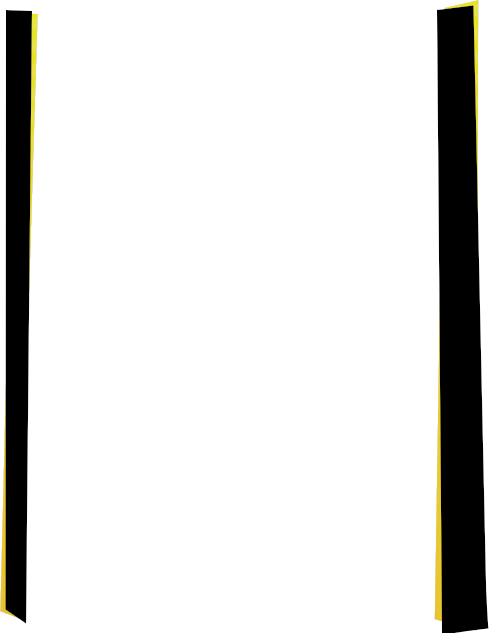
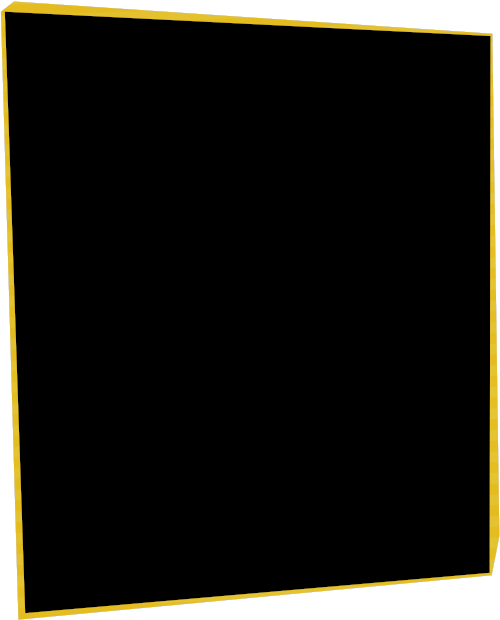
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
“羽化”を果たし、妄執の獣と決別する。その手にあるのは、道を拓くための知と炎。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
“羽化”を果たし、妄執の獣と決別する。その手にあるのは、道を拓くための知と炎。
6 / 30
1550 PS
ミナト
G-5
G-5







痛撃友の会
4
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
アイコン60pxの会
1
#片道切符チャット
#交流歓迎
2
アンジ出身イバラ陣営の集い
2
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
3
カード報告会
3
とりあえず肉食う?
5
銭田精肉所
6



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | イヌサフラン | 素材 | 35 | [武器]衰弱35(LV75)[防具]反衰35(LV80)[装飾]疫病35(LV80) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | 閃光10 | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | 造花 | 素材 | 30 | [武器]狂30(LV50)[防具]全祝25(LV40)[装飾]舞乱30(LV60) | |||
| 6 | チャート | 素材 | 35 | [武器]活力35(LV80)[防具]反護30(LV70)[装飾]強靭30(LV60) | |||
| 7 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||
| 8 | 火焔茸 | 素材 | 35 | [武器]猛毒30(LV70)[防具]反毒35(LV75)[装飾]舞衰30(LV70) | |||
| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | 耐疫15 | - | |
| 10 | |||||||
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | バンブーエディトリアン | 防具 | 300 | 加速20 | 活力30 | - | |
| 15 | コンサーティナペンダント | 装飾 | 327 | 攻撃30 | 体力10 | - | |
| 16 | トートイズシェルスピン | 装飾 | 381 | 耐災30 | 耐災30 | - | |
| 17 | リアリズムカレントブラスト | 大砲 | 306 | 体力20 | 追風15 | - | 【射程4】 |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 21 | 鱗 | 素材 | 20 | [武器]朦朧25(LV55)[防具]反水30(LV60)[装飾]耐火25(LV45) | |||
| 22 | チャート | 素材 | 35 | [武器]活力35(LV80)[防具]反護30(LV70)[装飾]強靭30(LV60) | |||
| 23 | レッドバーンビブリオ | 薬箱 | 81 | 耐疫15 | 耐疫15 | - | |
| 24 | クリアグロリエバインド | 装飾 | 260 | 活力20 | 活力20 | - | |
| 25 | 串焼き | 料理 | 109 | 攻撃12 | 防御12 | 増幅12 | |
| 26 | |||||||
| 27 | ローズクォーツ | 装飾 | 75 | 火纏10 | 火纏10 | - | |
| 28 | |||||||
| 29 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 30 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 31 | 秋刀魚の塩焼き | 料理 | 210 | 活力30 | 敏捷30 | 強靭30 | |
| 32 | 不思議な布 | 素材 | 25 | [武器]放魅30(LV55)[防具]耐狂25(LV45)[装飾]舞撃25(LV50) | |||
| 33 | |||||||
| 34 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 30 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 30 | 呪詛/邪気/闇 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 30 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 50 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 合成 | 5 | 合成に影響 |
| 料理 | 60 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 10 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 8 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| 練3 | ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| フィーバー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 練3 | ヘイルカード | 6 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 6 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| 練3 | カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 練3 | ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 16 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| 練3 | クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 6 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |
| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| リストア | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+環境変調を守護化 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 7 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 | |
| イラプション | 5 | 0 | 180 | 敵列:地撃+敵味全:火撃&炎上 | |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| パワフルヒール | 6 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| グレイシア | 8 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| マナブースター | 5 | 0 | 100 | 味列:魔力LV増 | |
| ウィザー | 5 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |
| デスグラスプ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&名前に「活」を含む付加効果1つを埋葬に変化 | |
| サモン:ビーフ | 7 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| ワイドアナリシス | 5 | 1 | 100 | 自:朦朧+味全:DX増(3T)&名前に「罠」を含む付加効果のLV減 | |
| 練3 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練3 | ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 |
| イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 | |
| ドレインライフ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&MHP奪取 | |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 | |
| フォースフィールド | 5 | 1 | 300 | 味全:AT増 | |
| グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 | |
| コンフィデンス | 7 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |
| スノーホワイト | 5 | 0 | 200 | 敵4:水痛撃&朦朧 | |
| 練3 | ディープブルー | 5 | 0 | 200 | 敵:水撃&水特性増 |
| 練3 | アルヒェ | 5 | 0 | 240 | 敵傷:水撃+味傷:水撃 |
| オディウム | 5 | 0 | 180 | 敵:4連闇撃&HATE増+自:盲目 | |
| アジール | 5 | 0 | 320 | 味全:鎮痛LV増 | |
| 練3 | バーニングカード | 5 | 0 | 80 | 敵3:火撃+自:強制炎上 |
| ディケイドミスト | 5 | 1 | 300 | 敵全:AG減(4T)&腐食+味全:DX増(4T)&腐食 | |
| 練3 | タイダルウェイブ | 5 | 0 | 330 | 敵:5連鎖水撃&DX・AG減(2T) |
| ブラッドレイン | 5 | 1 | 260 | 敵全:闇撃&自滅LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 練3 | 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 瘴気 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘離脱前】敵6:猛毒・麻痺・衰弱 | |
| 肉体変調特性 | 6 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 練3 | 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
| 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 | |
| 凍縛陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど凍縛LV増 | |
| 治癒領域 | 9 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 悪夢 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:SP闇撃&束縛 | |
| 凍結耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:凍結耐性増 | |
| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |
| 腐食耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:腐食耐性増 | |
| 盲目耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:盲目耐性増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |
| 生殺与奪 | 5 | 6 | 0 | 【攻撃命中後】対:火撃+対:水撃&味傷:HP増 | |
| 星火燎原 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】敵味炎:粗雑火撃&炎上奪取&自:炎上をAT化 | |
| 火霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:魔術LVが高いほどSP・火特性増 | |
| 水霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:命術LVが高いほどSP・水特性増 | |
| 闇霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |
| 千変万化 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |
| 火特性回復 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:火属性スキルのHP増効果に火特性が影響 | |
| 高速治癒 | 5 | 3 | 0 | 【HP回復後】自:HL増(2T)+連続増 | |
| 魔香作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で料理「魔香」を選択できる。魔香は体調が回復せず効果3しか付加されないが、食事に指定しても消費されない。 |
最大EP[25]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練3 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
|
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
|
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
|
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
|
ギフトカード (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |
5 | 500 | 自:エンペラー召喚 | |
|
余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター) |
0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 | |
|
フリーリィ・スカイシー・ダイブ (ワールウィンド) |
0 | 200 | 敵傷7:風撃 | |
|
血眼 (ブラッドアイズ) |
0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
|
スミの炭になりたい (ミゼラブルメモリー) |
2 | 200 | 敵:6連鎖SP闇撃 | |
|
疾痛猶予 (パワフルヒール) |
0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| 練3 |
神の涙 (ナース) |
0 | 180 | 味傷5:HP増 |
|
使いきり乾電池 (トールハンマー) |
0 | 320 | 敵:守護を麻痺化+光撃+自:朦朧 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]クリエイト:モンスター | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]ディケイドミスト |
| [ 3 ]クリエイト:コーラス | [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]グラトニー |
| [ 3 ]メテオ | [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]クリエイト:メガネ |
| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]ミゼラブルメモリー | [ 3 ]クリエイト:ワンダーランド | [ 3 ]ブレイブハート |
| [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]タイダルウェイブ | [ 3 ]イディオータ |
| [ 3 ]ゴッズディサイド | [ 3 ]フレイムインパクト |

PL / 紙箱みど