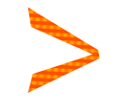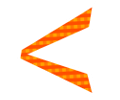<< 17:00~18:00




吉野暁海は帽子を目深に被り、早朝の大学構内を歩いている。
極力物音を立てず、ゆっくりと階段を登り、棟の間の渡り廊下を抜け、――第四学群。怪異学専攻大日向研究室、その教授の居室の前へ。
「……」
「……入れ」
ノックをするより先に、中から女の声がする。
傲慢で強気で、全てを見通すような年若い女の声。ごく一瞬手をかけるのが躊躇われ、けれど、吉野暁海はそこを開けなければならなかった。
「失礼します」
微かに震えた声。ドアの閉まる音とほぼ同時に、帽子のつばを跳ね上げた。宙に舞った帽子に手を伸ばすと、微かに傾いた身体のバランスはそれについていくことができない。
床に叩きつけられる身体。プラチナブロンドと称しても良い薄い色素の髪の下から、それは不釣り合いに覗いていた。

「……先生……」
「ボクからしてみればついに来たか、というのが感想だが、お前には説明してやる義務がある。座れ」
巻いた角。その手触りは生物の角より無機質で、例えるならハードカバーの本の表紙を触っているかのようだった。誰にも言えずにいた。自分の帽子の下に、そんなものが――正確に言えば、表皮が硬変し、色が変わりつつある場所ができているのを、誰にも言えなかった。
土の色と言うには濃く、濡れた土の色、と言うのが近い。けれど、この角はなんとなく木の感触がする。手触りの問題ではなく、もっと超越した感覚として。
来客用の椅子に腰掛けると、大日向がコーヒーを淹れている音がする。いつもの研究室だった。自分だけが、ずっと異質な存在として――あるいは異質であるという思い込みのもと、この場所にひとりいる。
「……俺は、無能力者で。俺は、【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚めた。そうですよね」
「そうだな。当時はそう定義するしかなかったが……定義とは移ろうものだ。学んでいる以上、それも分かるだろう?」
「ですけど……!!」
吉野暁海は長らく無能力者だった。弟と違い、その異能を見せびらかすような機会もなく、ただ一般的な学生として、小学校中学校、そして高校を卒業し、創峰大学に入学した。
大学に入学してからその異能――【知識の坩堝・ご都合主義】は発現し、能力者が一般的に義務境域などで学んでくる何もかもを、この大学に入ってから学んだ。どのように付き合うかのみならず、人へ向ける可能性がある場合の倫理的部分、その他“何か”起こった時の対処法……弟がとっくに知っているだろうことをようやく学べて、自分も肩を並べることができたと思ったのだ。思ったのに。
「では正直に話そうか。ボクも当然【知識の坩堝・ご都合主義】を持っているが、本来この系統のご都合主義は、生き物そのものを呼び出すことから、ごく一部の能力を自分に写すことまで自由自在だ。それ故に修得は比較的容易であり、学べば学ぶほど自分の有利な立ち回りを学ぶことができる。これは話したはずだ」
「……はい……」
【知識の坩堝・ご都合主義】(アーカイブマスタリ・アズユーライク)は、非常に自由度の高い、そして学びがその能力に直結する能力だ。例えば足を止めることなく走り続けるために、赤血球の構造を変化させたり。例えば重力を無視するために、ファンデルワールス力による吸盤を手足に実装したり。そのような動物がいて、どのような原理で発生していて、そしてその動物は何と――通名ではなく学名で――呼ばれているか。それらを揃えてようやく、実践級の能力に持ち上がる。
【ご都合主義】とは要するに、自分にとって不要な部分を切り捨てよ、という意味だ。その瞬間のために呼吸の方法まで変えてしまって窒息しては意味がないし、寒さで動けなくなっては意味がない。自分に必要なところだけを切り出し、継ぎ接ぎでもいいようにセットする。それこそ好きなように、自分という箱に力を詰め込むのだ。
「吉野。お前は何か悩んでいたことがなかったか?」
「……。……陸上の生物は、どうやっても、俺の身体に定着しませんでした。水中の生物……もっと言うと、海の……海の生き物しか……」
楽しみにしていたことがある。
【知識の坩堝・ご都合主義】をものにしたら、弟と戦ってみたかったのだ。戦うと言っても大げさなことでなく、例えるならじゃれあいくらいの、小さい頃に服を焼き焦がされて終わったような、それくらいのことでよかった。
そのためにどれだけ陸上の生物の特性を勉強し、学んでも。その特性を都合よく、その体に貼り付けることができない。
「ホタルやコウモリと言った“そのもの”を利用することはできる。まああの辺は基本のきだからな」
「……俺は、」
「もっと自分の肉体面が強化できることを期待していた」
「……ッ……」
言い返す言葉がなかった。
大日向研究室に所属している面々の殆どは、【知識の坩堝・ご都合主義】を修得しており、大なり小なりそれを利用している。基本のき、と大日向が言うように、少なくともこの研究室では、それができて当たり前のはずだった。
「悲観するな。それはそれで特化型だと言うことだ」
「……」
「ボクらは“似ている”ということで仮の名付けを行うことがある。お前の能力も【知識の坩堝・ご都合主義】に酷似していた、ただそれだけのことだ。だが明確に違う、ということがハッキリしたんだよ、吉野。お前が自分から戦おうとしたことで」
「カジキのことは忘れてくれませんか!!」
「無理だな」
長い白衣の袖から小さな手が覗いて、大きいマグカップになみなみ注がれたコーヒーを啜る。自分に出されていたコーヒーの水面を、ぼんやりと見つめていた。
「吉野。別段嘆く必要も、恐れる必要もない。お前は固有名を得ているということなのだからな」
「……けど、俺は……そんなのが欲しかったんじゃない!!」
「……」
無能力者でも問題ないよ、と言ってくれた父親。暁海は暁海だからね、と肯定してくれた母親。――兄貴は兄貴だよ、と言ってくれる弟。
そのどれもが信じられない。より正確に言えば、その言葉が信じられない。本当に、そんなことを言われていただろうか?
「受け入れろ。出たものを無に返すことは難しい」
「……」
「それともお前の学びとは、その程度で揺らぐものなのか?ならここを出ていけ」
「……こんなくらいで、出ていくと思って言ってますか」
「無論、出ていくようならそれまでだとも」
大日向を睨みつけている自分の顔が、自分のものでないように感じる。
白衣の人間を睨みつけるような経験なんてなかったはずだ。けれどその顔を、――自分を試すような顔を、知っている気がした。
「……ひどい話をするために呼び出したんですか?」
「呼び出し?アポを取ってきたのはお前だ」
「……すいません。何でもないです」
きっと、いつもより早く家を出てきたからだ。
きっと、この奇特な状況が全てを狂わせている。
「構わん。我々はすでにお前をどう定義するか決めている」
「……あ。【知識の坩堝】でないなら……」
女は一冊の本を書棚から抜き取った。それは古びた本だった。ぱらりぱらりと捲っていることが意味を成さないということに吉野暁海が気づいたのは、そこを覗き込んだときだった。
何も記されていない。
「【深閉架書庫の錨】(ダイビングライブラリーアンカー)。故にお前は海にしか潜れず、そして海と関連付けられる。」
ちょうど船が錨を下ろすように、強固に。そう言って、大日向はその本を吉野暁海に差し出した。
何のタイトルもなければ中身もない、ただ白紙の本だった。その割に随分年季が入っていて、折れや欠けが随所に見られるし、紙も焼けていた。
「……これは……」
「ある筋から手にしたものでね。お前の迷いを断ってくれるかもしれない」
「……俺は……迷ってるんですか?あんまりそういうつもりは」
何も書かれていない本が、自分の迷いを断ってくれるとは思えなかった。確かに読書は好きで、暇さえあれば本を読んでいたような幼少時代を過ごしたが、どうにもしっくり来なかった。
例えるなら、うまくはぐらかされているような、そんな感じだ。
「いずれ分かるさ。ところで午前八時になると西村が来るが」
「……コーヒー飲むまではいます」
「分かった。ボクは業務をするから好きにしていろ」
大日向が本来の座席に戻ってしまって、吉野暁海は何も聞けなくなった。いや、聞いても良かったのだろう。これが意味するところが一体何なのか、一体何を考えているのか。
自分が不要だ、と判断したのだ。だから、何も聞かなかった。何も聞かずにコーヒーを啜り、一限が来るのを待った。

ひょこり、と顔を出してくる姿に、ノータイムで肘を入れていた。
ぱかりと空いている空間から聞こえてくる男の呻き声の代わりに、顔を出したのは黒髪の少女だ。光を反射すらしない漆黒、ツートンカラーで構成されたひとでなし。
「ハリカリがついに渡したのか!と嬉々として出てくるところだったぞ」
「ボクにそれが予測できないと思っていたのかな。まあ君たちにはありがとうを言わなければならないのだが」
長い舌を出して笑っているのは、ハリカリという男の使い魔だ。黒いからスミ、というド安直命名だと聞いたが、その舌は白黒に映えるように赤い。
「けれどいいのか?スミたちは知っているが、あれは知らない」
「それは世界の理だ。ボクの狙いはそこじゃない」
「フーン……」
「あいてて……なあ大日向女史。その対応アリ?」
すぽん、とでも音が立ちそうな勢いで空間に引っ込んでいったスミの代わり、男が顔を出す。白髪を長く伸ばし、穏やかそうなツラでいるが、その本質は混沌であり、そして中立だ。面白そうだからという理由で対立する両陣営に軽率に手を貸し、自分はその場から逃げおおせ、手の届かないところから見ていたことを嬉々として話すような男だ。絶対中立主義とは言うものの、その中立の定義は己の中にある。
「当然だ。大業を成した以上一発入れるのが中立ではないか?」
「そんな中立条件設定したことも実行したこともないな……まあわざわざ探してきた“戯書”だ。これで君たちの望みもだいぶ叶うんじゃないか」
「ギショのニセモノで偽書な気はするけどな。スミってばてんさーい」
分厚くて大きく、そして何かの力を感じられる本であれば何でもよかった。【鈴のなる夢】は、これで感づくはずだからだ。
戯書。それは一月ばかりの間に、この男が探し当てた接点だ。パライバトルマリン、【鈴のなる夢】、そして【望遠水槽の終点】は、全てがそこに繋がるようにできている。何故“できている”と表現するのかといえば、本来の物語は幸せな結末で終わっているからだ。
幸せな結末を迎えなかった、迎えられなかった一つの可能性。それが【望遠水槽の終点】であり、故に終点と銘打たれているのだろう、というところまで、ハリカリは調べ上げ、適当な魔導書を戯書として偽造した。名前の通りに墨喰いであるスミの力で、文章のインクだけ引き抜いてしまえば、何か不思議な力がするまっさらな本の出来上がりだ。
「僕の仕事がこれで終わりだと思えば安いものとは思うけれど」
「いつ誰が終わりだと言った?貴様は徹底的に使い潰すぞ。やり口は覚えたからな」
「いいぞいいぞー。過労死だ。スミも応援しちゃう」
「勘弁してくれ」
扉が開く音と同時に、男と女の姿は霧散するように消える。



ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

以下の相手に送信しました




順(39) から クリアグロリエバインド を手渡しされました。
フェデルタ(165) から ローズクォーツ を手渡しされました。
ItemNo.22 生姜焼き を食べました!
体調が 2 回復!(13⇒15)
今回の全戦闘において 攻撃13 防御13 増幅13 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












魔術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
順(39) の持つ ItemNo.36 ビーフ から料理『ミートボール付きおにぎり』をつくりました!
ItemNo.31 すごいお魚 から料理『秋刀魚の塩焼き』をつくりました!
⇒ 秋刀魚の塩焼き/料理:強さ210/[効果1]活力30 [効果2]敏捷30 [効果3]強靭30
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.30 すごいナイフ に ItemNo.16 翌檜 を付加しました!
めぐみ(267) とカードを交換しました!
神の涙 (ナース)

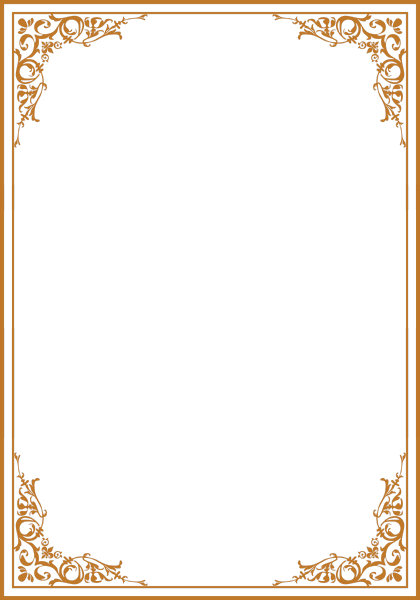
クリエイト:ワンダーランド を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:ワンダーランド を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:ワンダーランド を研究しました!(深度2⇒3)
悪夢 を習得!
盲目耐性 を習得!
フォースフィールド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は チャート を入手!
フェデルタ(165) は チャート を入手!
スズヒコ(244) は チャート を入手!
フェデルタ(165) は 小判 を入手!
フェデルタ(165) は 不思議な布 を入手!
スズヒコ(244) は 不思議な布 を入手!



ミナト区 C-2(山岳)に移動!(体調15⇒14)
ミナト区 D-2(沼地)に移動!(体調14⇒13)
ミナト区 E-2(沼地)に移動!(体調13⇒12)
ミナト区 F-2(沼地)に移動!(体調12⇒11)
ミナト区 G-2(沼地)に移動!(体調11⇒10)






[861 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[443 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[192 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[393 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[295 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[214 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[150 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[72 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[131 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[121 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[151 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[12 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[46 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
[3 / 300] ―― 《渡し舟》蝶のように舞い
―― Cross+Roseに映し出される。

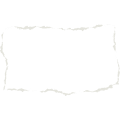
チャットが閉じられる――













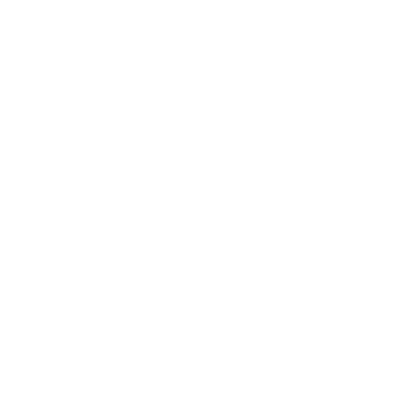
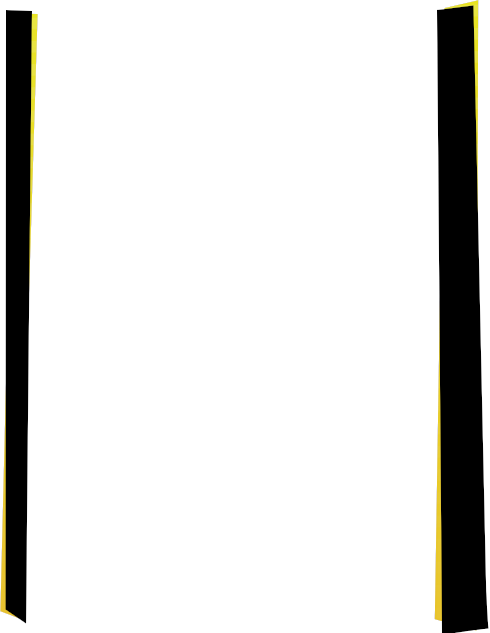
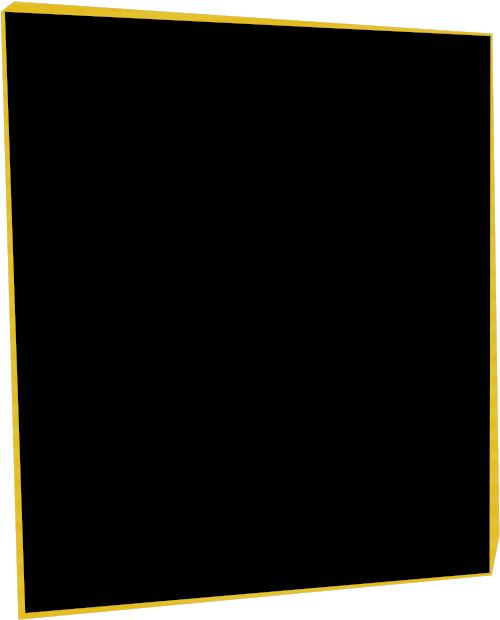





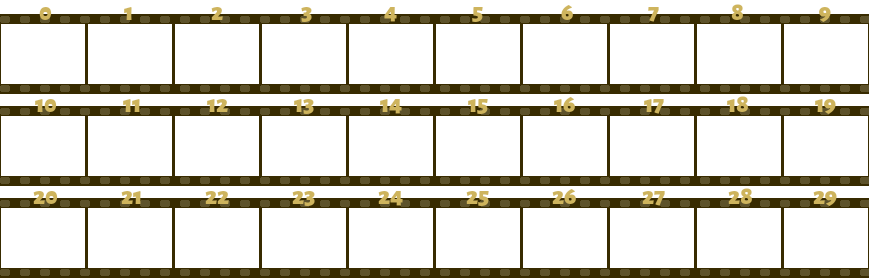









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



吉野暁海は帽子を目深に被り、早朝の大学構内を歩いている。
極力物音を立てず、ゆっくりと階段を登り、棟の間の渡り廊下を抜け、――第四学群。怪異学専攻大日向研究室、その教授の居室の前へ。
「……」
「……入れ」
ノックをするより先に、中から女の声がする。
傲慢で強気で、全てを見通すような年若い女の声。ごく一瞬手をかけるのが躊躇われ、けれど、吉野暁海はそこを開けなければならなかった。
「失礼します」
微かに震えた声。ドアの閉まる音とほぼ同時に、帽子のつばを跳ね上げた。宙に舞った帽子に手を伸ばすと、微かに傾いた身体のバランスはそれについていくことができない。
床に叩きつけられる身体。プラチナブロンドと称しても良い薄い色素の髪の下から、それは不釣り合いに覗いていた。

「……先生……」
「ボクからしてみればついに来たか、というのが感想だが、お前には説明してやる義務がある。座れ」
巻いた角。その手触りは生物の角より無機質で、例えるならハードカバーの本の表紙を触っているかのようだった。誰にも言えずにいた。自分の帽子の下に、そんなものが――正確に言えば、表皮が硬変し、色が変わりつつある場所ができているのを、誰にも言えなかった。
土の色と言うには濃く、濡れた土の色、と言うのが近い。けれど、この角はなんとなく木の感触がする。手触りの問題ではなく、もっと超越した感覚として。
来客用の椅子に腰掛けると、大日向がコーヒーを淹れている音がする。いつもの研究室だった。自分だけが、ずっと異質な存在として――あるいは異質であるという思い込みのもと、この場所にひとりいる。
「……俺は、無能力者で。俺は、【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚めた。そうですよね」
「そうだな。当時はそう定義するしかなかったが……定義とは移ろうものだ。学んでいる以上、それも分かるだろう?」
「ですけど……!!」
吉野暁海は長らく無能力者だった。弟と違い、その異能を見せびらかすような機会もなく、ただ一般的な学生として、小学校中学校、そして高校を卒業し、創峰大学に入学した。
大学に入学してからその異能――【知識の坩堝・ご都合主義】は発現し、能力者が一般的に義務境域などで学んでくる何もかもを、この大学に入ってから学んだ。どのように付き合うかのみならず、人へ向ける可能性がある場合の倫理的部分、その他“何か”起こった時の対処法……弟がとっくに知っているだろうことをようやく学べて、自分も肩を並べることができたと思ったのだ。思ったのに。
「では正直に話そうか。ボクも当然【知識の坩堝・ご都合主義】を持っているが、本来この系統のご都合主義は、生き物そのものを呼び出すことから、ごく一部の能力を自分に写すことまで自由自在だ。それ故に修得は比較的容易であり、学べば学ぶほど自分の有利な立ち回りを学ぶことができる。これは話したはずだ」
「……はい……」
【知識の坩堝・ご都合主義】(アーカイブマスタリ・アズユーライク)は、非常に自由度の高い、そして学びがその能力に直結する能力だ。例えば足を止めることなく走り続けるために、赤血球の構造を変化させたり。例えば重力を無視するために、ファンデルワールス力による吸盤を手足に実装したり。そのような動物がいて、どのような原理で発生していて、そしてその動物は何と――通名ではなく学名で――呼ばれているか。それらを揃えてようやく、実践級の能力に持ち上がる。
【ご都合主義】とは要するに、自分にとって不要な部分を切り捨てよ、という意味だ。その瞬間のために呼吸の方法まで変えてしまって窒息しては意味がないし、寒さで動けなくなっては意味がない。自分に必要なところだけを切り出し、継ぎ接ぎでもいいようにセットする。それこそ好きなように、自分という箱に力を詰め込むのだ。
「吉野。お前は何か悩んでいたことがなかったか?」
「……。……陸上の生物は、どうやっても、俺の身体に定着しませんでした。水中の生物……もっと言うと、海の……海の生き物しか……」
楽しみにしていたことがある。
【知識の坩堝・ご都合主義】をものにしたら、弟と戦ってみたかったのだ。戦うと言っても大げさなことでなく、例えるならじゃれあいくらいの、小さい頃に服を焼き焦がされて終わったような、それくらいのことでよかった。
そのためにどれだけ陸上の生物の特性を勉強し、学んでも。その特性を都合よく、その体に貼り付けることができない。
「ホタルやコウモリと言った“そのもの”を利用することはできる。まああの辺は基本のきだからな」
「……俺は、」
「もっと自分の肉体面が強化できることを期待していた」
「……ッ……」
言い返す言葉がなかった。
大日向研究室に所属している面々の殆どは、【知識の坩堝・ご都合主義】を修得しており、大なり小なりそれを利用している。基本のき、と大日向が言うように、少なくともこの研究室では、それができて当たり前のはずだった。
「悲観するな。それはそれで特化型だと言うことだ」
「……」
「ボクらは“似ている”ということで仮の名付けを行うことがある。お前の能力も【知識の坩堝・ご都合主義】に酷似していた、ただそれだけのことだ。だが明確に違う、ということがハッキリしたんだよ、吉野。お前が自分から戦おうとしたことで」
「カジキのことは忘れてくれませんか!!」
「無理だな」
長い白衣の袖から小さな手が覗いて、大きいマグカップになみなみ注がれたコーヒーを啜る。自分に出されていたコーヒーの水面を、ぼんやりと見つめていた。
「吉野。別段嘆く必要も、恐れる必要もない。お前は固有名を得ているということなのだからな」
「……けど、俺は……そんなのが欲しかったんじゃない!!」
「……」
無能力者でも問題ないよ、と言ってくれた父親。暁海は暁海だからね、と肯定してくれた母親。――兄貴は兄貴だよ、と言ってくれる弟。
そのどれもが信じられない。より正確に言えば、その言葉が信じられない。本当に、そんなことを言われていただろうか?
「受け入れろ。出たものを無に返すことは難しい」
「……」
「それともお前の学びとは、その程度で揺らぐものなのか?ならここを出ていけ」
「……こんなくらいで、出ていくと思って言ってますか」
「無論、出ていくようならそれまでだとも」
大日向を睨みつけている自分の顔が、自分のものでないように感じる。
白衣の人間を睨みつけるような経験なんてなかったはずだ。けれどその顔を、――自分を試すような顔を、知っている気がした。
「……ひどい話をするために呼び出したんですか?」
「呼び出し?アポを取ってきたのはお前だ」
「……すいません。何でもないです」
きっと、いつもより早く家を出てきたからだ。
きっと、この奇特な状況が全てを狂わせている。
「構わん。我々はすでにお前をどう定義するか決めている」
「……あ。【知識の坩堝】でないなら……」
女は一冊の本を書棚から抜き取った。それは古びた本だった。ぱらりぱらりと捲っていることが意味を成さないということに吉野暁海が気づいたのは、そこを覗き込んだときだった。
何も記されていない。
「【深閉架書庫の錨】(ダイビングライブラリーアンカー)。故にお前は海にしか潜れず、そして海と関連付けられる。」
ちょうど船が錨を下ろすように、強固に。そう言って、大日向はその本を吉野暁海に差し出した。
何のタイトルもなければ中身もない、ただ白紙の本だった。その割に随分年季が入っていて、折れや欠けが随所に見られるし、紙も焼けていた。
「……これは……」
「ある筋から手にしたものでね。お前の迷いを断ってくれるかもしれない」
「……俺は……迷ってるんですか?あんまりそういうつもりは」
何も書かれていない本が、自分の迷いを断ってくれるとは思えなかった。確かに読書は好きで、暇さえあれば本を読んでいたような幼少時代を過ごしたが、どうにもしっくり来なかった。
例えるなら、うまくはぐらかされているような、そんな感じだ。
「いずれ分かるさ。ところで午前八時になると西村が来るが」
「……コーヒー飲むまではいます」
「分かった。ボクは業務をするから好きにしていろ」
大日向が本来の座席に戻ってしまって、吉野暁海は何も聞けなくなった。いや、聞いても良かったのだろう。これが意味するところが一体何なのか、一体何を考えているのか。
自分が不要だ、と判断したのだ。だから、何も聞かなかった。何も聞かずにコーヒーを啜り、一限が来るのを待った。

ひょこり、と顔を出してくる姿に、ノータイムで肘を入れていた。
ぱかりと空いている空間から聞こえてくる男の呻き声の代わりに、顔を出したのは黒髪の少女だ。光を反射すらしない漆黒、ツートンカラーで構成されたひとでなし。
「ハリカリがついに渡したのか!と嬉々として出てくるところだったぞ」
「ボクにそれが予測できないと思っていたのかな。まあ君たちにはありがとうを言わなければならないのだが」
長い舌を出して笑っているのは、ハリカリという男の使い魔だ。黒いからスミ、というド安直命名だと聞いたが、その舌は白黒に映えるように赤い。
「けれどいいのか?スミたちは知っているが、あれは知らない」
「それは世界の理だ。ボクの狙いはそこじゃない」
「フーン……」
「あいてて……なあ大日向女史。その対応アリ?」
すぽん、とでも音が立ちそうな勢いで空間に引っ込んでいったスミの代わり、男が顔を出す。白髪を長く伸ばし、穏やかそうなツラでいるが、その本質は混沌であり、そして中立だ。面白そうだからという理由で対立する両陣営に軽率に手を貸し、自分はその場から逃げおおせ、手の届かないところから見ていたことを嬉々として話すような男だ。絶対中立主義とは言うものの、その中立の定義は己の中にある。
「当然だ。大業を成した以上一発入れるのが中立ではないか?」
「そんな中立条件設定したことも実行したこともないな……まあわざわざ探してきた“戯書”だ。これで君たちの望みもだいぶ叶うんじゃないか」
「ギショのニセモノで偽書な気はするけどな。スミってばてんさーい」
分厚くて大きく、そして何かの力を感じられる本であれば何でもよかった。【鈴のなる夢】は、これで感づくはずだからだ。
戯書。それは一月ばかりの間に、この男が探し当てた接点だ。パライバトルマリン、【鈴のなる夢】、そして【望遠水槽の終点】は、全てがそこに繋がるようにできている。何故“できている”と表現するのかといえば、本来の物語は幸せな結末で終わっているからだ。
幸せな結末を迎えなかった、迎えられなかった一つの可能性。それが【望遠水槽の終点】であり、故に終点と銘打たれているのだろう、というところまで、ハリカリは調べ上げ、適当な魔導書を戯書として偽造した。名前の通りに墨喰いであるスミの力で、文章のインクだけ引き抜いてしまえば、何か不思議な力がするまっさらな本の出来上がりだ。
「僕の仕事がこれで終わりだと思えば安いものとは思うけれど」
「いつ誰が終わりだと言った?貴様は徹底的に使い潰すぞ。やり口は覚えたからな」
「いいぞいいぞー。過労死だ。スミも応援しちゃう」
「勘弁してくれ」
扉が開く音と同時に、男と女の姿は霧散するように消える。



ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
順 「なんですか、この光の球は。気味が悪い」 |
| フェデルタ 「……空の裂け目から……か、更に余計なモンに引っ掻き回されるのは確かにゴメンだな」 |
順(39) から クリアグロリエバインド を手渡しされました。
フェデルタ(165) から ローズクォーツ を手渡しされました。
| フェデルタ 「これ、少しは役に立つといいけど」 |
ItemNo.22 生姜焼き を食べました!
体調が 2 回復!(13⇒15)
今回の全戦闘において 攻撃13 防御13 増幅13 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 64 増加!
影響力が 64 増加!



マガサ区 S-2:スターロッジ
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
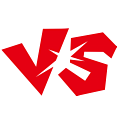 |
立ちはだかるもの
|



魔術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
順(39) の持つ ItemNo.36 ビーフ から料理『ミートボール付きおにぎり』をつくりました!
ItemNo.31 すごいお魚 から料理『秋刀魚の塩焼き』をつくりました!
⇒ 秋刀魚の塩焼き/料理:強さ210/[効果1]活力30 [効果2]敏捷30 [効果3]強靭30
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.30 すごいナイフ に ItemNo.16 翌檜 を付加しました!
めぐみ(267) とカードを交換しました!
神の涙 (ナース)

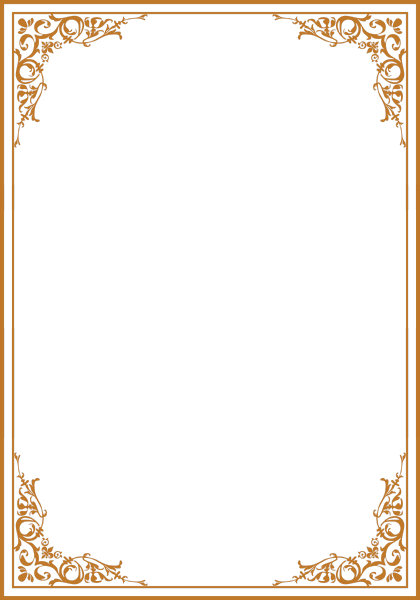
クリエイト:ワンダーランド を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:ワンダーランド を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:ワンダーランド を研究しました!(深度2⇒3)
悪夢 を習得!
盲目耐性 を習得!
フォースフィールド を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



順(39) は チャート を入手!
フェデルタ(165) は チャート を入手!
スズヒコ(244) は チャート を入手!
フェデルタ(165) は 小判 を入手!
フェデルタ(165) は 不思議な布 を入手!
スズヒコ(244) は 不思議な布 を入手!



ミナト区 C-2(山岳)に移動!(体調15⇒14)
ミナト区 D-2(沼地)に移動!(体調14⇒13)
ミナト区 E-2(沼地)に移動!(体調13⇒12)
ミナト区 F-2(沼地)に移動!(体調12⇒11)
ミナト区 G-2(沼地)に移動!(体調11⇒10)






[861 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[443 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[192 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[393 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[295 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[214 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[150 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[72 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[131 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[121 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[151 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[12 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[46 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
[3 / 300] ―― 《渡し舟》蝶のように舞い
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
ノウレット 「呼ばれなくても出てきちゃう☆ノウレッ――」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「・・・・・・・・・」 |
 |
ノウレット 「え、誰もいない! ・・・・・何か落ちてます。・・・・・・・・・紙切れ?」 |
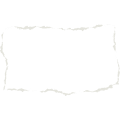
紙切れ
そうです、紙切れですよぉー。初めまして。
 |
ノウレット 「・・・えっとぉ・・・・・」 |
 |
《 サボってみます。 案内役一同 》 |
 |
ノウレット 「・・・・・・・・・・・・」 |
 |
ノウレット 「えええぇぇぇぇ・・・・・・・・・」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。





ENo.244
鈴のなる夢
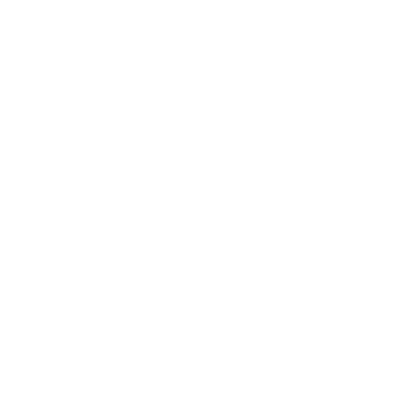
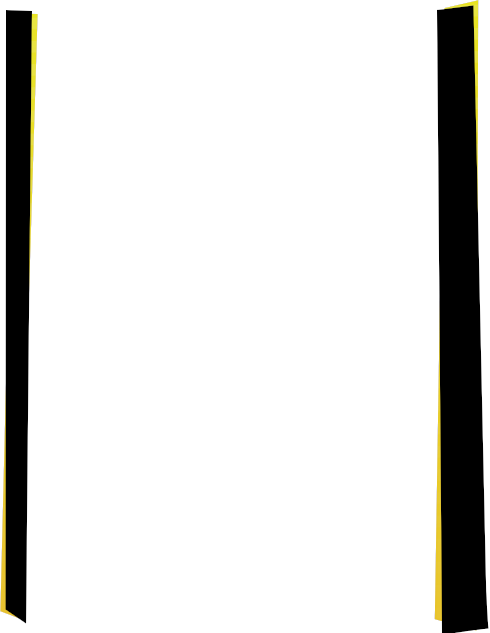
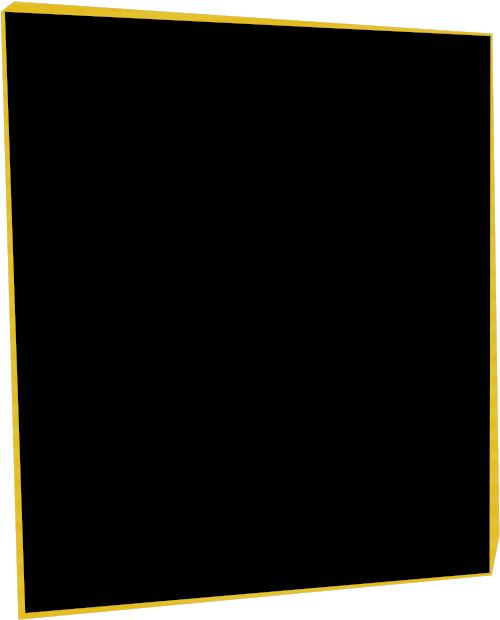
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
“羽化”を果たし、妄執の獣と決別する。その手にあるのは、道を拓くための知と炎。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
“羽化”を果たし、妄執の獣と決別する。その手にあるのは、道を拓くための知と炎。
10 / 30
1273 PS
ミナト
G-2
G-2







痛撃友の会
2
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
1
アイコン60pxの会
1
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
1
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
2
カード報告会
2
とりあえず肉食う?
4



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | 閃光10 | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | 角閃石 | 素材 | 40 | [武器]連撃35(LV70)[防具]閃撃35(LV80)[装飾]耐地35(LV65) | |||
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||
| 8 | 火焔茸 | 素材 | 35 | [武器]猛毒30(LV70)[防具]反毒35(LV75)[装飾]舞衰30(LV70) | |||
| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | 耐疫15 | - | |
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | 風柳10 | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | バンブーエディトリアン | 防具 | 300 | 加速20 | 活力30 | - | |
| 15 | コンサーティナペンダント | 装飾 | 327 | 攻撃30 | - | - | |
| 16 | 装甲 | 素材 | 35 | [武器]全護25(LV55)[防具]防御35(LV75)[装飾]耐災30(LV60) | |||
| 17 | リアリズムカレントブラスト | 大砲 | 306 | 体力20 | 追風15 | - | 【射程4】 |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 21 | 鱗 | 素材 | 20 | [武器]朦朧25(LV55)[防具]反水30(LV60)[装飾]耐火25(LV45) | |||
| 22 | チャート | 素材 | 35 | [武器]活力35(LV80)[防具]反護30(LV70)[装飾]強靭30(LV60) | |||
| 23 | レッドバーンビブリオ | 薬箱 | 81 | 耐疫15 | 耐疫15 | - | |
| 24 | クリアグロリエバインド | 装飾 | 260 | 活力20 | 活力20 | - | |
| 25 | 串焼き | 料理 | 109 | 攻撃12 | 防御12 | 増幅12 | |
| 26 | 装甲 | 素材 | 35 | [武器]全護25(LV55)[防具]防御35(LV75)[装飾]耐災30(LV60) | |||
| 27 | ローズクォーツ | 装飾 | 75 | 火纏10 | 火纏10 | - | |
| 28 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 29 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 30 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 31 | 秋刀魚の塩焼き | 料理 | 210 | 活力30 | 敏捷30 | 強靭30 | |
| 32 | 不思議な布 | 素材 | 25 | [武器]放魅30(LV55)[防具]耐狂25(LV45)[装飾]舞撃25(LV50) | |||
| 33 | |||||||
| 34 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 30 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 30 | 呪詛/邪気/闇 |
| 変化 | 20 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 50 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 60 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 10 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 8 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| 練3 | ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| 練3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| 練3 | マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| フィーバー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| 練3 | マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 6 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 6 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 15 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 6 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |
| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| リストア | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+環境変調を守護化 | |
| エリアグラスプ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 7 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 練3 | セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 |
| イラプション | 5 | 0 | 180 | 敵列:地撃+敵味全:火撃&炎上 | |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| 練3 | パワフルヒール | 6 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| グレイシア | 8 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| ウィザー | 5 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |
| サモン:ビーフ | 7 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| 練3 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| 練3 | ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 |
| 練3 | ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 | |
| 練3 | イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 |
| ドレインライフ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&MHP奪取 | |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 | |
| 練3 | フォースフィールド | 5 | 1 | 300 | 味全:AT増 |
| グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 | |
| 練3 | コンフィデンス | 6 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 |
| ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
| 練3 | グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 |
| スノーホワイト | 5 | 0 | 200 | 敵4:水痛撃&朦朧 | |
| 練3 | ディープブルー | 5 | 0 | 200 | 敵:水撃&水特性増 |
| バーニングカード | 5 | 0 | 80 | 敵3:火撃+自:強制炎上 | |
| ディケイドミスト | 5 | 1 | 300 | 敵全:AG減(4T)&腐食+味全:DX増(4T)&腐食 | |
| 練3 | タイダルウェイブ | 5 | 0 | 330 | 敵:5連鎖水撃&DX・AG減(2T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 瘴気 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘離脱前】敵6:猛毒・麻痺・衰弱 | |
| 肉体変調特性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
| 練3 | 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 |
| 凍縛陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど凍縛LV増 | |
| 治癒領域 | 8 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 悪夢 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:SP闇撃&束縛 | |
| 凍結耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:凍結耐性増 | |
| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |
| 腐食耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:腐食耐性増 | |
| 盲目耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:盲目耐性増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |
| 生殺与奪 | 5 | 6 | 0 | 【攻撃命中後】対:火撃+対:水撃&味傷:HP増 | |
| 星火燎原 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】敵味炎:粗雑火撃&炎上奪取&自:炎上をAT化 | |
| 火霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:魔術LVが高いほどSP・火特性増 | |
| 水霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:命術LVが高いほどSP・水特性増 | |
| 闇霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |
| 千変万化 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |
| 火特性回復 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:火属性スキルのHP増効果に火特性が影響 | |
| 魔香作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で料理「魔香」を選択できる。魔香は体調が回復せず効果3しか付加されないが、食事に指定しても消費されない。 |
最大EP[25]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練3 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| 練3 |
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
| 練3 |
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
|
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
|
ギフトカード (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |
5 | 500 | 自:エンペラー召喚 | |
|
余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター) |
0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 | |
| 練3 |
フリーリィ・スカイシー・ダイブ (ワールウィンド) |
0 | 200 | 敵傷7:風撃 |
|
血眼 (ブラッドアイズ) |
0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
|
スミの炭になりたい (ミゼラブルメモリー) |
2 | 200 | 敵:6連鎖SP闇撃 | |
| 練3 |
疾痛猶予 (パワフルヒール) |
0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| 練3 |
神の涙 (ナース) |
0 | 180 | 味傷5:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]タイダルウェイブ | [ 3 ]グラトニー | [ 3 ]ミゼラブルメモリー |
| [ 3 ]クリエイト:コーラス | [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]レーヴァテイン |
| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]イディオータ |
| [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]ディケイドミスト | [ 3 ]クリエイト:ワンダーランド | [ 3 ]フレイムインパクト |
| [ 3 ]クリエイト:モンスター | [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]ゴッズディサイド |
| [ 3 ]ブレイブハート |

PL / 紙箱みど