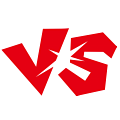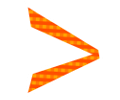<< 5:00~6:00




「吸うかい?」
「いりません、私一応まだ未成年ですし」
男は首を横に振る、不機嫌そうと言うより真面目な返答に呆れる様に──
一本だけ出した煙草を咥え、火をつけると煙が空を舞う。
中性的な顔立ちをした男性、悠里はその煙草の香りに不快そうな顔は決して浮かべなかった、くしゃみは出そうになるが一つ一つ指摘してはキリがないから、特に指摘する理由もなかったから。
「で、彼女の監視につけていた奴等が薙ぎ倒したの君だよね?何の益があってそんな事したんだい?ヒーローごっこか?」
「確かに私ですが、ヒーローごっこではありません。
職に誇りはありましたが今や神職ではない私が不審者を薙ぎ倒した事で咎められる謂れはありません」
今、この瞬間にももたれている木に片手が触れている様子に男性は溜息を吐く。
例の監視対象から聞いた人物像よりも過激的かつ能動的だと。
この場にいるのは男性同士とはいえ、少なくとも悠里と違い男性は良い年の荒事に慣れた人物なのだからそう言う状況になったとてその異能でどうにか出来る保証もないだろうにと。
「君ね、暴力あれば警察は動く。しかも…だ。
君に何かしたわけでもするわけでもない人をそうしたんだ…こちらがそう出たら君がただ不利なだけだよ。彼女に惚れてるのか?」
「それ位知っています、そして私の恋愛感情はとっくにたった1人に捧げています」
「なら尚更解せないな、理由がない」
「アレは一応血縁としても私の姉という事になっているんです、それにもし貴方達が調子に乗って祖母に手でも出そうものならと考えたから行動に移しました。
それ以上に理由が必要ですか?ストーカーがいるからと通報しなかっただけその場で済んだから良かったと私としては思って頂きたいのですが」
「…理由は納得した…が、随分と強気だな。
こちらの研究機関の話は彼女から聞いてるのだろう?やろうと思えばこちらは色んな手を使える」
それは挑発ではなく、悠理を本人なりに心配しての警告。
直接的にいえば、下手をすれば始末されかねないぞという言葉。
「人を殺められる人が、よく私に警察がどうのとか言えますね…」
「人の命の在り方が変わるかもしれない…という話だからな。本来は君みたいなただの子供の耳に入る話じゃないよ」
「…私ね、知らないんですよ」
「…?」
「彼女が介入しただけでは済んでないの、おかしいですよね。
彼女の異能は珍しい物でも決してない…少なくともこの町では…という話だから今に至るとは言え…
そんな異能の研究機関の話なんて私、知らないんですよ」
「大々的に宣伝されてるはずがないからな、知らないのも当然だ」
「そうじゃないですよ、私は貴方達の様な異物を知らないと言ってるんです」
「…」
静かに煙草が地面に捨てられ、踏まれる。煙が未練がましくまだ少し舞いながらも砂に混ざる灰。
ゆるりとした動作で男性のジャケットからは、ある物が取り出されて悠里に向けられる。
拳銃だ──
「…異能の街において銃は珍しくないだろう、彼女も本物の代わりを持たせてる」
「異能がある事と人殺しが軽くなる事は別です。命ですからね、人権とは私や貴方みたいな人間にも適用されます、命に貴賎はありません。
後、認めたのですか…?」
「いや、認めるも何も何が基準かすら分からないからね。
だが…その発想に至るのはどのみち危険だと考えたからこうするしかない」
悠里は極めて温和な人間で、天気の良い日に縁側でお茶を飲むのが好きな様な人間。
それが、彼を取り巻く環境が変わってからはこんな側面ばかりを見せている、自分が変わる様な思いもない。恐れがない。
強いていうなら、自分は思ったよりも頑固な様だと考える程度だろう。
「助けが来るとか思ってないか?君がもし女の子なら俺も助けただろう」
「思っていませんよ、それに…私が女の子であっても変わらないです。
貴方なんかに命を握られるのは耐えられませんから。馬鹿にしないでください」
「俺にも娘がいる、君と歳は近い」
「知ってます、情があるように見せるのならば最初からそれを向けないでください。
撃つなら撃ちなさい、撃てないなら私の前から立ち去りなさい。
貴方の迷いだらけの銃弾では私を殺せても貴方も死ぬだけです」
木を慈しむように撫でていた手が離れる──
「…悠里、死ぬ前に君の苗字位は聞いてやろうか」
微動だにせず、人気の少ない夜の河川敷で悠里は小さく笑みを浮かべる。
月光の下でその薄紫の髪を翻して──
「教えてあげない、実の娘さんに監視なんかつける様な人、私嫌いですから」
銃声が、夜を裂くように響く──



ENo.546 不幸喰らい とのやりとり




特に何もしませんでした。








武術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
イレイザー を習得!
チャクラグラント を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。





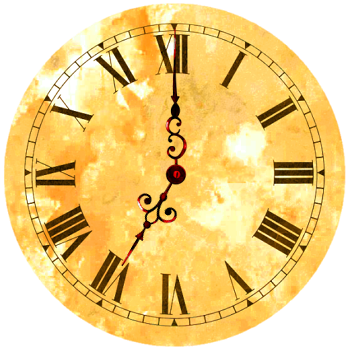
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映し出されるふたり。
チャットから消えるふたり。
チャットが閉じられる――







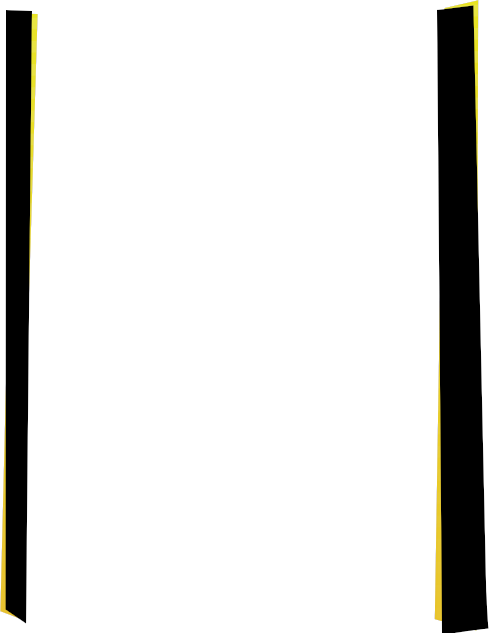
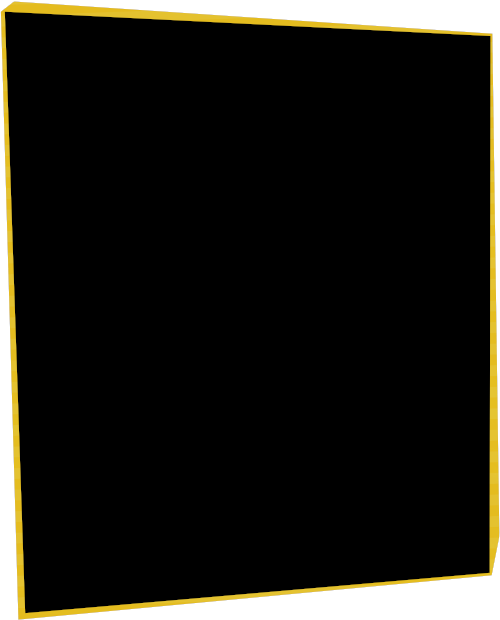





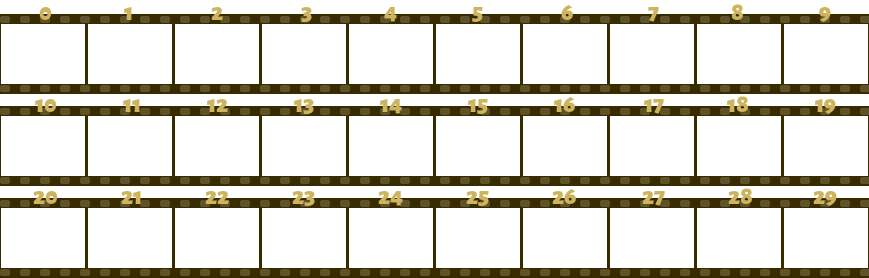





































異能・生産
アクティブ
パッシブ





[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



「吸うかい?」
「いりません、私一応まだ未成年ですし」
男は首を横に振る、不機嫌そうと言うより真面目な返答に呆れる様に──
一本だけ出した煙草を咥え、火をつけると煙が空を舞う。
中性的な顔立ちをした男性、悠里はその煙草の香りに不快そうな顔は決して浮かべなかった、くしゃみは出そうになるが一つ一つ指摘してはキリがないから、特に指摘する理由もなかったから。
「で、彼女の監視につけていた奴等が薙ぎ倒したの君だよね?何の益があってそんな事したんだい?ヒーローごっこか?」
「確かに私ですが、ヒーローごっこではありません。
職に誇りはありましたが今や神職ではない私が不審者を薙ぎ倒した事で咎められる謂れはありません」
今、この瞬間にももたれている木に片手が触れている様子に男性は溜息を吐く。
例の監視対象から聞いた人物像よりも過激的かつ能動的だと。
この場にいるのは男性同士とはいえ、少なくとも悠里と違い男性は良い年の荒事に慣れた人物なのだからそう言う状況になったとてその異能でどうにか出来る保証もないだろうにと。
「君ね、暴力あれば警察は動く。しかも…だ。
君に何かしたわけでもするわけでもない人をそうしたんだ…こちらがそう出たら君がただ不利なだけだよ。彼女に惚れてるのか?」
「それ位知っています、そして私の恋愛感情はとっくにたった1人に捧げています」
「なら尚更解せないな、理由がない」
「アレは一応血縁としても私の姉という事になっているんです、それにもし貴方達が調子に乗って祖母に手でも出そうものならと考えたから行動に移しました。
それ以上に理由が必要ですか?ストーカーがいるからと通報しなかっただけその場で済んだから良かったと私としては思って頂きたいのですが」
「…理由は納得した…が、随分と強気だな。
こちらの研究機関の話は彼女から聞いてるのだろう?やろうと思えばこちらは色んな手を使える」
それは挑発ではなく、悠理を本人なりに心配しての警告。
直接的にいえば、下手をすれば始末されかねないぞという言葉。
「人を殺められる人が、よく私に警察がどうのとか言えますね…」
「人の命の在り方が変わるかもしれない…という話だからな。本来は君みたいなただの子供の耳に入る話じゃないよ」
「…私ね、知らないんですよ」
「…?」
「彼女が介入しただけでは済んでないの、おかしいですよね。
彼女の異能は珍しい物でも決してない…少なくともこの町では…という話だから今に至るとは言え…
そんな異能の研究機関の話なんて私、知らないんですよ」
「大々的に宣伝されてるはずがないからな、知らないのも当然だ」
「そうじゃないですよ、私は貴方達の様な異物を知らないと言ってるんです」
「…」
静かに煙草が地面に捨てられ、踏まれる。煙が未練がましくまだ少し舞いながらも砂に混ざる灰。
ゆるりとした動作で男性のジャケットからは、ある物が取り出されて悠里に向けられる。
拳銃だ──
「…異能の街において銃は珍しくないだろう、彼女も本物の代わりを持たせてる」
「異能がある事と人殺しが軽くなる事は別です。命ですからね、人権とは私や貴方みたいな人間にも適用されます、命に貴賎はありません。
後、認めたのですか…?」
「いや、認めるも何も何が基準かすら分からないからね。
だが…その発想に至るのはどのみち危険だと考えたからこうするしかない」
悠里は極めて温和な人間で、天気の良い日に縁側でお茶を飲むのが好きな様な人間。
それが、彼を取り巻く環境が変わってからはこんな側面ばかりを見せている、自分が変わる様な思いもない。恐れがない。
強いていうなら、自分は思ったよりも頑固な様だと考える程度だろう。
「助けが来るとか思ってないか?君がもし女の子なら俺も助けただろう」
「思っていませんよ、それに…私が女の子であっても変わらないです。
貴方なんかに命を握られるのは耐えられませんから。馬鹿にしないでください」
「俺にも娘がいる、君と歳は近い」
「知ってます、情があるように見せるのならば最初からそれを向けないでください。
撃つなら撃ちなさい、撃てないなら私の前から立ち去りなさい。
貴方の迷いだらけの銃弾では私を殺せても貴方も死ぬだけです」
木を慈しむように撫でていた手が離れる──
「…悠里、死ぬ前に君の苗字位は聞いてやろうか」
微動だにせず、人気の少ない夜の河川敷で悠里は小さく笑みを浮かべる。
月光の下でその薄紫の髪を翻して──
「教えてあげない、実の娘さんに監視なんかつける様な人、私嫌いですから」
銃声が、夜を裂くように響く──



ENo.546 不幸喰らい とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||



特に何もしませんでした。







武術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
イレイザー を習得!
チャクラグラント を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。





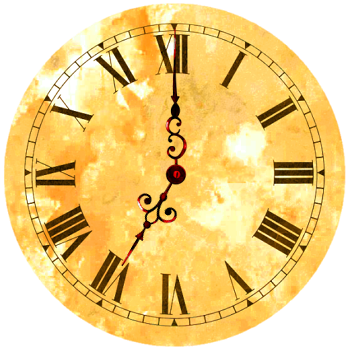
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「うんうん、順調じゃねーっすか。 あとやっぱうるせーのは居ねぇほうが断然いいっすね。」 |
 |
白南海 「いいから早くこれ終わって若に会いたいっすねぇまったく。 もう世界がどうなろうと一緒に歩んでいきやしょうワカァァ――」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カグハ 「・・・わ、変なひとだ。」 |
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
白南海 「――ん、んんッ・・・・・ ・・・なんすか。 お前らは・・・あぁ、梅楽園の団子むすめっこか。」 |
 |
カオリ 「チャットにいたからお邪魔してみようかなって!ごあいさつ!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
 |
白南海 「勝手に人の部屋に入るもんじゃねぇぞ、ガキンチョ。」 |
 |
カオリ 「勝手って、みんなに発信してるじゃんこのチャット。」 |
 |
カグハ 「・・・寂しがりや?」 |
 |
白南海 「・・・そ、操作ミスってたのか。クソ。・・・クソ。」 |
 |
白南海 「そういや、お前らは・・・・・ロストじゃねぇんよなぁ?」 |
 |
カグハ 「違うよー。」 |
 |
カオリ 「私はイバラシティ生まれのイバラシティ育ち!」 |
 |
白南海 「・・・・・は?なんだこっち側かよ。 だったらアンジニティ側に団子渡すなっての。イバラシティがどうなってもいいのか?」 |
 |
カオリ 「あ、・・・・・んー、・・・それがそれが。カグハちゃんは、アンジニティ側なの。」 |
 |
カグハ 「・・・・・」 |
 |
白南海 「なんだそりゃ。ガキのくせに、破滅願望でもあんのか?」 |
 |
カグハ 「・・・・・その・・・」 |
 |
カオリ 「うーあーやめやめ!帰ろうカグハちゃん!!」 |
 |
カオリ 「とにかく私たちは能力を使ってお団子を作ることにしたの! ロストのことは偶然そうなっただけだしっ!!」 |
 |
カグハ 「・・・カオリちゃん、やっぱり私――」 |
 |
カオリ 「そ、それじゃーね!バイビーン!!」 |
チャットから消えるふたり。
 |
白南海 「・・・・・ま、別にいいんすけどね。事情はそれぞれ、あるわな。」 |
 |
白南海 「でも何も、あんな子供を巻き込むことぁねぇだろ。なぁ主催者さんよ・・・」 |
チャットが閉じられる――





ENo.358
森山 花子

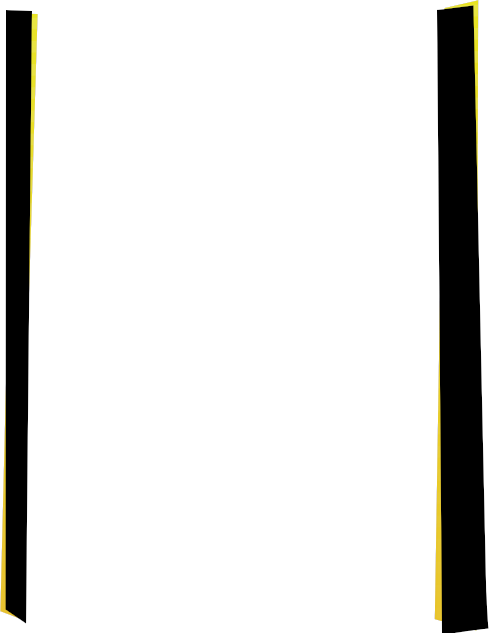
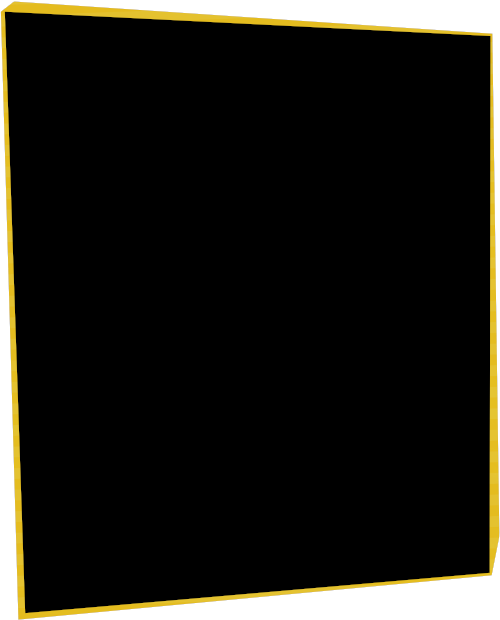
森山 花子(もりやま はなこ)
身長:145cm
一人称:私 二人称:貴方、お兄さん、お姉さん
性別:女性
年齢:85歳
森山駄菓子店の店長。
夫は既に他界している為、夫の駄菓子屋を継いで店長を務めている。
好物はさくらもち、チョコレートは板チョコが貰えただけでとても喜ぶ。
穏やかで面倒見の良いお婆ちゃん。
「いらっしゃい、おみくじもあるよ。
やっていかないかい?」
異能:「召し上がれ」
花子の差し出す食べ物には人の心を落ち着ける作用がある、言わば、精神干渉型の異能とも言える。
花子は昔から自身の異能に自覚がなく、それでも発動していることからこれは常時発動の異能と思われる。
サブキャラ
森山 薫(もりやま かおる)
身長:165cm
一人称:自分 二人称:君
性別:女性
年齢:17歳
「…よろしく頼む」
全身図
http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=soru72su3i&file=5CBFCD88-4E77-4CAC-9764-5C89EABA29D1.png
相良伊橋高校に秋に編入してきた女性。
薄い青紫色の長髪にワインレッドの瞳。
コヌマ区の森山駄菓子店で暮らしていて、そこの店主花子とは祖母と孫の関係だと花子は言っているが、薫は本当はドイツ出身、花子は純日本人だ。
堅苦しい喋り方に、クールで冷たい性格の様だが、話しかけると友好的、口数は多くないが本人が交流らしい交流に慣れていないだけで突き放す気は無い。
両太腿に本物の皮で出来たホルスターを巻いているが中に入っているのは水鉄砲。
実はカナヅチ
異能
・血の創造
血液をあらゆる物の代用品として扱える異能。
例えば赤い絵の具がない場合血を異能で使う事で本物の絵の具に変えられる。
赤と再現したのは使用する物は血の色になるから。違う物として異能で変化した後は参加して茶色くなったりせず新鮮な赤黒い色のまま。
服がない場合に血を利用して服に変える事もできるが真っ赤は目立つからと本人がその方法では利用しない。
代償
・血の消費量は代用にする物の規模に合わせて多くなる。
・一度実際に使用した事のある物しか代用品の生成は不可能
・薫は内臓移植を事故の後に受け、その内臓に付与された呪いで身体がボロボロである。
・彼女自体はこの町の外から来ている、しかし花子は彼女がそうである事を記憶が混濁してるからと言っている様だが…?
・彼女はどうやら死ぬらしい、死なないといけないらしい、ただそれだけ。たったそれだけのことである──
悠里
身長:170cm
一人称:私 二人称:貴方
性別:男性
年齢:19歳
女性にしか見えない顔立ちと男性にしては高め、女性にしてはハスキーな声が特徴。
普段は巫女服で歩き回っている。コスプレではなく正装なのだが、諸事情につきコスプレでしかない状態が悩み。
愛想の良さと笑顔が特徴。
異能
【慈悲なき魔の手】
触れた物を動かす能力。動かすと言っても超能力的ではなく、さながら命を与えるかのように。
しかし、触れた物それには正常な思考は宿らない。戦意だけの兵を作るのには持ってこいな能力だが、制御出来ない危険性がある。
人に触れれば人の元からある思考を上塗りしようとする強烈な負の感情に見舞われるが、意思の力で耐え切る事も出来る。
この能力は任意で発動出来るが、能力を切るには何か1つでも触れてからでないとその手の能力をオフには出来ない……
が、最近は制御を少し出来る様になったらしい。
・花子はイバラシティの住人だが、薫はアンジニティ出身の者だ──
テレーゼ=ジーベン
アンジニティでの薫はある神になった者の死後その代わりとなった少女。封じの為に目に両腕に片足に包帯が巻かれている。
村の守護を行えるようにと病、怪我、彼女は皆の代用品。生きたみがわり人形となる生であった。
しかし、ただの人間であった彼女は死亡し、その後テレーゼとして認められることのなかった生の末の行き先はアンジニティであった。
ハザマでの彼女の異能は血で代用、彼女は自身の命を代用にする事で創造を行える異能となっている。
しかし、その規模があるからこそ彼女は一度しか使えず、一度使えば彼女は死を迎える──
────────────
・花子、薫共に既知設定は許可相談あれば構いません!
・友好的なロールも不穏もなんでもok
身長:145cm
一人称:私 二人称:貴方、お兄さん、お姉さん
性別:女性
年齢:85歳
森山駄菓子店の店長。
夫は既に他界している為、夫の駄菓子屋を継いで店長を務めている。
好物はさくらもち、チョコレートは板チョコが貰えただけでとても喜ぶ。
穏やかで面倒見の良いお婆ちゃん。
「いらっしゃい、おみくじもあるよ。
やっていかないかい?」
異能:「召し上がれ」
花子の差し出す食べ物には人の心を落ち着ける作用がある、言わば、精神干渉型の異能とも言える。
花子は昔から自身の異能に自覚がなく、それでも発動していることからこれは常時発動の異能と思われる。
サブキャラ
森山 薫(もりやま かおる)
身長:165cm
一人称:自分 二人称:君
性別:女性
年齢:17歳
「…よろしく頼む」
全身図
http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=soru72su3i&file=5CBFCD88-4E77-4CAC-9764-5C89EABA29D1.png
相良伊橋高校に秋に編入してきた女性。
薄い青紫色の長髪にワインレッドの瞳。
コヌマ区の森山駄菓子店で暮らしていて、そこの店主花子とは祖母と孫の関係だと花子は言っているが、薫は本当はドイツ出身、花子は純日本人だ。
堅苦しい喋り方に、クールで冷たい性格の様だが、話しかけると友好的、口数は多くないが本人が交流らしい交流に慣れていないだけで突き放す気は無い。
両太腿に本物の皮で出来たホルスターを巻いているが中に入っているのは水鉄砲。
実はカナヅチ
異能
・血の創造
血液をあらゆる物の代用品として扱える異能。
例えば赤い絵の具がない場合血を異能で使う事で本物の絵の具に変えられる。
赤と再現したのは使用する物は血の色になるから。違う物として異能で変化した後は参加して茶色くなったりせず新鮮な赤黒い色のまま。
服がない場合に血を利用して服に変える事もできるが真っ赤は目立つからと本人がその方法では利用しない。
代償
・血の消費量は代用にする物の規模に合わせて多くなる。
・一度実際に使用した事のある物しか代用品の生成は不可能
・薫は内臓移植を事故の後に受け、その内臓に付与された呪いで身体がボロボロである。
・彼女自体はこの町の外から来ている、しかし花子は彼女がそうである事を記憶が混濁してるからと言っている様だが…?
・彼女はどうやら死ぬらしい、死なないといけないらしい、ただそれだけ。たったそれだけのことである──
悠里
身長:170cm
一人称:私 二人称:貴方
性別:男性
年齢:19歳
女性にしか見えない顔立ちと男性にしては高め、女性にしてはハスキーな声が特徴。
普段は巫女服で歩き回っている。コスプレではなく正装なのだが、諸事情につきコスプレでしかない状態が悩み。
愛想の良さと笑顔が特徴。
異能
【慈悲なき魔の手】
触れた物を動かす能力。動かすと言っても超能力的ではなく、さながら命を与えるかのように。
しかし、触れた物それには正常な思考は宿らない。戦意だけの兵を作るのには持ってこいな能力だが、制御出来ない危険性がある。
人に触れれば人の元からある思考を上塗りしようとする強烈な負の感情に見舞われるが、意思の力で耐え切る事も出来る。
この能力は任意で発動出来るが、能力を切るには何か1つでも触れてからでないとその手の能力をオフには出来ない……
が、最近は制御を少し出来る様になったらしい。
・花子はイバラシティの住人だが、薫はアンジニティ出身の者だ──
テレーゼ=ジーベン
アンジニティでの薫はある神になった者の死後その代わりとなった少女。封じの為に目に両腕に片足に包帯が巻かれている。
村の守護を行えるようにと病、怪我、彼女は皆の代用品。生きたみがわり人形となる生であった。
しかし、ただの人間であった彼女は死亡し、その後テレーゼとして認められることのなかった生の末の行き先はアンジニティであった。
ハザマでの彼女の異能は血で代用、彼女は自身の命を代用にする事で創造を行える異能となっている。
しかし、その規模があるからこそ彼女は一度しか使えず、一度使えば彼女は死を迎える──
────────────
・花子、薫共に既知設定は許可相談あれば構いません!
・友好的なロールも不穏もなんでもok
4 / 30
457 PS
カミセイ区
J-2
J-2





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | 防御10 | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | 回復10 | - | |
| 4 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 5 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 6 | 団子 | 料理 | 20 | 器用10 | 敏捷10 | - | |
| 7 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 8 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 9 | 腹巻き | 防具 | 25 | 敏捷10 | - | - | |
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 11 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 12 | 古雑誌 | 素材 | 20 | [武器]心酔15(LV30)[防具]鎮痛15(LV30)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
| 13 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
| 14 | 石英 | 素材 | 15 | [武器]光纏10(LV20)[防具]加速10(LV30)[装飾]地纏10(LV25) | |||
| 15 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 防具 | 15 | 防具作製に影響 |
| 装飾 | 5 | 装飾作製に影響 |
| 付加 | 15 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 15 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 7 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 6 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決1 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ストーンブラスト | 6 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| キュアブリーズ | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| スキューア | 6 | 0 | 100 | 敵貫:地痛撃&次受ダメ増 | |
| インビジブルウォール | 6 | 0 | 80 | 味傷:反射 | |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| ブランチ | 5 | 0 | 100 | 敵:地痛撃&領域値[地]3以上なら、敵傷:地領痛撃 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| クリエイト:マナクリスタル | 5 | 0 | 110 | 味:充填LV増 | |
| 決3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]アクアブランド | [ 3 ]ストライク | [ 1 ]氷水避け |
| [ 1 ]パワーブースター | [ 2 ]ウォーターフォール | [ 1 ]ヴィジランス |

PL / フィッシュ田井中