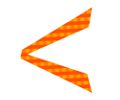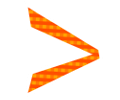<< 4:00~5:00




芙苑植物園イベント(http://lisge.com/ib/talk.php?s=860)用日記
※絶望や恐怖を含む回想になるため、重めの話になります。駄目な人は逃げてね。
『その■を、■■ないで』
「ゆーやーけーこーやーけーでまたあしたー、……あっおかあさんきた。おかーさーん」
ほいくえんがおわって、すべりだいの上でうたってると、いつもどおりおかあさんがむかえにきてくれた。
わたしはすぐにすべりおりて、おかあさんに手をふった。
「せんせーさよーなら。ねぇねぇおかあさん、きょうも『ざなどう』行く?」
「そうね。晩ごはんと、明日の牛乳を買いに行きましょ」
「やったー!」
ほいくえんの帰りに、おかあさんといっしょにスーパー『ざなどう』でおかいものをするのが、わたしはだいすき。
だって、わたしはおかあさんがだいすきだから。
おとうさん……は見たことないんだけど、
「おとうさんが遠くで一生懸命働いてるから、こうしてスーパーでお買い物出来るのよ」
っておかあさんが言ってたから、おとうさんもだいすき。……ってことにしといてあげる。
「あなたのまちのーふんふふーん 何とかかんとかふんふふーん」
「つむじ、その歌大好きねぇ」
「なんかねー、スーパーでまいにち聞くから覚えちゃった」
「ふふ。その割には音程も歌詞もうろ覚えだけど」
「おんてー?」
「ううん、何でもないわ。帰ったらご飯にしましょう。今日は菜の花のおひたしとから揚げよ」
「わーい!からあげだいすき!でもおひたしきらーい」
「我侭言わないの。お母さん毎回頑張って作ってるんだから」
「わがままじゃないもーん。こげこげだったり、にがかったりするからきらーい」
そう、おかあさんは、お料理がへたへたへたっぴなのだ。
半がくシールのついたからあげのほうが、わたしはだいすき。
かのこおばさんはあんなにおいしいたこ焼きがつくれるのにね。へんなの。

「さ、帰りましょ。つむじが手伝ってくれるから、お買い物が早く終わって助かるわ」
「あのね、つむじがみつけたの。半がくシールのからあげ!」
「そうね、ありがとう。お店の人にもありがとうって言った?」
「うん、ありがとーございますって言った!えらい?えらいよね?だから、きょうはからあげだけ食べていい?」
「だーめ。頑張ってお野菜食べましょ。今日はお料理きっと上手くいくから」
「ぶー」
おかあさんの『きっと』は、いつもあてにならない。これはきょうもきっとこげこげぷーだ。
「もー、しょーがないなー。そのかわり、ね」
わたしは、おかあさんにみぎの手をのばす。
えがおで買いものぶくろをみぎの手にまとめて、ひだりの手でわたしをぎゅってにぎってくれる。
おかあさんはわたしのほしいものをすぐにわかってくれる。じつはまほうつかいなのかも。
「えへへー」
ふんわり、おかあさんはレモンの良いにおい。
おかあさんのお料理はきらいだけど、おかあさんの手、だいすき。
おかあさんの手は、とってもあったかい。
おかあさんの手から、わたしのことだいすきってきもちが、ながれてくるみたい。
だから、わたしもおかあさんの手をぎゅってにぎるの。
わたしのおかあさんだいすきってきもちが、たくさんつたわるように。
「おっとっと」
「わ、おかあさんだいじょうぶ?」
おかあさんがきゅうにふらふらっとしたので、わたしもいっしょにふらふら。そのまましゃがみこんだ。
「ちょっとめまいがしただけ。平気平気」
「おかあさんびょうき?いたいとこない?」
「大丈夫大丈夫。一応明日にでも病院で見て貰いましょ」
「びょーいん!?だいじょうぶじゃなーい!貸して!買いものぶくろわたしが持つ!」
「きっと大丈夫だから。あぁもう無理したら危ないってば」
「だめー!わたしがもつのー!!!」
「ちょっとつむじ!袋引きずってるから!穴が開いちゃう!」
「わーたーしーがーもーつーのー!!」
「つーむーじー!!」
「以前から重度の味覚障害があった筈です」「今日から、いえ、今すぐに入院を」「場合によってはツクナミの大学病院に転院も視野に入れて」「いいですか、特にあの子とは何があっても隔離しなければいけない」
おばさんとおいしゃさんが、びょういんでおはなししてた。
わたしもドアのそとでこっそり聞いてたけど、おいしゃさんのことば、むずかしすぎてわかんない。
そのひから、わたしはおかあさんにあえなくなった。
ああ、そうか。『私』はあのときの夢を見ているのだ。
母が入院してから、一年。初めて、面会が許された。
私は一番お気に入りの服を着て、スキップしながら担当の医師と病院の廊下を歩いた。
母は面会謝絶の個室から4人部屋の一番奥、春の日差しが差し込む特等席に移されていた。
医師が間仕切りカーテンを開けると、そこにはあれほど待ちわびたはずの母の姿があった。
「――!」
一年ぶりの再会の時の衝撃を、恐怖を、絶望を、その時の『わたし』は口にすることが出来なかった。
レモンの匂いがしていた艶のある母の髪の毛は、頭皮からかろうじて繋がっている弱々しい糸にしか見えず。
私の我侭を受け止めていた優しい瞳は、白く濁って焦点すら合わせられず。
友達を家に呼ぶたびに羨望を集めた健康的な肌は、数十年の時を経たかのように無数の皺を刻んでいた。
立ち尽くすわたしに、「いいかい、絶対におかあさんに触れないようにね」と念を押して、医師は出て行った。
「……つむじ、そこに、いるの?」
「!! う、うん。いるよ。ここだよ」
「……そう、よかった」
かすれ切った声。まるで魔女のようだと思ってしまい、わたしは慌てて首を振って思考を追い出す。
「ずっと会えなくて、ごめんね。こんな格好で、びっくりしたでしょう」
「ううん、大丈夫だもん。つむじぜんぜん平気だもん」
「そう。……おばちゃんの、言うこと、きいてる?」
「うん。おばさんやさしいし、お料理はおいしいし。たこばっかりだけど」
「……そう、よかった」
いっそ別人だと思いたかった。でも、その声、左目の下の泣き黒子、そして苦痛に顔を歪めながら笑いかけようとするその優しさは、どうしようもなく母のものだった。わたしは、涙を我慢するので精一杯だった。
「つむじ。……手を、にぎっ、て、頂戴」
ずるり、と毛布の中から骨と皮ばかりの右手が出てくる。……駄目だ。やめろ。その手を握ってはいけない。『私』は『わたし』に呼びかける。しかしこれは、既に起こった過去。ただの観客である『私』は、映画の中の『わたし』を変えられない。『わたし』を掴もうとした『私』の手は、するりと空を切る。
「でも、お医者さんがだめだって」
「……お願い。お母さん、手をにぎってくれたら、きっと、元気になるから」
そう言われて、『わたし』は断ることが出来なかった。
母の『きっと』は嘘をつくときの口癖だと知りながら。
その時の母の手の感触が『わたし』を通じて蘇る。
恐る恐る触れた手は、わたしよりも痩せ細っており、まるで氷を掴んだかのように冷たかった。
「おかあさん、わたしが、きっとげんきにしてあげるから」
わたしは無理やり笑顔を作って、母の手を両手で握り締めた。
こらえきれなくなった涙が、ぼたぼたと手の甲を濡らしていった。
(かみさま。もしかしたら、いるかもしれないかみさま。
おねがいです。わたしの元気を、おかあさんにわけてください。
おかあさんが、いなくなるのはいやです。
わたしのいのちを、はんぶんおかあさんにあげてください。
そうしたら、ずっといっしょにいられるから――)
わたしは、ありったけの祈りをこめて、その手を握った。
私の手に宿る異能が、【奪う】ことしか出来ないとも知らずに。
三日三晩の高熱から回復した朝、わたしは伯母から母親の葬儀が終わったと伝えられた。
それから二十年。私は未だに、他人の手だとか、純粋な善意とかいうものを少しだけ苦手にしている。



ENo.493 志駁 とのやりとり

ENo.608 ルピス とのやりとり

以下の相手に送信しました













百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
カティーロ(1164) により ItemNo.14 白石 から射程1の武器『手に馴染むたこピック』を作製してもらいました!
⇒ 手に馴染むたこピック/武器:強さ82/[効果1]祝福10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
ItemNo.15 美味しい草 から料理『あげたこ』をつくりました!
⇒ あげたこ/料理:強さ55/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
たっきー(6) とカードを交換しました!
ブレイクスラッシュ (ハードブレイク)

五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度1⇒2)
ブレイドフォーム を研究しました!(深度1⇒2)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ツカサ(171) は 山査子 を入手!
オバチャン(880) は 山査子 を入手!
みぅ(1016) は ラベンダー を入手!
カティーロ(1164) は 山査子 を入手!
カティーロ(1164) は ボロ布 を入手!
ツカサ(171) は ネジ を入手!
みぅ(1016) は 毛皮 を入手!
カティーロ(1164) は 不思議な牙 を入手!
ツカサ(171) は 羽 を入手!
ツカサ(171) は ビーフ を入手!



チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調6⇒5)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調5⇒4)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- カティーロ(1164) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- ツカサ(171) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- オバチャン(880) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- みぅ(1016) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- カティーロ(1164) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――












梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・














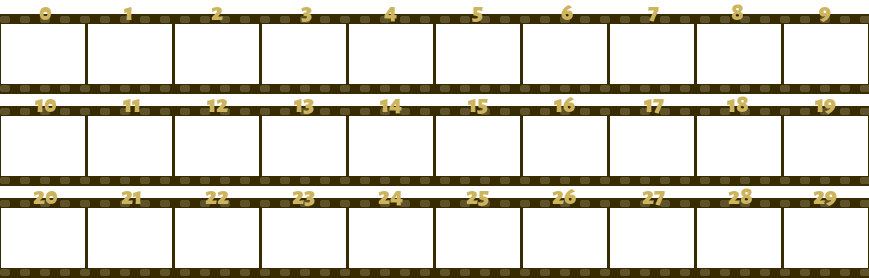







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



芙苑植物園イベント(http://lisge.com/ib/talk.php?s=860)用日記
※絶望や恐怖を含む回想になるため、重めの話になります。駄目な人は逃げてね。
『その■を、■■ないで』
「ゆーやーけーこーやーけーでまたあしたー、……あっおかあさんきた。おかーさーん」
ほいくえんがおわって、すべりだいの上でうたってると、いつもどおりおかあさんがむかえにきてくれた。
わたしはすぐにすべりおりて、おかあさんに手をふった。
「せんせーさよーなら。ねぇねぇおかあさん、きょうも『ざなどう』行く?」
「そうね。晩ごはんと、明日の牛乳を買いに行きましょ」
「やったー!」
ほいくえんの帰りに、おかあさんといっしょにスーパー『ざなどう』でおかいものをするのが、わたしはだいすき。
だって、わたしはおかあさんがだいすきだから。
おとうさん……は見たことないんだけど、
「おとうさんが遠くで一生懸命働いてるから、こうしてスーパーでお買い物出来るのよ」
っておかあさんが言ってたから、おとうさんもだいすき。……ってことにしといてあげる。
「あなたのまちのーふんふふーん 何とかかんとかふんふふーん」
「つむじ、その歌大好きねぇ」
「なんかねー、スーパーでまいにち聞くから覚えちゃった」
「ふふ。その割には音程も歌詞もうろ覚えだけど」
「おんてー?」
「ううん、何でもないわ。帰ったらご飯にしましょう。今日は菜の花のおひたしとから揚げよ」
「わーい!からあげだいすき!でもおひたしきらーい」
「我侭言わないの。お母さん毎回頑張って作ってるんだから」
「わがままじゃないもーん。こげこげだったり、にがかったりするからきらーい」
そう、おかあさんは、お料理がへたへたへたっぴなのだ。
半がくシールのついたからあげのほうが、わたしはだいすき。
かのこおばさんはあんなにおいしいたこ焼きがつくれるのにね。へんなの。

おかあさん
葦毛 魚々子(あしげ ななこ)
つむじの母。大判かのこの妹。
つむじと二人で暮らしている。
料理の腕が壊滅的。
つむじの母。大判かのこの妹。
つむじと二人で暮らしている。
料理の腕が壊滅的。
「さ、帰りましょ。つむじが手伝ってくれるから、お買い物が早く終わって助かるわ」
「あのね、つむじがみつけたの。半がくシールのからあげ!」
「そうね、ありがとう。お店の人にもありがとうって言った?」
「うん、ありがとーございますって言った!えらい?えらいよね?だから、きょうはからあげだけ食べていい?」
「だーめ。頑張ってお野菜食べましょ。今日はお料理きっと上手くいくから」
「ぶー」
おかあさんの『きっと』は、いつもあてにならない。これはきょうもきっとこげこげぷーだ。
「もー、しょーがないなー。そのかわり、ね」
わたしは、おかあさんにみぎの手をのばす。
えがおで買いものぶくろをみぎの手にまとめて、ひだりの手でわたしをぎゅってにぎってくれる。
おかあさんはわたしのほしいものをすぐにわかってくれる。じつはまほうつかいなのかも。
「えへへー」
ふんわり、おかあさんはレモンの良いにおい。
おかあさんのお料理はきらいだけど、おかあさんの手、だいすき。
おかあさんの手は、とってもあったかい。
おかあさんの手から、わたしのことだいすきってきもちが、ながれてくるみたい。
だから、わたしもおかあさんの手をぎゅってにぎるの。
わたしのおかあさんだいすきってきもちが、たくさんつたわるように。
「おっとっと」
「わ、おかあさんだいじょうぶ?」
おかあさんがきゅうにふらふらっとしたので、わたしもいっしょにふらふら。そのまましゃがみこんだ。
「ちょっとめまいがしただけ。平気平気」
「おかあさんびょうき?いたいとこない?」
「大丈夫大丈夫。一応明日にでも病院で見て貰いましょ」
「びょーいん!?だいじょうぶじゃなーい!貸して!買いものぶくろわたしが持つ!」
「きっと大丈夫だから。あぁもう無理したら危ないってば」
「だめー!わたしがもつのー!!!」
「ちょっとつむじ!袋引きずってるから!穴が開いちゃう!」
「わーたーしーがーもーつーのー!!」
「つーむーじー!!」
 |
つむじ 「……めて。その手を、……」 |
 |
魔女 「……。」 |
「以前から重度の味覚障害があった筈です」「今日から、いえ、今すぐに入院を」「場合によってはツクナミの大学病院に転院も視野に入れて」「いいですか、特にあの子とは何があっても隔離しなければいけない」
おばさんとおいしゃさんが、びょういんでおはなししてた。
わたしもドアのそとでこっそり聞いてたけど、おいしゃさんのことば、むずかしすぎてわかんない。
そのひから、わたしはおかあさんにあえなくなった。
ああ、そうか。『私』はあのときの夢を見ているのだ。
母が入院してから、一年。初めて、面会が許された。
私は一番お気に入りの服を着て、スキップしながら担当の医師と病院の廊下を歩いた。
母は面会謝絶の個室から4人部屋の一番奥、春の日差しが差し込む特等席に移されていた。
医師が間仕切りカーテンを開けると、そこにはあれほど待ちわびたはずの母の姿があった。
「――!」
一年ぶりの再会の時の衝撃を、恐怖を、絶望を、その時の『わたし』は口にすることが出来なかった。
レモンの匂いがしていた艶のある母の髪の毛は、頭皮からかろうじて繋がっている弱々しい糸にしか見えず。
私の我侭を受け止めていた優しい瞳は、白く濁って焦点すら合わせられず。
友達を家に呼ぶたびに羨望を集めた健康的な肌は、数十年の時を経たかのように無数の皺を刻んでいた。
立ち尽くすわたしに、「いいかい、絶対におかあさんに触れないようにね」と念を押して、医師は出て行った。
「……つむじ、そこに、いるの?」
「!! う、うん。いるよ。ここだよ」
「……そう、よかった」
かすれ切った声。まるで魔女のようだと思ってしまい、わたしは慌てて首を振って思考を追い出す。
「ずっと会えなくて、ごめんね。こんな格好で、びっくりしたでしょう」
「ううん、大丈夫だもん。つむじぜんぜん平気だもん」
「そう。……おばちゃんの、言うこと、きいてる?」
「うん。おばさんやさしいし、お料理はおいしいし。たこばっかりだけど」
「……そう、よかった」
いっそ別人だと思いたかった。でも、その声、左目の下の泣き黒子、そして苦痛に顔を歪めながら笑いかけようとするその優しさは、どうしようもなく母のものだった。わたしは、涙を我慢するので精一杯だった。
「つむじ。……手を、にぎっ、て、頂戴」
ずるり、と毛布の中から骨と皮ばかりの右手が出てくる。……駄目だ。やめろ。その手を握ってはいけない。『私』は『わたし』に呼びかける。しかしこれは、既に起こった過去。ただの観客である『私』は、映画の中の『わたし』を変えられない。『わたし』を掴もうとした『私』の手は、するりと空を切る。
「でも、お医者さんがだめだって」
「……お願い。お母さん、手をにぎってくれたら、きっと、元気になるから」
そう言われて、『わたし』は断ることが出来なかった。
母の『きっと』は嘘をつくときの口癖だと知りながら。
その時の母の手の感触が『わたし』を通じて蘇る。
恐る恐る触れた手は、わたしよりも痩せ細っており、まるで氷を掴んだかのように冷たかった。
「おかあさん、わたしが、きっとげんきにしてあげるから」
わたしは無理やり笑顔を作って、母の手を両手で握り締めた。
こらえきれなくなった涙が、ぼたぼたと手の甲を濡らしていった。
(かみさま。もしかしたら、いるかもしれないかみさま。
おねがいです。わたしの元気を、おかあさんにわけてください。
おかあさんが、いなくなるのはいやです。
わたしのいのちを、はんぶんおかあさんにあげてください。
そうしたら、ずっといっしょにいられるから――)
わたしは、ありったけの祈りをこめて、その手を握った。
私の手に宿る異能が、【奪う】ことしか出来ないとも知らずに。
 |
つむじ 「……。はぁ」 |
 |
魔女 「目が覚めたか。どうした、ずいぶんとうなされていたようだが」 |
 |
つむじ 「……ん。まぁちょっと、昔の夢をね。私病院でお見舞いしてたらその場で倒れちゃって即入院したことがあるんだけど、まぁそのあたりのこと……とか」 |
 |
魔女 「……そうか」 |
 |
つむじ 「その時はさ、三日三晩高熱が出て、そりゃもう大変だったんだから。おっと、寝てる暇なんて無いんだった。さーて今日もさくさく進まないと!」 |
 |
魔女 「……そうだな」 |
 |
魔女 (……『その手を握らないで』か。ただ熱にうなされただけの夢なら、そんなうわ言にはならないはずだが……一体どんな夢を、どんな過去を見たというのだ……?) |
三日三晩の高熱から回復した朝、わたしは伯母から母親の葬儀が終わったと伝えられた。
それから二十年。私は未だに、他人の手だとか、純粋な善意とかいうものを少しだけ苦手にしている。



ENo.493 志駁 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.608 ルピス とのやりとり
| ▲ |
| ||||
| |||||
以下の相手に送信しました



 |
ツカサ 「(………また、カティーロちゃんのことを仲間だと思って……来たのかな…?)」 |
 |
つむじ 「よーし、今日もさくさくすすみましょうか!」 |
 |
カティーロ 「無事全員合流できてよかった。さ、次は団子屋さんだね」 |





たことみこ
|
 |
水音と名月
|



百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
カティーロ(1164) により ItemNo.14 白石 から射程1の武器『手に馴染むたこピック』を作製してもらいました!
⇒ 手に馴染むたこピック/武器:強さ82/[効果1]祝福10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
 |
カティーロ 「いつも使うものなら馴染む方がいいって気持ち、よくわかるな」 |
 |
カティーロ 「じゃ、まずは手の計測からね!」 |
ItemNo.15 美味しい草 から料理『あげたこ』をつくりました!
⇒ あげたこ/料理:強さ55/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
 |
オバチャン 「油で揚げることによりカリカリ感も出せるよ」 |
たっきー(6) とカードを交換しました!
ブレイクスラッシュ (ハードブレイク)

五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度1⇒2)
ブレイドフォーム を研究しました!(深度1⇒2)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ツカサ(171) は 山査子 を入手!
オバチャン(880) は 山査子 を入手!
みぅ(1016) は ラベンダー を入手!
カティーロ(1164) は 山査子 を入手!
カティーロ(1164) は ボロ布 を入手!
ツカサ(171) は ネジ を入手!
みぅ(1016) は 毛皮 を入手!
カティーロ(1164) は 不思議な牙 を入手!
ツカサ(171) は 羽 を入手!
ツカサ(171) は ビーフ を入手!



チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調7⇒6)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調6⇒5)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調5⇒4)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- カティーロ(1164) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- ツカサ(171) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- オバチャン(880) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- みぅ(1016) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- カティーロ(1164) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――







フクロウって食べれるのかな?
|
 |
たことみこ
|




チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・





ENo.880
大判 かのこ/葦毛 つむじ



<大判 かのこ>
ウシ区でたこ焼き屋を営む人情オバチャン。
異能はない。
ハザマにおいてあまりに無力なので肉体を貸している。
職場「たこ焼きの店 オバチャン」
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1185
<タコヤキの魔女>
たこ焼きの情報を蒐集するのが生き甲斐の情報生命体。
たこ焼きが好き、たこ焼き屋が多いイバラシティも好き。
オバチャンと意気投合して、ハザマの間だけちょっと身体を借りる。
魔女なのでたこ焼きで攻撃できたり回復させたりするぞ。
ハザマ内レスでは基本オバチャンに意識を譲っているよ。(ご都合主義)
<サブキャラ>
葦毛 旋 (あしげ つむじ)
オバチャンの姪。
24歳女性、ウラド区在住。整体師。
性格はざっくり、時に守銭奴。
黒手袋と白衣とスニーカーがトレードマーク。
職場「整体・マッサージの店 あしげ」
http://lisge.com/ib/talk.php?s=711
異能『駄々漏れる生命(リーク・ライフ)』
手に触れた相手の生命力を自動的に吸ってしまう。
足から吸った分の生命力を任意に与えることが出来る。
この異能を使って足で整体をやっている。
感情が昂ぶると足からど根性タンポポとか大根とか生えてくる。
異能のせいか、脚は器用だが手は不器用。
プロフ絵&アイコン(11~17):水城待紘様
アイコン18 みわしいば様(少年少女好き?2)
<既知設定について>
テストプレイ時の方との既知設定ご自由に。
知ってる体で話すもよし、新しく絆を繋ぎなおすもよし。
ただしPLの脳みそがゆるゆるなので若干の矛盾はご容赦を。
なおオバチャンのテスト時の異能は「最初からなかった」ことになっております。ご理解ご協力をお願いします。
<PLについて>
脳みそが残念なのでロールや設定にあらが多いです。
雑食なので地雷は少ないよ。
夜8時から12時くらいを主な活動時間にしたい(願望)
置きレス歓迎。
生暖かい視線で見守って下さい。
ついった @dottokyom
ウシ区でたこ焼き屋を営む人情オバチャン。
異能はない。
ハザマにおいてあまりに無力なので肉体を貸している。
職場「たこ焼きの店 オバチャン」
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1185
<タコヤキの魔女>
たこ焼きの情報を蒐集するのが生き甲斐の情報生命体。
たこ焼きが好き、たこ焼き屋が多いイバラシティも好き。
オバチャンと意気投合して、ハザマの間だけちょっと身体を借りる。
魔女なのでたこ焼きで攻撃できたり回復させたりするぞ。
ハザマ内レスでは基本オバチャンに意識を譲っているよ。(ご都合主義)
<サブキャラ>
葦毛 旋 (あしげ つむじ)
オバチャンの姪。
24歳女性、ウラド区在住。整体師。
性格はざっくり、時に守銭奴。
黒手袋と白衣とスニーカーがトレードマーク。
職場「整体・マッサージの店 あしげ」
http://lisge.com/ib/talk.php?s=711
異能『駄々漏れる生命(リーク・ライフ)』
手に触れた相手の生命力を自動的に吸ってしまう。
足から吸った分の生命力を任意に与えることが出来る。
この異能を使って足で整体をやっている。
感情が昂ぶると足からど根性タンポポとか大根とか生えてくる。
異能のせいか、脚は器用だが手は不器用。
プロフ絵&アイコン(11~17):水城待紘様
アイコン18 みわしいば様(少年少女好き?2)
<既知設定について>
テストプレイ時の方との既知設定ご自由に。
知ってる体で話すもよし、新しく絆を繋ぎなおすもよし。
ただしPLの脳みそがゆるゆるなので若干の矛盾はご容赦を。
なおオバチャンのテスト時の異能は「最初からなかった」ことになっております。ご理解ご協力をお願いします。
<PLについて>
脳みそが残念なのでロールや設定にあらが多いです。
雑食なので地雷は少ないよ。
夜8時から12時くらいを主な活動時間にしたい(願望)
置きレス歓迎。
生暖かい視線で見守って下さい。
ついった @dottokyom
30 / 30
349 PS
チナミ区
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | たこピック | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 7 | ねぎたこ | 料理 | 50 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 9 | マヨたこ | 料理 | 50 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 10 | 薔薇色の髪飾り | 装飾 | 40 | 回復10 | - | - | |
| 11 | グリーンパーカー | 法衣 | 22 | 体力10 | - | 幸運7 | |
| 12 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 13 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 14 | 手に馴染むたこピック | 武器 | 82 | 祝福10 | - | - | 【射程1】 |
| 15 | あげたこ | 料理 | 55 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 16 | 山査子 | 素材 | 15 | [武器]防疫15(LV30)[防具]耐疫10(LV20)[装飾]快癒10(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 20 | 植物/鉱物/地 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 45 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| 練2 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| 練3 | アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 |
| レモンのブレンドハーブ (ヒールハーブ) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| 練3 | 激痛!!整体ヒール!! (パワフルヒール) | 6 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 珊瑚樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・領域値[水][地]増+守護+連続減 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
料理は鮮度が大事 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
おいしい水(500ml) (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
|
CODE:[0.87] (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
ひつじが4匹 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
|
ハンターだよ! (サモン:ハンター) |
4 | 300 | 自:ハンター召喚 | |
|
ブレイクスラッシュ (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒールミスト | [ 2 ]アクアヒール | [ 1 ]ファーマシー |
| [ 1 ]五月雨 | [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]イグニス |
| [ 1 ]ファイアボルト | [ 2 ]サモン:サーヴァント | [ 2 ]ダウンフォール |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 3 ]ハードブレイク | [ 2 ]ブレイドフォーム |

PL / どっと虚無