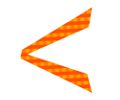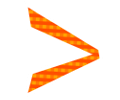<< 4:00~5:00




自己紹介をしよう。私の名前はナンディナ。
カダーヴェルヘールヴァ氏族のナンディナ。
とある分割世界に生きる長命種(これは人間を基準にした物だ)で、人間の血を生存に必要とする。
それ故にカダーヴェルヘールヴァ氏族は『吸血鬼』と呼ばれる。
悪竜の二つ名は氏族から——その分割世界からアンジニティに追放されるときにつけられた物だ。私は悪をなした。悪をもってそれを濯がねばならない。
発端は私の所領で疫病が出たことだ。
肺を病み、咳が出る。私はそういう症状を抑えるのに適したカダーヴェルヘールヴァであったから、所領の人々を癒やした。その数およそ五万人。
所領に平和が戻り、人々に笑顔が戻り、交易の人は絶えず。
——そして。
私がしたのは結局、「症状を抑える」事だけであって、病を癒やしたわけではなかったらしい。
私の所領の人間が通った場所に疫病が出た。
疫病は国を巡り、諸国を巡り、世界を巡った。
氏族の物が手を尽くした(私ももちろん尽力した)が、事態が収束した折には人間の数はあまりにも減ってしまった。
そうして私は氏族の円卓の前に膝をつかされていたのだった。
今や円卓に座ることは許されなかった。
聡明な氏族の仲間たちは原因を究明し、それが私の浅慮にあると結論した。
私は人間を助けたかった。そして助けたが、その行為はより多くの人間を死に追いやった。
その咎により『アンジニティ』と呼ばれる世界へ行かされる。と長老から宣告される。
そこで私が助けたのと同じ数の人を殺せば、この世界に戻れると約定がなされた。
私はそれを受け入れながら、到底無理だと思った。
私にはそんなことはできない。無論、氏族の誰にもだ。
人の身を超えた命と力を持っていても、人がどんなにか細く死にやすい命でも、奪おうと思わなければそれは不自然には奪われない物なのだ。
氏族の者は例外なく人間を愛していた。
その地に生きる営みを愛していた。
そうであればこそ、私にその条件が課せられたのだ。
愛する者を奪った者に、最も重い罰を。
罪を償う気すら萎える罰を。
そうであるから、アンジニティに降り立った私には枷の一つもはめられていなかった。
人の血が必要だといっても、それは人を殺す程には必要ではない。
それに私の必要とする血は月に四度ほどであるから、蒜手に嘘をついたまま、血について素知らぬ顔をしていられる。
残り30時間。
彼女に嘘を突き通すのにはあまりにも短いように思える。
彼女には、私が「南天然」の変化した姿だと、そう嘘をついたままでいよう。
嘘をつくのは心苦しいが、本当のことを話すのはあまりにも酷なように思えた。
彼女は私を信じてくれる。それはなんと尊いことだろう。
30時間後。もしもイバラシティを守りきった暁には彼女はどうなるのだろう。
彼女の記憶から私のことが消える。
南天然の事が消える。
私は私より後に死ぬ者の知り合いがいないが、それはまるで彼女より自分の方が先に死ぬのと同じ事のように思えた。
彼女より先に自分が死ぬ。
生まれて初めて直面する事態に、なんと心を抱いたら良いのかわからなかった。
もう一人、私を信じてくれるといった人物がいる。
目から(自称)ケチャップを流しながら私を、皆を信じているといった笹塚。
痛みで錯乱しているとしか思えない言動だった。
彼女は自分を大事にしない。
それがいかなる理由による物なのかはわからないが、痛みの中でさえ自暴自棄なことはあんなかわいらしい嘘に気がつかないと思っているのだろうか。
——思ったのかもしれない。
これらの信頼は南天然が培ったものだ。
あの、無防備に人を信じ、そして人に信じて貰える存在。
それがなんとも歯がゆかった。
それはひどく古い記憶。
まだ私が幼かったときにある人間に言われた言葉だ。
『吸血鬼』は人の血を糧にする。
それ以外の物を口にしなくともよいくらいだ。
だから人間をどんなに愛していても人間から信じられることはない。
蒜手からの親愛も、笹塚からの信用も
人間である南天然のものだ。
笹塚は南天然の存在を信じている。
そうであれば、それを守ることが彼女のところにとんでゆけない私にできる全てなのだろうか。
誠実に嘘を突き通すことが彼女のためならば、私はそうせねばならない。
笹塚もまた、私より長く生きることになるのだなと思った。
可能な限り苦悶のない生を。イバラシティで。そう願いたかった。
アンジニティの空は紅く、少し陰れば昼でも難なく出歩くことができた。
そして私は出会ったのだ。地に伏せる真白い裸身の少女に。
死んでいるのかと思ったが、か細く脈があったので私の城へ招いた。
蒜手を入れた影の部屋とは規模が違う、広大な影の城だ。
食事を用意し、寝床を整え、人が生きるのに必要とする子細を整えてなお、彼女は私を憤怒と屈辱の表情で見ていた。
力で押さえねばならないこともしばしばあった。
理由は簡単なことである。
信じて貰えないかもしれないが、これは本当に不慮の事故で、私はすっかり忘れていて。
三日ほど彼女に衣服を渡すのを忘れていた。
イバラシティは小鳥が自由に空を飛び、さえずることのできる楽園だ。
しかしアンジニティはそうではない。
ナトゥーラと名前を名乗った少女が一人で生きていくのは到底無理に思われる大地だった。
そうであるから私は彼女を鳥籠に入れた小鳥のように扱うことにした。
「やめて」と彼女は苦悶の表情を浮かべていう。
私の毒は彼女には効かなかった。効けば血を吸われる間も法悦のうちにあって痛みも感じないというのに、かわいそうな彼女はその効果のうちになかった。
彼女の血は蜜のように甘く、酒精の快さを忘れる程だった。
何もできないまま流れる時間に膿んで、私は彼女との時間を過ごした。
「殺してやる」と言うのが聞こえた。
影の城の一室の、甘い香りの中で。
どうやら彼女の香りにも毒があるようだったが、残念ながら私にはその毒は効かなかった。
思い出すまでもない私のアンブローシア。
…………甘美なだけの香り。
今やそれは、『それ』以外の意味を持っている。
あの香りを『僕』はイバラシティで嗅いだことがある。



ENo.17 サクマ とのやりとり

ENo.79 ミロ とのやりとり

ENo.95 暁人 とのやりとり

ENo.928 一抹 とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。









ミロ(79) に 10 PS 送付しました。
モモノメ(1137) に ItemNo.14 皮 を送付しました。
ミロ(79) に ItemNo.13 皮 を送付しました。
幻術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
具現LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ミロ(79) の持つ ItemNo.11 着古したスーツ に ItemNo.6 ボロ布 を付加しました!
コウキ(1026) とカードを交換しました!
風刃のコトダマ (エアブレイド)


パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
チャクラグラント を研究しました!(深度0⇒1)
バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
エチュード を習得!
ヒールポーション を習得!
プリディクション を習得!
マーチ を習得!
肉体変調耐性 を習得!
フィジカルブースター を習得!
コールドウェイブ を習得!
アクアリカバー を習得!
アイスソーン を習得!
カームソング を習得!
ウィークネス を習得!
ファゾム を習得!
トランス を習得!
精神変調耐性 を習得!
マナポーション を習得!
チャージ を習得!
アクアブランド を習得!
ガーディアンフォーム を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





現在のパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
暁人(95) からパーティに勧誘されました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- 南天(44) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ベアトリス(47) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ミロ(79) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 暁人(95) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!
- 南天(44) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- ベアトリス(47) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- ミロ(79) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- 暁人(95) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――












梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・














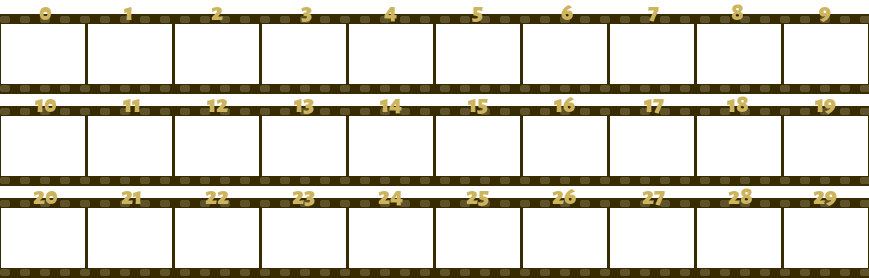









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「信じて貰えないかもしれないけれど
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
自己紹介をしよう。私の名前はナンディナ。
カダーヴェルヘールヴァ氏族のナンディナ。
とある分割世界に生きる長命種(これは人間を基準にした物だ)で、人間の血を生存に必要とする。
それ故にカダーヴェルヘールヴァ氏族は『吸血鬼』と呼ばれる。
悪竜の二つ名は氏族から——その分割世界からアンジニティに追放されるときにつけられた物だ。私は悪をなした。悪をもってそれを濯がねばならない。
発端は私の所領で疫病が出たことだ。
肺を病み、咳が出る。私はそういう症状を抑えるのに適したカダーヴェルヘールヴァであったから、所領の人々を癒やした。その数およそ五万人。
所領に平和が戻り、人々に笑顔が戻り、交易の人は絶えず。
——そして。
私がしたのは結局、「症状を抑える」事だけであって、病を癒やしたわけではなかったらしい。
私の所領の人間が通った場所に疫病が出た。
疫病は国を巡り、諸国を巡り、世界を巡った。
氏族の物が手を尽くした(私ももちろん尽力した)が、事態が収束した折には人間の数はあまりにも減ってしまった。
そうして私は氏族の円卓の前に膝をつかされていたのだった。
今や円卓に座ることは許されなかった。
聡明な氏族の仲間たちは原因を究明し、それが私の浅慮にあると結論した。
私は人間を助けたかった。そして助けたが、その行為はより多くの人間を死に追いやった。
その咎により『アンジニティ』と呼ばれる世界へ行かされる。と長老から宣告される。
そこで私が助けたのと同じ数の人を殺せば、この世界に戻れると約定がなされた。
私はそれを受け入れながら、到底無理だと思った。
私にはそんなことはできない。無論、氏族の誰にもだ。
人の身を超えた命と力を持っていても、人がどんなにか細く死にやすい命でも、奪おうと思わなければそれは不自然には奪われない物なのだ。
氏族の者は例外なく人間を愛していた。
その地に生きる営みを愛していた。
そうであればこそ、私にその条件が課せられたのだ。
愛する者を奪った者に、最も重い罰を。
罪を償う気すら萎える罰を。
そうであるから、アンジニティに降り立った私には枷の一つもはめられていなかった。
「信じて貰えないかもしれないけれど
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
人の血が必要だといっても、それは人を殺す程には必要ではない。
それに私の必要とする血は月に四度ほどであるから、蒜手に嘘をついたまま、血について素知らぬ顔をしていられる。
残り30時間。
彼女に嘘を突き通すのにはあまりにも短いように思える。
彼女には、私が「南天然」の変化した姿だと、そう嘘をついたままでいよう。
嘘をつくのは心苦しいが、本当のことを話すのはあまりにも酷なように思えた。
彼女は私を信じてくれる。それはなんと尊いことだろう。
30時間後。もしもイバラシティを守りきった暁には彼女はどうなるのだろう。
彼女の記憶から私のことが消える。
南天然の事が消える。
私は私より後に死ぬ者の知り合いがいないが、それはまるで彼女より自分の方が先に死ぬのと同じ事のように思えた。
彼女より先に自分が死ぬ。
生まれて初めて直面する事態に、なんと心を抱いたら良いのかわからなかった。
「信じて貰えないかもしれないけれど
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
もう一人、私を信じてくれるといった人物がいる。
目から(自称)ケチャップを流しながら私を、皆を信じているといった笹塚。
痛みで錯乱しているとしか思えない言動だった。
彼女は自分を大事にしない。
それがいかなる理由による物なのかはわからないが、痛みの中でさえ自暴自棄なことはあんなかわいらしい嘘に気がつかないと思っているのだろうか。
——思ったのかもしれない。
これらの信頼は南天然が培ったものだ。
あの、無防備に人を信じ、そして人に信じて貰える存在。
それがなんとも歯がゆかった。
「それは、私が貴方の食べ物だからですか?」
それはひどく古い記憶。
まだ私が幼かったときにある人間に言われた言葉だ。
『吸血鬼』は人の血を糧にする。
それ以外の物を口にしなくともよいくらいだ。
だから人間をどんなに愛していても人間から信じられることはない。
蒜手からの親愛も、笹塚からの信用も
人間である南天然のものだ。
笹塚は南天然の存在を信じている。
そうであれば、それを守ることが彼女のところにとんでゆけない私にできる全てなのだろうか。
誠実に嘘を突き通すことが彼女のためならば、私はそうせねばならない。
笹塚もまた、私より長く生きることになるのだなと思った。
可能な限り苦悶のない生を。イバラシティで。そう願いたかった。
「信じて貰えないかもしれないけれど
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
アンジニティの空は紅く、少し陰れば昼でも難なく出歩くことができた。
そして私は出会ったのだ。地に伏せる真白い裸身の少女に。
死んでいるのかと思ったが、か細く脈があったので私の城へ招いた。
蒜手を入れた影の部屋とは規模が違う、広大な影の城だ。
食事を用意し、寝床を整え、人が生きるのに必要とする子細を整えてなお、彼女は私を憤怒と屈辱の表情で見ていた。
力で押さえねばならないこともしばしばあった。
理由は簡単なことである。
信じて貰えないかもしれないが、これは本当に不慮の事故で、私はすっかり忘れていて。
三日ほど彼女に衣服を渡すのを忘れていた。
「信じて貰えないかもしれないけれど
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
僕たちは案外人間のことが大好きだ」
イバラシティは小鳥が自由に空を飛び、さえずることのできる楽園だ。
しかしアンジニティはそうではない。
ナトゥーラと名前を名乗った少女が一人で生きていくのは到底無理に思われる大地だった。
そうであるから私は彼女を鳥籠に入れた小鳥のように扱うことにした。
「やめて」と彼女は苦悶の表情を浮かべていう。
私の毒は彼女には効かなかった。効けば血を吸われる間も法悦のうちにあって痛みも感じないというのに、かわいそうな彼女はその効果のうちになかった。
彼女の血は蜜のように甘く、酒精の快さを忘れる程だった。
何もできないまま流れる時間に膿んで、私は彼女との時間を過ごした。
「殺してやる」と言うのが聞こえた。
影の城の一室の、甘い香りの中で。
どうやら彼女の香りにも毒があるようだったが、残念ながら私にはその毒は効かなかった。
思い出すまでもない私のアンブローシア。
…………甘美なだけの香り。
今やそれは、『それ』以外の意味を持っている。
あの香りを『僕』はイバラシティで嗅いだことがある。
thanks to 47, 928, 1314.



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.79 ミロ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.95 暁人 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.928 一抹 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。





望遠鏡で花見
|
 |
夕礼書店調査隊
|



ミロ(79) に 10 PS 送付しました。
モモノメ(1137) に ItemNo.14 皮 を送付しました。
ミロ(79) に ItemNo.13 皮 を送付しました。
幻術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
具現LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
領域LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ミロ(79) の持つ ItemNo.11 着古したスーツ に ItemNo.6 ボロ布 を付加しました!
コウキ(1026) とカードを交換しました!
風刃のコトダマ (エアブレイド)


パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
チャクラグラント を研究しました!(深度0⇒1)
バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
エチュード を習得!
ヒールポーション を習得!
プリディクション を習得!
マーチ を習得!
肉体変調耐性 を習得!
フィジカルブースター を習得!
コールドウェイブ を習得!
アクアリカバー を習得!
アイスソーン を習得!
カームソング を習得!
ウィークネス を習得!
ファゾム を習得!
トランス を習得!
精神変調耐性 を習得!
マナポーション を習得!
チャージ を習得!
アクアブランド を習得!
ガーディアンフォーム を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





現在のパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
暁人(95) からパーティに勧誘されました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- 南天(44) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ベアトリス(47) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ミロ(79) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 暁人(95) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!
- 南天(44) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- ベアトリス(47) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- ミロ(79) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園
- 暁人(95) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――







月世御D研究所特殊戦闘迎撃部門:チームSP
|
 |
水音と名月
|




チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・





ENo.44
南天



【ちょっと注意】
ハザマでは蒜手(47)と恋仲っぽいのですが、イバラでは全然そんなことをおくびにも出さない。というギミックです。しかしイバラでの南も恋愛関係不可キャラとなります。本人が恋人ほしそうにしてても、なんかこう、野良犬に餌をやらない気持ちでお付き合いください。野良犬に餌をやった場合めちゃくちゃ喜びますが、飼い犬にはなりません。そんな感じ。
▽IBARASITY
南 天然(みなみ てんぜん)
扇杷学院大学、文学部仏文学科一年生。
黒髪赤目、身長168cm。
気が弱くてお人好しで真面目。
趣味は読書。小説から文系の専門書までぼんやり読む。
しかし別に物知りではない。
絲車高校OB、元文芸部
高校の時のクラス内でのあだ名が「テンネン」なくらいには天然。
冗談は通じたり通じなかったりする。
異能は自分に対しては身体強化、自分や周りに対しては喉周りの症状を抑えることができる。せき、喉の痛み、しゃっくりなど。
STATiCEのモデルバイトをしている時がある。
↓主なポップ先
・バイト先のチナミ駅前のコンビニ(プレイス178)
・扇杷学院大学(スポット635)
・カスミ区の荊街総合図書館(スポット)
・イバライン有(プレイス2131)
・自宅は浄蓮コーポ201号室(プレイス462)
▽ANSINITY
ハザマの姿=悪竜ナンディナ
南天の異能はナンディナの能力のかけらである。
悪竜とは二つ名であって、実態は吸血鬼。
アンジニティにいる時はナトゥーラ(1314)を影の城に囲い、喰い物にしていた。
今は蒜手(47)のことを大変愛おしく思っており保護者を自認している。
主な能力はこちらのページを参照してください。
→https://ibarainfo.wiki.fc2.com/wiki/%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%253D%E5%8D%97%E3%80%80%E5%A4%A9%E7%84%B6
今はまだ自分がアンジニティの住人であることを周囲に明かせていない。奇妙に血の香りを纏わせているが、素直に考えるならば「南天然が変化のハザマでは異能を使っている」と思えるように振る舞っている。
明かした人→95、928、17、
◆ ◆ ◆
小酉分 有神(とりわけ ゆがみ)
サブキャラ。18歳フリーター。
脱色した髪にまだらに色を入れている。目は黒。身長174cm。
高知県民なので異能はない。
ファッションと音楽と古代文明とかエキゾチックなものが好き。
自分でアクセサリー作りをしたりもする。
駅前や公園でギターを弾いていることもある。
時折殺人に勤しみ、その事件が巷間を騒がせることもあるが未だ掴まっていない。
(フレーバーです。特にその類のロールをする予定はありません)
STATiCEイバモールチナミ店で働いている。(↓主なポップ場所)
・STATiCEイバモールチナミ店(プレイス2529)
・駅や公園、手芸店など
(現在ほぼイバラモード用キャラです。
STATiCE店舗で個人的に仲良くなるのは難しいとおもいます。)
◆ ◆ ◆
ディム (ディルムッド)
三十歳前後の研究者。
赤い髪に金色の目をしている。
シティの外から来たので特に異能はない。
体の一部が武器に置換される病気の研究をしており、その治療や制御についてイバラシティの変化形の異能が参考にできないか、ということで来ている。
医師と生化学者の間みたいなスキルツリー。
プレイボーイってやつです。
マガサ区に出没したいね!
◆ ◆ ◆
ねこ(ねこ)
のらねこ。しろくてまるいの。
えさを三回あげるとちょっとなつく(累計)
チナミ区でのらのらしている。
◆ ◆ ◆
◆ロール傾向、注意事項など。
・30分くらい待ってください。レスが遅いです。
・置きレスのときもあります。
・既知ロールは不自然でない範囲で歓迎します。
・情景描写が好きです。心理描写をしている時がありますが、汲み取ってなにかしろ、みたいなものではありません。どんどん裏切っていってください。
・打ち合わせ歓迎です。
・モブを動かすのが好きです。
・目標のあるロールが好きです。PC、モブ、を問わず「こんなきっかけがあったら動けるのにな〜〜」という時にご依頼通り?の情報を渡したりなんだりすることができますのでお気軽にご相談ください。(深くキャラクターや事件に関わってほしい、というご依頼については、私の方の好みやリソースの問題があるのでお受けできない場合があります)
ーーーーー
・市営バスのマスコットキャラクター、イバラスをみみぴいさんにお願いしました。
・ダイハシ合成・付加工場スポット説明と、同休憩所プレイス説明文をmahipipaさんにお願いしました。マスコットキャラクターのフッカーくんのイラストを鬼畜さんにお願いしました。
ハザマでは蒜手(47)と恋仲っぽいのですが、イバラでは全然そんなことをおくびにも出さない。というギミックです。しかしイバラでの南も恋愛関係不可キャラとなります。本人が恋人ほしそうにしてても、なんかこう、野良犬に餌をやらない気持ちでお付き合いください。野良犬に餌をやった場合めちゃくちゃ喜びますが、飼い犬にはなりません。そんな感じ。
▽IBARASITY
南 天然(みなみ てんぜん)
扇杷学院大学、文学部仏文学科一年生。
黒髪赤目、身長168cm。
気が弱くてお人好しで真面目。
趣味は読書。小説から文系の専門書までぼんやり読む。
しかし別に物知りではない。
絲車高校OB、元文芸部
高校の時のクラス内でのあだ名が「テンネン」なくらいには天然。
冗談は通じたり通じなかったりする。
異能は自分に対しては身体強化、自分や周りに対しては喉周りの症状を抑えることができる。せき、喉の痛み、しゃっくりなど。
STATiCEのモデルバイトをしている時がある。
↓主なポップ先
・バイト先のチナミ駅前のコンビニ(プレイス178)
・扇杷学院大学(スポット635)
・カスミ区の荊街総合図書館(スポット)
・イバライン有(プレイス2131)
・自宅は浄蓮コーポ201号室(プレイス462)
▽ANSINITY
ハザマの姿=悪竜ナンディナ
南天の異能はナンディナの能力のかけらである。
悪竜とは二つ名であって、実態は吸血鬼。
アンジニティにいる時はナトゥーラ(1314)を影の城に囲い、喰い物にしていた。
今は蒜手(47)のことを大変愛おしく思っており保護者を自認している。
主な能力はこちらのページを参照してください。
→https://ibarainfo.wiki.fc2.com/wiki/%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%253D%E5%8D%97%E3%80%80%E5%A4%A9%E7%84%B6
今はまだ自分がアンジニティの住人であることを周囲に明かせていない。奇妙に血の香りを纏わせているが、素直に考えるならば「南天然が変化のハザマでは異能を使っている」と思えるように振る舞っている。
明かした人→95、928、17、
◆ ◆ ◆
小酉分 有神(とりわけ ゆがみ)
サブキャラ。18歳フリーター。
脱色した髪にまだらに色を入れている。目は黒。身長174cm。
高知県民なので異能はない。
ファッションと音楽と古代文明とかエキゾチックなものが好き。
自分でアクセサリー作りをしたりもする。
駅前や公園でギターを弾いていることもある。
時折殺人に勤しみ、その事件が巷間を騒がせることもあるが未だ掴まっていない。
(フレーバーです。特にその類のロールをする予定はありません)
STATiCEイバモールチナミ店で働いている。(↓主なポップ場所)
・STATiCEイバモールチナミ店(プレイス2529)
・駅や公園、手芸店など
(現在ほぼイバラモード用キャラです。
STATiCE店舗で個人的に仲良くなるのは難しいとおもいます。)
◆ ◆ ◆
ディム (ディルムッド)
三十歳前後の研究者。
赤い髪に金色の目をしている。
シティの外から来たので特に異能はない。
体の一部が武器に置換される病気の研究をしており、その治療や制御についてイバラシティの変化形の異能が参考にできないか、ということで来ている。
医師と生化学者の間みたいなスキルツリー。
プレイボーイってやつです。
マガサ区に出没したいね!
◆ ◆ ◆
ねこ(ねこ)
のらねこ。しろくてまるいの。
えさを三回あげるとちょっとなつく(累計)
チナミ区でのらのらしている。
◆ ◆ ◆
◆ロール傾向、注意事項など。
・30分くらい待ってください。レスが遅いです。
・置きレスのときもあります。
・既知ロールは不自然でない範囲で歓迎します。
・情景描写が好きです。心理描写をしている時がありますが、汲み取ってなにかしろ、みたいなものではありません。どんどん裏切っていってください。
・打ち合わせ歓迎です。
・モブを動かすのが好きです。
・目標のあるロールが好きです。PC、モブ、を問わず「こんなきっかけがあったら動けるのにな〜〜」という時にご依頼通り?の情報を渡したりなんだりすることができますのでお気軽にご相談ください。(深くキャラクターや事件に関わってほしい、というご依頼については、私の方の好みやリソースの問題があるのでお受けできない場合があります)
ーーーーー
・市営バスのマスコットキャラクター、イバラスをみみぴいさんにお願いしました。
・ダイハシ合成・付加工場スポット説明と、同休憩所プレイス説明文をmahipipaさんにお願いしました。マスコットキャラクターのフッカーくんのイラストを鬼畜さんにお願いしました。
30 / 30
177 PS
チナミ区
D-2
D-2





































混沌としたコミュニティに犬が!!
6
アイコン120pxの会
3
アイコン1000pxの会
7
アンジ出身イバラ陣営の集い
8
#片道切符チャット
1
ログまとめられフリーの会
#交流歓迎
1
イバラNP建築協会
アンジニティタートルネック部
毎更新必ず何かしらやらかす
8
イバラシティの自分に物申したい!
2
モ
じゃんけん
16
とりあえず肉食う?
12
長文大好きクラブ
1



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 良い木材 | 素材 | 20 | [武器]攻撃15(LV30)[防具]敏捷15(LV30)[装飾]回復15(LV30) | |||
| 3 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 4 | 蝙蝠の影 | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 金の学生章 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 影の中で黒い長衣 | 法衣 | 20 | 敏捷10 | - | 幸運6 | |
| 7 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 9 | 影の群れ | 武器 | 67 | 追撃10 | 列撃10 | - | 【射程3】 |
| 10 | アセロラジュース(聖杯入り) | 料理 | 75 | 攻撃10 | 防御10 | 強靭15 | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 45 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| 練1 | ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| サンダーショット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:光撃&麻痺 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| 練3 | マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| コールドウェイブ | 5 | 0 | 80 | 敵4:水撃&凍結+自:炎上 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| 練3 | クリエイト:グレイル | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
| ビューティーフォーム | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
| ピュリフィケーション | 5 | 0 | 50 | 敵味腐:SP増+腐食状態なら、精確光撃&腐食を猛毒化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| 練2 | プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 |
| ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
| トランス | 5 | 0 | 100 | 自:混乱+自:AT・HL増+魅了を祝福化 | |
| マナポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 6 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| ブレイドフォーム | 6 | 0 | 160 | 自:AT増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 練3 | 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
| 練2 | 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
LOTA`S COLLECT01 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
青/井戸の水 (マナポーション) |
0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
|
->[n.守護天使を呼ぶ] (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| 練3 |
檜花粉、到来!! (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
|
鳥の詩 (ヒーリングソング) |
0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
|
風刃のコトダマ (エアブレイド) |
0 | 100 | 敵列:風撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]闇の祝福 | [ 1 ]チャクラグラント | [ 1 ]ストライク |
| [ 1 ]バーニングチューン | [ 1 ]デアデビル | [ 1 ]ヒールポーション |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]五月雨 | [ 1 ]火の祝福 |
| [ 1 ]クレイジーチューン | [ 1 ]血気 | [ 1 ]背水 |
| [ 1 ]見切 | [ 1 ]カレイドスコープ | [ 1 ]チャージ |
| [ 1 ]水の祝福 | [ 1 ]パワフルヒール | [ 1 ]ハードブレイク |

PL / コギト